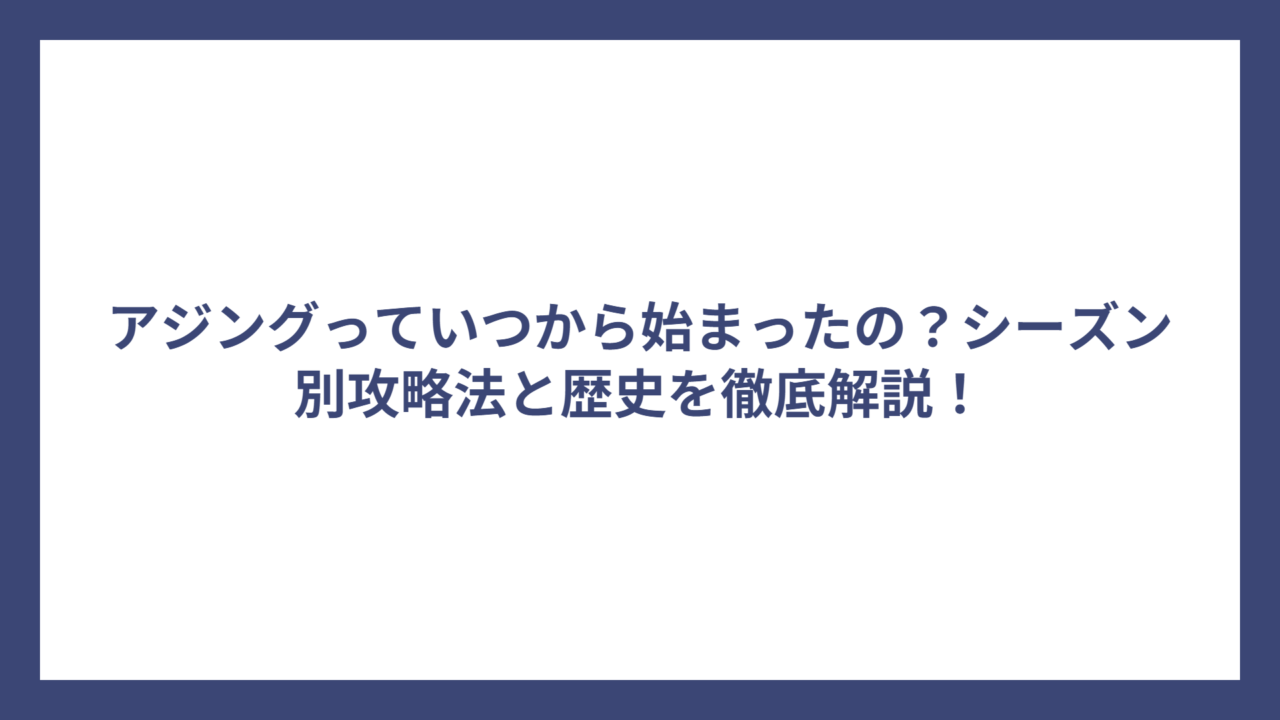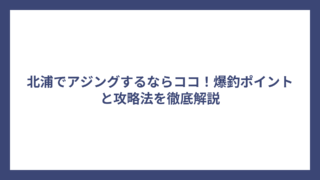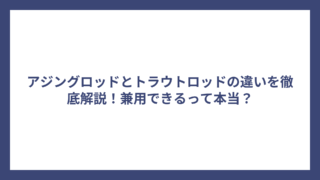「アジングっていつから始まった釣りなの?」「アジングを始めるならいつからがいいの?」そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。アジングは今でこそライトゲームの代表格として確立されていますが、その歴史や最適なシーズンについて詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、アジングという釣法がいつから始まり、どのように普及していったのかという歴史的な側面と、実際にアジングを楽しむならいつからいつまでがベストシーズンなのかという実践的な情報を、インターネット上の様々な情報を収集・分析してお届けします。地域別の違いや、季節ごとの攻略法まで網羅的に解説していきますので、これからアジングを始めたい初心者の方も、すでに楽しんでいる方も、ぜひ参考にしてください。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジングという名称が定着した時期と歴史的背景 |
| ✓ 全国的なアジングのベストシーズンと地域差 |
| ✓ 季節ごとの釣れるアジのサイズと攻略法 |
| ✓ 水温や時間帯など釣果を左右する重要要素 |
アジングはいつから始まった釣り方なのか
- アジングという名称が定着したのは2002〜2004年頃
- アジングの起源はメバリングの外道から始まった
- ルアーでアジが釣れることが広まったのは約25年前から
- アジング専門ブランドの登場で爆発的に普及した時期
- 地域によってアジングの歴史は異なる
- トラウトタックルから専用タックルへの進化
アジングという名称が定着したのは2002〜2004年頃
アジングという言葉が一般的に使われ始めたのは、2002年から2004年頃だと言われています。それ以前からルアーでアジを釣る人は存在していましたが、明確に「アジング」という名称で呼ばれるようになったのはこの時期からです。
記憶が曖昧で、たしか2002〜2004くらいにブログか雑誌で「アジング」として紹介されたと思います。
この情報からも分かるように、2000年代初頭にはすでにアジングという言葉が使われ始めていたようです。ただし、釣り方自体はそれ以前から存在しており、名称が後からついた形になります。
興味深いのは、渡邉長士さんという方が2002年発行の雑誌「TACKLE BOX」で「僕はいつも”アジング”って呼んでます。」と記載していたという記録が残っていることです。
平成14年発行ということで、少なくとも2002年には「アジング」と呼んで普及活動(!?)をしていたことになる。
当時は「アジングってなんだよソレ~」とかなり言われたそうで、今では当たり前になっている言葉も、最初は新しい概念として受け入れられるまでに時間がかかったことが伺えます。メバリングという言葉が先行して存在していたため、それに倣って「○○ing」という形で命名されたのではないかと推測されます。
アジングの起源はメバリングの外道から始まった
アジングが独立した釣法として確立される前は、メバリングの外道として釣れる魚という位置づけでした。ルアーでメバルを狙っていると、外道でアジが釣れることは多くの釣り人が経験していたのです。
それ以前に「メバリング」はありました。ルアーでメバル釣ってたら外道でアジが釣れるのは多くの人が知ってました。それをわざわざ「アジング」としてカテゴライズしたのがそのあたりだと思いますよ。
この証言から分かるように、アジがルアーで釣れること自体は以前から知られていましたが、それを意図的に狙う釣法として独立させたのがアジングの始まりと言えるでしょう。メバリングが先行していたからこそ、その延長線上でアジングが生まれたという歴史的な流れがあります。
一般的にアジはプランクトンイーターというイメージが強く、ルアーで積極的に狙える魚という認識が薄かったため、外道として釣れていても「アジを狙って釣る」という発想に至るまでには時間がかかったのかもしれません。しかし、実際にはアジも小魚やワームサイズのルアーに反応することが分かり、専門的に狙う価値がある魚種として認識されるようになっていきました。
ルアーでアジが釣れることが広まったのは約25年前から
アジングという名称が定着する以前から、ルアーでアジを釣る人は存在していました。その歴史は約25年前、つまり1990年代後半から2000年頃にさかのぼります。
渡邉長士さんの証言によると、彼が15〜16歳の頃(おそらく1990年代後半)に千葉県外房エリアでシーバス釣りをしていた際、水面でバシャバシャとしているベイトの正体を確かめようとしたところ、アジがルアー(トリプルフック)にくわえついてきたことが発見のきっかけだったそうです。
「当時は今ほど経験値も情報も少なかったですし、プランクトンイーターのイメージがあったアジですから、メチャクチャ驚きましたよ」
この発見以降、トラウト用のルアーやロッドを使用してアジを狙う試みが始まりました。当時はアジング専用のルアーなど存在しなかったため、小型のトラウトスプーンやミノーを流用していたようです。
他の証言でも「25年くらい前からやってます」「20年以上前からありました」という声があり、2000年前後にはすでにルアーでアジを釣る人が一定数存在していたことが分かります。ただし、それはまだマイナーな釣り方であり、一般的に認知されるようになったのは、やはり2000年代中盤以降ということになるでしょう。
アジング専門ブランドの登場で爆発的に普及した時期
アジングが爆発的にブームになったのは、専門ブランドやメーカーが本格的に参入し始めた2008年前後だと言われています。
アジングが爆発的にブームになったのは、やはり林漁具のアジングブランド「ティクト」の功績が高いです。まだ、34のオジサンが林漁具の社員だった頃ですね。ティクトが出来たのが2008年ですから、その前後からアジングがブームになりました。
ティクト(TICT)というアジング専門ブランドの登場は、アジング界において革命的な出来事でした。それまでトラウト用やメバル用のタックルを流用していた時代から、アジングに特化した専用設計のロッド、ジグヘッド、ワームが登場したことで、より効率的にアジを狙えるようになりました。
専門ブランドの登場により、アジングという釣法が一つのジャンルとして確立され、釣具店でも「アジングコーナー」が設けられるようになりました。これにより初心者でも始めやすい環境が整い、ファンが急速に増えていったと考えられます。
また、専門メーカーの登場は情報発信の活発化にもつながりました。釣法の解説、タックルセッティング、ポイント選びなど、体系的な情報が雑誌やウェブサイトで発信されるようになり、アジングの裾野が大きく広がっていったのです。
地域によってアジングの歴史は異なる
アジングの歴史は、全国一律ではなく地域によって異なる発展を遂げてきました。特に瀬戸内海や西日本の一部地域では、アジングという名称が広まる前から、独自にルアーでアジを狙う文化があったようです。
その前も、広島や瀬戸内など一部の地域ではアジを専門に狙う方も多く盛んに行われていました。
瀬戸内海エリアでは比較的早い時期からアジのルアー釣りが行われており、地域の釣り文化として根付いていた可能性があります。一方、東日本や日本海側では、全国的にアジングが認知され始めた2000年代中盤以降に本格的に始まった地域が多いのかもしれません。
地域による違いは、アジの回遊パターンや生息密度、海域の特性などが関係していると推測されます。アジが豊富に生息し、年間を通じて狙える地域では自然とルアーでの釣法も発達しやすかったのでしょう。
現在では全国的にアジングが楽しまれていますが、各地域で微妙に異なるスタイルや文化が存在し、それがアジングの多様性と面白さにつながっているとも言えます。
トラウトタックルから専用タックルへの進化
アジングの歴史を語る上で欠かせないのが、タックルの進化です。初期のアジングはトラウトタックルの流用から始まりました。
渡邉長士さんの証言によると、初期はトラウト用のスプーンやミノーを使用していたそうです。具体的には以下のようなルアーが使われていました:
📌 初期のアジングで使用されていたルアー例
- フォレストのトラウトスプーン「マーシャル」(1.5g)
- スミスのICミノー、ICサージャー
- ジャクソンのソリッドミノー3cm
- オーナーばりの「竹ミノー」
これらはいずれもトラウト用として開発されたルアーですが、アジのサイズ感に合っていたため流用されていました。ロッドもトラウトロッドが使用され、アジング専用という概念はまだ存在していませんでした。
2008年前後のアジング専門ブランドの登場により、状況は大きく変わります。アジの口のサイズや吸い込み方に最適化されたジグヘッド、アジが好む波動を生み出すワーム、感度と操作性を両立したロッドなど、専用設計のタックルが次々と開発されました。
現在では、極細のPEラインやエステルライン、超軽量ジグヘッド(0.4g〜)、ティップの感度を極限まで高めたロッドなど、高度に進化したアジング専用タックルが当たり前となっています。この進化により、より繊細なアプローチが可能になり、釣果も大きく向上しました。
アジングのシーズンはいつからいつまでがベストなのか
- 全国的なベストシーズンは初夏〜晩秋(6〜11月)
- 春(3〜5月)は産卵前の大型アジが狙える時期
- 夏(6〜8月)は豆アジの数釣りシーズン
- 秋(9〜11月)はサイズも数も期待できる最盛期
- 冬(12〜2月)は居付きの大型を狙う上級者向け
- 地域別のシーズン(瀬戸内、九州、東北など)
- 水温17度が釣れるかどうかの目安
- 時間帯は日の出・日の入りが狙い目
- まとめ:アジングいつから始めるのがベストか
全国的なベストシーズンは初夏〜晩秋(6〜11月)
アジングを始めるなら、全国的には初夏から晩秋にかけての6月〜11月がベストシーズンです。この時期は水温が適温になり、アジの活性が高まるため、初心者でも比較的釣りやすい条件が整います。
全国的な目線で見ると、アジ釣りのシーズンは初夏から晩秋にかけて。
この時期の特徴として、アジが湾内深くまで回遊してくることが挙げられます。春先は湾の入り口付近に留まっていることが多いアジも、海水温の上昇とともに徐々に湾奥や港内まで接岸してくるため、堤防や漁港から手軽に狙えるようになります。
ただし、6月〜11月の間でも時期によって釣れるアジのサイズや数は大きく変動します。6月頃は10cm前後の「豆アジ」が中心ですが、秋が深まるにつれてサイズアップし、10月〜11月には20cm以上の良型も期待できます。
📊 アジングベストシーズンの月別特徴
| 月 | サイズ感 | 釣りやすさ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 豆アジ中心(10cm前後) | ○ | 数釣り可能、初心者向け |
| 7月 | 小型(10〜15cm) | ◎ | 高活性、回遊多い |
| 8月 | 小型(10〜15cm) | ◎ | 夜釣りがおすすめ |
| 9月 | 中型(15〜20cm) | ◎ | サイズアップ開始 |
| 10月 | 中〜大型(20〜25cm) | ◎◎ | 最盛期 |
| 11月 | 大型(25cm以上も) | ◎ | 尺アジチャンス |
季節の進行とともにアジのサイズが大きくなるのは、春に生まれた個体が成長していくためです。したがって、豆アジで数釣りを楽しみたいなら初夏、良型狙いなら秋という使い分けができます。
春(3〜5月)は産卵前の大型アジが狙える時期
春のアジングは、産卵前の栄養を蓄えた大型アジが狙える特別なシーズンです。ただし、難易度は高く、釣れる時と釣れない時がはっきり分かれる上級者向けの時期とも言えます。
春のアジングでは、大型のアジが狙えるシーズンです。産卵期前で活性の高い個体が多いのが特徴です。
春の大きな特徴は、アジの産卵期と密接に関係していることです。西日本では1〜4月、東日本では2〜5月が産卵時期とされており、産卵直前の個体は栄養を蓄えるために活発にエサを追います。この時期に遭遇できれば、20cm以上の良型が連発することもあります。
ただし注意点として、産卵期に突入してしまった個体はほとんど反応しなくなります。産卵行動に入ると摂餌活動が鈍くなり、ルアーへの反応が極端に悪くなるのです。そのため、春のアジングは「産卵前」という限られたタイミングを捉える必要があり、地域の海水温や過去の実績から判断する経験値が求められます。
海水温が14℃を超える頃がスタートの目安とされており、その後16〜20℃の範囲で産卵適水温となります。この微妙な水温変化を読み取り、産卵前の活性が高い時期を狙うのが春アジング攻略のカギです。
春アジングの攻略ポイント:
- ✅ 海水温14℃以上がスタートの目安
- ✅ 産卵前の短期間が勝負
- ✅ 外洋に面したエリアが有利
- ✅ 日の出・日の入りの時間帯に絞る
- ✅ 大型対応のタックルを準備
春は釣れる日と釣れない日の差が激しいため、初心者が最初に挑戦するシーズンとしてはあまりおすすめできません。しかし、大型アジの引きを味わいたい経験者にとっては、非常にエキサイティングな時期と言えるでしょう。
夏(6〜8月)は豆アジの数釣りシーズン
夏は10cm前後の「豆アジ」が回遊し、数釣りを楽しめるシーズンです。初心者がアジングの基本を学ぶには最適な時期と言えます。
夏は活性の高いアジが多いので、数釣りを楽しめるシーズンになります。夏のアジといえば『子アジ・豆アジ』と呼ばれる小型のアジが群れで回遊していて釣りやすい
夏のアジは春に孵化した個体が成長初期段階にあり、サイズは小さいものの食欲旺盛で活性が非常に高いのが特徴です。群れで回遊することが多く、ポイントに回遊してくれば連発することも珍しくありません。
サビキ釣りでファミリーフィッシングを楽しむ人も多い時期ですが、ルアーでも十分に反応します。むしろ、豆アジは小さなワームに対して素早く反応するため、アジングの練習には最適です。キャスト、リトリーブ、アタリの取り方、アワセのタイミングなど、基本技術を磨くには絶好の機会と言えるでしょう。
夏のアジングで重要なのは時間帯の選択です。日中は水温が高すぎて活性が落ちることがあるため、夜釣りがおすすめです。特に常夜灯周りは、光に集まるプランクトンを狙ってアジが集まるため、好ポイントになります。
🌙 夏の夜アジング攻略法
- 常夜灯がある漁港や堤防を選ぶ
- 明暗の境目を重点的に探る
- 小型ワーム(1〜2インチ)を使用
- 軽量ジグヘッド(0.6〜1.5g)で表層を狙う
- 喰い込みを意識したゆっくりとしたアクション
豆アジは引きこそ小さいですが、数が釣れる楽しさがあります。また、から揚げや南蛮漬けにすると非常に美味しいため、食味の面でも満足度の高い釣りができます。
秋(9〜11月)はサイズも数も期待できる最盛期
秋はアジングの最盛期です。サイズ、数、釣りやすさのすべてにおいて最高の条件が揃うため、初心者から上級者まで誰もが楽しめるシーズンと言えます。
秋は初心者から上級者まで楽しめる最高のシーズンなので、『アジングは秋!』というのを覚えておいて損はありません。
秋のアジは春から夏にかけて成長した個体が20〜25cmのサイズになり、中には30cm以上の「尺アジ」も混じるようになります。サイズが大きくなるだけでなく、脂も乗って丸々と太っているため、引きも強く食べても美味しい最高の時期です。
秋のアジングが最盛期と言われる理由はいくつかあります。まず、水温が最適な範囲(18〜22℃程度)に安定すること。次に、イワシなどのベイトフィッシュが接岸するため、それを追ってアジも活発に回遊すること。そして、日中でも釣れる可能性があるため、時間帯の制約が少ないことなどが挙げられます。
特に10月〜11月は、多くの釣り場で最も釣果が上がる時期です。漁港や堤防、サーフなど様々なフィールドでアジの回遊が確認され、ポイント選びの選択肢も広がります。
秋アジング推奨タックル:
| アイテム | スペック | 理由 |
|---|---|---|
| ワーム | 2〜3インチ | サイズアップに対応 |
| ジグヘッド | 1.5〜3g | 遠投と感度のバランス |
| ライン | PE 0.3〜0.4号 | 感度と強度の両立 |
| リーダー | フロロ 1〜1.5号 | 大型対応の強度 |
秋は朝マズメや夕マズメの時合が特に良いですが、日中でもチャンスがあります。ナイトゲームでは常夜灯周りだけでなく、暗い場所でも良型が狙えるため、様々なアプローチを試せる楽しいシーズンです。
アジングを始めるなら秋からスタートすることを強くおすすめします。釣りやすく、サイズも期待でき、成功体験を得やすいため、アジングの魅力を最大限に感じられるはずです。
冬(12〜2月)は居付きの大型を狙う上級者向け
冬はアジの活性が最も低くなる難しいシーズンですが、その分釣れた時の喜びは格別です。上級者向けの時期と言えます。
冬はアジの活性が低く釣れにくいシーズンになります。しかし、全く釣れないわけではありません。冬に釣れるアジはほとんどが大型で、油も乗っていて美味しいのが特徴です。
冬のアジングが難しい理由は、水温の低下によりアジの代謝が落ち、摂餌活動が不活発になるためです。多くのアジは水温が安定した深場に移動してしまい、岸から狙える範囲には少数の「居付き個体」しか残りません。
しかし、冬のアジングには独特の魅力があります。まず、釣れるアジのサイズが大きいこと。冬を越せる体力のある個体は総じて大型で、25cm以上の良型が中心になります。また、脂が乗って味が最高なのも冬アジの特徴です。寒い時期のアジは身が締まり、刺身にすると絶品です。
冬のアジは回遊せず、特定のエリアに居付く傾向が強いため、一度ポイントを見つければ継続的に狙える可能性があります。常夜灯周りや水温が比較的安定している場所、潮通しの良い場所などが有望です。
❄️ 冬アジング攻略のコツ
- マズメ時に集中して釣行する
- 水温が高めの日を選ぶ
- 常夜灯周りを重点的に探る
- スローなアクションで誘う
- 長時間粘らず、ポイントを移動する
冬は1時間の釣行で0〜1匹という厳しい状況も珍しくありませんが、それだけに1匹釣れた時の達成感は大きいです。「なかなか釣れない中に釣れた1匹は、他のシーズンでは味わえない魅力がある」という声もあり、あえて冬にアジングをするプロアングラーもいるほどです。
初心者の方には冬からのスタートはおすすめできませんが、他のシーズンで経験を積んだ後、より高度な釣りに挑戦したい方にとっては、冬のアジングは新たな楽しみを提供してくれるでしょう。
地域別のシーズン(瀬戸内、九州、東北など)
アジングのシーズンは全国一律ではなく、地域によって最適な時期が異なります。これは水温や海流、アジの回遊パターンが地域ごとに違うためです。
🌊 主要エリア別アジングシーズン
| 地域 | ベストシーズン | 特徴 |
|---|---|---|
| 九州・瀬戸内 | 3月〜12月 | 長期間楽しめる、冬も可能性あり |
| 関東・東海 | 5月〜11月 | スタンダードなシーズン |
| 北陸・東北 | 6月〜10月 | 短期集中型、秋がピーク |
| 北海道 | 7月〜9月 | 限定的だが釣れる |
九州・瀬戸内エリア: このエリアは比較的温暖で、アジングシーズンが最も長いことで知られています。
秋の山形アジングの時期は青物の回遊時期とおおよそ同じで、10月から11月が最盛期となります。
瀬戸内海では3月頃から釣果情報が出始め、12月頃まで楽しめます。特に広島や愛媛などは古くからアジのルアー釣りが行われていた地域で、ノウハウも蓄積されています。冬でも水温が比較的高い日は狙えることがあり、ほぼ通年でチャンスがあると言えます。
関東・東海エリア: 東京湾、相模湾、伊豆半島、静岡などのエリアは、5月〜11月が中心となります。ゴールデンウィーク明けから豆アジが出始め、秋に向けてサイズアップしていくパターンが典型的です。
興味深いのは、最近の温暖化の影響で、静岡などでは冬でもアジが釣れる現象が報告されていることです。
海水温が低下し、アジの食欲が落ち込んでしまいます。回遊・釣れる時間があるのは1日のうちで1時間。日によっては数十分ということもあるほど。
水温が15℃を下回る日が少なくなり、通年で産卵が可能な環境になりつつあるという指摘もあります。これにより、本来オフシーズンであった冬にも豆アジが釣れるという状況が生まれています。
北陸・東北エリア: 山形県庄内地方など日本海側のエリアは、アジングシーズンが比較的短いのが特徴です。
山形県庄内地方でアジが釣れる時期は、4月から11月です。庄内地方のベストシーズンは春(5月~6月)と秋(10月~11月)になります。
山形では酒田と鶴岡でも微妙に時期がずれ、酒田は桜が咲く頃から、鶴岡は桜が散る頃からアジが釣れ始めるそうです。このような地域内での差も興味深いポイントです。秋は10〜11月がピークで、12月以降は厳しくなります。
地域によるシーズンの違いを理解することで、遠征先を選ぶ際の参考にもなりますし、引っ越しや転勤などで釣り場が変わった際にも役立ちます。
水温17度が釣れるかどうかの目安
アジングにおいて水温は釣果を大きく左右する最重要ファクターの一つです。特に、水温17度前後が一つの重要な目安となります。
アジの適水温をネットで調べると17度〜23度あたりになります。ちなみに、春に産卵するアジの産卵温度は19度〜21度あたりです。
アジの適水温は一般的に17〜23度とされており、この範囲内であれば活性が高く、ルアーへの反応も良くなります。逆に、水温が15度を下回ると活性が明らかに落ち、釣果が厳しくなる傾向があります。
水温がアジの行動に影響を与える理由は、変温動物である魚の代謝が水温に大きく依存するためです。水温が高いほど代謝が活発になり、餌を多く食べる必要が生じます。逆に水温が低いと代謝が落ち、あまり動かず、餌も食べなくなります。
📊 水温とアジの活性の関係
| 水温 | アジの状態 | 釣果の期待度 |
|---|---|---|
| 13℃以下 | 深場に移動、不活発 | × |
| 14〜16℃ | やや活性低い | △ |
| 17〜23℃ | 適水温、高活性 | ◎ |
| 24℃以上 | 活性高いが浅場は避ける傾向 | ○ |
特に春先や晩秋など、季節の変わり目には水温の変化が激しく、数日の気温変化で水温が2〜3度変わることもあります。このような時期は、釣行前に海水温の情報をチェックすることが重要です。
気温が上がり水温も上昇した日に釣果が上がることが多いという経験則もあります。したがって、春や秋の肌寒い日よりも、気温が17度以上になる暖かい日を選んで釣行する方が成功確率は高まるでしょう。
ただし、水温が適温範囲にあっても、潮の流れや時間帯、ベイトの有無など他の要素も重要です。水温はあくまで一つの指標として捉え、総合的に判断することが大切です。
時間帯は日の出・日の入りが狙い目
アジングにおいて時間帯の選択は釣果を大きく左右します。最も釣れる可能性が高いのは、日の出と日の入りの時間帯、いわゆる「マズメ時」です。
アジは日の出・日の入りの時間帯に接岸することが多くみられます。時間をしぼって釣りにいくのも好釣果の秘訣です!
なぜマズメ時に釣れやすいのでしょうか。これには複数の理由があります。まず、日の出の時間帯は水中の植物性プランクトンが光合成を始めるため活動が活発になり、それを捕食する動物性プランクトンも活動を開始します。そのプランクトンを食べる小魚が集まり、さらにそれを狙ってアジも活発に動き出すという食物連鎖が起こります。
日の入りの時間帯も同様で、夜行性のプランクトンが活動を始めることで生態系全体が活性化します。明るさの変化が生物の行動スイッチになっていると考えられます。
🌅 時間帯別の狙い方
| 時間帯 | 特徴 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 朝マズメ(日の出前後1時間) | 活性最高、大型のチャンス | ◎◎◎ |
| 日中 | 活性低い、深場や影を狙う | △ |
| 夕マズメ(日の入り前後1時間) | 活性高い、回遊が増える | ◎◎◎ |
| ナイト(常夜灯周り) | 豆アジ〜中型が狙える | ◎◎ |
| ナイト(暗い場所) | 大型の可能性、難易度高 | ○ |
特に春や冬など、アジの活性が全体的に低いシーズンでは、マズメ時の限られた時間しかチャンスがないこともあります。「1日のうちで1時間、日によっては数十分」という状況も珍しくありません。
したがって、限られた時間で効率よく釣果を上げたいなら、マズメ時を中心にプランを立てることをおすすめします。特に朝マズメは狙い目で、早起きして釣り場に向かう価値は十分にあります。
ナイトゲームの場合は、常夜灯周りが定番ポイントになります。光に集まるプランクトンを狙ってアジが集まるため、安定して釣果が期待できます。明暗の境目を重点的に探ると効果的です。
まとめ:アジングいつから始めるのがベストか
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングという名称が広まったのは2002〜2004年頃で、それ以前からルアーでアジを釣る人は存在していた
- アジングの起源はメバリングの外道から始まり、独立した釣法として確立されていった
- ルアーでアジが釣れることが認知され始めたのは約25年前(1990年代後半)から
- 2008年前後にアジング専門ブランドが登場し、爆発的に普及した
- 地域によってアジングの歴史は異なり、瀬戸内海では早くから行われていた
- 初期はトラウトタックルを流用していたが、現在は高度に進化した専用タックルが主流
- 全国的なアジングのベストシーズンは初夏〜晩秋の6月〜11月である
- 春(3〜5月)は産卵前の大型が狙えるが難易度は高い
- 夏(6〜8月)は豆アジの数釣りシーズンで初心者の練習に最適
- 秋(9〜11月)はサイズも数も期待できる最盛期で、初心者から上級者まで楽しめる
- 冬(12〜2月)は難易度が高いが大型の居付き個体が狙える上級者向けシーズン
- 地域によってシーズンは異なり、九州・瀬戸内は長期間、東北は短期集中型
- 水温17度前後がアジの適水温で、釣果を左右する重要な指標となる
- 時間帯は日の出・日の入りのマズメ時が最も釣れやすい
- 初心者がアジングを始めるなら、秋(9〜11月)からのスタートが最もおすすめ
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- アジングっていつから始まった釣り方ですか? – Yahoo!知恵袋
- アジングの時期はいつ?アジのサイズ別おすすめのシーズンを徹底解説! – 釣猿
- 【アジングに歴史ありvol.1】アジがルアーで釣れると知った「あの日」を渡邉長士さんに聞いた – つりそく
- アジ釣りは『時期』が重要!シーズンごとの傾向とポイントが合えば簡単に釣れます – TSURI HACK
- アジングができる地域と季節 – デュエル
- アジが釣れるのはいつ?山形県庄内地方のアジングの時期を解説 – 週末の釣りブログ
- 異常!?今年はヤバい豆アジ事情 – ClearBlue
- オンスタックル発!ダウンショットアジング – オンスタックル OFFICIAL Blog
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。