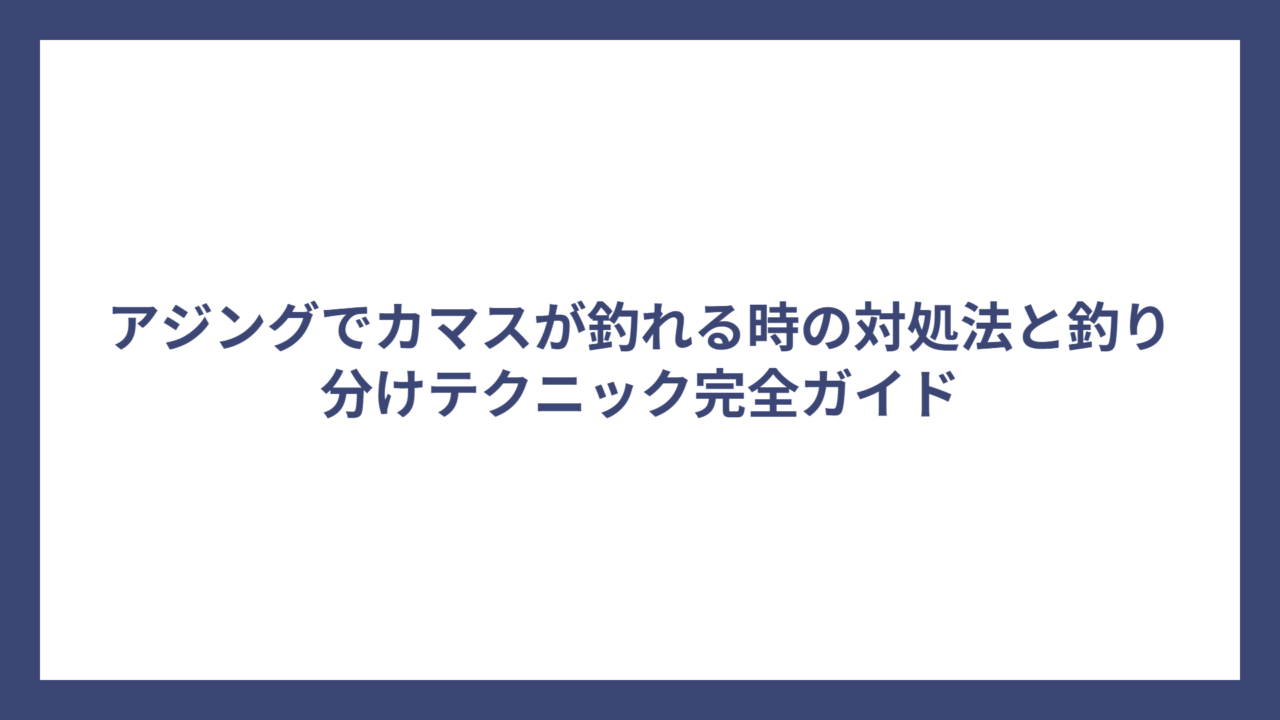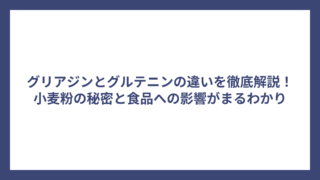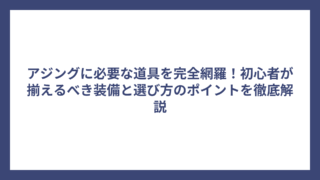アジングを楽しんでいると、突然強烈な引きとともに現れる「カマス」。鋭い歯でリーダーを切られたり、ワームをズタボロにされたりと、厄介なゲストとして扱われがちですが、実は戦略次第で効率的に釣り分けることができます。アジング装備をそのまま活用しながらカマスゲームを楽しむ方法や、カマスが混じるエリアでアジを狙い続けるための対策まで、実践的なテクニックが数多く存在します。
本記事では、インターネット上に散らばるアングラーたちの実釣情報を収集・分析し、アジングとカマスの関係性について多角的に解説していきます。リーダーの太さ調整からワームの選択、時合いの見極め方、さらにはコストを抑えながら効率よく釣るための小技まで、幅広い情報を網羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジングでカマスが釣れる理由と混じるパターンの理解 |
| ✓ カマス対策のリーダー・仕掛け・ワームの選び方 |
| ✓ アジングタックルを活用した効率的なカマス狙いのテクニック |
| ✓ カマスとアジを状況に応じて釣り分ける実践的方法 |
アジングでカマスが混じる理由と基本対策
- アジングでカマスが釣れるのは夜間の常夜灯周りが多い
- カマス対策はリーダーを5lb以上に太くすることが基本
- ジグヘッドの重さは1.5g~3gがカマスに効果的
- ワームはシャッドテール系やピンテール系が反応良好
- フォール主体よりも巻きの釣りがカマス狙いには有効
- カマスの歯によるラインブレイクを防ぐスナップ活用法
アジングでカマスが釣れるのは夜間の常夜灯周りが多い
アジングの定番ポイントである常夜灯周りは、実はカマスにとっても絶好のフィーディングエリアです。光に集まる小魚を狙って、カマスも活発に捕食活動を行います。特に秋から冬にかけてのシーズンは、カマスの接岸時期と重なるため、アジング中にカマスが混じる確率が格段に高まります。
常夜灯の色によってもカマスの行動パターンは変化するとされています。一般的に白色の明かりの場合は明暗の境目付近、オレンジ色の明かりの場合は明るいエリアにカマスが潜んでいることが多いようです。これはベイトフィッシュの集まり方と連動しており、カマスはその捕食に有利なポジションを取ります。
夜間のアジングでカマスが釣れるもう一つの理由は、カマスの視覚能力の高さにあります。カマスは目が良く、薄暗い環境でも小魚を捕食できる能力を持っています。そのため、アジング用の小さなワームやジグヘッドにも積極的に反応し、時にはアジ以上の高活性を見せることがあります。
フグ、ベラ、そして「カマス」。どれも鋭い歯を持つライトゲームのゲストで、3lb・4lbくらいの細いリーダーならば噛み切ることがある。たまに釣れるくらいならば大きな問題にならないが、カマスはわっと大群で入ってくるタイミングがあり、入れ食い状態、投げてはリーダーが切られるとなると、たいへん困る。
上記の引用からもわかるように、カマスは大群で回遊する習性があります。一匹釣れたら次々とヒットが続くパターンが多く、「カマス一匹底千匹」という表現がぴったりの状況になることも珍しくありません。このような群れの回遊パターンを理解しておくことで、アジングとカマス釣りを効率的に使い分けることができるようになります。
デイアジングではフグやベラといった昼行性の魚が厄介ですが、ナイトアジングにおけるカマスは避けがたいターゲットと言えるでしょう。ただし、カマスが混じること自体は決してマイナスではなく、考え方を変えればアジング装備で楽しめる新たなゲームフィッシングの機会とも捉えられます。
カマス対策はリーダーを5lb以上に太くすることが基本
アジングでカマスが混じるエリアで釣りを続ける場合、最も効果的で簡単な対策はリーダーの号数を上げることです。通常のアジングでは3lb~4lb程度のフロロカーボンリーダーを使用することが多いですが、カマス対策としては5lb~6lbに太くすることが推奨されます。
🎣 カマス対策リーダーの太さ比較
| 状況 | リーダー強度 | 太さ | 用途 |
|---|---|---|---|
| 通常のアジング | 3lb~4lb | 0.8号~1.0号 | 小型アジメイン |
| カマスが時々混じる | 5lb | 1.2号 | バランス型 |
| カマス高活性 | 6lb | 1.5号 | カマス優先 |
| 尺アジ・チヌ混じり | 5lb~8lb | 1.2号~2.0号 | 大物対応 |
5lbというリーダーの太さは、実は尺アジ(30cm以上のアジ)やキビレ・クロダイが混じるポイントで使用するスタンダードな号数でもあります。つまり、アジングアングラーとしては必ず持っておきたい号数であり、カマス対策のためだけに特別な準備が必要というわけではありません。
リーダーを太くすることで得られるメリットは、単にラインブレイクを防ぐだけではありません。カマスの鋭い歯による摩擦ダメージに耐えられることはもちろん、やり取りの際にドラグを締め気味にして素早く取り込むことが可能になります。これにより、一匹あたりの釣り時間が短縮され、回遊してきたカマスの群れを効率的に釣ることができます。
高活性でカマスばかりになる時には、6lbまで上げるという選択肢もあります。特に秋の消波ブロック帯からオープンに投げるアジングで、カマスや大型カサゴが混じる場合には、この太さが安心感を与えてくれます。ただし、リーダーを太くしすぎると、アジの繊細なアタリを感じにくくなる可能性もあるため、バランスを見極めることが重要です。
リーダーの交換頻度も考慮すべきポイントです。カマスの歯で傷ついたリーダーは、見た目には問題なくても強度が低下している可能性があります。数匹釣ったら先端部分をカットして結び直すか、定期的に交換することで、不意のラインブレイクを防ぐことができます。
ジグヘッドの重さは1.5g~3gがカマスに効果的
アジングでカマスを狙う際、ジグヘッドの重さ選択は釣果を大きく左右する要素です。通常のアジングでは0.6g~1.5g程度の軽量ジグヘッドを使用することが多いですが、カマスを効率的に狙う場合は1.5g~3g、場合によっては5g~7gのやや重めのジグヘッドが有効です。
重めのジグヘッドを使用する理由は複数あります。第一に、飛距離の向上です。カマスは沖目を回遊していることが多く、軽いジグヘッドでは届かないレンジにいることがあります。重めのジグヘッドなら遠投が可能になり、広範囲を探ることができます。
✅ ジグヘッドの重さと用途
- 0.6g~1g:繊細なアジング、スローフォール
- 1.5g~2g:汎用性が高い、アジ・カマス両対応
- 3g:カマス狙い、遠投重視
- 5g~7g:大型カマス、潮流が速いエリア
第二に、フォールスピードの調整です。カマスはアジよりも速いフォールに反応することが多く、重めのジグヘッドによる素早い沈下がバイトを誘発します。特に底付近にカマスの群れがいる場合、速いフォールで底を取り、そこからのリフト&フォールや巻きで誘うパターンが効果的です。
ジグ単の重量を重くしてフォールスピードを速くする。針のシャンクを長くするやスナップをつけて、歯で切られにくくする。この辺の効率を上げた方が良いと思います。一回結び直すとかが1番時間かかります。
上記のように、効率を重視するアングラーは重めのジグヘッドを推奨しています。カマスの群れが回遊している時合いは限られており、その短い時間内にできるだけ多く釣るためには、手返しの良さが重要になります。
ただし、重すぎるジグヘッドはアジングロッドのティップに負担をかける可能性があります。使用するロッドの適合ウェイトを確認し、範囲内で使用することが大切です。また、ジグヘッドのフック形状も重要で、カマスの口は硬いため、針先が鋭く貫通力の高いものを選ぶと、フッキング率が向上します。
タングステン素材のジグヘッドを使用するのも一つの選択肢です。タングステンは鉛よりも比重が高いため、同じ重さでもコンパクトなシルエットになり、飛距離と沈下速度を両立できます。価格は高めですが、カマス狙いには投資する価値があるでしょう。
ワームはシャッドテール系やピンテール系が反応良好
カマス狙いのワーム選択は、アジング用ワームの延長線上で考えることができますが、いくつかの重要なポイントがあります。カマスはテール部分の動きに強く反応する傾向があり、シャッドテール系やピンテール系といった、巻いた時にテールがアクションするワームが特に効果的です。
ダイソーのシャッドテールワームがカマスに非常に効果的であるという情報が複数の釣行記録で確認できます。価格が安いため、カマスの歯でワームがダメージを受けてもコストを気にせず使えるというメリットがあります。カマスは一投ごとにワームを損傷させることが多いため、コストパフォーマンスは重要な要素です。
🎯 カマスに効果的なワームの特徴
| 特徴 | 理由 |
|---|---|
| テールアクション | 視覚的アピールが強い |
| 1.7~2.5インチ | カマスの口に入りやすいサイズ |
| クリア系カラー | ベイトフィッシュを模倣 |
| ピンテール | ナチュラルなアクション |
| シャッドテール | 強めの波動でアピール |
ワームは レインさん アジアダー フィッシング遊オリカラ の 「ミスティア」 チビキャロスワンプ 「必殺イワシ」 などが反応よかったです。
ワームのカラー選択については、クリア系や金粉入りといった、ベイトフィッシュを模倣したナチュラルカラーが基本です。特に夜間の常夜灯周りでは、光を透過するクリア系が効果的とされています。ただし、濁りがある場合や活性が低い時は、チャート系やオキアミカラーといった視認性の高いカラーも試す価値があります。
ワームのサイズについては、1.7インチ~2.5インチ程度が使いやすいでしょう。大きすぎるワームはカマスの口に入りにくく、フッキング率が下がります。逆に小さすぎるとアピール力が不足する可能性があります。カマスのサイズに応じて調整することが理想的ですが、迷った場合は2インチ前後を基準にすると良いでしょう。
ワームの耐久性を高める方法として、アロンアルファーでジグヘッドに固定するテクニックがあります。これにより、カマスのショートバイトでワームがズレることを防ぎ、手返しが向上します。接着剤を使用する場合は、針先に接着剤が付かないよう注意が必要です。
フォール主体よりも巻きの釣りがカマス狙いには有効
アジングの基本はフォール主体の釣りですが、カマスを効率的に狙う場合は、巻きの釣りが有効なケースが多いです。カマスは遊泳力が高く、動くものに対して積極的に追いかけて捕食する習性があります。そのため、ただ巻きやリトリーブ中心の釣り方が、フォールよりも反応を得やすい傾向にあります。
具体的な巻きのパターンとしては、キャスト後に底まで沈め、そこから一定速度でのリトリーブが基本です。巻き速度は、ゆっくりから速めまで、その日のカマスの活性に応じて調整します。一般的には、アジングよりもやや速めの巻きが効果的とされており、「リアクション的な逃げる小魚の演出」がカマスの捕食スイッチを入れると考えられています。
ジグヘッドにグラスミノーの小さいの付けて引いてみて。簡単に釣れます。尻尾がピロピロ動くワームが効きますよ。口が硬いのでフッキングがちょっと悪いですが。
巻きの釣りにバリエーションを持たせることも重要です。例えば、「巻き+チョンチョンアクション」という組み合わせは、ロッドティップを小刻みに動かしながら巻くことで、ワームに不規則な動きを与えます。このアクションがカマスの捕食本能を刺激し、バイトを誘発します。
フォール主体の釣りが完全に無効というわけではありません。状況によっては、フォール中にバイトが集中することもあります。重要なのは、フォールと巻きの両方を試し、その日のカマスの反応パターンを見極めることです。群れが回遊してきた初期段階ではフォールが効き、活性が上がるにつれて巻きが効くといったパターンも考えられます。
巻きの釣りのもう一つのメリットは、広範囲を効率的に探れることです。フォール主体だとどうしても縦方向の動きが中心になりますが、巻きの釣りは横方向の広い範囲をカバーできます。カマスの群れがどこにいるかわからない状況では、まず巻きで探り、反応があったレンジを重点的に攻めるという戦略が有効でしょう。
カマスの歯によるラインブレイクを防ぐスナップ活用法
カマスの最大の特徴である鋭い歯は、釣り人にとって厄介な存在です。リーダーを太くしても完全には防げないラインブレイクに対して、スナップを活用することで大幅にトラブルを減らすことができます。
スナップをジグヘッドとリーダーの間に挟むことで、金属部分がカマスの歯による攻撃を受け止めてくれます。特にショートバイトが多い状況では、ワームの先端部分ではなくジグヘッド付近に歯が当たることがあり、この時にスナップがあるとリーダーが守られます。
🔧 スナップ使用のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✓ 歯による切断を防ぐ | ✗ 若干の重量増加 |
| ✓ ワーム交換が素早い | ✗ アクションへの影響 |
| ✓ リーダー結び直しの頻度減少 | ✗ 小型スナップは破損リスク |
| ✓ 手返しの向上 | ✗ 繊細なアジングには不向き |
スナップのサイズ選択も重要です。大きすぎるスナップはワームのアクションを阻害し、重量が増してティップに負担をかけます。逆に小さすぎるスナップは、カマスとのやり取り中に破損する可能性があります。一般的には、アジング用の小型スナップよりも一回り大きいサイズが、カマス対策には適していると言えるでしょう。
スナップを使用する際の注意点として、結束強度の確保があります。スナップとリーダーの接続部分は、最も負荷がかかるポイントです。ユニノットやクリンチノットといった信頼性の高い結び方を選び、結束後は必ず引っ張って強度を確認しましょう。
また、スナップを使用することで、ワームの交換が非常にスムーズになるというメリットもあります。カマスは一投ごとにワームにダメージを与えるため、頻繁な交換が必要です。スナップがあれば、いちいちリーダーを結び直す必要がなく、時合いを逃さず釣り続けることができます。
針のシャンク(軸の長い部分)が長いジグヘッドを選ぶことも、歯による切断を防ぐ有効な手段です。シャンクが長ければ、カマスの歯がリーダーに届きにくくなります。ただし、シャンクが長すぎるとフッキングが決まりにくくなる可能性もあるため、バランスを考慮して選択しましょう。
カマスを効率的に狙うアジングタックル活用術
- キャロライナリグでの遠投がカマスの群れに効く
- 時合いは朝夕マズメが最も活性が高い
- カマスの群れは底から中層を回遊する
- アジングロッドでカマスを釣る際の注意点
- カマスとアジを釣り分ける方法
- ワームの消耗を抑えるアロンアルファ固定テクニック
- まとめ:アジングでカマスを楽しむためのポイント
キャロライナリグでの遠投がカマスの群れに効く
アジングでカマスを狙う際、より効率的にアプローチできる仕掛けがキャロライナリグ(Mキャロ)です。通常のジグ単(ジグヘッド単体)では届かない沖目のポイントや、底付近を広範囲に探りたい時に威力を発揮します。
キャロライナリグの基本構造は、メインラインに重めのシンカー(キャロシンカー)を通し、スイベルを介してリーダーとジグヘッドを接続するものです。シンカーの重さは5g~22g程度まで幅広く、ポイントの水深や潮流、飛距離によって選択します。カマス狙いの場合は、10g~15g程度が使いやすいとされています。
🎣 キャロライナリグのセッティング例
| パーツ | 仕様 | 役割 |
|---|---|---|
| メインライン | PE0.3~0.6号 | 飛距離確保 |
| キャロシンカー | 5~22g | 遠投・沈下速度調整 |
| スイベル | ラクリップ推奨 | 絡み防止 |
| リーダー | 5~6lb、30~50cm | カマスの歯対策 |
| ジグヘッド | 0.4~1.5g | アクション付与 |
ティクトのミニMキャロ5.0gに、アジスタのM、0.4gをラクリップを使ってセット。ワームは、ギョピンの1.7インチ、どクリアを選択。キャストして底を取り、巻き上げながら、チョンチョンとアクションを入れます。「コココンッ!!」鋭いカマスのアタリが楽しいです
キャロライナリグの最大のメリットは飛距離です。ジグ単では4色(約40m)程度が限界だったポイントも、キャロを使えば7色(約70m)以上の遠投が可能になります。カマスの群れは沖目を回遊していることも多く、この飛距離の差が釣果に直結するケースは少なくありません。
もう一つのメリットは、レンジキープのしやすさです。重いシンカーが先行して沈むため、ジグヘッド部分は比較的ゆっくりとしたスピードで沈下します。これにより、カマスが回遊している底~中層のレンジをより長い時間探ることができます。特にドシャロー(浅い)エリアでは、このレンジキープ能力が釣果を左右します。
キャロライナリグでの釣り方は、キャスト後に底を取り、そこからゆっくりと巻き上げながらロッドティップで小刻みにアクションを加える方法が基本です。シンカーが底を叩く感覚を感じながら、ジグヘッドとワームが底から少し浮いた状態を維持するイメージで操作します。
ただし、キャロライナリグにもデメリットはあります。仕掛けが複雑になるため、準備や結び直しに時間がかかります。また、感度が若干低下するため、繊細なアジのアタリは取りにくくなる可能性があります。状況に応じてジグ単とキャロを使い分けることが、効率的なカマス狙いの鍵となるでしょう。
時合いは朝夕マズメが最も活性が高い
カマスの活性が最も高まる時間帯は、朝マズメと夕マズメです。この時間帯は光量が変化するタイミングであり、ベイトフィッシュの活動も活発になるため、それを捕食するカマスも積極的にフィーディングを行います。
朝マズメは特に釣果が期待できる時間帯です。日の出前後の1~2時間は、カマスが群れで接岸し、爆発的な釣果につながることがあります。釣り場によっては、この時間帯だけで30匹以上釣れたという報告も珍しくありません。ただし、人気ポイントでは早朝から多くの釣り人が集まるため、場所取りが課題となることもあります。
朝6時に太陽光で光量が変化した時間帯から釣れ始め、8時半あたりにいったん朝マヅメパワーが終了しました。それまで継続してアタリがありました。「みんな釣れすぎて、釣り人が帰る。」「カマス一匹底千匹!継続中!」
夕マズメも朝マズメに劣らず有望な時間帯です。日没前後の時間は、昼間は沖にいたカマスが岸寄りしてくるタイミングと重なります。仕事帰りに釣行する場合は、この夕マズメを狙うことになるでしょう。朝マズメに比べて釣り人が少ない傾向にあり、ゆったりと釣りを楽しめる可能性があります。
⏰ カマスの時合いパターン
| 時間帯 | 活性度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日の出前~日の出後1時間 | ★★★★★ | 最高の時合い、群れの接岸 |
| 午前中 | ★★☆☆☆ | 徐々に活性低下 |
| 日中 | ★☆☆☆☆ | 活性低い、沖目に移動 |
| 日没前~日没後1時間 | ★★★★☆ | 活性上昇、岸寄り開始 |
| 夜間 | ★★★☆☆ | 常夜灯周りで釣れる |
潮の動きも時合いに影響を与えます。満潮前後の上げ潮や、干潮前後の下げ潮といった、潮が動いているタイミングが一般的に有利とされています。潮が動くことでベイトフィッシュが活性化し、それに連動してカマスも捕食モードに入ります。
ただし、必ずしもマズメだけが時合いというわけではありません。夜間の常夜灯周りでも、カマスの群れが回遊してくれば入れ食い状態になることがあります。特に秋から冬にかけてのシーズンは、夜間でも安定して釣果が期待できるようです。
時合いを最大限に活かすためには、事前の準備が重要です。タックルセッティングを済ませ、ワームやリーダーの予備を準備し、時合いの時間帯には釣りに集中できる状態を作りましょう。時合いは短時間で終わることも多く、その貴重な時間をトラブル対応で無駄にしないよう注意が必要です。
カマスの群れは底から中層を回遊する
カマスを効率的に釣るためには、カマスが回遊するレンジ(水深帯)を理解することが不可欠です。一般的に、カマスは底付近から中層を群れで回遊することが多く、表層を意識することは少ないと言われています。この習性を知っていれば、無駄な投数を減らし、効率的に釣果を上げることができます。
底を重点的に探ることがカマス狙いの基本戦略となります。キャスト後はしっかりと底を取り、そこから巻き上げるか、底付近でアクションさせることで、カマスのバイトを誘います。底を取る感覚が掴めない場合は、ジグヘッドの重さを重くするか、ラインの出方を観察して着底のタイミングを見極めましょう。
カマスはやはり底を中心にいるので、キャスト後は着底させて、その後にタダ巻でした。巻き速度はけっこうゆっくり巻きましたが、他のジグヘッドのみの方々は早巻きでけっこう早い印象です。
ただし、カマスが常に底にいるわけではありません。活性が上がると中層まで浮いてくることもあります。底で反応が薄い場合は、カウントダウン方式でレンジを変えながら探ることが有効です。例えば、キャスト後に10秒カウントして巻き始め、反応がなければ次は8秒、6秒と短くしていくことで、カマスがいるレンジを特定できます。
群れの回遊パターンも把握しておくと有利です。カマスは一定のルートを回遊する習性があり、一度釣れたポイントには再び群れが回ってくる可能性が高いです。そのため、一箇所で粘るのではなく、複数のポイントをローテーションしながら探る戦略も効果的でしょう。
🐟 カマスのレンジ別攻略法
- 底付近:最も基本的なレンジ。着底後のリフト&フォールや底ズル引きが効果的
- 底~中層:カマスが活性化している証拠。巻きのスピードを上げて反応を見る
- 中層:高活性時や追い食いパターン。連続ヒットのチャンス
- 表層:あまり期待できない。表層で反応があったら青物の可能性も
水深の浅いエリアでは、必然的にカマスのレンジも浅くなります。堤防の足元や消波ブロック周りなど、水深3~5m程度のポイントでは、底から1~2mのレンジを重点的に探ることになります。逆に、水深のあるポイントでは、底を取るまでに時間がかかるため、重めのジグヘッドやキャロライナリグが有効になります。
カマスの群れが回遊してきた瞬間は、周囲のアングラーの動きでわかることがあります。それまで静かだったポイントで急に複数人が立て続けにヒットし始めたら、群れが入ってきたサインです。このタイミングを逃さず、同じレンジ・同じ釣り方で攻めることで、効率的に釣果を伸ばすことができます。
アジングロッドでカマスを釣る際の注意点
アジングロッドでカマスを釣ることは十分可能ですが、いくつか注意すべきポイントがあります。アジングロッドは繊細なアタリを感じ取るために設計されており、カマスのような引きの強い魚には若干オーバースペック、または逆にアンダースペックになる可能性があります。
まず、ロッドのパワーとティップの硬さを確認しましょう。一般的なアジングロッドはL(ライト)クラスやUL(ウルトラライト)クラスが多く、小型カマス(20cm前後)なら問題なく対応できます。しかし、30cm以上の良型カマスになると、ロッドが負けてしまい、十分にフッキングが決まらないケースがあります。
🎣 アジングロッドのパワー別適合魚種
| ロッドパワー | 適合ジグヘッド | カマス対応 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| UL(ウルトラライト) | 0.3~1.5g | 小型のみ | 繊細な釣り向き |
| L(ライト) | 0.5~3g | 中型まで | アジング標準 |
| ML(ミディアムライト) | 1~5g | 大型対応 | カマス・メバル兼用 |
カマスは口が硬く、しっかりとしたフッキング動作が必要です。柔らかすぎるロッドだと、アワセを入れても針が貫通せず、バラシにつながることがあります。この問題に対しては、ロッドのティップがやや硬めのRF(レギュラーファースト)テーパーや、ML(ミディアムライト)パワーのロッドを選ぶことで改善できます。
22 ディアルーナB96ML は若干 カマス には固くてオーバースペックだったかも。30㎝ぐらいの カマス での余裕がある。でも十分曲がって楽しめた。カマス が相手ならもっと柔いロッドの方が楽しめそう。
ロッドの長さも考慮すべき要素です。アジングロッドは6フィート前後が標準的ですが、カマス狙いで遠投が必要な場合は7~8フィート程度の長めのロッドが有利です。長いロッドは飛距離が出やすく、カマスの群れが沖目にいる状況では大きなアドバンテージとなります。
ドラグ設定も重要です。アジング用に緩めに設定していると、カマスの強い引きに対応できず、走られ過ぎてバラシにつながることがあります。カマスが混じる状況では、ドラグをやや締め気味にして、素早く取り込む戦略が有効です。ただし、締めすぎるとラインブレイクのリスクが高まるため、バランスを見極めましょう。
ロッドの破損リスクにも注意が必要です。カマスは予想外の方向に走ることがあり、無理な角度でロッドを曲げると破損の原因になります。特にティップ部分は繊細なので、カマスとのファイト中はロッドを立てすぎず、適度な角度を保つことが大切です。
カマスとアジを釣り分ける方法
同じポイントでカマスとアジが混在している状況では、ターゲットを釣り分けるテクニックが役立ちます。完全に分離することは難しいですが、仕掛けやアプローチ方法を変えることで、ある程度狙いを絞ることが可能です。
アジを優先的に釣りたい場合は、軽量ジグヘッド(0.6~1g)とスローフォールが基本です。アジは警戒心が強く、ゆっくりとナチュラルに落ちてくるワームに反応する傾向があります。カマスは速い動きにも反応しますが、アジはスローな展開を好むため、この差を利用します。
逆にカマスを優先的に狙いたい場合は、重めのジグヘッド(2~5g)と巻きの釣りを選択します。前述の通り、カマスは活発に泳ぐベイトを追いかける習性があるため、リトリーブ主体の釣りが効果的です。アジはこの速い動きにはあまり反応しないため、結果的にカマスの割合が増えます。
🎯 アジとカマスの釣り分け戦略
| ターゲット | ジグヘッド | アクション | レンジ | ワームサイズ |
|---|---|---|---|---|
| アジ優先 | 0.6~1g | スローフォール | 中層~表層 | 1.5~2インチ |
| カマス優先 | 2~5g | 巻き・速いフォール | 底~中層 | 2~2.5インチ |
| 両方狙う | 1~1.5g | フォール+巻き | 全レンジ探る | 2インチ前後 |
ワームのカラーでも差別化を図ることができます。アジはクリア系やホワイト系といったナチュラルカラーを好む傾向があり、カマスは金粉入りやシルバー系といったフラッシング効果のあるカラーにも反応します。ただし、これはあくまで傾向であり、日によって逆転することもあるため、現場での試行錯誤が必要です。
釣る時間帯による棲み分けも考えられます。アジは夜間の常夜灯周りで安定して釣れますが、カマスは朝夕マズメに活性が上がります。朝マズメにカマスを狙い、夜間はアジングに専念するといった、時間帯でターゲットを変える戦略も有効でしょう。
群れの回遊パターンを観察することも重要です。カマスの群れが入ってきたタイミングでは、しばらくカマスばかりが釣れる状況になります。この時は無理にアジを狙わず、カマスゲームを楽しむ方が効率的です。群れが去った後に再びアジングに戻るという、柔軟な対応が釣果を最大化する鍵となります。
ワームの消耗を抑えるアロンアルファ固定テクニック
カマス釣りにおける最大のコスト要因は、ワームの消耗です。カマスの鋭い歯は、一投ごとにワームにダメージを与え、時には一投目で尻尾だけ持っていかれることもあります。この問題に対する効果的な解決策が、アロンアルファー(瞬間接着剤)を使ったワーム固定テクニックです。
この方法は非常にシンプルで、ジグヘッドにワームをセットする際、接合部分に少量のアロンアルファーを塗るだけです。接着剤が固まることで、ワームがジグヘッドからズレにくくなり、カマスのショートバイトでもワームが無駄にならなくなります。
✅ アロンアルファー固定のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✓ ワームのズレを防止 | ✗ ワーム交換に時間がかかる |
| ✓ 手返しが向上 | ✗ 接着剤の乾燥を待つ必要 |
| ✓ コスト削減 | ✗ 針先に付くと危険 |
| ✓ 短いワームも最後まで使える | ✗ ワームが硬くなる可能性 |
後、当たりでワームずれて無駄もあるので、アロンアルファーで着けるも効果的です。乗らなくても、ワームずれないので直ぐに次が食います。
アロンアルファーを使用する際の注意点がいくつかあります。まず、針先に接着剤が付かないよう細心の注意を払うことです。針先に接着剤が付くと、フッキング性能が著しく低下します。また、手指に付くと非常に取れにくいため、作業中は慎重に扱いましょう。
接着剤の量も重要です。多すぎるとワームが硬くなり、本来のナチュラルなアクションが損なわれます。少量を接合部分に塗り、軽く押さえて固定する程度が理想的です。塗りすぎた場合は、余分な接着剤を拭き取ってから使用しましょう。
アロンアルファー以外の方法として、ワームキーパーが優れたジグヘッドを選ぶという選択肢もあります。リューギのジグヘッド ヴェスパなど、ワームキーパーの形状が工夫されている製品は、接着剤なしでもワームのズレを最小限に抑えることができます。これらの製品は価格が高めですが、耐久性とワームの持ちを考慮すれば、投資する価値があるかもしれません。
ダイソーなどの安価なワームを使用することも、コスト削減の有効な戦略です。高級ワームを使って一投で無駄にするよりも、安価なワームをアロンアルファーで固定して複数回使う方が、トータルコストは抑えられます。釣果に大きな差がない場合は、コストパフォーマンスを優先する判断も賢明でしょう。
ワームの保管方法にも工夫の余地があります。使用後のワームは、洗って塩分を落としてから保管することで、劣化を遅らせることができます。また、直射日光を避け、密閉容器で保管することで、ワームの寿命を延ばすことができます。
まとめ:アジングでカマスを楽しむためのポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングでカマスが釣れるのは、夜間の常夜灯周りや朝夕マズメが多く、カマスは大群で回遊する習性がある
- カマス対策の基本はリーダーを5lb~6lb(1.2号~1.5号)に太くすることで、ラインブレイクを大幅に減らせる
- ジグヘッドは1.5g~3g程度の重めを選ぶことで、飛距離とフォールスピードの両面でカマス狙いに有利になる
- ワームはシャッドテール系やピンテール系が効果的で、サイズは1.7~2.5インチが使いやすい
- フォール主体よりも巻きの釣りがカマスには効果的で、速めのリトリーブがバイトを誘発する
- スナップを使用することで、カマスの歯によるラインブレイクを防ぎ、ワーム交換も素早くできる
- キャロライナリグを使えば、ジグ単では届かない沖目のカマスの群れにアプローチできる
- 時合いは朝マズメと夕マズメが最も有望で、この時間帯に集中的に狙うのが効率的である
- カマスの群れは底から中層を回遊するため、着底後の巻き上げやリフト&フォールが基本戦術となる
- アジングロッドでカマスを釣る際は、ドラグ設定を締め気味にし、ロッドの破損に注意しながらファイトする
- カマスとアジを釣り分けるには、ジグヘッドの重さとアクションの速さを調整することが重要である
- アロンアルファーでワームを固定することで、ワームの消耗を抑え、手返しを向上させられる
- カマスは食べても美味しい魚であり、塩焼きや天ぷらなど様々な調理法で楽しめる
- 群れの回遊パターンを理解し、時合いを逃さず効率的に釣ることがカマスゲームの鍵となる
- 安価なダイソーワームを使用することで、コストを抑えながらカマス釣りを楽しむことができる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- アジング釣行の厄介なゲスト「カマス」対策 タチウオにはお手上げ? | TSURINEWS
- 【楽しむ】アジ!カマス!根魚!釣れる魚は何でも釣る! | 釣具のポイント
- アジングゲームで35cm頭にカマス爆釣 気づけばカマスゲームに夢中 | TSURINEWS
- 続・カマス好調です!アジングでヒット! | フィッシング遊
- アジングタックルでカマスゲーム | STAFFのブログ
- カマス釣り!アジングキャロとベイトタックルで! – gagarablog’s
- アジングロッドでカマスを釣る!! | メッキを釣る!!
- カマス釣り!アジングキャロとベイトタックルで! – gagarablog’s
- でかカマス用ジグヘッドの小細工 | ちょいとアジング行こ
- アジングをしていてカマスが釣れることがあります。カマスが釣れるならカマスを優先… – Yahoo!知恵袋
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。