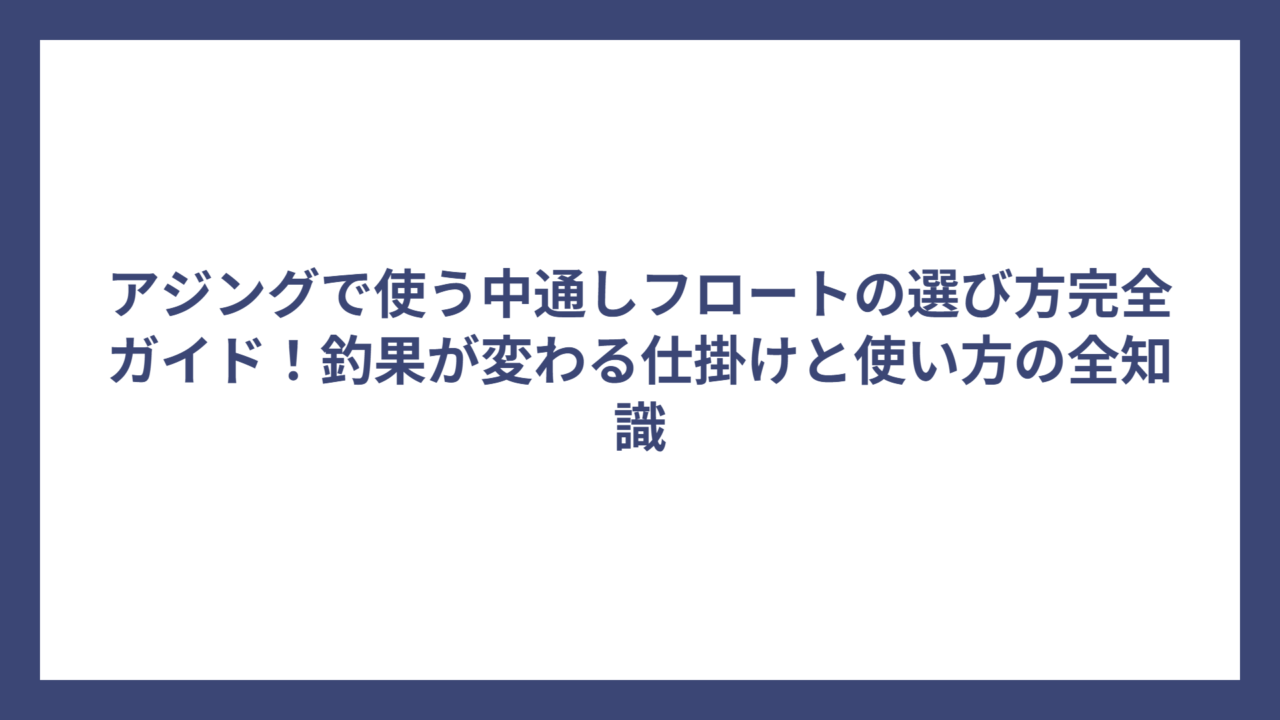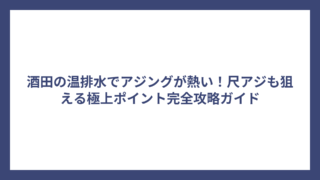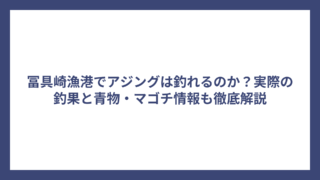アジングでジグ単では届かない沖のポイントを攻略したい――そんな時に活躍するのが「中通しフロート」です。軽量ジグヘッドでは到達できない遠距離のポイントへアプローチできる中通しフロートは、サーフアジングや大型アジ狙いに欠かせないアイテムとなっています。しかし、フロートにも中通しタイプと固定式タイプがあり、それぞれに特徴があります。
この記事では、インターネット上に散らばるアジングのフロートリグに関する情報を収集・整理し、特に中通しフロートに焦点を当てて、その選び方から仕掛けの作り方、実釣での使い方まで徹底的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、基礎知識から実践的なテクニックまで、段階的にご紹介していきます。
この記事のポイント | ✓ 中通しフロートと固定式フロートの違いと使い分け方法<br>✓ 中通しフロートリグの正しい仕掛けの組み方と必要なパーツ<br>✓ 重さや浮力の選び方とシチュエーション別の使い分け<br>✓ 実釣での操作方法とトラブル回避のコツ |
アジングにおける中通しフロートの基礎知識と選び方
- アジングで中通しフロートを使うメリットは操作性と食い込みの良さ
- 中通しフロートと固定式フロートの違いは自由度と感度にある
- 中通しフロートの重さは7~10gが標準的
- ぶっ飛びRockerⅡは中通しフロートの定番モデル
- フローティングとシンキングの使い分けが釣果を左右する
- かっ飛びボールは初心者におすすめの光る中通しフロート
アジングで中通しフロートを使うメリットは操作性と食い込みの良さ
中通しフロートの最大の特徴は、ライン上をフロートが自由に動く誘導式の構造にあります。この構造により、アジがワームに食いついた際、フロートがラインを滑るため魚に与える違和感が軽減されます。固定式フロートと比較すると、フッキング率の向上が期待できるでしょう。
複数の釣り情報サイトでは、中通しフロートのメリットとして以下の点が挙げられています。まず、フロート越しにジグヘッドを操作できるため、リフト&フォールを生かした縦の釣りが可能になります。藻場や沈み磯、ストラクチャー周りなどをピンポイントに攻める釣りに適しているのです。
また、他のリグとの相性も良く、状況に応じてキャロライナリグやスプリットショットリグなどへの変更がしやすいという利点もあります。特に、ピンスポットの縦の釣りを演出したい場合や、他のリグとの流用が必要なシチュエーションでは中通し式のフロートリグが効果的と言えます。
さらに、渋い時やアフターのメバル・アジなどにも有効で、食い込みの良さからバイトチャンスを逃しにくいというメリットも見逃せません。ただし、若干組むのに時間がかかるという点は留意しておく必要があります。
📊 中通しフロートの主なメリット
| メリット | 詳細説明 |
|---|---|
| 食い込みの良さ | フロートが誘導式のため、魚に違和感を与えにくい |
| 縦の釣りが可能 | フロート越しにジグヘッドを操作できる |
| 汎用性の高さ | 他のリグへの変更や流用がしやすい |
| 渋い状況に強い | 食い渋り時でもバイトチャンスを増やせる |
| ピンスポット攻略 | ストラクチャー周りなどの攻略に最適 |
一方で、固定式(直結タイプ)と比較すると遠投性能では劣るという側面もあります。キャスト時にフロートが先行して飛んでいく固定式の方が、飛距離は伸びる傾向にあります。そのため、可能な限りの遠投が有効的なポイントでは固定式(Fシステム)が選ばれることが多いようです。
中通しフロートと固定式フロートの違いは自由度と感度にある
フロートリグには大きく分けて中通しタイプと固定式(直結)タイプの2種類が存在します。それぞれに明確な特徴があり、釣り場の状況や狙いたい釣り方によって使い分けることが重要です。
中通し式、固定式。それぞれのフロートリグシステム
一つは【ぶっ飛びRocker】を使用した最も一般的な中通し式のフロートリグシステム。もう一つが、弊社ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の【シャローフリーク】を使用した【Fシステム】という固定式フロートリグシステムです。
固定式(Fシステム)の大きな特徴として、キャスト時にフロートが先行するカタチで飛行するため、中通し式よりも飛距離が伸びる点が挙げられます。また、フロートがジグヘッドに干渉することを抑えることができるので、沖の表層付近でジグヘッド単体リグのようなアクションを演出できます。さらに感度が向上し、フッキングレスポンスに長けるという利点もあります。
一方、固定式のデメリットとしては、シャローフリークのような製品の場合、本体の残浮力が低いことで、残浮力以上のウエイトのジグヘッドを使用した際にリグが沈下してしまう点や、その特異なリグシステムが他リグへ応用しづらいという意見もあるようです。
対して中通し式フロートは、ウエイトキャパシティーが低いロッドでも使用できるサイズラインナップがあり、SS(スローシンキング)モデルが規格品で存在するため、フロートのローテーションを簡単に行えます。また、リグシステムが他のリグへ変更しやすく、様々なシチュエーションに対応しやすいという特徴があります。
🎯 中通し vs 固定式の比較マトリクス
| 項目 | 中通しタイプ | 固定式タイプ |
|---|---|---|
| 飛距離 | △ やや劣る | ◎ 優れている |
| 感度 | ○ 良好 | ◎ 非常に良好 |
| 食い込み | ◎ 非常に良い | ○ 良い |
| 操作性 | ◎ リフト&フォール◎ | ○ 表層の釣り◎ |
| 汎用性 | ◎ 他リグへの変更容易 | △ やや限定的 |
| 初心者向け | ○ 比較的扱いやすい | △ やや慣れが必要 |
実際の使い分けとしては、遠投性に優れたフロートリグが圧倒的に有利なフィールドであるゴロタなどへ出掛ける際には固定式(Fシステム)、水深があるポイントでのアジングなど、現状は水面直下に反応であっても、状況によってアプローチやリグを変更する可能性がある場合は中通し式のフロートリグが選ばれることが多いようです。
中通しフロートの重さは7~10gが標準的
中通しフロートを選ぶ際、最も重要な要素の一つが**重さ(ウェイト)**です。フロートの重さによって飛距離や操作性が大きく変わってくるため、釣り場の状況や使用するタックルに合わせた選択が求められます。
一般的なアジング用の中通しフロートは、4g~12g程度のラインナップが展開されています。初心者の方や標準的な釣り場で使用する場合、7~10g程度のフロートが最も扱いやすいと考えられます。この重量帯であれば、通常のアジングロッド(7~8ft)で問題なくキャストでき、適度な飛距離も確保できるでしょう。
アルカジックジャパンの「ぶっ飛びRockerⅡ」を例に取ると、M、L、LLの3サイズが展開されており、それぞれ重量と残浮力が異なります。Mサイズは約4.8~6.6g、Lサイズは約7.4~9.2g、LLサイズは約10.0~11.8gとなっています。初めてフロートリグに挑戦する方は、**Lサイズ(7~9g程度)**から始めるのが無難かもしれません。
📌 フロートの重さ選びのポイント
- ✅ 4~6g:軽量で近距離~中距離向け、操作性重視
- ✅ 7~10g:標準的な重さ、最も汎用性が高い
- ✅ 10g以上:遠投特化、サーフや大規模な釣り場向け
- ✅ ロッドのキャスト可能重量を確認すること
- ✅ 風や波の状況も考慮に入れる
重いフロートを使えば当然飛距離は伸びますが、ロッドのキャストウェイトを超えると破損の原因になります。特にフロートは空気抵抗が大きいため、通常のルアーよりもロッドへの負荷が大きくなる点に注意が必要です。アジング専用ロッドの多くは10~15g程度までの対応となっているため、自身のタックルスペックを確認してから選択しましょう。
また、サーフアジングのように風の影響を受けやすい場所では、ある程度重量のあるフロートの方が安定したキャストが可能になります。逆に、堤防など比較的風の影響が少ない場所では、軽めのフロートでも十分対応できるでしょう。
ぶっ飛びRockerⅡは中通しフロートの定番モデル
中通しフロートの中で特に高い人気と実績を誇るのが、**アルカジックジャパンの「ぶっ飛びRockerⅡ」**シリーズです。多くのアジングやメバリングアングラーに支持されているこのフロートには、どのような特徴があるのでしょうか。
「ぶっ飛びRockerⅡ」の最大の特徴は、低重心バランス設計にあります。これにより飛行姿勢が安定し、クルクルと回転することなく綺麗に飛んでいきます。また、前後にはSICリングが搭載されており、ラインの摩擦抵抗を最小限に抑え、スムーズな誘導を実現しています。
現行モデルは「ぶっ飛びRockerⅡ EVO」となっており、さらに飛行姿勢と水中での安定性を追究したボディー形状に進化しています。カラーは白色を基調としており、日中でも視認性が高く、フロートの位置を目で追いやすくなっています。
🎣 ぶっ飛びRockerⅡ EVOのスペック一覧
| サイズ | タイプ | 重量 | 残浮力 | 適合ジグヘッド目安 |
|---|---|---|---|---|
| M | HF | 4.8g | 1.5g | ~1.5g |
| M | F | 5.2g | 1.0g | ~1.0g |
| M | F0 | 6.3g | 0g | 0.4~0.6g |
| M | SS | 6.6g | マイナス | スローシンキング |
| L | HF | 7.4g | 1.5g | ~1.5g |
| L | F | 7.9g | 1.0g | ~1.0g |
| L | F0 | 8.9g | 0g | 0.4~0.6g |
| L | SS | 9.2g | マイナス | スローシンキング |
| LL | HF | 10.0g | 1.5g | ~1.5g |
| LL | F | 10.4g | 1.0g | ~1.0g |
| LL | F0 | 11.5g | 0g | 0.4~0.6g |
| LL | SS | 11.8g | マイナス | スローシンキング |
このように、重さと残浮力で12種類もの豊富なラインナップが用意されており、様々な状況に対応できます。特に注目すべきは**F0(エフゼロ)**タイプで、残浮力がゼロのため、軽量ジグヘッドと組み合わせることで、沖の潮に0.4gジグ単を乗せるような釣りが可能になります。
ただし、このフロートは全く目に見えない(特に夜間)ため、ロッドを通しての感覚だけで釣る必要があり、やや上級者向けと言えるかもしれません。初心者の方は、後述する光るタイプのフロートから始めるのも一つの選択肢でしょう。
フローティングとシンキングの使い分けが釣果を左右する
中通しフロートを選ぶ際、重さと並んで重要なのが**浮力(フローティングかシンキングか)**です。この選択が、狙えるレンジ(層)を決定し、釣果に直結します。
**フローティングタイプ(HF・F)**は、水面に浮くタイプのフロートです。表層のアジ攻略に最適で、ハイフロート(HF)とフロート(F)に分かれます。HFは1.5g程度のジグヘッドまで浮力を保てるため、サーフアジングなどで重めのジグヘッドを使う場合に適しています。一方、Fは1.0g程度までの浮力なので、シャローエリアを0.6g以下の軽量ジグヘッドで攻める場合におすすめです。
**スローシンキングタイプ(SS・F0)**は、ゆっくりと沈むタイプで、中層から深場を狙う際に効果的です。F0は残浮力がゼロのため、ジグヘッドと一緒にゆっくり沈んでいきます。SSはさらに沈降速度が速く、より深いレンジを探ることができます。
基本は全誘導の形で使う前提です。
表層探りたければスイベルより下のリーダーを短くし、常に引きながら糸にテンション掛けとけば表層を、中層や下層を探りたければ、ストップさせてジグヘッドを沈めるって感じ。ただ巻きかストップ&ゴーが基本的な使い方になると思います。
この引用からもわかるように、中通しフロートでは**全誘導(フロートがライン上を自由に動く状態)**で使用するのが基本です。表層を探る場合はテンションをかけながら巻き、中層以深を探る場合はストップさせてジグヘッドを沈める、というシンプルな使い分けが効果的です。
💡 浮力タイプ別の使い分け指針
- 🔵 HF(ハイフロート):サーフや遠浅の表層、1.5g前後のジグヘッド使用時
- 🔵 F(フロート):堤防やシャローの表層、0.6~1.0gのジグヘッド使用時
- 🔵 F0(エフゼロ):中層をスローに探る、0.4~0.6gの軽量ジグヘッドとの組み合わせ
- 🔵 SS(スローシンキング):中層~ボトム狙い、深場や流れの速いエリア
浅いエリアでメバリングやアジングをする場合、LのF-F0-SSがあれば十分という意見もあります。逆に10mを超えるような深場では、ファストシンキングやエクストラシンキングといった、より沈降速度の速いタイプが必要になることもあるでしょう。
かっ飛びボールは初心者におすすめの光る中通しフロート
中通しフロートの中でも、特に初心者に優しいのが、ハピソンから発売されている「かっ飛びボール」です。このフロートの最大の特徴は、フロート自体が光るという点にあります。
かっ飛びボールは電池を内蔵しており、ブルー、グリーン、レッドの3色で発光します。これにより、常にフロートの位置が目で確認できるため、リグの位置を見失うことがありません。特にナイトゲームでは、この視認性の高さが大きなアドバンテージとなります。
フロートで特に有名なメーカーはアルカジックジャパンです。アルカジックジャパンの中通しタイプはぶっ飛びロッカーⅡです。(中略)ぶっ飛びロッカーは10g以上の物も有り超遠投が可能で、沈み方も4種類有って攻略の幅は広いですが全く目に見えないので、ロッドを通しての感覚だけで釣る上級者向けです。
かっ飛びボールは7gまでなので超遠投とは行きませんが十分な飛距離は出せます。かっ飛びボールの最大の特徴はフロート自体が光る為、リグの位置が目で見て分かると言う事です。
この記事の著者も指摘しているように、ぶっ飛びRockerⅡは性能面では優れているものの、目視できないため感覚で釣る必要があり、初心者には難易度が高いかもしれません。対してかっ飛びボールは、フロートの動きを目で追いながら操作できるため、フロートリグの基本を学ぶには最適なアイテムと言えるでしょう。
🌟 かっ飛びボールのラインナップ
| 型番 | タイプ | 重量 | 沈降速度 | カラー展開 |
|---|---|---|---|---|
| YF-300 | サスペンド | 4.6g | 浮く | ブルー/グリーン/レッド |
| YF-307 | スローシンキング | 5.5g | ゆっくり沈む | ブルー/グリーン/レッド |
| YF-305 | ファストシンキング | 6.0g | 普通に沈む | ブルー/グリーン/レッド |
| YF-303 | エクストラシンキング | 7.0g | 約3秒/m | ブルー/グリーン/レッド |
各カラーにも意味があり、ブルーは魚が好んで見に来る波長に近く集魚効果が高め、グリーンは大型魚(シーバスやチヌ)を警戒させアジを散らさない効果、レッドは水面の透過率が低く足元狭い場所で魚に見えずリグを操れるという特性があります。
浅いエリアではサスペンドかスローシンキングがあれば十分対応できますが、10mを超えるような深場では、ファストシンキングやエクストラシンキングが必要になるでしょう。価格もぶっ飛びRockerⅡと比較して購入しやすい価格帯となっており、フロートリグ入門にはうってつけのアイテムです。
中通しフロートリグの仕掛け作りと実釣テクニック
- 中通しフロートリグの仕掛けはシンプルな構造
- ウキ止めゴムの選び方がトラブル回避の鍵
- 中通しフロートの釣り方はただ巻きが基本
- 中通しフロートに合うジグヘッドは0.5g前後
- 中通しフロートのトラブル対策は投げ方とサミングが重要
- 中通しフロートで狙うべきポイントは沖の表層
- まとめ:アジングで中通しフロートを使いこなすポイント
中通しフロートリグの仕掛けはシンプルな構造
中通しフロートリグの仕掛けは、一見複雑に見えるかもしれませんが、実はシンプルな構造です。基本的な構成要素を理解すれば、誰でも簡単に組むことができます。
基本的な仕掛けの構成は以下の通りです:
- メインライン(PEライン0.4~0.6号程度)
- リーダー(フロロカーボン1.5号程度、約1~1.5m)
- 中通しフロート
- ウキ止めゴム(またはシモリ玉)
- スイベル
- リーダー(フロロカーボン1号程度、約40~80cm)
- スナップ
- ジグヘッド+ワーム
この構成において重要なのは、リーダーを二段階に分けるという点です。PEラインからスイベルまでのリーダーは太め(1.5号程度)、スイベルからジグヘッドまでのリーダーは細め(1号程度)にすることで、万が一根掛かりした場合に細い方のリーダーだけが切れるようになり、高価なフロートのロストを防ぐことができます。
🔧 中通しフロートリグの組み方手順
- PEラインとリーダー(1.5号)を結束(FGノットなど)
- リーダーに中通しフロートを通す
- ウキ止めゴムをセット(フロートの穴より少し大きめ)
- スイベルを結ぶ
- スイベルのもう一方に細いリーダー(1号)を結ぶ
- リーダーの先端にスナップを付ける
- スナップにジグヘッドを装着
ウキ止めゴムの位置は、スイベルのすぐ上(5~10cm程度)に設置します。これがストッパーとなり、フロートがスイベルより下に落ちないようにします。ウキ止めゴムの代わりに、専用の「ノットプロテクター」や「クッションゴム」を使用することもできます。
また、より手軽にフロートリグを組みたい場合は、三又サルカンを使用する方法もあります。三又サルカンの一方にフロート、もう一方にジグヘッドを接続することで、フロートとジグヘッドの絡みを軽減できます。ただし、三又サルカンの重量分、残浮力が減少する点には注意が必要です。
三又サルカンを使用してフロートとジグヘッドを接続するようにしていました。このおかげで、三又サルカンがあるぶん残浮力を打ち消してしまいますが、フロートの交換が容易になりました。サーフでのアジングにおいては、残浮力を打ち消してしまうことよりも、状況によってフロートを交換したり、フロートとジグヘッドの絡みが少ないことが優先されるかなと思ったため、このような仕掛けでやっていました。
このように、状況や優先事項に応じて仕掛けの組み方をアレンジすることも可能です。基本を押さえた上で、自分なりの工夫を加えていくのも、フロートリグの面白さの一つと言えるでしょう。
ウキ止めゴムの選び方がトラブル回避の鍵
中通しフロートリグにおいて、意外と重要なのがウキ止めゴムの選び方です。ウキ止めゴムのサイズや種類を間違えると、様々なトラブルの原因となってしまいます。
最も重要なポイントは、フロートの穴より少し大きめのサイズを選ぶということです。小さすぎるウキ止めゴムを使用すると、フロートの穴に詰まってしまい、誘導式のメリットが完全に失われてしまいます。これは非常によくある失敗例です。
ウキ止めゴムが小さ過ぎるとフロートの穴に詰まって誘導式のメリットが消えるので、穴より少し大き目が良いです!
一般的に、アジング用の中通しフロートの穴径は2~3mm程度です。これに対して、市販のウキ止めゴムは様々なサイズが展開されていますが、S~Mサイズが適合することが多いようです。ただし、メーカーによってサイズ表記が異なるため、購入前にパッケージの適合ライン径を確認しましょう。
🎯 ウキ止めゴム選びのチェックリスト
- ✅ フロートの穴径より0.5~1mm程度大きいサイズを選ぶ
- ✅ PE用のウキ止めゴムは少ない(フロロ用でOK)
- ✅ 視認性の良いカラー(ピンクやオレンジ)がおすすめ
- ✅ 劣化したら定期的に交換する
- ✅ 複数個セットしておくと安心
ウキ止めゴムの代替品として、シモリ玉や専用のクッションビーズを使用する方法もあります。アルカジックジャパンからは「ノットプロテクター」という専用パーツも発売されており、こちらはクッション性があるため、フロートがスイベルに当たる衝撃を和らげる効果も期待できます。
また、ティクトから発売されている「Mキャロ用スイベル&クッションセット」のように、スイベルとクッションがセットになった製品もあります。これらを活用すれば、仕掛け作りがさらに簡単になるでしょう。
ウキ止めゴムの設置位置については、スイベルから5~10cm程度上に配置するのが一般的です。あまりスイベルに近すぎると、フロートがスイベルに当たりやすくなり、かといって離しすぎると、フロートの遊びが大きくなりすぎて操作性が悪くなります。最初は標準的な位置から始めて、実釣の中で微調整していくとよいでしょう。
中通しフロートの釣り方はただ巻きが基本
中通しフロートリグの基本的な釣り方は非常にシンプルです。難しいアクションは必要なく、初心者でもすぐに実践できる内容となっています。
最も基本となるのが**「ただ巻き」です。キャスト後、糸ふけを巻き取ったら、一定のスピードでリールを巻くだけ。これだけでアジは十分に釣れます。巻くスピードは、「張らず緩めず」**がポイントです。テンションをかけすぎるとワームが不自然に動き、逆に緩めすぎるとアタリが取りにくくなります。
フロートの釣りはとにかく沖の良型メバルを狙いたい訳です!思いっきり遠投して糸ふけが出易いので先ずは糸ふけをきっちり巻き取ります。
完全フロートやぶっ飛びロッカーのF0ならそのまま張らず緩めずで潮に乗せておくとアタリが有ります。ジグヘッドを浮かせたい時は少し早めに巻くと良いです。逆に沈めたい時は緩めてラインを送り込む感じです。
フローティングタイプのフロートを使用している場合、表層をゆっくり引くことで、表層を意識しているアジにアピールできます。一方、シンキングタイプのフロートでは、常に巻いていないとどんどん沈んでしまうため、ただ巻きに時々ストップを入れる程度の誘いが効果的です。
📝 中通しフロートの基本アクション
- 🎣 ただ巻き:最も基本的で効果的。一定速度で巻き続ける
- 🎣 ストップ&ゴー:数秒巻いて2~3秒止める。シンキングタイプで効果大
- 🎣 ドリフト:潮の流れに乗せて漂わせる。張らず緩めずがコツ
- 🎣 リフト&フォール:竿を上げ下げしてフロート越しにジグヘッドを動かす
- 🎣 テンションフォール:キャスト後、テンションを保ちながらゆっくり沈める
特に有効なのが**「ドリフト釣法」**です。潮の流れにフロートを乗せて、自然に漂わせる釣り方で、フロートリグならではの強みが発揮されます。「重たいなぁ」と感じたら巻くのを遅くし(もしくは巻かない)、「軽いなぁ」と感じたら少し早めに巻いてテンションを調整します。
また、中通しフロートの特性を活かした縦の釣りも効果的です。ストラクチャー周りや藻場など、ピンポイントで攻めたい場所では、リフト&フォールで誘いをかけることで、そこに居着いているアジを狙い撃ちできます。
巻くスピードについては、一般的なジグヘッドリグよりもゆっくり目を意識しましょう。フロート自体が水の抵抗を受けるため、通常の速度で巻いているつもりでも、実際にはかなり速く動いていることがあります。「巻きが重い」「投げたところと違う方から帰ってくる」と感じた時は、いつもよりゆっくり巻くように調整してください。
中通しフロートに合うジグヘッドは0.5g前後
中通しフロートリグで使用するジグヘッドの重さは、フロートの残浮力との兼ね合いで決まります。適切なジグヘッドを選ぶことが、快適な釣りと釣果向上の鍵となります。
一般的に、中通しフロートと組み合わせるジグヘッドは0.2~1.0g程度が標準的です。中でも0.4~0.6gが最も汎用性が高く、多くの状況で使いやすい重さと言えるでしょう。フロートの残浮力によっても適正なジグヘッドの重さは変わってきます。
例えば、ぶっ飛びRockerⅡのHF(ハイフロート)タイプは残浮力が1.5gあるため、1.5gまでのジグヘッドであれば浮力を保てます。一方、F(フロート)タイプは残浮力が1.0gなので、1.0g以下のジグヘッドが適しています。F0(エフゼロ)は残浮力が0gなので、0.4~0.6g程度の軽量ジグヘッドと組み合わせることで、スローにフォールさせる釣りが可能になります。
⚖️ フロートタイプ別の適正ジグヘッド重量
| フロートタイプ | 残浮力 | 適正ジグヘッド | 釣り方の特徴 |
|---|---|---|---|
| HF(ハイフロート) | 1.5g | 0.6~1.5g | サーフや遠浅の表層攻略 |
| F(フロート) | 1.0g | 0.4~1.0g | 堤防やシャローの表層 |
| F0(エフゼロ) | 0g | 0.2~0.6g | 中層をスローに探る |
| SS(スローシンキング) | マイナス | 0.4~0.8g | 中層~ボトム狙い |
ここで重要な注意点があります。ジグヘッドの重さでフォール速度を調整しようとするのはNGです。もう少し沈めたいからといってジグヘッドを重くすると、キャスト時に重心が二つになってトラブルが増えたり、飛距離が落ちたりします。また、せっかくのフロートリグの「ゆっくり探れる」というメリットが失われてしまいます。
フロートのフォール速度はジグヘッドで調整NG!?
良くあるのがこのケース。もう少し沈めたいからといってジグヘッドを重くするのはあまりよくありません。キャスト時に重心が二つになるので、トラブルが増えたりそもそも飛距離が落ちます。せっかくスローに探れるフロートなので、重くしちゃうとジグヘッドが早く動くのでメリット消えますね。
フォール速度を調整したい場合は、ジグヘッドではなくフロートの浮力タイプを変更するか、リーダー部分にガン玉を打つ方法が推奨されます。ガン玉をメインラインとフロートの間のリーダー部分に打つことで、フォール速度を微調整できます。この場合、フロートはスローシンキングタイプを使用すると調整がしやすいでしょう。
また、ジグヘッドの形状も重要です。フロートリグではゆっくりとした動きが基本となるため、丸型やアーキー型など、フォール姿勢が安定するタイプが扱いやすいと考えられます。矢じり型など抵抗の大きいタイプは、フロートリグではあまり向かないかもしれません。
中通しフロートのトラブル対策は投げ方とサミングが重要
中通しフロートリグを使用する上で、避けて通れないのがライントラブルです。特にキャスト時の糸絡みは頻繁に発生するため、トラブルを最小限に抑える技術を身につけることが重要です。
最も効果的なトラブル対策は、キャスト方法の工夫です。フロートは重たく空気抵抗も大きいため、通常のルアーと同じように投げると簡単にロッドが折れてしまう可能性があります。ゆっくりと竿を振りかぶって投げるペンデュラムキャスト(振り子投げ)が推奨されます。
投げる時は、ゆっくり竿を振りかぶって投げるペンデュラムキャストで投げましょう。また着水時の糸絡みを防ぐために、必ずサミング(飛行中にスプールに手を添えて、糸ふけを少なくする)を行い、ジグヘッドを沖側へ着水させましょう。
サミングも非常に重要なテクニックです。キャスト後、フロートとジグヘッドが空中を飛んでいる間、スプールに軽く手を添えて糸の出を調整します。これにより余分な糸ふけが出るのを防ぎ、着水時の糸絡みを大幅に減らすことができます。
🛡️ フロートリグのトラブル対策チェックリスト
- ✅ ペンデュラムキャスト(振り子投げ)を習得する
- ✅ キャスト時は力を入れすぎず、ゆっくり振りかぶる
- ✅ 飛行中は必ずサミングを行う
- ✅ ジグヘッドが先に着水するようタイミングを調整
- ✅ 風が強い日は向かい風を避ける
- ✅ リーダーの長さは長すぎないように(1m前後)
- ✅ スイベルは回転性能の良いものを選ぶ
また、着水の順番も重要なポイントです。理想的には、ジグヘッドが先に着水し、その後フロートが着水する形が望ましいです。フロートが先に着水してしまうと、リーダーがフロートに絡みやすくなります。サミングでタイミングを調整し、ジグヘッドを沖側へ着水させるよう意識しましょう。
風の強い日は特にトラブルが増えます。横風や向かい風が強い日は、風の影響を受けやすいフロートリグではライン絡みが頻発します。こうした日は、風裏のポイントを選ぶか、より重いフロートを使用して飛行姿勢を安定させるなどの工夫が必要です。
キャスト後の糸ふけ処理も忘れてはいけません。着水後、すぐに余分な糸ふけをきっちり巻き取ることで、その後の操作がスムーズになり、アタリも取りやすくなります。フロートリグは通常のジグ単よりも糸ふけが出やすいため、この処理を怠るとアタリを逃す原因にもなります。
中通しフロートで狙うべきポイントは沖の表層
中通しフロートリグの最大の強みは、ジグ単では届かない沖のポイントを攻略できることにあります。では、具体的にどのようなポイントを狙えば良いのでしょうか。
最も期待できるのが**「沖の表層」**です。大型のアジは沖を回遊していることが多く、サイズを狙うのであれば遠投は必須となります。ジグ単の1g前後で探れる範囲にいるアジは、多くのアングラーに狙われているためスレていることが多いのに対し、沖のアジは比較的プレッシャーが低く、サイズも良いことが多いようです。
沖の竿抜けポイントで20センチ以上の良型メバルを狙うには、フロートリグが最適です!重いフロートで遠投を可能にして、その先には軽量ジグ単をセットする事で、沖の竿抜けポイントで軽量ジグ単の釣りが可能になります。
サーフも中通しフロートが活躍するフィールドです。サーフでは足元から水深があることは少なく、沖のブレイクラインや離岸流周辺にアジが回遊しています。これらのポイントに届かせるには、フロートリグが必須と言えます。
🎯 中通しフロートで狙うべき具体的なポイント
- 🌊 沖の潮目:異なる潮がぶつかる場所にベイトとアジが集まる
- 🌊 ブレイクライン:急に深くなる場所、特にサーフで重要
- 🌊 離岸流:サーフの離岸流周辺は一級ポイント
- 🌊 沖の沈み磯:中通しならピンポイントで狙える
- 🌊 常夜灯の外側:明暗部の暗い側の表層
- 🌊 沖のウィードエリア:ウィードの切れ目や頂点付近
堤防釣りでも、常夜灯の外側は有望なポイントです。常夜灯直下はジグ単で攻められますが、その外側の暗がり部分は届かないことが多いです。フロートリグなら、こうした明暗部の境目を効率的に探ることができます。
また、潮の流れを意識することも重要です。フロートは潮の流れを感じやすいため、流れに乗せてドリフトさせることで、広範囲を効率的に探ることができます。特に潮がヨレている場所(潮目)には、プランクトンやベイトフィッシュが集まり、それを追ってアジも集まってきます。
深さについては、中通しフロートは表層から中層を得意とします。ボトム付近を狙いたい場合は、キャロライナリグの方が適しているかもしれません。フロートは浮き上がりも強いため、深場のボトムを探るのは不向きです。
時間帯としては、マズメ時が最も効果的でしょう。特に夕マズメから日没後の時間帯は、アジの活性が上がり、表層を意識することが多くなります。この時間帯に沖の表層をフロートリグで攻めることで、良型アジとの出会いが期待できます。
まとめ:アジングで中通しフロートを使いこなすポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- 中通しフロートは誘導式の構造で、魚に違和感を与えにくく食い込みが良い
- 固定式と比較すると飛距離は劣るが、操作性と汎用性に優れる
- 標準的な重さは7~10g程度で、ロッドのキャストウェイトを確認すること
- ぶっ飛びRockerⅡは12種類のラインナップで様々な状況に対応できる定番モデル
- フローティングタイプは表層攻略、シンキングタイプは中層以深の攻略に適する
- かっ飛びボールは光るため初心者でも扱いやすく、ナイトゲームに最適
- 仕掛けはPEライン-リーダー-フロート-ウキ止め-スイベル-リーダー-ジグヘッドの順
- リーダーは二段階に分け、細い方が切れるようにしてフロートのロストを防ぐ
- ウキ止めゴムはフロートの穴より少し大きめを選び、詰まらないようにする
- 基本の釣り方は「ただ巻き」で、張らず緩めずのテンションを保つ
- ジグヘッドは0.4~0.6g前後が標準的で、フロートの残浮力に合わせて選ぶ
- フォール速度の調整はジグヘッドではなくフロートの浮力タイプで行う
- キャストはペンデュラムキャスト(振り子投げ)でゆっくり投げる
- 飛行中は必ずサミングを行い、ジグヘッドを先に着水させる
- 狙うべきポイントは沖の表層、潮目、ブレイクライン、離岸流周辺
- サーフアジングでは特にフロートリグが威力を発揮する
- マズメ時が最も効果的な時間帯で、良型アジの実績が高い
- ドリフト釣法やリフト&フォールなど、状況に応じた誘い方の使い分けが重要
- 風の強い日や荒れた天候ではライントラブルが増えるため注意が必要
- フロートリグは深場のボトム攻略には不向きで、表層~中層が得意レンジ
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 中通し?固定式?悩めるフロートリグのセレクトについて | アルカジックジャパン
- 釣り初心者ですアジングに使うフロート(中通しタイプ)はジグヘッドが沈んでもフ… – Yahoo!知恵袋
- アジング用フロートおすすめ11選|図でわかるタックルセッティングと使い方-釣猿
- アジング遠投フロートおすすめ10選!飛ばしウキの種類等も紹介! | タックルノート
- 【フロートリグ大全】作り方から使い方のコツまで徹底解説!アジング&メバリングアングラー必見です | TSURI HACK
- 【メバリング】フロートリグの釣り方解説!!ぶっ飛びロッカー|かっ飛びボール編 – ザルツBLOG
- 三男くんとフロートリグのアジング入れ食い〜大阪泉南 – J フィッシングダイアリー
- 【サーフアジング】フロートリグの組み方を変えてみた – 100日後に尺アジを釣る釣りバカ
- 【堤防のアジを攻略】さらなる飛距離を生み出す「フロート」と、気になるアイテム | つりそく
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。