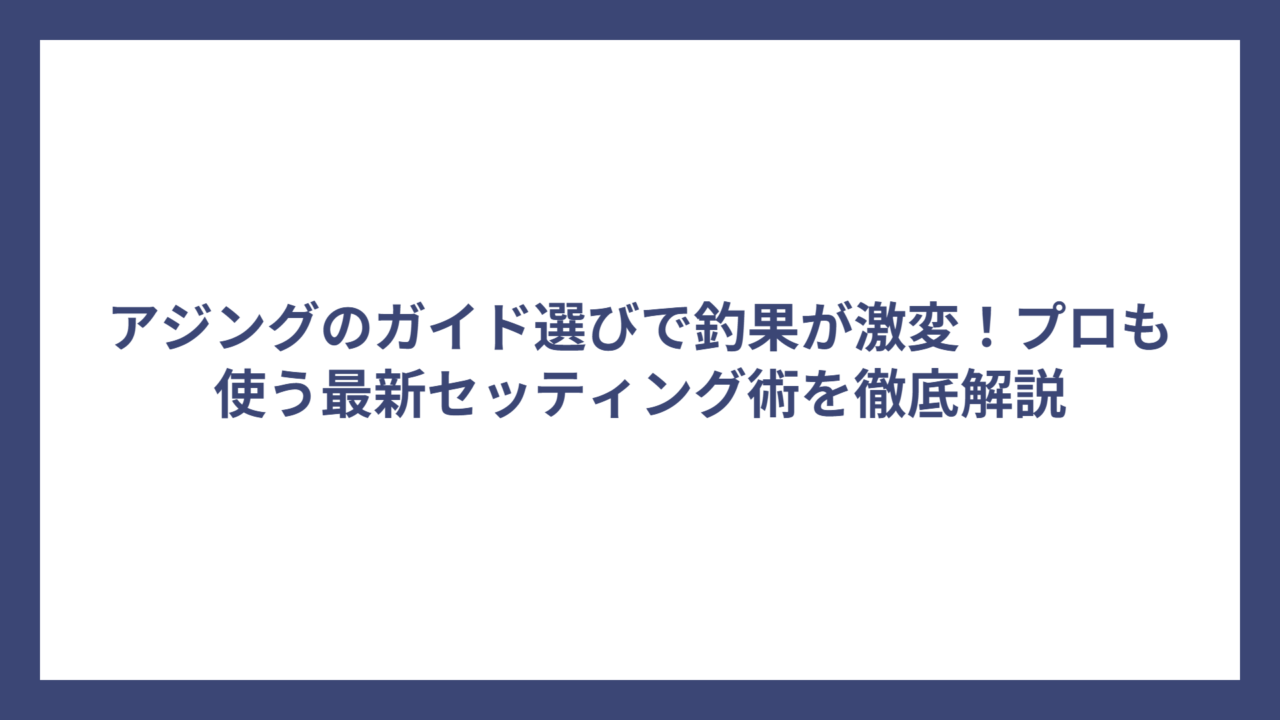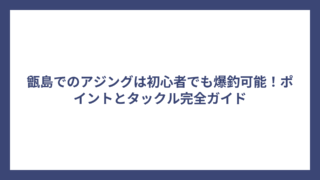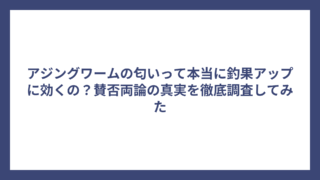アジングロッドのガイド選びやセッティングについて、「どれを選べばいいのか分からない」「ガイドにラインが当たって飛ばない」といった悩みを抱えていませんか?実は、ガイドの種類や配置は感度や飛距離に直結する重要な要素なんです。チタンフレームやトルザイトリングといった最新素材から、ローガイドセッティングや小径ガイドの効果まで、メーカー開発者やロッドビルダーたちが実践している知識を集約しました。
この記事では、ネット上に散らばるガイドに関する専門情報を収集・整理し、初心者から上級者まで役立つ実践的な知識をお届けします。市販ロッドの選び方から自作ロッドのガイドセッティング、さらにはBFアジングでのトラブル対策まで、幅広くカバーしていきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ チタンフレーム+トルザイトリングが最新のガイドトレンド |
| ✓ ローガイド・小径ガイドで感度と風対策を両立できる |
| ✓ ガイドセッティングの基本は倍数間隔と適切なサイズ選択 |
| ✓ BFアジングのガイド当たり問題は結束・ライン・キャストの3要素で解決 |
アジングのガイド選びで釣果が変わる理由
このセクションでは、アジングロッドにおけるガイドの重要性と、素材や配置が釣りのパフォーマンスに与える影響について解説していきます。
- アジングにおけるガイドの役割は感度と飛距離に直結すること
- チタンフレームガイドが軽量化と高感度を実現する理由
- トルザイトリングとSiCリングの違いは内径と重量にある
- ローガイドセッティングで風の影響を軽減できる
- 小径ガイドが感度向上につながるメカニズム
- ガイド数を減らすことで得られるメリットとは
アジングにおけるガイドの役割は感度と飛距離に直結すること
アジングロッドにとって、ガイドは単なる「ラインを通す輪」ではありません。ガイドの性能や配置は、感度・飛距離・操作性といった釣りの根幹に関わる要素すべてに影響を及ぼします。
アジングは0.3g~1.8g程度の軽量リグを扱う繊細な釣りです。このような超軽量ルアーでは、わずかなアタリや潮の変化をティップで感じ取る必要があります。ガイドが重かったり配置が適切でなかったりすると、この繊細な情報が手元まで伝わらなくなってしまうのです。
ガイドはロッド中でも一番大切な部分ですね。無いとロッドがただのカーボンの棒になってしまいますから(笑) と、まぁ冗談はさておきガイドは種類や配置する位置でロッドのアクションや調子が大きく変化する部分だと思います。
この指摘は非常に的確で、ガイドがロッド性能を決定づける重要パーツであることを示しています。特にアジングのような繊細な釣りでは、ガイド選びの重要性がさらに高まります。
飛距離の面でも、ガイドは大きな役割を果たします。キャスト時にラインがスムーズに放出されるかどうかは、ガイドの内径・配置・高さによって決まります。ガイドにラインが当たる抵抗が大きければ飛距離は落ち、小さければ飛距離は伸びます。
また、ガイドの重量配分はロッドバランスにも影響します。先端部分が重ければ持ち重り感が増し、長時間の釣りで疲労が蓄積します。逆に適切な重量配分であれば、軽快な操作感で一日中快適に釣りができます。
📊 ガイドが釣りに与える影響
| 要素 | ガイドの影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 感度 | ラインとブランクの距離・ガイド重量 | アタリの明瞭さ・潮の変化の把握 |
| 飛距離 | ガイド内径・配置・高さ | キャスト時のライン抵抗 |
| 操作性 | ガイドの重量配分 | ロッドバランス・疲労度 |
| 耐久性 | リング素材の硬度 | ラインの摩耗・ガイドの寿命 |
つまり、ガイド選びを適当に済ませてしまうと、どんなに高性能なブランクスを使っていても、その性能を十分に引き出せないことになります。逆に言えば、適切なガイド選択とセッティングによって、ロッド全体の性能を大きく向上させることが可能なのです。
チタンフレームガイドが軽量化と高感度を実現する理由
近年のアジングロッドでは、チタンフレームガイドが主流となっています。従来のステンレスフレームと比較して、チタンフレームには明確な優位性があるためです。
チタンは比重が約4.5と、ステンレス(約7.9)の約6割程度の軽さです。同じ強度を保ちながら大幅な軽量化が実現できるため、特にティップ側のガイドに使用することで、ロッド全体のバランスが格段に向上します。
軽量化のメリットは単に「軽い」ということだけではありません。ガイドが軽くなることでブランクスの本来の曲がりを阻害しにくくなり、結果として感度が向上します。また、キャスト時のブレも少なくなるため、より正確なキャストが可能になります。
加えて、チタンは弾性率が高く振動減衰が少ない特性を持っています。つまり、ラインを通じて伝わってくるアタリの振動を、チタンフレームが効率よくブランクスに伝達してくれるのです。これがステンレスフレームとの感度の違いを生み出しています。
🔧 フレーム素材の比較
| 素材 | 比重 | 特徴 | 適性 |
|---|---|---|---|
| チタン | 約4.5 | 軽量・高弾性・振動伝達良好 | アジング・メバリング全般 |
| ステンレス | 約7.9 | 重い・安価・耐久性高い | 入門機・パワーゲーム |
| カーボン | 約1.8 | 超軽量・高価・繊細 | ハイエンドモデル |
市販のアジング専用ロッドを見ても、中級機以上ではほぼすべてチタンフレームガイドが採用されています。例えば、富士工業のTシリーズ(ハイテンシルチタンフレーム)は、多くのメーカーのアジングロッドで標準採用されています。
コスト面では確かにステンレスフレームより高価になりますが、アジングという繊細な釣りにおいては、チタンフレームへの投資は十分に価値があると言えるでしょう。特に0.3g~1g程度の軽量ジグ単を多用する釣りスタイルでは、チタンフレームの恩恵を強く感じられるはずです。
ロッドビルドを行う際も、予算が許す限りチタンフレームを選択することをおすすめします。わずかな重量差が、実釣での快適性と釣果に大きく影響することは、多くのアングラーが実感しているところです。
トルザイトリングとSiCリングの違いは内径と重量にある
ガイドのリング素材として、現在主流なのはSiC(炭化ケイ素)とトルザイト(富士工業の商標)の2種類です。一見すると似たような素材に思えますが、実は明確な違いがあります。
最も重要な違いは、同じサイズ表記でもトルザイトリングの方が内径が大きいという点です。例えば、3mmサイズで比較すると、SiCリングとトルザイトリングでは内径が異なり、トルザイトの方が実質的にワンサイズ大きいリングを使っているのと同等になります。
気になっていたのが最小径ガイドのサイズでした。現在【トルザイトリング】の最小径は3mm。従来の【sicリング】3mmと同サイズの内径ならば、2.5mmサイズが欲しいのですがラインナップにありません。(中略)実際に【トルザイトリング】3mm【sicリング】3mmを比較してみました。(中略)写真のように同じ間隔で問題がありませんでした。逆に内径が大きい為ラインの抜けが向上しより爽快なキャストフィーリングが可能になりました。
出典:ロッド開発ストーリー
この内径の違いがもたらすメリットは大きく、キャスト時のライン放出がスムーズになり、飛距離が向上します。特にPE0.3号~0.4号といった細いラインを使用するアジングでは、この差が体感できるレベルで現れます。
さらにトルザイトは、同サイズのSiCリングと比較して約40%軽量という特徴があります。トルザイトはセラミック素材であり、SiCよりも密度が低いためです。この軽量化により、ロッド全体のバランスが向上し、特にティップ側での感度アップに貢献します。
💎 リング素材の性能比較
| 項目 | トルザイト | SiC |
|---|---|---|
| 内径(同サイズ表記時) | 大きい(ワンサイズ上相当) | 標準 |
| 重量 | 約40%軽い | 重い |
| 硬度 | 高い | 高い |
| ライン抵抗 | 低い | やや高い |
| 価格 | 高価 | 比較的安価 |
| 適用 | ハイエンド・競技用 | 汎用・入門~中級 |
ただし、トルザイトにもデメリットがあります。それは価格が高いという点です。SiCガイドと比較すると、トルザイトガイドは1.5~2倍程度の価格になることが一般的です。
DUOのアジングロッド「リアクト」の開発者は、ガイドについてこう語っています。
ガイドは全てトルザイトチタンガイドを使用しなるべくブランクスに沿うような低いガイドと小径を使用しました。(中略)小径ガイドこちらもガイド径が大きいと風を受やすくなるので小さく!しかしそれだけではなく、ガイド径が小さいとよりラインが絞られガイドに糸が触れる面積が増えますよね?そうなると・・・バイトがある→ガイドに糸が当たる→ブランクスにその振動が伝わる→手元に伝わる!そうです!糸が当たる面積が増えている為アジからのバイト感度も分かりやすくなっているんです!
この説明からも分かるように、トルザイトリングの大きな内径は、単に飛距離だけでなく感度面でも有利に働いています。小径化しても内径が確保できるため、ラインとブランクスの距離を近づけつつ、ライン放出もスムーズという理想的な状態を実現できるのです。
予算に余裕があれば、少なくともティップ側の数個だけでもトルザイトガイドを採用することで、ロッドの性能を大きく向上させることができるでしょう。
ローガイドセッティングで風の影響を軽減できる
アジングは夜釣りがメインとなることが多く、夜間は風が強まる傾向にあります。風はアジングにとって大敵で、特に軽量リグを扱う際は、ラインが風に煽られてアタリが取りにくくなったり、飛距離が落ちたりします。
この問題に対する有効な対策の一つが、ローガイドセッティングです。ガイドをできるだけブランクスに近い位置に配置することで、ラインとブランクスの距離を縮め、風の影響を受ける面積を減らすことができます。
ローガイドセッティングのメリットは風対策だけではありません。ラインがブランクスに近いということは、ライン経由で伝わる振動が直接ブランクスに伝わりやすくなるということでもあります。つまり、感度の向上にも寄与するのです。
何故低く・小径ガイドなの?と言うと。その1・ローガイドにすることにより風の影響を多少なりとも受けなくしたかったから。どうしてもアジングをやっていると風がつきものでこの風が邪魔をしてきて釣り難い…と皆さん思っていると思います。その為少しでもブランクスに沿わせ風の抵抗を減らせないか?と思いローガイドセッティングを選んだのです。
ただし、ローガイドセッティングにも注意点があります。ガイドが低すぎると、キャスト時にラインがブランクスに当たりやすくなり、かえって飛距離が落ちる可能性があります。特にバットガイド付近では、リールから出るラインの放出角度を考慮した高さ設定が必要です。
🌬️ ガイド高さによる影響
| ガイド高さ | メリット | デメリット | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| ローガイド | 風の影響小・感度向上・見た目がスマート | キャスト時のライン干渉リスク | 風が強い環境・繊細な釣り |
| ハイガイド | キャスト時のライン抜け良好・トラブル少ない | 風の影響大・やや重い | 飛距離重視・パワーゲーム |
| 標準 | バランス型 | 特化した性能なし | オールラウンド |
ローガイドセッティングを採用する際は、特にティップ側に注目すると効果的です。ティップ側のガイドをできるだけ低く配置することで、風の影響を最小限に抑えつつ、感度の向上も狙えます。
一方、バット側のガイドは、リールからのライン放出角度を考慮して適切な高さを保つ必要があります。この部分は飛距離に直結するため、あまり低くしすぎないバランス感覚が求められます。
市販ロッドでも、近年はローガイド傾向が強まっています。ロッドを横から見たときに、ガイドがブランクスにぴったり沿っているようなデザインが増えているのは、このようなメリットを追求した結果と言えるでしょう。
小径ガイドが感度向上につながるメカニズム
アジングロッドのガイドセッティングにおいて、もう一つの重要なトレンドが小径ガイドの採用です。ガイドのリングサイズを小さくすることで、感度が向上するというのは一見不思議に思えるかもしれませんが、そこには明確な理由があります。
小径ガイドの最大のメリットは、ラインとブランクスの距離を近づけられるという点です。ガイドのリングが小さければ、その分ラインがブランクスに近い位置を通ることになります。そうすると、ライン経由で伝わる振動が効率よくブランクスに伝達され、最終的に手元まで届きやすくなるのです。
さらに、小径ガイドには別の感度向上メカニズムもあります。それは、ラインがガイドリングに触れる面積が増えるということです。
この点について、開発者は以下のように説明しています(前述の引用を再掲):
ガイド径が小さいとよりラインが絞られガイドに糸が触れる面積が増えますよね?そうなると・・・バイトがある→ガイドに糸が当たる→ブランクスにその振動が伝わる→手元に伝わる!
つまり、小径ガイドではラインがより多くガイドに接触するため、アタリの振動がガイド→ブランクス→手元という経路でも伝わりやすくなるということです。これは大径ガイドでは得られない効果です。
🎯 ガイド径とアジングへの影響
| 要素 | 小径ガイド | 大径ガイド |
|---|---|---|
| ラインとブランクスの距離 | 近い→感度良好 | 遠い→感度低下 |
| ライン接触面積 | 多い→振動伝達良好 | 少ない→振動伝達やや劣る |
| キャスト時の抵抗 | やや大きい→飛距離やや短い | 小さい→飛距離出る |
| 風の影響 | 小さい | 大きい |
| 適用リグ | 0.3g~1.5g程度 | 1g以上の重めのリグ |
ただし、小径ガイドにもデメリットがあります。それはキャスト時のライン抵抗が増えるため、飛距離がやや落ちる可能性があるという点です。ラインがガイドに多く接触するということは、摩擦抵抗も増えるということだからです。
しかし、実際の開発現場では、この飛距離低下はほとんど問題にならないレベルだという報告もあります。
その反面糸が当たる為飛距離は落ちてはいますが…いますが!元々近距離のシューティングロッドの5ftの方は全く持って使っていて飛ばない…なんて事は思わないと思います!
アジングは基本的に近~中距離の釣りであり、バスフィッシングやシーバスのような遠投性能を求められることは少ないです。そのため、わずかな飛距離低下よりも感度向上のメリットの方が大きいと判断されることが多いのです。
実際の小径ガイドのサイズとしては、トップガイドで3mm、その下が3~3.5mm、チョークガイドで4~6mm程度が一般的です。トルザイトリングを使用する場合は、前述の通り内径が大きいため、さらに小さいサイズ表記でも実用上問題ありません。
小径ガイドの恩恵を最も受けるのは、0.3g~1g程度の超軽量ジグ単を使用する繊細な釣りです。この重量帯では飛距離よりも感度が重要になるため、小径ガイドの選択は理にかなっていると言えるでしょう。
ガイド数を減らすことで得られるメリットとは
ガイドセッティングを考える際、意外と見落とされがちなのがガイドの数です。一般的なイメージでは「ガイドは多い方が良い」と思われがちですが、実はアジングロッドではガイド数を減らすことにも明確なメリットがあります。
まず、ガイドを減らす最大のメリットは軽量化です。ガイドは一個一個は軽量でも、数が増えればトータルの重量は無視できなくなります。特にティップ側のガイドを減らすことで、先重り感が軽減され、ロッドバランスが大幅に改善されます。
次に、ガイドが少ないことでライン抵抗が減少し、飛距離が向上する可能性があります。ラインがガイドを通過する際には、わずかながら摩擦抵抗が発生します。ガイド数が少なければ、その抵抗ポイントも減るため、理論上は飛距離が伸びることになります。
実際のロッドビルド経験者からは、以下のような報告があります。
試作二号機は6ガイドで、かなりガイド数が少なくても問題は感じません。(中略)今のところ、どの試作ロッドも飛ばない等のトラブルは発生していません。
この6ガイドというのは、トップガイド含めて6個という意味です。一般的なアジングロッドが7~8個のガイドを持つことを考えると、かなり少ない数と言えます。
📉 ガイド数と性能の関係
| ガイド数 | メリット | デメリット | 適用 |
|---|---|---|---|
| 少ない(6個前後) | 軽量・飛距離良好・シンプル | ライン角度が急・ブランクスへの負荷大 | ショートロッド・軽量リグ特化 |
| 標準(7~8個) | バランス型 | 特化した性能なし | 汎用性重視 |
| 多い(9個以上) | ラインがスムーズ・ブランクス負荷分散 | 重い・コスト高 | ロングロッド・パワー重視 |
ただし、ガイド数を減らしすぎることには注意が必要です。ガイドが少なすぎると、各ガイド間の角度が急になり、キャスト時やファイト時にブランクスへの負荷が一点に集中してしまう可能性があります。これは破損リスクを高める要因となります。
また、ガイド間隔が広すぎると、ラインがブランクスに接触しやすくなり、キャストフィールが悪化することもあります。特に細いブランクスを使用しているアジングロッドでは、この傾向が顕著に現れることがあります。
適切なガイド数は、ロッドの長さやブランクスの特性によって変わります。5フィート台のショートロッドであれば6~7個、6フィート台であれば7~8個が一つの目安となるでしょう。
ガイド数を減らすアプローチは、特に感度を最優先したい場合や、できるだけ軽量なロッドを求める場合に有効です。自作ロッドを組む際は、まず標準的なガイド数から始めて、実釣での使用感を確認しながら調整していくのが賢明なアプローチと言えます。
アジングのガイドセッティングで知っておくべき実践知識
このセクションでは、具体的なガイドセッティングの方法やトラブル対策など、実践で役立つ知識を詳しく解説していきます。
- バットガイドは10~16サイズから選ぶのが基本
- ガイド間隔は倍数で広げていくのがセオリー
- チタンティップ使用時のガイド配置には特別な配慮が必要
- BFアジングでガイド当たりを防ぐ3つのポイント
- 変則2ピースでキャスト性能が向上する理由
- オリジナルガイドセッティングを考える際の基準
- まとめ:アジング ガイド選びとセッティングの要点
バットガイドは10~16サイズから選ぶのが基本
ガイドセッティングを考える際、意外と悩むのがバットガイド(リールに最も近いガイド)のサイズ選択です。バットガイドは、リールから出るラインを最初に受け止める重要な位置にあり、サイズ選択が飛距離や快適性に大きく影響します。
アジングロッドのバットガイドとして一般的なのは、10~16サイズの範囲です。この範囲内で、ロッドの長さや想定するリグの重量、使用するリールのサイズなどに応じて選択します。
5フィート台のショートロッドで0.3g~1g程度のジグ単メインであれば、10~12サイズが適しています。より遠投性能を求める場合や、1g以上のリグを多用する場合は、12~16サイズを選択することになります。
バットガイドは安定のATガイド。サイズは10、12を使いますが10で落ちつきました。
この経験談からも、10サイズが一つの基準になることが分かります。ただし、これは5フィート台のロッドでの話であり、6フィート以上のロッドではもう少し大きめのサイズが適していることもあります。
🎣 バットガイドサイズの選択基準
| サイズ | 適用ロッド長 | 適用リグ重量 | 使用リール | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5ft台 | 0.3~1g | 1000番台 | 軽量・繊細 |
| 12 | 5.5~6ft | 0.5~1.5g | 1000~2000番 | バランス型・汎用性高 |
| 14 | 6~6.5ft | 0.8~2g | 2000番台 | 遠投性能・やや重い |
| 16 | 6.5ft以上 | 1~3g | 2000~2500番 | 最大飛距離・パワー重視 |
バットガイドのサイズが大きいほど、リールから出るラインをスムーズに受け止められるため、キャスト時の抵抗が減り飛距離が伸びます。しかし、大きすぎると重量が増し、ロッドバランスが悪化する可能性があります。
逆にバットガイドが小さすぎると、キャスト時にラインがガイドに当たる抵抗が大きくなり、飛距離が落ちます。特に太めのライン(PE0.6号以上)を使用する場合は、この傾向が顕著になります。
実際にロッドビルドを行う際は、使用するリールのスプール径とバットガイドの内径の関係を考慮することが重要です。一般的には、スプール径の約1.5~2倍程度の内径を持つバットガイドが適していると言われています。
アジング用の1000番台リールのスプール径はおおよそ40~43mm程度ですので、その1.5~2倍となると60~86mm程度の内径が理想となります。これは、富士工業のガイドで言うと10~16サイズに相当します。
バットガイドの選択で迷った場合は、まず12サイズから始めることをおすすめします。12サイズは汎用性が高く、多くの状況で無難に機能するサイズです。実釣を重ねる中で「もっと飛距離が欲しい」と感じたら大きめに、「もっと軽快に振りたい」と感じたら小さめにシフトしていけば良いでしょう。
ガイド間隔は倍数で広げていくのがセオリー
ガイドセッティングの基本中の基本が、ガイド間隔の設定です。適切なガイド間隔は、ロッドへのストレス分散、キャスト性能、感度に大きく影響します。
基本的なセオリーは、トップガイドからリール方向に向かって、一定の倍率で間隔を広げていくというものです。一般的には1.2~1.5倍程度の倍率が使われることが多いです。
例えば、トップガイドから第1ガイドまでが45mmだとすると、第1ガイドから第2ガイドまでは54~68mm(45×1.2~1.5)、第2ガイドから第3ガイドまでは65~102mm、という具合に広がっていきます。
実際のガイドセッティング例を見てみましょう。
試作三号機 ティクトのロッドを参考に改変したもの トップ〜1番 45ミリ 1番〜2番 55ミリ 2番〜3番 65ミリ(チタンティップ継目) 3番〜4番 115ミリ 4番〜5番 165ミリ 5番〜6番 230ミリ 6番〜7番 290ミリ 7番〜リールフット中央 585ミリ
このセッティングを見ると、ティップ側は比較的緻密に配置され(45mm→55mm→65mm)、バット側に行くにつれて間隔が大きく広がっていく(115mm→165mm→230mm→290mm)ことが分かります。
📐 ガイド間隔設定の考え方
| 区分 | 位置 | 間隔の特徴 | 目的 |
|---|---|---|---|
| ティップ側 | トップ~第3ガイド | 狭い(40~80mm程度) | 感度向上・繊細なラインコントロール |
| ミドル | 第3~第5ガイド | 中間(100~200mm程度) | ストレス分散・バランス |
| バット側 | 第5~バットガイド | 広い(200~600mm程度) | 飛距離確保・パワー伝達 |
なぜこのような倍数配置が有効なのでしょうか。それは、キャスト時やファイト時にロッドが曲がった際、各ガイド間のラインの角度が均等になり、ブランクスへのストレスが分散されるためです。
もしガイド間隔が不均等だと、特定のポイントに過度な負荷がかかり、破損リスクが高まります。また、キャスト時のライン放出も不均一になり、飛距離や精度に悪影響を及ぼします。
ただし、このセオリーは絶対的なものではありません。メーカーやビルダーによって、独自の理論に基づいたガイドセッティングを採用していることもあります。
市販品のアジングロッドを確認してみると、メーカーによってガイド位置が全く違うし、上の富士工業株式会社の表にも従っていません。でも、市販品のロッドは飛ばないというものはあまりない、つまり、ある程度理論さえしっかりしていればガイドセッテイングは富士工業株式会社の表から変えても差し支えないと判断しました。
この指摘の通り、基本セオリーを理解した上で、自分の釣りスタイルやロッドの特性に合わせてカスタマイズしていくことが、最適なガイドセッティングへの道と言えるでしょう。
初心者がロッドビルドを始める際は、まず富士工業のガイドスペック表や、信頼できるメーカーのロッドを参考にすることをおすすめします。その上で、実釣を重ねながら微調整していくアプローチが現実的です。
チタンティップ使用時のガイド配置には特別な配慮が必要
チタンティップ(チタンソリッドティップ)を使用したアジングロッドでは、通常のソリッドティップやチューブラーティップとは異なる特別なガイド配置が求められます。
チタンティップは、カーボンソリッドと比較して非常に高い反発力と感度を持つ一方、継ぎ目の処理やガイド配置には特別な配慮が必要です。チタンティップとメインブランクスの接続部分は、素材の違いから剛性が急激に変化するポイントとなります。
この継ぎ目付近にガイドを配置することが、チタンティップロッドのガイドセッティングにおける重要なポイントです。
・チタンティップは、トップと継ぎ目にガイドを置き、その間に1〜2個のガイドを配置
つまり、チタンティップの先端(トップガイド)、チタンティップとメインブランクスの継ぎ目、そしてその間に1~2個のガイドという配置が基本となります。この配置により、チタンティップ部分とメインブランクス部分の両方から効率よく情報を取得できるのです。
🔧 チタンティップロッドのガイド配置例
| 位置 | ガイド | 距離(参考値) | 目的 |
|---|---|---|---|
| 先端 | トップガイド | – | ライン出口 |
| ティップ中間 | 第1ガイド | 45~70mm | チタンの振動を感知 |
| 継ぎ目 | 第2ガイド | 55~80mm | 剛性変化点のサポート |
| メイン側 | 第3ガイド以降 | 倍数間隔 | 通常配置 |
チタンティップとメインブランクスの継ぎ目にガイドを配置する理由は、この部分に大きな負荷がかかるのを防ぐためです。継ぎ目付近にガイドがないと、キャストやファイト時に過度な曲げ応力が集中し、破損のリスクが高まります。
また、チタンティップ部分にどの程度の数のガイドを配置するかも重要です。一般的には、30cm~40cm程度のチタンティップに対して、トップガイド含めて2~3個のガイドを配置することが多いです。
チタンティップを使用した自作ロッドの例では、以下のような配置が報告されています。
試作二号機 サーティーフォーのロッドを見て改変したもの トップ〜1番 70ミリ 1番〜2番 80ミリ(チタンティップ継目) 2番〜3番 155ミリ 3番〜4番 205ミリ 4番〜5番 315ミリ 5番〜リールフット中央 510ミリ
この例では、チタンティップ部分(トップから継ぎ目まで)に2個のガイドが配置され、継ぎ目の第2ガイドからメインブランクス側の第3ガイドまでの間隔が一気に広がっています(80mm→155mm)。これは、素材の変化に対応した配置と言えるでしょう。
チタンティップロッドを自作する際は、まず継ぎ目の位置を正確に把握し、そこから逆算してガイド位置を決めていくアプローチが有効です。市販のチタンティップロッドを参考にしながら、自分のブランクスに最適な配置を探っていくことをおすすめします。
BFアジングでガイド当たりを防ぐ3つのポイント
ベイトフィネス(BF)アジングでは、通常のスピニングタックルとは異なる特有の問題が発生することがあります。その代表的なものがガイド当たり問題です。結束部分がガイドに引っかかり、飛距離が出なかったり、キャストフィールが悪化したりする現象です。
この問題を解決するためには、3つの要素に注目する必要があります:結束方法、ラインの太さ、そしてキャスティング技術です。
①結束方法の最適化
BFアジングでガイド当たりを防ぐには、できるだけ小さく強固な結束を作ることが重要です。
結論を先に書くと、俺が今使っているノットはFGノットです。ただ、一般的にFGノットはリーダーにPEを巻き付ける回数が15回~20回としている事が多いですが、俺は5回~8回程度に抑えて巻き付けています。その後のハーフヒッチですが、これは3回程度、最後のハーフヒッチ2回と、合計5回ハーフヒッチで締めています。5回巻き付けて5回ハーフヒッチって感じです。
通常のFGノットよりも巻き付け回数を大幅に減らすことで、結束部分のコブを小さくできます。アジングで使用する細いラインであれば、この程度の巻き付け回数でも十分な強度が得られるとのことです。
また、PEラインの端の処理も重要で、できるだけ短く(1mm程度)カットすることで、ガイドへの引っかかりを最小限に抑えられます。
②ラインの太さの選択
結束を小さくしても、元のラインが太ければ結束部分も大きくなります。そのため、できるだけ細いラインを使用することが重要です。
どれだけノットに拘ってコブを小さくしても、元々のラインが太いとノットそのものも大きくなるので、細いラインを使いましょう。自分で試した限りPE0.8号でかなりギリギリ。PE0.6号でちょっと余裕があるけど太い感じ。0.4号からストレス無く使えます。
BFアジングにおける推奨ラインは、メインラインPE0.3~0.4号、リーダー0.6号という組み合わせです。この太さであれば、結束部分が小さくなり、ガイド当たりの問題が大幅に軽減されます。
③キャスティング技術の改善
結束とラインを最適化しても、キャスティング時にティップが暴れると、結束部分がガイドに当たってしまいます。
キャストする際に、「ティップブレ」が発生して、ティップ部分が暴れて、ノットがガイドに当たっているという事も考えられます。(中略)そこで秀星式ベイトフィネスキャスティング講座で良く教えるのは、「ロッドのテイクバックをしっかりとる」という手法です。
BFアジングでは、スピニングのような速い振りではなく、ロッドを180度寝かせるくらいのテイクバックを取り、大きくゆっくりとロッドを振ることが推奨されています。これにより、ティップの暴れが抑えられ、スムーズなキャストが可能になります。
✅ BFアジングのガイド当たり対策まとめ
| 対策 | 具体的方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 結束の最適化 | FGノット5~8回巻き+5回ハーフヒッチ | 結束部分の小型化 |
| ライン選択 | PE0.3~0.4号、リーダー0.6号 | 結束全体の小型化 |
| キャスト改善 | 180度テイクバック、大きくゆっくり振る | ティップブレ防止 |
これら3つの要素を総合的に改善することで、BFアジングのガイド当たり問題はほぼ解消できるでしょう。特に初心者の方は、まずラインを細くすることから始めると、効果を実感しやすいかもしれません。
BFアジングは繊細なタックルバランスが求められる釣りですが、適切な対策を講じることで、スピニングタックルとはまた違った楽しさを味わうことができます。
変則2ピースでキャスト性能が向上する理由
アジングロッドの多くは2ピース(2本継ぎ)構造ですが、その継ぎ目の位置によって性能が大きく変わることは、意外と知られていません。特に変則2ピースと呼ばれる構造は、キャスト性能の向上に大きく貢献します。
通常の2ピースロッドは、ロッド全体をほぼ中央で分割します。しかし変則2ピースでは、バット側に近い位置で分割します。これにより、第1セクション(ティップ側)が長くなり、第2セクション(バット側)が短くなります。
変則2ピースのメリットは主に2つあります。
①キャスト時のロードが向上する
第1セクションが長いということは、キャスト時にロッドに荷重がかかる部分が長くなるということです。これにより、軽量リグでもしっかりとロッドに「乗る」感覚が得られ、飛距離が伸びます。
変則2ピースを採用し継ぐ位置をバット近くにする事で#1はキャスト時にジグヘッドの重みがよりロッドに載るように#2は継ぎがバット近くになるのでバットパワーの向上を実現。
出典:ロッド開発ストーリー
0.3g~1g程度の超軽量リグを扱うアジングでは、ロッドにリグの重みを感じられるかどうかが、正確なキャストの鍵となります。変則2ピースはこの課題を解決する有効な手段なのです。
②バットパワーが向上する
継ぎ目がバット側に近いということは、バット部分が一体構造に近くなるということです。これにより、ファイト時のパワー伝達がスムーズになり、大型アジや不意に掛かったシーバスなどとのやり取りでも安心感があります。
🎣 2ピース構造の比較
| 構造 | 継ぎ目位置 | メリット | デメリット | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 通常2ピース | ほぼ中央 | 仕舞寸法が短い・バランス良好 | 特化した性能なし | 一般的なロッド |
| 変則2ピース | バット寄り | キャスト性能向上・バットパワー向上 | 仕舞寸法やや長い | 軽量リグ特化ロッド |
| 逆並継ぎ | 様々 | 継ぎ部の軽量化・感度向上 | 強度やや劣る | ハイエンドモデル |
変則2ピースと併せて採用されることが多いのが、**逆並継ぎ(印籠継ぎ)**です。通常の並継ぎでは、第1セクションの中に第2セクションが入りますが、逆並継ぎではその逆で、第2セクションの中に第1セクションが入ります。
継ぎは逆並継ぎを採用し継ぎの部分を軽量化してキャスト時のブレもなくしました。
出典:ロッド開発ストーリー
逆並継ぎのメリットは、継ぎ部分の軽量化です。通常の並継ぎでは、第1セクションの末端部分が二重になり重くなりますが、逆並継ぎでは第2セクションの根元部分が二重になるため、ティップ側の軽量化が図れます。
変則2ピース+逆並継ぎという組み合わせは、近年のハイエンドアジングロッドで採用が増えています。この構造により、携帯性を保ちながら、ワンピースロッドに近い性能を実現できるのです。
市販ロッドを選ぶ際も、継ぎ目の位置に注目してみると良いでしょう。仕舞寸法がやや長めのロッドは、変則2ピースを採用している可能性が高く、キャスト性能に優れている傾向があります。
オリジナルガイドセッティングを考える際の基準
ロッドビルドにおいて、最も創造性を発揮できるのがオリジナルガイドセッティングです。市販ロッドにはない、自分の釣りスタイルに最適化されたガイド配置を実現できます。
オリジナルガイドセッティングを考える際の基準として、以下のポイントが重要です。
①バットガイドの位置
バットガイド(リールフット側の第1ガイド)の位置は、飛距離と操作性のバランスを決定づけます。一般的には、リールフット中央から50~60cm程度が基本となります。
・バットガイドは、リールフット中央から50〜60センチメートル位
この距離を基準に、使用するリールのサイズやラインの太さに応じて微調整します。1000番台の小型リールであれば50cm寄り、2000番台であれば60cm寄りが適していることが多いです。
②ガイド数の決定
5フィート台のアジングロッドでは、7~8個程度のガイドが標準的です。ただし、前述の通り、感度や軽量性を優先する場合は6個程度に減らすことも有効です。
・ガイド数は7〜8個程度
ガイド数を決める際は、ロッドの長さとブランクスの硬さを考慮します。長いロッドや柔らかいブランクスでは、ガイド数を増やしてストレスを分散させる必要があります。
③ガイド径の選択
トップガイドからバットガイドに向かって、段階的にサイズを大きくしていきます。アジングロッドの一般的なサイズ選択は以下の通りです。
📏 ガイド径の選択例(トルザイトリング使用時)
| 位置 | サイズ | 型番例 | 用途 |
|---|---|---|---|
| トップ | 3mm | T-KGTT3 | 最も繊細な部分 |
| 第1~2 | 3~3.5mm | T-KTTG3.5 | ティップ感度重視 |
| 第3~4 | 4~5mm | T-KTTG4~5 | 中間部バランス |
| 第5~6 | 5.5~7mm | T-KTTG5.5~7 | チョーク部分 |
| バット | 10~16mm | T-ATTG10~16 | 飛距離確保 |
SiCリングを使用する場合は、トルザイトよりも内径が小さいため、ワンサイズ大きめを選択するのが基本です。
④実釣での確認と調整
オリジナルガイドセッティングは、一度作って終わりではありません。実釣を通じて、以下のポイントを確認し、必要に応じて調整します。
- 飛距離:想定より飛ばない場合、バットガイドのサイズアップや配置変更を検討
- 感度:アタリが取りにくい場合、ティップ側のガイドを小径化・低位置化
- バランス:持ち重り感がある場合、ガイド数を減らすか軽量素材に変更
- トラブル:ライントラブルが多発する場合、ガイド間隔や高さを見直し
様々なこだわりの相乗効果で今までにないロッドが完成いたしました。
出典:ロッド開発ストーリー
プロの開発者でさえ、試行錯誤を重ねて最適なガイドセッティングを見つけ出しています。自作ロッドでは、失敗を恐れずに色々試すことが、最高の一本を見つける近道となるでしょう。
最初は既存のロッドや富士工業のスペック表を参考にしながら、徐々に自分なりのアレンジを加えていくアプローチが現実的です。何本も作っていくうちに、自分の釣りスタイルに最適なガイドセッティングの「型」が見えてくるはずです。
まとめ:アジング ガイドの選び方とセッティングの全知識
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングロッドにおいてガイドは感度・飛距離・操作性すべてに影響する最重要パーツである
- チタンフレームガイドは軽量で高感度、振動伝達に優れアジングに最適な素材である
- トルザイトリングはSiCリングより内径が大きく約40%軽量でキャスト性能が向上する
- ローガイドセッティングにより風の影響を軽減し感度も向上できる
- 小径ガイドはラインとブランクスの距離を近づけガイド接触面積を増やして感度を向上させる
- ガイド数を減らすことで軽量化とライン抵抗軽減による飛距離向上が期待できる
- バットガイドは10~16サイズから選択しロッド長とリグ重量に応じて決定する
- ガイド間隔はトップから1.2~1.5倍の倍率で広げていくのが基本セオリーである
- チタンティップ使用時は継ぎ目にガイドを配置しその間に1~2個のガイドを追加する
- BFアジングのガイド当たりは結束の小型化・細いライン・適切なキャストで解決できる
- 変則2ピース構造は継ぎ目をバット寄りにすることでキャスト性能とバットパワーを向上させる
- オリジナルガイドセッティングはバットガイド位置・ガイド数・ガイド径を総合的に設計する
- 実釣での確認と調整を繰り返すことで自分に最適なセッティングが見つかる
- 市販ロッドのガイドセッティングを参考にしながら独自のアレンジを加えることが重要である
- ガイド選びに投資することでロッド全体の性能を大きく向上させることができる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- GUIDEPOST(ガイドポスト)EMR-64 – アジング ライトゲーム フィッシング|THIRTY34FOUR(サーティフォー)
- ロッドビルド考察『ガイド編』 | 年中夢求 ~A dream is searched for always~
- GUIDEPOST(ガイドポスト)LHR-69 – アジング ライトゲーム フィッシング|THIRTY34FOUR(サーティフォー)
- チタンティップアジングロッドのガイドセッティング|アジング一年生re
- 萩原 トオル|アジングロッドリアクト Vol.2 ガイド編 – スタッフレポート|DUO International / ルアーメーカー デュオ
- ロッド開発ストーリー | アジング – ClearBlue –
- 【楽天市場】アジング ガイド チタンの通販
- ここに気をつけろ!BFアジングのガイド当り問題! | アジング – ClearBlue –
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。