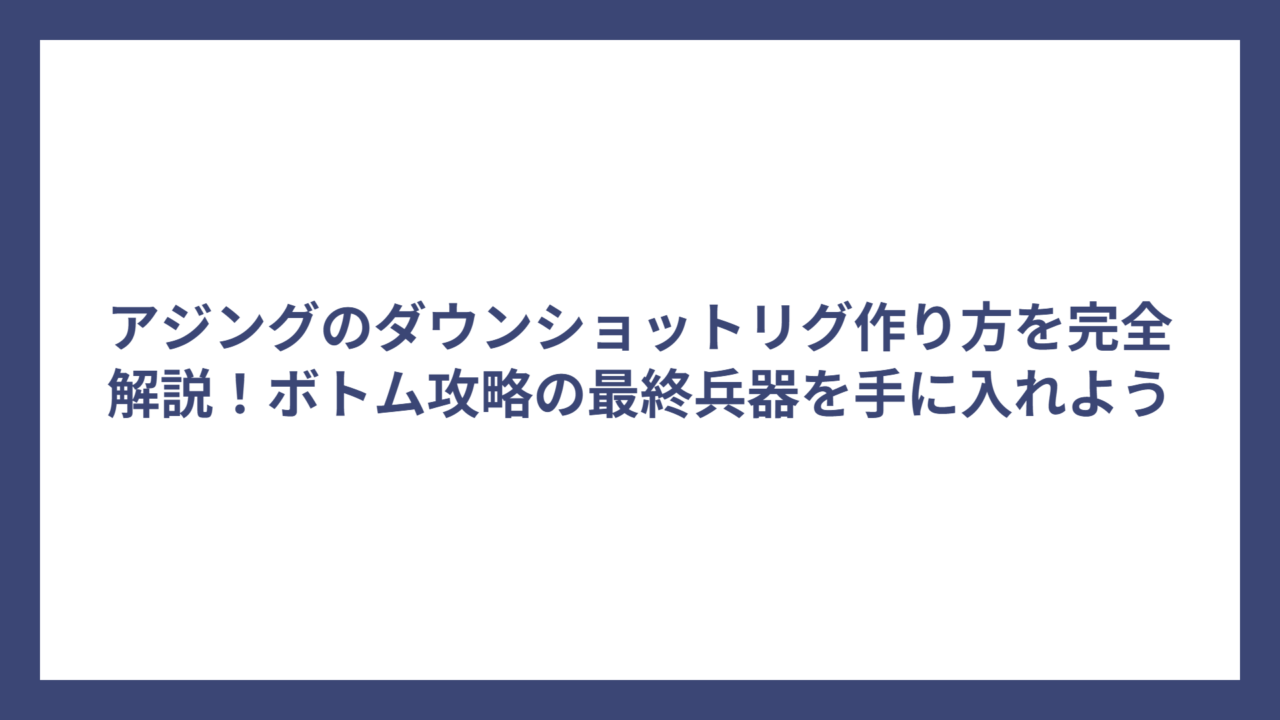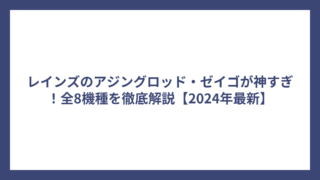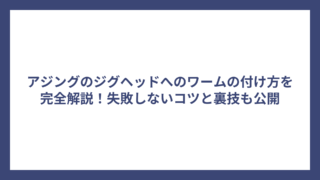アジングと言えばジグヘッド単体(ジグ単)が主流ですが、ボトム付近を効率よく攻めたい場面や、強風下でも安定した釣りを展開したい時には「ダウンショットリグ」が非常に有効です。バス釣りで広く知られるこのリグですが、近年アジングシーンでも注目度が高まっています。しかし、いざ作ろうとすると「どんなパーツが必要?」「エダスの長さはどうすれば?」といった疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、インターネット上に散らばるダウンショットリグに関する情報を収集・整理し、初心者でも迷わず作れるよう具体的な手順とコツを解説します。さらに、ダウンショットリグが活躍するシチュエーションや効果的な使い方、トラブル対策まで網羅的にお届けします。ジグ単だけでは攻略できなかったポイントを開拓したい方、アジングの引き出しを増やしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ ダウンショットリグの具体的な作り方と必要なパーツ |
| ✅ エダスの長さやシンカーの重さなど各部の最適なセッティング |
| ✅ ジグ単との使い分けやダウンショットが効果的な状況 |
| ✅ トラブルを防ぐためのリグ作りのコツと実釣テクニック |
アジングにおけるダウンショットリグの基本と作り方
- アジング用ダウンショットリグの作り方は3つのパーツを順番に組むだけ
- ダウンショットリグが底攻略に最適な理由
- エダス(ハリス)の長さは5cm前後がベストバランス
- フックからシンカーまでの距離は20~30cmが理想
- シンカーの重さは3.5g~7gを使い分ける
- 使用するフックは細軸で吸い込みやすいタイプを選ぶ
アジング用ダウンショットリグの作り方は3つのパーツを順番に組むだけ
ダウンショットリグの構造は実にシンプルです。メインラインの先端にシンカー(オモリ)を配置し、その上にエダス(枝糸)を出してフックを取り付けるという胴付き仕掛けと同じ形態になります。一見複雑に思えるかもしれませんが、必要なパーツは「シンカー」「フック」「リーダーライン」の3つだけです。
具体的な作り方の手順を見ていきましょう。まず、メインラインとリーダーラインを結束します。アジングではPEライン0.4号程度をメインに使用することが多く、リーダーにはフロロカーボン1~2号(4~8lb)を1~2m程度FGノットなどで接続します。次に、リーダーの先端から20~30cm程度の位置にエダスを取り付けます。エダスの取り付け方法にはいくつかありますが、最もシンプルなのは8の字結びやハーフヒッチでエダスを出す方法です。
エダスの長さは5~10cm程度を確保し、その先端にフックを結びます。フックの結束には**漁師結び(完全結び)**が強度と信頼性の面で推奨されます。そして最後に、リーダーの先端にシンカーを取り付けます。シンカーは直接結んでもよいですし、クイックスナップを使えば交換が容易になります。これで基本的なダウンショットリグの完成です。
リーダーに捨て糸を結束する際、ハーフヒッチの締め込みが弱いとズレてほしくないときにズレてしまいます。特に、仕掛けを投入時にオモリの重さがかかるだけでスルスルと移動してエダスの長さがゼロになってしまいます。
この引用からも分かるように、エダスの結束強度は非常に重要です。ハーフヒッチで取り付ける場合は7~9回程度しっかりと巻き付け、最後にエンドノットを2回行って締め込むことで、意図しないズレを防ぐことができます。エダスが勝手に移動してしまうとボトムからの距離が変わってしまい、せっかくのリグの利点が活かせなくなってしまいます。
また、より簡単に作りたい場合は三又サルカンやトリプルサルカンを使用する方法もあります。三又の3つの環のうち、1つにメインライン、1つにエダス+フック、もう1つにシンカーを接続すれば完成です。サルカンを使うメリットは糸ヨレを軽減できることと、各パーツの交換が容易な点です。ただし、サルカンを介すことでダイレクトな感度はやや損なわれる可能性があります。
実際に作ってみると分かりますが、慣れれば5分もかからずに組むことができます。最初は自宅で練習してから釣り場に持っていくと、現場でのトラブル時にも素早く対応できるでしょう。
ダウンショットリグが底攻略に最適な理由
ダウンショットリグの最大の特徴は、シンカーが最下部にあることでボトムを常に感知しながら釣りができる点にあります。ジグヘッド単体では、軽量なジグヘッドを使用する関係上、底を取るのに時間がかかったり、流れが速いとボトムに到達する前に流されてしまったりすることがあります。一方、ダウンショットリグは重めのシンカーで素早く底を取り、フックとワームはシンカーより上にあるため根掛かりのリスクも軽減されます。
📊 ダウンショットリグとジグ単の比較
| 項目 | ダウンショットリグ | ジグ単 |
|---|---|---|
| ボトム感知 | ◎ 明確に感じ取れる | △ 軽量だと分かりにくい |
| 根掛かり | ○ シンカーのみが接地 | △ フック全体が接地 |
| 飛距離 | ◎ 重いシンカーで遠投可能 | △ 軽量だと飛ばない |
| アタリの取りやすさ | ○ ダイレクトに伝わる | ◎ 最もダイレクト |
| 一点シェイク | ◎ 得意 | △ 難しい |
| 操作の簡単さ | ○ 初心者でも扱いやすい | △ 慣れが必要 |
特に深場や流れの強いエリアでは、ジグヘッド単体だとボトムを感知できずに空振りに終わることも珍しくありません。ダウンショットリグなら3.5g~7g程度のシンカーを使用するため、強風下や潮流の速い状況でもしっかりと底を取ることが可能です。また、シンカーが底に着いた状態でロッドをシェイクすると、ワームだけが水中でふわふわと漂うようなアクションを演出でき、これがアジの捕食本能を強く刺激します。
ダウンショットアジングは強い味方になりそうですね。ところで、PEを使用した釣りをされていますが、ラインシステムは、どんなシステムでされてますか?細いPEでFGノットを組むのが難しいので、うららさんが、使っておられるシステムも紹介していただければ、ありがたいです。
PEとリーダーの接続は電車結びです。接続部分に大きな力がく掛かる釣りでは無いので問題無く釣行しています。ラインの巻き付け回数はフロロ側2~3回、PE側3~5回です。
このやり取りからも分かるように、ダウンショットアジングでは必ずしも完璧な強度のノットを組む必要はなく、シンプルな結束方法でも十分に対応できます。アジングではバス釣りのように大きな負荷がかかることは少ないため、扱いやすさを優先してもよいでしょう。
さらに、ダウンショットリグは着底後の一点シェイクが非常に効果的です。シンカーを底に置いたまま、ロッドティップを小刻みに動かすことで、ワームだけが微細に震えるアクションを生み出せます。これはボトム付近でじっとしているアジに対して非常に有効で、プランクトンを模したナチュラルなアピールができます。
エダス(ハリス)の長さは5cm前後がベストバランス
ダウンショットリグにおいて、エダス(枝糸)の長さは釣果に直結する重要な要素です。エダスが長すぎると糸絡みなどのトラブルが増え、短すぎるとフッキング率が低下します。多くの実績あるアングラーが推奨しているのは5cm前後という長さです。
短いほどトラブルは少ないですが、フッキング率が悪くなります。食いが渋くなればなおさらです。様々な長さをテストした結果5cm前後がバランス良くオススメです。中層狙いの場合は10cm位まで長くする事も有りますが、それ以上長くなると絡み等のトラブルが激増しました。
この引用から分かるように、5cmという長さはトラブルレスとフッキング率のバランスが最も取れた設定と言えます。エダスが短いとフックの可動域が制限され、アジがワームを咥えた瞬間にシンカーやメインラインの重さを感じて違和感を覚え、すぐに吐き出してしまう可能性が高まります。一方、エダスを長くしすぎると、キャスト時や巻き上げ時にメインラインに絡みついてしまい、せっかくのチャンスを逃すことになります。
ただし、状況によってはエダスの長さを調整することも有効です。例えば、中層を狙いたい場合は10cm程度まで伸ばすこともあります。エダスが長いほどワームの可動域が広がり、よりナチュラルな動きを演出できるからです。しかし、それ以上長くするとトラブルが激増するため、基本的には5~10cmの範囲内で調整するのが賢明でしょう。
🎣 エダスの長さによる特性比較
| エダスの長さ | メリット | デメリット | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| 3cm以下 | トラブルが最小 | フッキング率低下 | 初心者の練習時 |
| 5cm | バランス最良 | – | ボトム狙いの基本 |
| 7~10cm | ワームの動き良好 | やや絡みやすい | 中層狙い |
| 10cm以上 | 最もナチュラル | トラブル激増 | 非推奨 |
エダスの素材については、メインのリーダーと同じかやや細いフロロカーボンラインを使用するのが一般的です。太さはリーダーが1.5号なら1.5号、リーダーが0.6~0.8号なら同じ太さを使用します。一部の情報では、リーダーを折り返してエダスにしているケースもあり、これなら追加のラインを用意する必要がなく経済的です。
また、エダスの取り付け角度も重要です。エイトノットで結ぶことで、エダスがやや張りを持ってメインラインから離れるため、トラブルを回避しやすくなります。単純に結ぶとエダスがダランと垂れ下がってしまい、メインラインに絡みやすくなるので注意しましょう。
フックからシンカーまでの距離は20~30cmが理想
エダスの長さと並んで重要なのが、フック(エダスの取り付け位置)からシンカーまでの距離です。この距離が短すぎると、ワームが海底に近すぎて根掛かりしやすくなったり、食いが悪くなったりします。逆に長すぎると、キャストが困難になったり、感度が低下したりします。
実際にテストを重ねた結果、20~30cmという距離が最も汎用性が高く、様々な状況に対応できることが分かっています。この距離設定には明確な理由があります。遠投してロッドアクションを加えた際、水中でのラインは斜めになっています。この時、シンカーとフックの距離が20~30cmあることで、ワームがボトムから適度に浮いた状態をキープでき、アジの視界に入りやすくなるのです。
遠投してロッドアクションさせた時には、水中でのラインの角度は斜めになっています。短くすると食いが悪くなったり、根掛かりが増加します。テストの結果、その長さを20cm~30cmとする事で問題無く釣果を得る事が出来ました♪長すぎるとキャストが困難になります。
この引用が示すように、20~30cmという距離は経験に基づく実証済みの設定値です。特に注目すべきは、距離が短いと根掛かりが増加するという点です。一見すると、シンカーとフックの距離が近い方が根掛かりしにくいように思えますが、実際には逆なのです。これは、距離が短いとワームが海底スレスレを引きずることになり、岩や海藻に引っかかりやすくなるためです。
また、キャスト時のバランスも考慮する必要があります。シンカーからフックまでの距離が長すぎると、キャスト時にリグ全体がバラバラに飛んでいき、飛行姿勢が安定しません。結果として飛距離が伸びず、着水時の糸絡みリスクも高まります。20~30cmという距離なら、キャスト時もリグがコンパクトにまとまり、安定した飛行姿勢を保てます。
さらに、この距離設定はシンカーの重さとのバランスも重要です。軽いシンカー(1.5~3g)を使う場合は20cm程度、重めのシンカー(5~7g)を使う場合は30cm程度と、シンカーの重さに応じて微調整するのが効果的です。重いシンカーほど底にしっかり着くため、フックまでの距離を長めに取ってもワームが適度に浮いた状態をキープできるからです。
🔧 シンカー重量別の推奨距離
| シンカー重量 | フックまでの推奨距離 | 適した水深・条件 |
|---|---|---|
| 1.5~3g | 20cm | 浅場・弱い流れ |
| 3.5~5g | 25cm | 中深場・標準的な条件 |
| 5~7g | 30cm | 深場・強風下 |
実釣では、最初は25cm程度でセッティングし、根掛かりが多い場合は少し長めに、アタリが遠い場合は少し短めに調整するとよいでしょう。ただし、極端な変更は避け、±5cm程度の範囲内での微調整にとどめるのが無難です。
シンカーの重さは3.5g~7gを使い分ける
ダウンショットリグで使用するシンカーの重さは、釣り場の条件によって使い分ける必要があります。基本的には3.5g、5g、7gの3種類を用意しておけば、ほとんどの状況に対応できるでしょう。
シンカーの重さ選びで最も重要なのは、ボトムを確実に感知できる重さであることです。軽すぎると流されてしまい底が取れず、重すぎるとロッドへの負担が大きくなったり、アジがシンカーの存在に警戒したりする可能性があります。
ライトタックルを使用するのであまりにも重いシンカーを使用するのはロッドの破損などに繋がります。最大で7g(ご使用になるロッドの適合を確認の上、ウエイトをセレクトして下さい)。この7gで、非常に過酷な強風下でもボトムを感知出来ました。ジグヘッドリグ・キャロライナリグではボトム感知不可能でした・・・。
この引用から分かるように、7gという重さは強風下でもボトムを感知できる限界値として設定されています。通常のアジングロッドは5~10g程度のルアーウェイトに対応していることが多いため、7gなら許容範囲内です。ただし、ロッドのスペックは必ず確認し、無理な負荷をかけないよう注意しましょう。
一方、3.5gは標準的な条件下での基本ウェイトと考えてよいでしょう。風が穏やかで、水深も5~10m程度なら3.5gで十分にボトムを取れます。この重さなら飛距離も確保でき、かつアジへの警戒心を最小限に抑えられます。
5gは中間的な選択肢として非常に使いやすいウェイトです。やや風がある日や、水深が10~15m程度ある場所、流れがやや速いポイントなど、3.5gでは心もとないが7gほどは必要ない場面で活躍します。おそらく、最も使用頻度が高いのがこの5gではないでしょうか。
シンカーの形状については、**丸型(ナス型)**が最もストレスなく使用できるとされています。様々な形状がテストされた結果、特殊な形状よりもシンプルな丸型が根掛かりしにくく、感度も良好であることが判明しています。ナス型オモリなら釣具店で安価に入手できるため、コストパフォーマンスも優れています。
📦 シンカー重量と使用シーン
| 重量 | 推奨条件 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1.5~3g | 浅場・無風 | アジへの違和感最小 | 流されやすい |
| 3.5g | 標準的条件 | バランス良好 | – |
| 5g | やや風あり・中深場 | 最も汎用性高い | – |
| 7g | 強風・深場 | 確実に底が取れる | ロッド負担大 |
シンカーの交換を素早く行いたい場合は、クイックスナップやスナップ付きサルカンを使用すると便利です。特にスナップ付きサルカンは、シンカーの回転による糸ヨレも防いでくれるため、一石二鳥です。ただし、サルカンを追加することで若干感度が落ちる可能性もあるため、状況に応じて使い分けましょう。
使用するフックは細軸で吸い込みやすいタイプを選ぶ
ダウンショットリグで使用するフックは、細軸・軽量で吸い込みやすいタイプが推奨されます。ダウンショットリグの利点の一つは、重いシンカーとフックが分離していることで、アジがワームを咥えた瞬間にシンカーの重さを感じにくく、違和感なく吸い込めることです。この利点を最大限に活かすためには、フック自体も軽量である必要があります。
具体的には、#8または#6サイズの細軸フックが最適とされています。アジの口は意外と小さく、特にサイズが20cm以下の個体では大きなフックを吸い込みきれないことがあります。#8サイズなら小型から中型のアジまで幅広く対応でき、#6なら中型から大型狙いに適しています。
ダウンショットでの使用でフックに求められるのは吸い込みの良さ。カルティバ スプリットショッターは細軸軽量で非常に吸い込みが良く、マゴバチとの相性も◎フックサイズは#8がおすすめです♪
この引用で紹介されている「スプリットショッター」は、まさにダウンショットリグ用に設計されたフックです。細軸設計により水抵抗が少なく、アジが違和感なく吸い込めます。また、フックポイント(針先)が鋭く研がれているため、軽いフッキング動作でも確実に掛かります。
フックの形状については、ストレートシャンクタイプが基本です。オフセットフックのようなクランク(曲がり)があると、ワームのセッティングが難しくなったり、フッキング率が低下したりする可能性があります。シンプルなストレート形状が最も扱いやすく、確実なフッキングが期待できます。
また、フックの色についてはブラックやシルバーが一般的です。ブラックは目立たず自然な印象を与え、シルバーは小魚のような反射を生み出します。状況によって使い分けてもよいですが、個人的にはブラックの方が汎用性が高いと感じます。
🎣 推奨フックスペック
| 項目 | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| サイズ | #8~#6 | アジの口サイズに適合 |
| 軸の太さ | 細軸 | 吸い込みやすさ重視 |
| 形状 | ストレートシャンク | セッティング容易 |
| 針先 | 鋭角研磨 | フッキング率向上 |
| 色 | ブラック or シルバー | 自然な印象 |
フックの結び方は**漁師結び(完全結び)**が最も信頼性が高いです。巻き付け回数は5回程度で十分な強度が得られます。結束後の端糸は5mm程度残してカットすると、解けにくくなります。
なお、ダウンショットリグではフックの向きも重要です。エダスにフックを結ぶ際、フックポイントが上を向くようにセットすることで、フッキング率が向上します。アジは基本的に下から餌を吸い込むため、針先が上を向いていると口の中で自然に掛かりやすくなるのです。
アジングでダウンショットリグを効果的に使うテクニック
- ダウンショットリグの基本アクションはリフト&フォール
- ジグ単では攻略困難な状況で真価を発揮
- 逆ダウンショットリグという選択肢もある
- トラブルを防ぐためのリグ作りのコツ
- ダウンショットに最適なワームの選び方
- おすすめタックルセッティング
- まとめ:アジングのダウンショットリグ作り方と活用法
ダウンショットリグの基本アクションはリフト&フォール
ダウンショットリグの操作方法は意外とシンプルです。基本となるのはリフト&フォールというアクションで、これさえマスターすればほとんどの状況に対応できます。
リフト&フォールとは、文字通りロッドを持ち上げてリグを浮かせ(リフト)、その後ロッドを下げてリグを沈める(フォール)という動作の繰り返しです。具体的には、ロッドティップを30~50cm程度ゆっくりと持ち上げ、1~2秒ポーズを入れてからゆっくりと元の位置に戻します。この動作により、シンカーは底に着いたままで、ワームだけがふわふわと上下に漂うようなアクションが生まれます。
基本は、ボトムをとって、軽くシャクって、フォールで再びボトムまで。この週末は是非「ダウンショットアジング」で楽しんで下さい♪
この引用が示すように、軽くシャクってフォールという単純な動作で釣りが成立します。難しいロッドワークは必要なく、初心者でもすぐに実践できるのがダウンショットリグの大きなメリットです。
リフト&フォールのコツは、フォール中にラインを張りすぎず、緩めすぎずのテンションをキープすることです。完全にラインを緩めてしまうとアタリが分からなくなり、逆に張りすぎるとワームが不自然な動きになります。軽くラインにテンションを感じる程度が理想的です。
また、一点シェイクも非常に効果的なアクションです。シンカーを底に着けたまま、ロッドティップを小刻みに揺らすことで、ワームが微細に震えるアクションを演出できます。これはプランクトンを模した動きで、食い渋ったアジに口を使わせる最終手段として有効です。シェイクの振り幅は5~10cm程度、振動は秒間2~3回程度のゆっくりとしたリズムが効果的です。
さらに、ボトムステイも忘れてはいけません。リグを底に置いたまま30秒~1分程度放置するだけですが、この間にアジが近寄ってきてワームを発見し、食いつくことがあります。特に低活性時や、アジがボトムにべったり張り付いている状況では、動かさないことが最良の選択となることもあるのです。
🎯 ダウンショットリグの主要アクション
| アクション | 方法 | 効果的な状況 |
|---|---|---|
| リフト&フォール | ロッドを上下させる | 基本・万能 |
| 一点シェイク | ティップを小刻みに揺らす | 食い渋り時 |
| ボトムステイ | 底に置いたまま待つ | 低活性時 |
| ズル引き | 底を引きずる | 広範囲サーチ |
ただし、これらのアクションは状況によって使い分ける必要があります。アジの活性が高い時はリフト&フォールでテンポよく誘い、活性が低い時はステイやゆっくりとしたシェイクで粘り強く誘うのが基本です。
ジグ単では攻略困難な状況で真価を発揮
ダウンショットリグが最も威力を発揮するのは、ジグ単では釣りにならない状況です。具体的には以下のようなシチュエーションが挙げられます。
💨 強風時
風が強いとジグ単ではラインが煽られてしまい、リグの位置が把握できなくなります。特に1g以下の軽量ジグヘッドでは、風の影響で着水地点も定まらず、まともな釣りができません。一方、ダウンショットリグなら5~7gの重いシンカーで風を切って飛ばせますし、着水後も重みでしっかりと沈むため、風の影響を最小限に抑えられます。
風が強い日にジグ単ではアタリが取れず釣りにならない状況下でも、Mキャロなら遠投が出来る事と、バックスライドでテンションを張って行く事でアタリも明確に分かるんです。過去に風速10mでも釣りが成立しました!
この引用はMキャロ(ミッドキャロライナリグ)についてですが、ダウンショットリグも同様に強風下で有利です。風速10mという過酷な条件でも釣りが成立するというのは、遠投系リグの大きなアドバンテージと言えるでしょう。
🌊 深場・流れの速いポイント
水深が10m以上ある場所や、潮流が速いポイントでは、軽量ジグヘッドだとボトムに到達する前に流されてしまいます。また、到達したとしても「今ボトムに着いたのか?」が分からないこともしばしばです。ダウンショットリグなら重いシンカーで素早く底を取り、着底も明確に分かります。手返しも格段に良くなり、効率的にポイントを探ることができます。
🎣 アジが沖に居る時
岸際にアジが寄っておらず、沖の回遊待ちをする必要がある場面では、飛距離が釣果を左右します。1gのジグヘッドでは頑張って30~40m程度の飛距離ですが、ダウンショットリグなら50~70m先まで届きます。この差は非常に大きく、沖にしかアジが居ない状況では決定的な差となります。
🪨 根掛かりが多いポイント
岩礁帯や海藻が多いポイントでは、ジグヘッド全体が海底と接触するため根掛かりのリスクが高まります。ダウンショットリグならシンカーだけが接地し、フックとワームは少し浮いた状態をキープできるため、根掛かりを大幅に軽減できます。
🌟 ダウンショットリグが有利な状況まとめ
| 状況 | ジグ単の課題 | ダウンショットの利点 |
|---|---|---|
| 強風 | ラインが煽られる | 重さで安定 |
| 深場 | 底が取れない | 素早く着底 |
| 速い流れ | 流される | しっかり底キープ |
| 沖狙い | 飛距離不足 | 遠投可能 |
| 根掛かり多発 | フック全体が接地 | シンカーのみ接地 |
おそらく、ダウンショットリグを一度使ってみれば、その便利さに驚くはずです。特に「今日は風が強いから釣りを諦めよう」と思っていた日でも、ダウンショットリグなら釣りが成立する可能性があります。ジグ単だけに固執せず、状況に応じてリグを使い分けることが、釣果アップへの近道と言えるでしょう。
逆ダウンショットリグという選択肢もある
ダウンショットリグには、通常のタイプとは逆の構成になった逆ダウンショットリグ(逆ダン)というバリエーションがあります。通常のダウンショットリグがリーダーの先端にシンカー、途中にフックという構成なのに対し、逆ダンはリーダーの先端にフックを直結し、途中から捨て糸を出してシンカーを吊るすという構成になります。
この逆ダンが好まれる理由は主に3つあります。
📡 ダイレクトな感度
逆ダンではメインラインからリーダー、そしてフックへと直線的に繋がっているため、サルカンなどの余計なパーツを介しません。そのため、アジがワームに触れた瞬間の微細なアタリも手元にダイレクトに伝わります。バチコンアジング(ボートアジング)など、より繊細なアタリを取る必要がある釣りでは、この感度の差が釣果に直結します。
🔧 エダスの長さ調整が容易
逆ダンでは捨て糸をハーフヒッチでリーダーに結束するため、結束位置を変えることでエダスの長さを簡単に調整できます。通常のダウンショットリグでは、エダスの長さを変えるには結び直しが必要ですが、逆ダンならハーフヒッチの位置をスライドさせるだけで調整可能です(ただし、強く締め込んだ後は動きません)。
💪 結束強度の高さ
逆ダンはメインラインからフックまでが一本のラインで繋がっているため、結束点が少なく全体の強度が高いという利点があります。通常のダウンショットリグでサルカンを使用すると、結束点が増えて強度が低下する可能性がありますが、逆ダンなら大型のアジが掛かっても安心です。
ダウンショットリグと逆になるので逆ダウンショットリグと言われています。ダイレクトでアタリが取りやすい、エダスの長さを調整できる、ライン強度を最大限に引き出せる
この引用が端的に逆ダンの利点をまとめています。特にライン強度を最大限に引き出せるという点は、大型狙いでは見逃せないメリットです。
ただし、逆ダンにもデメリットはあります。最大の問題は捨て糸のズレです。ハーフヒッチで結束しているため、締め込みが甘いとキャスト時や魚が掛かった際にズレてしまい、エダスの長さが変わってしまいます。これを防ぐには、ハーフヒッチを7~9回しっかりと巻き、最後にエンドノットで固定する必要があります。
⚖️ 通常ダウンショットと逆ダンの比較
| 項目 | 通常ダウンショット | 逆ダウンショット |
|---|---|---|
| 感度 | ○ | ◎ ダイレクト |
| エダス調整 | △ 結び直し必要 | ○ 位置変更可能 |
| 強度 | △ サルカン使用時低下 | ◎ 一本繋ぎ |
| 作りやすさ | ◎ サルカンで簡単 | △ ハーフヒッチ技術要 |
| トラブル | ○ 少ない | △ ズレの可能性 |
初心者には通常のダウンショットリグ(サルカン使用)が作りやすくおすすめですが、ある程度慣れてきたら逆ダンにもチャレンジしてみるとよいでしょう。特にボートアジングや大型狙いでは、逆ダンの方が有利な場面が多いかもしれません。
トラブルを防ぐためのリグ作りのコツ
ダウンショットリグを使う上で最も避けたいのが糸絡みなどのトラブルです。せっかくポイントに到着しても、キャストのたびに絡まっていては時間の無駄ですし、チャンスを逃してしまいます。ここでは、トラブルを最小限に抑えるためのリグ作りのコツを紹介します。
🔄 スイベル(サルカン)の活用
糸ヨレはトラブルの最大の原因です。リグが回転することでラインがねじれ、これが蓄積すると糸が絡みやすくなります。これを防ぐには高回転サルカンやクレン付きサルカンを使用するのが効果的です。特にWクレン(ダブルクレン)やトリプルクレンは回転箇所が複数あるため、より効果的に糸ヨレを防げます。
シンカーとリーダーの間にスナップ付きローリングスイベルを入れることで、シンカーが回転してもリーダーに糸ヨレが伝わりにくくなります。ダイワのDスイベルSSシリーズやオーナーのWクレンシリーズなどが高性能でおすすめです。
⚖️ ジグヘッドの重さ選び
意外と見落とされがちですが、ジグヘッドが軽すぎるとキャスト時に回転して糸絡みの原因になります。ダウンショットリグでは0.5g程度のジグヘッドが推奨されることが多いですが、風が強い日やワームが大きい場合は1~2gに上げることでトラブルを減らせます。
キャロやフロートと一緒に使うジグヘッドはよく0.5g前後が使われることが多いが、渡邉さんは1g以上、ワームのが空気抵抗が大きければ2gまで使うという。その理由はキャスト時にジグヘッドが回転しないようにするため。
この引用が示すように、トラブルレスを優先するなら、ジグヘッドは少し重めを選ぶのが賢明です。0.5gで糸絡みが頻発するようなら、1gに変更してみましょう。
📏 エダスの角度を意識
エダスがメインラインにダランと垂れ下がっていると、絡みやすくなります。エイトノットで結ぶことで、エダスがやや張った状態で横に出るため、絡みにくくなります。結び方一つでトラブル率は大きく変わるので、丁寧に結束しましょう。
🧵 しなやかなリーダーを選ぶ
リーダーラインの材質も重要です。硬いラインは感度が高い反面、糸グセがつきやすく絡みやすい傾向があります。「しなやか」タイプのフロロカーボンラインを選ぶことで、糸グセを軽減し、トラブルを減らせます。
リーダーラインはずっとダイワ製を使用していましたが、最近では「KGC シーガー グランドマックス」を使用しています。このラインは、感度を重視しており硬めのラインです。前回、糸ヨレ・糸クセがひどかったので同じシーガー製の「グランドマックスFX」に変更しました。このラインは感度よりもしなやかさを重視して糸ヨレ・糸クセを軽減します。
感度としなやかさはトレードオフの関係にありますが、トラブルが多発するようなら、しなやかタイプに変更することも検討しましょう。
🛠️ トラブル対策チェックリスト
| 対策 | 具体的方法 | 効果 |
|---|---|---|
| サルカン使用 | Wクレン・トリプルクレン | 糸ヨレ防止 |
| ジグヘッド重め | 1~2g | 回転防止 |
| エイトノット | エダス結束時 | 角度確保 |
| しなやかライン | FXタイプ選択 | 糸グセ軽減 |
これらの対策を組み合わせることで、トラブルは劇的に減少するはずです。最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度セッティングを決めてしまえば、あとは同じ方法で組めば安定したトラブルレスな釣りができます。
ダウンショットに最適なワームの選び方
ダウンショットリグで使用するワームは、状況に応じて使い分けることが重要です。ワームの形状、サイズ、カラー、素材によって水中での動きや波動が変わり、それがアジの反応に直結します。
🎨 カラーローテーションの重要性
アジは非常に目が良く、同じカラーを使い続けると飽きてしまう(スレる)ことがあります。特にプレッシャーの高い釣り場では、カラーローテーションが釣果を左右します。基本的には、以下のようなカラーを揃えておくとよいでしょう。
✅ 基本カラーラインナップ
- 🔵 クリア系:ナチュラルで警戒心を与えない
- 🟡 グロー系(夜光):暗い時間帯や濁り潮で視認性UP
- 🔴 ピンク・レッド系:アピール力高く活性時に効果的
- ⚫ ブラック系:シルエットがはっきりし曇天時に有効
- 🌈 ラメ入り:フラッシング効果で広範囲にアピール
状況が読めない最初の一投は、クリア系やナチュラルカラーから始めるのが無難です。反応がなければグロー系やピンク系に変更し、それでもダメなら全く違うブラック系を試すといった具合に、系統の異なるカラーをローテーションしていきます。
📏 ワームのサイズと形状
ダウンショットリグでは2~3インチのワームが使いやすいサイズです。小さすぎると視認性が落ち、大きすぎると不自然な動きになります。
形状については、ピンテール、ストレート、シャッドテールなどがあります。それぞれの特徴は以下の通りです。
📊 ワーム形状別の特徴
| 形状 | 水抵抗 | 動き | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| ピンテール | 小 | 微波動 | 低活性・クリアウォーター |
| ストレート | 小 | ナチュラル | 万能・基本形 |
| シャッドテール | 大 | 強波動 | 高活性・濁り潮 |
| カーリーテール | 大 | アピール | 広範囲サーチ |
一般的には、ストレートワームやピンテールが基本となります。これらは水抵抗が少なく、スローなアクションでもしっかりと動いてくれます。活性が高い時や広範囲を探りたい時は、シャッドテールやカーリーテールで強めにアピールするのも効果的です。
💧 素材の違いも重要
ワームの素材には大きく分けて通常素材とスーパーソフト素材があります。スーパーソフト素材は非常に柔らかく、アジが咥えた時の違和感が少ないため、吸い込みが良くなります。特にダウンショットリグとの相性が良く、多くのアングラーがスーパーソフト素材を選んでいます。
マゴバチはスーパーソフトマテリアル採用で吸い込みが非常に良く「ダウンショットアジング」に完全対応です♪
この引用で紹介されている「マゴバチ」は、ダウンショットアジングの定番ワームとして知られています。スーパーソフト素材を採用し、吸い込みやすさを重視した設計になっています。
他にも、月下美人シリーズ(ダイワ)の「ピンビーム」や「ブレーキンビーム」、アミアミ(ジャッカル)、デカジール(クリアブルー)なども人気が高く、実績のあるワームです。
最終的には、実際にフィールドで試してみて、その日のアジの好みに合ったワームを見つけることが大切です。複数のカラー、形状、サイズを持参し、状況に応じてローテーションすることが釣果アップの秘訣と言えるでしょう。
おすすめタックルセッティング
ダウンショットリグを快適に使うためには、適切なタックルセッティングが不可欠です。ジグ単用の6フィート台のショートロッドでは、遠投性能も操作性も不十分です。ここでは、ダウンショット専用のタックルセッティングを紹介します。
🎣 ロッド選び
ダウンショットリグには7.5~8フィート程度のアジングロッドが最適です。この長さなら遠投性能と操作性のバランスが良く、リグのアクションもコントロールしやすくなります。
渡邉さんは7.5~8フィートのアジング用ロッドが操作性と飛距離のバランスが取れていて扱いやすいと言う。
ロッドパワーはLクラス~MLクラスが使いやすいでしょう。あまり柔らかすぎると7gのシンカーをキャストした際に負担が大きく、逆に硬すぎるとアジのアタリを弾いてしまいます。ルアーウェイトの許容範囲が5~15g程度のモデルを選ぶと安心です。
具体的な製品としては、以下のようなモデルがおすすめです(あくまで一例です)。
✅ おすすめロッド例
- 🎣 ダイワ「月下美人エアAGS 710L/M-T」
- 🎣 ダイワ「月下美人EX 66L-S”凛”」(遠投用)
- 🎣 ヤマガブランクス「ブルーカレント」シリーズ
- 🎣 メジャークラフト「ソルパラアジングシリーズ」(コスパ重視)
🎣 リール選び
リールは2000~2500番のスピニングリールがバランス良好です。ハイギヤモデル(ギヤ比5.5~6.0程度)を選ぶと、リトリーブ時の巻き取り速度が速くなり、手返しが良くなります。
リールは2500番スピニングリールのハイギヤモデルで、PEラインは0.4号を使用。
番手が大きいと感じるかもしれませんが、遠投系リグでは糸巻き量とパワーが必要になるため、2000~2500番が適しています。ドラグ性能も重要で、大型のアジが掛かった際にスムーズにラインが出ることで、ラインブレイクを防げます。
✅ おすすめリール例
- 🎣 ダイワ「エアリティLT2000S-H」
- 🎣 シマノ「ヴァンキッシュC2000S」
- 🎣 ダイワ「月下美人AIR」シリーズ
- 🎣 シマノ「ソアレBB」(コスパ重視)
🧵 ライン選び
メインラインはPEライン0.3~0.5号が標準的です。0.4号が最もバランスが良く、遠投性能と強度を両立できます。PEラインは伸びが少ないため、遠距離でのアタリも明確に取ることができます。
リーダーには**フロロカーボン4~8ポンド(1~2号)**を使用します。リーダーの長さは1~2m程度で、FGノットなどでしっかりと結束します。フロロカーボンは比重が高く沈みやすいため、ダウンショットリグとの相性が良好です。
📊 タックルセッティング早見表
| パーツ | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| ロッド | 7.5~8ft、L~MLクラス | 遠投性と操作性のバランス |
| リール | 2000~2500番、ハイギヤ | 糸巻き量とパワー確保 |
| メインライン | PE0.3~0.5号 | 遠投性と強度の両立 |
| リーダー | フロロ4~8lb(1~2号) | 沈みやすさと耐摩耗性 |
| リーダー長 | 1~2m | PEラインの保護 |
これらのタックルを揃えることで、ダウンショットリグのポテンシャルを最大限に引き出せます。初期投資はかかりますが、ジグ単だけでは攻略できなかったポイントや状況に対応できるようになり、釣りの幅が大きく広がるでしょう。
まとめ:アジングのダウンショットリグ作り方と実践活用法
最後に記事のポイントをまとめます。
- ダウンショットリグはシンカー、フック、リーダーの3つのパーツで簡単に作れる
- エダスの取り付けは8の字結びかハーフヒッチで行い、しっかり締め込むことが重要
- エダスの長さは5cm前後がトラブルとフッキング率のバランスが最良
- フックからシンカーまでの距離は20~30cmが根掛かりと食いの良さを両立
- シンカーは3.5g、5g、7gを状況に応じて使い分ける
- フックは#8~#6の細軸タイプが吸い込みやすく推奨
- ダウンショットリグは強風時、深場、沖狙いなどジグ単で困難な状況で威力を発揮
- 基本アクションはリフト&フォール、一点シェイクも効果的
- 逆ダウンショットリグはより感度が高く大型狙いに有利
- トラブル防止にはサルカンの使用、適切なジグヘッド重量、しなやかなリーダー選びが重要
- ワームはカラーローテーションを行い、ストレートやピンテール形状が基本
- タックルは7.5~8ftのロッド、2000~2500番リール、PE0.4号が標準
- スーパーソフト素材のワームは吸い込みが良くダウンショットと相性抜群
- ナス型オモリはコスパが良く扱いやすいシンカーとして推奨
- エダスの角度を意識した結束がトラブル軽減の鍵
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- オンスタックル OFFICIAL Blog:オンスタックル発!ダウンショットアジング♪
- アジング専門/アジンガーのたまりば:アジング新革命ダウンショットリグの使い方
- ルアマガプラス:この仕掛けはヤバい!キモは「水の抵抗と浮遊感」。アジング軽量ジグ単至上主義へのアンチテーゼ!?
- オンスタックルデザイン:アジ・メバル
- 外房 アジの遠投 カゴ釣り日記:ダウンショットリグのアジングとガシリング|仕掛けと作り方
- タックルノート:アジングでダウンショットの仕掛けは有効?誘い方のコツ!
- ザルツBLOG:【アジングのやり方】基本の仕掛けとアクションを解説!初心者~上級者が楽しめる釣り♪
- 釣りの総合ニュースサイト「LureNewsR」:【渡邉長士の外房アジング】知っておきたい地域のクセと改めて見直したい「ダウンショット」
- 横浜アジング:【バチコンアジング】ダウンショットリグと逆ダウンショットリグをトラブルレスにする方法を考えてみた
- つり人:アジングの遠投系リグの使い方│フロート、キャロ、ダウンショットなど
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。