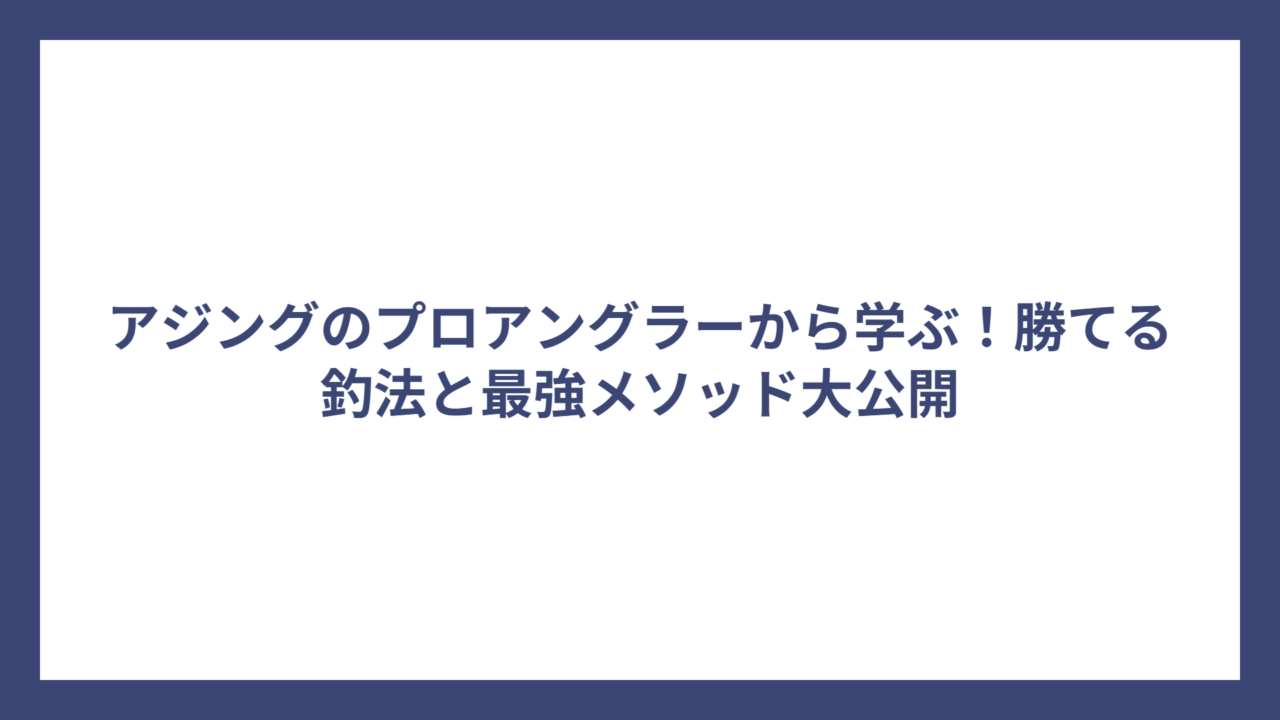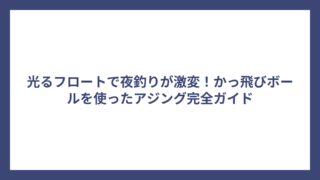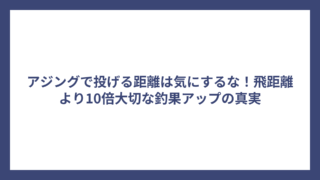アジングという釣りジャンルが確立されて以来、数多くの実力派アングラーが登場し、独自のメソッドや理論を発信しています。しかし「プロアングラー」と一口に言っても、実は明確な定義は存在しません。メーカーと契約しているフィールドテスター、大会で実績を残した競技者、YouTubeで情報発信する実力者など、様々な形でアジング界を牽引する人々がいます。
本記事では、インターネット上に散らばる情報を収集・分析し、アジング界で注目すべき実力派アングラーたちの技術やメソッド、使用タックルなどを徹底解説します。初心者から上級者まで、プロの知見から学べるポイントは数多く存在します。彼らの経験と理論を知ることで、あなたのアジングスキルも格段に向上するはずです。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジング界の主要な実力派アングラーとその特徴を網羅的に理解できる |
| ✓ プロが実践する具体的なタックルセッティングと釣法を学べる |
| ✓ アジング王BATTLEなど競技大会の実態と戦略が分かる |
| ✓ 各プロアングラーの独自メソッドと理論的背景を把握できる |
アジングのプロアングラーが実践する圧倒的テクニック
- アジング界のプロアングラーとは明確な定義がないが実力者は多数存在する
- 藤原真一郎はアジング王BATTLEで二代目王者に輝いた理論派
- 家邊克己は34代表でアジング界の伝道師と呼ばれる存在
- 安田ヒロキはバグるメソッドで注目されるマルチアングラー
- プロの基本タックルはエステルライン+フロロリーダーの組み合わせ
- ジグヘッドは0.6~1.8gを使い分け1gを基準とする
- ワームはクリア系を基本にギョピンやキメラベイトが定番
アジング界のプロアングラーとは明確な定義がないが実力者は多数存在する
アジングにおける「プロアングラー」という言葉は、実は釣り業界全体を見渡しても明確な定義が存在しません。バスフィッシングのようにプロトーナメントが確立されているジャンルと異なり、アジングは比較的新しい釣法であるため、プロの概念も曖昧なのが現状です。
一般的には、釣具メーカーと契約してフィールドテスターを務める人々、メディアで情報発信を行う実力者、競技大会で実績を残したアングラーなどが、実質的なプロとして認識されています。彼らは釣りに関連する活動で収入を得ており、かつ一定以上の釣果実績を持っているという共通点があります。
重要なのは肩書きではなく実力と釣果です。どれだけ理論を語っても、実際にアジを釣れなければ説得力はありません。逆に言えば、契約の有無に関わらず、圧倒的な釣果を出し続ける人物こそが真の実力者と言えるでしょう。
📊 プロアングラーの主な活動形態
| 活動形態 | 具体例 | 収入源 |
|---|---|---|
| フィールドテスター | メーカー契約、商品開発協力 | 契約料、テスト報酬 |
| メディア出演 | 釣りビジョン、雑誌掲載 | 出演料、原稿料 |
| YouTube配信 | りんたこ、矢野(あおむし)など | 広告収入、スポンサー料 |
| インストラクター | 釣り教室、ガイド業 | 講習料、ガイド料 |
| 競技者 | アジング王BATTLEなど | 賞金、スポンサー契約 |
近年はSNSやYouTubeの普及により、従来のメーカー契約型のプロとは異なる形で活躍する実力者も増えています。彼らは自身の経験と技術を惜しみなく公開し、アジング人口の拡大に貢献しています。本記事では、そうした様々な形で活躍する実力派アングラーたちを紹介していきます。
藤原真一郎はアジング王BATTLEで二代目王者に輝いた理論派
藤原真一郎氏は、2018年に開催された「アジング王BATTLE」セカンドシーズンで見事優勝を果たし、二代目アジング王の座に輝いた実力派アングラーです。彼の最大の特徴は、明るい人柄と冷静な理論的思考の両立にあります。
決勝戦では郷ノ浦港という難しい条件下で、唯一アジのハニースポットを見つけてポイントを伸ばしてきたアングラーがいた。そう、藤原真一郎さんだ。
この引用からも分かるように、藤原氏の強みは状況判断力の高さにあります。他の実力者たちが苦戦する中、独自の分析で釣果を重ねる姿は、まさに理論と実践の融合と言えるでしょう。
🎣 藤原真一郎の主要タックル情報
| アイテム | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | ラグゼ宵姫 天 S61L-Solid / ラグゼ宵姫 華 S82H-Solid |
| リール | がまかつ製(詳細不明) |
| ライン | エステル・フロロ・PEを状況で使い分け |
| 主な釣法 | Fシステム(遠投戦術) |
| 得意レンジ | 近・中距離戦 |
藤原氏が開発した**「Fシステム」は、遠投を可能にする独自の仕掛けシステムとして知られています。一見すると遠距離特化型のイメージがありますが、実は彼の真骨頂は近・中距離戦にあり、状況に合わせて細かく釣りを変化させるアジャスト能力**が非常に高いとされています。
競技という特殊な環境下で、初代王者トミー敦氏を含む強豪たちを抑えて優勝した実績は、藤原氏の総合力の高さを物語っています。平常心を保ちながら、冷静に状況を分析し、最適な戦略を選択する──これこそがトップアングラーの条件なのかもしれません。
家邊克己は34代表でアジング界の伝道師と呼ばれる存在
家邊克己(いえべ・かつみ)氏は、アジング界において**「伝道師」**とも呼ばれる重要人物です。釣り歴40年以上という豊富な経験を持ち、現在は釣具メーカー「34(サーティフォー)」の代表として、アジング用品の開発にも深く関与しています。
家邊氏の凄さは、単に釣りが上手いだけでなく、アジングという釣法そのものの普及と発展に尽力してきた点にあります。初心者向けの基礎講座から、豆アジ特化の技術、尺アジを狙う高度なテクニックまで、幅広い知識と経験を持っています。
彼の特徴的なアプローチとして、常夜灯下のプランクトンパターンの解明があります。多くのアングラーが何となく常夜灯周りで釣りをする中、家邊氏はプランクトンの動きや集まり方を科学的に分析し、より効率的な攻略法を確立しました。
📚 家邊克己が提唱する主な理論
- 軽量ジグヘッドの極限追求:0.4g以下の超軽量リグの使用
- プランクトンパターンの理解:光に集まる習性の利用
- 豆アジ専用セッティング:10~15cm級に特化したタックル
- 尺アジへのアプローチ:大型専用の戦略立案
家邊氏が展開する情報発信は、理論と道具の両面からアジングを解説する点で非常に分かりやすく、多くのアジンガーが参考にしています。「この人を知らずしてアジングは語れない」と言われるほど、業界における影響力は絶大です。
特に注目すべきは、彼が単なる釣り人ではなくメーカー代表として商品開発にも携わっている点です。実際のフィールドで得た知見を製品に反映させることで、より実用的なアイテムが生まれています。これは、プロアングラーの新しい形とも言えるでしょう。
安田ヒロキはバグるメソッドで注目されるマルチアングラー
安田ヒロキ氏は、1990年生まれの神奈川県在住のアングラーで、シーバスフィッシングでの活躍が有名ですが、実はアジングにおいても高い実力を持っています。彼を一躍有名にしたのが、バグラチオンというルアーを使った早巻きメソッド**「バグる」**です。
安田氏の特徴は、アングラーとしての真摯な姿勢と安全・環境問題への高い意識にあります。メーカーやテスターに対してあまり良い印象を持っていなかった人々も、彼の人柄に触れることでファンになるケースが多いようです。
ロッド:APIA ・GRANDAGE LITE55 リール:シマノ・19バンキッシュ C2000SSS ライン:YGK よつあみ・D-PET 0.3号 リーダー:YGK よつあみ・AMBERCORD FC 4.6lb
このタックルセッティングで注目すべきは、やや太めのフロロリーダーを矢引き分(約75cm)の長さで使用している点です。その理由について、安田氏は「水中でリーダーを立たせたいから」と説明しています。リーダーがしっかり立つことで流れの抵抗を感じやすくなり、ジグヘッドの状態を把握しやすくなるという理論です。
🎯 安田ヒロキのアジング基本メソッド
- 着水後はベイルを返さずフリーフォール
- 任意のレンジに到達したら糸ふけをとる
- 数回シェイクしながらリフト
- ピタッと止めてカーブフォール
- 止める時に誘った分のロッド位置を下げない
このメソッドは、一般的に知られている「着水後すぐにベイルを返してカーブフォール」という手法とは真逆のアプローチです。特に水深のある場所では、フリーフォールによって長い距離をトレースできるため、より効率的に魚を探せるという利点があります。
安田氏はまた、ボートアジングの有効性も強調しています。オカッパリで釣果が上がらない初心者が、確実に魚がいる場所で純粋に技術を磨くことができるため、上達の近道になるという考えです。この提案は、実践的で親切なアドバイスと言えるでしょう。
プロの基本タックルはエステルライン+フロロリーダーの組み合わせ
アジングのプロアングラーたちのタックルセッティングを分析すると、ある共通点が浮かび上がってきます。それは、メインラインにエステル、リーダーにフロロカーボンを使用するという組み合わせです。この選択には、それぞれ明確な理由があります。
エステルラインが選ばれる理由:
- 感度の高さ:伸びが少なく、微細なアタリも手元に伝わる
- 沈みやすさ:水に沈むため、ディープレンジを探りやすい
- 風の影響を受けにくい:PEと比較して風に強い
- 視認性の確保:色付きエステルなら着底やフォール中のバイトが分かりやすい
一方、フロロカーボンリーダーの役割は以下の通りです:
- 耐摩耗性:ボトムや障害物への接触に強い
- 適度な張り:リーダーが水中で立ちやすい
- 透明度:魚に警戒されにくい
- 結節強度:エステルとの結束で強度を確保
📊 プロアングラーのライン選択比較
| アングラー | メインライン | リーダー | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 安田ヒロキ | D-PET 0.3号(色付き) | FC 4.6lb(長め) | リーダーを立たせる設計 |
| 藤原真一郎 | エステル/PEを使い分け | 状況により変更 | 多様な状況に対応 |
| 一般的推奨 | エステル 0.25~0.3号 | フロロ 3~4lb | バランス重視 |
ライン選択において重要なのは、ロッドとのバランスです。高価なリールを使えば良いというわけではなく、ロッドの硬さや長さ、リールの重量などを総合的に考慮する必要があります。高級品を安易に購入すると持ち重りが発生し、かえって扱いづらくなる可能性もあるのです。
特に注目すべきは、色付きエステルラインの使用です。視認性が高いことで、フリーフォール時の着底判断やフォール中のバイト検知が容易になります。また、ライントラブルの早期発見にも繋がるため、初心者にもおすすめの選択と言えるでしょう。
ジグヘッドは0.6~1.8gを使い分け1gを基準とする
プロアングラーたちのジグヘッド選択を見ると、1gを基準として、0.6~1.8g程度の範囲で使い分けるというパターンが一般的です。この重量選択には、ポイントの水深、潮の流れの速さ、アジの活性など、様々な要因が関係しています。
「ジグヘッドは一回でも使ったら交換する」
この発言は、某ルアーメーカー大手でライトゲーム関連の開発を担うプロとの会話で明かされたものです。洗うとか研ぐとかではなく、一度使ったら交換。これは極端に聞こえるかもしれませんが、アジングにおいてハリ先の鋭さが最重要であることを示しています。豆アジ相手でも常に万全の態勢を整えるというプロの姿勢が表れています。
🔧 ジグヘッド重量の使い分け基準
| 重量 | 使用状況 | 特徴 |
|---|---|---|
| 0.4~0.6g | 超スローフォール、表層狙い | 食わせ重視、風や流れが弱い時 |
| 0.8~1.0g | 標準的な状況 | 最もバランスが良い、汎用性高 |
| 1.2~1.5g | やや深場、流れがある時 | 素早く沈める必要がある場合 |
| 1.8g以上 | ディープエリア、強い流れ | ボトム攻略、遠投が必要な時 |
ジグヘッドの形状も重要な要素です。プロの間で人気が高いのは34(サーティフォー)のストリームヘッドです。このジグヘッドが選ばれる理由は、アジの捕食行動に基づいた設計にあります。
アジは捕食時に一度口の中に吸い込んで吐き出す習性があるとされています。ストリームヘッドは、この吐き出す瞬間に自然とフッキングするよう設計されているのです。つまり、アジの生態を理解した上での形状選択というわけです。
また、ワームとジグヘッドの間に隙間があると全く食ってこないという指摘も重要です。そのため、瞬間接着剤で固定するプロも多いようです。こうした細かな工夫の積み重ねが、釣果の差として現れるのでしょう。
ジグヘッド選びにおいては、単に重さだけでなく、フックサイズ、フック形状、ヘッド形状なども考慮する必要があります。ジャッカルの「スイスイスイムジグヘッド」のように、重量が刻印されているタイプは現場での判断がしやすく便利です。
ワームはクリア系を基本にギョピンやキメラベイトが定番
プロアングラーたちが使用するワームを調査すると、いくつかの定番アイテムが浮かび上がってきます。特に推奨されることが多いのが、TiCTのギョピン1.7インチと34のキメラベイト2.0インチです。
ワームはクリア系が基本!クリアや、クリアベースでラメの入ったカラーを中心にして、その他カラーはスレの進行を抑えるためにローテーションする
この助言は非常に重要です。多くの初心者は様々なカラーを試したくなりますが、プロの基本はクリア系。これには明確な理由があります。クリアカラーは自然界に存在するプランクトンや稚魚に近い透明感を持ち、警戒心の高いアジにも違和感を与えにくいのです。
🐟 定番ワームの特徴比較
| ワーム名 | サイズ | 特徴 | 使用場面 |
|---|---|---|---|
| ギョピン | 1.7インチ | スタンダードな形状 | オールラウンド |
| キメラベイト | 2.0インチ | 抵抗大、フォール遅い | アピール強化時 |
| デカキビナ~ゴ | 2.5インチ | パールホワイトが人気 | 活性高い時 |
ワームサイズの選択も重要です。一般的にメバルを狙う際のスタンダードは2インチとされていますが、アジングではもっと小さいサイズも有効です。食いが渋い時は1.5インチ以下にサイズダウンすることで、シルエットを小さくして警戒心を和らげることができます。
興味深いのは、あるライトゲームのレジェンドが語った以下のエピソードです:
「昔はメバルを狙う時、アオイソメをそのまま1匹つけていた。15cmもあるような……」エサで狙う時は5inchも8inchもあるような長さのエサなのに、なぜワームにするとみんな小さくなるのか?
この発言は、ワームサイズに対する固定観念を打ち破るものです。エサ釣りでは大きなアオイソメを使うのに、ルアーになると小さくしがち。しかし、あえて大きなワームを使うことで、メバル(やアジ)側も本気で食ってこないといけない状況を作り出せるという考え方です。
ワームの形状も重要な要素です。ストレート系、シャッド系、グラブ系など様々な形状があり、それぞれ「波動」や「水噛み」といった特性が異なります。波動とはワームが水中で生み出す振動のことで、水噛みとは水の抵抗を受ける度合いのことです。フォールスピードを遅くしたい時はキメラベイトのように抵抗の大きいボディ形状を選ぶ、といった使い分けが可能になります。
プロアングラーから見るアジングの深層世界
- プロの釣り方は着底後シェイク&カーブフォールが基本動作
- アジング王BATTLEは実力派が競う公式競技大会
- プロアングラーの多くはメーカーのフィールドテスターを務める
- りんたこや矢野(あおむし)などYouTuberプロも活躍中
- 丹羽喜嗣や本岡利將など独自メソッドを持つプロたち
- まとめ:アジングのプロアングラーから学ぶべきポイント
プロの釣り方は着底後シェイク&カーブフォールが基本動作
多くの初心者が動画で学ぶアジングの基本動作は、「着水後ベイルを返してカーブフォール→任意のレンジでチョンチョンとアクション→ゆっくりと竿でサビくように一定レンジをキープ」というパターンでしょう。しかし、プロアングラーの実践する基本動作は、これとは異なるアプローチを取ることが多いようです。
プロが実践する基本動作(夏季・ボトム中心の場合):
- キャスト:できるだけライナー性の軌道を心掛ける
- フリーフォール:着水後ベイルを返さずにフリーフォール
- 着底確認:任意のレンジ(ボトム)に到達
- リトリーブ開始:糸ふけを取って数回シェイクしながらリフト
- ステイ:ピタッと止める(この時ロッド位置を下げない)
- カーブフォール:テンションを保ったまま落とす
- 繰り返し:4~6を繰り返す
この手法の最大のポイントは、「ピタッと止める」瞬間にあります。シェイクで誘った後、誘った分のロッドティップの位置を下げずに静止することで、明確な「食わせの間」を作り出します。この止めた瞬間にバイトが集中するため、ここでの集中力が釣果を左右します。
🎯 状況別アプローチの違い
| 状況 | アプローチ | 理由 |
|---|---|---|
| 表層パターン | カーブフォール中心 | プランクトンを意識 |
| ボトムパターン | フリーフォール→シェイク | 素早く沈めて効率的に探る |
| 中層回遊 | 水平移動重視 | 一定レンジをキープ |
| 低活性 | 超スローor超ファスト | 極端な動きで反応を誘う |
興味深いのは、速い釣りも有効という指摘です。一般的にアジングはゆっくりした釣りというイメージがありますが、ある実力者は以下のように語っています:
「釣れない状況が続くと不必要にルアーを軽く/小さくしたりゆっくり深く・長く流したりなど、やりがちである。しかし、それでも食わないとなるとその逆を行くしか手立てがありません」
つまり、連続トゥイッチで素早く誘い、食わせの間を入れるという、フィッシュイーターを誘うような釣り方も状況によっては非常に効果的だということです。アジは成長するにつれて稚魚も捕食するようになるため、逃げ惑う小魚を演出することで捕食スイッチを入れられる可能性があるのです。
また、バイトがない時は回遊を待つのではなく移動するというのもプロの考え方です。アジは居る場所には長時間居座る傾向があるため、反応がなければ魚が居る場所を探してランガンした方が効率的だという理論です。これは競技という時間制限のある状況では特に重要な戦略となります。
アジング王BATTLEは実力派が競う公式競技大会
「アジング王BATTLE」は、ルアーマガジンソルト誌で連載されているアングラー対戦企画で、アジング界における最も注目度の高い競技大会の一つです。本誌によって選出されたプロアングラー8名が1対1で対決し、勝ち上がった4人が決勝戦に進むというトーナメント形式で行われます。
2018年のセカンドシーズン決勝戦は、長崎県の壱岐島で開催されました。ファイナリストとして残ったのは、藤原真一郎、丹羽喜嗣、渡邉長士、そして初代王者のトミー敦(富永敦)という、いずれも実力者揃いの顔ぶれでした。
📊 2018年アジング王BATTLE決勝戦ファイナリスト
| アングラー | 主な特徴 | 使用ロッド | 戦略 |
|---|---|---|---|
| 藤原真一郎 | Fシステム、近中距離が真骨頂 | ラグゼ宵姫 天/華 | アジャスト能力 |
| 丹羽喜嗣 | ウルトラシュート開発、ロジカル | ソアレCI4+ | 効率的戦略 |
| 渡邉長士 | マルチアングラー、経験豊富 | 月下美人AIR AGS | 堅実な試合運び |
| トミー敦 | 初代王者、高いアジャスト能力 | SRAM EXR-57S他 | コンパクトな釣り |
決勝戦は非常にドラマチックな展開となりました。最初のポイント「郷ノ浦港・東南部」は、夕マヅメに尺を超えるアジが釣れる場所として知られていましたが、実際には予想以上にシビアな条件でした。
大差がつきにくいと思われていた、郷ノ浦港のシビアな条件下の中、唯一、アジのハニースポットを見つけてポイントを伸ばしてきたアングラーがいた。そう、藤原真一郎さんだ。
競技ならではのルールも興味深い要素です。例えば、移動提案は2名以上の賛成が必要で、意見が分かれた場合は代表者によるじゃんけんで決着。また、「マイフィールド宣言」というルールがあり、宣言者を中心に半径5mへの侵入を30分間拒否できるという戦略的要素も含まれています。
決勝戦では、トミー・渡邉ペアが移動を拒否し、湯ノ本への移動タイミングをコントロールしようとする戦略を展開しました。彼らの狙いは、終了時間を見越したタイミングでマイフィールド宣言を使い、効果終了時からでは巻き返せないようにすることでした。しかし、結果的にこの戦略は裏目に出てしまいます。
最終結果は、藤原真一郎13尾13ポイント、渡邉長士7尾9ポイント、丹羽喜嗣8尾8ポイント、トミー敦6尾6ポイントとなり、藤原真一郎氏が二代目アジング王の座に輝きました。ペースを崩さず平常心で釣りを続けた彼の対応力は、まさに圧巻でした。
プロアングラーの多くはメーカーのフィールドテスターを務める
アジング界のプロアングラーを見渡すと、その多くが釣具メーカーのフィールドテスターとして活動していることが分かります。フィールドテスターとは、メーカーが開発中の製品を実際のフィールドでテストし、改善点や使用感をフィードバックする役割を担う人々です。
例えば、SHIMANOの契約アングラーには丹羽喜嗣氏の名前があり、ソルトウォーター部門で活躍しています。SHIMANOのような大手メーカーとの契約は、アングラーにとって大きなステータスであり、同時に責任も伴います。
🏢 主要メーカーとフィールドテスター例
| メーカー | 代表的なテスター | 主な活動内容 |
|---|---|---|
| 34(サーティフォー) | 家邊克己 | 代表兼開発責任者 |
| SHIMANO | 丹羽喜嗣 | ソアレシリーズのテスト |
| APIA | 安田ヒロキ | グランデージシリーズの使用 |
| がまかつ | 藤原真一郎 | ラグゼ宵姫シリーズ |
| DAIWA | 渡邉長士 | 月下美人シリーズ |
| ティクト | トミー敦 | SRAM シリーズ |
フィールドテスターの仕事は、単に製品を使うだけではありません。実戦での使用感、改善提案、ユーザーへの情報発信など、多岐にわたります。特に重要なのが、一般アングラーに対する製品の使い方や有効性を伝える役割です。
メーカーにとって、フィールドテスターは製品開発のパートナーであり、ブランドの顔でもあります。そのため、単に釣りが上手いだけでなく、コミュニケーション能力や人柄も重視されます。安田ヒロキ氏のように、礼儀正しく人懐っこい人柄が評価されるのは、こうした背景があるからです。
また、フィールドテスターは製品に対する忠実性も求められます。契約メーカーの製品を使用し、その良さを伝えることが基本です。ただし、最も重要なのは釣果であり、どれだけ製品を褒めても釣れなければ説得力はありません。
近年では、YouTubeやSNSを通じた情報発信も重要な役割となっています。動画で実際の使用シーンを見せることで、製品の特徴や使い方がより分かりやすく伝わるためです。これにより、従来の雑誌やイベントだけでなく、デジタル媒体での活躍も求められるようになっています。
りんたこや矢野(あおむし)などYouTuberプロも活躍中
近年のアジング界では、YouTubeを主な活動の場とする新しいタイプのプロアングラーが台頭しています。その代表格が**りんたこ(岩崎林太郎)と矢野(あおむし)**です。彼らは従来のメーカー契約型とは異なる形で影響力を持っています。
りんたこ / Angler Rintaco
YouTubeチャンネル登録者数は109K(約11万人)を超え、実釣中心の動画に加えて細やかなテクニック解説も充実しています。彼はDAIWAのサポートを受けるプロアングラーであり、開発者としての視点も持ち合わせています。
特筆すべきは、デイアジングの攻略法や満月時の奥義など、通常のナイトゲームだけでなく、より難易度の高い状況での攻略法も発信している点です。また、メバリングでも高い実力を持ち、「尺メバルハンター」としても知られています。
ちなみに、りんたこ氏の配偶者は秋丸美帆氏(通称:みっぴ)で、彼女もまた美人釣りガールとして有名です。お二人とも釣り業界で活躍する、いわゆる「釣りカップル」として注目を集めています。
矢野(あおむし)
矢野氏は愛媛県を拠点とするベテランアングラーで、累計30,000匹以上のアジを釣り上げたという驚異的な実績を持っています。2013年から国内最古の針メーカー「土肥富(どひとみ)」のフィールドテスターを務め、レンジクロスヘッドやフロードライブヘッドなど、数々の人気ジグヘッドの設計・テストに携わっています。
YouTubeチャンネル「矢野のアジングch」は登録者2万人超で、初心者にもわかりやすい釣法解説やタックル紹介を発信しています。また、ブログ「あおむしの釣行記4」では、より詳細な情報や考察を提供しており、文章による情報発信も充実しています。
📺 YouTuberプロの特徴比較
| アングラー | 登録者数 | 主なコンテンツ | 強み |
|---|---|---|---|
| りんたこ | 約11万人 | 実釣、ギア紹介、デイゲーム | エンタメ性と実用性の両立 |
| 矢野(あおむし) | 約2万人 | 初心者向け解説、タックル紹介 | 30,000匹の実績に基づく説得力 |
YouTuberプロの最大の強みは、動画による分かりやすさにあります。文章や写真だけでは伝わりにくいロッドワークやアタリの取り方、ランディングの様子などを、実際の映像で確認できるため、視聴者の理解が深まります。
また、YouTubeの広告収入やスポンサー契約により、従来のメーカー契約に依存しない収入源を確保できる点も特徴です。これにより、より自由な立場で情報発信ができるという利点もあります。ただし、定期的な動画投稿や編集作業など、コンテンツ制作の労力は相当なものだと推測されます。
丹羽喜嗣や本岡利將など独自メソッドを持つプロたち
アジング界には、独自のメソッドや理論を確立し、それを体系化して発信している実力派アングラーが数多く存在します。その中でも特に注目すべきなのが、**丹羽喜嗣(にわ・よしつぐ)と本岡利將(もとおか・としまさ)**です。
丹羽喜嗣の理論と活動
丹羽氏はSHIMANO契約フィールドテスターとして活躍し、**「ウルトラシュート」**という遠距離特化型フロートリグを開発したことで知られています。しかし、彼の真の強みは遠距離だけでなく、ジグ単での近距離戦にもあります。
普段、デイアジングを楽しむことから、よりシビアな環境でのアジングが本戦でも活きたといえる。また、釣りが非常にロジカルで効率的。
丹羽氏の特徴は、フカセ釣りの理論をルアーゲームに応用するという独自のアプローチです。魚の行動と地形・潮の関係を深く理解し、理論と現場を融合させた釣りを展開します。彼はオンラインサロン「丹羽喜嗣のミリオンアジング」を運営し、参加者と情報交換しながらノウハウを磨く双方向型の活動も行っています。
本岡利將のベイトフィネスとハードルアー
本岡氏はClearBlue代表であり、17年以上のアジング歴を持つ探究心の塊のようなアングラーです。彼の最大の特徴は、アジングにベイトタックルやハードルアーを導入するなど、従来の常識にとらわれない新たなアプローチを開拓している点です。
彼が提唱する釣法の一つに、ショートスプリットショットリグがあります。これは通常のスプリットショットよりもリーダーを短く設定することで、より感度を高める仕掛けです。また、全国各地で尺アジを釣りまくる実績があり、「感度バカ」を自称するほど感度にこだわりを持っています。
本岡氏は釣りビジョンの番組「青色アジング」に出演しており、ベイトフィネスアジングやハードプラグの使用など、ユニークな釣りを披露しています。おそらく、こうした新しい試みは一般アングラーには受け入れられにくい面もあるかもしれませんが、釣りの可能性を広げる重要な実験と言えるでしょう。
🎣 独自メソッドを持つプロアングラー
| アングラー | 独自メソッド | 活動拠点 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 丹羽喜嗣 | ウルトラシュート、フカセ理論応用 | 瀬戸内 | ロジカル・効率的 |
| 本岡利將 | ベイトフィネス、ハードルアー | 全国各地 | 探究心・感度重視 |
| 有馬義昭 | 激流エリア攻略 | 北九州 | 20年以上の経験 |
| ピン子(P!NKO) | クイック&スロー戦略 | 福岡 | 時短・都市部特化 |
他にも、有馬義昭氏は福岡・北九州を拠点に20年以上のアジング歴を持ち、湾奥から関門海峡の激流エリアまで幅広く対応する実力者です。彼は定期的に「鯵馬塾」という講習会を開催しており、地元での普及活動にも熱心です。
また、**ピン子(P!NKO)**は福岡のライトゲームシーンで活躍し、「クイック&スロー」の2本軸戦略を提唱しています。彼が開発に関わったオリジナルワーム「アジピンピン」は豆アジ特化のアイテムとして注目を集めました。都市部での時短アジングにも精通しており、玄界島など近郊離島での効率的な釣り方を伝授しています。
萩原トオル氏は、テトラワークス(DUO)のブランド責任者として、年間200日以上釣行するというストイックな活動を続けています。Instagramでの情報発信やルアマガプラスでのビギナー向け講座など、親しみやすい「アジおじさん」キャラで幅広い層から支持されています。
まとめ:アジングのプロアングラーから学ぶべきポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングにおける「プロアングラー」の明確な定義は存在しないが、メーカー契約者や競技実績者が実質的なプロとして認識されている
- 藤原真一郎は2018年アジング王BATTLE優勝者で、Fシステムを開発した理論派アングラーである
- 家邊克己は34代表としてアジング用品開発に携わる「伝道師」的存在で、軽量ジグヘッド技術を確立した
- 安田ヒロキはシーバスで有名だがアジングでも高い実力を持ち、「バグる」メソッドで注目を集めた
- プロの基本タックルはエステルライン0.25~0.3号にフロロリーダー3~4lbの組み合わせが主流である
- ジグヘッドは1gを基準に0.6~1.8gを使い分け、ハリ先の鋭さを保つため頻繁に交換する
- ワームはクリア系を基本とし、ギョピン1.7インチやキメラベイト2.0インチが定番アイテムとされる
- プロの基本動作はフリーフォール→着底→シェイクしながらリフト→ピタッと止めてカーブフォールという流れである
- アジング王BATTLEは8名のプロアングラーがトーナメント形式で競う公式競技大会で、2018年は藤原真一郎が優勝した
- 多くのプロアングラーは釣具メーカーのフィールドテスターとして製品開発やテストに携わっている
- りんたこ(登録者11万人)や矢野(累計3万匹釣果)などYouTuberプロが新しい形で影響力を持つ
- 丹羽喜嗣はウルトラシュート開発者でロジカルな釣りを展開し、本岡利將はベイトフィネスなど新手法を開拓する
- 有馬義昭は北九州で20年以上の経験を持ち鯵馬塾を開催、ピン子は時短アジングの第一人者である
- 萩原トオルはテトラワークス責任者として年間200日以上釣行し、初心者向け情報発信に熱心である
- プロの釣り方には「速い釣り」も含まれ、連続トゥイッチで誘う手法も状況次第で有効である
- バイトがない時は回遊待ちではなくランガンして魚を探す方が効率的とされる
- ワームとジグヘッドの隙間は瞬間接着剤で固定するなど細部へのこだわりが釣果を分ける
- プロアングラーは単に釣りが上手いだけでなく、人柄やコミュニケーション能力も評価される
- 競技では釣座優先権やマイフィールド宣言など戦略的要素が勝敗を左右する
- YouTubeやSNSを通じた情報発信が現代のプロアングラーには不可欠な活動となっている
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 元釣具屋店員が教える「プロアングラーから聞いて驚いた小話」4選 | TSURINEWS
- 【2018アジング最強は誰だ!】アジング王BATTLEセカンドシーズン壱岐島決勝戦! 二代目アジング王がついに決定。その名は……│ルアマガプラス
- 【安田ヒロキ直伝】迷える初心者の為のアジング基本講座 | 釣リズム
- 最強のアジンガーを紹介!? タヌキが注目してるアジングのプロは? | アジング専門/アジンガーのたまりば
- 契約アングラー | SHIMANO シマノ
- 【アジング釣行記】マイクロジグでスレがかり連発?特徴や体験談を踏まえて理由をプロアングラーが考察してみた|ねこりく
- オールナイトアジング!爆釣良型入れ食い編 | teamOMT事務局長のフィッシングライフ
- 【アジング】ゆっくり巻いたり 流すだけじゃありませんよ|okada_tsuri
- 家邊克己 – アジング ライトゲーム フィッシング|THIRTY34FOUR
- 矢野のアジングch – YouTube
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。