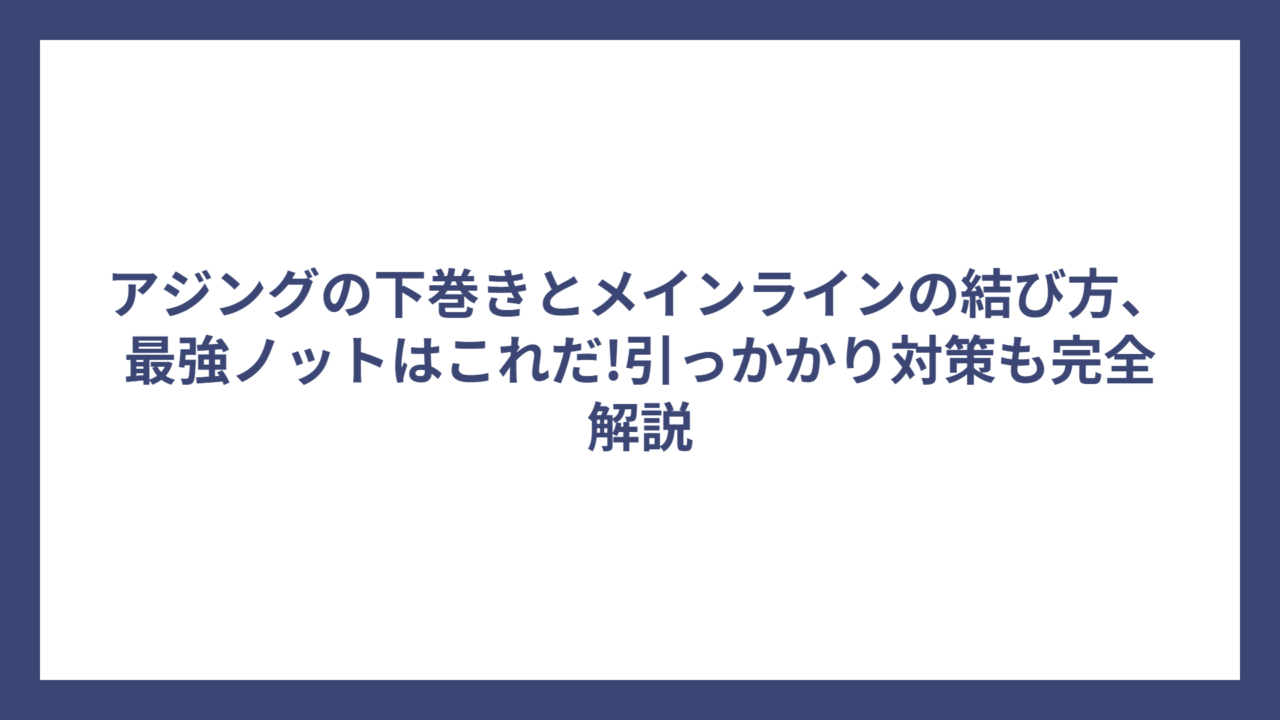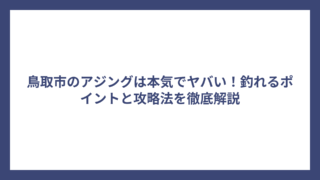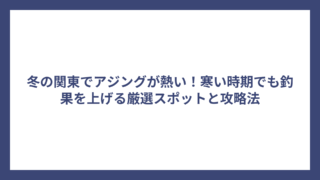アジングをやっていると避けて通れないのが、リールへのライン巻き。特に下巻きとメインラインをどう結ぶかは、初心者から中級者まで悩むポイントですよね。結び方を間違えると、キャスト時に結び目が引っかかったり、いざという時に切れてしまったりと、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。
実は、アジングで使うラインの種類(PE、エステル、フロロなど)によって、最適な結び方は変わってきます。ネット上には様々な情報が散らばっていますが、今回はそれらを徹底的に調査し、実際の強度テストデータや使用者の声を集めて、本当に使える結び方を厳選しました。この記事を読めば、あなたのアジングタックルがもっと信頼できるものになるはずです。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジングで使える下巻きとメインラインの結び方3種を強度データで比較 |
| ✓ 結び目が引っかかる問題の具体的な解決策 |
| ✓ エステルライン・PE使用時の下巻き計算方法と注意点 |
| ✓ リール番手別の下巻き必要性と実践的なテクニック |
アジングで使う下巻きとメインラインの結び方の基本
- アジングの下巻きとメインラインの結び方は「電車結び」「ブラッドノット」「フィッシャーマンズノット」が主流
- 電車結びは簡単だが強度は約50%程度
- ブラッドノットは強度80%で最もおすすめ
- フィッシャーマンズノットは中間的な選択肢
- PE同士の下巻き結び方は電車結びが基本
- エステルラインの下巻き結び方はテンション管理が重要
アジングの下巻きとメインラインの結び方は「電車結び」「ブラッドノット」「フィッシャーマンズノット」が主流
アジングにおける下巻きとメインラインの結束方法は、大きく分けて3つのノットが実用的とされています。それぞれ特徴があり、使用するラインの種類や求める強度によって使い分けることが重要です。
まず理解しておきたいのは、下巻きとメインラインの結束では、FGノットなどの摩擦系ノットは向いていないという点です。なぜなら、下巻きのライン先端はスプールに固定されているため、編み込み系の複雑なノットは非常に結びにくいからです。
📋 アジングで使われる主要な下巻き結束ノット
| ノット名 | 難易度 | 結束強度 | 結び目サイズ | 向いているライン |
|---|---|---|---|---|
| 電車結び | ★☆☆ | 約50% | 中 | PE・エステル・ナイロン全般 |
| ブラッドノット | ★★☆ | 約80% | 小 | 同素材同士、細いライン向き |
| フィッシャーマンズノット | ★☆☆ | 約70% | 中 | PE・エステル・ナイロン全般 |
インターネット上の釣り情報を調査したところ、実際に下巻きラインまでラインを出し切ってしまう状況は稀ですが、ゼロではないことが分かりました。特にドテラ流しでアルミ製軽比重ジグを使用する際や、高切れでラインキャパシティが減った状態で釣りをする場合など、想定外の状況は起こりうるのです。
風で船が流される関係で極端に斜めに入っていることもあるのですが、とうとう巻いてあるPEラインをすべて出し切って、下巻きがすこし出るくらいまでラインを流してしまうことがありました。
このような実例から、「下巻きは見えないから適当でいい」という考えは危険です。むしろ、いざという時のための保険として強度の高い結び方を選ぶべきと言えます。
また、下巻きとメインラインの素材の組み合わせも重要です。ナイロンとPE、フロロとエステルなど、異なる素材を結ぶ場合、素材の硬さや表面の滑りやすさの違いが結束強度に影響します。一般的には、同じ素材同士の方が結束しやすいとされていますが、必ずしもそうとは限らないケースもあります。
さらに、結び方を選ぶ際は「結び目のサイズ」も考慮ポイントです。結び目が大きいと、キャスト時にガイドに引っかかったり、巻き取り時にスプールへの食い込みが起きやすくなります。特に極細ラインを使用するアジングでは、できるだけコンパクトな結び目を作ることが望ましいでしょう。
電車結びは簡単だが強度は約50%程度
電車結びは、アジングやメバリングなどライトゲーム全般で最も基本的な結束方法として知られています。2本のラインをお互いにユニノットで結び合わせるだけという、非常にシンプルな構造です。
この結び方の最大のメリットは、覚えやすく、暗闇でも結べるという点にあります。ナイトゲームが多いアジングでは、この「暗い中でも結べる」という特性は非常に重要です。複雑なノットは明るい場所でないと難しいですが、電車結びなら慣れれば1分もかからず結べます。
「電車結び」とは、ラインとラインを繋ぎ合わせる結び方の一つ。結び方も非常に簡単かつシンプルで、結ぶために特別な道具も必要ない事から、初心者が覚えるのにはピッタリなノットである。
しかし、気になるのはその強度です。実際に強度テストを行ったデータによると、ナイロン3号を下巻きに使用し、PE2号をメインラインとして電車結びで結束した場合、約2.5kg前後で切れたという結果が報告されています。これはナイロン単体の強度(約5kg)の約50%程度です。
🔍 電車結びの強度テスト結果
| 測定項目 | 結果 |
|---|---|
| 使用ライン | 下巻き:ナイロン3号 / メイン:PE2号 |
| 破断強度 | 約2.5kg |
| ライン単体強度に対する割合 | 約50% |
| 切れ方 | ナイロン側のノット部分 |
この50%という数値をどう評価するかは、釣りのスタイルによって変わります。通常のアジング(豆アジ~25cm程度)であれば、2.5kgもの負荷がかかることはまずありません。リールのドラグを適切に設定していれば、下巻きまでラインが出た状態で魚を掛けても、おそらく問題なく対応できるでしょう。
ただし、不意に大型の外道(メバル、シーバス、チヌなど)が掛かった場合や、根ズレが発生した場合は注意が必要です。特にリールからラインが多く出た状態では、物理法則上ドラグ力が強くなっていくため、想定以上の負荷がかかる可能性があります。
それでも電車結びが広く使われているのは、シンプルさと実用性のバランスが取れているからです。結び方を覚える手間、現場での結びやすさ、そして実釣で十分な強度を考えると、初心者から中級者にとって最初に習得すべきノットと言えるかもしれません。
ブラッドノットは強度80%で最もおすすめ
アジングの下巻き結束において、最も高い強度を実現できるノットがブラッドノットです。強度テストの結果では、電車結びやフィッシャーマンズノットを大きく上回る約80%の強度を記録しています。
ブラッドノットは、2本のラインを互いに巻き付け合う構造で、見た目は少し複雑に見えますが、実際にやってみると意外と簡単です。PE側の巻き付け回数を7回程度に増やすことで、より強度を高めることができます。
ブラッドノット
私がジギングを覚える前、ボートや堤防でアジなどを狙っていた時によく使っていたノットです。複雑そうに見えますがとっても簡単なのでオススメです。これもPE側の巻きつけを7回と増やして結んでいます。結果は4kg前後。80%です。
この約4kg(80%)という数値は、ナイロン3号+PE2号の組み合わせで測定されたものです。電車結びの2.5kg(50%)と比較すると、1.6倍の強度差があることになります。これは大きな違いです。
📊 各ノットの強度比較(ナイロン3号+PE2号)
| ノット名 | 破断強度 | 強度率 | 電車結びとの差 |
|---|---|---|---|
| 電車結び | 約2.5kg | 約50% | – |
| フィッシャーマンズノット | 約3.25kg | 約70% | +0.75kg |
| ブラッドノット | 約4.0kg | 約80% | +1.5kg |
ブラッドノットが高強度を発揮する理由は、ラインの接触面積が大きく、力が分散される構造にあると推測されます。電車結びが単純に2つのユニノットを引き寄せるのに対し、ブラッドノットは互いに巻き付け合うため、より多くのラインの摩擦力を利用できるのです。
ただし、ブラッドノットにも弱点があります。それは極端に太さが違うライン同士では結びにくいという点です。例えば、下巻きが5号で メインラインが0.3号といった組み合わせでは、巻き付けのバランスが取りにくく、結束強度が落ちる可能性があります。
また、すべての強度テストで確認されているように、切れる箇所はナイロン側のノット部分です。つまり、下巻きのラインが太ければ太いほど、結束部分の強度も上がることになります。一般的には3号~5号程度のナイロンやフロロを下巻きに使うことが多いですが、大物狙いや安心感を重視するなら、5号以上を選ぶのも一つの選択肢でしょう。
ブラッドノットは少し練習が必要ですが、一度覚えてしまえば安定して強度の高い結束ができます。特にアジング以外の釣りでも幅広く使えるノットなので、習得しておいて損はありません。
フィッシャーマンズノットは中間的な選択肢
フィッシャーマンズノットは、電車結びとブラッドノットの中間的な性能を持つノットとして位置づけられます。強度テストでは約3.25kg(約70%)という結果が出ており、電車結びよりは強く、ブラッドノットよりはやや劣るという特性です。
このノットは、基本的には電車結びの変形版と考えることができます。構造は電車結びに似ていますが、PE側の巻き付け回数を増やすことで強度を向上させています。そのため、電車結びを覚えた人であれば、比較的スムーズに習得できるでしょう。
✅ フィッシャーマンズノットの特徴
- ✓ 電車結びの応用版で覚えやすい
- ✓ 強度は約70%と中間的
- ✓ 結び目のサイズは中程度
- ✓ 異素材同士でも使用可能
- ✓ 巻き付け回数の調整で強度を微調整できる
フィッシャーマンズノットが有効なのは、「電車結びでは強度が不安だけど、ブラッドノットを覚えるのは面倒」という場合です。実際、アジングでは豆アジから尺アジまで様々なサイズが釣れますが、その中間サイズ(15~23cm程度)を主なターゲットとするなら、70%の強度でも十分実用的かもしれません。
ただし、正直なところ、どうせノットを覚えるなら最初からブラッドノットを習得した方が効率的という意見もあります。フィッシャーマンズノットは「中途半端」と捉えられることもあり、使用者の数は電車結びやブラッドノットと比べると少ない印象です。
それでも、このノットには独自の価値があります。それは巻き付け回数を自由に調整できるという柔軟性です。状況に応じて3回巻き、5回巻き、7回巻きと変えることで、結び目のサイズと強度のバランスを自分好みに調整できます。この「カスタマイズ性」は、他のノットにはない特徴と言えるでしょう。
また、フィッシャーマンズノットは古くから登山やキャンプなどアウトドア全般で使われてきた歴史があります。ロープワークとしての信頼性は証明されており、釣り以外の場面でも役立つ知識です。アウトドアを幅広く楽しむ人にとっては、覚えておいて損のないノットと言えます。
PE同士の下巻き結び方は電車結びが基本
下巻きにPEラインを使用し、メインラインもPEという組み合わせの場合、電車結びが最も一般的です。同じ素材同士の結束なので、比較的安定した強度が得られます。
実は、下巻きにPEを使うという方法は、あまりメジャーではありませんが、いくつかのメリットがあります。特にエステルラインをメインに使う場合、下巻きにナイロンやフロロを使うと、素材の硬さの違いから結び目が引っかかりやすいという問題が起こることがあります。
元々、ナイロンラインを下糸に巻いていたのですが、いざキャストしてみると下糸とメインラインの結び目部分に引っかかってしまうという事がありました。ナイロンの素材の硬さもあると思いますが、下糸に使用するような長く細いラインが売っておらず仕方なく少し太めの下糸を使用していた事もあると思います。
PEを下巻きに使うメリットは以下の通りです:
🎯 下巻きにPEを使うメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 結び目が小さくなる | 柔らかい素材なので結び目がコンパクト |
| 引っかかりにくい | ナイロンより柔軟性が高い |
| 細いラインが選べる | 0.8号~1号程度の細いPEが使える |
| 食い込み防止 | メインラインがスプールに食い込みにくい |
| カラーバリエーション | 好みの色が選べる |
特に、結び目のサイズが小さくなるという点は大きなメリットです。細いPE(0.8号~1号程度)を下巻きに使い、エステルやPEをメインラインとして電車結びで接続すれば、非常にコンパクトな結び目が作れます。
ただし、デメリットもあります。それはコストがやや高くなるという点です。ナイロンの下巻き用ラインは非常に安価(数百円で数百メートル)ですが、PEラインは同じ長さでもやや高価になります。とはいえ、使い古したPEラインを下巻きに流用すれば、このデメリットは解消できるでしょう。
PE同士を電車結びで接続する際のコツは、締め込みすぎないことです。PEラインは摩擦熱に弱いため、急激に締め込むとラインが傷んで強度が落ちます。結び目を水や唾液で湿らせてから、ゆっくりと締め込むようにしましょう。
また、PE同士の場合、電車結びの巻き付け回数を4~5回にするのが一般的ですが、より強度を求めるなら6~7回に増やすのも有効です。ただし、巻き付け回数を増やすと結び目が大きくなるため、バランスを考える必要があります。
エステルラインの下巻き結び方はテンション管理が重要
エステルラインをメインラインとして使用する場合、下巻きとの結束以上に重要なのが巻く際のテンション管理です。エステルラインは他のラインと比べて特殊な性質を持っているため、巻き方を間違えるとトラブルの原因になります。
エステルラインの最大の特徴は、強度が低いという点です。号数に対する引張強度が、PEやナイロンと比べて明らかに低く、締め込みすぎるとすぐに切れてしまいます。そのため、リールに巻く際は「テンションをかけすぎず、緩めすぎず」という絶妙なバランスが求められるのです。
ラインの材質はいろいろ。代表的なものでPE、フロロ、ナイロンがあるが、エステルラインだけは少し特殊なイトである。ラインの号数(太さ)に対して、強度が低い。つまり切れやすい。リールに収めていくときには、テンションをかけすぎないことに注意。といってフワーッと巻いていくとバックラッシュのもとになる。
エステルラインを巻く際の具体的な方法として、布を使ったテンション管理が推奨されています。柔らかい布でバットガイドからスプールまでのラインを優しく撫でるようにすることで、適度なテンションをかけながら巻くことができます。
📝 エステルライン巻き取りの手順
- ボールペン(または鉛筆)をラインボビンの穴に通す
- ボールペンを両足の指で挟んで固定
- リールをロッドにセットし、ラインをガイドに通す
- スプールにラインを結ぶ(簡易なノットでOK)
- 柔らかい布でラインを軽く挟みながら巻き取る
- または指で軽くフェザーリングしながら巻き取る
布を使わない場合は、指で軽くテンションをかける方法もあります。ただし、強くつまむように持つのは厳禁です。エステル0.2号程度の極細ラインは、指でつまむだけでも切れてしまう可能性があります。あくまで「触る」程度の力加減を意識しましょう。
また、下巻きの量を調整する際も注意が必要です。エステルラインは非常に細いため、下巻きの量を見誤りやすいのです。実際、0.13号などの極細エステルをスプールに巻くと、「本当に150m巻けているのか不安になる」という声も聞かれます。下巻きの色が透けて見えることもあるため、視覚的にも判断が難しいでしょう。
このため、エステルラインを使う場合は、最初は釣具店で巻いてもらうのがおすすめです。一度プロに巻いてもらえば、適切な下巻き量や巻き具合の感覚がつかめます。その後、自分で巻き直す際の参考にもなるでしょう。
アジングの下巻き結び方で知っておくべき実践テクニックと注意点
- 下巻きの結び目が引っかかる問題はテープや細いラインで解決
- スプールへの下巻き結び方はユニノットが確実
- 下巻きにPEを使うメリットは結び目が小さくなること
- エステルライン使用時の下巻き計算は慎重に
- リール番手によって下巻きの必要性が変わる
- ベイトリールでも下巻きのテクニックは同様
- まとめ:アジングの下巻きとメインラインの結び方
下巻きの結び目が引っかかる問題はテープや細いラインで解決
アジングで下巻きを使用する際、最もよく聞かれるトラブルが「キャスト時に結び目が引っかかる」という現象です。これは特に、太めのナイロンやフロロを下巻きに使い、細いエステルやPEをメインラインにした場合に起こりやすいトラブルです。
結び目が引っかかる原因は主に2つあります。1つ目は結び目のサイズが大きすぎること。2つ目は下巻きとメインラインの太さの差が大きいことです。太いラインと細いラインを結ぶと、どうしても結び目に段差ができてしまい、これがガイドやスプールのエッジに引っかかるのです。
この問題に対する解決策はいくつかあります:
🔧 結び目引っかかり対策
| 対策方法 | 効果 | 実施難易度 |
|---|---|---|
| セロテープで結び目を覆う | ★★☆ | 簡単 |
| より細い下巻きラインを使う | ★★★ | 簡単 |
| 下巻きにPEを使用する | ★★★ | 簡単 |
| 結び目を押し込む | ★☆☆ | やや難 |
| 結び目をスプール奥に配置 | ★★☆ | 簡単 |
最も手軽な対策はセロテープを使う方法です。Yahoo!知恵袋の回答にも、この方法が紹介されています:
細いライン使うのに結び目が出来ると邪魔になりますよ(^_^;)アジングやらメバリングみたいに細いライン使う時は結ばずにセロテープで下巻きのラインを止めちゃうのがよろしいかと(。・ω・)y-゚゚゚
ただし、テープを使う方法は見た目があまり良くないという欠点があります。また、テープの粘着力が弱まってくると、巻き取り時にテープがはがれてトラブルになる可能性もゼロではありません。
より根本的な解決策は、下巻きラインを細くすることです。例えば、ナイロン3号ではなく1.5号~2号程度の細いラインを使えば、メインラインとの太さの差が小さくなり、結び目も目立たなくなります。細いラインを使っても、下巻きまでラインが出ることは稀なので、強度的には問題ないでしょう。
また、前述のように下巻きにPEを使うという方法も有効です。PE0.8号~1号程度を下巻きに使えば、柔らかい素材特性により結び目がコンパクトになり、引っかかりのリスクを大幅に減らすことができます。
さらに、結び目をスプールの手前側(奥側)に配置するというテクニックもあります。メインラインを巻き始める前に、下巻きラインを数メートル余分に巻いておき、結び目をスプールの底の方に沈めてしまうのです。こうすれば、結び目がガイドやスプール上部に接触するリスクが減ります。
スプールへの下巻き結び方はユニノットが確実
下巻きラインをスプール本体に結ぶ際の方法も、意外と重要なポイントです。ここで使うノットは、スプールから抜けないことが最優先で、強度はそこまで求められません。なぜなら、下巻きが見えるほどラインが出た状態で、さらにスプールから抜けるほどの力がかかることは、現実的にほぼあり得ないからです。
最も一般的なのはユニノット(またはアーバーノット)です。スプールにラインを通し、輪を作って3~4回巻き付け、締め込むだけという簡単な構造です。
📌 スプールへの結束方法(ユニノット)
- スプールにラインを掛ける
- ラインで輪を作る
- 輪の中にラインを3~4回通す
- ゆっくり引いて強く締め込む
- 余分なラインをカット
ラインを二重にスプールに巻くと滑りにくくなる。
ユニノットの利点は、確実に締まり、滑りにくいという点です。特にPEラインのような滑りやすいラインでも、しっかりとスプールに固定できます。また、ノット自体が小さいので、下巻きラインを巻いていく際の邪魔になりません。
一部の釣り人は、スプールへの結束をさらに確実にするためにテープを併用しています。ユニノットで結んだ後、その上から透明なテープを貼ることで、万が一ノットが緩んだ場合でも抜けないようにするのです。これは「二重の保険」として有効な方法と言えるでしょう。
ただし、テープを使う場合は粘着力の弱いテープを選ぶことが重要です。強力な両面テープなどを使うと、後でラインを巻き替える際にテープがきれいに剥がれず、スプールが汚れてしまう可能性があります。
また、スプールへの結束で気をつけたいのが、結び目の大きさです。大きなコブを作ってしまうと、その上に巻いていくラインに凹凸ができ、ライントラブルの原因になります。できるだけコンパクトな結び目を作ることを心がけましょう。
スプールがアルミ製の場合、ラインが滑りやすいことがあります。このような場合は、スプールにマスキングテープを一周巻いてからラインを結ぶという方法もあります。マスキングテープの表面は少しざらついているため、ラインが滑りにくくなり、より確実に固定できます。
下巻きにPEを使うメリットは結び目が小さくなること
下巻きにPEラインを使用するという方法は、一般的にはあまり知られていませんが、実はいくつかの明確なメリットがあります。特にエステルラインをメインに使用する場合、この組み合わせが非常に有効です。
PEを下巻きに使う最大のメリットは、前述の通り結び目が小さくなるという点です。ナイロンやフロロは素材が硬いため、結び目がどうしても大きくなりがちです。一方、PEは柔軟性が高く、結び目をコンパクトにまとめることができます。
実際の使用例を見てみましょう:
自分はシマノのシャロースプールにTORAYのPEライン ソラローム 0.8号(12lb)75mを全て巻きSUNLINE 鯵の糸 NightBlue を80m巻いて丁度いいくらいでした!
この組み合わせでは、PE0.8号を75m、エステルを80mという配分になっています。シャロースプールの場合、このくらいの量でちょうどスプールいっぱいになるでしょう。
🎨 下巻きPE+エステルの組み合わせ例
| リール番手 | 下巻きPE | メインライン(エステル) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1000番シャロー | 0.8号 75m | 0.3号 80m | 155m |
| 2000番シャロー | 1.0号 100m | 0.4号 100m | 200m |
| 500番 | なし | 0.3号 150m | 150m |
下巻きにPEを使うもう一つのメリットは、カラーバリエーションが豊富という点です。ナイロンの下巻きラインは透明やピンクなど限られた色しかありませんが、PEラインなら様々な色から選べます。グレー、ブラック、マルチカラーなど、好みに合わせて選択できるのは、道具にこだわる釣り人にとって嬉しいポイントです。
また、使い古したPEを有効活用できるというコスト面のメリットもあります。他の釣りで使っていたPEラインが古くなってきたら、捨てずに下巻き用として再利用できます。これはエコでもあり、経済的でもあります。
ただし、デメリットもあります。PE0.8号~1号程度でも、専用の下巻きラインと比べるとやや高価です。新品を買うとなると、数百円の差が出てきます。また、PEラインは紫外線に弱いため、長期間使用すると劣化する可能性があります。とはいえ、下巻きは直射日光に晒されることがほとんどないため、この点はあまり心配する必要はないかもしれません。
エステルライン使用時の下巻き計算は慎重に
エステルラインを使用する際、下巻きの量を計算するのが意外と難しいという問題があります。エステルラインは極端に細いため、同じ号数のPEやナイロンと比べて、巻ける長さが大きく変わってくるのです。
例えば、同じ1000番のシャロースプールでも、PE0.2号なら200m巻けるとされていますが、エステル0.2号を巻くと200mでは余ってしまうことがあります。これは、ラインの構造や巻き取り時のテンションの違いが影響していると推測されます。
⚠️ エステルライン使用時の注意点
- ✓ カタログスペックより実際の巻量が少ない場合がある
- ✓ 下巻きの透け具合で視覚的な判断が難しい
- ✓ 巻き取りテンションで巻量が大きく変わる
- ✓ 号数によって下巻き量を調整する必要がある
下巻きの計算を間違えると、以下のような問題が発生します:
下巻きが多すぎる場合:
- メインラインが十分に巻けない
- スプールから糸が飛び出してライントラブル
- 再度巻き直す手間がかかる
下巻きが少なすぎる場合:
- スプールに余裕ができすぎて飛距離が落ちる
- メインラインを無駄に多く使ってしまう
- コストパフォーマンスが悪い
このため、エステルラインを使う場合は、最初に試し巻きをするのがおすすめです。まずメインラインだけを巻いてみて、どのくらいの長さでスプールがいっぱいになるかを確認します。その後、必要な下巻き量を逆算するのです。
また、同じエステルラインを3回分使うという考え方も実用的です。例えば、240m巻きのエステルラインを購入した場合、80mずつ3回に分けて使います。1回目は新しいラインで釣りを楽しみ、劣化してきたら2回目に交換、さらに3回目も使うという流れです。このサイクルなら、下巻きの量を固定できるため、計算が楽になります。
リール番手によって下巻きの必要性が変わる
アジングで使用するリールの番手によって、下巻きが必要かどうかは大きく変わります。これを理解しておくと、無駄なラインを巻くことなく、効率的にセッティングできます。
一般的にアジングで使われるリールは、500番~2000番の範囲です。それぞれの番手で、下巻きの必要性を見てみましょう:
🎣 リール番手別の下巻き必要性
| リール番手 | スプール深さ | 下巻きの必要性 | 推奨ライン量 |
|---|---|---|---|
| 500番 | 超シャロー | ほぼ不要 | 100~150m |
| 1000番シャロー | シャロー | 状況次第 | 150m程度 |
| 2000番シャロー | やや深め | 必要 | 100m+下巻き |
| 2000番ノーマル | 深い | 必要 | 100m+下巻き多め |
500番や1000番のシャロースプールは、アジングなどライトゲーム専用に設計されているため、基本的に下巻きは不要です。細いライン(0.2~0.3号程度)を150m巻けばちょうどスプールいっぱいになる設計なので、無駄がありません。
ラインキャパシティはナイロン2lbが115m巻ける設計で、ナイロンやフロロなどモノフィラメントラインであれば細糸も下巻きなしで使用できます。
一方、2000番のノーマルスプールを使う場合は、下巻きがほぼ必須です。このサイズのスプールに0.3号のラインを下巻きなしで巻くと、200m以上巻かなければスプールがいっぱいにならないこともあります。アジングで200mもラインを使うことはまずないので、明らかに無駄です。
下巻きをすることで、以下のメリットがあります:
✅ 下巻きのメリット
- メインラインの消費を抑えられる
- ライン交換の頻度を上げられる
- 複数の釣りでリールを兼用できる
- ウエイトバランスが取りやすい
逆に、下巻き不要なリールを選ぶメリットもあります:
✅ 下巻き不要リールのメリット
- セッティングが簡単
- 巻き直しが楽
- 結び目の心配がない
- リール自体が軽量
どちらを選ぶかは、釣りのスタイルや他の釣りとの兼用の有無で決めるといいでしょう。アジング専用のタックルなら下巻き不要のリールが便利ですし、シーバスやエギングなど他の釣りにも使いたいなら、2000番を選んで下巻きを調整する方が汎用性が高いです。
ベイトリールでも下巻きのテクニックは同様
アジングはスピニングリールが主流ですが、一部の釣り人はベイトタックルでアジングを楽しんでいます。ベイトリールでも下巻きの考え方は基本的に同じですが、いくつか注意すべき点があります。
まず、ベイトリールはスピニングリールと違い、スプールが回転してラインを放出する構造です。このため、スプールの角にラインが当たって飛距離が落ちるという問題は起こりにくいとされています。
ベイトリールはスプールの角にラインがあたり、飛距離が落ちるために下巻きをほどこしています(店で頼んで)。ベイトリールは必要ありますか?
ただし、ベイトリールでも下巻きが有効なケースはあります。それはライン容量を調整したい場合です。例えば、PE1.5号を100m使いたいのに、リールのラインキャパシティが1.5号200mという場合、下巻きをすることでメインラインの無駄を省けます。
🔄 ベイトリールでの下巻きポイント
| 項目 | スピニングとの違い |
|---|---|
| 下巻きの必要性 | やや低い(スプール構造の違い) |
| 結び方 | 同じ(電車結び、ブラッドノットなど) |
| 注意点 | バックラッシュに注意 |
| テンション管理 | より重要(親指でコントロール) |
ベイトリールで下巻きをする場合、バックラッシュのリスクが高まる点に注意が必要です。特に、下巻きとメインラインの結び目部分は、若干の段差ができるため、キャスト時にスプールの回転が不規則になりやすいのです。
これを防ぐためには、結び目をできるだけ小さく、滑らかにすることが重要です。ブラッドノットのようにコンパクトな結び目を作るノットが向いています。また、結び目の上から薄くセロテープを貼って段差を埋めるという方法も有効でしょう。
ベイトリールの場合、下巻きラインはやや太め(3~4号程度)を選ぶ人が多いようです。これは、スプールへの食い込みを防ぐためと、結束強度を確保するためです。細すぎるラインを下巻きに使うと、キャスト時の遠心力で食い込みが発生し、次のキャストでバックラッシュする原因になることがあります。
まとめ:アジングの下巻きとメインラインの結び方
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングの下巻き結束には「電車結び」「ブラッドノット」「フィッシャーマンズノット」の3つが主流である
- 電車結びは最も簡単だが強度は約50%程度で、初心者向けの基本ノットである
- ブラッドノットは約80%の強度を実現し、最もおすすめの結び方である
- フィッシャーマンズノットは約70%の強度で、電車結びとブラッドノットの中間的な選択肢である
- PE同士の結束には電車結びが基本で、巻き付け回数を増やすことで強度を向上できる
- エステルラインを巻く際はテンション管理が最重要で、布や指を使った適度なテンション調整が必要である
- 結び目が引っかかる問題は、セロテープ、細いライン、PE下巻きなどで解決できる
- スプールへの結束はユニノットが最も確実で滑りにくい
- 下巻きにPEを使うと結び目が小さくなり、引っかかりのリスクを減らせる
- エステルライン使用時は下巻き計算が難しく、試し巻きをしてから調整するのが確実である
- 500番や1000番シャロースプールは下巻き不要で、2000番は下巻きが必要になる
- ベイトリールでも下巻きの考え方は基本的に同じだが、バックラッシュに注意が必要である
- 下巻きラインの太さは3~5号程度が一般的で、太いほど結束強度が上がる
- リールからラインを多く出すとドラグ力が強くなるため、下巻き部分での結束強度は重要である
- 使い古したPEラインを下巻きに再利用することで、コストを抑えながら性能を向上できる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- アジングやメバリングで – リールの下糸とPEラインを結ぶ時どの… – Yahoo!知恵袋
- 【ノット解説】電車結びの結び方 | 釣りビジョン マガジン
- アジングする人は絶対読んでほしい | つり具 山陽 SANYO
- スプールにラインを結ぶ|おすすめノット|ユニチカフィッシングライン
- 【ライン同士の基本結束】電車結びのやり方を分かりやすく解説! | TSURI HACK
- 今さら聞けない『エステルライン』のキホン:リールへの巻き方 | TSURINEWS
- どのノットがおすすめ? リールの下巻きラインとPEラインの結び方 | ジギング魂
- アジング新戦力 | 三池の虎の備忘録
- 【アジング】エステルラインの下糸にPEがおすすめ! | 楽の釣りブログ
- アジングリールに下巻きは必要?おすすめ機種も紹介! | タックルノート
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。