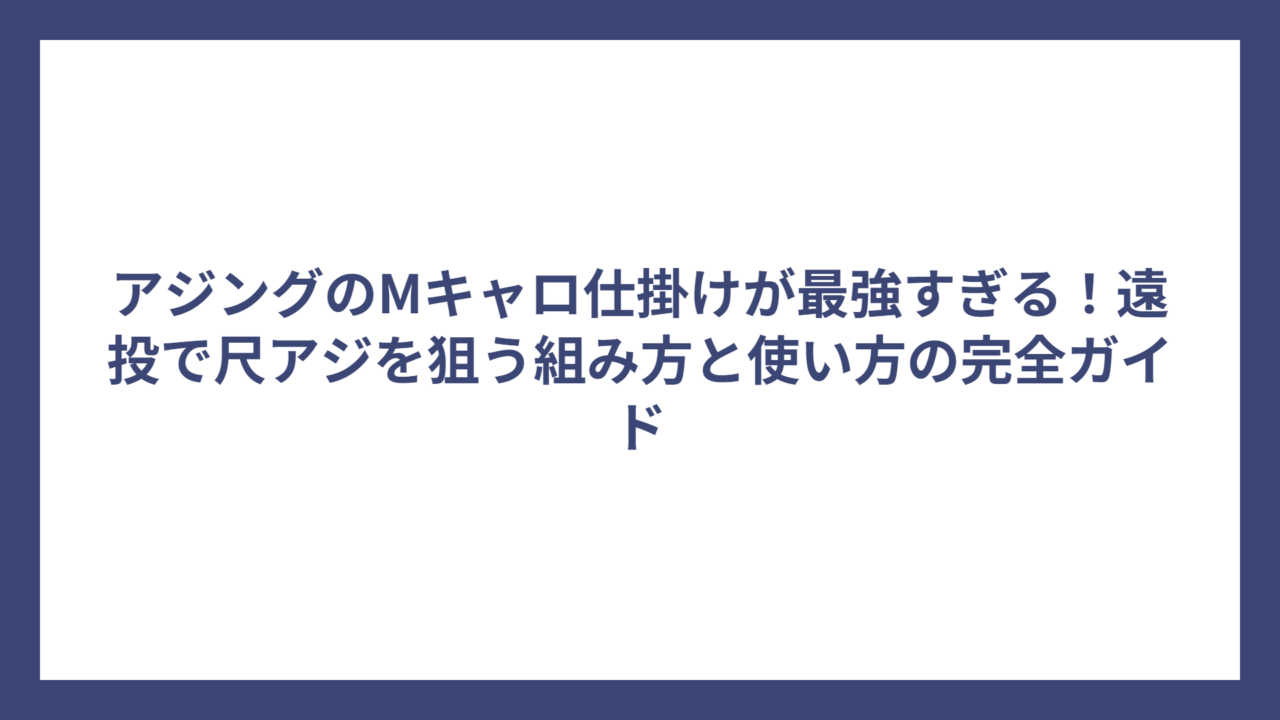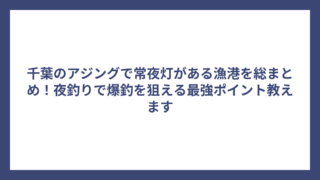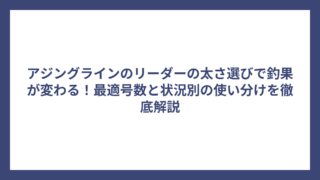アジングで「もっと沖を攻めたい」「ジグ単では届かないポイントにアジがいる」と感じたことはありませんか?そんな悩みを一気に解決してくれるのが、Mキャロ(エムキャロ)仕掛けです。この仕掛けは、軽量ジグヘッドを圧倒的な飛距離で遠投できる画期的なリグとして、多くのアジンガーから支持を集めています。
本記事では、インターネット上に散らばるMキャロに関する情報を収集・整理し、仕掛けの組み方から実践的な使い方、さらには「釣れない」と感じる原因まで徹底解説します。初心者の方でもすぐに実践できるよう、具体的なパーツ選びやタックルセッティング、トラブル回避のコツまで網羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ Mキャロ仕掛けの基本構造と必要なパーツがわかる |
| ✓ タイプ別の特徴と使い分け方法を理解できる |
| ✓ 絡みトラブルを防ぐ具体的なテクニックが身につく |
| ✓ 釣れない原因と対策方法が明確になる |
アジングのMキャロ仕掛けの基本と組み方
- アジングのMキャロ仕掛けは遠投特化型の中通しシンカーリグ
- Mキャロの仕掛けに必要なパーツは6つ
- Mキャロの正しい組み方手順
- リーダーの長さは20〜60cmが基本
- ジグヘッドの重さは0.4〜0.8gの軽量タイプを選ぶ
- Mキャロのタイプ選びはフォール角度で決まる
アジングのMキャロ仕掛けは遠投特化型の中通しシンカーリグ
Mキャロ仕掛けとは、ティクト(TICT)が開発した遊動式の中通しシンカーを使った遠投専用リグのことです。一般的なキャロライナリグを進化させたもので、浮力体とシンカーを組み合わせることで、圧倒的な飛距離とスローフォールを両立させています。
この仕掛けの最大の特徴は、バックスライドフォールと呼ばれる独特の沈み方です。着水後、シンカーが沖に向かって斜めに沈んでいくため、キャスト後もさらに飛距離が伸びる仕組みになっています。
Mキャロは、キャロライナリグをさらに進化させた仕掛けで、沖にいる尺アジ、メバルなどを狙えて、沖のポイントを幅広く探ることが出来る仕掛けです。
<cite>出典:Mキャロ仕掛けで尺アジ・尺メバルを狙う!</cite>
この説明の通り、Mキャロは単なる飛距離アップのための道具ではありません。沖の潮目に潜む大型アジや、ジグ単では到達できない深場のアジを効率的に狙えるという点で、アジングの攻略範囲を大きく広げてくれる仕掛けなのです。
通常のジグヘッド単体(ジグ単)では15m程度の飛距離が限界だとしても、Mキャロを使えば30m以上、重量のあるタイプなら50m以上の遠投も可能になります。この飛距離の差は、釣果に直結する重要な要素といえるでしょう。
また、バックスライドフォールによって、リトリーブ時やアクション時に自然とラインテンションがかかりやすくなるため、レンジキープ力にも優れています。一定の深さを維持しながらゆっくりと誘えるため、活性の低いアジにも効果的にアピールできます。
さらに、中通し式のため感度も良好です。シンカーとジグヘッドが分離しているため、アジのアタリが直接ロッドに伝わりやすく、違和感なく吸い込ませることができるのも大きなメリットです。
Mキャロの仕掛けに必要なパーツは6つ
Mキャロ仕掛けを組むために必要なパーツは以下の6つです。それぞれの役割と選び方を理解することで、状況に応じた最適なセッティングが可能になります。
📦 Mキャロ仕掛けの必須パーツ一覧
| パーツ名 | 役割 | 選び方のポイント |
|---|---|---|
| Mキャロ本体 | 飛距離を出すシンカー兼レンジキープ | タイプ(L/N/S)と重量を状況に応じて選択 |
| ウキ止めゴム | Mキャロの位置を固定 | 専用品がセットで販売されている |
| スイベル | リーダーとの接続部 | 極小サイズを使用 |
| リーダー(ハリス) | スイベルとジグヘッドを繋ぐ | フロロカーボン3〜8lb、長さ20〜60cm |
| ジグヘッド | ワームを装着 | 0.4〜0.8gの軽量タイプ |
| ワーム | アジを誘う | 1.5〜2.5インチが基本 |
これらのパーツを適切に組み合わせることで、Mキャロ仕掛けが完成します。特に重要なのは、Mキャロ本体の選択とリーダーの長さ設定です。
まず、Mキャロ本体については、ティクトから発売されているタイプL、N、Sの3種類があり、それぞれフォール角度が異なります(詳細は後述)。初めて使用する場合は、汎用性の高いタイプNの6〜8g程度がおすすめです。
リーダーについては、メインラインよりも若干細めのフロロカーボンラインを使用します。これは根掛かり時にMキャロ本体をロストしないための工夫です。リーダーが先に切れることで、高価なMキャロを回収できる可能性が高まります。
ウキ止めゴムとスイベルは、ティクトから専用のセット商品が販売されています。これを使用すれば、Mキャロの棒部分が割れるのを防ぐクッションゴムも含まれているため、初心者の方には特におすすめです。
TICT(ティクト) Mキャロ用 スイベル
<cite>出典:アジングのキャロライナリグ(Mキャロ)の使い方を徹底解説!</cite>
ジグヘッドは、Mキャロ本体に重量があるため、吸い込みやすさを重視して0.4〜0.8gの軽量タイプを選びます。ストレートゲイブ(針先が真っすぐ)のものが、ベイトパターンの釣りでは有利とされています。
ワームは、ベイトのサイズに合わせるのが基本ですが、迷った場合は1.5〜2.3インチ程度の汎用サイズを選んでおけば間違いありません。特に実績の高いワームとしては、マルキューの「熟成アクア 活アジストレート」などが挙げられます。
Mキャロの正しい組み方手順
Mキャロ仕掛けの組み方は、一見複雑に見えますが、手順を理解すれば誰でも簡単に作ることができます。以下、ステップバイステップで解説していきます。
🔧 Mキャロ仕掛けの組み立て手順
- メインラインにショックリーダーを結束
PEラインを使用している場合、FGノットなどで1〜2号のフロロカーボンリーダーを30〜40cm程度結びます。このリーダーは「元リーダー」と呼ばれ、Mキャロ本体を通すための太めのラインです。 - 元リーダーにMキャロ本体を通す
リーダーにMキャロのチューブ部分を通します。この時、バックスライドする方向を確認しておきましょう。 - ウキ止めゴムを装着
Mキャロの後ろ側にウキ止めゴム(クッションゴム)を装着します。これがないとMキャロの棒部分が破損する原因になります。 - スイベルを結束
元リーダーの先端に極小スイベルを結びます。ユニノットやクリンチノットで確実に結束しましょう。 - スイベルにハリス(先リーダー)を結ぶ
スイベルのもう一方に、元リーダーより若干細めのフロロカーボンライン(3〜8lb)を20〜60cm結びます。これが「ハリス」または「先リーダー」と呼ばれる部分です。 - ジグヘッドを結んでワームを装着
ハリスの先端にジグヘッドを結び、ワームをセットすれば完成です。
この組み方で重要なポイントは、元リーダーと先リーダーの太さを変えることです。元リーダーを10〜12lb、先リーダーを4〜8lb程度にすることで、根掛かり時に先リーダーから切れて、Mキャロ本体を回収できる可能性が高まります。
万が一根掛かりした場合、リグ全体を無くしてしまうことがあるので、元から4lbほど先リーダーを落としておくのが良いですね。
<cite>出典:アジング&ライトゲーム向けキャロライナリグ大全!</cite>
もし同じ太さのラインを使ってしまうと、元リーダーから切れてリグ全体をロストしてしまうリスクがあります。この点は必ず守るようにしましょう。
また、結束部をガイドの中に入れてキャストしないことも重要です。FGノットなどの結び目がガイドに引っかかると、キャスト切れの原因になります。リーダーの長さは、結束部がガイドの外に出る程度に調整すると安全です。
初めて組む際は手間に感じるかもしれませんが、一度慣れてしまえば5分程度で組めるようになります。釣行前に自宅で複数のリグを組んでおけば、現場でのトラブル時にも素早く対応できるでしょう。
リーダーの長さは20〜60cmが基本
Mキャロ仕掛けにおいて、リーダー(ハリス)の長さ設定は釣果を大きく左右する重要な要素です。多くのアジンガーが試行錯誤を重ねた結果、基本的には20〜60cmの範囲が最適とされています。
リーダーの長さによって、仕掛けの動き方や絡みやすさ、アジの食い込みの良さが変わってきます。以下、長さ別の特徴を整理してみました。
📏 リーダー長さ別の特徴比較
| リーダーの長さ | メリット | デメリット | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| 20〜30cm(短め) | ・絡みトラブルが少ない<br>・フォール時の感度が良い<br>・手返しが早い | ・食い込みがやや悪くなる可能性<br>・ナチュラルな動きが出にくい | 活性が高い時、流れが速い時、根が荒い場所 |
| 40〜50cm(標準) | ・バランスが良い<br>・様々な状況に対応<br>・適度なナチュラルさ | 特になし(汎用的) | オールラウンド、初めてのポイント |
| 50〜60cm(長め) | ・ワームの自由度が高い<br>・食い込みが良い<br>・アタリが多くなる傾向 | ・絡みやすい<br>・フォール時の感度が下がる | 活性が低い時、プレッシャーが高い場所 |
リーダーの長さですが、私がフォール中心でやる場合はリーダーは20cmがベストと思っています。流れが速い場所や根が荒い場所では特にオススメで、どんなシュチュエーションでもトラブルが一番少ないです。
<cite>出典:Mキャロの使い方 その1</cite>
この引用にもあるように、経験豊富なアジンガーの中には20cmの短いリーダーを好む方もいます。確かに、フォール中心の釣りでは短いリーダーの方が感度が良く、絡みトラブルも少なくなります。
一方で、「リーダーが短すぎるとアジがスレるのでは?」という疑問を持つ方もいるでしょう。しかし実際には、10cmでも問題なく釣れるという報告もあります。アジングでは大きなアクションよりも、むしろナチュラルな誘いが重要なため、リーダーが短いことによる警戒心の増加は限定的と考えられます。
ただし、15cm以下にすると、今度はワームの動きが制限されたり、逆にアクションが伝わりすぎて不自然な動きになる可能性があります。そのため、最短でも20cm程度は確保するのが無難でしょう。
私の考察としては、初心者は40〜50cmからスタートし、釣り場の状況や自分の釣りスタイルに応じて調整していくのがおすすめです。活性が高い時や時合いが短い時は短め、活性が低くじっくり誘いたい時は長めといった使い分けができるようになれば、さらに釣果は伸びていくはずです。
ジグヘッドの重さは0.4〜0.8gの軽量タイプを選ぶ
Mキャロ仕掛けで使用するジグヘッドは、0.4〜0.8gの軽量タイプが基本です。これは、Mキャロ本体に十分な重量があるため、ジグヘッド自体を重くする必要がないためです。
軽量ジグヘッドを使用することで、以下のようなメリットが得られます。
✅ 軽量ジグヘッドのメリット
- アジが吸い込みやすく、フッキング率が向上する
- ワームの自然な動きが出しやすい
- バイトに対する違和感を与えにくい
- フォール時の沈下速度が遅くなり、食わせの間が長くなる
逆に、1〜2gの重めのジグヘッドを使用してしまうと、いくつかの問題が発生します。
まず、キャスト時の飛距離が落ちる可能性があります。Mキャロとジグヘッドの重量バランスが悪くなり、空中で仕掛けがバラついてしまうためです。せっかくのMキャロの飛距離性能を活かしきれません。
次に、フォールスピードが速くなりすぎる問題があります。Mキャロの特徴であるスローフォールとレンジキープ力が損なわれ、ジグヘッドが先に沈んでしまいます。
重くすると、シンカーとジグヘッドとキャスト時に重さがバラついて飛距離が落ちたり、せっかくのゆっくり落とせるキャロがあるのに、ジグヘッドが先に落ちるためメリットが無くなりますよね。適正なウエイトは、0.2〜0.5gほどの間が良いでしょう。
<cite>出典:アジング&ライトゲーム向けキャロライナリグ大全!</cite>
この指摘の通り、重いジグヘッドを使うとMキャロの利点が相殺されてしまいます。アクション後にラインがすぐに張ってしまい、アジが吸い込みにくくなるという問題も発生します。
📌 おすすめジグヘッド重量の目安
| Mキャロの重量 | 推奨ジグヘッド重量 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 4〜6g | 0.4〜0.5g | 表層〜中層、活性が低い時 |
| 7〜9g | 0.5〜0.6g | 中層〜ボトム、標準的な状況 |
| 10g以上 | 0.6〜0.8g | ディープ、流れが速い時 |
ジグヘッドの形状については、ストレートゲイブ(針先が真っすぐ)のものが基本です。Mキャロの釣りはベイトパターンが多く、吸い込むようなバイトよりも追い食いのパターンが多いため、ストレートゲイブの方がフッキング率が高くなります。
ティクトの「アジスタ」シリーズなど、アジング専用の軽量ジグヘッドを使用すると、さらに釣果は安定するでしょう。針先の鋭さも重要で、小型のアジを掛ける際には特に、針先が鈍っていないかチェックすることをおすすめします。爪に引っ掛からないフックは即交換が鉄則です。
Mキャロのタイプ選びはフォール角度で決まる
Mキャロには、タイプL、N、Sの3種類があり、それぞれフォール角度が異なります。この特性を理解して使い分けることが、Mキャロ攻略の鍵となります。
ティクトの公式情報によると、各タイプのフォール角度は以下の通りです。
🎯 Mキャロ タイプ別フォール角度
| タイプ | フォール角度 | 特徴 | 重量ラインナップ |
|---|---|---|---|
| タイプL | 15° | 最もスローフォール | 5.3g / 6.3g / 7.0g / 9.5g |
| タイプN | 30° | バランス型・汎用性高 | 4.6g / 6.0g / 8.0g / 11.0g |
| タイプS | 60° | 最も速く沈む | 5.3g / 6.3g / 7.0g / 9.5g |
各タイプの使い分けについて、具体的に見ていきましょう。
【タイプL:表層攻略の切り札】
タイプLは、15°という最も緩やかな角度でバックスライドするため、沈下速度が最も遅いタイプです。沖の表層にアジがいる状況や、食い渋っている時にゆっくりと誘いたい場合に威力を発揮します。
風の影響をほとんど受けない状況で、水深7m程度までのポイントを攻める際に適しています。フォールスピードが遅いため、同じレンジにワームを長く停滞させることができ、活性の低いアジに対してもじっくりとアピールできます。
【タイプN:オールラウンダー】
タイプNは、30°の中間的なフォール角度を持つバランス型です。初めてのポイントで広く早くサーチしたい時や、少し風がある状況でタイプLでは釣りがしにくい時などに活躍します。
汎用性が高く、様々なシチュエーションに対応できるため、初心者が最初に購入するならタイプNがおすすめです。特に8.0g前後のウエイトが使いやすく、多くのアジンガーから支持されています。
【タイプS:ディープ攻略専用】
タイプSは、60°という急角度でフォールするため、3つの中で最も速く沈みます。水深が深いポイントや、潮の流れが速い状況で真価を発揮します。
ボトム付近でしか反応がない時や、手返しを重視したい高活性時にも有効です。ただし、フォールが速い分、食わせの間が短くなるため、活性が低い時には不向きかもしれません。
タイプL:風の影響を殆ど受けない状態で水深7m程度までのアジを狙う場合。テンションを入れると一番ゆっくりフォールするのでスローに展開したい場合に使用 タイプM(N):初めてのポイントで広く早くサーチしたい場合。少し風が強くタイプLだと釣りがやりにくい場合。 タイプS:私はほぼ使う事はありませんが、水深が深く、潮が速い場合。ボトムで釣れる場合
<cite>出典:【Mキャロ虎の巻】</cite>
この実釣経験に基づいた使い分けは非常に参考になります。特に、タイプSをほとんど使わないという点は興味深く、多くの状況ではタイプLとNで対応できることを示唆しています。
私の考えとしては、まずはタイプNの6〜8gを軸に、表層狙いや渋い状況用にタイプLを追加していくのが効率的なタックル構成ではないかと思います。タイプSは、明確にディープや速潮が必要な釣り場がある場合に限定して導入すれば良いでしょう。
アジングのMキャロ仕掛けで釣果を上げる実践テクニック
- Mキャロが釣れないのは使いどころの間違いが原因
- Mキャロの基本アクションはシャクリ+リトリーブ
- 絡みトラブルを防ぐ3つのコツ
- フロートリグとの使い分けが重要
- Mキャロに適したタックルセッティング
- 沈下速度の違いを理解して使い分ける
- 自作よりも市販品を使うべき理由
- まとめ:アジングのMキャロ仕掛けで沖の大型アジを狙おう
Mキャロが釣れないのは使いどころの間違いが原因
「Mキャロを使っているのに全然釣れない」という声をよく耳にします。しかし、その多くは使うべき状況を間違えていることが原因です。Mキャロはオールマイティな仕掛けではなく、特定の状況で真価を発揮するリグなのです。
まず、Mキャロが本領を発揮する状況を整理してみましょう。
🎣 Mキャロが有効な状況
| シチュエーション | 理由 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 回遊ルートが沖にズレている時 | ジグ単では届かないエリアにアジがいる | 他のアジンガーが攻められない場所を狙える |
| 常夜灯周りに魚が寄っていない時 | 沖の潮目や深場にアジが付いている | 広範囲サーチで魚を見つけやすい |
| 風が強い日 | 重量があるため風の影響を受けにくい | ジグ単では不可能な状況でも釣りが成立 |
| 水深があるポイント | 重量で素早くボトムまで到達 | 手返し良くディープを攻略 |
| 流れが速いポイント | 重量とレンジキープ力で対応 | 流されずに一定レンジを維持 |
逆に、Mキャロが不向きな状況も存在します。
❌ Mキャロが向いていない状況
- 足元でアジが釣れている時:わざわざMキャロを使う必要がない
- 超スローフォールが必要なプランクトンパターン:フロートリグの方が有利
- 浅い(ドシャロー)ポイント:根掛かりリスクが高い
- ピンスポット狙い:飛距離が出すぎてコントロールしにくい
ジグ単で攻めきれないエリアを攻められるのがキャロの良いところ。しっかりとキャロの特性を活かして沖の魚にもアプローチすることで必ずサイズも数も伸びるはず。
<cite>出典:アジング&ライトゲーム向けキャロライナリグ大全!</cite>
この指摘は核心を突いています。Mキャロは「ジグ単の代替」ではなく、「ジグ単では攻略できない場所を攻めるための専用武器」として捉えるべきです。
また、「釣れない」原因として、タックルセッティングの問題も考えられます。ジグ単用の6フィート前後のロッドや、エステルライン0.3号といった繊細なセッティングでは、Mキャロをフルキャストするのは困難です。10g前後のリグを投げられる7〜8フィートのロッドと、直線強度の高いPE0.4〜0.6号といったセッティングが必要になります。
さらに、アクションやレンジの選択ミスも「釣れない」要因です。Mキャロはバックスライドの特性上、リトリーブやリフト&フォールが基本アクションとなります。ジグ単のようなドリフトやカーブフォールは不向きです。また、表層を狙いたいのにタイプSを使ってしまうなど、タイプ選択のミスマッチも釣果を落とす原因になります。
私の考察としては、Mキャロで釣れない時は、まず「本当にMキャロが必要な状況か?」を冷静に判断することが重要です。もし足元でジグ単に反応があるなら、素直にジグ単を使った方が効率的です。Mキャロは、どうしても沖を攻めなければならない時の「最終兵器」として温存しておくのも一つの戦略といえるでしょう。
Mキャロの基本アクションはシャクリ+リトリーブ
Mキャロの基本的なアクションは、シャクリ(トゥイッチ)とリトリーブの組み合わせです。ティクトが推奨する3つの基本パターンを押さえておくことで、様々な状況に対応できるようになります。
🎯 Mキャロ 3つの基本アクションパターン
①シャクリ+リトリーブ(最もおすすめ)
この方法は、最も汎用性が高く、初心者にもおすすめのアクションです。
- 任意のレンジまで沈める(カウントダウン)
- ロッドを2〜3回軽くシャクって存在をアピール
- ゆっくりとリトリーブ、またはロッドを立ててレンジキープ
- アタリがあったら軽くアワセを入れる
ポイントは、リトリーブよりもロッドを立ててレンジキープする方がアタリがわかりやすいという点です。Mキャロのバックスライド特性により、ロッドを立てるだけで自然とテンションがかかり、沖に向かう力と手前に引く力が均衡してレンジが維持されます。
②シャクリ+テンションフォール
こちらはフォールでの食わせを意識したパターンです。
- 2〜3回シャクリを入れる
- ロッドを立ててラインを張ったまま静止
- 仕掛けが岸に向かいながらゆっくり沈む
- テンションが張っているのでアタリを感じたらアワセ
ラインを張った状態で待つため、アタリも取りやすく、違和感を感じたらすぐにアワセを入れられます。活性がやや低い時や、ボトム付近を探りたい時に有効です。
③シャクリ+フリーフォール(最終手段)
これは上記2パターンで反応がない時の切り札的な使い方です。
- 2〜3回シャクリを入れる
- 立てたロッドを下ろし、ラインにテンションをかけずにフォール
- フォール後に空アワセを入れる
ラインにテンションがかからないため、アジが違和感なく食い込めるメリットがありますが、アタリは全くわからなくなります。そのため、一定時間フォールさせた後に空アワセを入れる必要があります。
シャクリ+リトリーブが一番オススメな基本パターン。仕掛けを投入して、任意のレンジまで沈めたら、2~3回ほどシャクリを入れてワームの存在をアピール!その後は、ゆっくりとリトリーブ(巻く)、あるいはロッドをゆっくりと立ててレンジをキープします。
<cite>出典:アジングのキャロライナリグ(Mキャロ)の使い方を徹底解説!</cite>
この基本パターンに加えて、状況に応じた応用テクニックもあります。例えば、リフト&フォールは、ボトム付近を重点的に攻めたい時に有効です。ロッドを上げてMキャロを持ち上げ、その後テンションフォールで沈める動作を繰り返すことで、ボトム〜中層を効率よく探れます。
また、**ステイ(止め)**を入れることで、食わせの間を作ることもできます。特に活性が低い時は、動きを止めた瞬間にバイトが集中することがあります。
アクションの強さについては、ロッドティップを大きく動かしても、水中では思ったほどフック(ジグヘッド)は動いていません。特に遠投した状態では、Mキャロが手前に引かれるだけで、ジグヘッドへのアクション伝達は限定的です。
そのため、アクションの目的はワームを動かすことよりも、Mキャロを動かしてレンジを変える・維持することと考えた方が良いでしょう。過度に派手なアクションは必要なく、むしろナチュラルな誘いを意識することが重要です。
絡みトラブルを防ぐ3つのコツ
Mキャロの最大のデメリットとも言えるのが、**ライントラブル(絡み)**です。シンカー、スイベル、ジグヘッドと複数のパーツで構成されているため、ジグ単に比べると確かに絡みやすい傾向があります。
しかし、適切な対策を講じることで、絡みトラブルは劇的に減らすことができます。
🛡️ 絡みトラブルを防ぐ3つのコツ
①着水直前に強めのサミングを行う
キャスト後、仕掛けが着水する直前にスプールを親指でしっかり押さえて(サミング)、Mキャロにブレーキをかけます。これにより、Mキャロが減速し、ジグヘッドが先行して沖側に着水します。
このテクニックは絡み防止に最も効果的で、多くの経験者が実践しています。サミングが甘いと、Mキャロが先に着水してバックスライドを始め、後から飛んでくるジグヘッドと絡んでしまうリスクが高まります。
②着水後は素早くテンションフォールに移行
着水した瞬間に余分なラインを素早く巻き取り、テンションフォール(ラインを張った状態でのフォール)に移行します。フリーフォールでバックスライドさせると、Mキャロとジグヘッドの距離関係が乱れて絡みやすくなります。
少しテンションをかけた状態でフォールさせることで、Mキャロからリーダー、ジグヘッドまでが一直線に近い状態を保ち、絡みを防げます。
③リーダーを短めに設定する
前述の通り、リーダーの長さは絡みやすさに直結します。フォール中心の釣りなら20〜30cmに短縮することで、トラブルは大幅に減少します。
ちなみにリーダーの長さですが、私がフォール中心でやる場合はリーダーは20cmがベストと思っています。流れが速い場所や根が荒い場所では特にオススメで、どんなシュチュエーションでもトラブルが一番少ないです。
<cite>出典:Mキャロの使い方 その1</cite>
この経験談は非常に説得力があります。トラブルを最小限に抑えたいなら、まずは20〜30cmの短めリーダーから始めるのが賢明です。
さらに、絡んでいるかどうかをアクション後にチェックする方法もあります。トゥイッチを入れた直後、正常ならMキャロがバックスライドして穂先に「トんっ」という反応が返ってきます。絡んでいる場合は、この反応がなく、何も感じません。
このチェックを数秒に1回行うことで、絡んだまま釣りを続ける無駄な時間をなくせます。グダグダに絡む前に回収できるため、復旧作業も簡単です。
📋 絡み防止チェックリスト
- [ ] キャスト時に垂らしを十分にとっているか(30cm以上)
- [ ] 着水直前に強めのサミングを入れたか
- [ ] 着水後すぐにテンションを取ったか
- [ ] リーダーは適切な長さか(20〜50cm)
- [ ] 定期的にアクション後のチェックをしているか
- [ ] ジグヘッドの重さは適正か(0.4〜0.8g)
これらを意識するだけで、絡みトラブルは確実に減少します。特にキャスト直後の処理が重要で、ここを丁寧に行うかどうかで、その後の釣りの快適さが大きく変わってきます。
もしそれでも絡みが頻発する場合は、ジグヘッドが重すぎる可能性があります。前述の通り、1g以上の重いジグヘッドを使うと、キャスト時の重量バランスが崩れて絡みやすくなります。0.4〜0.5g程度の軽量タイプに変更してみることをおすすめします。
フロートリグとの使い分けが重要
アジングの遠投系リグには、Mキャロの他にフロートリグも存在します。どちらも遠投できるリグですが、特性が異なるため、状況に応じた使い分けが釣果アップの鍵となります。
⚖️ Mキャロとフロートリグの比較
| 項目 | Mキャロ | フロートリグ |
|---|---|---|
| 飛距離 | 〇(30〜50m) | ◎(40〜60m以上) |
| フォール速度 | やや速い〜中速 | 超スロー可能 |
| レンジキープ力 | ◎(優れている) | 〇(フロートの浮力依存) |
| 手返しの良さ | ◎(速い) | △(遅い) |
| 波・風の影響 | 受けにくい | やや受けやすい |
| 深場攻略 | ◎(得意) | △(苦手) |
| 表層攻略 | 〇(可能) | ◎(得意) |
| プランクトンパターン | △(不向き) | ◎(最適) |
| ベイトパターン | ◎(最適) | 〇(可能) |
| アタリの取りやすさ | ◎(直接伝わる) | △(フロート経由) |
この比較から見えてくるのは、Mキャロは効率重視・ディープ攻略型、フロートは繊細・表層攻略型という棲み分けです。
フロートリグが有利な状況としては、以下が挙げられます。
🎈 フロートリグが有利なシーン
- プランクトンを捕食している時(ワームが沈まない方が良い)
- 超スローフォールが必要な低活性時
- 表層〜中層をゆっくり探りたい時
- 最大限の飛距離が欲しい時
逆に、Mキャロが有利なのは次のような状況です。
⚓ Mキャロが有利なシーン
- ベイト(小魚)を追っている高活性時
- 中層〜ボトムをテンポよく探りたい時
- 深場や流れが速いポイント
- 波が高い日や風が強い日
- 時合いが短く、手返し重視の釣りをしたい時
プランクトンパターンには不向き。ワームのズレが頻発する場合はプランクトンパターンの場合があるので、フロートに変えると爆釣するかもw
<cite>出典:Mキャロ仕掛けで尺アジ・尺メバルを狙う!</cite>
この指摘は実践的で非常に有用です。ワームがズレやすいということは、アジが弱々しくつついているだけで、しっかりとバイトしていない証拠です。このような状況では、プランクトンを意識している可能性が高く、フロートリグの方が適しています。
私の考えとしては、両方のリグを準備しておき、状況によって切り替えるのが理想的です。例えば、朝マズメでベイトを追う活性の高いアジをMキャロでサーチし、日が高くなって活性が落ちたらフロートリグに切り替えるといった戦略が考えられます。
また、釣り場によっても使い分けが重要です。水深が浅いサーフや磯場ではフロートが有利ですが、港湾部や水深のある堤防ではMキャロの出番が多くなるでしょう。
最終的には、「どちらが絶対に良い」ということはなく、その日の状況とアジの活性を見極めて使い分ける判断力が重要になってきます。両方のリグの特性を理解し、タックルボックスに忍ばせておくことをおすすめします。
Mキャロに適したタックルセッティング
Mキャロを効果的に使うためには、専用のタックルセッティングが必要です。ジグ単用の繊細なタックルでは、Mキャロの性能を十分に引き出せないだけでなく、破損のリスクも高まります。
🎣 Mキャロ専用タックルの推奨スペック
【ロッド】
| 項目 | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| 長さ | 7.5〜8.6フィート | 飛距離を出すための遠投性能 |
| ルアーウエイト | MAX 10〜20g | Mキャロ本体の重量に対応 |
| パワー | L〜ML | 適度な張りでキャスト切れを防ぐ |
| タイプ | ソリッドティップ推奨 | アタリの取りやすさと繊細さ |
一般的なアジングロッドは6フィート前後ですが、Mキャロ用としては少し短すぎます。7.5〜8フィート程度の長めのロッドを使うことで、垂らしを長く取ってもキャストしやすく、飛距離も伸びます。
ロッド:7.5~8.5ft 6ftクラスのロッドでも可能だが飛距離が落ちます 私は8.6ftのエギングロッド
<cite>出典:【Mキャロ虎の巻】</cite>
この事例のように、アジング専用ロッドにこだわらず、エギングロッドのML(ミディアムライト)クラスを流用するのも一つの手です。エギングロッドは元々遠投性能を重視して設計されているため、Mキャロとの相性も良好です。
【リール】
| 項目 | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| 番手 | 2000〜2500番 | PEラインを十分に巻ける |
| ギア比 | ノーマル〜ハイギア | 状況に応じて選択 |
| 糸巻き量 | PE0.6号で150m以上 | 遠投とラインブレイク対策 |
| 重量 | できるだけ軽量 | 感度と疲労軽減 |
遠投すると50m以上ラインが出ることもあるため、十分な糸巻き量が必要です。もしラインブレイクが発生した場合を考えると、最低でも150m、できれば200m巻けるリールが安心です。
ギア比については、手返し重視ならハイギア、ゆっくり誘いたいならノーマルギアと使い分けると良いでしょう。個人的には、多少巻き速度を調整できるノーマルギアの方が汎用性が高いと感じます。
【ライン】
| ライン種類 | 推奨号数 | 特徴 |
|---|---|---|
| PE(推奨) | 0.4〜0.6号 | 最も飛距離が出る・風の影響を受けにくい |
| フロロカーボン | 3〜4lb | 風に強いが飛距離は落ちる |
| エステル | 0.4〜0.6号 | 感度は良いが強度に不安 |
Mキャロの遠投性能を最大限に活かすなら、PE0.5〜0.6号がおすすめです。エステルラインは感度が良い反面、10g前後の重量をフルキャストすると切れやすく、劣化も早いため、経験者向けといえます。
【リーダー】
メインラインがPEの場合、必ずショックリーダーを組みます。
- 元リーダー:フロロカーボン10〜12lb(1.5〜2号)を30〜40cm
- 先リーダー(ハリス):フロロカーボン4〜8lb(1〜1.5号)を20〜60cm
元リーダーを太く、先リーダーを細くすることで、根掛かり時にMキャロ本体をロストしないようにする工夫です。
🛠️ おすすめタックル例(予算別)
【エントリークラス:3万円前後】
- ロッド:ダイワ「アジメバルX 66L-S」または「月下美人 68L-S」
- リール:ダイワ「23レガリス LT2000S-P」
- ライン:ラパラ「ラピノヴァX マルチゲーム PE0.6号」
【ミドルクラス:5〜7万円】
- ロッド:がまかつ「宵姫 爽 S73L-solid」またはティクト「SRAM EXR-73S-Sis」
- リール:シマノ「20ヴァンフォード C2000S」
- ライン:デュエル「アーマード F+ 0.5号」
これらのタックルを基本として、釣り場や自分の釣りスタイルに合わせて微調整していくと良いでしょう。特にロッドは、長さとルアーウエイトの許容範囲をしっかり確認して選ぶことが重要です。
沈下速度の違いを理解して使い分ける
Mキャロを使いこなすうえで重要なのが、沈下速度の違いを理解することです。タイプ(L/N/S)と重量の組み合わせによって、沈下速度は大きく変わります。
沈下速度をコントロールできれば、アジがいるレンジを効率的に探り、長く留まらせることができます。この技術が釣果の差を生み出します。
⏱️ タイプ別・重量別の沈下速度イメージ
| タイプ | 重量 | 沈下速度 | 適した水深 |
|---|---|---|---|
| タイプL | 5.3g | ★☆☆☆☆(最も遅い) | 3〜7m |
| タイプL | 7.0g | ★★☆☆☆ | 5〜10m |
| タイプN | 4.6g | ★★☆☆☆ | 3〜7m |
| タイプN | 8.0g | ★★★☆☆ | 7〜15m |
| タイプS | 6.3g | ★★★★☆ | 10〜20m |
| タイプS | 9.5g | ★★★★★(最も速い) | 15m以上 |
沈下速度は、単純に「重いほど速い」というわけではありません。タイプによるフォール角度の違いも大きく影響します。例えば、タイプLの9.5gよりも、タイプSの6.3gの方が速く沈むケースもあります。
実釣において沈下速度をどう活用するかですが、カウントダウンが基本テクニックとなります。
📊 カウントダウンの実践例
- 着水後、カウントを取りながらフォールさせる
「1、2、3…」と秒数を数えながら沈めます。最初は着底までのカウント数を把握しましょう。 - アタリがあったカウント数を記憶する
例えば「カウント15でアタリがあった」という情報は、そのレンジにアジがいる証拠です。 - 同じカウント数で繰り返し攻める
次のキャストでも同じカウント15まで沈めてから誘い始めれば、効率的にアジを釣り続けられます。 - 反応がなくなったらカウントを変える
カウント10、20など、レンジを変えて再度探ります。
このカウントダウンを活用することで、無駄なく効率的にアジのいるレンジを特定できます。特に時合いが短いマズメ時などは、この技術の有無で釣果が大きく変わります。
沈下速度をさらにコントロールする方法として、テンションの調整があります。
- テンションを緩める(フリーフォール)→ より速く沈む
- テンションをかける(テンションフォール)→ よりゆっくり沈む
Mキャロはバックスライド特性があるため、テンションをかけるとバックスライドと手前に引く力が釣り合い、沈下速度が遅くなります。この特性を利用して、同じMキャロでも沈下速度に変化をつけられるのです。
Mキャロにはタイプ別で15°から60°の角度へ、後ろへ向かって落ちていくので、ゆっくり探れます。また垂直には落ち無いので、フォールでレンジがあまり変わらないという特徴もあります。
<cite>出典:Mキャロアジングで尺アジを狙え!</cite>
この特徴を活かし、同じレンジをより長く攻めることができるのがMキャロの強みです。垂直にストンと落ちるジグ単やスプリットショットリグと比較すると、レンジキープ力の差は歴然です。
私の考えとしては、初心者はまずタイプN 8.0gからスタートし、カウントダウンの感覚を掴むことをおすすめします。慣れてきたら、よりスローに誘いたい時はタイプL、もっと速く沈めたい時はタイプSや重量アップと、状況に応じて使い分けられるようになるでしょう。
自作よりも市販品を使うべき理由
「Mキャロ 自作」というキーワードで検索する方も多いようです。確かに、Mキャロは構造的にはシンプルで、浮力体とシンカー、チューブで構成されているため、自作することも不可能ではありません。
しかし、実際に自作を試みた経験者の多くが、最終的には市販品に戻るという選択をしています。その理由を整理してみましょう。
❌ 自作Mキャロの問題点
①完成度と安定性の差
市販のMキャロは、バージョンアップを重ねながら細かな改良が施されています。現在販売されているMキャロ ver.2は、初代から多くの改善点が盛り込まれており、素人が簡単に再現できるレベルではありません。
自己満足もあるでしょうけど、さすがに製品の完成度と安定性には素人ではちとかなわんです。実際Mキャロもバージョン2になって細かな改良がいくつもされているのでその辺も理解出来てないとなかなかね・・・
<cite>出典:Mキャロの使い方 その1</cite>
この指摘は的確で、実際に使い込んでみると、バランスの取れた浮力とシンカーの配置、チューブの材質など、細部にわたって計算されていることがわかります。
②コストパフォーマンスの問題
自作すれば確かに1個あたりのコストは下がります。しかし、必要な材料を揃えるための初期投資、失敗作の材料費、製作にかかる時間などを考慮すると、トータルでのコストパフォーマンスは必ずしも良くありません。
特に、満足できる性能の自作品を完成させるまでには、何度も試作を繰り返す必要があり、その過程で使う時間と材料を考えれば、市販品を購入した方が結果的に安上がりになるケースも多いでしょう。
③品質の均一性
自作の場合、毎回同じ性能のものを作るのは困難です。わずかな重量バランスの違いで、フォール角度や飛距離が変わってしまいます。市販品は工場で精密に製造されているため、品質が安定しています。
④修理・メンテナンス
Mキャロは適切に使用すれば長く使えます。多少の修理が必要になっても、構造を理解していれば対応可能です。ロストしなければ、コストパフォーマンスは十分に高いといえます。
💡 市販Mキャロを長く使うコツ
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| クッションゴムの使用 | スイベルとの接触でMキャロが割れるのを防ぐ |
| 根掛かり回避 | ドシャローでの使用を避ける |
| 適切な保管 | 直射日光を避け、専用ケースで保管 |
| 定期チェック | チューブの劣化や破損がないか確認 |
ティクトのMキャロは、重量やタイプにもよりますが、1個800〜1,000円程度です。確かに消耗品としては安くありませんが、性能と耐久性を考えれば妥当な価格といえるでしょう。
もちろん、「自作することで釣り道具への理解が深まる」「自分で作ったもので釣りたい」という目的であれば、自作にチャレンジする価値はあります。ただし、実釣性能を求めるなら市販品を使うべきというのが、多くの経験者の結論です。
私の考えとしては、Mキャロに限らず、完成度の高い専用品が存在する場合は、まずそれを使ってみて、十分に理解した上で「もっとこうしたい」という明確な改良点が見つかった時に初めて自作を検討する、というアプローチが賢明ではないかと思います。
まとめ:アジングのMキャロ仕掛けで沖の大型アジを狙おう
最後に記事のポイントをまとめます。
- Mキャロはティクトが開発した遠投特化型の中通しシンカーリグである
- バックスライドフォールにより着水後も飛距離が伸び、レンジキープ力に優れる
- 必要なパーツはMキャロ本体、ウキ止めゴム、スイベル、リーダー、ジグヘッド、ワームの6つ
- リーダーは元を太く(10〜12lb)、先を細く(4〜8lb)設定し、根掛かり時のロストを防ぐ
- ジグヘッドは0.4〜0.8gの軽量タイプを使用し、アジの吸い込みを良くする
- タイプL(15°)は表層向け、タイプN(30°)は汎用型、タイプS(60°)はディープ向けである
- Mキャロが釣れない原因は使いどころの間違いやタックルセッティングの不適合が多い
- 基本アクションはシャクリ+リトリーブで、ロッドを立ててレンジキープするとアタリが取りやすい
- 絡みトラブルは着水直前のサミング、テンションフォール、短めリーダーで防げる
- フロートリグはプランクトンパターンや表層攻略、Mキャロはベイトパターンやディープ攻略に向く
- Mキャロ専用タックルは7.5〜8.6フィートのロッド、2000〜2500番リール、PE0.5〜0.6号が基本
- 沈下速度はタイプと重量の組み合わせで変わり、カウントダウンで効率的にレンジを探る
- 自作よりも市販品の方が完成度・安定性・品質均一性の面で優れている
- Mキャロはジグ単では届かない沖の大型アジを狙うための最終兵器である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- Mキャロアジングで尺アジを狙え! – gagarablog’s
- アジング&ライトゲーム向けキャロライナリグ大全!作り方&釣り方、釣れないキャロまで徹底解説 | TSURI HACK
- 【アジング】キャロライナリグって何?最適タックルや仕掛けについて紹介 | つりにいく
- Mキャロ仕掛けで尺アジ・尺メバルを狙う!
- アジングの強者”キャロ”仕掛けがまじ釣れる理由【デカアジ捕獲におすすめ】 | AjingFreak
- Mキャロでアジング | かずゆきのアジング日記
- アジングのキャロライナリグ(Mキャロ)の使い方を徹底解説! – 釣りメディアGyoGyo
- 【Mキャロ虎の巻】 – 山陰釣り天国
- Mキャロの使い方 その1 | 釣りにいこい♪
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。