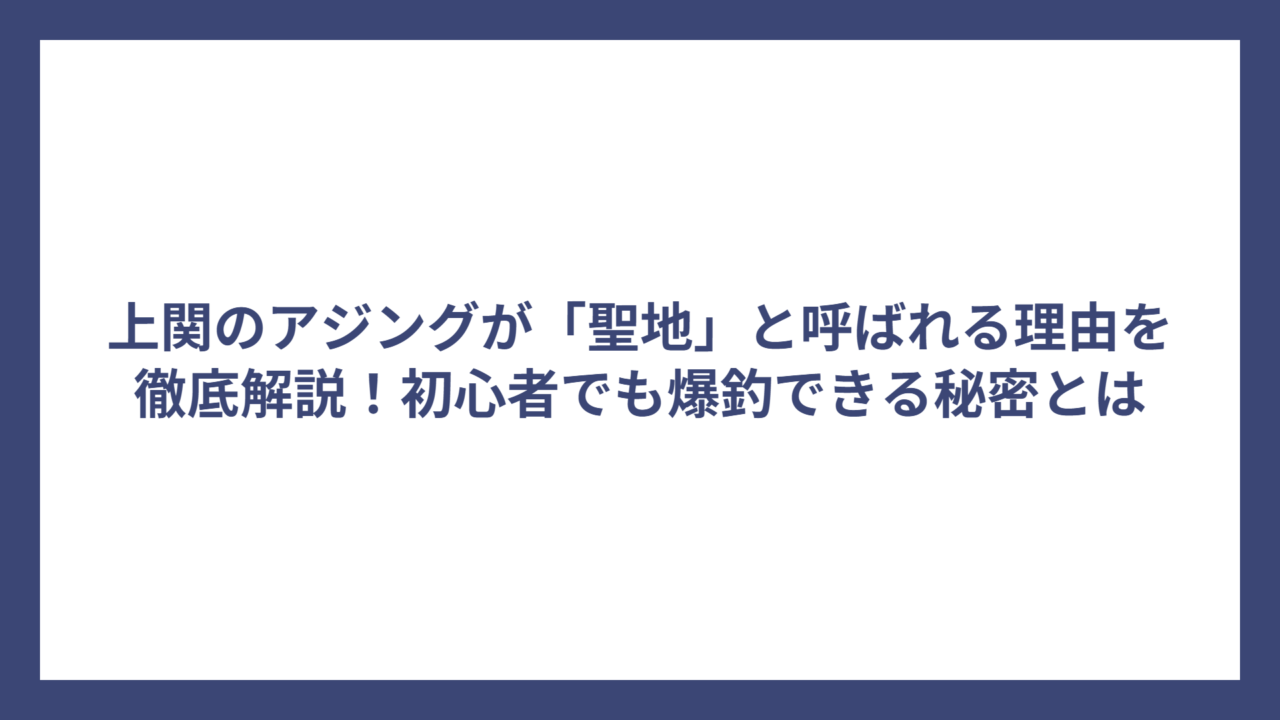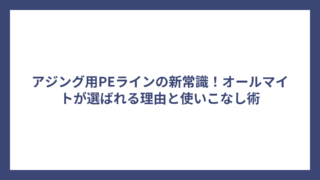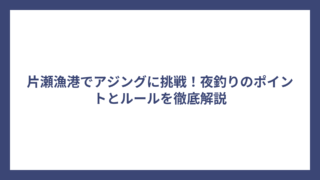山口県の上関町は、アジング愛好家の間で「聖地」として知られています。なぜこの場所がこれほど人気なのか、そしてなぜ初心者でも高確率で釣果を上げられるのか。インターネット上に散らばる釣行記や攻略情報を収集・分析した結果、上関アジングには他のエリアにはない明確な優位性があることが分かりました。魚影の濃さ、アクセスの良さ、多彩なポイント、そして何より「釣れる確率の高さ」が、多くのアングラーを惹きつけているようです。
この記事では、上関でアジングを始めたい方、あるいはさらに釣果を伸ばしたい方に向けて、具体的なポイント情報からタックル選び、実践的な釣り方まで、幅広い情報を網羅的にお届けします。実際の釣行記から見えてきた攻略のコツや、地元アングラーが実践しているテクニック、さらには周辺エリアとの比較情報まで、上関アジングの全貌を明らかにしていきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 上関が「アジングの聖地」と呼ばれる具体的な理由 |
| ✓ 初心者でも釣果を上げられる実績ポイントの詳細情報 |
| ✓ 上関攻略に最適なタックル選びと推奨ワーム |
| ✓ アミパターンをはじめとする実践的な釣り方テクニック |
上関アジングの魅力と実績ポイントを徹底調査
- 上関が「アジングの聖地」として認知されている理由
- 上関アジングで期待できる釣果とサイズ感
- 上関大橋周辺が人気を集める具体的な理由
- 室津漁港のキンキラ常夜灯ポイントの特徴
- ホワイトビーチポイントの攻略法
- その他の注目ポイント(KM漁港、デカアジポイントなど)
上関が「アジングの聖地」として認知されている理由はアジの魚影の濃さにある
上関がアジングの聖地と呼ばれるようになった最大の理由は、他エリアと比較して圧倒的に濃いアジの魚影にあります。
とりあず、運転しんどいけれどアジを釣るなら上関へ行け。ワームは鉄板の「アジアダー」
海域によって、アジの食性や群れの入り方は全然違います。その点、上関エリアのアジの魚影は抜群に濃いです。博打ではなく、とりあえずアジングを成立させたいという人は「上関」へ行きましょう。
この証言から分かるように、上関は「博打ではなく確実にアジングが成立する場所」として評価されています。広島市内近郊や他のエリアでは、特定の地合いやポイントを知らなければ素人がアジングを成立させるのが難しいという状況があるのに対し、上関では比較的容易にアジと出会えるというのが大きな違いです。
この魚影の濃さには、上関の地理的条件が大きく関係していると考えられます。上関瀬戸という潮通しの良い海峡部に位置し、豊富なプランクトンやベイトフィッシュが集まりやすい環境が整っているのでしょう。また、常夜灯が設置された漁港が複数あり、夜間にベイトが集まりやすい条件も揃っています。
実際の釣行記を見ると、「1回の釣行で20~25センチを15尾近く」という釣果や、「ツ抜け(10尾以上)達成」といった報告が頻繁に見られます。これは偶然ではなく、恒常的に魚影が濃い状態が維持されているということを示しています。
ただし、時期によって釣果にばらつきがあることも事実です。冬から春にかけてが最も好調で、夏場は少し渋くなる傾向があるようです。それでも他エリアと比較すれば、年間を通じて安定した釣果が期待できる場所と言えるでしょう。
また、上関へのアクセスも重要なポイントです。広島方面からは山陽自動車道を利用して約1時間30分程度、県内各地からも比較的アクセスしやすい立地にあります。「運転しんどい」という表現はあるものの、釣果と天秤にかければ十分に価値がある距離と言えるかもしれません。
上関アジングで期待できる釣果はアベレージ20-25cmで数釣りも可能
上関でのアジングで期待できる釣果について、複数の釣行記から具体的なデータが見えてきます。
📊 上関アジングの典型的な釣果データ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| アベレージサイズ | 20~25cm |
| 1回の釣行での平均釣果 | 10~15尾 |
| 最大サイズの報告 | 28cm |
| ツ抜け達成率 | 高い(多くの釣行記で10尾以上を記録) |
上関に通うようになる前、自分にとってアジングというのは「雑誌とか動画紹介されている自分とは縁のない釣り」でした。というのも、そのころホームエリアにしていた広島市内近郊部やとびしまでは、特定の地合いやポイントを知らなければ、「ど素人」にはアジングを成立させることが難しかったのです。
それが、上関で修業したおかげで・・・(いや、上関という場所のおかげで)1回の釣行のアベレージが、20~25センチを15尾近く釣るまでになりました。
この証言は非常に重要です。アジング初心者が約半年間上関に通うことで、安定して15尾近くを釣れるようになったという実績は、上関の「教育効果」の高さを示しています。魚影が濃いため試行回数を多く重ねられ、結果として釣りの腕が上がるという好循環が生まれているのでしょう。
サイズに関しては、20~25cmがメインで、時折28cm前後の良型も混じるというのが標準的なパターンのようです。尺(30cm)サイズの報告は少ないものの、食べて美味しいサイズが数釣れるという点で、多くのアングラーにとって満足度の高い釣りができる場所と言えます。
別の釣行記では、「最大28センチ、超久々にツ抜け達成」という報告もあります。ツ抜けは10尾以上を意味する釣り用語ですが、上関ではこれが「達成できる目標」として現実的なラインになっているのが特徴的です。
また、時期による釣果の変動も報告されています。冬から春にかけては特に好調で、「爆釣」という表現が使われることも多いです。一方で、「最近渋い」という時期もあるようですが、それでも他エリアと比較すれば十分な釣果が期待できる水準を保っているようです。
釣行時間帯については、夕マズメから夜間にかけてが最も実績が高いようです。ただし、日中でもアジの反応があるポイントも存在し、時間帯を問わず楽しめる可能性があります。これも魚影の濃さゆえの特徴と言えるでしょう。
初心者の方は、まず「ツ抜け達成」を目標に、20cm前後のアジを安定して釣ることを目指すのが良いかもしれません。経験を積めば、より大型を狙ったり、数を伸ばしたりと、レベルアップの楽しみも広がっていくはずです。
上関大橋周辺が人気を集める理由は潮の流れと反転流にある
上関大橋周辺は、上関アジングの中でも特に人気の高いエリアです。その理由は、潮の流れが作り出す反転流にあります。
上関大橋下ポイントへ移動する。ここでの釣り方は、満ち潮で潮が右から左へ流れている時は大橋の下側の本流の直ぐ脇の反転流の潮が緩んでいる所へ2グラムのジクヘッド単体でドリフト潮にシンクロさせながら落とすとアジが良く釣れる。
引き潮時は潮が左から右側へ流れる。本流の脇に反転流ができ丁度カーブミラー付近に反転流ができる。そこに、ジグヘッド単体をドリフトして潮にシンクロさせるとアジが良く釣れる。
この情報から分かるように、上関大橋下では潮の満ち引きに応じて反転流が発生する場所が変わります。満ち潮時と引き潮時で攻めるポイントを変える必要があるという、やや技術的な要素がありますが、これが逆に「釣れるパターン」を学ぶ良い教材になっているとも言えます。
🎣 上関大橋周辺の潮汐別攻略ポイント
| 潮の状態 | 潮の流れ | 狙うべきポイント | 推奨ジグヘッド |
|---|---|---|---|
| 満ち潮 | 右から左 | 大橋下側の本流脇、反転流の潮が緩い場所 | 2g |
| 引き潮 | 左から右 | カーブミラー付近の反転流 | 2g |
反転流が重要な理由は、アジが強い流れを避けて、流れが緩んだエリアに溜まる習性があるためです。本流では餌を追いにくく体力も消耗するため、反転流のような「ヨレ」に身を潜めながら、流れてくる餌を効率的に捕食しているのでしょう。
ドリフト釣法とは、ジグヘッドを潮の流れに乗せて自然に流していく釣り方です。「潮にシンクロさせながら落とす」という表現からは、ただ投げて巻くのではなく、潮の流れに同調させる繊細なテクニックが求められることが分かります。
上関大橋周辺は人気ポイントゆえに釣り人も多く、「ポイントに2人の釣り人が入っていたので入れず」という状況も報告されています。週末や好条件の日は早めに入ることを考慮した方が良いかもしれません。
また、大橋周辺は潮が速すぎて釣りにならない状況もあるようです。潮の流れは時間帯や潮汐によって大きく変わるため、タイドグラフを確認して潮が程よく動いている時間帯を狙うのが賢明でしょう。潮止まり前後は流れが緩むため、初心者でも釣りやすい時間帯かもしれません。
上関大橋周辺で釣りをする際は、電線が張り巡らされている場所もあり、遠投する際は注意が必要という情報もあります。安全に十分配慮しながら釣りを楽しむことが大切です。
室津漁港のキンキラ常夜灯ポイントは高活性時の実績が高い
室津漁港は上関エリアの中でも特に常夜灯周りのアジングで実績の高いポイントです。
複数の釣行記で「室津漁港のキンキラ常夜灯ポイント」という表現が使われており、明るい常夜灯がアジを集める重要な要素になっていることが分かります。常夜灯周りでは、光に集まったプランクトンやベイトフィッシュを追ってアジが集まる典型的なパターンが成立します。
最初に到着したのが室津漁港のキンキラ常夜灯ポイント、ここは潮が速過ぎて釣りにならない。ポイントに2人の釣り人が入っていたので入れず釣果なし。
この報告から分かるのは、室津漁港も潮の流れが速い時間帯があり、条件が合わないと釣りにならないということです。おそらく潮が緩む時間帯を狙うのが効果的でしょう。
別の釣行記では、室津漁港周辺で「アミ」が重要なキーワードとして登場します。アミとは小型の甲殻類で、アジの重要な餌となります。常夜灯周りにアミが集まると、それを追ってアジが高活性になるパターンがあるようです。
💡 室津漁港攻略のポイント
- ✓ 常夜灯周りを重点的に探る
- ✓ 潮が速すぎる時は避け、潮が緩む時間帯を狙う
- ✓ アミの存在を確認する(水面に白い線が見えることも)
- ✓ 人気ポイントのため、早めの入釣を検討
室津漁港は「上関で釣るなら外せないポイント」という位置づけのようですが、条件が揃わないと厳しい面もあります。潮汐を事前にチェックし、潮が緩む時間帯に合わせて入るのが賢明かもしれません。
また、テレビ番組で「上関の室津漁港アジ一人20匹」と紹介されたこともあるようで、メディアでも取り上げられるほどの実績ポイントです。ただし、そのような情報が流れた後は当然釣り人も増えるため、混雑を覚悟する必要があるでしょう。
常夜灯周りでの釣り方は、明暗の境目を意識することが重要です。明るい部分だけでなく、光が届く範囲の外側や、影になっている部分にもアジが潜んでいることがあります。表層から中層、ボトムまで、レンジを変えながら探ることで反応を得やすくなるはずです。
室津漁港での釣行を計画する際は、複数のポイントをランガンする前提で考え、条件が合わなければ素早く移動する判断も必要かもしれません。上関エリアには他にも多くのポイントがあるため、固執せずに柔軟に対応するのが釣果を伸ばすコツと言えるでしょう。
ホワイトビーチポイントは波止の内側も有望な選択肢
ホワイトビーチは上関アジングのもう一つの代表的なポイントです。駐車場からのアクセスも良く、多くのアングラーが訪れる場所となっています。
土曜日の20時頃であるので波止の先端付近は人だかり、目指すアジングポイントには入れず、波止の内側に遠投してアジを二匹釣るのがやっとです。
この証言からは、ホワイトビーチが非常に人気の高いポイントであることが分かります。特に週末の夜は混雑が予想され、好ポイントに入れないことも多いようです。
しかし、注目すべきは「波止の内側に遠投してアジを二匹釣る」という部分です。先端に入れなくても、波止の内側から遠投することで釣果を得ることができるということは、アジの回遊範囲が広いことを示唆しています。
🏖️ ホワイトビーチエリアの特徴
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| アクセス | 駐車場から近く、入釣しやすい |
| 混雑度 | 週末の夜は特に混雑、先端付近は人だかり |
| 代替戦略 | 先端に入れない場合は内側から遠投 |
| シーバスの実績 | アジング以外にシーバスも回遊 |
別の釣行記では、ホワイトビーチポイントでシーバスが入っているという情報もあります。「そのポイントは釣り人が多く」とあることから、アジングだけでなく複合的に魚種が狙えるエリアとして人気があることが分かります。
ホワイトビーチで釣果を上げるためには、混雑を避けるタイミングで入釣するか、あるいは人気の先端にこだわらず、波止の内側や側面から広範囲を探るという戦略が有効かもしれません。
また、遠投が必要になるケースもあるため、軽量ジグヘッドだけでなく、キャロライナリグやフロートリグなど、飛距離を稼げる仕掛けも用意しておくと選択肢が広がるでしょう。
ホワイトビーチは駐車場からのアクセスが良いという利点があり、初めて上関を訪れる方にとっては入釣しやすいポイントと言えます。ただし、その分人気も高いため、平日や早朝・深夜など、混雑を避けられる時間帯を狙うのも一つの戦略です。
その他の注目ポイントはKM漁港やデカアジポイントなど複数存在する
上関エリアには、これまで紹介した以外にも注目すべきポイントが複数存在します。
次は、KM漁港へ転戦する。15分位でKM漁港へ到着。常夜灯が点灯している内側のL字型の波止へ入ります。ここでのポイントはL字型の角の位置がポイントですが、土曜の20時過ぎということもあって、なかなか目指すポイントは確保できません。
KM漁港(おそらく匿名化されたポイント名)は、L字型の波止が特徴で、角の位置が一級ポイントとされています。角は潮が当たって流れが変化する場所であり、アジが溜まりやすいという一般的な釣り場の特徴に合致しています。
また、「デカアジポイント」と呼ばれる場所も存在するようです。
次は、上関のデカアジポイントに急行します。ここは最近波止の先端が30メートル延長され、アジの通る道が消滅してアジが釣れなくなりました。
この情報は重要です。かつて「デカアジポイント」として知られていた場所が、波止の延長工事により環境が変わり、釣果が落ちたという事例です。釣り場は常に変化しており、過去の情報が必ずしも現在に当てはまらないことを示しています。
📍 上関エリアのその他のポイント
- 上関漁協:かつては実績があったが、常夜灯消灯後は釣果が落ちた
- 上関大橋直ぐポイント:電線が張り巡らされ遠投が難しい
- デカアオリポイント:アオリイカの実績もある複合ポイント
- 四代漁港:長島の最南端、護岸からも実績あり
これらのポイント情報から分かるのは、上関エリアには非常に多くの釣り場が点在しており、「ランガン(移動しながらの釣り)」が有効な戦略だということです。一つのポイントに固執せず、複数のポイントを効率的に回ることで、その日の好条件なポイントを見つけることができるでしょう。
また、環境の変化によって釣果が変わることもあるため、最新の釣果情報をSNSや釣具店でチェックすることも重要です。2010年の釣行記では釣れていたポイントが、現在は条件が変わっている可能性もあります。
上関アジングを最大限に楽しむためには、メインとなる2~3ヶ所のポイントを押さえつつ、時間や潮の状況に応じて柔軟に移動する戦略が効果的と言えるでしょう。車での移動が前提となるため、ポイント間の距離や移動時間も事前に把握しておくことをお勧めします。
上関アジングを成功させるタックルと実践テクニック
- 上関アジング成功のカギはミドルクラス以上のロッド選択にある
- 推奨ジグヘッドは0.6g~2gで状況に応じて使い分けが必要
- ワーム選びの鉄板は「アジアダー」を中心に複数カラーを用意
- アミパターンへの対応が上関攻略の最重要テクニック
- 表層からボトムまでレンジを探ることが釣果アップのコツ
- 潮の流れを読みドリフト釣法をマスターすべき
- 時期による釣れ方の違いと最適シーズンの見極め
- まとめ:上関でのアジングを最大限楽しむために
上関アジング成功のカギはミドルクラス以上のロッド選択にある
上関でアジングを始める際、タックル選びは非常に重要です。特にロッドについては、明確な推奨があります。
とりあえず、道具はミドルクラスのものを。安いものはあきまへんでー。
アジのバイトは本当に繊細です。下手なロッドでは、手元に振動を感じた時には、もうアジはワームを吐き出しています。とりあえず、ミドルクラス以上のアジングロッドがおすすめです。感度が全然違います。
この証言から分かるのは、エントリーモデルの安価なロッドでは、アジの繊細なバイトを感じ取りにくいということです。バイトを感じた時にはすでにワームを吐き出されている、という状況では、せっかくのチャンスを逃してしまいます。
具体的な推奨タックルとして、以下のような情報が提供されています。
ちなみに自分はAPIAのグランデージシリーズの「グランデージライト64(GLANDAGE LITE 64)」を愛用しています。こいつは、分類上はメバリングロッドなのですが、アジもメバルも両方いける便利な竿です。
パツパツなアジングロッドほどは弾かず、アジの繊細なあたりも感知し、かつメバリングのような巻きの釣りにも対応してくれます。
🎣 推奨タックルの具体例
| カテゴリー | 推奨アイテム | 価格帯 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ロッド | APIA グランデージライト64 | 約2万円台中盤 | メバリング・アジング兼用、ジグ単から5gキャロまで対応 |
| リール | ダイワ カルディア LT2000S | 約2万円前後 | カラーリングも良く、スペック十分 |
| 合計投資額 | – | 約4万円 | 一生使える投資として推奨 |
「最初に4万ちょっと、投資のつもりで買っておくと一生ものですよ」というアドバイスは、安物を買って買い替えを繰り返すよりも、最初からしっかりしたタックルを揃える方が結果的にコスパが良いという考え方です。
ロッドの長さについては、7フィート前後が使いやすいようです。上関のポイントは比較的足元から釣れることも多く、極端に長いロッドは必要ない場面が多いかもしれません。ただし、ホワイトビーチのように遠投が必要な状況もあるため、7.6フィート程度のロッドも選択肢として持っておくと良いでしょう。
また、「釣りの腕を頑張って磨く前に、釣り具にそれなりに投資してください」というアドバイスは示唆的です。技術の向上には時間がかかりますが、道具の性能は購入した瞬間から釣果に直結します。特に初心者の場合、感度の高いロッドを使うことで、アジのバイトを明確に感じ取れるようになり、学習速度が上がるという効果も期待できます。
とはいえ、最初から高額なタックルを揃えるのが難しい場合もあるでしょう。その場合は、少なくとも「ミドルクラス」と呼ばれる価格帯(ロッドで2万円前後、リールで1万5千円~2万円程度)を目安に選ぶことをお勧めします。エントリーモデルとミドルクラスの間には、感度や操作性において明確な差があるようです。
推奨ジグヘッドは0.6g~2gで状況に応じて使い分けが必要
上関アジングで使用するジグヘッドの重さは、状況に応じて0.6g~2g程度を使い分けるのが効果的です。
ちゃんとジグヘッドを0.5gにして、表層からほぼテンションをかけずにアプローチするとさっきまでの反応が嘘のように爆釣!
軽いジグヘッドの時期が来ましたね~✨
この情報から、時期によってアジの活性やいるレンジが変わり、それに応じてジグヘッドの重さを調整する必要があることが分かります。0.5g~0.6gという超軽量ジグヘッドが有効な時期もあれば、1g~2gが必要な状況もあります。
⚖️ ジグヘッドの重さ別使用シーン
| 重さ | 使用状況 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 0.5~0.6g | 無風・表層狙い・高活性時 | ゆっくり沈む、自然なフォール | 風に弱い、飛距離が出ない |
| 1g | オールマイティ | バランスが良い標準ウェイト | 最も使用頻度が高い |
| 1.5~2g | 風が強い時・ボトム狙い・遠投 | 飛距離が出る、素早く沈む | フォールスピードが速すぎることも |
実際の釣行記では、「風が強いので今回は1g&34プランクトン」という選択がされています。風の影響を受けやすい軽量ジグヘッドでは釣りにならない状況で、1g程度の重さにすることでキャストの精度や仕掛けの安定性が向上するのでしょう。
また、「0.6gジグヘッドにフロートリグ」という組み合わせも報告されています。これは、軽いジグヘッドを使いたいが飛距離も欲しいという状況で、フロート(浮き)を併用することで両立させるテクニックです。フロートからジグヘッドまでを1.5mに設定し、狙いたいレンジにジグヘッドを送り込むという高度な釣り方も実践されています。
ジグヘッドを0.6gにチェンジ。ワームはそのままでフロートリグにして、フロートからジグヘッドまでを1.5mに設定。波紋よりも沖に投げてジグヘッドをなじませた状態で波紋が立つ場所へ潮に乗せて引き込むと……アジがヒット。
この釣り方は、まるでウキ釣りのようにジグヘッドを潮に乗せて流し込むという発想です。アジが表層に浮いている状況や、特定のレンジに集中している状況で非常に効果的なようです。
ジグヘッドの形状については、詳しい言及はありませんが、一般的にはラウンド型やダート型など、複数のタイプを用意しておくと状況に応じた対応が可能になります。
初心者の方は、まず1gのジグヘッドを中心に、0.6gと1.5gを予備として持っておくのが良いかもしれません。釣り場で風の強さや潮の流れを見ながら、最適な重さを見つけていくプロセスも、アジングの醍醐味の一つと言えるでしょう。
ワーム選びの鉄板は「アジアダー」を中心に複数カラーを用意
上関アジングにおけるワーム選びでは、「アジアダー」が鉄板として推奨されています。
ワームは鉄板の「アジアダー」
あと、何のワームを使ったらいい?という質問をよく受けますが、レインズの「アジアダー」を数色持っていれば、まあ間違いないですよ。どんな状況でも力を発揮してくれます!!
レインズのアジアダーは、アジング用ワームとして長年の実績があり、多くのアングラーに支持されている定番ワームです。「どんな状況でも力を発揮してくれる」という評価は、安心して使えるワームということを示しています。
🐟 推奨ワームカラー
- 上関ブルーエンゼル:地名を冠したカラー、上関での実績が高い
- 桃色グロス:視認性が高く、濁り潮でも効果的か
- 日向夏:柑橘系の明るいカラー、状況によって効く
カラーローテーションは釣果を左右する重要な要素です。「数色持っていれば」というアドバイスの通り、最低でも3~5色は用意しておきたいところです。
別の釣行記では、「スパテラ2.5インチ」「リヴァーチ1.6インチ」といったワームも使用されています。アジアダーだけでなく、複数のワームを試すことで、その日のアジの好みを探ることも有効でしょう。
ジグヘッド(1gとスパテラ2.5インチ)をキャスト。18~20cmとまずまずのサイズのメバルがヒットします。
ワームのサイズについては、1.6インチ~2.5インチ程度が使用されているようです。アジのサイズやその日の活性に応じて、ワームサイズも調整すると良いかもしれません。小型のアジが多い場合は小さめのワーム、良型を狙う場合は2インチ以上のワームという使い分けも考えられます。
また、「34プランクトン」というワームも登場しています。これは34(サーティーフォー)というメーカーのワームで、アジング専用設計の製品です。アジアダーと並んで、信頼できる選択肢の一つと言えるでしょう。
ワームの装着方法も重要です。真っ直ぐに刺さっているか、ジグヘッドとのバランスは適切かなど、細かい点にも注意を払うことで、ワームの動きが自然になり、釣果につながります。
初心者の方は、まずアジアダーの3色セットを購入し、そこから徐々にバリエーションを増やしていくのが良いでしょう。高価なワームを一つ買うよりも、複数の色を揃えることで、その日のヒットカラーを見つけやすくなるはずです。
アミパターンへの対応が上関攻略の最重要テクニック
上関アジングで最も重要なパターンの一つが「アミパターン」です。これは多くの釣行記で強調されている、上関特有の攻略法と言えます。
上関はアミを攻めろ!!!
自分が上関に通い始めてまず思ったこと。それは「アミ」が目印となって釣れることが多い、ということです。特に常夜灯の周辺に、白い泡が線のようになって表れている場合はフィーバーパターンです。
その線の下には、アジやメバルが狂喜乱舞している可能性があります。風が弱ければ、超軽量(0.6gとか)ジグ単で、風があれば、ミニMキャロに、超軽量ジグヘッドをつけてスローに表層付近を探りましょう!!
アミとは小型のエビの仲間で、プランクトンの一種です。このアミが水面付近に群れると、「白い線」や「白い泡」のように見えます。これを見逃さないことが、上関アジング成功の鍵となります。
🦐 アミパターンの見つけ方と攻略法
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 発見 | 水面に白い線や泡を探す | 特に常夜灯周辺を注視 |
| 2. アプローチ | 風が弱い→0.6g超軽量ジグ単 | 表層をスローに探る |
| 3. アプローチ | 風が強い→ミニMキャロ+軽量ジグヘッド | 飛距離を確保しつつ表層狙い |
| 4. 注意点 | 向かい風の日は足元にアミが寄る | 足元周辺を重点的に |
「素人の釣り人はアミの線が出ていても普段のようにジグ単で遠投したりして、あまり状況を気にせず釣ってしまっています」という指摘は重要です。アミが目の前にあるのに、それを無視して通常通りの釣りをしていては、せっかくのチャンスを逃してしまいます。
アミパターンが発生している時は、アジやメバルが表層付近に浮いて捕食している高活性状態です。この時は、無理にボトムを探る必要はなく、表層~中層をスローに引いてくる釣り方が効果的です。
このアミの線がキャストしやすい範囲(足元周辺)に来るときはえてして向かい風の爆風の日が多いです。こういう日こそ足元のアミの線を攻めましょう!
この情報は戦略的に非常に価値があります。向かい風の日は釣りにくい条件ですが、その風によってアミが岸際に寄せられることで、足元で好釣果が得られる可能性があるということです。
別の釣行記でも、シラス(アミと同様の小型ベイト)の存在が釣果を左右した例が報告されています。
アジもメバルもシーバスも胃からたっぷりシラスが出てきました。ワームが有効なのに納得。
魚の胃内容物からシラスが大量に出てきたという事実は、その時期にシラス(アミ)を主食としていたことを示しています。ワームがシラスやアミに似ているから効果的だったという、納得のいく結果です。
アミパターンへの対応は、目視でアミの存在を確認する観察力と、それに合わせてタックルやアプローチを変える判断力の両方が求められます。釣り場に到着したら、まず水面をじっくり観察し、アミやベイトの存在を確認する習慣をつけることが重要でしょう。
表層からボトムまでレンジを探ることが釣果アップのコツ
アジがどのレンジ(水深)にいるかを探ることは、アジングにおいて基本かつ重要なテクニックです。
釣行記の中で、「表層ではメバル・セイゴが釣れ、ボトム付近でアジが数匹釣る」という記述があります。これは、同じポイントでも魚種によって、また同じ魚種でも状況によって、いるレンジが異なることを示しています。
📏 レンジ別の傾向と攻略法
| レンジ | 傾向 | 使用ジグヘッド | アクション |
|---|---|---|---|
| 表層(0~50cm) | 高活性時、アミパターン時、メバルも混じる | 0.5~1g | スローリトリーブ、ドリフト |
| 中層(50cm~1.5m) | 標準的なレンジ | 1~1.5g | カウントダウンで狙う |
| ボトム(底付近) | 低活性時、日中 | 1.5~2g | ボトムバンプ、ステイ |
レンジを探る基本的な方法は「カウントダウン」です。キャスト後、ジグヘッドが着水してから「1、2、3…」とカウントし、何カウントで反応があったかを記憶します。例えば「5カウント」でヒットしたら、次のキャストも5カウント沈めてから巻き始めることで、効率的にアジのいるレンジを攻められます。
海面から1.5mほど下のレンジにアジがいるのが分かりました。でもシラスを食べている高活性のメバルが表層でヒットするため、アジのレンジまでジグヘッドリグが届きません。
この状況は非常に興味深いものです。アジは中層にいるのに、表層でメバルが先に食ってしまうため、狙ったレンジに仕掛けが届かない。このような時は、ジグヘッドの重さを変えるか、フロートリグを使うなど、工夫が必要になります。
また、時間帯によってもレンジは変化します。一般的に、日中はボトム付近にいることが多く、夕マズメから夜にかけては中層~表層に浮いてくる傾向があります。ただし、これは絶対的なルールではなく、その日の潮や水温、ベイトの状況によって変わります。
レンジを探る際のコツは、「同じレンジばかり探らない」ことです。「今日はボトムで釣れた」という先入観があると、翌日も同じレンジばかり攻めてしまいがちですが、魚は毎日同じレンジにいるとは限りません。釣り始めは表層からボトムまで、一通り探ってみる姿勢が大切です。
さらに、一度釣れたレンジでも、時間経過とともに変化することがあります。定期的にレンジを再確認することで、その時々の最適なレンジを見つけ続けることができるでしょう。
潮の流れを読みドリフト釣法をマスターすべき
上関アジングで効果的な釣法の一つが「ドリフト釣法」です。これは潮の流れを利用した釣り方で、上関のような潮通しの良い場所では特に有効です。
2グラムのジクヘッド単体でドリフト潮にシンクロさせながら落とすとアジが良く釣れる。
「潮にシンクロさせながら」という表現が重要です。これは、ジグヘッドを潮の流れに逆らわず、自然に流していくイメージです。不自然なテンションをかけず、潮と一体になって流すことで、アジに違和感を与えない自然なアプローチが可能になります。
🌊 ドリフト釣法のポイント
- 潮の流れを把握する:まず水面の動きや漂流物を観察し、潮の方向と速さを確認
- 潮上にキャスト:潮の流れてくる方向に投げる
- テンションを抜く:ラインを張りすぎず、潮と同じ速度で流す
- 当たりを取る:糸ふけを完全に出すのではなく、アタリが取れる程度のテンションは維持
- 流れに乗せる:ジグヘッドが潮と同じ速度で移動するイメージ
ドリフト釣法は、「ただ巻き」とは異なるアプローチです。ただ巻きはリールを一定速度で巻くことでワームを動かしますが、ドリフトは潮の力でワームを動かします。より自然な動きになるため、警戒心の強いアジにも効果的です。
上関大橋下での釣り方説明でも、「ドリフトして潮にシンクロさせる」という表現が使われており、この釣法が上関攻略の重要なテクニックであることが分かります。
ただし、ドリフト釣法にはコツがあります。完全にラインを緩めてしまうとアタリが分からなくなるため、「張らず緩めず」の絶妙なテンションコントロールが求められます。これは経験が必要なテクニックですが、上関のように魚影が濃い場所で練習すれば、比較的早く習得できるでしょう。
また、風が強い日はドリフトが難しくなります。ラインが風に煽られてしまい、潮の流れとは別の動きをしてしまうからです。そのような日は、ジグヘッドを重くして風の影響を受けにくくするか、風裏のポイントを選ぶなどの対策が必要になります。
ドリフト釣法は、特に潮が動いている時間帯に有効です。潮止まりの時間帯は流れがないため、ドリフトではなくただ巻きやリフト&フォールといった他のアクションを試すのが良いかもしれません。
時期による釣れ方の違いと最適シーズンの見極め
上関アジングは年間を通じて楽しめますが、時期によって釣れ方や釣果に違いがあります。
複数の釣行記を分析すると、冬から春にかけて(12月~4月頃)が最も好調なシーズンのようです。「爆釣、冬の上関アジング!!」というタイトルの記事や、「今年も恒例のアジング納め」といった12月の釣行記が多く見られます。
🗓️ 季節別の傾向(推測を含む)
| 時期 | 状況 | 特徴 | 推奨度 |
|---|---|---|---|
| 冬(12~2月) | 好調 | サイズも良く数も出る、「爆釣」報告多数 | ★★★★★ |
| 春(3~5月) | 好調 | 引き続き良好、シラス・アミパターン | ★★★★★ |
| 夏(6~8月) | やや渋い | 釣果は落ちるが全く釣れないわけではない | ★★★☆☆ |
| 秋(9~11月) | 回復傾向 | 水温低下とともに活性上昇 | ★★★★☆ |
冬場の釣行記では、「この日色々なルアーを試しましたが反応の良かったルアーは…」といった記述や、「先週から鯵が出だした!」という情報提供が見られ、冬季がハイシーズンであることが伺えます。
一方で、「最近渋い上関アジング調査編」という2月の釣行記もあり、同じ冬場でも年によって、あるいは細かい時期によって状況が変わることも分かります。ただし、この「渋い」とされる釣行でも、「でも、結局釣り欲には勝てません」と出かけて実際に釣果を得ているところに、上関の底力が表れています。
最近渋いと聞き行くのを躊躇していた福ちゃんです💦 でも、結局釣り欲には勝てません😇釣れないの覚悟で釣行へ🔥🎣
この釣行では「渋さが嘘のように釣れました」という結果になっており、「渋い」という情報も鵜呑みにせず、実際に行ってみることの大切さを教えてくれます。
季節による違いとして、使用するジグヘッドの重さも変わってきます。1月の釣行記では「軽いジグヘッドの時期が来ましたね」と0.5gが効果的だった一方、別の時期には1g以上が必要という報告もあります。これは水温やアジの活性、いるレンジなどが季節によって変化するためでしょう。
また、シラスやアミの接岸時期も釣果に大きく影響します。これらのベイトが豊富な時期は、アジの活性も高くなり、釣果も伸びやすいです。地元の釣具店やSNSで「シラス・アミが入っている」という情報が流れたら、好機と捉えて出かけるのが良いかもしれません。
天候や水温も考慮要素です。冬場でも暖かい日が続いた後は活性が上がることもあれば、冷え込みが続くと渋くなることもあります。気象情報と合わせて判断することで、より釣れる日を選べるでしょう。
最適なシーズンを一言で言えば、12月から4月の冬春シーズンが上関アジングのベストタイミングと言えそうです。ただし、それ以外の時期でも上関の魚影の濃さゆえに十分な釣果が期待できるため、年間を通じて挑戦する価値があります。
まとめ:上関でのアジングを最大限に楽しむために知っておくべきこと
最後に記事のポイントをまとめます。
- 上関は「アジングの聖地」と呼ばれ、他エリアと比較して圧倒的に魚影が濃い
- 初心者でも1回の釣行で20~25cmのアジを10~15尾釣る実績がある
- 上関大橋周辺、室津漁港、ホワイトビーチなど複数の実績ポイントが存在する
- 潮の満ち引きによる反転流を理解し、適切な場所を狙うことが重要
- ミドルクラス以上のロッド(2万円台)を使用することで感度が格段に向上する
- ジグヘッドは0.6g~2gを状況に応じて使い分ける必要がある
- ワームは「アジアダー」が鉄板で、複数カラーを用意するのが効果的
- 「アミパターン」への対応が上関攻略の最重要テクニック
- 水面に白い線や泡が見えたら、その下を超軽量ジグヘッドで攻める
- 表層からボトムまでレンジを探り、その日のアジがいる層を見つける
- ドリフト釣法をマスターし、潮の流れを利用した自然なアプローチを心がける
- 冬から春(12月~4月)が最も好調なシーズンである
- 人気ポイントは混雑するため、複数ポイントをランガンする戦略が有効
- 釣り場の環境は変化するため、最新の釣果情報を常にチェックする
- 初心者は上関で経験を積むことで、短期間でアジングの腕を上達させられる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 素人でも釣れる?上関アジング!! – 瀬戸内アジンガー Ucchy’s Ajing diary
- アジング上関 | 華金スカイウォーカーのブログ
- 上関・アジの通る道を伝授する為にランガン! – ワーミング日記
- それゆけアジング「上関編その4」&「ロックブレード復活のお知らせ」(バンダナ釣行記)
- 土居ちゃんのいっ釣行きますか!「久しぶりの爆釣上関アジング!」【551】 | 釣具のポイント
- 上関大橋周辺 アジ 陸っぱり 釣り・魚釣り | 釣果情報サイト カンパリ
- ☆福ちゃんの釣り修行☆最近渋い上関アジング調査編!! | 釣具のポイント
- 岡山県宇野沖にタイラバに釣行すると、良型のヒラメがヒット! | 釣りぽ TSURIPO
- 山口県の上関町でアジングとメバリング
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。