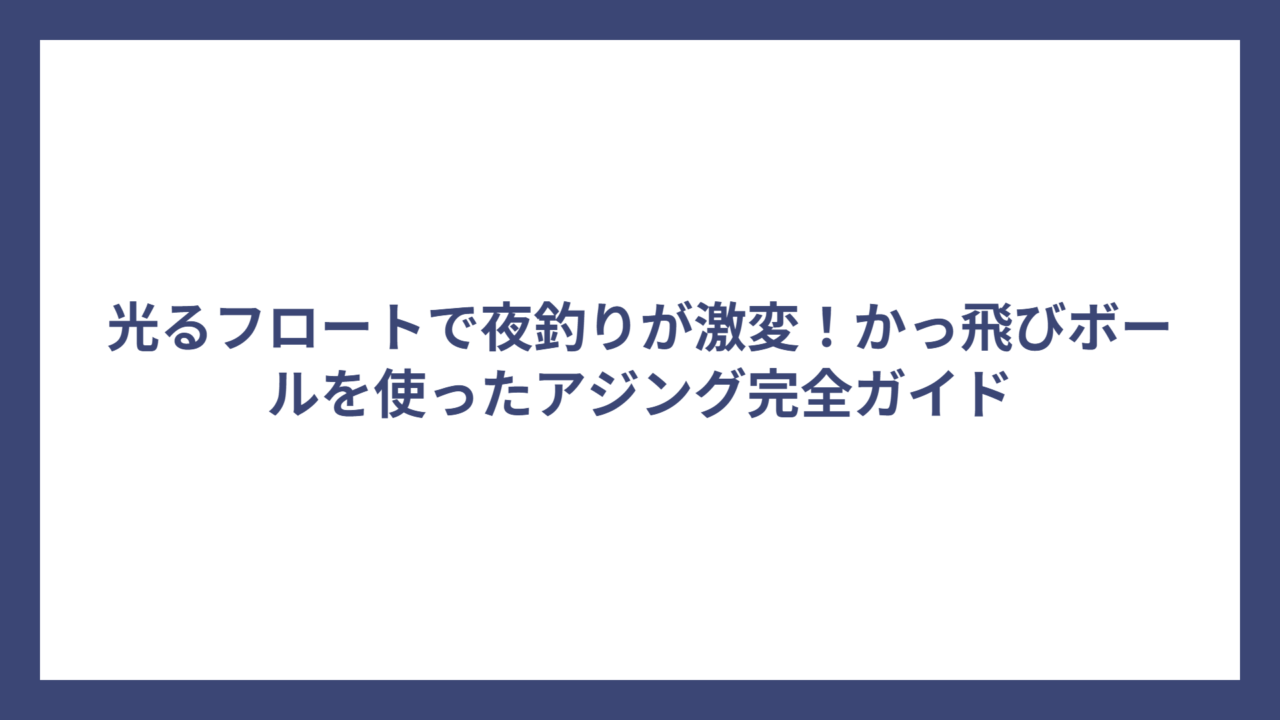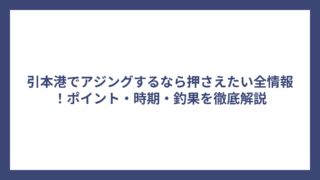アジングで「フロートを使ってみたいけど、暗闇でどこにあるかわからない」という悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。そんな悩みを一気に解決してくれるのが、ハピソンから発売されているLED発光フロートリグ「かっ飛びボール」です。一般的なフロートリグは蓄光やケミホタルで光らせますが、かっ飛びボールは高輝度LEDで発光するため、フルキャスト先でも目視できる圧倒的な視認性を誇ります。
本記事では、インターネット上に散らばるかっ飛びボールに関する情報を収集・整理し、製品の特徴から実際の使い方、実釣インプレッションまで網羅的にご紹介します。「どのタイプを選べばいいの?」「仕掛けの組み方は?」「実際に釣れるの?」といった疑問に、独自の分析と考察を交えながらお答えしていきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ かっ飛びボールの圧倒的な視認性とLED発光の仕組み |
| ✓ 中通しタイプとカン付きタイプの選び方と使い分け |
| ✓ 4種類の沈下速度別モデルの特徴と適した状況 |
| ✓ 実際の釣行での使用感と釣果実績 |
かっ飛びボールで変わるアジングの世界
- かっ飛びボールがアジングで人気の理由はLED発光による圧倒的な視認性
- かっ飛びボールの種類は中通しとカン付きの2タイプから選べる
- かっ飛びボールの浮力は4段階の沈下速度で使い分けられる
- ハピソンかっ飛びボールのスペックと製品ラインナップ
- かっ飛びボールSPは表層狙いに最適なサスペンドタイプ
- かっ飛びボールSSはゆっくり沈むスローシンキング
かっ飛びボールがアジングで人気の理由はLED発光による圧倒的な視認性
かっ飛びボールが関西地方で爆発的にヒットした背景には、夜釣りにおける「見えない」という根本的な問題を解決した点にあります。従来のフロートリグでは、蓄光塗料やケミホタルを使用しても、フルキャストした先では視認性が不十分でした。特に潮の流れが速い場所や、障害物周りを攻める際には、フロートの位置が把握できず釣りにならないという声が多くありました。
チップ型高輝度LED×2個を搭載したかっ飛びボールは、この問題を根本から解決しました。実際の使用者からは「ケミホタルダブルでも見失うことがあったが、かっ飛びボールなら暗闇でもきちんと目視できる」という評価が寄せられています。LED発光の明るさは、写真では伝わりにくいものの、実際に使用すると着水から沈下まで常に位置を把握できるレベルです。
暗闇でも視認性がよいLED発光システムを内包した飛ばしウキ。この視認性の高さは大きな武器になります。シモリのサイドや障害物ギリギリを暗闇でも的確にトレースできたり、潮の状況、ルアーの沈み具合などを明るさから確認できたりします。
この引用からもわかるように、視認性の高さは単に「見える」だけではなく、釣りの精度を大幅に向上させる効果があります。障害物ギリギリを攻められることで、今まで届かなかったポイントを狙えるようになり、結果として釣果アップにつながるのです。
さらに注目すべきは、初心者でも扱いやすいという点です。フロートリグはジグ単に比べて難易度が高いと思われがちですが、かっ飛びボールなら目で見てフロートの動きを確認できるため、ウキ釣り感覚で楽しめます。実際に「特に、初心者に釣りをしていただくときに、ご好評を頂いています」という開発者のコメントもあり、入門者向けアイテムとしても優れていることがわかります。
加えて、アタリの取り方も多様化します。手元に伝わらない微細なアタリでも、フロートの動きで視覚的に捉えられるため、合わせのタイミングを逃しません。通常のフロートリグでは気づけなかったアタリも、LED発光によって明確に見えるため、釣果が向上する可能性が高まります。
このように、かっ飛びボールの人気の理由は単なる「光る」という機能だけでなく、釣りの質そのものを変える革新性にあると言えるでしょう。一度使うとリピーターが続出するというのも、この圧倒的な使い勝手の良さが評価されている証拠です。
かっ飛びボールの種類は中通しとカン付きの2タイプから選べる
かっ飛びボールには中通しタイプとカン付きタイプの2種類が用意されており、それぞれに明確な使い分けがあります。釣り方やシチュエーションに応じて選択することで、より効率的なアジングが可能になります。
📌 かっ飛びボールの2タイプ比較表
| 項目 | 中通しタイプ | カン付きタイプ |
|---|---|---|
| 構造 | ラインが本体を貫通 | スナップでカンに装着 |
| 交換性 | やや手間 | 素早く交換可能 |
| 感度 | 高感度 | やや劣る |
| トラブル | 少ない | スナップ部分に注意 |
| 適した場面 | じっくり探る釣り | タイプを頻繁に変える釣り |
中通しタイプは、ラインがフロート本体を貫通する構造で、一般的なキャロライナリグと同じ仕組みです。リーダーにかっ飛びボールを通し、スイベルで止め、その先にハリスとルアーを結ぶだけのシンプルな仕掛けです。メリットとしては、感度が高く、ライントラブルが少ない点が挙げられます。フロートが直接ラインに接触しないため、魚のアタリがダイレクトに伝わりやすく、繊細なアジングに適しています。
一方で、沈下速度の異なるモデルに変更する際には、一度仕掛けを解く必要があるため、交換にやや手間がかかるのがデメリットです。ただし、状況が安定していて頻繁に交換する必要がない場合は、中通しタイプの方がストレスなく釣りを続けられるでしょう。
カン付きタイプは、フロート本体にカン(金具)が付いており、スナップで簡単に着脱できる構造です。最大のメリットは交換の速さで、状況に応じて素早くタイプを変更できます。例えば、表層で反応がなければサスペンドからファストシンキングに変更するなど、臨機応変な対応が可能です。
実際の使用者からは「カン付きタイプを多用する」という声もあり、特に試行錯誤しながら最適なレンジを探る釣りに向いています。デメリットとしては、スナップ部分が若干弱点になる可能性があることや、中通しに比べてやや感度が劣る点が挙げられますが、実釣上大きな問題にはならないでしょう。
どちらを選ぶべきかは釣りスタイル次第です。「一つのタイプで粘り強く探りたい」なら中通し、「状況に応じて柔軟に対応したい」ならカン付きがおすすめです。両方揃えておいて使い分けるのも一つの手段と言えます。
また、仕掛けの組み方については、中通しタイプはTICTのMキャロ用スイベルとクッションゴムのセット商品を使うと手っ取り早く組めます。カン付きタイプはジャングルジムのキャロ・フロートスイベルを使えば、ラインを切らずにかっ飛びボールを交換できるため、さらに利便性が向上します。
かっ飛びボールの浮力は4段階の沈下速度で使い分けられる
かっ飛びボールは**サスペンド(SP)、スローシンキング(SS)、ファストシンキング(FS)、エクストラシンキング(XS)**の4種類の沈下速度が用意されており、それぞれ重量が異なります。これらを使い分けることで、アジの活性やレンジに応じた効果的なアプローチが可能になります。
🎣 かっ飛びボール沈下速度別スペック表
| タイプ | 重量 | 沈下特性 | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| SP(サスペンド) | 4.6g | ほぼ浮力中性 | 表層~中層をゆっくり探る |
| SS(スローシンキング) | 5.5g | ゆっくり沈む | 中層をじっくり攻略 |
| FS(ファストシンキング) | 6.0g | 比較的速く沈む | 深場や速い潮流 |
| XS(エクストラシンキング) | 7.5g | 最も速く沈む | ボトム付近や遠投 |
サスペンド(SP)タイプは、水中でほぼ浮力が中性になるため、表層付近をゆっくりと流す釣りに最適です。アミパターンなど、プランクトン系を捕食しているアジに対して、ワームを自然に漂わせたい時に効果的です。ある使用者は「比較的浅場をゆっくりと潮になじませるように流したい」という理由でサスペンドを選択し、実際に好釣果を得ています。
メバリングでも、活性が高く表層に浮いているメバルを狙う際には、サスペンドが推奨されています。着底させずに表層~中層を長時間キープできるため、ターゲットが浮いている状況では非常に有効です。
スローシンキング(SS)タイプは、ゆっくりと沈んでいくため、中層を丁寧に探りたい時に適しています。表層で反応がない時や、少し深いレンジにアジが溜まっている時に効果を発揮します。ある釣行記では「レンジを替えて狙うならSSがもってこいです」と評価されており、レンジ調整の自由度が高い点が魅力です。
沈下速度がゆっくりなため、アジにじっくりとアピールできるのもメリットです。活性が低い時や、プレッシャーが高いポイントでは、スローシンキングのゆったりとしたフォールが功を奏することもあります。
ファストシンキング(FS)タイプは、比較的速く沈むため、深場や潮流が速い場所で活躍します。表層~中層では反応がなく、ボトム付近を探りたい時や、遠投して沖の深いエリアを攻略したい時に選択します。アジングでは「表層から底付近まで広い層を探るため、ファストシンキングモデルがおすすめ」とされており、レンジの幅を広げたい時に有効です。
エクストラシンキング(XS)タイプは最も重く、最速で沈下するタイプです。遠投性能が高く、沖の深いポイントや、ボトム付近を重点的に攻めたい時に使用します。ただし、根掛かりのリスクが上がるため、ボトムの状況を把握した上で使用することが推奨されます。
どのタイプを選ぶかは、その日のアジの活性とレンジ次第です。まずはサスペンドやスローシンキングで表層~中層を探り、反応がなければファストシンキングやエクストラシンキングで深いレンジを攻めるという順序が、一般的には効率的でしょう。
ハピソンかっ飛びボールのスペックと製品ラインナップ
ハピソン(山田電器工業株式会社)は、パナソニックで培われた釣具事業のノウハウを引き継ぎ、電気ウキやライトアイテムに強みを持つメーカーです。かっ飛びボールは、その技術力を結集した代表的な製品と言えます。
📦 かっ飛びボール基本スペック一覧
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー | 山田電器工業株式会社(ハピソン) |
| 対象魚 | アジ、メバル、タチウオほか |
| 発光部 | チップ型高輝度LED×2個 |
| 使用電池 | リチウム電池BR311×2個 |
| 電池寿命 | 連続約6時間 |
| カラー展開 | ブルー、グリーン、レッド |
| サイズ | φ20×27.5mm(SP/SS/FS)、φ20×30mm(XS) |
| 価格 | オープン価格(実売1,400~1,800円程度) |
全ラインナップは4種類の沈下速度×3色=12アイテムとなっており、さらに中通しタイプとカン付きタイプを合わせると、合計24種類の選択肢があります。これだけのバリエーションがあれば、あらゆる状況に対応できると言えるでしょう。
電池のBR311は3V型のピン形リチウム電池で、やや特殊な規格のため、釣具店やネット通販で事前に購入しておくことをおすすめします。電池寿命は連続約6時間とされていますが、実際の使用では点灯・消灯を繰り返すため、もう少し長持ちする可能性もあります。
一方で、「電池の交換がイマイチ」「電池挿入部が割れた」といったレビューも散見されるため、電池交換時は慎重に扱う必要がありそうです。特に、電池交換の際にボディをひねる必要があるため、滑りやすく力が入りにくいという声もあります。この点は改善の余地があるかもしれません。
また、防水性能についても注意が必要です。「数回使うと海水が入って使いものにならなくなる」というレビューがあり、コストパフォーマンスの面で不満を持つユーザーもいます。おそらく、Oリングの締め込みが不十分だったり、経年劣化で防水性能が低下したりすることが原因と推測されます。使用後はしっかりと真水で洗浄し、Oリング部分を定期的にチェックすることで、寿命を延ばせるかもしれません。
価格については、一般的なフロートリグに比べるとやや高めですが、LED発光による視認性の向上を考えれば、妥当な価格設定と言えます。ただし、「中華の安いのがいいな」という意見もあり、コストを重視する方にとっては悩ましいところでしょう。
製品の耐久性については賛否両論ありますが、「視認性抜群」「フロートとしてかなり良い」という高評価も多く、一度使うとその利便性からリピーターが続出するという開発者のコメント通り、多くのユーザーに支持されていることは間違いありません。
かっ飛びボールSPは表層狙いに最適なサスペンドタイプ
**かっ飛びボールSP(サスペンド)**は、重量4.6gで水中でほぼ浮力が中性になるタイプです。このタイプが特に威力を発揮するのは、表層付近にアジやメバルが浮いている状況です。
サスペンドタイプの最大の特徴は、一定のレンジをキープしやすい点にあります。沈みすぎず、浮きすぎず、潮の流れに乗せてワームを自然に漂わせることができるため、警戒心の強いアジに対しても違和感を与えにくいのです。
ある釣行記では、かっ飛びボールSPを使用して「アミなどプランクトン系を捕食しているアジに対して、水中を自然に漂っているワームを違和感なくバイトしてほしい」という目的で選択されています。結果として、15~16cmのマアジを7匹釣り上げており、狙い通りの釣果を得ています。
仕掛けは先日までタチウオ釣りで使っていたかっ飛びボールを使ったフロートリグを試してみます。かっ飛びボールを使うと20〜30mぐらいは飛ぶし、LEDの明かりのおかげで飛んでいく方向も分かりとても便利です。
この引用からもわかるように、飛距離が20~30m程度確保できる点も見逃せません。ジグ単では届かない沖のポイントを狙えるため、プレッシャーの低いエリアにいるアジにアプローチできるのです。
また、サスペンドタイプは風や潮の影響を受けやすいという特性もあります。これは一見デメリットのように思えますが、逆に言えば潮に乗せてナチュラルにドリフトさせることができるため、アジの捕食パターンに合わせやすいとも言えます。
メバリングでも、サスペンドタイプは高評価を得ています。「メバルは活性が上がると浅いタナに浮くため、サスペンドかスローシンキングが最適」とされており、表層を意識したゲームでは必須のアイテムと言えるでしょう。
使い方のコツとしては、キャスト後しばらく放置して潮に乗せることが重要です。すぐに巻き始めるのではなく、フロートの動きを見ながらアジの回遊を待つイメージです。LEDで位置が明確にわかるため、この「待ちの釣り」がやりやすいのも、かっ飛びボールSPの大きなメリットです。
かっ飛びボールSSはゆっくり沈むスローシンキング
**かっ飛びボールSS(スローシンキング)**は、重量5.5gでゆっくりと沈下していくタイプです。サスペンドでは反応がない時や、やや深めのレンジを丁寧に探りたい時に効果を発揮します。
スローシンキングの利点は、フォール中にもアピールできる点にあります。アジは落ちてくるベイトに反応することが多いため、ゆっくりとしたフォールは非常に効果的です。特に活性が低い時や、レンジが定まらない時には、スローシンキングで広範囲を探ることが有効でしょう。
実際の使用例では、「レンジを替えて狙うならSSがもってこいです。どこにルアーがあるのか分かるので、夜釣りには持ってこいです」という評価があります。このレンジ調整の自由度の高さが、スローシンキングの最大の魅力と言えます。
また、スローシンキングはリトリーブとフォールの組み合わせが効果的です。一定距離巻いて止め、フォールさせるという繰り返しにより、アジにリアクションバイトを誘発できます。このような使い方は、サスペンドタイプでは難しいため、スローシンキングならではの戦術と言えるでしょう。
メバリングにおいても、スローシンキングは推奨されています。メバルは表層だけでなく、中層にも溜まることがあるため、「サスペンドかスローシンキングが最適」とされています。特に、風が強い日や潮が速い日には、サスペンドでは流されすぎてコントロールが難しくなるため、やや重いスローシンキングが扱いやすい場合もあります。
重量が5.5gと比較的軽いため、タックルへの負担も少なく、アジングロッドで快適にキャストできます。ただし、遠投性能はファストシンキングやエクストラシンキングに劣るため、飛距離を重視する場合は別のタイプを選択した方が良いかもしれません。
総じて、スローシンキングはオールラウンドに使えるバランス型と言えます。初めてかっ飛びボールを購入する方は、サスペンドかスローシンキングのどちらかを選んでおけば、多くの状況に対応できるでしょう。
かっ飛びボールを使いこなすための実践ガイド
- かっ飛びボールの使い方は一般的なフロートリグと同じ要領
- かっ飛びボールの仕掛けはシンプルで初心者でも簡単
- かっ飛びボールの電池交換と連続使用時間について
- かっ飛びボールのカラー選択は緑が視認性抜群
- かっ飛びボールの実釣インプレッション集
- かっ飛びボールヘビーや他バリエーションの展開
- まとめ:かっ飛びボールでアジングをもっと楽しく快適に
かっ飛びボールの使い方は一般的なフロートリグと同じ要領
かっ飛びボールの使い方は、基本的には一般的なフロートリグと全く同じです。LED発光という特殊な機能がありますが、操作方法自体は通常のフロートと変わりません。そのため、フロートリグの経験がある方なら、すぐに使いこなせるでしょう。
🎣 かっ飛びボール基本の使い方手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① キャスト | 目標地点に向けてフルキャスト |
| ② 着水確認 | LED発光で位置を確認 |
| ③ 沈下待ち | 狙いのレンジまで沈むのを待つ |
| ④ リトリーブ | 一定速度で巻くor潮に乗せてドリフト |
| ⑤ アタリ確認 | フロートの動きで目視+手元の感触 |
まず、キャストの際は通常のフロートリグと同様に投げるだけです。重量が4.6g~7.5gあるため、ジグ単に比べて格段に飛距離が出ます。20~30mは確実に飛ぶため、沖のポイントも狙えます。
着水後は、LEDの光で位置を確認します。ここがかっ飛びボール最大の利点で、真っ暗な海でもフロートの位置が一目瞭然です。通常のフロートでは「どこに着水したかわからない」ということがありますが、かっ飛びボールならその心配は無用です。
次に、狙いのレンジまで沈むのを待ちます。サスペンドなら表層キープ、スローシンキングなら数秒待って中層、ファストシンキング以上ならさらに長く待ってボトム付近を狙うという具合です。LED発光により、沈んでいく様子も目視できるため、「今どのくらいの深さにいるか」が感覚的にわかります。
リトリーブは、一定速度で巻く方法と、潮に乗せてドリフトさせる方法があります。アジングでは後者が効果的なことが多く、ある釣行記でも「潮に乗せて流してやるとコツッと本日の初アタリがありました」と報告されています。ドリフトさせる際も、LEDで位置がわかるため、フロートとティップを真っ直ぐに保ちやすく、アタリを逃しにくいのです。
アタリの確認は、目視と手元の感触の両方で行います。フロートが「ピクッ」と動いたり、横に流れたりする動きは、手元に伝わらない微細なアタリの可能性があります。通常のフロートではこのような動きを見逃しがちですが、かっ飛びボールなら明確に視認できるため、合わせのチャンスが増えるのです。
また、障害物周りを攻める際も、LED発光は大きな武器になります。シモリのサイドやテトラのキワなど、根掛かりリスクの高い場所でも、フロートの位置を常に把握できるため、ギリギリまで攻めることができます。これは通常のフロートでは難しい芸当です。
初心者の方には、「ウキ釣りの感覚で楽しめる」という点も大きなメリットです。フロートリグは本来テクニカルな釣りですが、かっ飛びボールなら目で見て状況を把握できるため、ルアー釣り未経験者でも取っつきやすいと言えるでしょう。
かっ飛びボールの仕掛けはシンプルで初心者でも簡単
かっ飛びボールの仕掛けは非常にシンプルで、初心者でも5分あれば組めるレベルです。中通しタイプとカン付きタイプで若干異なりますが、基本的な考え方は同じです。
🔧 中通しタイプの仕掛け構成
- ✅ メインライン(PEライン0.3~0.6号程度)
- ✅ ショックリーダー(フロロカーボン4~6lb)
- ✅ かっ飛びボール(中通し)
- ✅ クッションゴム
- ✅ スイベル
- ✅ ハリス(フロロカーボン3~5lb、30~50cm)
- ✅ ジグヘッド+ワーム
中通しタイプの組み方は以下の通りです。
- メインラインとショックリーダーを結束(FGノットやPRノット推奨)
- リーダーにかっ飛びボール(中通し)を通す
- クッションゴムをリーダーに通す
- スイベルをリーダーに結ぶ
- スイベルのもう一方にハリスを結ぶ
- ハリスの先端にジグヘッドを結ぶ
- ジグヘッドにワームをセット
この仕掛けでは、クッションゴムとスイベルがストッパーの役割を果たします。ティクトのMキャロ用スイベルには、クッションゴムがセットになっているため、これを使えばパーツを別々に揃える手間が省けます。
ハリスの長さは30~50cm程度が標準ですが、状況に応じて調整します。ハリスが長いほどワームの動きが自然になりますが、遠投時に絡みやすくなるため、バランスを取ることが重要です。
🔧 カン付きタイプの仕掛け構成
- ✅ メインライン
- ✅ ショックリーダー
- ✅ スナップ or キャロ・フロートスイベル
- ✅ かっ飛びボール(カン付き)
- ✅ スイベル
- ✅ ハリス
- ✅ ジグヘッド+ワーム
カン付きタイプは、スナップでカンに装着するだけなので、さらに簡単です。ジャングルジムのキャロ・フロートスイベルを使えば、リーダーを切らずにかっ飛びボールを交換できるため、現場での対応がスムーズになります。
仕掛けを組む際の注意点として、リーダーノットはしっかり組むことが挙げられます。フロートリグはキャスト時に大きな負荷がかかるため、ノットが甘いと切れてしまいます。FGノットやPRノットなど、強度の高い結び方を推奨します。
また、スイベルは必ず使用しましょう。スイベルがないとラインがよじれてトラブルの原因になります。特にかっ飛びボールは回転しやすい形状のため、スイベルの有無で快適さが大きく変わります。
ワームは、アジングの定番であるピンテール系やシャッド系が一般的です。ある釣行記では「アジリンガー(レイン)」が使用されており、好釣果を得ています。ワームサイズは1.5~2インチ程度が標準で、ジグヘッドは0.6~1.5g程度が使いやすいでしょう。
仕掛けの組み方自体はシンプルですが、各パーツの選択と調整が釣果に影響します。最初は標準的な構成から始めて、釣りをしながら自分なりのセッティングを見つけていくのが良いでしょう。
かっ飛びボールの電池交換と連続使用時間について
かっ飛びボールの電池はピン形リチウム電池BR311を2個使用し、連続点灯時間は約6時間とされています。ただし、実際の釣行では常に点灯しているわけではないため、使用方法次第でもっと長持ちする可能性があります。
🔋 かっ飛びボール電池情報まとめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 電池規格 | BR311(3V型ピン形リチウム電池) |
| 使用個数 | 2個 |
| 連続点灯時間 | 約6時間 |
| 入手先 | 釣具店、ネット通販 |
| 価格 | 2個セットで500~600円程度 |
| 交換頻度 | 使用時間による(おそらく数回の釣行で交換) |
BR311はやや特殊な規格のため、コンビニやホームセンターでは入手しにくいかもしれません。事前に釣具店やAmazon、楽天などのネット通販で購入しておくことをおすすめします。製品にはテスト用の電池が同梱されていますが、連続使用時間が短い可能性があるため、予備を持っておくと安心です。
電池交換の方法は、本体をひねって開ける構造になっています。ただし、レビューでは「滑って回しにくい」「電池が小さくて交換しづらい」といった声があり、やや扱いにくいという評価もあります。おそらく、濡れた手や冬場の冷たい手では、さらに開けにくくなるでしょう。
また、「電池を入れる時にすでに接触不良」「電池の差し込みが甘いためついたり消えたり」といった不具合報告もあります。これは電池の接触部分の精度に個体差がある可能性を示唆しています。購入後は、使用前に必ず点灯確認をしておくことが重要です。
防水性についても注意が必要です。電池交換のたびにOリング部分を開け閉めするため、締め込みが甘いと海水が浸入してしまいます。「数回使うと海水が入って使いものにならなくなる」というレビューもあるため、使用後は真水で洗浄し、Oリング部分のゴミを取り除いておくことが寿命を延ばすコツと言えます。
電池の持ちについては、一般的には2~3回の釣行で交換という頻度になるかもしれません。1回の釣行が3~4時間として、連続点灯が6時間なら、単純計算で2回分です。ただし、実際にはキャスト時のみ点灯し、手元に戻ってきたら消灯するという使い方もできるため、工夫次第でもっと長持ちさせることは可能でしょう。
電池寿命を延ばすコツとしては、使わない時は必ず消灯することが基本です。また、保管時も電池を抜いておくことで、微弱な放電を防げるかもしれません。ただし、電池の抜き差しが頻繁になると接触不良のリスクが上がるため、バランスが難しいところです。
一部のユーザーからは「電池の持ちが非常に悪く、2時間ほど使用した後、外しておき、翌週使うと点灯しなかった」という報告もあります。これが電池の消耗なのか接触不良なのかは不明ですが、長期間使わない場合は電池を抜いておく方が安全かもしれません。
総じて、電池周りはかっ飛びボールの数少ない弱点と言えます。メーカー側も改善の余地があると考えられますが、現状では使用者側が注意深く扱うことで、ある程度のトラブルは防げるでしょう。
かっ飛びボールのカラー選択は緑が視認性抜群
かっ飛びボールはブルー、グリーン、レッドの3色が用意されていますが、視認性という観点ではグリーン(緑)が最も見やすいとされています。多くの使用者がグリーンを選択しており、実釣でも高い評価を得ています。
🎨 かっ飛びボールカラー別特性表
| カラー | 視認性 | 特性・用途 |
|---|---|---|
| グリーン | ★★★ | 最も視認性が高い、迷ったらこれ |
| ブルー | ★★☆ | 魚が興味を持ちやすく集魚効果 |
| レッド | ★☆☆ | 魚に目立ちにくい、スレ対策 |
**グリーン(緑)**は、人間の目が最も感度が高い波長域にあるため、暗闇でも非常に見やすい色です。実際に使用したユーザーからは「緑が見易いと思いますよ」「視認性抜群」といったコメントが多数寄せられています。初めてかっ飛びボールを購入する方や、視認性を最優先する方には、グリーンが最もおすすめです。
ただし、視認性が高いということは、魚からも見えやすいという可能性もあります。プレッシャーの高いポイントでは、グリーンの光がアジを警戒させるのではないかという懸念もあるかもしれません。しかし、実際の釣果報告を見る限り、グリーンでも十分に釣れているため、過度に心配する必要はなさそうです。
**ブルー(青)**は、「魚が興味を持ちやすく集魚効果のある光の波長」とされています。集魚灯などでもブルー系の光が使われることが多く、アジを引き寄せる効果が期待できるかもしれません。視認性はグリーンに劣りますが、十分に見える範囲です。
ブルーを選択する理由としては、集魚と視認性のバランスを取りたい場合が考えられます。アジの活性が低く、少しでも寄せたいという状況では、ブルーが効果的かもしれません。ただし、これは推測の域を出ませんので、実際に試してみて判断する必要があるでしょう。
**レッド(赤)**は、「魚に目立ちにくい」という特性があります。赤色光は水中で減衰しやすいため、人間には見えても魚には見えにくいとされています。そのため、プレッシャーの高いポイントや、スレたアジを狙う際には、レッドが有効かもしれません。
ただし、視認性は3色の中で最も低いため、遠投した際に見失うリスクがあります。ある程度目の良さに自信がある方や、近距離での使用が中心の方には問題ありませんが、初心者にはやや扱いにくいかもしれません。
カラー選択についての結論としては、迷ったらグリーン一択です。視認性が最も高く、実釣でも問題なく釣れているため、最も安全な選択と言えます。慣れてきたら、状況に応じてブルーやレッドも試してみると、新たな発見があるかもしれません。
また、複数のカラーを揃えておいて、日によって使い分けるのも一つの戦略です。例えば、月明かりのある夜はレッド、新月の真っ暗な夜はグリーン、といった具合です。ただし、これらは一般的な傾向であり、絶対的なルールではありません。最終的には、自分の目で見やすく、釣果が上がるカラーを選ぶのが正解です。
かっ飛びボールの実釣インプレッション集
ここでは、実際にかっ飛びボールを使用した方々のインプレッションをご紹介します。良い点も悪い点も含めて、リアルな使用感を知ることで、購入の参考になるでしょう。
📝 実釣インプレッション①:加古川エリアでのアジング
仕掛けは先日までタチウオ釣りで使っていたかっ飛びボールを使ったフロートリグを試してみます。かっ飛びボールを使うと20〜30mぐらいは飛ぶし、LEDの明かりのおかげで飛んでいく方向も分かりとても便利です。
このインプレッションでは、飛距離と視認性が高く評価されています。実際に20~30mの飛距離が出ており、ジグ単では届かないポイントを攻略できたことがわかります。結果として15~16cmのマアジを7匹釣り上げており、釣果にも直結しています。
特筆すべきは、「表層ではアタリは無いので少し沈めて仕掛けを潮に乗せて流してやるとコツッと本日の初アタリがありました」という部分です。これは、LED発光によってレンジ調整が容易であることを示しています。通常のフロートでは「今どのレンジにいるか」がわかりにくいですが、かっ飛びボールなら目視で確認できるため、試行錯誤がしやすいのです。
📝 実釣インプレッション②:視認性の高さを実感
使用者からは「とにかく明るい!!」「ケミホタルダブルでも見失うことがあったが、かっ飛びボールなら暗闇でもきちんと目視できる」という声が寄せられています。実際に比較検証した記事では、ケミホタルをダブルでセットしたメバルロケットと並べて撮影したところ、圧倒的にかっ飛びボールの方が明るいという結果になっています。
この明るさにより、「フルキャスト先でも着水~沈下まで、暗闇でもきちんと目視できる」という利点があります。初心者でもフロートの位置を見失わず、安心して釣りに集中できるのは大きなメリットです。
📝 実釣インプレッション③:初心者への優しさ
開発者のコメントとして「特に、初心者に釣りをしていただくときに、ご好評を頂いています」という言葉があります。実際に、フロートリグ初心者の方からは「暗闇でフロートがどこにあって、どっちに流されて、どのくらい沈んでいるのかよくわからない難しいものというイメージでしたが、この【かっ飛び!ボール】は視認性抜群なので、夜間でも操作感を失うことなく、アジングを楽しむことができそうです」という感想が寄せられています。
このように、ルアー釣り未経験者やフロートリグ初心者にとって、かっ飛びボールは非常に取っつきやすいアイテムと言えます。ウキ釣りの感覚で楽しめるため、エサ釣りからルアー釣りに移行したい方にもおすすめです。
📝 実釣インプレッション④:タチウオ釣りでも大活躍
かっ飛びボールは、アジングだけでなくタチウオ釣りでも大ヒットしています。「かっ飛びボールが大ヒットするきっかけとなったのが、タチウオ釣りです」とされており、関西地方で爆発的に売れた要因の一つになっています。
タチウオ釣りでは、かっ飛びボールの先に市販のタチウオ仕掛けを結ぶだけで楽しめます。「ゆっくりと沈めながら広いタナを探る、沈め探り釣りがおすすめ」とされており、アジング以外の釣りにも応用できる汎用性の高さがわかります。
📝 実釣インプレッション⑤:ネガティブな意見も
一方で、ネガティブな意見も存在します。「数回使うと海水が入って使いものにならなくなる割にクソ高いのでコスパは最悪です」「電池の交換がイマイチ」「届いて試しに電池を入れて点灯した後、電池を抜こうとしたら電池挿入部が割れていました」といったレビューがあり、耐久性や電池周りの問題が指摘されています。
これらの意見は無視できないものの、「視認性抜群」「釣れる」という高評価が多数を占めているため、全体としてはメリットがデメリットを上回っていると考えられます。ただし、購入時には初期不良がないか確認し、使用後のメンテナンスを怠らないことが重要でしょう。
かっ飛びボールヘビーや他バリエーションの展開
かっ飛びボールシリーズには、通常モデル以外にもかっ飛びHEAVYやかっ飛び太刀リグセットなど、複数のバリエーションが展開されています。これらは特定の釣りに特化したモデルで、用途に応じて選択できます。
🎣 かっ飛びシリーズ関連商品一覧
| 商品名 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| かっ飛びボール | LED発光フロートリグ | アジング・メバリング |
| かっ飛びHEAVY | より重いモデル | 遠投や深場攻略 |
| かっ飛び太刀リグセット | タチウオ専用セット | タチウオ釣り |
| タチフロート用かっ飛びHEAVY | タチウオ用重量級 | タチウオの遠投 |
| 太刀リグワーム | タチウオ専用ワーム | タチウオ釣り |
かっ飛びHEAVYは、通常のかっ飛びボールよりも重量があるモデルと推測されます。おそらく、さらなる飛距離を求める場合や、深場を攻略したい場合に適していると考えられます。ただし、具体的なスペックについては提供された情報に詳細がないため、メーカーHPや釣具店で確認する必要があるでしょう。
かっ飛び太刀リグセットは、タチウオ釣り専用のセット商品です。かっ飛びボールとタチウオ仕掛けが一体になっており、初めてタチウオをルアータックルで狙う方には便利なアイテムです。タチウオ釣りでは「かっ飛びボールの先に市販のタチウオ仕掛けを結ぶだけで楽しめます」とされているため、このセット商品を使えばすぐに釣りを始められるでしょう。
また、タチフロート用かっ飛びHEAVYは、タチウオ専用のさらに重いモデルと考えられます。タチウオは遠投が必要な釣りであり、重量のあるフロートが有利です。通常のかっ飛びボールでも十分ですが、より遠くを攻めたい場合はこちらを選択すると良いかもしれません。
これらのバリエーション展開は、かっ飛びボールシリーズが多様な釣りに対応できることを示しています。アジングやメバリングだけでなく、タチウオやその他のターゲットにも応用できるため、一つ持っておけば様々な釣りに流用できるでしょう。
また、将来的にはさらなる新製品が登場する可能性もあります。例えば、青物用のさらに重いモデルや、より長時間点灯できる省エネモデルなど、ユーザーのニーズに応じた商品開発が期待されます。
かっ飛びボールの自作についても触れておくと、LED発光部分を自作するのは技術的に難しいため、市販品を購入するのが現実的です。ただし、通常のフロートにLEDライトを取り付けるといったDIYは可能かもしれませんが、防水性や重量バランスを考えると、やはり専用設計されたかっ飛びボールに軍配が上がるでしょう。
まとめ:かっ飛びボールでアジングをもっと楽しく快適に
最後に記事のポイントをまとめます。
- かっ飛びボールは高輝度LED×2個を搭載した発光フロートリグで、暗闇でも圧倒的な視認性を誇る
- 中通しタイプとカン付きタイプの2種類があり、釣りスタイルに応じて選択できる
- サスペンド、スローシンキング、ファストシンキング、エクストラシンキングの4段階の沈下速度で多様なレンジに対応
- ハピソン製で電池はBR311を2個使用し、連続約6時間の点灯が可能
- カラーはブルー、グリーン、レッドの3色で、グリーンが最も視認性が高い
- 使い方は一般的なフロートリグと同じで、初心者でもウキ釣り感覚で楽しめる
- 仕掛けはシンプルで5分程度で組め、専用のスイベルやクッションゴムを使うとさらに簡単
- 実釣では20~30mの飛距離が出て、ジグ単では届かないポイントを攻略できる
- LED発光により障害物周りを的確にトレースでき、アタリも目視で確認できる
- アジングだけでなくメバリングやタチウオ釣りにも対応し、汎用性が高い
- 電池交換がやや面倒で、防水性に注意が必要という弱点もある
- 価格はやや高めだが、視認性と使い勝手の良さからリピーターが続出している
- 初心者からベテランまで幅広く支持されており、夜釣りの必携アイテムとなっている
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- かっ飛びボール – Hapyson
- かっ飛びボールアジング – 神戸界隈での釣り日記
- アジングやメバリングに有効! 闇夜でも「見える」飛ばしウキ【かっ飛びボール(ハピソン)】
- 【大流行の予感】夜釣りには「かっ飛びボール」を絶対もっていこう! | TSURI HACK[釣りハック]
- Amazon | ハピソン(Hapyson) YF-300-G かっ飛びボール サスペンド グリーン
- 爆光フロート×ハピソンの【かっ飛び!ボール】購入レビュー | TULINKUBLOG
- かっ飛びボールで見えるフロートメバリング|初心者におすすめです!
- ハピソン かっ飛びボールのおすすめ人気商品一覧 通販 – Yahoo!ショッピング
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。