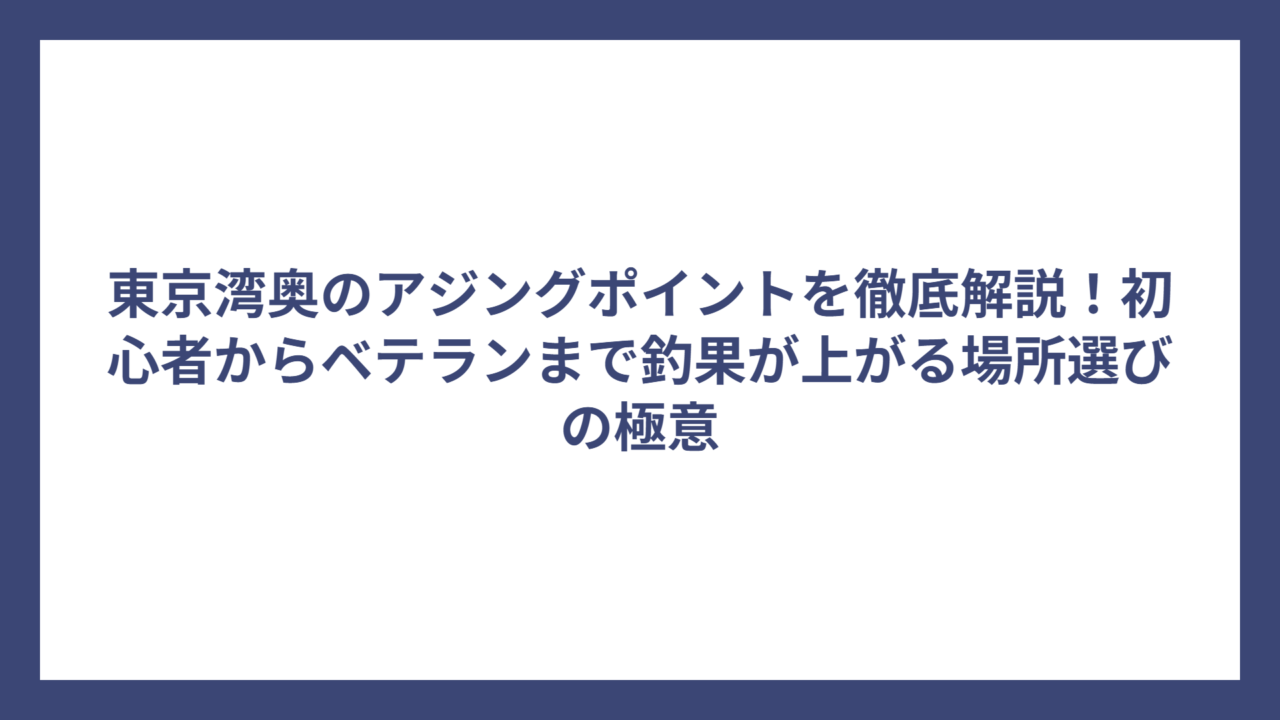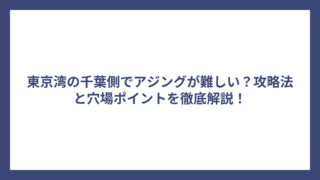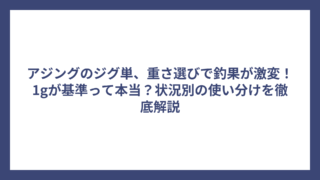東京湾奥でアジングを楽しみたいけれど、どこで竿を出せばいいのか迷っていませんか?都心からアクセスしやすい東京湾奥エリアは、実はアジングのポテンシャルが非常に高い釣り場なんです。ただし、外房や南房といった本格的なアジングフィールドとは異なる攻略法が求められるため、湾奥特有の特徴を理解することが釣果アップの鍵となります。
本記事では、東京湾奥におけるアジングの有望ポイントから、季節ごとの狙い方、タックル選び、さらには釣れる条件まで、インターネット上に散らばる情報を収集・分析し、独自の視点で解説していきます。横浜エリアから川崎、東京都内まで、幅広いエリアの情報を網羅していますので、ぜひ最後までお読みください。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 東京湾奥で実績のあるアジングポイント15箇所以上を具体的に紹介 |
| ✓ 湾奥特有の攻略法と外房との違いを明確に解説 |
| ✓ 季節ごとの釣れるタイミングと条件を詳しく説明 |
| ✓ 初心者でも釣果を上げやすいポイントの特徴を分析 |
東京湾奥アジングの実績ポイントと特徴を徹底解説
- 東京湾奥でアジングができる有望ポイントは横浜・川崎エリアに集中している
- 湾奥アジングは「投げない」「足元狙い」が基本戦略になる
- 常夜灯周辺より河口エリアのほうが実績が高い傾向にある
- 根岸湾エリアは温排水の影響で周年アジが狙える
- 東扇島西公園は24時間釣りができる人気スポット
- 潮位と時間帯の組み合わせが釣果を大きく左右する
東京湾奥でアジングができる有望ポイントは横浜・川崎エリアに集中している
東京湾奥でアジングを楽しむなら、横浜市と川崎市のエリアが最も有望です。都内の釣り場と比較すると、アジの魚影が格段に濃く、実際に釣果を上げやすい環境が整っています。
東京湾奥では馴染みの薄いクロダイ、キビレのボトムゲームですが、今シーズン時間をかけてやってみました。西のほうでは人気のある釣りですが、調べてみると東京湾の情報はネットでもあまりないようです。
<cite>出典:まとめ 東京湾奥 クロダイ・キビレ ボトムチニング調査結果</cite>
上記の引用はチニングに関するものですが、アジングについても同様の状況があります。東京湾奥のアジング情報は外房や南房と比べて圧倒的に少なく、地元のアングラーが試行錯誤しながら開拓しているのが現状です。しかし、だからこそ穴場的なポイントが多く残されているとも言えるでしょう。
横浜エリアでは、根岸湾周辺、大黒ふ頭西緑地、ふれーゆ裏、八景島対岸などが代表的なポイントとして知られています。これらのエリアは火力発電所の温排水の影響を受けており、水温が安定しやすいという特徴があります。そのため、冬場でもアジが居着きやすく、シーズンを通して狙えるのが大きなメリットです。
川崎エリアでは東扇島西公園が最も人気のあるスポットです。24時間釣りができる環境が整っており、夜間の回遊を狙ったアジングに最適です。朝夕のまずめ時だけでなく、夜に湾内を回遊するアジを効率的に狙えるため、仕事帰りのナイトゲームにも向いています。
📍 横浜・川崎エリアの主要アジングポイント
| エリア | ポイント名 | 特徴 | アクセス |
|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | ふれーゆ裏 | 24時間釣り可、沖にアジ釣り船が来るほど魚影濃い | 電車・車ともに可 |
| 川崎市 | 東扇島西公園 | 24時間開放、先端部が好ポイント | 車推奨 |
| 横浜市磯子区 | 根岸湾 | 温排水影響で周年狙える | 電車・車ともに可 |
| 横浜市金沢区 | 大黒ふ頭西緑地 | 秋~冬に実績高い、22時~5時は道路封鎖 | 車必須 |
| 横浜市金沢区 | 金沢水際線緑地 | 旧福浦岸壁、投げ釣り禁止 | 電車・車ともに可 |
一方、東京都内のポイントについては、残念ながら現状では厳しいと言わざるを得ません。豊洲ぐるり公園や水の広場公園などがネット記事で紹介されることもありますが、実際の釣果は限定的です。サバが大量に回遊していた2020年頃と比べると、近年はアジの数が減少しているという情報もあります。
湾奥アジングは「投げない」「足元狙い」が基本戦略になる
東京湾奥のアジングで最も重要なコツは、意外にも「投げない」ことです。これは外房や南房のアジングとは大きく異なる点で、湾奥特有の攻略法と言えるでしょう。
湾奧で釣る際の最大にして最強のコツは、「投げない」ことです!割と言い切って良いと思ってます!釣り場に付いてからの第一投(?)はクラッチを切ってリグを送り込んで、足元でチョンチョン!。とすると、カサゴやメバル等々の根魚が高確率で遊んでくれます!
<cite>出典:マイホーム!湾奧アジングのススメ</cite>
この「投げない」戦略が有効な理由は、湾奥の水深が比較的浅く、アジが岸壁際まで接岸してくるためです。特に夜間や満潮前後の潮位が高い時間帯には、足元数メートル以内にアジが回遊してくることが多々あります。遠投してしまうと、かえって手前の好ポイントを素通りしてしまうことになりかねません。
具体的な釣り方としては、まずクラッチを切ってリグを真下に落とし、足元をチョンチョンと誘います。これでカサゴやメバルなどの根魚が釣れることも多いのですが、アジが回遊している時間帯であれば、この足元狙いでヒットします。足元で反応がなければ、少しずつ横にズラしながらランガンしていくのが効果的です。
次に狙うべきは「沿い」です。岸壁に沿ってリグを引いてくると、アジが溜まっていることがあります。この釣り方はキャストの練習にもなり、真っすぐ投げないと地面に飛んでいったり、沿いから外れてしまったりするため、狙ったところに正確にキャストする技術が身につきます。
🎣 湾奥アジングの基本アプローチ順序
- 第一段階:足元の縦の動き
- クラッチを切ってリグを真下に落とす
- 足元をチョンチョンと誘う
- 反応がなければ横にズラしてランガン
- 第二段階:沿いの横の動き
- 岸壁に沿ってリグを引く
- 真っすぐ投げる練習にもなる
- アジが溜まっているポイントを発見
- 第三段階:明暗の境目を狙う
- 常夜灯がある場合は明暗を狙う
- 軽量リグ(0.6g~1g)を使用
- より沖を回遊するアジを狙う
この順序で攻めていくことで、効率的にアジを探すことができます。最初から遠投してしまうと、手前のチャンスを逃してしまう可能性が高いため、まずは近場から丁寧に探っていくことをおすすめします。
常夜灯周辺より河口エリアのほうが実績が高い傾向にある
東京湾奥のアジングでは、一般的にイメージされる「常夜灯の下でアジングを楽しむ」というシチュエーションが実は少ないのが特徴です。むしろ河口エリアのほうが実績が高い傾向にあります。
千葉県側湾奥では釣り番組で見るような外洋に面した場所に常夜灯が並んだ漁港というシチュエーションは殆どありません…というかあっても立ち入り禁止が殆どです。なので常夜灯のない場所、河川の河口、変化の乏しい護岸やテトラ帯からのアジングを強いられます。
<cite>出典:東京湾奥アジングの注意点</cite>
この引用が示すように、湾奥では理想的な常夜灯ポイントが非常に限られています。あったとしても立ち入り禁止になっているケースが多く、現実的には常夜灯のない場所、河川の河口、護岸やテトラ帯からアジングを行うことになります。
河口エリアが有望な理由はいくつかあります。まず、アジは意外にも淡水の混じる場所を嫌わず、河口付近にも多く回遊してきます。大雨の後など極端に真水が流れ込む状況でなければ、十分にポイントとして成立します。また、河口には照明のある橋脚があることが多く、これが明暗を作り出してアジを集める役割を果たしています。
さらに、河口にはテナガエビやハゼなどのベイトが豊富に生息しており、これらを捕食するためにアジが集まってきます。特にテナガエビが接岸する6月から8月にかけては、河口エリアでのアジングが最も釣りやすい時期と言えるでしょう。
🌊 河口エリアが有望な理由
| 要因 | 詳細 | 効果 |
|---|---|---|
| 淡水耐性 | アジは適度な淡水混じりを嫌わない | 河口でも十分狙える |
| 橋脚照明 | 橋に設置された照明が明暗を作る | アジを集魚 |
| ベイト豊富 | テナガエビ、ハゼなどが豊富 | 捕食のために回遊 |
| 流れの変化 | 潮汐と河川の流れが複雑に絡む | アジの活性が上がる |
| プレッシャー低 | 一般的なイメージと異なるため人が少ない | 魚がスレていない |
実際に、柏店のスタッフによる釣行記では、港湾部で釣れなかった後に河川に移動したところ、濁りの少ない場所でアジが連発したという報告があります。川でアジが釣れるのか疑問に思う方も多いかもしれませんが、実際には十分に釣果が期待できるのです。
ただし、河口エリアでのアジングには注意点もあります。チヌ(クロダイ)やシーバスなどの外道が多いため、エステルラインだけでなくPEラインのタックルも用意しておくと安心です。また、潮位の変化が大きいため、潮位が高い時間帯を狙うことが重要になります。
根岸湾エリアは温排水の影響で周年アジが狙える
根岸湾エリア(磯子周辺)は、東京湾奥のアジングにおいて特筆すべきポイントです。火力発電所の温排水の影響により、冬場でも水温が安定しやすく、周年アジを狙うことができる貴重なエリアとなっています。
根岸湾の最大の特徴は、その地形と環境です。湾内には電源開発前護岸や磯子海釣り施設などがあり、アジが居着きやすい条件が揃っています。特に5月から6月のGW前後からの産卵時期には、多くのアジンガーが集まる人気スポットとなります。
釣り方としては、足元や近距離でアジが安定して釣れる傾向にあります。ローソン周辺は障害物が多く、足元や近距離にアジが溜まりやすいポイントとして知られています。柵などはないため落下には注意が必要ですが、その分ロッドが扱いやすく、水面も近いためアジング自体はしやすい環境です。
⏰ 根岸湾での釣れる時間帯と条件
- 最も釣れる時間帯:夕マズメから日が沈んでしばらく
- 夜間の実績:深夜から入った場合や朝マズメはあまり釣れない印象
- 潮位:満潮前後の潮位が高い時間帯が有利
- シーズン:5~6月が最盛期だが、秋冬も狙える
根岸湾でのアジングには、いくつかのポイント選びのコツがあります。まず、できる限り潮通しがよい場所に釣り座を構えることが重要です。湾内の奥まったエリアよりも、外海に近い場所のほうがアジの回遊が多い傾向にあります。
また、日中はほとんど釣れないため、朝夕のまずめや夜間、特に満潮前後の潮位が高い時間帯に狙うのがセオリーです。サビキ釣りよりも、遠投カゴ釣りやアジングのほうが釣果が出やすい傾向があるため、ルアータックルでの釣りに適したフィールドと言えるでしょう。
ただし、根岸湾にも課題があります。常連アジンガーの中にはマナーの悪い方もいるようで、酒を飲んで騒いだ上で飲酒運転をするような人もいるとの情報があります。釣り場を守るためにも、一人ひとりがマナーを守り、節度ある行動を心がける必要があります。
東扇島西公園は24時間釣りができる人気スポット
川崎市にある東扇島西公園は、東京湾奥のアジングにおいて最も人気のあるスポットの一つです。最大の魅力は24時間釣りができる環境が整っていることで、仕事帰りのナイトゲームにも最適です。
東扇島西公園の特徴は、その立地と環境にあります。潮通しがよく、朝夕のまずめ以外にも、夜に湾内を回遊するアジを狙うことができます。サビキ釣り、遠投カゴ釣り、ルアーを使ったアジングと、さまざまな釣り方に対応できる懐の深さも魅力です。
公園内で最も有利なのは先端部(川崎新堤側)に近いエリアです。潮通しがよく、アジの回遊も多いため、多くのアングラーがこのエリアを狙います。ただし、人気が高いため、早めに釣り座を確保する必要があるでしょう。一方、夜間は入口付近までアジが回遊してくるため、先端部が取れなくても十分にチャンスはあります。
🏞️ 東扇島西公園の施設情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 営業時間 | 24時間開放 |
| 駐車場 | あり |
| トイレ | あり |
| 釣具店 | 出張所が常駐 |
| アクセス | 車推奨(公共交通機関では行きにくい) |
| 水深 | 深い(深場まである) |
| 釣り座 | 広い(多くの釣り人を収容可能) |
東扇島西公園でアジングをする際の注意点もいくつかあります。まず、水深が深かったり、目立った障害物がなかったりするため、アジのいるポイントを探すのが若干難しい面があります。頻繁に通ってパターンを掴むか、釣具店の出張所で情報を仕入れることをおすすめします。
また、この公園は先端部分に常連が常に竿受けなどを設置して場所取りをしていたり、釣り道具やガラクタなどが公園の一角に積まれていたりと、一部の常連のマナーが問題視されています。新しく訪れるアングラーは、こうした常連とのトラブルを避けるため、無理に先端部を狙わず、少し離れた場所から始めるのも一つの選択肢かもしれません。
東扇島西公園は、どちらかというとサビキや泳がせでの青物狙いなどが盛んな印象の釣り場です。アジングで釣れている人はそれほど多くないという情報もありますが、夜間の回遊を狙えば十分に釣果は期待できるでしょう。特にアジの回遊が活発な春から秋にかけては、ナイトゲームでの実績が高いようです。
潮位と時間帯の組み合わせが釣果を大きく左右する
東京湾奥のアジングにおいて、潮位と時間帯の組み合わせは釣果を大きく左右する重要な要素です。外房や南房と異なり、湾奥は水深が浅いポイントが多いため、潮位の影響を特に強く受けます。
基本的なセオリーとして、満潮前後の4時間程度が最も釣りやすい時間帯と言われています。潮位が低い時間帯は、アジが岸によってこないため、どんなにテクニックがあっても釣果を上げるのは難しいでしょう。特に岩壁や堤防の際の水深が3~5m程度しかないポイントでは、この傾向が顕著です。
釣れる条件:干潟も河口も潮位の高いときよりも、ある程度下げてからのほうが釣れる印象でした。自分の場合は下げ五分以降を狙っていくことが多かったです。理由としてはゴロタに入っているベイト(ハゼ・カニ・テナガエビ)が、潮位が下がって沖に払いだされるため、そのタイミングで活性が上がると考えております。
<cite>出典:まとめ 東京湾奥 クロダイ・キビレ ボトムチニング調査結果</cite>
上記はチニングの情報ですが、アジングにも応用できる考え方です。ただし、アジの場合は潮が下げるタイミングよりも、満潮前後のほうが実績が高い傾向にあります。これは、潮位が高いときにアジが浅場まで回遊してくるためと考えられます。
📊 時間帯別の釣果傾向
| 時間帯 | 潮位 | 釣果期待度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 夕マズメ | 満潮前後 | ★★★★★ | 最も釣れる黄金タイム |
| 夜間 | 満潮前後 | ★★★★☆ | ナイトゲームで狙い目 |
| 朝マズメ | 満潮前後 | ★★★★☆ | 早起きする価値あり |
| 日中 | どの潮位でも | ★☆☆☆☆ | 基本的に厳しい |
| 夕マズメ | 干潮前後 | ★★☆☆☆ | 潮位が低いと厳しい |
| 夜間 | 干潮前後 | ★★☆☆☆ | ポイント次第では狙える |
時間帯と潮位の組み合わせで最も釣果が期待できるのは、夕マズメから夜間にかけての満潮前後です。この時間帯は、アジの活性が上がり、浅場まで積極的に回遊してくるため、足元狙いでも十分に釣果が期待できます。
また、流れが効いている最中よりも、若干緩むタイミングが釣りやすく、特に干潮前後も狙い目となります。ただし、これは河口エリアでの話で、干潟の場合は穏やかな海況のほうが良い釣りができる傾向にあります。底荒れすると極端に反応が鈍くなるため、天候にも注意が必要です。
雨、風、濁りなどの条件も重要です。河川の場合、これらの要素があったほうが、アジの警戒心が緩むため良い釣りができるケースが多いです。逆に干潟の場合は穏やかな海況のほうが吉で、底荒れすると極端に反応が鈍くなります。このように、ポイントの種類によって好条件が異なる点も、湾奥アジングの奥深さと言えるでしょう。
東京湾奥アジングの季節別攻略法とタックル選び
- 春は産卵期で釣果にムラが出やすいが荒食いのタイミングを狙える
- 夏は豆アジが接岸しテクニカルなゲームが楽しめる時期
- 秋は最も安定して釣果が上がるハイシーズン
- 冬は水深のある場所で居着きのアジを狙う修行の季節
- ジグヘッドは0.6g~2gの軽量リグが基本
- ワームは小型のクロー系やストレート系が効果的
- ロッドは8フィート前後のLクラスが扱いやすい
春は産卵期で釣果にムラが出やすいが荒食いのタイミングを狙える
春は東京湾奥のアジングにおいて、最もドラマティックなシーズンと言えるかもしれません。産卵を控えたアジが荒食いをする一方で、産卵直前には口を使わなくなるため、釣果にムラが出やすい時期です。
産卵を意識し始めたタイミングでは、体力をつけるために積極的にベイトを”荒食い”するタイミングがあります。しかしながら、産卵が近くにつれて、今度は無駄な体力を消費しないように捕食行動を取ることが少なくなっていくのです。
<cite>出典:【東京湾アジングの名手『キムソウ』が指南】湾奥アジのシーズナルパターンと攻略法</cite>
この引用が示すように、春のアジングは「荒食い」のタイミングに当たれば大きな釣果が期待できますが、外してしまうとなかなか口を使ってくれません。したがって、春のアジングでは情報収集が特に重要になります。釣具店やSNSで最新の釣果情報をチェックし、荒食いのタイミングを逃さないようにしましょう。
産卵行動は、サイズや水温によって前後しますが、春の兆候が見え始める頃から始まり、初夏の頃まで続きます。具体的には3月下旬から6月頃までが産卵期と考えられ、この期間は週単位、日単位で釣果が大きく変動します。
🌸 春のアジング攻略ポイント
- 3月~4月前半:産卵前の荒食い期、大型が狙える
- 4月後半~5月:産卵最盛期、釣果にムラが大きい
- 5月後半~6月:産卵後の回復期、徐々に安定
- 狙い目ポイント:根岸湾、八景島周辺などの産卵場所近く
- ベストタイム:夕マズメ~夜間の満潮前後
春のアジングで特に注意すべきは、産卵場所に近いポイントを狙うことです。根岸湾周辺や八景島対岸などは、産卵場所として知られており、この時期に多くのアジが集まります。特にGW前後からの1ヶ月間は、根岸湾のローソン周辺に多くのアジンガーが集まる人気のシーズンとなります。
春のアジは体力をつけるために積極的に捕食するため、リグの動きに対する反応も良い傾向にあります。通常よりもやや大きめのワーム(2~2.5インチ)を使用しても問題なく、むしろボリュームのあるワームのほうがアピール力が高く、荒食い中のアジに効果的かもしれません。
ただし、産卵直前になると、アジは無駄な体力を消費しないように捕食行動を控えるようになります。この時期は、いくら丁寧に誘っても反応が得られないことが多いため、無理に粘らず、別のポイントに移動するか、時期をずらして再挑戦するほうが賢明でしょう。
夏は豆アジが接岸しテクニカルなゲームが楽しめる時期
夏は、東京湾奥に豆アジや小型のアジが大量に接岸してくる季節です。サイズは小さいものの、数釣りが楽しめ、テクニカルなゲーム性の高いアジングができる時期と言えます。
産卵を終えて体力を消耗したアジたちは、積極的に捕食をしながら、より多くのエサを求めてプランクトン量の多い浅場へと回遊を始めます。各地でアジの釣果が聞かれるようになる時期で、アジングを楽しむアングラーにとってはようやく本格的なシーズンインの兆しを感じる時期でもあります。
浅場へ回遊するのは小型のアジが中心で、水温に対してデリケートな大型のアジは水深のある場所で過ごすことが多いのが特徴です。サイズは伸びませんが、テクニカルでゲーム性の高い豆アジゲームが面白い季節ですね。
<cite>出典:【東京湾アジングの名手『キムソウ』が指南】湾奥アジのシーズナルパターンと攻略法</cite>
夏のアジングの特徴は、何と言っても豆アジの数釣りです。10cm前後の豆アジから、15cm程度の小アジまで、サイズはまちまちですが、条件が合えば数十匹単位での釣果も珍しくありません。サビキ釣りでも十分に楽しめますが、アジングで狙うことで、よりゲーム性の高い釣りが展開できます。
🌞 夏のアジング戦略
| 項目 | 詳細 | 推奨 |
|---|---|---|
| 主な対象サイズ | 10~15cm程度 | 豆アジ・小アジ |
| リグウェイト | 0.4~1g | 超軽量が基本 |
| ワームサイズ | 1~1.5インチ | 小型を使用 |
| ベストエリア | 干潟、浅い護岸 | 水深2~3m |
| 狙い目の時間 | 夕マズメ~夜間 | 日中は厳しい |
| ベイトパターン | プランクトンメイン | 表層~中層を意識 |
夏のアジングでは、軽量リグの使用が必須となります。浅場にいる豆アジは警戒心が強く、重いリグでは見切られてしまうことが多いためです。0.4g~1g程度のジグヘッドに、1~1.5インチの小型ワームを組み合わせるのがセオリーです。ベイトタックルでこの重さのリグを投げるのは難易度が高いですが、練習すれば必ず投げられるようになります。
夏のアジングで重要なのは、水温の管理です。浅場の水温はまだまだ安定しない季節で、日中は高水温になりすぎることもあります。そのため、水温が落ち着く夕方から夜間にかけての釣行が効果的です。また、潮通しの良い場所や、河口など流れのある場所を選ぶことで、水温の変化を緩和し、アジの活性を保つことができます。
豆アジとはいえ、引きは意外と強く、軽量タックルで掛けると十分に楽しめます。また、夏は海の状況も穏やかなことが多く、初心者がアジングを始めるには最適な季節と言えるでしょう。数釣りを楽しみながら、基本的なテクニックを磨くには最高の時期です。
秋は最も安定して釣果が上がるハイシーズン
秋は東京湾奥のアジングにおいて、最も安定して釣果が上がるハイシーズンです。水温が下がり始め、さまざまな魚が沿岸部に接岸してくる季節で、アジも活発に捕食活動を行います。
秋に入ると、夏の高水温から冬へ向かい水温が下がり始め、さまざまな魚が沿岸部に接岸してきます。夏の間に接岸してきたイワシなどのベイトを求め、シーバスや太刀魚、アオリイカなどにメバルやアジなどの小型の魚まで、多種多様な魚たちが荒食いを始めるのです。
この頃のアジはエサの多い場所を見つけて定住する居着きのアジと、まだ居着いていない回遊の群れとに分かれて、それぞれ異なる捕食行動をします。この時期は、居着きか否かや、周囲に大型の多魚種が居るかなどを加味して釣り方やパターンを見つけ出し、釣果に繋げるといった最もゲーム性の高いアジングが楽しめるのが特徴です。
<cite>出典:【東京湾アジングの名手『キムソウ』が指南】湾奥アジのシーズナルパターンと攻略法</cite>
秋のアジングの魅力は、居着きのアジと回遊のアジという、2つのパターンを攻略できる点にあります。居着きのアジは、餌の多い場所に定住しており、比較的予測しやすい行動をします。一方、回遊のアジは、群れで移動しながら捕食するため、タイミングを合わせることが重要になります。
🍂 秋のアジング2つのパターン
居着きパターン
- 特徴:特定の場所に定住している
- 狙い方:同じポイントを丁寧に攻める
- 時間帯:夕マズメ~夜間が中心
- リグ:軽量(0.6~1g)でゆっくり誘う
- ポイント:ストラクチャー周り、カキ殻エリア
回遊パターン
- 特徴:群れで移動しながら捕食
- 狙い方:広範囲をランガンして探す
- 時間帯:朝夕のまずめ時が特に有効
- リグ:やや重め(1~2g)で手返し良く
- ポイント:潮通しの良い先端部、明暗の境
秋のアジングでは、夏の間に地道に積み上げた情報が生きてきます。夏の間に群れが入りやすかった場所や、高水温の夏でも潮通しの良いワンドなど、自分なりのデータベースを持っているアングラーが有利になります。また、この時期は引き出しの多さが釣果を左右するため、さまざまな釣り方を試してみることをおすすめします。
秋のアジは、夏の豆アジよりもサイズアップしており、20cm前後の良型が混じることも珍しくありません。特に9月から11月にかけては、尺アジ(30cm以上)が釣れる可能性もあり、大型を狙うなら最も期待できる季節と言えるでしょう。
ただし、秋は釣り人も多い季節です。週末の人気ポイントは早い時間から混雑することが予想されるため、平日を狙うか、早めに釣り場に到着して場所を確保することが重要です。また、夜間のほうが比較的空いていることが多いので、ナイトゲームを中心にするのも一つの戦略です。
冬は水深のある場所で居着きのアジを狙う修行の季節
冬は東京湾奥のアジングにおいて、最も難易度が高い「修行の季節」と言われています。かつては「冬のアジは深場に落ちて陸から狙うのは無理」という常識がありましたが、現在では適切なポイントと条件を選べば、冬でも十分に狙えることがわかっています。
「冬の低水温期、アジは深場に落ちて陸から狙うのは無理」10年ほど前にはそれが常識として通っていたのは事実で、そういう行動をとる群れもいます。しかし、アジは低水温を嫌うのではなく、水温の変動を嫌う性質があり安定した水温の場所では、冬の間でも狙うことができるというのが今現在の常識となりました。
<cite>出典:【東京湾アジングの名手『キムソウ』が指南】湾奥アジのシーズナルパターンと攻略法</cite>
この引用が示すように、アジは低水温そのものを嫌うのではなく、水温の変動を嫌う性質があります。したがって、水温が安定しやすい深場を狙うことで、冬でもアジングが成立するのです。具体的には、4メートルを超える水深がある場所であれば、冬でも釣れる可能性が高いとされています。
❄️ 冬のアジング攻略ポイント
- 水深:4m以上ある場所を選ぶ
- ポイント:船の接岸する岸壁、運河筋
- メインベイト:ボトムのエビやカニなどの甲殻類
- 釣り方:フォールよりボトムステイが効果的
- 動き:少ない動きでじっくり誘う
- タイミング:満潮前後、潮が緩むタイミング
冬のアジングでは、狙うレンジも変わってきます。風や雨で簡単に水温が変わってしまう浅場ではなく、足元から水深のある場所にかたまるため、そういう場所が狙い目となります。船の接岸する岸壁や、船の航行を目的とした運河筋などがおすすめです。これらの場所は、船の航行を安全に行えるようしっかりと浚渫してあり、潮位の低い時間帯でも水深が確保されています。
冬のアジングで特に重要なのは、餌の種類を意識することです。冬はプランクトン量が少なく、水もクリアになりがちなので、アジの主な餌はボトムのエビやカニといった甲殻類になります。そのため、フォールよりもボトムステイといった動きの少ない釣り方で結果が出やすいです。
🎣 冬のアジング推奨タックル
| アイテム | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| ジグヘッド | 1.5~3g | 深場を狙うためやや重め |
| ワーム | クロー系2インチ | 甲殻類をイミテート |
| カラー | ナチュラル系 | クリアウォーターを意識 |
| リーダー | フロロ3~4号 | 根ズレ対策 |
| アクション | ボトムステイ中心 | 動きを最小限に |
根岸湾のような温排水の影響を受けるエリアは、冬でも比較的水温が安定しやすいため、狙い目となります。ただし、冬のアジングは忍耐を強いられる釣りであり、数時間粘っても1匹も釣れないということも珍しくありません。それでも、冬に釣れた1匹の価値は、他のシーズンとは比較にならないほど高く、達成感も格別です。
寒い冬にする釣りとしては辛いことが多いですが、その分、釣れたときの喜びは大きいものです。冬のアジングは、まさに「修行の季節」と呼ぶにふさわしく、この時期を乗り越えることで、アジングのスキルが大きく向上することでしょう。
ジグヘッドは0.6g~2gの軽量リグが基本
東京湾奥のアジングにおいて、ジグヘッドの選択は釣果を左右する重要な要素です。基本的には0.6g~2gの軽量リグが中心となりますが、ポイントや状況によって使い分けが必要になります。
俺は湾奧のポイントでは1g以下のジグヘッドを使う事が多く、一番使う重さは0.6gです。始めは中々投げるのに苦労する重さだと思いますが、俺の過去記事とかみて是非チャレンジしてください!練習すれば必ず投げられるようになります!!
<cite>出典:マイホーム!湾奧アジングのススメ</cite>
この引用にあるように、湾奥では1g以下のジグヘッドが主力となります。特に0.6gは、東京湾奥の浅い水深と軽い潮流にマッチした重さと言えるでしょう。ただし、初心者にとっては投げにくい重さでもあるため、最初は1g程度から始めて、徐々に軽いリグにチャレンジするのがおすすめです。
一方、東京湾奥でも状況によっては重めのジグヘッドが必要になることもあります。特に遠投が必要な場面や、風が強い日、流れが速い場所などでは、1.5g~2.5g程度のジグヘッドが活躍します。
⚖️ ジグヘッドの重さ別使い分け
| 重さ | 使用場面 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 0.4~0.6g | 超浅場、豆アジ狙い | 自然な動き、喰わせ力高い | 投げにくい、風に弱い |
| 0.8~1g | 標準的な湾奥アジング | バランスが良い、扱いやすい | 特になし |
| 1.5~2g | 遠投、強風時、深場 | 飛距離が出る、底取りしやすい | 警戒される場合も |
| 2.5~3g | 特殊な状況のみ | 深場や強流エリア対応 | 湾奥では出番少ない |
ジグヘッドの形状も重要です。東京湾奥では、ボトムで根掛かりの少ない形状のものを選ぶことが推奨されます。いわゆるフットボールジグの形状、つまり上から見たときに前のオモリが横に長いタイプが根掛かりしにくく、おすすめです。
具体的な製品としては、カツイチの「タンクヘッド」や、ハヤブサの「シューティングボール」などが人気です。これらのジグヘッドは、フットボール形状で根掛かりしにくく、東京湾奥の環境に適しています。重さは状況に応じて使い分けますが、2/0号のフックサイズで、2~3.5gの範囲を中心に揃えておくと良いでしょう。
近年では、フリーリグも注目されています。フリーリグは、ジグヘッドに比較して根がかりが少ないのがメリットです。チニングの場合は、ボトムで食わすイメージなのでシンカーストッパーを使用したほうが良いとされていますが、アジングでも応用できる可能性があります。フックはオフセットの#2前後を中心に使用すると良いでしょう。
ワームは小型のクロー系やストレート系が効果的
東京湾奥のアジングにおいて、ワーム選びもジグヘッドと同様に重要です。基本的には小型のクロー系やストレート系が効果的で、サイズは1~2インチ程度が中心となります。
ワームの選択については、正直なところ「何でも釣れる」という意見もありますが、やはり実績のあるワームを使用するほうが、特に初心者にとっては安心感があるでしょう。東京湾奥で実績の高いワームとしては、バークレイの「インチホッグ」シリーズや「サンドワーム」などが挙げられます。
実績ワームは以下になります。なんとなくベイトにシルエット寄せたくクロー系の出番が多かったですが、ストレートワームでも遜色なく釣れます。自分の主力は市販のチヌ用ワームの中でも割と小さめの部類ですね。理由としては小さいほうがしっかりと口の中に入ることが多かったためです。
<cite>出典:まとめ 東京湾奥 クロダイ・キビレ ボトムチニング調査結果</cite>
この引用はチニング用のワームに関するものですが、アジングにも応用できる考え方です。小さいワームのほうが、アジの口にしっかりと入り、針掛かりが良くなる傾向にあります。特に東京湾奥のアジは、外房や南房と比べてサイズが小さめなので、ワームも小さめを選択するのが賢明です。
🐛 おすすめワームの特徴
クロー系ワーム
- サイズ:1~2インチ
- 特徴:カニやエビをイミテート
- カラー:ナチュラル系(クリア、グロー)
- 使用場面:ボトム中心の釣り
- 代表製品:インチホッグ、ドライブクロー
ストレート系ワーム
- サイズ:1.5~2インチ
- 特徴:ハゼやイソメをイミテート
- カラー:レッド、ピンク、クリア
- 使用場面:中層~ボトムまで幅広く
- 代表製品:サンドワーム、グラスミノー
ワームのカラー選択も重要な要素です。一般的には、水がクリアなときはナチュラル系のカラー(クリア、ウォーターメロンなど)、濁りが入っているときはアピール系のカラー(レッド、ピンク、グローなど)が効果的とされています。ただし、東京湾奥では濁りが入っている状況が多いため、アピール系のカラーを中心に揃えておくと良いでしょう。
ワームの素材も考慮すべきポイントです。ガルプのような匂い付きワームは、アジの食い気が渋いときに効果を発揮します。手っ取り早く魚を見つけたい場合は、ガルプが良いのですが、持ちに難ありという欠点もあります。根掛かりを外すと裂けたりしてしまい、消耗が激しいため、コストパフォーマンスを考えると通常のワームのほうが経済的かもしれません。
ワームのサイズについては、状況に応じて使い分けることが重要です。豆アジや小アジが中心の夏場は1~1.5インチの極小サイズが有効ですが、春や秋の良型狙いであれば2~2.5インチのやや大きめのサイズも効果的です。ただし、あまり大きすぎると針掛かりが悪くなるため、基本は小さめのサイズを中心に、状況に応じて大きくしていくという考え方が良いでしょう。
ロッドは8フィート前後のLクラスが扱いやすい
東京湾奥のアジングにおいて、専用ロッドを持っていない場合でも、強めのメバルロッドやシーバスロッドで十分に対応可能です。ただし、より快適に釣りを楽しむためには、適切なロッド選びが重要になります。
ロッドの長さとしては、8フィート前後が最も扱いやすいでしょう。これは、湾奥の釣り場の多くが護岸や堤防からの釣りとなるため、あまり長いロッドだと取り回しが悪くなるためです。また、足元狙いが基本となる湾奥アジングでは、長すぎるロッドは不利になることもあります。
パワークラスについては、Lクラス(ライト)が最も汎用性が高いと言えます。MLクラス(ミディアムライト)だと、豆アジや小アジとのやり取りで魚の引きを楽しみにくく、瞬殺してしまう可能性があります。一方、Lクラスであれば、魚の引きが楽しめて丁度良い感じになります。
🎣 ロッド選びのポイント
| 項目 | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| 長さ | 7.6~8.6フィート | 取り回しと飛距離のバランス |
| パワー | L~ML | 魚の引きを楽しめる |
| アクション | ファスト | 感度重視 |
| 素材 | カーボン高配合 | 操作性と感度 |
| グリップ | セパレート | 軽量化 |
| ガイド | Kガイド推奨 | PEライン対応 |
専用ロッドの場合、シーバスロッドやエギングロッドよりも、さらに感度の向上が望めます。具体的には、リグの操作感や、ボトム感知能力の部分に差が出ます。これが最終的に、小さなアタリをより多く捉えたり、根がかりを回避したりといった利点に繋がります。
ロッドの調子(テーパー)も重要です。東京湾奥のアジングでは、ファストテーパー(先調子)のロッドが推奨されます。これは、軽量リグの操作性と、小さなアタリを感知する感度を重視するためです。ただし、あまりに先調子すぎるとバラシが多くなる可能性もあるため、適度にベリーが入るファストテーパーが理想的です。
メーカー別で見ると、オリムピックの「シルベラード」シリーズや、メジャークラフトの「ファーストキャスト」シリーズなど、エントリーモデルでも十分に対応可能です。高価なロッドほど感度や軽量性に優れますが、初心者のうちは1万円前後のモデルでも十分に楽しめるでしょう。
シーバスロッドを流用する場合は、9フィート前後のLクラスが適しています。ディアルーナXRのS900Lなどは、アジングにも十分対応できる性能を持っています。ただし、シーバスロッドはアジング専用ロッドと比べると、やや重く感じることがあるため、長時間の釣行では疲労感が増す可能性があります。
最後に、ロッドを選ぶ際は、実際に店頭で持ってみて、重量バランスやグリップの握りやすさを確認することをおすすめします。カタログスペックだけでは分からない部分も多いため、自分の手に馴染むロッドを選ぶことが、長く釣りを楽しむためには重要です。
まとめ:東京湾奥のアジングポイントとシーズン別攻略法
最後に記事のポイントをまとめます。
- 東京湾奥のアジングポイントは横浜・川崎エリアに集中し、根岸湾や東扇島西公園などが有望である
- 東京都内のポイントは魚影が薄く、初心者には厳しい環境である
- 湾奥アジングの基本戦略は「投げない」「足元狙い」から始めることである
- 常夜灯ポイントは少なく、河口エリアのほうが実績が高い傾向にある
- 根岸湾は温排水の影響で周年アジが狙える貴重なエリアである
- 東扇島西公園は24時間釣りができ、ナイトゲームに最適である
- 潮位と時間帯の組み合わせが釣果を大きく左右し、満潮前後の夕マズメが最も有望である
- 春は産卵期で釣果にムラがあるが、荒食いのタイミングを狙えば大型が期待できる
- 夏は豆アジが接岸し、テクニカルなゲームが楽しめる数釣りシーズンである
- 秋は最も安定して釣果が上がるハイシーズンで、居着きと回遊の2パターンを攻略できる
- 冬は水深のある場所で居着きのアジを狙う修行の季節だが、条件が合えば釣果は期待できる
- ジグヘッドは0.6g~2gの軽量リグが基本で、フットボール形状が根掛かりしにくい
- ワームは小型のクロー系やストレート系が効果的で、1~2インチが中心サイズである
- ロッドは8フィート前後のLクラスが扱いやすく、感度重視のファストテーパーが推奨される
- 東京湾奥のアジは外房や南房と比べてサイズが小さめだが、都心からのアクセスの良さが魅力である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- マイホーム!湾奧アジングのススメ
- 東京湾奥アジングの注意点
- 首都圏でのアジングについて
- 東京湾湾奥で釣れたアジの釣り・釣果情報
- 【東京湾アジングの名手『キムソウ』が指南】湾奥アジのシーズナルパターンと攻略法
- 東京・神奈川で「アジ」を狙える釣り場16選
- 東京湾奥河川でナイトアジング
- 埼玉県在住の最近アジングを始めた者です
- まとめ 東京湾奥 クロダイ・キビレ ボトムチニング調査結果
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。