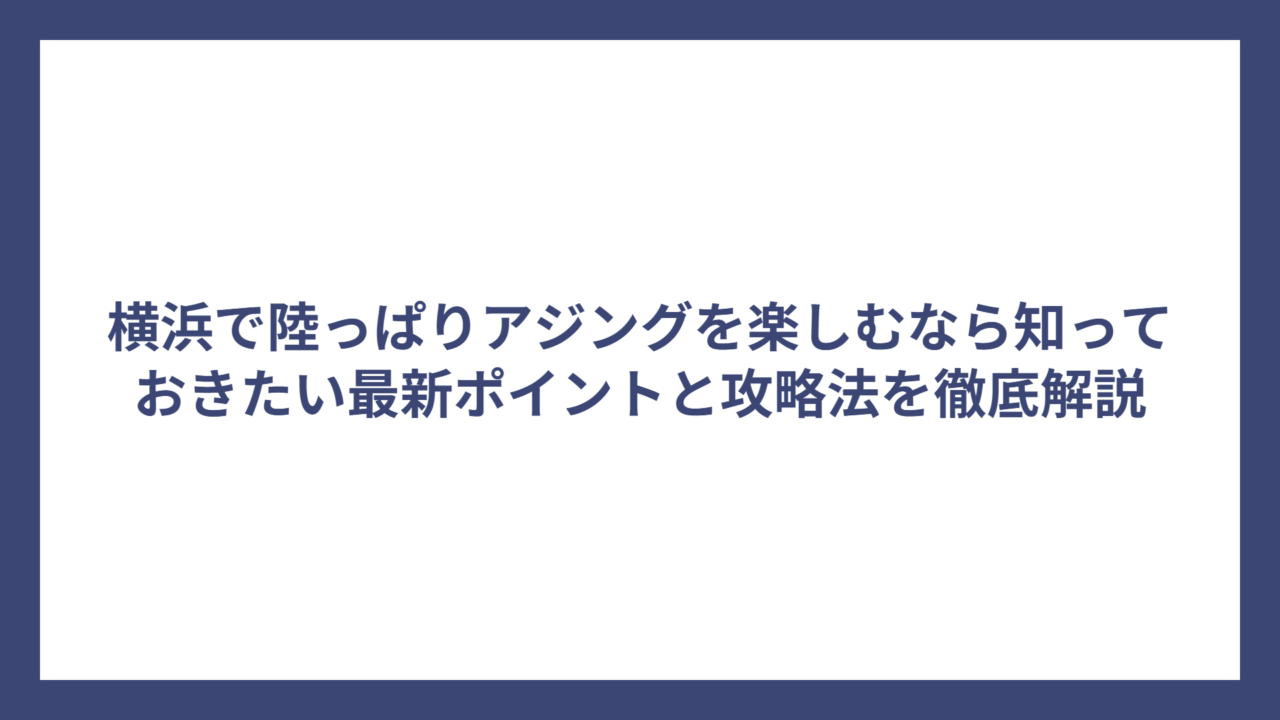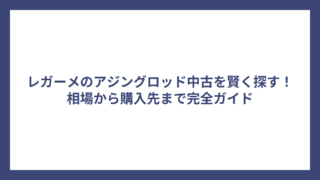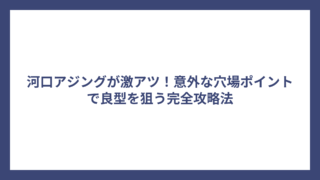横浜エリアは首都圏から気軽にアクセスできるアジングの人気フィールドです。工業地帯から流れる温排水の影響により、一年を通してアジを狙うことができる恵まれた環境が整っています。しかし、実際に陸っぱりで釣果を上げるには、ポイント選びやシーズン、釣り方のコツなど押さえておくべき情報がいくつかあります。
この記事では、インターネット上に散らばる横浜アジングの情報を収集し、初心者から経験者まで役立つ実践的な知識を整理してお届けします。穴場ポイントの紹介から、常夜灯周りの攻略法、時期ごとの釣り方の違い、おすすめタックルまで、横浜での陸っぱりアジングを成功させるための情報を網羅的に解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 横浜の陸っぱりアジングで実績のある主要ポイントと穴場スポットがわかる |
| ✓ シーズンごとの釣り方の違いと最適な時期が理解できる |
| ✓ 常夜灯周りでの効果的な攻略法が身につく |
| ✓ 初心者でも釣果を上げやすいタックルセッティングがわかる |
横浜の陸っぱりアジングで押さえておきたい主要ポイントと穴場情報
- 横浜の陸っぱりアジングは温排水の恩恵で周年狙える貴重なフィールド
- 根岸港は5〜6月の産卵期に多くのアングラーが集まる人気スポット
- 大黒ふ頭西緑地(ベイ下)は秋から冬にかけてアジンガーで賑わう
- ふれーゆ裏は東京からアクセスしやすいが初心者には難易度高め
- 東扇島西公園は釣り場環境は良いがアジングには向かない面も
- 穴場スポットも存在するが釣り禁止エリアには要注意
横浜の陸っぱりアジングは温排水の恩恵で周年狙える貴重なフィールド
横浜エリアがアジングのメッカと呼ばれる最大の理由は、工業地帯からの温排水により東京湾のアジにオフシーズンがないという点にあります。一般的に冬場は水温が下がりアジの活性が落ちるものですが、横浜周辺では温排水の影響で比較的安定した水温が保たれています。
神奈川釣りポイントマップによれば、川崎・横浜エリアは工業地帯が多く、そこから流れる温排水によって一年中アジを釣ることができると紹介されています(出典:【アジング】神奈川(川崎・横浜)でアジ釣りができるポイント)。この特性により、他のエリアでは釣りにならない真冬でも、横浜なら陸っぱりでアジを狙うチャンスがあるわけです。
ただし、横浜エリアには独特の課題も存在します。それは釣り場の少なさです。多くの場所が転落防止柵で囲まれており、いわゆる「The 漁港」のような開放的な釣り場はほとんどありません。ClearBlueのコラムでは「他のエリアに比べおかっぱりは非常に釣り場が少ない」「釣りが出来る場所は9割型フェンス(転落防止柵)があり、いわゆる”The漁港”はありません」と指摘されています(出典:横浜のこの時期のアジング)。
このような制約があるからこそ、限られた釣り場には多くのアングラーが集中します。週末ともなれば人気ポイントは早朝から場所取りが始まることも珍しくありません。一方で、こうした都市部特有の環境だからこそ味わえる「アーバンアジング」の魅力もあります。夜景を背景にしたナイトゲーム、常夜灯の明かりが織りなす幻想的な雰囲気の中での釣りは、横浜ならではの体験といえるでしょう。
また、横浜のアジは脂のりが良く美味しいことでも知られています。これも豊富なプランクトンが育む東京湾の恵みです。春先や秋のハイシーズンには体高のあるメタボなアジが狙え、釣って楽しい、食べて美味しいという二重の満足感が得られます。
釣り場が少ない分、情報収集とポイント選びが釣果を左右する重要な要素となります。次のセクションからは、具体的なポイントごとの特徴と攻略法を詳しく見ていきましょう。
根岸港は5〜6月の産卵期に多くのアングラーが集まる人気スポット
根岸港は横浜アジングを代表する一級ポイントで、特に5月から6月のゴールデンウィーク前後の産卵シーズンに多くのアジンガーで賑わいます。このエリアの最大の魅力は、比較的安定した釣果と釣りやすい環境にあります。
noteの釣行記によれば「ローソン周辺は障害物などが多く、足元や近距離でアジが安定して釣れやすい」「柵などはないので落下には注意が必要だが、その分ロッドは扱いやすく水面も近いためアジング自体はしやすい」と評価されています(出典:首都圏でのアジングについて)。
根岸港の釣りで押さえておきたいポイントは以下の通りです。まず、時間帯は夕マズメから日没後が最も釣れるとされています。深夜からのエントリーや朝マズメはそれほど実績がないようです。また、ローソン周辺は近くにトイレがあり買い物もできるという利便性の高さも魅力の一つです。
ただし、人気ポイントゆえの課題もあります。産卵シーズンには平日の深夜でもそこそこ人が集まり、週末になれば昼間から場所取りする人もいるほど混雑します。さらに、一部のアングラーのマナーの悪さも指摘されており、酒を飲んで騒いだ後に飲酒運転で帰るような人もいるとの情報もあります。
📊 根岸港の特徴まとめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ベストシーズン | 5〜6月の産卵期 |
| 釣れる時間帯 | 夕マズメ〜日没後 |
| メリット | 足元・近距離で安定、水面が近く釣りやすい、コンビニ・トイレあり |
| デメリット | シーズン中は激混み、一部マナーの悪い常連あり |
| 推奨レンジ | 岸壁際の浅い明暗部 |
根岸港で釣果を上げるコツは、障害物周りを丁寧に探ることです。岸壁際や明暗部にアジが付いていることが多いため、遠投よりも手前を重点的に攻めるのが効果的でしょう。また、混雑を避けたいなら平日の夜や、シーズンオフの秋〜冬にチャレンジするのも一つの手かもしれません。
大黒ふ頭西緑地(ベイ下)は秋から冬にかけてアジンガーで賑わう
横浜ベイブリッジの真下に位置することから「ベイ下」とも呼ばれる大黒ふ頭西緑地は、秋から冬にかけて特に人気の高いアジングスポットです。根岸港が春〜初夏のイメージが強いのに対し、こちらは秋冬のメインフィールドという位置づけです。
このポイントの大きな特徴は夜間の入場制限があることです。22時から翌朝5時までは緑地に通じる道路が封鎖されるため、22時までに帰るか、5時まで夜通し釣りをするかの二択になります。これは釣行計画を立てる上で重要な情報ですので、必ず頭に入れておきましょう。
環境面では、近くの公園に公衆トイレがあるため設備は悪くありません。ただし、一部のアングラーが緑地内で立ち小便をしている例も報告されており、良識ある釣り人はきちんとトイレまで歩くべきでしょう。なお、2025年4月からは公園内が禁煙になったとの情報もあり、隣の釣り人のタバコの煙に悩まされることは少なくなったかもしれません。
🎣 大黒ふ頭西緑地の人気ポイント
| ポイント名 | 特徴 |
|---|---|
| ベイブリッジ真下やや左の防波堤周辺 | アジ目当ての釣り人が最も集まる一級ポイント |
| 緑地左端 | 壁際を攻めやすく実績あり |
| 緑地右端 | 比較的空いていることが多い |
| その他のエリア | 人気ポイント以外でもそれなりに釣れる可能性あり |
釣り方としては、足元付近や防波堤周りなど壁際でよく釣れる傾向があります。柵はあるものの、ふれーゆのように海面が極端に遠くはないため、比較的釣りやすい環境といえます。
アクセス面ではやや不便さがありますが、その分だけ釣り場の快適性は保たれているともいえるでしょう。冬場に水温が下がる時期でも、ここなら温排水の影響でアジが狙える可能性があります。22時以降も釣りを続けるなら防寒対策をしっかりして臨みましょう。
ふれーゆ裏は東京からアクセスしやすいが初心者には難易度高め
ふれーゆ裏は東京方面から横浜へアクセスする際に最も通いやすい釣り場の一つとして知られています。地理的な利便性の高さから、首都圏のアングラーにとって第一候補となることも多いでしょう。
しかし、アクセスの良さとは裏腹に、アジングの難易度は比較的高めと評価されています。noteの記事では「サビキでのアジはそこそこ狙えたが、初心者がアジングするには厳しかった」と振り返られています(出典:首都圏でのアジングについて)。
ふれーゆ裏が初心者に厳しい理由はいくつか挙げられます。まず、堤防から水面までの距離が遠く風の影響を受けやすいこと。軽量リグを扱うアジングでは風は大敵ですから、この点は大きなハンディキャップとなります。次に、根が多くボトムを探ると根がかりしやすいこと。海藻か何かが沈んでいることも多く、レンジを探る際の選択肢が狭まります。
さらに、アジの魚影がそこまで濃くない可能性も指摘されています。サビキでポツポツ釣れる程度の魚影だと、ルアーで効率よく釣り上げるのは経験とテクニックが必要になるでしょう。
⚠️ ふれーゆ裏の注意点
- 堤防の高さがあり水面まで遠い → 風の影響を受けやすい
- 根が多い → ボトム探索時に根がかり頻発
- 魚影がそれほど濃くない → ポイントやレンジを絞りにくい
- アジよりカサゴが多い傾向
- 駐車場が使えない(以前は使えたが現在は不可)
ただし、これらの難点を克服できれば、逆に腕を磨く良い練習場所になるかもしれません。実際、カサゴの魚影は濃いようなので、アジが渋い時はロックフィッシュゲームに切り替えるという選択肢もあります。根が多いということは魚の隠れ家も多いということですから、攻め方次第では面白い釣りができる可能性もあるでしょう。
駐車場が使えないため、夜間や早朝は車を停める場所がないという点も事前に確認しておくべきポイントです。路上駐車している人も多いようですが、もちろん推奨はできません。
東扇島西公園は釣り場環境は良いがアジングには向かない面も
川崎市にある東扇島西公園は、横浜からは少し離れますが、首都圏からのアクセスは悪くなく、釣り場としての環境が非常に整った場所です。広い駐車場、トイレ、釣具店の出張所も常駐しており、ファミリーフィッシングにも適した施設が整っています。
神奈川釣りポイントマップでは「駐車場もあるし、釣具店もある。またその釣具店から釣果情報を知ることもできる」と紹介されており、勇竿釣具店のウェブサイトで情報が確認できるとしています(出典:【アジング】神奈川(川崎・横浜)でアジ釣りができるポイント)。
しかしながら、アジングのポイントとしては必ずしも最適ではないという評価もあります。水深が深かったり、目立った障害物がなかったりと、アジのいるポイントが若干探りづらい地形になっているようです。アジングで釣れている人をあまり見かけないという証言もあり、どちらかというとサビキ釣りや泳がせでの青物狙いが盛んな釣り場という印象です。
🏞️ 東扇島西公園の評価
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| アクセス・設備 | ★★★★★ 駐車場、トイレ、釣具店あり |
| アジング適性 | ★★☆☆☆ 水深や地形的にやや不向き |
| 他の釣り | ★★★★☆ サビキ、青物の泳がせなど |
| 混雑度 | ★★★☆☆ 人気ポイントは激混み |
| マナー | ★☆☆☆☆ 一部常連のマナーが最悪 |
特に注意すべきは、一番人気の先端部分に常連が常時竿受けなどを設置して場所取りをしているという点です。さらに、そういった人たちのものと思われる釣り道具やガラクタが公園の一角に積まれているなど、常連のマナーは最悪との指摘もあります。こうした環境は初めて訪れる人にとってはかなりストレスになるかもしれません。
釣り場の環境が良いことと、釣りやすいことは別問題です。東扇島西公園は設備面では優れていますが、アジングという観点からは他のポイントを優先したほうが良いかもしれません。ただし、青物やサビキなど、他の釣りも楽しみたいという場合には選択肢に入るでしょう。
穴場スポットも存在するが釣り禁止エリアには要注意
横浜エリアには、ここまで紹介した有名ポイント以外にも数人しか入れないような穴場スポットが存在します。そうした場所では、タイミングが合えばかなりの数釣りができることもあるようです。
ただし、注意しなければならないのは、穴場の大半は釣り禁止エリアやグレーゾーンだということです。あるアングラーは「一応釣りが黙認?されており連日アジンガーが通っている穴場スポットもあり、数人しか入れないもののかなり数釣りができる。穴場スポットのため場所は伏せる」と述べつつ、ネットに釣り場情報を上げた人が叩かれていたことがあるとも指摘しています(出典:首都圏でのアジングについて)。
アングラーズなどの釣果投稿サイトを見ていると、明らかに釣り禁止エリアでの釣果を堂々と上げている例も散見されます。本牧や大黒周辺には立ち入り禁止区域も多く、そうした場所での釣りは法的にも倫理的にも問題があります。
🚫 釣り禁止エリアでの釣りがもたらすリスク
- 法的リスク:不法侵入として警察沙汰になる可能性
- 安全リスク:緊急時に救助が困難、事故の責任は自己負担
- 社会的リスク:釣り人全体のイメージ悪化、新たな規制強化につながる
- 倫理的問題:ルールを守る釣り人への不公平感
一時的に釣果が上がったとしても、長期的には釣り場の閉鎖や規制強化につながり、すべての釣り人にとってマイナスです。「黙認されている」という曖昧な状況に甘えるのではなく、明確に釣りが許可されている場所で楽しむべきでしょう。
どうしても穴場を開拓したいなら、自力で調査し、管理者に釣りの可否を確認するというプロセスを踏むことをおすすめします。インターネット上で安易に場所を公開しないという配慮も必要ですが、そもそも禁止エリアで釣りをしないという基本姿勢が最も重要です。
横浜は釣り場が少ない分、一つ一つの釣り場を大切にする意識が求められます。マナーを守り、環境を保全することが、将来にわたって釣りを楽しむための前提条件なのです。
横浜の陸っぱりアジングで釣果を上げるための実践テクニックと時期別攻略法
- 横浜アジングの好シーズンは5〜6月の産卵期と9〜11月の秋
- 真夏(7〜9月)は豆アジメインで軽量リグが必須となる
- 常夜灯周りでは明暗部を狙いドリフトで流す釣り方が効果的
- 強風時でも手前の岸壁際を攻めれば釣果が期待できる
- タックルは0.6g以下の軽量ジグヘッドを扱えるセッティングが理想
- ワームは小型が基本だが吸い込みやすい柔らかい大型も有効な場面がある
- 冬場(2月頃)は湾奥の水温低下で厳しいが外房方面なら可能性あり
横浜アジングの好シーズンは5〜6月の産卵期と9〜11月の秋
横浜エリアでアジングを楽しむなら、シーズンの見極めが釣果を大きく左右します。一年を通して狙えるとはいえ、やはり釣りやすい時期と難しい時期があるのは事実です。
最も釣りやすいとされているのが5月から6月のゴールデンウィーク前後です。この時期はアジの産卵シーズンにあたり、接岸してくる個体が多くなります。根岸港をはじめとする各ポイントで安定した釣果が期待でき、サイズも20cm前後のまずまずの型が中心となります。
次に狙い目なのが9月から11月にかけての秋シーズンです。あるブログでは「例年だと10月-12月のハイシーズン一歩手前。水温も徐々に下がってアジの高活性な適温になりつつある時期」「レンジ幅も広くどの層でもアジが居る(オールレンジ)なんて事もありうるので初心者にはこれからがもってこい」と紹介されています(出典:東京湾横浜|ボートアジング|メバリング【SkyreadFG】)。
📅 横浜アジングの年間スケジュール
| 時期 | 釣れやすさ | サイズ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1〜2月 | ★☆☆☆☆ | 小〜中 | 水温低下で厳しい時期 |
| 3〜4月 | ★★☆☆☆ | 小〜中 | 徐々に回復傾向 |
| 5〜6月 | ★★★★★ | 中〜大 | 産卵期で一級シーズン |
| 7〜8月 | ★★★☆☆ | 小 | 豆アジ中心、数釣り可能 |
| 9〜11月 | ★★★★★ | 小〜大 | 秋の好シーズン、初心者向き |
| 12月 | ★★★☆☆ | 中 | まだ釣れるが寒さ対策必要 |
春のシーズンでは体高のある脂ののった個体が多く、食べても非常に美味しいのが魅力です。秋はサイズにばらつきがあるものの、レンジが広くアジがどの層にもいる可能性があるため、初心者でも比較的釣りやすいといえます。
逆に厳しいのが真冬の1月から2月です。湾奥は水温が12℃以下になることもあり、アジの適水温である15℃を大きく下回ります。ただし、温排水の影響がある場所では冬でも可能性がゼロではありません。
シーズンを見極めることで、限られた時間を効率よく使い、確実に釣果につなげることができるでしょう。
真夏(7〜9月)は豆アジメインで軽量リグが必須となる
夏場の横浜アジングは豆アジが主体となり、春や秋とは異なるアプローチが求められます。対象が15cm以下の小型個体となるため、タックルセッティングから釣り方まで、繊細な対応が必要です。
ClearBlueのコラムでは、豆アジ狙いでは「針の長さ、大きさが違います」「釣る対象(アジの大きさ)を見極めてフックサイズを選ぶと良い」「針を小さくするだけではなく、普段使われているg数より より軽い物が必要」「0.6g以下を使えると攻略の近道」と解説されています(出典:横浜のこの時期のアジング)。
豆アジ攻略の最大のポイントは軽量リグを使いこなせるかどうかです。0.6g以下のジグヘッドを投げられない、あるいは海中でリグの存在感がわからないというレベルでは、なかなか釣果につながりません。まずは軽量リグの扱いに慣れることが大前提となります。
🎯 豆アジ攻略のタックルセッティング
| アイテム | 推奨スペック | 備考 |
|---|---|---|
| ジグヘッド | 0.4〜0.8g | 0.6g以下が理想的 |
| フックサイズ | 小型(例:#8〜#10) | 豆アジの口に合わせたサイズ |
| ワーム | 1〜2インチ | アジール2.0、ピンチ1など |
| ライン | エステル0.3号 | 感度重視のセッティング |
| リーダー | フロロ0.8〜1号 | 細めで吸い込みやすく |
ワーム選びでも工夫の余地があります。基本は小型ワームですが、実は吸い込みを妨げない柔らかい素材の大型ワームも効果的な場面があります。たとえばセクシービースーパーソフトのような柔らかいハンドメイドワームは、サイズがあってもアジが吸い込みやすく、アピール力も高いためアタリを引き出せる可能性があります。
「大きいから釣れない」という固定観念を捨て、柔らかさを利用してしっかり見せて食わせるという発想の転換が、時に釣果の差を生むのです。実際に使ってみることで、自分なりのパターンが見えてくるでしょう。
豆アジシーズンは数釣りが楽しめる一方で、繊細なアプローチが求められる奥深い釣りです。軽量リグの扱いをマスターすれば、豆アジだけでなく中型以上のアジにも有効なテクニックとなるため、ぜひ積極的に練習してみてください。
常夜灯周りでは明暗部を狙いドリフトで流す釣り方が効果的
横浜の陸っぱりアジングでは常夜灯周りが一級ポイントとなることが多く、明暗部を効果的に攻略できるかが釣果の鍵を握ります。都市部ならではの豊富な照明がアジを集めるため、光を味方につけた釣りが展開できるのです。
釣り方の基本はあまり大きなアクションを入れずにドリフトで流すことです。ClearBlueのコラムでは「経験上あまり動かさない方が良い」「ジッと竿先に意識をむけ潮の重みを感じる程度に張らず緩めず流して釣る【ドリフト】の釣りが良い」と解説されています(出典:横浜のこの時期のアジング)。
横浜特有の環境として、多くの釣り場で柵があり遠投しづらい状況があります。しかし実はアジは手前の岸壁際の浅い明暗を回遊していることがかなり多いのです。横に投げられれば良いですが、投げられない時は後ろに下がって岸壁際を狙うというテクニックも有効です。
💡 常夜灯周りの攻略ポイント
| 要素 | アプローチ方法 |
|---|---|
| 明暗部の境目 | 暗い側から明るい側へ流す |
| 岸壁際 | 足元〜近距離を重点的に探る |
| アクション | 大きく動かさずドリフト中心 |
| アタリの取り方 | ズズズというアタリでワンテンポ遅らせて合わせ |
| レンジ | 表層から中層、ボトム付近まで広く探る |
アタリの取り方にも特徴があります。豆アジの場合、通常のアジ特有の「コンっ」というアタリではなく、ズズズというようなアタリ方になることが多いです。このため、合わせもワンテンポ遅らせてゆっくりさびいてかけるほうがキャッチ率が上がります。
常夜灯の光は、プランクトンを集め、それを追ってベイトフィッシュが集まり、さらにそれを狙ってアジが寄ってくるという食物連鎖を作り出します。この仕組みを理解し、光と影のコントラストを意識することで、効率的にアジを狙えるようになるでしょう。
また、ワームの形状を利用してよりナチュラルに誘うことも重要です。流している最中にワームがテールを振動させたり、水流を受けて微妙に動いたりする様子をイメージしながら釣ると、違和感のない自然なアプローチができます。
強風時でも手前の岸壁際を攻めれば釣果が期待できる
アジングは軽量リグを扱うため風が強い日は避けるというアングラーも多いでしょう。しかし実は、強風時でも攻め方を変えることで釣果が期待できるのです。むしろ、強風で他のアングラーが少ない分、快適に釣りができることもあります。
あるブログでは強風向かい風のポイントで「4投目ぐらい」でアジがヒットし、「強風時はこれが快感。誰もいない中でこっそり釣れちゃう」と振り返っています。さらに「こういう強風時はリグが飛ばないんだけど、別にいいんです。だって手前にいるから。なんだったら本当足元付近にいる時も多いし」と解説しています(出典:初夏の横浜アジング3連戦!爆釣有名ポイントを避けた場所で釣る!)。
強風時の攻略法は以下のポイントに集約されます。まず、飛距離は諦めて手前を重点的に探ること。アジは足元付近にもいることが多いため、無理に遠投する必要はありません。次に、風が少し緩んだ瞬間を狙って投げること。突風を避けることでアタリも取りやすくなります。
🌬️ 強風時のアジング戦略
| 項目 | 通常時 | 強風時 |
|---|---|---|
| 狙うレンジ | 広範囲を探る | 手前〜中距離に集中 |
| キャストタイミング | 任意 | 風が緩んだ瞬間 |
| ジグヘッド重量 | 0.6〜1.5g | やや重め1.0〜2.0g |
| 釣り場選び | 人気ポイント | 向かい風でも釣れる穴場 |
| 混雑度 | 高い | 低い(快適) |
強風時はリグが飛ばないからこそ、手前にいるアジを狙いやすいというメリットもあります。一匹釣れると連発することも多く、群れが入っていればテンポよく釣り上げられるでしょう。
また、強風向かい風のポイントは週末でも空いていることが多いという利点もあります。混んでいる場所が苦手な人にとっては、むしろ好都合な状況といえるかもしれません。
ただし、安全面には十分注意が必要です。強風時は波も高くなりがちですし、足場が濡れて滑りやすくなることもあります。無理をせず、危険を感じたら早めに撤退する判断も大切です。
「風が強いから釣りに行かない」ではなく、「風が強い日は手前を攻める」という発想の転換が、新たな釣果につながるかもしれません。
タックルは0.6g以下の軽量ジグヘッドを扱えるセッティングが理想
横浜アジングで安定した釣果を上げるには、適切なタックルセッティングが欠かせません。特に豆アジが多いシーズンや、プレッシャーの高いポイントでは、繊細なアプローチが求められます。
ロッドは5〜6フィート台のアジング専用ロッドが扱いやすいでしょう。あるボートアジングガイドでは「ロッド:5-6.4feet(5feet台の短さは正義よ)」と紹介されています(出典:東京湾横浜|ボートアジング|メバリング【SkyreadFG】)。陸っぱりでも、取り回しの良さと感度のバランスを考えると、この範囲が理想的です。
リールは1000〜2000番のスピニングリールで、ラインはエステル0.3号が定番です。エステルラインは伸びが少なく感度に優れているため、軽量リグの着底やアタリを明確に捉えられます。リーダーはフロロカーボン0.8〜1号を20cm前後結ぶのが一般的です。
🎣 横浜アジング推奨タックルセッティング
| パーツ | スペック | 選定理由 |
|---|---|---|
| ロッド | 5〜6.4ft、アジング専用 | 取り回しと感度のバランス |
| リール | 1000〜2000番 | 軽量で疲れにくい |
| ライン | エステル0.3号 | 高感度、伸びが少ない |
| リーダー | フロロ0.8〜1号、20cm前後 | 吸い込みやすさと強度の両立 |
| ジグヘッド | 0.6〜2.0g | メインは1.5g、状況で使い分け |
| ワーム | 1〜2インチ各種 | 3〜4種類あれば十分 |
ジグヘッドは1.5gをメインに、水深や潮の速さによって2.0g、3.0gを使い分けるのが基本です。豆アジ狙いや浅場では0.6〜0.8gも用意しておくと良いでしょう。深場で潮が早い場合は4.0gが必要になることもあります。
ワームは「アジング」と記載されたものなら何でも基本的にはOKですが、形状によってバイトの質や量が変わる場合もあります。3〜4種類用意しておけば、状況に応じて使い分けられるでしょう。
注意点として、エステルラインは劣化しやすいため、定期的な巻き替えが必要です。「昨日巻き替えたばかり」と思っていても、保管状況によっては劣化している可能性があります。釣行前に必ずラインの状態を確認し、傷や毛羽立ちがあれば交換しましょう。
また、陸っぱりで使用しているアジングロッドでも、ジグヘッド単体に向かない強めのロングロッドは避けたほうが無難です。ロッドのパワーやアクションが軽量リグに合っていないと、せっかくの繊細なアタリを捉えられなくなります。
適切なタックルセッティングは、釣果を左右する基本中の基本です。初期投資は必要ですが、長く使えるものですから、しっかりしたものを揃えることをおすすめします。
ワームは小型が基本だが吸い込みやすい柔らかい大型も有効な場面がある
ワーム選びはアジングにおいて釣果に直結する重要な要素です。基本的には小型ワームが中心となりますが、状況によっては大型ワームが効く場面もあるため、柔軟な発想が求められます。
横浜の豆アジ狙いでよく使われるのは1〜2インチの小型ワームです。ClearBlueのコラムでは「アジール2.0インチ」や「ピンチ1インチ」がよく使われると紹介されています(出典:横浜のこの時期のアジング)。小型ワームは豆アジの小さな口にも吸い込まれやすく、フッキング率が高いのが利点です。
しかし、「小さければ良い」という単純な話ではありません。時にはボリュームのあるワームが劇的に効くこともあるのです。ポイントは吸い込みを妨げない柔らかさにあります。たとえばセクシービー2.0インチのようなハンドメイドワームは、通常のワームより柔らかく、特にセクシービースーパーソフトは極めて柔軟性が高いため、サイズがあってもアジが吸い込みやすいという特徴があります。
🪱 ワームの使い分け戦略
| 状況 | ワームタイプ | サイズ | 狙い |
|---|---|---|---|
| 豆アジメイン | 小型ストレート | 1〜1.5インチ | 吸い込みやすさ優先 |
| 活性が高い時 | 小型シャッドテール | 1.5〜2インチ | アピール力とナチュラルさの両立 |
| アタリが少ない時 | 柔らかい大型 | 2〜2.5インチ | 視認性とアピール力で誘う |
| 中型以上狙い | やや大きめ | 2〜3インチ | ベイトサイズに合わせる |
ワームのカラーも重要な要素です。常夜灯周りではクリア系やグロー系が定番ですが、日中や濁りがある時はピンクやオレンジなどの視認性の高いカラーが効果的な場合もあります。最低でも明るい色と暗い色を数種類ずつ用意しておくと、状況に応じて対応できるでしょう。
また、ワームのメンテナンスも忘れてはいけません。使用後はしっかり水洗いし、直射日光を避けて保管することで劣化を防げます。特に柔らかいワーム同士がくっついてしまうと使い物にならなくなるため、個別にパッケージングするか、仕切りのあるケースに入れることをおすすめします。
「釣れないからワームを変える」のではなく、「状況に合わせて最適なワームを選ぶ」という考え方が大切です。固定観念にとらわれず、様々なワームを試してみることで、自分なりの引き出しが増えていくでしょう。
冬場(2月頃)は湾奥の水温低下で厳しいが外房方面なら可能性あり
横浜アジングの数少ない弱点が真冬の水温低下です。特に2月頃は湾奥の水温が12℃以下になることもあり、アジの適水温である15℃を大きく下回ります。この時期は横浜でのアジングはかなり厳しい状況となります。
しかし、東京湾の外側に目を向ければ選択肢が広がります。あるアングラーは「冬(2月など)には水温が12℃以下になる時期がある」「そんな時期でも東京湾の外側であれば黒潮の影響を受けるため、水温が15℃程度あったりする」としてアクアラインを渡って外房(勝浦、鴨川周辺)などにアジングに通っていたと述べています(出典:首都圏でのアジングについて)。
外房エリアは黒潮の影響で冬場でも水温が比較的安定しており、15℃前後を保つことが多いようです。ただし、横浜とは違った釣り方が必要で、なかなか難しいという声もあります。一方で、横浜より大きいサイズが狙えるというメリットもあるようです。
🗺️ 冬場のエリア別水温と釣りやすさ
| エリア | 2月頃の水温 | 釣りやすさ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 横浜(湾奥) | 12℃以下 | ★☆☆☆☆ | 水温低下で厳しい |
| 三浦半島 | 13〜15℃ | ★★☆☆☆ | やや可能性あり |
| 外房(勝浦・鴨川) | 14〜16℃ | ★★★☆☆ | 黒潮の影響で安定 |
| 相模湾 | 14〜15℃ | ★★☆☆☆ | アジング情報は少なめ |
外房エリアでは、勝浦から鴨川あたりだけでも10箇所以上の漁港等が存在しており、開拓しがいのあるフィールドです。また、カマスシーズンにはとんでもない数のカマスが回ってくる漁港もあり、アジングタックルで狙うのも面白いでしょう。
ただし、2024年春あたりから勝浦港の釣り禁止エリアが広がるなど、外房も逆風が吹いている面があります。訪れる際は最新の釣り場情報を確認し、ルールを守って楽しむことが大切です。
冬場に無理に横浜で粘るよりも、水温の高いエリアに遠征するという選択肢を持つことで、年間を通してアジングを楽しめる可能性が広がります。少し足を伸ばす手間はかかりますが、新しいフィールドの開拓はそれ自体が楽しい経験となるでしょう。
また、横浜でも温排水の影響が強い場所であれば、冬でも可能性はゼロではありません。厳しいながらも挑戦してみる価値はあるかもしれません。
まとめ:横浜でアジングを陸っぱりで楽しむための総合ガイド
最後に記事のポイントをまとめます。
- 横浜は工業地帯からの温排水により周年アジングが可能な首都圏屈指のフィールドである
- 主要ポイントは根岸港、大黒ふ頭西緑地、ふれーゆ裏、東扇島西公園などだが特性が異なる
- 根岸港は5〜6月の産卵期に最も人気で夕マズメから日没後が狙い目である
- 大黒ふ頭西緑地は秋から冬がメインシーズンで壁際を攻めるのが効果的である
- 釣り場が少なく混雑しやすいため平日や時間帯をずらす工夫が必要である
- 穴場スポットも存在するが釣り禁止エリアでの釣りは絶対に避けるべきである
- ベストシーズンは5〜6月の産卵期と9〜11月の秋で初心者にもおすすめである
- 7〜9月の真夏は豆アジ中心となり0.6g以下の軽量リグが必須となる
- 常夜灯周りでは明暗部を狙いドリフトで流す釣り方が基本である
- 強風時でも手前の岸壁際を攻めれば釣果が期待できる
- タックルは5〜6フィート台のロッドにエステル0.3号の組み合わせが理想的である
- ワームは小型が基本だが柔らかい素材の大型ワームも状況次第で有効である
- 冬場(2月頃)は湾奥の水温低下で厳しいが外房方面なら可能性がある
- マナーを守り環境保全に努めることが横浜アジングの未来を守ることにつながる
- 情報収集とポイント選びが釣果を左右する重要な要素である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- だいぶ久しぶりの横浜おかっぱりアジング – 今週も鯵釣る? Season3
- 【アジング】神奈川(川崎・横浜)でアジ釣りができるポイント | 神奈川釣りポイントマップ
- 寒夜〜の横浜アジング✨ – かる〜く フィッシング
- 初夏の横浜アジング3連戦!爆釣有名ポイントを避けた場所で釣る!
- 東京湾横浜|ボートアジング|メバリング【SkyreadFG】スカイリード フィッシングガイド
- 【C&R釣物語】~おかっぱりアジングin横浜~ – CLAB
- 横浜のこの時期のアジング | アジング – ClearBlue –
- 横浜港~水江町公園 アジング 陸っぱり 釣り・魚釣り | 釣果情報サイト カンパリ
- 首都圏でのアジングについて|宮
- 横浜アジングの夏!アジは釣れれば良型!高級魚ムツも連発でお土産確保
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。