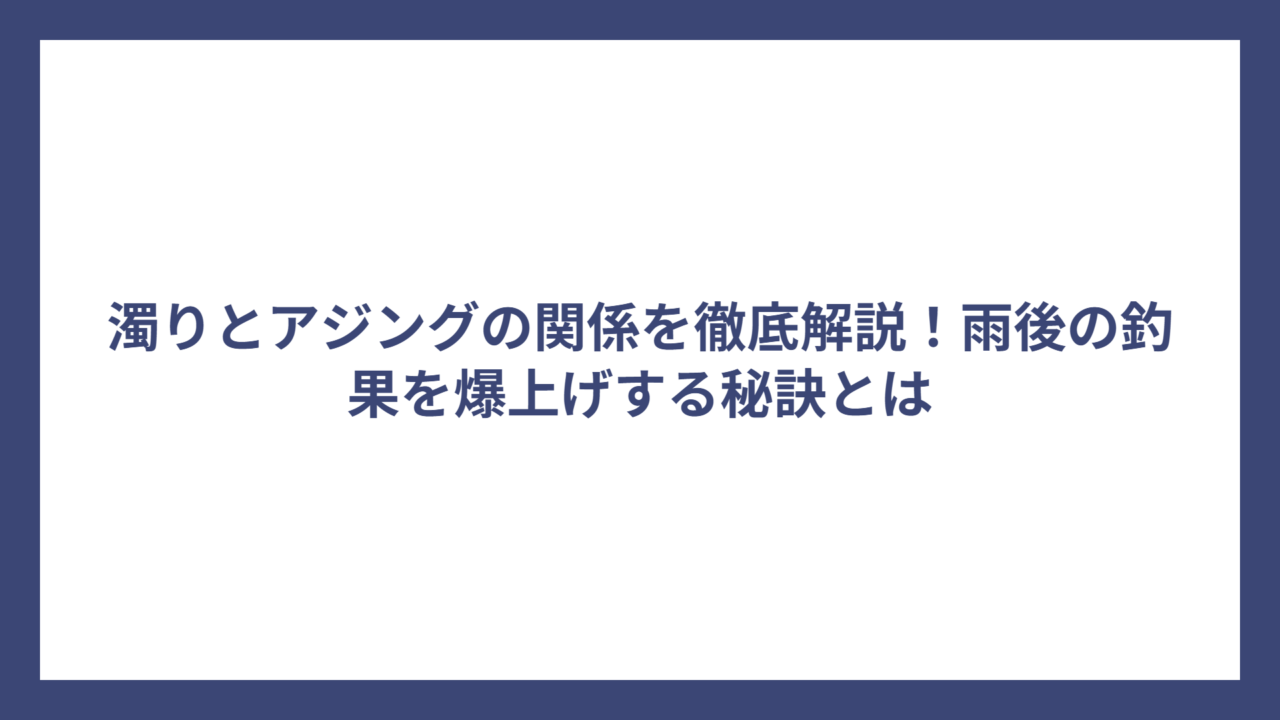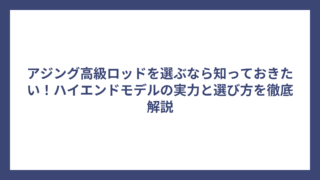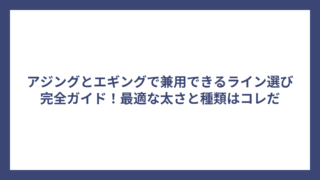「雨が降った翌日、海が濁っているけどアジングって釣れるの?」こんな疑問を持ったことはありませんか。実は、多くのアングラーが濁りに対してマイナスイメージを持っていますが、実際には濁りはアジングにとって必ずしも悪条件ではありません。むしろ、適度な濁りはアジの警戒心を和らげ、釣果アップにつながることもあるのです。
本記事では、インターネット上の様々な情報を収集・分析し、濁りの種類や程度に応じた攻略法、有効なワームカラーの選び方、ジグヘッドの重さやアクションの付け方まで、濁りアジングで釣果を上げるための実践的なテクニックを網羅的に解説します。雨上がりの釣行を諦める前に、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ 適度な濁りはアジの警戒心を下げ、釣果アップにつながる理由 |
| ✅ 濁りの種類(笹濁り・泥濁り・赤潮)による攻略法の違い |
| ✅ 濁り時に効果的なワームカラーとジグヘッドの選び方 |
| ✅ 雨後の水温変化や塩分濃度の影響とその対処法 |
濁りがアジングに与える影響と攻略の基本戦略
- 濁りはアジングにとってプラス要因になることが多い
- 雨による水温変化の方が濁りよりも影響が大きい
- アジは濁った水でも高い視認能力を持っている
- 濁りの種類によって釣果が変わる理由
- 激濁り時のワームカラーはマット系やチャート系が有効
- クリア系カラーが効かない状況の見極め方
- 濁り時のジグヘッドの重さ選択は重くするのが鉄則
濁りはアジングにとってプラス要因になることが多い
多くのアングラーが「濁り=釣れない」というイメージを持っているかもしれませんが、実際には適度な濁りはアジングにとってプラスに働くケースが多いのです。透明度が高すぎる澄み潮では、アジがルアーをじっくり観察してしまい、警戒心が高まる傾向があります。
澄めば澄むほど大きな群れは入ってきませんし、個体自体小さいです。
この情報から分かるように、むしろ澄んだ状況の方がアジの活性や群れのサイズに悪影響を及ぼす可能性があるのです。特にプレッシャーの高い港湾部では、濁りによってアジが常夜灯の真下や足元付近まで大胆に寄ってくるという報告が多数あります。
笹濁り程度の濁りであれば、アジのライズが派手に出たり、広範囲に餌を追う姿を目撃することもあるでしょう。実際に、経験豊富なアングラーの多くが「濁りの中でアジがバシャバシャとライズする状況を何度も見てきた」と証言しています。
ただし、注意すべきは濁りの程度です。笹濁りや適度な濁りは好条件ですが、透明度がほぼゼロに近いドロドロの激濁りになると、さすがにアジの視認性が極端に落ちるため釣果は下がる傾向にあります。
📊 濁りの程度と釣果の関係
| 濁りの状態 | 透明度 | アジの活性 | 釣果への影響 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| 澄み潮 | 5m以上 | やや低い | 警戒心が高まる | ★★☆☆☆ |
| 笹濁り | 2〜4m | 高い | プラス要因 | ★★★★★ |
| 適度な濁り | 0.5〜2m | 高い | プラス要因 | ★★★★☆ |
| 激濁り | 0.5m以下 | やや低い | マイナス要因 | ★★☆☆☆ |
| 泥濁り | ほぼ見えない | 低い | 大きなマイナス | ★☆☆☆☆ |
濁りを恐れずに、むしろチャンスと捉えて積極的に釣行することで、他のアングラーが諦めた状況で好釣果を得られる可能性が高まります。
雨による水温変化の方が濁りよりも影響が大きい
濁りそのものよりも、実は雨によってもたらされる急激な水温変化の方がアジの活性に大きな影響を与えることが多いのです。特に冷たい雨水が大量に流れ込むと、表層付近の水温が急低下し、アジが沖へ移動してしまったり、活性が著しく低下するケースがあります。
アジを含む魚類は変温動物であり、急激な水温変化には非常に敏感です。数度の水温変化でも行動パターンが大きく変わることがあるため、濁りよりもむしろ水温の安定性に注目すべきでしょう。
一方で、夏場の高水温時には逆に雨による水温低下が好影響をもたらすこともあります。高すぎる水温はアジの活性を下げる要因となるため、適度な雨による水温低下は活性を高めるきっかけになります。実際に「夏アジングで雨の翌日に爆釣した」という報告は少なくありません。
🌡️ 季節別・雨による水温変化の影響
| 季節 | 雨前の水温 | 雨後の変化 | アジへの影響 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 15〜18℃ | ±2〜3℃ | やや悪影響 | 深場を探る |
| 夏(6〜8月) | 25〜28℃ | -3〜5℃ | 好影響 | 積極的に狙う |
| 秋(9〜11月) | 20〜23℃ | -2〜4℃ | やや悪影響 | 水温が安定したポイントを選ぶ |
| 冬(12〜2月) | 10〜13℃ | -3〜5℃ | 悪影響大 | 釣行を避けるのも選択肢 |
河川に直結しているポイントでは、大雨の後に真水が大量に流れ込み、急激な水温低下が発生しやすいです。このような場所では、濁りよりも水温変化によってアジが抜けてしまう可能性が高いと考えられます。
逆に、河川から離れた外洋に面したポイントや、水深のある場所では、雨の影響が比較的小さく、表層だけが真水で覆われていても、ボトム付近は安定した水温・塩分濃度を保っていることがあります。このような場所では、濁りの影響を受けながらも、アジが底付近に留まっている可能性が高いでしょう。
アジは濁った水でも高い視認能力を持っている
「濁っていると魚は餌を見つけられないのでは?」という懸念を持つ方もいるかもしれませんが、実はアジは濁った水中でも高い視認能力を持っている魚です。そもそもアジの目は魚類の中でも大きく発達しており、暗い場所や濁った環境でも餌を見つけることができるとされています。
カフェオレみたいに濁りが入ってたとしても、釣れるところは釣れるし、とくに濁りが強いからグローって感じも無くてですねー。
この証言からも分かるように、カフェオレのような泥濁りでも、アジは普通のワームで釣れることが実証されています。発光させなくても、アジは十分にルアーを見つけて捕食できるのです。
アジの視覚能力が高い理由として、以下の特徴が挙げられます:
- 大きな眼球:体のサイズに対して目が大きく、光を取り込む能力が高い
- 側線の発達:水の振動を敏感に感じ取り、濁りの中でも餌の位置を把握できる
- 嗅覚の活用:視覚だけでなく嗅覚も使って餌を探す
したがって、濁りがあるからといって過度にアピール力の強いルアーを使う必要はなく、状況に応じた適切なカラー選択が重要になります。むしろ、激しすぎるアピールは逆効果になることもあります。
濁りの種類によって釣果が変わる理由
一口に「濁り」と言っても、その原因や性質によって釣果への影響は大きく異なります。大きく分けると、泥濁り、プランクトン濁り(赤潮・青潮)、砂濁りの3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
🌊 濁りの種類と特徴
| 濁りの種類 | 発生原因 | 色の特徴 | アジの反応 | 釣果への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 泥濁り | 大雨、河川からの流入 | 茶色〜黄土色 | やや低い | △ |
| プランクトン濁り | プランクトン大発生 | 緑色〜赤褐色 | 高い | ◎ |
| 砂濁り | 底荒れ、波浪 | 白濁 | 中程度 | ○ |
| 笹濁り | 軽度の雨、潮流 | やや緑がかった透明 | 非常に高い | ◎◎ |
泥濁りは河川からの雨水流入によって発生し、塩分濃度の低下や水温変化を伴うことが多いです。この場合、濁りそのものよりも水質の変化がアジに影響を与えます。
大雨で塩分濃度が極端にかわると喰いは悪くなると思います。プランクトンで濁る場合は喰いがよくなりますよ。
一方、プランクトン濁りは餌となるプランクトンが豊富な証拠であり、それを捕食する小魚、さらにそれを狙うアジという食物連鎖が成立しやすくなります。この種類の濁りは、アジングにとって最も好条件と言えるでしょう。
砂濁りは底荒れによって発生する白濁で、一時的なものが多いです。潮が動けば徐々に解消されるため、タイミングを見計らえば釣果を得やすい状況です。
赤潮については別途注意が必要です。赤潮は海水中の酸素濃度を低下させる可能性があり、魚の活性を著しく下げることがあります。赤潮が発生している海域では、おそらく釣果は期待しにくいと推測されます。
激濁り時のワームカラーはマット系やチャート系が有効
濁りが強い状況では、ワームのカラー選択が釣果を大きく左右します。一般的にはマット系やチャート系、グロー系のカラーが有効とされていますが、実際の使い分けには細かいコツがあります。
常夜灯+アジ=クリア系という定説に反してカラーは「マットなオレンジ系」をセレクト!すると2投目でキャッチに成功!
この実釣報告からも分かるように、濁りが強い状況では従来のセオリーである「常夜灯下ではクリア系」という定説が通用しないことがあります。視認性が悪い状況では、適度な存在感を出せるマット系カラーが圧倒的に有利なのです。
🎨 濁り度合い別のおすすめカラー
| 濁りの程度 | 第一選択 | 第二選択 | 避けるべきカラー | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 笹濁り | クリア+ラメ | ナチュラル系 | 強発光グロー | 適度な視認性で十分 |
| 適度な濁り | チャート | マットオレンジ | 濃いダーク系 | 目立ちつつなじむ |
| 激濁り | マット系チャート | 強発光グロー | クリア系全般 | 存在感が必要 |
| 泥濁り | ホワイト系 | マットピンク | 透明系 | コントラストが重要 |
マット系カラーは光の透過が少なく、ワーム自体のシルエットがはっきりと出るため、濁った水中でもアジが発見しやすいのです。特にオレンジやピンク、チャート系のマットカラーは、潮色になじみつつも適度な存在感を出すことができます。
チャート系カラーは視認性が非常に高く、濁りの中でも目立ちます。ただし、アピールが強すぎるとアジがスレてしまう可能性もあるため、連続して使用せず、ナチュラル系とローテーションすることをおすすめします。
ホワイト系カラーも濁り時には効果的です。特に泥濁りのような茶色系の濁りに対しては、白いワームのコントラストが際立ち、アジの反応が良くなる傾向があります。
クリア系カラーが効かない状況の見極め方
通常、常夜灯下やデイアジングではクリア系カラーが定番とされていますが、濁りが入った状況ではクリア系が全く効かなくなるケースがあります。この見極めができると、無駄な時間を省いて効率的に釣果を上げることができます。
クリア系カラーが効かない状況の特徴:
✅ 海面から50cm下が見えないほどの濁り ✅ 雨後の茶色〜黄土色の泥濁り ✅ 底まで濁りが入っている状況 ✅ 常夜灯の光が水中で拡散して見えない ✅ 数投してもアタリすら出ない
このような状況では、クリア系カラーは「存在感が薄すぎてアジが気づかない」可能性が高いです。早めに見切りをつけて、マット系やチャート系にチェンジすることをおすすめします。
逆に、クリア系が有効な濁り状況もあります:
✅ 表層だけが濁っていて底は澄んでいる ✅ 笹濁り程度の軽い濁り ✅ 常夜灯の光が水中まで届いている ✅ プランクトン濁りで透明度が1m以上ある
重要なのは、実際に海を見て濁りの質を判断することです。同じ「濁り」でも、その性質によって適切なカラーは変わります。釣り場に到着したら、まず海面をよく観察し、水の色、透明度、常夜灯の光の届き方などをチェックしましょう。
また、クリア系で反応がない場合は、すぐに別のカラーに変更する判断力も重要です。10投以上投げてアタリが出なければ、カラーローテーションのタイミングと考えて良いでしょう。
濁り時のジグヘッドの重さ選択は重くするのが鉄則
濁りが入った状況では、ワームのカラーだけでなくジグヘッドの重さ選択も重要なポイントになります。基本的には、濁り時には通常よりも重めのジグヘッドを使用するのが効果的です。
ジグヘッドを約3gに上げてやる。1投目でスコンとアタリがあってようやく1匹目を釣る事に成功。
この実釣例では、濁りが強い状況で3gのジグヘッドに変更することで釣果を得ています。重いジグヘッドを使う理由は以下の通りです:
⚓ 濁り時にジグヘッドを重くする理由
- より遠くへキャストできる:濁りで釣れるエリアが限定される中、遠投して潮通しの良い場所を探れる
- 深いレンジを効率よく探れる:表層が濁っていても底付近は澄んでいる可能性がある
- アクションにメリハリが出る:重いジグヘッドの方がフォール速度が速く、リアクションバイトを誘いやすい
- 潮流に負けない:濁りが入る状況は潮が動いていることが多く、軽いジグヘッドでは流されやすい
- 真水の影響を受けにくい:表層の真水エリアを素早く通過し、塩分濃度の安定した層を探れる
📏 状況別ジグヘッドの重さ選択ガイド
| 状況 | 通常時 | 濁り時 | 増加量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 常夜灯下(港湾) | 0.6〜1.0g | 1.2〜2.0g | +0.6〜1.0g | 濁りの程度で調整 |
| 外洋(漁港) | 1.0〜1.5g | 2.0〜3.0g | +1.0〜1.5g | 潮流も考慮 |
| 河口域 | 0.8〜1.2g | 1.5〜2.5g | +0.7〜1.3g | 真水の影響大 |
| デイゲーム | 1.5〜2.5g | 2.5〜4.0g | +1.0〜1.5g | 視認性確保 |
ただし、重すぎるジグヘッドは食い込みが悪くなる可能性もあるため、状況を見ながら微調整することが大切です。まずは通常の1.5倍程度の重さから試し、反応を見ながら調整していくと良いでしょう。
また、濁りが入るとアジが散っている可能性も高いため、広範囲を探る意味でも遠投できる重めのジグヘッドは有利です。特に河口域では、濁りの境目付近にアジが溜まっていることがあり、そこまで届かせるためには重めのジグヘッドが必須となります。
濁りアジングで釣果を上げるワームカラーと実践テクニック
- 夜の濁りアジングはボトム付近を重点的に探る
- 赤潮による濁りは釣果に悪影響を及ぼす可能性がある
- 河口付近の濁りエリアは意外と好ポイント
- 濁りに強いワームの特徴とおすすめアイテム
- 濁り時のアクションはメリハリを付けることが重要
- グローカラーの使い方は発光させないテクニックもある
- まとめ:濁りアジングを制するための総合的なアプローチ
夜の濁りアジングはボトム付近を重点的に探る
夜間に濁りが入っている状況では、ボトム付近を重点的に探るのが効果的です。雨によって表層に真水が流れ込むと、比重の関係で表層と底層で大きく環境が異なることがあります。
連日の雨で表層は真水の影響が強くなっていると考え、昼も夜も、なるべく雨の影響が少ないであろうボトム付近を中心に狙いました。
表層が真水で覆われると、そこは塩分濃度が低く、水温も不安定になります。アジは塩分濃度の変化には比較的強い魚ですが、急激な変化には弱いため、安定した塩分濃度のボトム付近に身を寄せる傾向があります。
🎣 夜の濁りアジング・レンジ攻略法
| 時間帯 | 優先レンジ | カウント数 | アクション | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 日没直後 | ボトム〜中層 | 15〜20 | スロー系 | まだ表層に真水の影響が残る |
| 夜間(前半) | ボトム中心 | 20〜30 | ストップ&ゴー | 最も安定した環境 |
| 夜間(後半) | 中層〜ボトム | 10〜20 | やや速めのリトリーブ | 潮が動き始める |
| 夜明け前 | 全レンジ | 5〜25 | 様々試す | アジが浮き始める |
ボトムを探る際の具体的なテクニックとしては、以下が有効です:
- カウントダウンでしっかり底を取る:濁りで底が見えないため、着底を確実に感じ取る
- ボトムから1mまでの範囲を丁寧に探る:この範囲にアジが集中している可能性が高い
- チョンチョンアクション+カーブフォール:メリハリをつけてアピール
- テンションフォール中のアタリを見逃さない:濁り時はフォール中のバイトが多い
ただし、ボトム付近にはゴミや障害物が沈んでいることもあるため、根掛かりには注意が必要です。特に雨後は流木や枯れ枝なども流れ込んでいる可能性があるため、ロストを覚悟の上で攻める必要があります。
また、潮が動き始めるタイミングでは、表層の真水も沖へ流れていくため、徐々にレンジを上げていくのも効果的です。時間帯による水の動きを意識しながらレンジを調整することで、効率的にアジを探すことができるでしょう。
赤潮による濁りは釣果に悪影響を及ぼす可能性がある
濁りの中でも特に注意が必要なのが赤潮による濁りです。赤潮はプランクトンの大発生によって海水が赤褐色や緑色に変色する現象で、一見すると餌が豊富で好条件に思えますが、実際には釣果に悪影響を及ぼすケースが多いのです。
赤潮が釣りに与える悪影響:
❌ 海中の酸素濃度が低下する:プランクトンの呼吸により酸素が消費される ❌ 魚の活性が著しく低下する:酸欠状態で食欲が落ちる ❌ 魚が沖へ逃げる可能性:居心地の悪い環境から離れようとする ❌ 魚が口を使わなくなる:ストレス状態で捕食行動が鈍る
特に夏場に発生しやすい赤潮は、高水温と相まって海中の酸素濃度を極端に下げることがあります。この状況では、おそらくアジも岸から離れた場所へ移動してしまい、おかっぱりからの釣果は期待しにくいと推測されます。
ただし、赤潮にも種類があり、すべての赤潮が悪影響をもたらすわけではありません。一般的には以下のように分類できます:
🔴 赤潮の種類と影響
| 赤潮の種類 | 色の特徴 | 発生時期 | 影響度 | 釣果への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 渦鞭毛藻類 | 赤褐色 | 7〜9月 | 大 | ×× |
| 珪藻類 | 茶色〜黄土色 | 春・秋 | 小〜中 | △ |
| 鞭毛藻類 | 緑色 | 夏 | 中 | × |
| 藍藻類 | 青緑色 | 夏 | 中〜大 | × |
赤潮が発生しているかどうかの判断ポイント:
- 水面に油膜のようなものが浮いている
- 海水が異常に着色している(赤・緑・茶など)
- 生臭い匂いがする
- 小魚が水面でパクパクしている
- 死んだ魚が浮いている
これらの兆候が見られる場合は、無理に釣行せず、別のポイントを探すか、日を改めることをおすすめします。赤潮の状況下で粘っても釣果が上がる可能性は低く、時間を無駄にしてしまう可能性が高いでしょう。
河口付近の濁りエリアは意外と好ポイント
一見すると避けたくなる河口付近の濁りエリアですが、実は意外と好ポイントになることがあります。河口域は濁りと澄み潮の境目ができやすく、そこにベイトフィッシュやアジが集まることが多いのです。
よくあるのが、河川から濁った水が入り込んだり、潮の流れによって澄んだ水と濁った水が喧嘩しているような状態。こういう時はついつい水が澄んでいる場所の方が釣れるような感じもするけど、むしろ濁った場所にアジが差してきていることもあったり・・・。
河口域が好ポイントになる理由:
🌊 河口域のメリット
- 餌が豊富:川から流れてくる有機物や虫などがベイトを引き寄せる
- 潮目ができやすい:濁りと澄み潮の境目にアジが集まる
- 変化が多い:塩分濃度や水温の変化がアジの捕食スイッチを入れる
- 警戒心が薄れる:濁りによってアジの警戒心が下がる
- 他のアングラーが少ない:敬遠されがちなエリアのため競争が少ない
河口域で釣る際のポイント:
✅ 濁りの境目を狙う:完全な濁りではなく、澄み潮との境界線を探す ✅ やや重めのジグヘッドで遠投:濁りの中の良い潮を探す ✅ レンジは中層〜ボトム:表層の真水を避ける ✅ アクションはメリハリを付ける:濁りの中でも存在をアピール ✅ 潮が動くタイミングを狙う:満潮前後や潮止まり前が狙い目
ただし、河口域での釣りには注意点もあります。大雨直後は流木や枯れ枝などのゴミが大量に流れてきており、ラインブレイクやロストのリスクが高まります。また、急激な水温変化や塩分濃度の低下により、一時的にアジが抜けてしまうこともあるでしょう。
河口域での釣りは、雨が止んで1〜2日経過してからがベストタイミングと言えます。ゴミも落ち着き、水質も安定してくる頃には、餌を求めてアジが戻ってくる可能性が高いのです。
濁りに強いワームの特徴とおすすめアイテム
濁りの状況で釣果を上げるには、ワームの選択も重要です。濁りに強いワームには、いくつかの共通した特徴があります。
💡 濁りに強いワームの特徴
| 特徴 | 効果 | 具体例 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| マット系ボディ | シルエットが明確 | マットオレンジ、マットピンク | ★★★★★ |
| 強発光グロー | 暗闇でも目立つ | クレイジーグロー系 | ★★★★☆ |
| ラメ入り | 光を反射してアピール | ゴールドラメ、シルバーラメ | ★★★★☆ |
| 大きめシルエット | 視認性が高い | 2.5inch以上 | ★★★☆☆ |
| コントラストカラー | 潮色との差別化 | ホワイト、チャート | ★★★★★ |
実際の商品例として、以下のようなワームが濁り時に効果的とされています:
🐟 濁り時のおすすめワームカラー
常夜灯下・港湾部向け:
- アジール2.0「アミライム」:適度な濁りに最適
- アジール2.0「クレイジーオレンジ」:激濁り対応の強発光
- セクシービー2.0「ゴールドキウイ」:マット系で視認性良好
外洋・離島向け:
- アジール2.0「チャートグローホロ」:濁りの中でも目立つ
- アジール2.0「クレイジーブルー」:激濁り対応
- セクシービー2.0「ホワイトキャンディ」:コントラストが効く
ラメの選び方:
- ゴールドラメ:弱いアピール、笹濁り〜適度な濁りに
- 赤ラメ・黒ラメ:強いアピール、濁りが強い時に
- ホログラムラメ:中程度のアピール、オールマイティ
ワームのサイズについても、濁りの程度によって使い分けることが推奨されます。軽い濁りなら通常サイズ(1.5〜2.0inch)で問題ありませんが、激濁りの場合は**やや大きめのサイズ(2.0〜2.5inch)**を選ぶことで、シルエットを大きくして視認性を高めることができます。
また、濁り時にはワームのローテーションも重要です。同じカラーを使い続けるとアジがスレてしまうため、3〜5匹釣ったら別のカラーに変更するのが効果的でしょう。特にアピール系のカラーは飽きられやすいため、ナチュラル系と交互に使うことをおすすめします。
濁り時のアクションはメリハリを付けることが重要
濁りが入った状況では、ワームのカラーやジグヘッドの重さだけでなく、アクションの付け方も釣果を左右する重要な要素です。基本的には、濁りの中でもアジがワームの存在に気づけるよう、メリハリのあるアクションを心がけることが大切です。
濁っている時は表層付近に小型のベイトが溜まりやすかったりするので、アジのレンジが普段より上になることが多いように感じる。
🎯 濁り時の効果的なアクションパターン
| アクション名 | やり方 | 効果 | 使用タイミング | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| チョンチョン+カーブフォール | 2〜3回軽くロッドを煽ってフォール | メリハリで存在アピール | 基本技、常時使える | ★☆☆☆☆ |
| ストップ&ゴー | 3秒巻いて2秒止める | 波動でアピール | 中層〜表層 | ★☆☆☆☆ |
| リフト&フォール | 大きくロッドを上げて落とす | リアクションバイト誘発 | ボトム付近 | ★★☆☆☆ |
| ただ巻き(やや速め) | 一定速度で巻く | サーチ的に使える | 全レンジ | ★☆☆☆☆ |
| テンションフォール | ラインをピンと張った状態で落とす | バイトを取りやすい | ボトム〜中層 | ★★★☆☆ |
濁り時のアクションで特に意識すべきポイント:
✅ 動きと静のメリハリをつける:チョンチョンとアクションさせた後、ピタッと止めて「間」を作る ✅ フォールスピードを調整:濁りが強い時はやや速めのフォールでリアクションを狙う ✅ レンジキープを意識:アジが溜まっているレンジを見つけたら、そこを重点的に探る ✅ アタリはフォール中が多い:特にテンションフォール中のアタリを見逃さない ✅ ロッドワークは小刻みに:大きなアクションよりも小刻みな動きの方が効果的
逆に、濁り時に避けるべきアクション:
❌ デッドスローのただ巻き:濁りの中では存在感が薄すぎる ❌ 長時間の放置:アジが気づかずに通り過ぎてしまう ❌ 激しすぎるジャーク:不自然な動きで警戒される可能性 ❌ 同じパターンの繰り返し:飽きられてスレる原因に
アクションの効果を最大化するためには、潮の流れも意識することが重要です。濁りが入る状況は潮が動いていることが多いため、潮の流れに逆らってワームを動かすことで、より自然な動きを演出できます。
また、アジの活性によってもアクションを変える必要があります。高活性時は速めのアクションでも食ってきますが、低活性時はスローでナチュラルなアクションの方が効果的でしょう。状況を見ながら柔軟にアクションを変えていくことが、濁りアジングで釣果を上げる鍵となります。
グローカラーの使い方は発光させないテクニックもある
濁り時の定番カラーとして知られるグロー系ワームですが、実は「発光させない使い方」も存在します。多くのアングラーはグローカラーを使う際、ライトでしっかり蓄光させて使いますが、状況によってはあえて光らせない方が効果的なケースもあるのです。
あえて光を当てることなくグローカラーのルアーを使ったりすることで、弱く発光することで魚の反応が良くなるパターンもある。
グローを光らせすぎることのデメリット:
⚠️ 過度な発光による問題点
- アピールが強すぎてアジがスレる
- 不自然な光でアジが警戒する
- 連続使用で効果が急速に低下する
- プレッシャーの高いポイントでは逆効果
🌙 グローカラーの使い分け戦略
| 状況 | 蓄光方法 | 発光レベル | 使用タイミング | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 激濁り | ライトで10秒以上 | 強 | 先行者がいない時の第一投 | ★★★★★ |
| 適度な濁り | ライトで3〜5秒 | 中 | 通常時の基本 | ★★★★☆ |
| 笹濁り | 蓄光なし | 弱 | アジがスレてきた時 | ★★★☆☆ |
| 月明かりが強い夜 | ライトで10秒以上 | 強 | 強い光に負けないため | ★★★★☆ |
| プレッシャー高 | 蓄光なし〜弱め | 弱 | 警戒心を和らげる | ★★★★☆ |
グローカラーを効果的に使うテクニック:
- 初めは強発光で使う:まずは強くアピールして反応を見る
- 反応が鈍ったら弱発光に切り替え:スレ対策として蓄光を弱める
- スポットグローを活用:ワーム全体ではなく部分的に光るタイプを使う
- 発光色を変える:グリーン→オレンジ→ブルーなど、色を変えて目先を変える
- 時間を空けて再度使う:しばらくナチュラル系を使った後、再びグローを投入
発光色による使い分けも重要です。一般的に、グリーン系グローが最もバランスが良く、多くの状況で使えます。オレンジ系グローはやや弱めの発光で、スレ対策に有効です。ブルー系グローは強い発光で、激濁りや月明かりが強い夜に効果的とされています。
また、グローカラーは投入するタイミングも重要です。最初から使うのではなく、ナチュラル系のカラーで反応が悪い時や、他のアングラーが帰った後など、「ここぞ」というタイミングで投入することで、爆発的な釣果につながることもあります。
まとめ:濁りアジングを制するための総合的なアプローチ
最後に記事のポイントをまとめます。
- 適度な濁りはアジの警戒心を和らげ、釣果アップにつながる好条件である
- 濁りよりも雨による急激な水温変化の方がアジの活性に大きな影響を与える
- アジは濁った水中でも高い視認能力を持ち、普通のワームでも十分に捕食できる
- 濁りには泥濁り、プランクトン濁り、砂濁りがあり、それぞれ攻略法が異なる
- 激濁り時はマット系やチャート系のワームカラーが圧倒的に有効
- クリア系カラーが効かない状況は、底まで濁りが入っている時や泥濁りの時
- 濁り時はジグヘッドを通常の1.5倍程度の重さに変更し、遠投して深場を探る
- 夜の濁りアジングではボトム付近を重点的に攻めることで釣果が安定する
- 赤潮による濁りは酸素濃度を低下させ、アジの活性を著しく下げる可能性がある
- 河口付近の濁りエリアは餌が豊富で、濁りと澄み潮の境目に魚が集まりやすい
- 濁りに強いワームの特徴はマット系ボディ、強発光グロー、ラメ入りである
- 濁り時のアクションはチョンチョン+カーブフォールなどメリハリを付ける
- グローカラーは状況に応じて発光の強さを調整し、あえて光らせない使い方も有効
- ワームのローテーションを行い、3〜5匹釣ったら別のカラーに変更する
- 濁りの程度、時間帯、潮の動きを総合的に判断して戦略を立てることが重要
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- Yahoo!知恵袋 – アジは濁ると釣れなくなりますか?
- アングリングネット – 濁り潮でもアジは釣れます♪〜勝負の決め手はワームカラーにあり!〜
- まるなか大衆鮮魚 – アジングにおける雨・濁りの影響とカラーセレクトのパターン例
- リグデザイン – アジングは雨でもできる?その影響と濁りに対する問題点を洗いざらい書き出してみる
- ぽけっとの小物GOMOKU日誌 – 雨上がりの泥濁りの海でもアジは釣れるのかな?
- ルアーニュースR – 家邊克己が大雨の激濁りの中でアジングをして新たに気付いたこと
- TULINKUBLOG – 激濁りアジング×有効カラー
- ルアーニュースR – おかっぱりアジング 抹茶オーレ系の激濁り状況で効くワームのカラーとは?
- ClearBlue – 初めに揃えるワームカラー
- あおむしの釣行記 – 赤潮による濁りアジング、ちょいと遠投してなんとかボーズ回避
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。