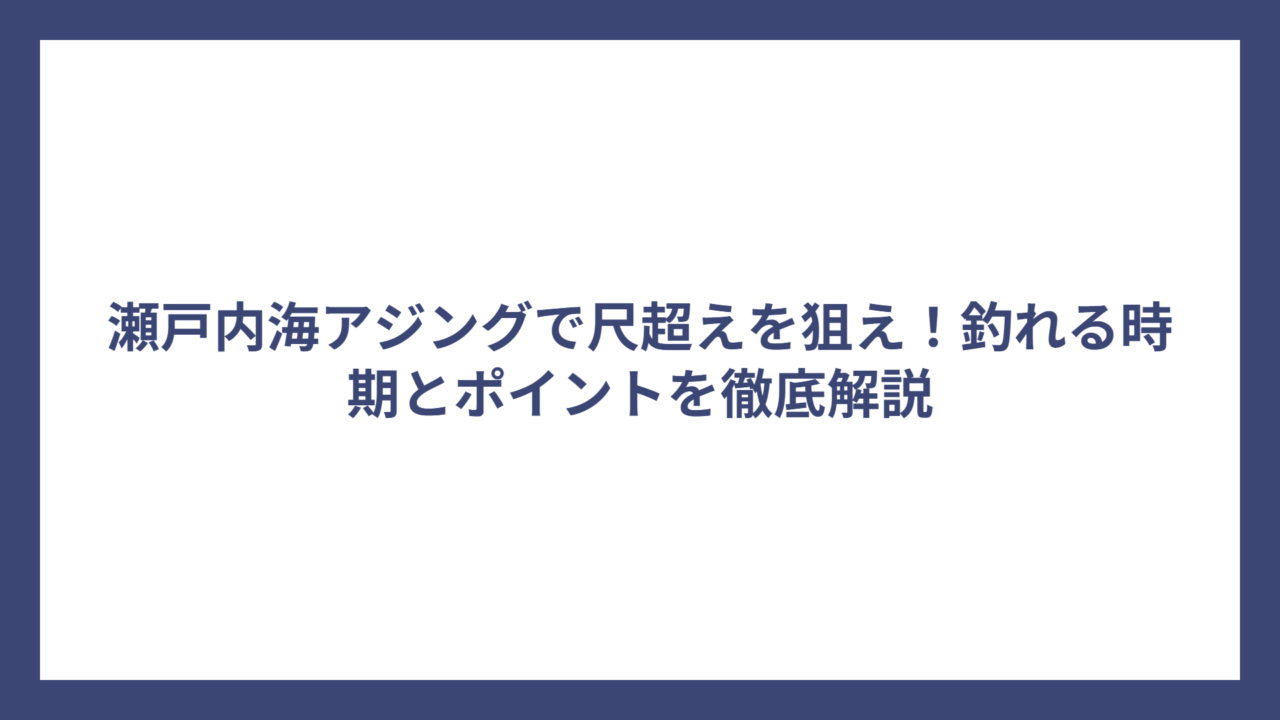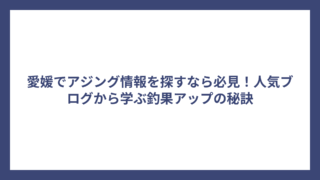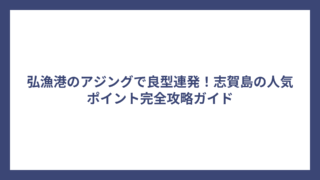瀬戸内海は多島海と呼ばれ、無数の島々が点在する日本有数の釣り場です。潮流が速く、鳴門のマダイや明石のマダコなど、ブランド魚介類を生み出すこのエリアは、実はアジングにおいても”聖地”と呼ばれるフィールドが数多く存在します。かつては「希少種」とまで言われていた瀬戸内海のアジですが、近年では魚影が濃くなり、2桁釣果も珍しくなくなってきました。さらに、20cm前後はもちろん、尺超え、さらには40cm~50cmオーバーの「ギガアジ」まで狙える夢のようなフィールドなのです。
本記事では、インターネット上に散らばる瀬戸内海アジングの情報を収集・分析し、釣れる時期やポイント、具体的なテクニックまでを網羅的に解説します。しまなみ海道周辺、釣島、祝島といった有名スポットの特徴や、季節ごとの攻略法、実際に効果的なリグやカラーの選び方まで、独自の視点で考察を加えながらお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 瀬戸内海アジングの最適シーズンと季節別攻略法 |
| ✓ 釣島・祝島・しまなみ海道など注目スポットの特徴 |
| ✓ ジグ単・ドリフト釣法など実践的テクニック |
| ✓ タイミングとレンジの見極め方 |
瀬戸内海アジングの基本戦略と釣れる時期
- 瀬戸内海アジングの特徴は魚影の濃さと大型の期待値
- 最も釣れる時期は初夏と冬の2シーズン
- 季節パターンを意識することが釣果アップの鍵
- タイミングを見極めるには潮流の変化を読む
- ジグ単が基本で1g前後のウェイトが最適
- ドリフト釣法で広範囲を効率的に探る
- レンジを刻むことがアジを見つける最短ルート
瀬戸内海アジングの特徴は魚影の濃さと大型の期待値
瀬戸内海のアジングが他のエリアと一線を画す最大の特徴は、魚影の濃さとサイズの期待値の高さです。一般的に、瀬戸内海は干満差が大きく、場所によっては4mもの潮位差が発生します。この潮流の強さが豊富なプランクトンを運び、それを追ってベイトフィッシュが集まり、さらにそれを捕食するアジが回遊してくるという好循環が生まれているのです。
特に注目すべきは、近年の魚影の回復傾向です。しまなみ海道周辺では、かつて「希少種」とまで言われていたアジが、今では安定して釣果を期待できるようになりました。2桁釣果も珍しくなく、かつては完全にオフシーズンとされていた2~3月でさえ、まばらながら釣れるほどになっています。仲間内では1~12月まで毎月釣果報告があるというから驚きです。
さらに魅力的なのがサイズ面です。瀬戸内海では20cm前後のアジは「普通サイズ」で、25cm前後が平均的な釣果となる場所も少なくありません。そして、アングラーなら誰もが憧れる尺超え(30cm以上)のアジも十分に狙える範囲内。特に釣島や祝島といった離島では、尺クラスが当たり前で、40cm~50cmオーバーの「ギガアジ」も夢ではないとされています。
瀬戸内海の地形的特徴も見逃せません。多くの島々で形成される水道(島と島の間の海峡)に面したポイントが豊富で、それぞれが異なる潮流や水深の特性を持っています。このため、「湾内や潮溜まりを探る緩い釣り」から「ドリフトを多用した流し込む釣り」まで、多様なアプローチが可能です。同じエリア内でも、ポイントを変えれば全く異なる釣りを楽しめるのが、瀬戸内海アジングの奥深さと言えるでしょう。
初心者にとっても優しいフィールドであることも特筆すべき点です。魚影が濃いため、基本的なテクニックさえ押さえておけば、数釣りは十分に可能です。サビキ釣りなどの伝統的な釣法はもちろん、近年人気のアジング(アジのルアーフィッシング)でも、比較的容易にファーストフィッシュを手にできるでしょう。ただし、「釣れる」と「釣り続ける」は別の話。安定した釣果を出し続けるには、このエリアならではのセオリーを理解する必要があります。
最も釣れる時期は初夏と冬の2シーズン
瀬戸内海アジングには、初夏(5~7月)と冬(12~2月)という2つの明確なハイシーズンがあります。それぞれのシーズンで狙えるサイズや釣り方、アジの行動パターンが異なるため、季節に応じた戦略が求められます。
🌊 季節別の特徴比較表
| シーズン | 狙えるサイズ | 魚影 | 特徴 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 初夏(5~7月) | 20~30cm | 非常に濃い | 産卵後の回復期、ベイトを積極的に追う | ★★☆☆☆ |
| 夏(7~8月) | 豆アジ中心 | 濃い | 尺アジと豆アジの入れ替わり時期 | ★☆☆☆☆ |
| 秋(9~11月) | 20~25cm | 普通 | 徐々にサイズアップ | ★★★☆☆ |
| 冬(12~2月) | 25~35cm以上 | やや薄い | 大型狙いのベストシーズン | ★★★★☆ |
| 早春(3~4月) | 20~30cm | 薄い | 回遊性が高い | ★★★★☆ |
**初夏シーズン(5~7月)**は、瀬戸内海アジングの最盛期です。産卵を終えたアジが体力回復のため活発にベイトフィッシュを追う時期で、数・型ともに期待できます。この時期のアジは回復のために栄養を求めているため、ベイトの多い場所を選ぶことが成功の鍵となります。しまなみ海道周辺では、この時期に20cm~尺クラスまでが安定して釣れるとされています。
「瀬戸内の中央部に位置する、広島~愛媛県を結ぶ『しまなみ海道』周辺のアジングは例年、この初夏の時期にハイシーズンをむかえます。」
一方、**冬シーズン(12~2月)**は、数は減るものの大型を狙える貴重な時期です。外気の冷え込みは厳しくなりますが、多くの釣り人が憧れる大型のアジがねらえる季節となっています。冬場のアジは脂がのり、味も他の季節以上に良くなるという嬉しいおまけ付きです。特に瀬戸内海では、尺前後サイズが狙える絶好のタイミングとされており、アベレージサイズも25cm前後と悪くありません。
ただし、冬シーズンには注意点もあります。天候の急変とアジの足の早さです。数日前まで爆発的に釣れていた場所でも、当日には全く反応がないということもよくあるそうです。そのため、直近の釣果情報をこまめにチェックし、タイミングを逃さないことが重要になります。
季節パターンを意識することが釣果アップの鍵
瀬戸内海アジングで安定した釣果を出すためには、季節ごとのパターンを理解し、それに応じた戦略を立てることが不可欠です。しまなみ海道は南北に広がるエリアで、季節ごとに釣れる場所もパターンも様々ですが、大まかな傾向を把握しておくことで、アジとの遭遇率を格段に上げることができます。
📅 月別攻略パターン
| 時期 | 主な特徴 | 狙うべき場所 | ポイント選びのコツ |
|---|---|---|---|
| 3~4月 | 回遊性が高い | 潮流の変化が大きな場所 | 潮通しの良い水道部 |
| 5~6月 | 産卵後の回復期 | ベイトの多い場所 | 湾内や常夜灯周り |
| 7~8月 | 尺アジと豆アジの入れ替わり | サイズを意識した場所選び | 深場寄りor外洋側 |
| 9~11月 | 徐々に深場へ | 深めのポイント | ボトム中心の攻略 |
| 12~2月 | 大型が接岸 | 実績のある深場 | じっくり狙う |
3~4月の早春パターンでは、アジの回遊性が非常に高くなります。このため、潮流の変化の大きな場所が有利とされています。島と島の間の水道部や、岬の先端など、潮がぶつかるようなポイントを選ぶと良いでしょう。ただし、この時期はまだ水温が低く、アジの活性も不安定です。一発大型が期待できる反面、ボウズのリスクも高い、やや難易度の高いシーズンと言えます。
5~6月の初夏パターンは、最も釣りやすい時期です。産卵を終えたアジが体力回復のため、積極的にベイトフィッシュを追います。この時期はベイトの多い場所を選ぶことが成功の鍵です。小魚の群れが見える湾内や、常夜灯周りにプランクトンが集まる港内などが狙い目になります。朝夕のマズメ時はもちろん、夜間でも好釣果が期待できる時期です。
7~8月は少し特殊な時期で、尺アジと豆アジの入れ替わり時期となります。産卵を終えた大型のアジが徐々に深場へ移動し、代わりに当歳魚(その年生まれの小型個体)が浅場に入ってきます。数釣りを楽しみたいなら豆アジ狙い、サイズを求めるなら深場寄りや外洋側を攻めるという、サイズを意識した場所選びが重要になります。
冬に向かう9~11月は、アジが徐々に深場へ移動する過渡期です。水温の低下とともに、浅場での釣果は徐々に減少し、深めのポイントやボトム付近を意識した釣りが効果的になってきます。そして12~2月の真冬になると、大型のアジが深場の実績ポイントに集まります。この時期は数は期待できませんが、じっくりと粘ることで尺超えクラスとの出会いが待っているかもしれません。
このように季節感を意識して出かけることで、早くアジに出会える確率が高まります。もちろん、年によって海水温の変化や潮の状況は異なるため、あくまで目安として捉え、現地の最新情報と組み合わせて判断することが大切です。
タイミングを見極めるには潮流の変化を読む
瀬戸内海アジングにおいて、潮流の変化を読むことは、季節パターンの理解と並んで極めて重要なスキルです。瀬戸内海は干満差が大きく、潮の動きが魚の活性に直結するフィールドです。アジの回遊するタイミングを狙うことがキモとなります。
🌊 潮汐と釣果の関係
潮の動きとアジの活性には、明確な相関関係があります。一般的に、潮が動き始める時間帯や満潮・干潮の前後が好機とされています。特に瀬戸内海では、満潮前後がタイミングとなり、転流(潮の流れる向きが変わる瞬間)によって釣れ始めるパターンが多く報告されています。
「瀬戸内アジングでは、アジの回遊するタイミングを狙うことがキモとなります。例えば、満潮前後がタイミングとなり、転流によって釣れ始めるパターン。アジの実績のある場所で、このような潮流の変化がある時はチャンス!」
ただし、「いるけど食わない」「レンジがあっていない」ということも往々としてあります。アジがポイントに入っていることは確実でも、なぜか反応がない…そんな経験は誰にでもあるはずです。そんな時こそ、潮の動きを注意深く観察し、あの手この手を試すことが求められます。
⏰ 時間帯別の攻略ポイント
| 時間帯 | 潮の状態 | アジの行動 | 攻略法 |
|---|---|---|---|
| 朝マズメ | 上げ始め~上げ7分 | 表層~中層で活発 | 浅めのレンジから探る |
| 日中 | 潮止まり | 深場や日陰に潜む | ボトム中心、ゆっくりと |
| 夕マズメ | 下げ始め~下げ7分 | 表層~中層で活発 | 広範囲をスピーディに |
| 夜間 | 転流のタイミング | 常夜灯周りに集まる | レンジを細かく刻む |
| 深夜 | 潮が動く時 | 回遊してくる | 我慢強く待つ |
実際の釣行では、釣れなかった時の経験も大切にすべきです。例えば、上げ潮では回遊がなかった場合、「下げ潮で試してみよう」「潮はよく流れていたのでもう一度チャレンジ」といった判断材料になります。あるいは、「思い切ってエリアを変えてみよう」「2週間後の潮で来てみよう」という次の戦略にもつながります。
このような試行錯誤を繰り返すことで、新たなパターンや群れを発見したり、釣れた時の嬉しさも一層増すはずです。潮見表(タイドグラフ)は必ず確認し、満潮・干潮の時刻、潮の大きさ(大潮・小潮など)を事前にチェックしておきましょう。現地では、海面の動きやゴミの流れ方などから、リアルタイムで潮の状態を把握する習慣をつけることも重要です。
ジグ単が基本で1g前後のウェイトが最適
瀬戸内海アジングで最も基本となるリグは、**ジグヘッド単体リグ(通称:ジグ単)**です。シンプルながら非常に効果的で、多くのアングラーがメインで使用しています。ワームとジグヘッドだけというシンプルな構成ですが、その分、繊細なアタリを感じ取りやすく、アジのバイトを確実にフッキングに持ち込めます。
🎣 基本タックルセッティング
ジグヘッドのウェイトは、1gを基準として、潮に馴染む(浮かず沈みすぎず)よう調整するのがセオリーです。潮流が速い場所や水深がある場所では1.5g~2g、逆に湾内の穏やかな場所では0.6g~1gといった具合に使い分けます。
| ジグヘッドウェイト | 適した状況 | 使用レンジ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 0.6~0.8g | 湾内・穏やかな場所 | 表層~中層 | スローフォールでナチュラルに誘える |
| 1.0~1.2g | 標準的な状況 | 全レンジ対応 | 最も汎用性が高い |
| 1.5~2.0g | 潮が速い・深場 | 中層~ボトム | 素早く沈めて効率的に探れる |
ワームのサイズは1.8~2.6インチが主流です。「艶じゃこ」や「尺獲ムシ」といった実績の高いワームが多用されています。カラーに関しては、ケイムラピンクからスタートし、海の色を見て「あみだんご(ベージュ系)」や「チャートラメ」にチェンジして反応を見るという方法が効果的です。
ケイムラ(紫外線発光)カラーは、水中で紫外線に反応して発光するため、特に朝夕のマズメ時や濁りがある時に有効とされています。一方、ナチュラル系のあみだんごカラーは、プレッシャーが高い場所やアジの警戒心が強い時に威力を発揮します。チャートラメは視認性が高く、濁り潮や夜間に効果的です。
ライン選択も重要なポイントです。エステルライン0.3~0.35号が多く使われており、感度と飛距離のバランスが良好です。PEライン0.4号を使用する場合は、リーダーにフロロカーボン4~8lbを結束します。エステルラインは伸びが少なく感度に優れる反面、やや強度が劣るため、根ズレに注意が必要です。PE+リーダーシステムは、強度と飛距離に優れますが、風の影響を受けやすいというデメリットもあります。
ジグ単以外のリグとしては、スプリットショットリグやフロートリグも状況に応じて使い分けます。スプリットショットリグは、流れが複雑で強い場所で有効で、1.8~5.0gのシンカーを使用します。フロートリグは、シャローエリアや遠投が必要な場面で活躍します。ただし、基本はジグ単で攻め、状況に応じて他のリグに変更するという順序が推奨されます。
ドリフト釣法で広範囲を効率的に探る
瀬戸内海アジングの特徴的なテクニックとして、ドリフト釣法があります。これは、潮の流れを利用してリグを自然に流し込む釣り方で、広範囲を効率的に探ることができます。特に潮流が速い瀬戸内海では、この釣法が非常に効果的とされています。
🌊 ドリフト釣法の基本手順
ドリフト釣法の基本は、潮上にキャストして潮下へ流し込むことです。キャスト後、ラインは張らず緩めず、適度なテンションを保ちながらリグを流していきます。この時、ロッドティップ(竿先)でラインの動きを注視し、わずかな変化も見逃さないようにします。
「ポイントによって潮流の有無、強弱、水深が違うので、『これ!』と決めてのアプローチは難しいのですが、まず潮流の合わせたウェイトを選択して潮上にキャストし潮下へ流し込む。フォールメインでも、レンジキープメインでも、ジグ単なら0.6~1.5gを使い分けて、アジとの距離を縮めてゆきます。」
ドリフト釣法には、フォールメインとレンジキープメインの2つのアプローチがあります。フォールメインは、リグを沈めながら誘う方法で、アジが中層以上にいる時や活性が高い時に効果的です。一方、レンジキープメインは、特定の水深を維持しながら流す方法で、アジが一定のレンジに固まっている時に有効です。
💡 ドリフト釣法のコツとポイント
- 潮の流れを読む:まず現場で潮の流れる方向と強さを確認します。ゴミや泡の動きを観察すると良いでしょう。
- 適切なウェイトを選ぶ:潮に負けず、かつ沈みすぎないウェイトを選びます。流されるのが早すぎる場合は重く、底に張り付く場合は軽くします。
- ラインテンションを保つ:完全に緩めると感度が落ち、張りすぎると不自然な動きになります。微妙なテンションコントロールが鍵です。
- アクションを加える:ただ流すだけでなく、時折トゥイッチ(竿先でチョンチョンと動かす)を入れることで、アジにアピールします。
この釣法で最も重要なのは、流れの中でリグがどう動いているかをイメージすることです。海面から見えない水中の様子を、ラインの動きやロッドに伝わる感覚から想像します。アジがリグにアタックしてくる瞬間は、わずかな重みの変化やラインの走りとして現れます。この微妙な変化を感じ取り、素早くアワセを入れることで、確実にフッキングできるようになります。
レンジを刻むことがアジを見つける最短ルート
瀬戸内海アジングで最も重要なテクニックの一つが、レンジを刻むことです。レンジとは水深のことで、アジがどの深さにいるかを見つけ出すことが、釣果を大きく左右します。アジは回遊魚であり、その日の潮や天候、ベイトの状況によって遊泳する深さが変わります。
📏 レンジの刻み方(基本プロセス)
- カウントダウンで沈める:キャスト後、「1、2、3…」とカウントしながらリグを沈めます
- 各カウントで誘う:例えば3カウントで止めて誘い、反応がなければ5カウント、7カウントと徐々に深く探ります
- ヒットレンジを記憶:アタリがあったカウント数を覚えておきます
- 同じレンジを攻める:次のキャストも同じカウント数で同じレンジを攻めます
- 微調整を繰り返す:±1カウント程度の微調整で、より確実にバイトレンジを捉えます
アジが特定のレンジに固まっている場合、そのレンジを外すと全く釣れないことがあります。例えば、ボトムから1m程度の中層にアジの群れが浮いている場合、表層を引いても、完全にボトムを攻めても反応がありません。このような状況では、カウントでヒットレンジを見つけることが絶対的に重要になります。
「各リグ共に基本的なアプローチは『レンジを刻む』こと。これに尽きます。キャスト後のカウントダウンから、ラインは張らず緩めず。アクションと、ラインスラッグ処理のためのトゥイッチを入れながら、テンションフォール。常にカウントしながらバイトレンジを探してゆきます。」
特に難しいのが、中途半端な中層に浮いているパターンです。フォールのみで釣ろうとすると、リグが狙いのレンジを一瞬で通過してしまうため、いわゆる「拾い釣り」的な散漫なヒットになり、群れを捕まえることができません。この場合、バイトのあるレンジに集中してリグを引いてくる必要があります。
具体的には、ヒットレンジまでカウントで沈めた後、そのレンジを維持するようにロッドで引いてくる、あるいはラインテンションを強めにかけてフォール幅を狭くしたテンションフォールを多用します。こうすることで、アジが集まっている狭いレンジを長時間攻め続けることができ、連続ヒットにつながります。
もう一つ重要なのは、状況判断です。フォールの釣りでアタリが続かない場合、「特定の狭いレンジのみをグルグルと回遊している」ことを疑ってください。そして、狙いのレンジをより丁寧にアプローチすることが必要です。単純にボトムまで沈めて巻くだけでは、このようなアジを効率的に釣ることはできません。常にレンジを意識し、アジがどこにいるかを探り続ける姿勢が、安定した釣果への近道なのです。
瀬戸内海アジングの実践テクニックとおすすめスポット
- 釣島は離島ならではの豊かなフィールド
- 祝島は尺超えが当たり前のアジングの聖地
- しまなみ海道周辺は通年で狙える好ポイント
- 港内と外洋で狙い方を変えることが重要
- 実績を積み重ねることで新たなパターンを発見できる
- まとめ:瀬戸内海アジングを制するための要点
釣島は離島ならではの豊かなフィールド
愛媛県の沖合に浮かぶ釣島は、瀬戸内海アジングを語る上で欠かせない名所です。その名前からして「釣りの島」というインパクトがありますが、実際にアジやメバルが多い豊かな島として知られています。人口約500人の小さな離島ですが、釣り人にとっては夢のようなフィールドなのです。
🚢 釣島へのアクセス情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 出発港 | 三津浜港(松山空港から約1,500円でアクセス可能) |
| 便数 | 1日2便(午前・午後) |
| 所要時間 | 約40分 |
| 料金 | 大人1名510円、車両(4m以上5m未満)1台と運転手3,500円 |
| 運航会社 | 中島汽船 |
釣島の最大の魅力は、豊かな魚影です。アジはもちろん、メバル、カサゴ、クロダイなども狙えます。瀬戸内海の中でも特にアジの密度が高く、初心者でも釣りやすいのが特徴です。近年はアジング(アジのルアーフィッシング)が人気で、同じ仕掛けでメバルもねらえるため、両方を楽しむアングラーも多いようです。
冬シーズンの釣島は、特に大型アジを狙うのに最適です。外気の冷え込みこそ強くなりますが、大型のアジがねらえる季節となっています。釣島への交通は1日に2便のフェリーで、アジ釣りには夜が適しているため、16時40分に三津浜港からのフェリーに乗って島に渡るのが一般的なパターンです。
「釣島は、アジやメバルが多い豊かな島。また、ほかにもカサゴ、クロダイなどもねらえる。瀬戸内海のアジの密度はとても高く、初心者でも釣りやすいのが特徴だ。」
釣島で釣れるアジのサイズは、25cm前後が平均的で、冬場は特に脂が乗り、味も他の季節以上に良くなります。釣った魚をその場で刺身にして食べるのも、釣りキャンプの醍醐味の一つです。仲間とともに釣りをしながら、新鮮なアジの刺身を一口、二口と食べていると、いつの間にか空が白んでいる…そんな贅沢な時間を過ごせるのが釣島なのです。
島には特に観光地と呼べるものはありませんが、それこそがこの島の魅力とも言えます。明るい時間に灯台まで上ってみると、一周するのにさほど時間がかかるとも思えない大きさの島です。漁港で会う人は人懐っこい笑顔を浮かべ、ここまで釣りに来たというと驚かれることも多いそうです。静かな海を前に釣りザオを振り、冬の澄んだ星空の下で魚とたわむれる時間は、得がたい喜びに満ちているでしょう。
祝島は尺超えが当たり前のアジングの聖地
山口県の南の沖合に浮かぶ小さな離島祝島は、”アジングの聖地”とまで呼ばれる超一級のフィールドです。瀬戸内海でも屈指の漁場である周防灘と、太平洋の海流が入る伊予灘の境に位置し、魚影が抜群に濃く、多くのアングラーが足を運ぶ夢のフィールドとなっています。
🏆 祝島の圧倒的な実績
祝島が「聖地」と呼ばれる最大の理由は、そのサイズです。尺クラス(30cm以上)が釣れるのは当たり前で、40cmオーバーや50cmオーバーの「ギガアジ」を釣ることも夢ではありません。一般的な釣り場では尺アジは「大物」として扱われますが、祝島では「普通サイズ」という感覚です。これほどまでにコンスタントに大型が釣れる場所は、全国的に見ても極めて稀でしょう。
| 祝島アクセス情報 | 詳細 |
|---|---|
| 出発港 | 室津港 |
| 便数 | 1日3本 |
| 所要時間 | 約1時間 |
| レンタル自転車 | 1日300円(無人・料金箱方式) |
「祝島は、山口県の南の沖合に浮かぶ小さな離島で、人口は約500人。瀬戸内海でも屈指の漁場である周防灘と、太平洋の海流が入る伊予灘の境に位置し魚影が抜群に濃く、多くのアングラーが足を運ぶ夢のフィールドなのです。なかでも特に『アジング』といわれる釣りジャンルにおいて、『聖地』とまで呼ばれるこの祝島。尺クラスが釣れるのは当たり前で、40cmオーバーや50cmオーバーの『ギガアジ』を釣ることも夢ではありません。」
祝島での釣りは、基本的にジグ単から始めます。ただし、ここでのアジは大型が多いため、やや重めの1.5~2.0gのジグヘッドを使用する人も多いようです。ワームも2.5~3インチクラスの大きめサイズが効果的な場合があります。大型のアジは小さなベイトフィッシュを追うこともありますが、ある程度の大きさのあるベイトも積極的に捕食するため、ワームサイズもそれに合わせるという考え方です。
釣島と同様、祝島でも釣りキャンプが人気です。島には民宿もありますが、近くの中島などにも宿泊施設があり、それらをフェリーで巡りつつ、あらかじめ釣りと観光を組み合わせたプランを考えると良いでしょう。数日の旅程を確保して、じっくりと祝島アジングを楽しむのがおすすめです。
ただし、一つ注意点があります。祝島は天候の急変とアジの足の早さに注意が必要です。特に冬場は爆発的な釣果が期待できる反面、数日前まで釣れていたのに当日は全く…ということもよくあるそうです。そのため、直近の釣果情報をこまめにチェックし、天候も含めて慎重に釣行日を選ぶことが成功の鍵となります。
しまなみ海道周辺は通年で狙える好ポイント
広島県と愛媛県を結ぶしまなみ海道周辺は、瀬戸内海アジングの中心的なエリアです。釣島や祝島のような離島と異なり、陸続きでアクセスしやすく、かつ多様なポイントが点在しているため、ランガン(移動しながらの釣り)に適しています。
🌉 しまなみ海道エリアの特徴
しまなみ海道周辺の最大の特徴は、多くの島々で形成されている水道に面したポイントが豊富なことです。干満差が大きく、場所によっては4mもの潮位差があります。この干満差が大きいことで潮流が強いポイントが多くなり、「湾内や潮溜まりを探る緩い釣り」から「ドリフトを多用した流し込む釣り」まで、多様なアプローチでアジを狙えます。
かつては「希少種」とまで言われていたこのエリアのアジですが、近年では魚影が格段に濃くなっています。2桁釣果も狙えるほどに安定した釣果が見込めるようになり、これまで完全にオフシーズンとされていた2~3月でも、まばらながら釣れるほどになっています。1~12月まで毎月釣果報告があるという話もあり、ほぼ通年で楽しめるフィールドと言えるでしょう。
📍 主要ポイントの特徴比較
| エリア | 特徴 | 適した時期 | アクセス |
|---|---|---|---|
| 今治周辺 | 潮通しが良く大型期待 | 通年 | 車でのアクセス良好 |
| 大三島周辺 | 多様なポイント | 春~秋 | しまなみ海道で直接アクセス |
| 生口島周辺 | 湾内の穏やかなポイント | 初夏 | しまなみ海道で直接アクセス |
| 因島周辺 | 水道部の激流ポイント | 初夏・冬 | しまなみ海道で直接アクセス |
しまなみ海道周辺でのアジングは、季節パターンを意識することが重要です。前述の通り、3~4月は回遊性が高いため潮流の変化の大きな場所、5~6月は産卵後の回復のためベイトの多い場所、7~8月は尺アジと豆アジの入れ替わり時期でサイズを意識…といった具合に、季節ごとの傾向を把握しておくことで、効率的にアジを見つけられます。
このエリアでのアジングは、ランガンスタイルが基本となります。一つのポイントで粘るよりも、短時間で見切りをつけて次のポイントへ移動する方が、結果的に釣果が伸びることが多いようです。ただし、地続きといえど、ポイント間の移動には30分から小一時間ほど車で走る場合もあるため、事前に複数のポイントをリストアップしておくことをおすすめします。
港内と外洋で狙い方を変えることが重要
瀬戸内海アジングにおいて、港内と外洋では全く異なるアプローチが必要です。同じエリア内であっても、港の中と外では潮の流れ方、水深、ベイトフィッシュの種類が大きく異なるため、それぞれに適した釣り方を使い分けることが釣果アップの鍵となります。
🏖️ 港内と外洋の違いと攻略法
港内の特徴と攻略法:
港内は比較的穏やかで、潮の流れも緩やかです。常夜灯があるポイントでは、光に集まるプランクトンを求めて小魚が集まり、それを追ってアジも回遊してきます。港内では、ウイード(海藻)が生えている場合も多く、これがアジの隠れ家やベイトフィッシュの住処になっています。
港内での基本的なアプローチは、軽めのジグヘッド(0.6~1.0g)でゆっくりと探ることです。アジが表層~中層に浮いていることが多いため、カウントダウンも浅めからスタートします。常夜灯周りでは、明暗の境目を重点的に攻めると効果的です。また、ウイード周りを攻める際は、根掛かりを恐れずにボトム付近もしっかり探ることが大切です。
「港内で反応するアジと外洋で反応するアジは、意識しているシチュエーションも大きく異なる。その『意識しているもの』に対してベストなアプローチを展開すれば、答えもすぐに返ってくる!!」
外洋の特徴と攻略法:
港の外側、特にシャローエリア(浅場)では、潮の流れが強く、ボトム(底)の地形変化が重要になります。岩礁帯やゴロタ石があるエリアは、ベイトフィッシュの隠れ家となり、アジもそれを狙って回遊してきます。
外洋シャローでの攻略は、ボトム攻めが基本となります。やや重めのジグヘッド(1.5~2.0g)を使用し、しっかりとボトムまで沈めてから、ゆっくりとリフト&フォールを繰り返します。ボトムを感じながら、地形の変化を探りつつ、そこにアジが着いているかを確認していくイメージです。
また、外洋側ではプラグの早引きも効果的な場合があります。特に朝夕のマズメ時には、表層を高速で泳ぐベイトフィッシュを模したプラグに、アジが果敢にアタックしてくることがあります。ただし、これは活性が高い時限定のテクニックで、常に有効というわけではありません。
🎯 状況判断のポイント
港内と外洋、どちらを攻めるべきかは、以下のような要素で判断します:
- 潮の動き:潮が大きく動いている時は外洋側、潮止まりの時は港内が有利なことが多い
- 時間帯:朝夕のマズメは外洋のシャロー、夜間は港内の常夜灯周りが期待できる
- ベイトの有無:ベイトフィッシュの群れが見える方を優先する
- 天候:風が強い日は港内の方が釣りやすい
このように、港内と外洋では全く異なる戦略が必要です。一つのポイントで釣れない時は、「反対側を試してみる」という発想も重要です。同じエリア内でも、場所を変えるだけで状況が一変することもあるのが、瀬戸内海アジングの面白さでもあり、難しさでもあります。
実績を積み重ねることで新たなパターンを発見できる
瀬戸内海アジングで安定した釣果を出し続けるためには、釣れた実績だけでなく、釣れなかった実績も大切にするという姿勢が重要です。多くのアングラーは、釣れた時の記録は詳細に残しますが、釣れなかった時の状況については軽視しがちです。しかし、釣れなかった理由を分析することで、次回以降の戦略が格段に向上します。
📊 実績の記録と活用法
釣行後には、以下のような情報を記録しておくことをおすすめします:
| 記録項目 | 具体例 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 日時 | 2024年12月28日 16:30~22:00 | 同じ時期の再訪判断材料 |
| 潮汐 | 満潮18:30、大潮3日目 | 潮回りとの相関を分析 |
| 天候 | 晴れ、北西の風3m、気温8℃ | 天候パターンの把握 |
| 釣果 | 25cm×3匹、20cm×5匹 | サイズ傾向の把握 |
| ヒットルアー | ジグヘッド1.2g+ケイムラピンク | 有効パターンの記録 |
| ヒットレンジ | カウント7~9(中層) | レンジパターンの把握 |
| ベイト | 小魚の群れあり | ベイトとの関連性 |
| 反省点 | 上げ潮時は反応なし | 次回の改善ポイント |
特に重要なのが、釣れなかった時の分析です。例えば、上げ潮では回遊がなかった場合、次のような仮説と対策が考えられます:
✓ 仮説と対策の例
- 仮説1:このポイントは下げ潮の方が良いのかもしれない
- 対策:次回は下げ潮のタイミングで来てみよう
- 仮説2:潮はよく流れていたので、タイミングの問題かもしれない
- 対策:同じ潮回りでもう一度チャレンジしてみよう
- 仮説3:季節的に魚が抜けているのかもしれない
- 対策:思い切ってエリアを変えてみよう
- 仮説4:大潮すぎて流れが速すぎたのかもしれない
- 対策:2週間後の小潮で来てみよう
このような試行錯誤を繰り返すことで、新たなパターンや群れを発見できます。そして、釣れた時の嬉しさも一塩です。ただ漫然と釣りをするのではなく、「なぜ釣れたのか」「なぜ釣れなかったのか」を常に考え、次回に活かすという姿勢が、上達への近道となります。
また、同じポイントでも時期によって全く異なる顔を見せるのが瀬戸内海アジングです。春に良かったポイントが夏には全く釣れず、秋にまた復活する…といったことは珍しくありません。こうした季節ごとの変化も記録しておくことで、年間を通じた攻略パターンが見えてきます。
実績を積み重ねる上で大切なのは、他のアングラーの情報も参考にすることです。釣具店の釣果情報、SNS、釣りブログなど、様々な情報源から最新の状況をキャッチアップしましょう。ただし、鵜呑みにするのではなく、自分の実釣データと照らし合わせて、信頼性を判断することも重要です。
まとめ:瀬戸内海アジングで大型を手にするための要点
最後に記事のポイントをまとめます。
- 瀬戸内海アジングの最大の魅力は、魚影の濃さと大型の期待値の高さである
- 最も釣れる時期は初夏(5~7月)と冬(12~2月)の2シーズンで、それぞれ異なる特徴がある
- 3~4月は回遊性が高く潮流の変化が大きな場所、5~6月はベイトの多い場所を狙うべき
- 7~8月は尺アジと豆アジの入れ替わり時期で、サイズを意識した場所選びが重要
- 満潮前後や転流のタイミングなど、潮流の変化を読むことが釣果アップの鍵となる
- 基本リグはジグ単で、1g前後のウェイトが最も汎用性が高い
- ドリフト釣法は潮の流れを利用して広範囲を効率的に探る瀬戸内海の定番テクニック
- レンジを刻むことがアジを見つける最短ルートで、カウントダウンによるレンジ管理が必須
- 釣島は離島ならではの豊かなフィールドで、25cm前後のアジが安定して釣れる
- 祝島は尺超えが当たり前の「聖地」で、40~50cmオーバーのギガアジも夢ではない
- しまなみ海道周辺は通年で狙える好ポイントで、ランガンスタイルが基本となる
- 港内と外洋では全く異なるアプローチが必要で、状況に応じて使い分けることが重要
- 釣れた実績だけでなく、釣れなかった実績も大切にすることで新たなパターンを発見できる
- 季節パターンを意識し、潮汐や天候、ベイトの状況など総合的に判断することが安定した釣果につながる
- ケイムラピンク、あみだんご、チャートラメなど、状況に応じたカラーチェンジが効果的である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 瀬戸内海で釣れたアジの釣り・釣果情報 – アングラーズ
- 【愛媛県・釣島】瀬戸内海に浮かぶアジの島|ANA
- 瀬戸内海…アジング | 2023エギングのち時々アジング…アジ散歩♪
- 瀬戸内アジングの上達のポイント | アルカジックジャパン
- 瀬戸内海マニアックなアジング | 2023エギングのち時々アジング…アジ散歩♪
- 今がハイシーズン! ドリフトで狙う、初夏の瀬戸内アジング!!
- 念願の初上陸!アジングの聖地『祝島』の魅力 | WEBマガジン HEAT
- 【トミー敦のあじすた!vol.3】冬シーズンの良型狙い!! in瀬戸内エリア
- アジングでメッキを釣りたくて | madaoもアジング
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。