山中湖でブラックバス釣りを楽しみたいアングラーにとって、「いつ放流されるのか」「どこで放流されるのか」という情報は非常に重要です。最新の放流情報を知ることで、より効率的にバスを狙うことができるでしょう。しかし近年、山中湖を含む富士五湖のブラックバス放流には将来的な変更が検討されているという情報もあります。
この記事では山中湖漁業協同組合の情報をもとに、最新の放流状況から今後の放流見通しまで、山中湖のブラックバス釣りに関する情報を包括的にお届けします。また、周辺の河口湖や西湖との比較や、外来生物としてのブラックバスの扱いについても解説します。山中湖でバス釣りを楽しむすべてのアングラーにとって役立つ情報となるでしょう。
記事のポイント!
- 山中湖での最新のブラックバス放流情報(時期と場所)
- 山中湖漁協の将来的な放流計画と漁業権返上の見通し
- 富士五湖(河口湖・西湖・山中湖)のブラックバス政策の違い
- 放流バスの特徴と効果的な釣り方
山中湖でのバス釣り放流に関する最新情報
- 山中湖では定期的にブラックバスの放流が行われている
- 最新の放流情報は2024年10月に平野地区で実施
- 山中湖の放流バスの平均サイズは35cm前後
- 放流場所は主に平野地区、山中地区、旭日丘地区の3カ所
- 放流後はシャロー周辺でルアーフィッシングが効果的
- 放流時のマナーとして過度な場所取りや放流車追跡は禁止
山中湖では定期的にブラックバスの放流が行われている
山中湖では漁業協同組合によって定期的にブラックバス(オオクチバス)の放流が行われています。調査の結果、山中湖漁業協同組合のホームページには放流情報がこまめに更新されており、年に複数回の放流が実施されていることがわかりました。
特に春のゴールデンウィーク前と夏のハイシーズン前には放流が計画されることが多いようです。最近では2024年の4月と10月に放流が行われました。これらの放流は山中湖でのバス釣りの魅力を維持し、多くのアングラーを引き寄せる重要な要素となっています。
放流の告知は通常、実施の1〜2週間前に山中湖漁業協同組合のホームページで「オオクチバス放流予定」として発表されます。実際の放流が完了すると「オオクチバス放流のお知らせ」として報告が上がります。アングラーはこれらの情報をチェックすることで、最新の放流状況を把握することができます。
山中湖でのブラックバス放流は観光資源として重要な役割を果たしていますが、後述するように将来的には変更が検討されています。現時点では安定して行われていますが、今後の展開には注意が必要でしょう。
放流の頻度は年によって異なりますが、過去のパターンからは年に2〜4回程度実施されていると推測されます。2023年は4月と8月に、2022年は4月と7月に放流が行われていました。
最新の放流情報は2024年10月に平野地区で実施

調査によると、山中湖での最新のブラックバス放流は2024年10月15日に実施されました。この放流は平野地区で行われたことが山中湖漁業協同組合のホームページで報告されています。
その前の放流は2024年4月25日にも平野地区で行われています。また、2024年10月8日の告知では「10月中にオオクチバスを放流する予定です」と発表されており、これが10月15日の放流につながったと考えられます。
放流の実施時期はある程度のパターンがあり、春先(4月頃)、夏前(7月頃)、秋(10月頃)に行われることが多いようです。釣りシーズンの前や釣り客が多く訪れる時期に合わせて放流が計画されています。
山中湖漁業協同組合は放流の事実と場所は公表していますが、具体的な放流量や時間などの詳細情報は公開されていないようです。これは過剰な混雑や放流車の追跡などのマナー違反を防ぐための配慮と考えられます。
アングラーとしては、放流後数日から数週間が最も釣果が期待できる時期であると言われています。ただし、放流されたバスは環境に順応するまで時間がかかることもあるため、必ずしも放流直後が最良というわけではありません。
山中湖の放流バスの平均サイズは35cm前後
山中湖に放流されるブラックバスのサイズについては、調査によると平均35cm前後のサイズが一般的なようです。河口湖の情報ではありますが、「アベレージは35cm前後」という記述があり、山中湖も同様のサイズが放流されていると推測されます。
放流されるバスのサイズはかなり良質で、キロオーバー(40cm以上)のサイズも混ざっていることがあります。ブログ記事には「グッドサイズをゲット!たぶんキロオーバー!!」という記述もあり、中には大型の個体も含まれていることがわかります。
山中湖の放流バスは養殖された個体であり、自然繁殖のバスと比較して見た目が異なることがあります。養殖バスは餌付けされているため、野生のバスよりも太りぎみで、色も若干異なる場合があります。
放流されたバスは初めは比較的簡単に釣れることがありますが、時間が経つにつれて自然環境に適応し、ルアーに対する反応も慎重になっていきます。SNSの情報によると「放流した当日ってことでやる気なさげ?」という記述もありますが、環境に慣れるまでは警戒心が少ない傾向にあります。
なお、放流されたバスの生存率は様々な要因に左右されます。ある釣り人のコメントによれば「放流バスは自然界で餌の取り方を知らないため、長くは生きられない」という指摘もありますが、一部は自然環境に適応して生き延びていきます。
放流場所は主に平野地区、山中地区、旭日丘地区の3カ所
山中湖でのブラックバスの放流場所は主に3カ所があることが分かっています。調査の結果、過去数年の放流記録から、平野地区、山中地区、旭日丘地区の3カ所が主な放流ポイントとなっています。
2024年10月15日と4月25日の放流は平野地区で行われました。2023年4月27日の放流は山中地区と旭日丘地区で実施されています。2022年7月29日の放流は山中地区と平野地区でした。このように、放流場所はある程度パターン化されているようです。
各地区の特徴としては、平野地区は山中湖の南東部に位置し、比較的アクセスが良い場所です。山中地区は湖の南西部にあり、周辺には飲食店なども多くあります。旭日丘地区は東側に位置し、富士山の眺望が良い場所として知られています。
放流場所の選定には、アクセスの良さや周辺環境、過去の放流実績などが考慮されていると推測されます。また、一度に複数箇所で放流することで、湖全体にバスを分散させる意図があるのかもしれません。
アングラーにとっては、放流場所の情報は非常に重要ですが、漁協は放流日当日の「車での追いかけ及び過剰な場所取り等」を禁止しています。これは円滑な放流作業のためだけでなく、一部のアングラーが有利になりすぎないための配慮とも考えられます。
放流後はシャロー周辺でルアーフィッシングが効果的
山中湖での放流後のバス釣りでは、シャロー(浅瀬)周辺でのルアーフィッシングが効果的であるという情報があります。「ガイド情報によると、日替わりでシャローが良い時は…ウィードアウトサイドのクランクやウィードトップのフロッグ等で釣れている」という記述がみられます。
放流直後のバスはまだ環境に慣れていないため、比較的シンプルなアプローチでも反応することが多いようです。「ダウンショットのロングステイでヒット!」という釣果報告もあり、じっくりとアピールする釣り方も効果的です。
放流バスの攻略には、以下のようなルアーやタックルが有効と考えられます:
- クランクベイト(特にウィードのアウトサイド)
- フロッグ(ウィードトップ)
- ダウンショットリグ(ロングステイ)
- ジグ系(ボトム周り)
水温や天候、時期によっても効果的な釣り方は変わってきます。春から初夏にかけては水温の上昇に伴って活性が高まり、夏場は早朝・夕方や沖のディープエリアがねらい目になることもあります。
また、「沖が良い日は表層で〜」という情報もあるように、日によってバスの居場所は変化します。その日の状況を見極めながら柔軟に釣り方を変えていくことが重要でしょう。放流バスは時間の経過とともに自然環境に適応していくため、放流から時間が経つほど通常のバス釣りのアプローチが必要になってきます。
放流時のマナーとして過度な場所取りや放流車追跡は禁止
山中湖でのブラックバス放流に関しては、いくつかのマナーやルールが設けられています。特に重要なのは、放流作業の妨げになる行為を避けることです。
山中湖漁業協同組合のホームページでは「放流場所については、従来通りお問い合わせして頂いても、お応えできません」と明記されています。また「放流日当日の車での追いかけ及び過剰な場所取り等はやめてください」と注意喚起がされています。これは円滑な放流作業を行うためだけでなく、全てのアングラーが公平に釣りを楽しめるようにするための配慮です。
放流車を追いかけることは、作業の妨げになるだけでなく、漁協関係者や一般の方に不快感を与える行為です。また、過度な場所取りも他のアングラーとのトラブルの原因になりかねません。
放流バスを狙う際には以下のようなマナーを心がけましょう:
- 放流場所や時間を無理に聞き出そうとしない
- 放流作業中は適切な距離を保つ
- 過度な場所取りは避け、他のアングラーと共存する
- 湖畔や周辺環境の美化に協力する
- 釣ったバスの扱いは漁協のルールに従う
また、山中湖での釣りには遊漁券が必要です。遊漁券は湖畔の売店や自動販売機で購入できます。ルールを守り、マナーを大切にすることで、山中湖のバス釣り環境が長く維持されることにつながります。
山中湖バス釣り放流の将来と関連情報
- 山中湖漁協は10年以内にブラックバス漁業権の返上を検討
- 富士五湖全体でブラックバス依存度の低減が進行中
- 河口湖と比較すると山中湖は放流から自然繁殖への移行が早い
- 西湖は既に放流を停止し自然繁殖のみに移行しつつある
- ブラックバスは外来生物だが富士五湖では特例として管理されている
- ブラックバス以外にもワカサギやヘラブナの放流も行われている
- まとめ:山中湖バス釣り放流の現状と今後の展望
山中湖漁協は10年以内にブラックバス漁業権の返上を検討
重要な情報として、山中湖漁業協同組合は将来的にブラックバスの漁業権を返上することを検討しています。調査によると、2023年8月に開催された県内水面漁場管理委員会で、山中湖漁協が「10年後の更新時に免許を返上することを検討する」方針を示したことが報告されています。
この検討は、ブラックバスが外来生物法で本来は放流が禁止されていることを受けた対応です。山中湖漁協は放流量の削減を継続しつつ、10年後(2033年頃)には漁業権免許の返上を視野に入れているとのことです。
これは山中湖でのブラックバス釣りの将来に大きな影響を与える可能性がある動きです。漁業権免許が返上されれば、正式な放流は行われなくなり、自然繁殖のみに頼ることになります。
現時点では放流は継続されているものの、長期的には徐々に縮小していく可能性が高いと言えるでしょう。ただし、現在の段階では山中湖でのブラックバス釣りが禁止されるわけではなく、自然繁殖による資源維持を前提とした釣り場としての利用は続くと考えられます。
バス釣りファンとしては、今後の10年間は山中湖での釣りを楽しみつつ、将来的な変化にも目を向けておく必要があるでしょう。具体的な移行計画や実施時期については、今後の山中湖漁協や県の発表を注視する必要があります。
富士五湖全体でブラックバス依存度の低減が進行中
富士五湖(河口湖、山中湖、西湖、本栖湖、精進湖)全体で、ブラックバスへの依存度を低減する動きが進んでいます。特に河口湖、山中湖、西湖の3湖では、それぞれ異なるペースでブラックバス漁業に関する方針転換が検討されています。
山梨県の内水面漁場管理委員会の情報によると、県側は「早期の免許返上が望ましい」という立場を示しており、漁協に対して新たな収入源の確保などに向けて支援する考えを示しています。
この背景には、ブラックバスが特定外来生物に指定されていることがあります。本来であれば放流は禁止されているところ、特例として認められてきた経緯がありますが、長期的には法令順守の方向性が強まっているようです。
富士五湖周辺で進行しているブラックバス依存度低減の具体的な取り組みには以下のようなものがあります:
- 放流量の段階的削減
- 自然繁殖への移行
- 他の魚種(ワカサギ、ニジマス、ヘラブナなど)の振興
- 新たな観光資源の開発
これらの変化は10年程度の期間をかけて徐々に進められる計画のようです。急激な変更ではなく、釣り人や地域経済への影響を最小限に抑えながら、段階的に移行していく方針と考えられます。
アングラーとしては、こうした変化の中でも富士五湖の自然環境と調和したバス釣りの楽しみ方を模索していくことが求められるでしょう。
河口湖と比較すると山中湖は放流から自然繁殖への移行が早い
富士五湖の中でも、河口湖と山中湖ではブラックバスに関する方針に違いがあります。調査の結果、河口湖は山中湖よりもブラックバスへの依存度が高く、放流から自然繁殖への移行も緩やかに進められる方針であることがわかりました。
河口湖漁協では、遊漁券収入の約8割をブラックバスが占めているとされ、この状況からの脱却には時間を要するとしています。そのため、河口湖は「バスの依存度を低減する」との目標にとどめており、山中湖のような10年以内の漁業権返上までは言及していません。
具体的な数字として、河口湖は10年後までに放流量を3.5トンから2.6トンまで減少させる計画とのことです。これは約26%の削減にあたりますが、完全な放流中止ではなく、段階的な縮小にとどまっています。
一方、山中湖は10年間で放流を少しずつ減らし、10年後にはゼロとする方針です。河口湖と比較すると、山中湖は自然繁殖への移行をより早いペースで進める方針と言えるでしょう。
この違いは各湖の収益構造や観光パターン、生態系の状況などによるものと推測されます。河口湖はバス釣りの人気が特に高く、山中湖はバス釣り以外の魚種や観光資源も比較的豊富である可能性があります。
アングラーとしては、各湖の特徴や方針を理解した上で釣り場を選ぶことが重要になってくるでしょう。
西湖は既に放流を停止し自然繁殖のみに移行しつつある
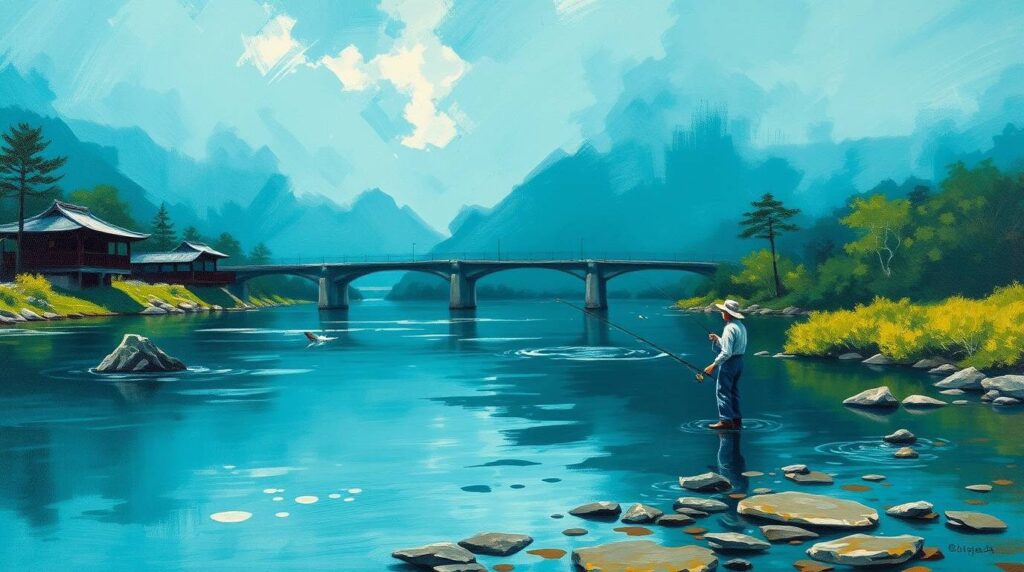
調査によると、富士五湖の中で西湖は既にブラックバスの放流を停止し、自然繁殖のみでの資源維持に移行しつつあることが分かりました。具体的には、西湖漁協は過去10年間バスの放流を行っておらず、産卵床整備など増殖のみを行ってきたとのことです。
さらに西湖は「この先10年以内の免許返上を検討する」方針を示しており、来年度からは産卵場所の整備も停止する方向とされています。これは3湖(河口湖、山中湖、西湖)の中で最も積極的にブラックバスからの脱却を進めている状況と言えるでしょう。
西湖漁協がこのような方針を取る背景には、西湖に生息する「クニマス」の保護という観点もあったようです。クニマスは一度絶滅したと考えられていた貴重な魚種で、2010年に西湖で再発見されました。当初はブラックバスがクニマスに悪影響を与えるのではないかという懸念がありましたが、「その後の研究でバスがクニマスの生態系に及ぼす影響は小さいことが判明した」とされています。
しかし、西湖漁協は現在、クニマス保護ではなく「バスの放流禁止を定めた法の順守を目的に免許返上を検討する方針」を示しています。これは外来生物法を尊重する姿勢の表れと言えるでしょう。
西湖での釣りを検討するアングラーは、放流が行われていないことを理解した上で、自然繁殖によるバスを対象に釣りを楽しむことになります。放流直後の比較的釣れやすい状況は期待できませんが、ナチュラルな環境でのバス釣りを楽しむことができるでしょう。
ブラックバスは外来生物だが富士五湖では特例として管理されている
ブラックバス(オオクチバス)は日本の生態系には本来存在しない外来魚であり、特定外来生物に指定されています。特定外来生物に指定されると、基本的には「生体として持ち歩くことは禁止」「むやみに放流してはいけない(キャッチアンドリリース禁止)」などの規制が適用されます。
しかし、富士五湖(特に河口湖、山中湖、西湖)ではブラックバスの漁業権が特例として認められており、管理された状態での放流や釣りが許可されています。これは観光資源としての重要性や地域経済への貢献などを考慮した措置と考えられます。
関東地域ではこの他にも、相模湖や芦ノ湖、津久井湖などの神奈川県の湖でも同様に条例で特例が認められています。これらの湖ではブラックバス釣りが正式に認められた釣り場として多くのアングラーに親しまれています。
ただし、こうした特例的な扱いも徐々に見直される傾向にあります。前述のように、山中湖や西湖では将来的に漁業権の返上が検討されており、長期的には法令順守の方向に進む可能性が高いと言えるでしょう。
アングラーとしては、ブラックバスの外来種としての位置づけを理解し、法令や各湖のルールを守りながら釣りを楽しむことが重要です。例えば、特例が認められていない水域でのブラックバスの放流は厳格に禁止されており、生態系保全の観点からもそのようなルール違反は避けるべきでしょう。
ブラックバス以外にもワカサギやヘラブナの放流も行われている
山中湖ではブラックバス以外にも複数の魚種が放流されており、多様な釣りが楽しめる環境が整えられています。調査によると、特にワカサギとヘラブナの放流が行われていることが確認できました。
2022年11月14日には「ヘラブナ放流のお知らせ」として、平野地区でのヘラブナ放流が報告されています。ヘラブナはコイ科の魚で、穏やかな引きを楽しむ釣りとして人気があります。
また、ワカサギについては通常は放流ではなく、自然繁殖が基本となっているようですが、9月頃から解禁となることが多く、「試し釣りの結果も良く、ワカサギの大きさも6cm~11cmと状態も良い」との情報もあります。ワカサギ釣りは冬季の氷上穴釣りなどで人気があります。
山中湖漁協がブラックバス以外の魚種にも力を入れていることは、将来的にブラックバスの漁業権返上を検討していることとも関連しているかもしれません。多様な魚種を振興することで、バス釣り以外の釣り客も呼び込む戦略と推測されます。
アングラーとしては、季節によって釣りの対象魚を変えるなど、山中湖の多様な魚種を楽しむアプローチも検討する価値があるでしょう。ブラックバスだけでなく、ワカサギやヘラブナなど様々な魚種の釣りを体験することで、山中湖の魅力をより深く知ることができます。
なお、各魚種の釣りには適切な遊漁券が必要であり、解禁時期や禁漁期が異なることもあるため、釣行前に最新情報を確認することをおすすめします。
まとめ:山中湖バス釣り放流の現状と今後の展望
最後に記事のポイントをまとめます。
- 山中湖では現在もブラックバス放流が継続されており、2024年は4月と10月に平野地区で放流が実施された
- 放流場所は主に平野地区、山中地区、旭日丘地区の3カ所で行われている
- 放流されるバスの平均サイズは35cm前後で、時にはキロオーバーの大型個体も含まれる
- 山中湖漁協は10年以内(2033年頃まで)にブラックバス漁業権の返上を検討している
- 富士五湖全体でブラックバス依存度の低減が進行中だが、河口湖は依存度が高いため段階的な移行となっている
- 西湖は既に放流を停止しており、自然繁殖のみに移行しつつある
- ブラックバスは特定外来生物だが、富士五湖では特例として管理された状態での釣りが認められている
- 放流時には「車での追いかけ及び過剰な場所取り等」が禁止されており、マナーを守ることが重要
- 放流後の釣りではシャロー周辺でのクランクやフロッグ、ダウンショットなどが効果的
- 山中湖ではブラックバス以外にもワカサギやヘラブナなどの放流も行われ、多様な釣りが楽しめる
- 将来的には自然繁殖のみに頼るバス釣りへの移行が進む可能性が高い
- アングラーは現状を理解し、ルールやマナーを守りながら釣りを楽しむことが求められる
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。






