八郎潟バス釣り禁止って本当なの?よく聞くけど、実際のところどうなんだろう…と気になっている方も多いのではないでしょうか。秋田県の八郎潟は「北の楽園」とも呼ばれ、かつては全国から多くのバスアングラーが集まる人気スポットでした。しかし、2000年代初頭からリリース禁止などの規制が導入され、その釣り場としての姿は大きく変わってきました。
この記事では、八郎潟でのブラックバス釣りの現状、リリース禁止の詳細、なぜそのような規制が行われているのか、そして現在でも八郎潟でバス釣りを楽しむ方法について詳しく解説します。また、八郎潟周辺のエリア別攻略法や、リリース禁止の規制がない代替釣り場についても紹介していきます。八郎潟に釣りに行く前に、ぜひ知っておきたい情報が満載です。
記事のポイント!
- 八郎潟ではバス釣りそのものは禁止ではなく、釣ったバスをリリース(再放流)することが禁止されている
- リリース禁止違反には、漁業法に基づく1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則がある
- 八郎潟は東部・西部・残存湖のエリアに分かれており、それぞれに適した釣り方がある
- 全国的には47都道府県中14県のみがリリース禁止であり、多くの地域ではまだバス釣りを楽しめる
八郎潟でバス釣り禁止の現状と規制内容
- 八郎潟ではバス釣りそのものは禁止ではなくリリースが禁止されている
- 秋田県内水面漁場管理委員会指示によるリリース禁止の詳細ルール
- 八郎潟バス釣り禁止の罰則は漁業法に基づく1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- リリース禁止で釣れたバスの適切な処理方法は回収BOXの利用または持ち帰り
- 八郎潟バス釣り禁止の背景には地元漁業者とのトラブル増加がある
- 八郎潟のバス釣り事情は2000年頃から規制が始まり今に至る
八郎潟ではバス釣りそのものは禁止ではなくリリースが禁止されている
まず最初に押さえておきたいのは、八郎潟においてバス釣り自体は禁止されていないという点です。禁止されているのは、釣り上げたブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)やブルーギルを再び湖に放流する「リリース」行為です。
八郎潟西部承水路からの注意喚起でも明確に述べられているように、「手遅れになる前に考えて行動しよう」という呼びかけがあります。この水域では産卵期のライブウェル(生かしておくための水槽)使用も禁止されており、釣ったバスはリリースせずに回収することが求められています。
八郎潟町の公式サイトにも「漁業従事者への配慮、ゴミの持ち帰りなどのルールを守り、八郎潟での釣りをお楽しみ下さい。特にブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)、ブルーギルは八郎潟ではリリースが禁止されております」と明記されています。
釣り自体は可能ですので、ルールを守れば八郎潟でバス釣りを楽しむことができます。しかし、リリース禁止という規制があるため、釣った魚の処理方法をあらかじめ考えておく必要があります。
釣りを楽しむ上での大前提として、このリリース禁止のルールをきちんと理解し、遵守することが求められています。
秋田県内水面漁場管理委員会指示によるリリース禁止の詳細ルール
八郎潟でのリリース禁止は「秋田県内水面漁場管理委員会指示」によって定められています。この指示は漁業法に基づく法的な効力を持ち、県内の内水面における魚類資源の保護や漁業秩序の維持を目的としています。
具体的には、秋田県内でブラックバス(オオクチバス、コクチバス)やブルーギルなどの特定外来生物を釣った場合、それらを再び水中に放流(リリース)することが禁止されています。これは「キャッチ&リリース」と呼ばれるバス釣りで一般的な行為が禁止されているということです。
この規制は八郎潟だけでなく秋田県全域に適用されています。調査によると、全国47都道府県中14県でリリース禁止の規制が設けられており、秋田県もその一つです。
内水面漁場管理委員会指示の対象区域は非常に広範囲で、県内の公共用水面全体が含まれます。そのため、八郎潟だけでなく、秋田県内の川や池などでもブラックバスをリリースすることはできません。
このルールは2000年頃から徐々に整備され、現在では明確に運用されています。特に八郎潟においては、このルールが厳格に適用されている水域のひとつとして知られています。
八郎潟バス釣り禁止の罰則は漁業法に基づく1年以下の懲役または50万円以下の罰金

八郎潟でのブラックバスリリース禁止に違反した場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。「秋田県内水面漁場管理委員会指示」に違反した場合の罰則は漁業法に基づいて定められています。
具体的には、この指示に従わなければ、知事から指示に従うよう命じられることがあります。さらに、この命令に違反した場合は、漁業法第139条に基づき「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処せられる可能性があります。
ただし、一般的には最初からこのような厳しい罰則が適用されるわけではありません。まずは指導や注意から始まり、悪質な違反や繰り返しの違反があった場合に、より厳しい処分が検討されることになります。
その他にも、特定外来生物法という別の法律もあります。この法律では、特定外来生物(ブラックバスやブルーギルを含む)の「飼養、栽培、保管、運搬」が原則として禁止されています。そのため、リリースだけでなく、釣ったバスを生きたまま持ち帰ることも法律違反となる可能性があるので注意が必要です。
釣り人としては、これらの規制を理解し、地元のルールに従って釣りを楽しむことが重要です。罰則を受けるリスクを避けるためにも、リリース禁止のルールはしっかりと守りましょう。
リリース禁止で釣れたバスの適切な処理方法は回収BOXの利用または持ち帰り
八郎潟でブラックバスを釣った場合、リリースができないため、適切な処理方法を知っておく必要があります。釣り人がとるべき正しい対応として以下のいくつかの選択肢があります。
まず、漁港やマリーナには「回収BOX」が設置されていることがあります。これらのBOXは釣り上げたバスを適切に回収・処分するためのものです。釣りの際はこれらの回収BOXの場所を事前に確認しておくと良いでしょう。
次に、釣ったバスを持ち帰る方法です。持ち帰った魚は、地域のルールに従って生ゴミとして処理することができます。また、食用として調理して食べることも可能です。バスは淡水魚特有の臭みがありますが、適切な下処理をすれば美味しく食べることができます。
Yahoo!知恵袋の回答によると、「死魚を持ち帰って地域のルールに従って生ごみ処理をする」「回収BOXがあれば利用する」「死魚を持ち帰って食べる、もしくはその場で食べる」といった対応が推奨されています。
一方で、「その辺に捨てる」行為は不法投棄となり、別の法律違反になってしまいます。また、生きたまま持ち運ぶことは特定外来生物法違反となる可能性があるため避けるべきです。
八郎潟の現状を見ると、残念ながら一部の釣り人がこうした適切な処理を行わず、湖岸に魚を放置するケースもあるようです。こうした行為は環境汚染や悪臭の原因となるだけでなく、釣り人全体のイメージを損なうことにもつながります。
八郎潟バス釣り禁止の背景には地元漁業者とのトラブル増加がある
八郎潟でリリース禁止が導入された背景には、釣り人と地元漁業者との間のトラブル増加があります。朝日新聞秋田版(2000年5月29日付)の記事によると、八郎潟は「バス釣りのメッカ」として全国的に名高くなり、一日に千人を超える愛好家が訪れるようになりました。
しかし、釣り客の増加に伴い様々なトラブルが発生しました。路上駐車やゴミの投げ捨てといった軽微な問題だけでなく、ボートのスクリューで漁師の定置網を切ってしまったり、網に引っかかった釣り針で漁師がけがをするといった深刻な事故も報告されています。あるインタビューでは「綱を引いていたら、針が指に刺さって手術をした。一体だれが補償してくれるのか」と漁師が怒りを語っています。
また、八郎潟の特殊な事情として、「漁業権が放棄されている」点が挙げられます。八郎潟干拓事業の際に漁業補償が行われ、漁業権が放棄されたため、公式には漁業権が設定されていません。そのため、釣り人から遊漁料を徴収する制度も存在せず、地元漁業者にとっては釣り人が増えても直接的な利益につながらないという状況がありました。
これらの背景から、環境保全や地元漁業者の保護を目的として、県や地元自治体がリリース禁止などの規制を導入することになりました。初期の目的は「釣った人に駆除してもらうことで、少しでもブラックバス全体を少なくしていこう」というものでした。
このように、八郎潟バス釣り禁止(リリース禁止)の背景には、単なる環境保護だけでなく、地域社会との共存という課題があったことがわかります。
八郎潟のバス釣り事情は2000年頃から規制が始まり今に至る
八郎潟でのバス釣り規制の歴史を振り返ると、2000年頃がひとつの転換点となっています。朝日新聞秋田版(2000年5月29日付)の記事によれば、当時すでに「バス釣りのメッカ」として八郎潟は全国的に名高く、県と地元漁業者が共同でブラックバスの駆除を開始することを決めていました。
2000年当時は、秋田県水産漁港課が「害魚」と認めてブラックバスの駆除を許可し、リリース禁止などの規制が検討され始めました。その後、2003年(平成15年)頃には、ブラックバスのリリース禁止が条例で定められるようになりました。
「はな&康太&悠太 成長日記」というブログの2006年の記事によれば、当時はすでに「平成15年からブラックバスのリリース禁止が条例で定められました」と書かれており、規制がすでに施行されていたことがわかります。
また、2004年には国の特定外来生物法が制定され、2005年にブラックバスが特定外来生物に指定されたことで、全国的にも外来魚対策が強化されていきました。八郎潟では特にこうした規制が早期から導入されていたといえます。
これらの規制導入後、八郎潟を訪れる釣り人は大幅に減少したと報告されています。2006年のブログでは「条例が制定された当初は、環境保護の観点から各マスコミで取り上げました。しかし3年目となった今は、ほとんど耳にすることもなくなりました」と記されており、規制後の状況変化がうかがえます。
このように、八郎潟のバス釣り事情は約20年以上前から規制が始まり、現在に至るまで継続しているのです。
八郎潟バス釣り禁止後の釣り場の現状と代替案
- 八郎潟バス釣り禁止後の釣り人減少により水域環境が変化している
- 八郎潟バス釣り禁止でも賑わいを取り戻す取り組みは継続されている
- 八郎潟エリアでのバス釣りは西部承水路や東部承水路など場所別の攻略法がある
- 八郎潟以外の東北地方でリリース可能なバス釣りスポットは青森県や福島県がある
- 全国のバス釣りリリース禁止エリアは14県のみで多くの場所でまだ釣りが楽しめる
- まとめ:八郎潟バス釣り禁止は全面禁止ではなくルールを守れば釣りを楽しめる
八郎潟バス釣り禁止後の釣り人減少により水域環境が変化している
リリース禁止が導入されてから、八郎潟を訪れる釣り人の数は大幅に減少しました。これにより、水域環境にもいくつかの変化が生じています。
2006年のブログ記事によれば、「条例が制定された後は、釣り人が激減しているそうです。釣る人がいなくなれば、そもそもリリースする人も、駆除する人もいなくなります」と指摘されています。釣り人の減少は、皮肉なことに外来魚の駆除という当初の目的に反する結果をもたらした可能性があります。
また、Yahoo!知恵袋の質問には「その昔は楽園だった八郎潟でバスがほとんど釣れなくなった、わんさかいた小さいバスさえほとんど見かけなくなった」と書かれており、バスの生息数自体にも変化が生じているようです。
環境面では、「アオコがひどくなった」「水生植物が激減した」という指摘もあります。これらの変化が直接リリース禁止と関連しているかは明確ではありませんが、釣り人の減少により人間活動の影響が変化したことは考えられます。
経済的な影響も見逃せません。釣り客の減少は周辺の釣具店や宿泊施設、ガソリンスタンドなどの売上に影響を及ぼしています。朝日新聞の記事によれば、ある地元ガソリンスタンドではバスブームが始まってから「シーズンには売り上げが三割ほど伸びる。なくなれば打撃だ」と語っていました。
こうした状況を受け、地元の一部では「共存策」を模索する声も上がっています。料金を徴収して釣り客を受け入れる仕組みや、漁業権の設定などが提案されていますが、実現には至っていないようです。
八郎潟バス釣り禁止でも賑わいを取り戻す取り組みは継続されている
リリース禁止後に釣り人が減少した八郎潟ですが、再び賑わいを取り戻すための取り組みも続けられています。特に地元の企業やマリーナなどが中心となって、ルールを守った釣りの促進や情報発信に力を入れています。
例えば、「シェルターマリン」という男鹿市のマリーナは、八郎潟西部承水路での釣りに関する情報発信を積極的に行っています。同社のブログでは危険エリアのマップや釣り方のアドバイスを掲載し、安全で責任ある釣りを推進しています。
また、「バス釣り大学」というウェブサイトでは、八郎潟の東部エリア、西部エリア、残存湖エリアそれぞれの攻略法を詳細に紹介しています。このサイトでは「八郎潟が釣れなくなった原因と現在の攻略法」について説明し、「特徴を知らないと余裕で凸る」「水中のオアシス探しがキー」など具体的なアドバイスを提供しています。
地元の八郎潟町も観光情報の一環として釣り情報を発信しています。町の公式サイトでは「漁業従事者への配慮、ゴミの持ち帰りなどのルールを守り、八郎潟での釣りをお楽しみ下さい」と呼びかけ、ルールを守った釣りを推奨しています。
高梨憲一氏(OSPスタッフ)のレポートによれば、2014年頃には「久しぶりに八郎潟へ行って」「久々の釣行」としながらも、当日は「何艇ものバスボートを見て、まだまだ八郎潟は熱い!バスフィッシングは熱い!と感じました」と報告しています。
こうした情報発信や取り組みにより、リリース禁止というルールの中でも八郎潟でのバス釣りを楽しむ方法が模索され続けています。釣り人側もルールを理解し、適切に対応することで、この素晴らしいフィールドを維持していくことが期待されています。
八郎潟エリアでのバス釣りは西部承水路や東部承水路など場所別の攻略法がある
八郎潟は大きく分けて「東部エリア」「西部エリア」「残存湖エリア」の3つのエリアに分けられており、それぞれに適した釣り方が存在します。リリース禁止のルールはありますが、これらのエリアごとの特性を理解すれば効果的にバス釣りを楽しむことができます。
まず、「東部エリア」には東部承水路をメインとする大型の水路と、そこに流れる小規模な流入水路や中型河川があります。このエリアでの攻略法としては、「小規模水路攻略」「中規模河川攻略」「河口攻略」が有効とされています。特に水の動きがある場所や小さな入り江など、バスが身を隠せる場所を重点的に狙うことで成果が期待できます。
次に「西部エリア」は西部承水路という大きな河川と葦原、そこに流れ込むインレットや水門が特徴です。このエリアでは「橋攻略」「水の動くインレット」「天候攻略」といった方法が効果的とされています。橋脚周辺やインレット(流入口)付近はバスが潜んでいることが多く、攻略のキーポイントになります。
最後に「残存湖エリア」は東部と西部承水路から流れてくる流入に加え、そこに流れ込む中型河川や水門が特徴です。ここでは「中型河川攻略」「水門攻略」「河口付近攻略」といった方法が有効です。
バス釣り大学のサイトでは「釣れない!と言われる現在の八郎潟ですが、釣れる場所に適切なタイミングで入ることが出来れば普通に釣れます」と指摘しています。また、「ポテンシャルは決して低い場所ではありません」とも述べられており、適切な攻略法を用いれば十分に釣果が期待できることが示唆されています。
2013年から2014年頃のOSPレポートでも、八郎潟で「プリプリの1600グラムオーバー」や「ワンキャストワンヒット」が味わえる可能性が言及されており、適切な時期と攻略法を選べば充実した釣りが楽しめることがわかります。
八郎潟以外の東北地方でリリース可能なバス釣りスポットは青森県や福島県がある
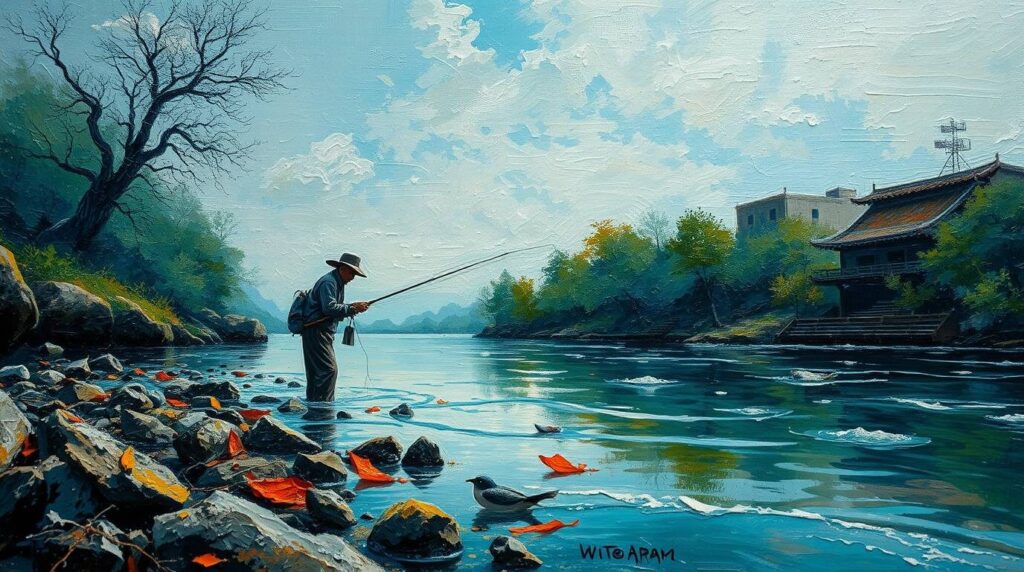
八郎潟でリリース禁止のルールに抵抗を感じる方や、より自由にバス釣りを楽しみたい方には、東北地方の他のバス釣りスポットも検討する価値があります。東北地方では、県によってリリース禁止の有無が異なります。
青森県は、調査によるとリリース禁止規制がありません。ただし、北海道と同様に寒冷な気候のため、バスの生息域は限られている可能性があります。2019年時点の情報では、青森県内でバス釣りが楽しめる水域があるようです。
福島県も同様にリリース禁止の規制がありません。特に裏磐梯エリアは東北地方の有名なバスフィッシングスポットとして知られています。OSPスタッフのレポートでも「福島県裏磐梯は、漁業権があり、年間で多くのお金が一般の釣り人から、漁協に落とされます。貴重な財源のひとつになっている」と述べられており、地元経済との共存モデルが確立されています。
一方、調査によると岩手県や宮城県、秋田県、山形県ではリリース禁止の規制が設けられています。ただし、宮城県には「フィッシングポンド神次郎」と「フィッシャーズイン」という2つの管理釣り場があり、これらの施設では特定外来生物法第5条、環境省・農林水産省の飼養許可を得ているため、リリースが可能とされています。
また、山形県の「前川ダム」は漁業権が及んでいないため、リリースが可能な場所として知られています。
東北地方でバス釣りを楽しむ際には、事前に各県や水域の最新のルールを確認することが重要です。規制は時に変更されることがあり、最新情報を把握しておくことが釣り人としての責任です。
これらの情報は2019年時点のものであり、現在は変更されている可能性もありますので、実際に釣りに行く前には必ず最新の情報を確認することをおすすめします。
全国のバス釣りリリース禁止エリアは14県のみで多くの場所でまだ釣りが楽しめる
全国的な視点で見ると、ブラックバスのリリースが禁止されている県は意外に少ないことがわかります。2019年の調査によると、全国47都道府県中、リリース禁止の規制を設けているのはわずか14県にとどまります。
リリース禁止が導入されている14県は以下の通りです:
- 東北地方:岩手県、宮城県、秋田県、山形県
- 関東地方:栃木県、群馬県(スモールマウスバスのみ)、埼玉県、神奈川県(例外あり)
- 中部地方:新潟県、長野県(野尻湖は例外)、山梨県(例外あり)
- 中国地方:鳥取県、広島県(江の川水系のみ)
- 九州地方:佐賀県(北山湖は例外)
一方、以下の県ではリリースが可能です:
- 北海道(ただしバスの生息は確認されていない)
- 青森県、福島県
- 茨城県、東京都、千葉県
- 静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、石川県、福井県
- 滋賀県(レジャー活動として釣る場合は禁止)、京都府、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県
- 岡山県、島根県、山口県
- 四国地方全県(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)
- 福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県(藺牟田池を除く)、熊本県(江津湖を除く)、長崎県、沖縄県
また、リリース禁止の県であっても、例外的にリリースが認められている水域が存在します。例えば、山梨県の河口湖・山中湖・西湖、長野県の野尻湖、神奈川県の津久井湖・相模湖・丹沢湖・芦ノ湖などです。これらの場所では遊漁料を支払うことでバス釣りを楽しむことができます。
このように、日本全国を見渡すと、まだ多くの場所でバス釣りを楽しむことができます。「バス釣り界隈にとって、お先真っ暗な10年となるでしょう」という悲観的な見方もありますが、現状ではまだ多くの釣り場が残されているといえるでしょう。
ただし、規制は年々厳しくなる傾向にあり、常に最新の情報を入手することが重要です。また、どの釣り場でも地元のルールやマナーを守り、環境に配慮した釣りを心がけることが、今後もバス釣りを続けていくために不可欠です。
まとめ:八郎潟バス釣り禁止は全面禁止ではなくルールを守れば釣りを楽しめる
最後に記事のポイントをまとめます。
- 八郎潟では「バス釣り」そのものは禁止されておらず、釣ったバスをリリース(再放流)することが禁止されている
- リリース禁止は「秋田県内水面漁場管理委員会指示」によって定められており、法的拘束力を持つ
- 違反した場合、漁業法に基づき「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則がある
- 釣ったバスの適切な処理方法は「回収BOXの利用」「持ち帰って食べる」「地域ルールに従って処分」である
- リリース禁止導入の背景には「地元漁業者とのトラブル増加」「環境保全の観点」がある
- 規制導入後、釣り人は減少し水域環境や地元経済にも変化が生じている
- 八郎潟は「東部エリア」「西部エリア」「残存湖エリア」に分かれており、それぞれに適した釣り方がある
- 東北地方では青森県や福島県ではリリースが可能だが、岩手・宮城・秋田・山形ではリリース禁止
- 全国では47都道府県中14県のみがリリース禁止で、多くの場所でまだバス釣りが楽しめる
- 釣り場のルールを守り環境に配慮することが、今後もバス釣りを続けていくために不可欠である
- 八郎潟は適切な攻略法を用いればポテンシャルの高い釣り場であり、ルールを守れば充実した釣りが楽しめる
- リリース禁止の規制は年々厳しくなる傾向にあり、常に最新情報を入手することが重要
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。






