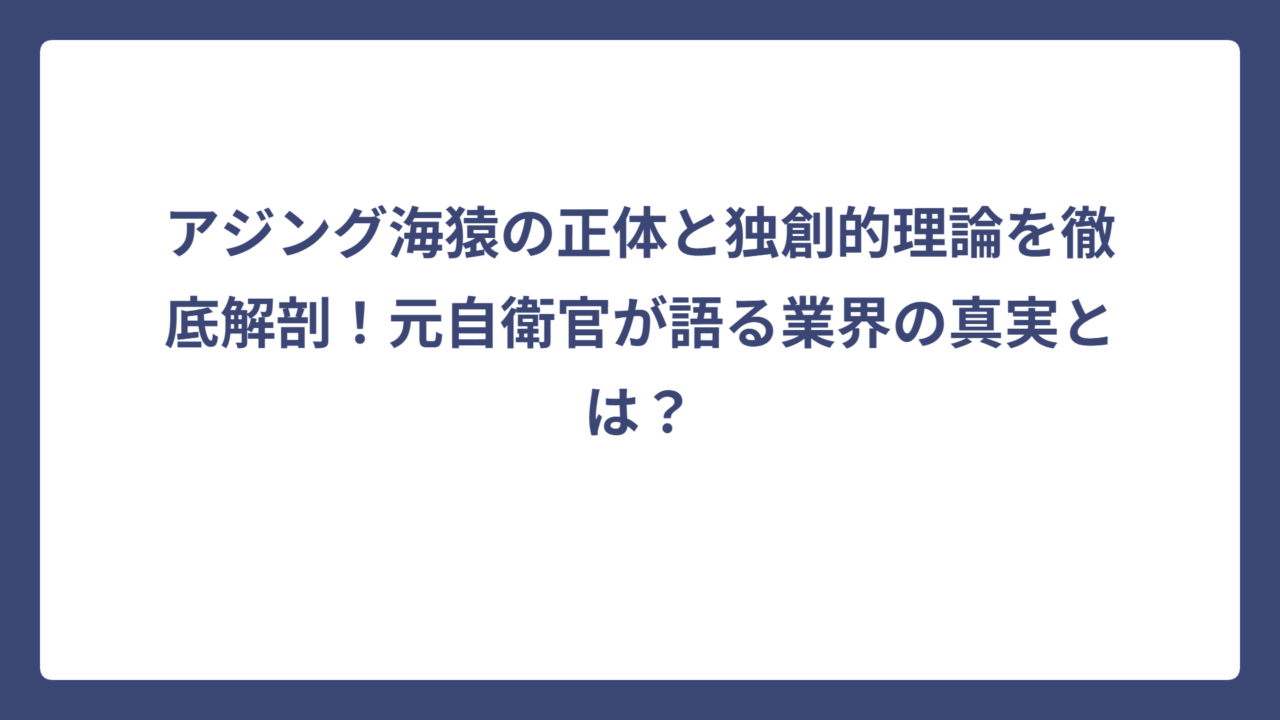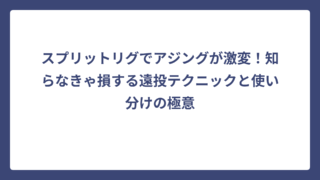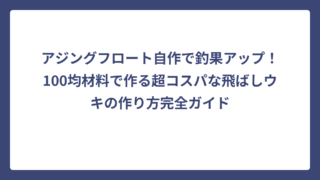アジング界で話題の「海猿」という人物をご存知でしょうか。本名を中村剛士氏といい、30年間勤務した陸上自衛隊を50歳で依願退職し、釣りメーカー「MIZAR」を設立した異色の経歴を持つアングラーです。彼が発信する独創的なアジング理論は、従来の常識を覆す内容で業界に波紋を広げています。
海猿氏は「アミパターンは存在しない」「ワームのカラーは関係ない」など、一般的なアジング理論とは真逆の主張を展開し、多くのアングラーから注目を集めています。また、アジングチャンピオンシップの開催や清掃活動など、業界の発展にも積極的に取り組んでいる人物として知られています。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジング海猿(中村剛士氏)の詳しい経歴と人物像 |
| ✓ 海猿が提唱する革新的なアジング理論の内容 |
| ✓ MIZAR設立の背景と製品開発への想い |
| ✓ 業界に与える影響と今後の展望 |
アジング海猿という人物の正体と経歴
- 海猿の本名は中村剛士で元陸上自衛官という異色の経歴
- 30年間の自衛隊勤務を経て釣りメーカーMIZARを設立
- アジング歴15年以上の実績を持つベテランアングラー
- ブログやYouTubeで独自のアジング理論を発信
- アジングチャンピオンシップなどイベントの企画運営
- 清掃活動を通じた釣り場環境保全への取り組み
海猿の本名は中村剛士で元陸上自衛官という異色の経歴
アジング海猿として知られる人物の本名は中村剛士氏です。彼の最も特筆すべき経歴は、30年間という長期にわたって陸上自衛隊に勤務していたことでしょう。一般的に、釣り業界で活躍する人物の多くは若い頃から釣り関連の仕事に従事していることが多い中、海猿氏は全く異なるキャリアを歩んできました。
自衛隊という規律正しい組織で培われた几帳面さと論理的思考力は、彼のアジング理論の構築にも大きく影響していると考えられます。軍事的な戦術思考や状況判断能力は、魚の行動パターンを分析し、効果的な釣り方を編み出す上で重要な要素となっているのかもしれません。
また、自衛隊での豊富な人生経験は、釣り業界の既成概念にとらわれない独創的な発想を生み出す源泉となっています。多くのアングラーが当たり前だと思っている理論に対して、「本当にそうなのか?」と疑問を投げかける姿勢は、まさに軍人としての検証精神の現れといえるでしょう。
海猿氏は令和4年(2022年)1月に50歳という年齢で自衛隊を依願退職し、長年の夢であった釣りメーカーの設立という新たな挑戦を開始しました。人生の転換点において、安定した公務員生活を手放してまで挑戦する姿勢は、多くの人に勇気と感動を与えています。
自衛隊時代に培った責任感と使命感は、現在のアジング界への貢献活動にも表れており、単なる趣味の範囲を超えて業界全体の発展を考えた活動を展開しています。
30年間の自衛隊勤務を経て釣りメーカーMIZARを設立
海猿氏は30年間という長期にわたる自衛隊勤務を経て、2022年に釣りメーカー「MIZAR(ミザール)」を設立しました。この決断は、単なる趣味の延長ではなく、アジング業界に対する深い想いと使命感に基づいたものでした。
MIZARの設立背景には、海猿氏が感じていた既存の釣り業界への疑問がありました。多くのメーカーが販売促進を目的とした過大表現や根拠のない理論を展開していることに対し、彼は「真実を伝える」ことの重要性を強く感じていたのです。
📊 MIZAR設立の背景要因
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 業界への疑問 | 過大表現や偽りでアングラーを煽る販売手法への不満 |
| 真実の追求 | 根拠に基づいた正確な情報の提供への使命感 |
| 技術革新 | チタンティップなど独自技術の製品開発 |
| アングラー目線 | 実釣経験に基づいた本当に使える製品の提供 |
MIZAR設立当初は、資金面や販路開拓など多くの困難に直面しました。しかし、海猿氏の理論に共感するアングラーたちの支持を得て、徐々に認知度を高めていきました。特に、チタンティップを使用したロッドや独自開発のワームなどは、従来品とは一線を画す性能で注目を集めています。
メーカー設立から約1年後には、かめや釣具などの実店舗でも取り扱いが開始され、一般アングラー向けの販売が本格化しました。これは、個人が立ち上げたメーカーとしては異例のスピードでの成長といえるでしょう。
海猿氏がMIZARを通じて目指しているのは、単なる商品販売ではありません。アジング業界全体のレベルアップと、アングラーが本当に楽しめる釣りの普及が最終的な目標なのです。
アジング歴15年以上の実績を持つベテランアングラー
海猿氏のアジング歴は15年以上に及び、その間に蓄積された実釣経験と技術は業界でも屈指のレベルに達しています。彼の釣行回数は年間を通じて非常に多く、様々な条件下でのアジング経験を積み重ねてきました。
彼の実績で特筆すべきは、単に魚を釣ることだけでなく、その過程で得られた知見を理論化し、他のアングラーに伝える能力に長けていることです。一般的なアングラーが経験則として感じていることを、論理的に説明し、再現可能な形で体系化している点は高く評価されています。
🎣 海猿氏の主な釣行エリアと実績
| エリア | 特徴 | 実績 |
|---|---|---|
| 瀬戸内海 | ホームエリア、年間を通じた継続的な釣行 | 40cm超えの実績多数 |
| 関東エリア | 東京勤務時代の主戦場 | アジング技術の基礎を確立 |
| 九州エリア | 営業活動と釣行を兼ねた遠征 | 地域特性の違いを研究 |
| 日本海 | 異なる環境でのデータ収集 | 理論の汎用性を検証 |
海猿氏の釣りに対するアプローチは、単なる趣味の範囲を超えて研究レベルに達しています。魚の行動パターン、潮流の影響、ベイトフィッシュとの関係など、様々な要素を総合的に分析し、最適な釣り方を導き出すメソッドは多くのアングラーから支持されています。
また、彼の実績は数字だけでなく、理論の正確性にも表れています。従来の常識とは異なる理論を提唱しながらも、実釣で確実に結果を出し続けていることが、その理論の正しさを証明しているのです。
15年という長期間にわたる継続的な活動は、アジングという釣法の発展とともに歩んできた歴史でもあります。初期の頃から最新の技術まで、すべてを体験し理解している数少ないアングラーの一人といえるでしょう。
ブログやYouTubeで独自のアジング理論を発信
海猿氏は「【Real.アジング~真実へ~】第5章」というブログを通じて、独自のアジング理論を発信し続けています。このブログは、従来のアジング常識に疑問を投げかける内容で話題を呼び、多くのアングラーから注目を集めています。
ブログの特徴は、感覚的な表現ではなく論理的で具体的な説明にあります。例えば、「アミパターンは存在しない」という主張についても、単なる個人的な意見ではなく、実釣データと理論的根拠を基に詳細に説明されています。
「アジは常にアミを捕食している印象である。日本人で例えるならば、【白米】である。貴方は外食する時に【白米】の有無を意識してお店を選びますか?」
出典:海猿的アジング考察Vol.81マッチザレンジ【アミパターンは存在しない】
この引用からも分かるように、海猿氏は複雑な理論を身近な例えを使って分かりやすく説明する能力に長けています。アミパターンという一般的に信じられている概念について、アジの食性を詳細に観察した結果として「常にアミを食べているからパターンではない」という独自の見解を示している点は注目に値します。
YouTubeチャンネル「中年ヒーロー」では、より視覚的にアジング理論を解説しており、文字だけでは伝わりにくい技術的な内容も動画を通じて分かりやすく説明されています。これらのメディアを通じた情報発信は、アジング界に新たな視点を提供し、多くのアングラーの釣技向上に貢献しています。
アジングチャンピオンシップなどイベントの企画運営
海猿氏は理論の発信だけでなく、実際のイベント企画・運営も積極的に行っています。特に注目されるのが「アジングチャンピオンシップ」の開催で、これは単なる釣り大会ではなく、真の実力者を決定する本格的な競技として設計されています。
アジングチャンピオンシップの特徴は、参加者のスキルを公正に評価できるルール設定にあります。ボートアジングでの開催により、陸っぱりでは生じがちな場所取りの問題を排除し、純粋な技術力で勝敗が決まる仕組みを構築しています。
🏆 アジングチャンピオンシップ2022の概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催時期 | 令和4年10月~12月の4日間 |
| 参加資格 | 18歳以上、アジング好きなアングラー |
| 試合形式 | 16名によるトーナメント方式 |
| 競技方法 | ボートアジング、JH単体のみ |
| 優勝賞品 | チタンティップロッド(推定75,000円相当) |
このイベントの画期的な点は、参加費に船代や保険料が含まれており、参加者の負担を最小限に抑えていることです。また、競技の模様はインスタライブで生配信され、参加できないアングラーも楽しめる工夫がなされています。
競技ルールも非常に厳格で、「釣った匹数で決定(サイズ問わず)」「JH単体のみ使用可能」「取り込みは自分で行う」など、実力差が明確に現れる設定となっています。これにより、運に左右されにくい真の実力勝負が実現されています。
海猿氏がこのようなイベントを開催する背景には、アジング界のレベルアップへの強い想いがあります。競技を通じて技術の向上を図り、同時にアングラー同士の交流を深めることで、業界全体の発展を目指しているのです。
清掃活動を通じた釣り場環境保全への取り組み
海猿氏の活動で特筆すべきは、単なる釣りの技術向上だけでなく、釣り場環境の保全にも積極的に取り組んでいることです。「瀬戸内海と釣り場を守る友の会【広島】」の活動を通じて、定期的な清掃活動を実施しています。
この清掃活動は、海猿氏が東京勤務時代に千葉県勝浦市で始めた活動がルーツとなっています。当時の活動がSNSを通じて全国に影響を与え、各地でアングラーによる清掃活動が活発化したという実績があります。
🌊 清掃活動の実施概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 活動名 | 瀬戸内海と釣り場を守る友の会【広島】 |
| 開催頻度 | 定期的(月1回程度) |
| 活動内容 | 港湾部や海岸でのゴミ拾い |
| 参加対象 | 一般アングラー、釣り関係者 |
| 協賛企業 | 釣り具メーカー各社 |
清掃活動の重要性について、海猿氏は単なるゴミの除去以上の意味があると考えています。参加者同士の交流を通じて顔見知りになることで、釣り場でのマナー向上に繋がるという長期的な視点を持っているのです。
「ゴミの量が減るというよりも参加された皆さんが交流、顔見知りになる事はいろんな意味で【釣り場のマナー向上】に繋がっていると感じる」
この活動には、釣り具メーカーからの協賛も得られており、業界全体で環境保全に取り組む流れを作り出しています。ただし、海猿氏はメーカーやメディアアングラーがもっと積極的に清掃活動を主導すべきだという厳しい意見も述べており、業界に対する建設的な批判も忘れていません。
清掃活動を継続することで、釣り場に対する地域住民の印象改善や、次世代アングラーへの環境意識の継承など、長期的な効果も期待されています。これらの活動は、海猿氏の人格と責任感を象徴する取り組みといえるでしょう。
アジング海猿が提唱する革新的な釣り理論
- 「アミパターンは存在しない」という従来常識への挑戦
- ワームのカラーは釣果に影響しないという画期的な主張
- アジングに高感度ロッドは不要だという技術論
- レンジコントロールこそが最重要という独自メソッド
- アクションよりもアプローチが重要という実践理論
- ドラグ調整とライン強度の正しい認識方法
- まとめ:アジング海猿が業界に与える革命的インパクト
「アミパターンは存在しない」という従来常識への挑戦
アジング界で広く信じられている「アミパターン」について、海猿氏は明確に「存在しない」と断言しています。この主張は、多くのアングラーやメーカーが当然のものとして扱ってきた概念に対する根本的な疑問提起となっています。
海猿氏の理論によると、アミパターンが存在しないと考える根拠は複数あります。まず、アジを捌く際に必ずといっていいほどアミが胃袋から出てくることから、「アジは常にアミを捕食している」という観察結果があります。これは、特定の状況でのみアミを食べるのではなく、日常的にアミを摂取していることを示しています。
真の「パターン」とは、特定のベイトに固執した魚の状態を指すべきだと海猿氏は主張します。しかし、アミしか胃袋に入っていないアジでも、目の前にイワシやイカが現れればそれらも捕食するため、アミに固執しているわけではないのです。
📋 アミパターン否定論の根拠
| 根拠 | 詳細説明 |
|---|---|
| 常時摂取 | アジは常にアミを食べており、特定パターンではない |
| 食性の柔軟性 | アミ以外のベイトにも積極的に反応する |
| ワームサイズ | アミサイズと大きく異なるワームでも釣れる |
| 実釣結果 | ラメ無しワームや大型ワームでも同様の釣果 |
この理論が業界に与えた影響は非常に大きく、従来「アミパターン専用」として販売されていたワームやルアーの存在意義を問い直すきっかけとなりました。海猿氏は、メーカーが販売促進のために作り出した概念に過ぎないのではないかという疑問も呈しています。
実際の釣り場では、「アミパターンだから」という理由で特定のワームやカラーを選択するアングラーが多く見られますが、海猿氏の実釣データでは、そのような選択をしなくても同等以上の釣果が得られることが証明されています。
この理論は単なる否定論ではなく、アングラーがより本質的な部分(レンジやアプローチ)に集中できるよう導くためのものです。不必要な道具選択に時間を費やすのではなく、魚の居場所や適切なアプローチ方法に意識を向けることで、確実に釣果向上に繋がるというのが海猿氏の考えです。
ワームのカラーは釣果に影響しないという画期的な主張
海猿氏のもう一つの革新的な理論が「ワームのカラーは釣果に影響しない」というものです。この主張は、カラーローテーションが重要だと考える多くのアングラーにとって衝撃的な内容となっています。
この理論の背景には、海猿氏の長年にわたる実釣経験があります。様々なカラーのワームを使用して比較検証を行った結果、カラーによる明確な釣果差は確認できなかったというのが結論です。むしろ、カラー選択に時間を費やすよりも、適切なレンジやアプローチに集中する方が圧倒的に重要だと主張しています。
🎨 カラー無関係論の実証データ
| 検証項目 | 結果 |
|---|---|
| 同一ポイント | 異なるカラーで同様の釣果 |
| 時間帯変化 | カラー変更による釣果差なし |
| 水質条件 | 濁りの有無でカラー差なし |
| ベイト状況 | ベイトカラーとの一致不要 |
海猿氏は「世界中どこのアジも【好きな一色】だけで普通に釣れる」と断言しており、実際に特定のカラーのみを使用して継続的に高い釣果を上げています。この実績が、理論の正しさを実証する何よりの証拠となっています。
従来のカラー理論では、「濁ったらチャート」「クリアならナチュラル」といった経験則が語られてきました。しかし、海猿氏はこれらの理論について、実際の効果よりも心理的な安心感を与える程度の意味しかないのではないかと疑問視しています。
この理論が特に価値を発揮するのは、初心者アングラーの上達過程においてです。カラー選択という複雑な要素を排除することで、より本質的な技術(キャスト精度、レンジコントロール、アクション等)に集中できるようになります。
また、経済的なメリットも無視できません。多数のカラーバリエーションを揃える必要がなくなることで、コストを大幅に削減できる上、荷物も軽量化できます。これにより、より多くの時間を実際の釣りに充てることが可能になるのです。
アジングに高感度ロッドは不要だという技術論
アジング界では長い間「高感度ロッドが必須」という考えが支配的でしたが、海猿氏はこの常識にも疑問を投げかけています。彼によると、現在市販されている1万円以下の安価なロッドでも、アジングに必要十分な感度は確保されており、それ以上の高感度化は釣果向上に寄与しないというのです。
この理論の根拠となっているのは、アジのバイトの性質に関する詳細な分析です。海猿氏は「アジのバイトは特別シビアなわけではない」と断言しており、極端に高感度なロッドでなければ感知できないようなバイトは存在しないと主張しています。
⚡ 感度に関する海猿理論
| 感度の種類 | 重要度 | 海猿氏の見解 |
|---|---|---|
| バイト感度 | 低 | 安価なロッドで十分 |
| 操作感度 | 高 | アジングの核心部分 |
| 反響感度 | 中 | チタンティップで向上可能 |
| スロー感度 | 高 | 最も軽視されている要素 |
海猿氏が重視するのは「バイト感度」よりも「操作感度」です。操作感度とは、リグの動きや位置を正確に把握できる能力のことで、これこそがアジングの上達に欠かせない要素だと説明しています。しかし、現在市販されている多くのロッドは、初心者向けの「パッツン系」と呼ばれる、素早いアクションにのみ特化した設計になっているという問題点も指摘しています。
特に注目すべきは「スローな操作感度」という概念です。これは、ゆっくりとしたリフトやフォール時のリグの状態を正確に感じ取る能力のことで、海猿氏はこれがアジング上達の鍵だと考えています。ところが、市販のロッドのほとんどは、この重要な能力を軽視した設計になっているのです。
「今時のエントリーモデルの【バイト感度】が有れば、アジを捕る性能は十分足りているワケでそれ以上の【感度】なんざ釣果upに全く影響しない。」
この引用は、海猿氏の感度論を端的に表しています。多くのアングラーが高感度ロッドの必要性を信じ込んでいる現状に対し、実釣に基づいた冷静な分析を示している点が注目されます。
海猿氏の理論では、ロッドの価格や感度よりも、使用者の技術と理解が圧倒的に重要だとされています。高価なロッドを購入する前に、まず基本的な技術を身につけることが先決だという主張は、多くの初心者アングラーにとって有益なアドバイスとなっています。
レンジコントロールこそが最重要という独自メソッド
海猿氏のアジング理論の中核を成すのが「レンジコントロール」の重要性です。彼は「マッチザベイト」よりも「マッチザレンジ」が圧倒的に重要だと主張し、この考え方はアジング界に新たな視点をもたらしています。
従来のアジング理論では、ベイトフィッシュの種類に合わせてルアーを選択する「マッチザベイト」の概念が重視されてきました。しかし、海猿氏の長年の観察と実釣結果によると、ベイトの種類よりも「アジがどのレンジで捕食活動を行っているか」を正確に把握することが遥かに重要だというのです。
🎯 レンジコントロール理論の核心
| 要素 | 重要度 | 理由 |
|---|---|---|
| レンジ | 最高 | アジの存在位置そのもの |
| アプローチ | 高 | リグを正確にレンジに送り込む技術 |
| スピード | 中 | レンジ内での滞在時間に影響 |
| ルアー種類 | 低 | レンジが合えばほぼ何でも釣れる |
海猿氏の実釣データでは、正確なレンジに適切なアプローチができれば、ワームの種類やカラーに関係なく安定した釣果が得られることが証明されています。逆に、どんなに高価で優秀なルアーを使用しても、レンジを外していれば全く釣れないという結果も出ています。
レンジコントロールの技術習得には、水深の正確な把握、潮流の影響計算、ジグヘッドの沈下速度理解など、複数の要素を総合的に判断する能力が必要です。これらは一朝一夕に身につくものではありませんが、一度習得すれば確実に釣果向上に繋がる技術です。
特に深場でのアジングにおいて、この理論の威力が発揮されます。水深10メートル以上のポイントでは、1メートルのレンジの違いが釣果を大きく左右することがあり、正確なレンジコントロール技術を持つアングラーと持たないアングラーの差が顕著に現れます。
海猿氏は「全レンジ、全アクション、全アプローチ」を基本方針として掲げており、これは効率的にアジの居るレンジを探り当てるための実践的なメソッドです。闇雲に同じレンジを攻め続けるのではなく、体系的にレンジを探っていくことで、短時間でアジの居場所を特定できるようになります。
アクションよりもアプローチが重要という実践理論
多くのアングラーが重視する「アクション」について、海猿氏は「アジングにアクションは関係なし」という大胆な理論を展開しています。この主張は、日本全国様々なポイントでの豊富な実釣経験に基づいており、従来のアジング常識を根底から覆すものです。
海猿氏の観察によると、アングラーが「今日のヒットパターンはこのアクション」だと感じる現象の多くは、実際にはアクションの違いではなく、リグのレンジが変わったことによるものだというのです。アクションを変えることで、意図せずアジの居るレンジにリグがアプローチできたため、結果的に釣れたという状況が大部分を占めているという分析です。
🎣 アクション無関係論の実証例
| 状況 | アングラーの認識 | 実際の原因 |
|---|---|---|
| ボトムステイで爆釣 | ステイが効いた | 実はテンションフォールでレンジ直撃 |
| リフト&フォールで連発 | アクションが良かった | リフト時にアジのレンジを通過 |
| 巻きで好調 | スピードが合った | 一定レンジでの長時間滞在 |
| ただ巻きで釣果 | シンプルが一番 | 偶然適正レンジをトレース |
海猿氏は日本各地(広島、山口、千葉、神奈川、茨城など)で釣行を重ねていますが、どのエリアでも基本的に同じアクションでアジングを行い、安定した釣果を上げています。この実績が、地域による有効アクションの違いが存在しないことを証明しています。
特に興味深いのは、隣で「特定のアクションでないと釣れない」と主張するアングラーがいる状況で、海猿氏が全く異なるアクションでも同様の釣果を上げているという事例です。これは、アクション理論の多くが思い込みに過ぎないことを示す強力な証拠となっています。
「限定的なアクションやカラーでないと釣れない状況に遭遇してないだけか?まあ、隣りでボコボコに釣られて『我は釣れない』状況にでも成らなければ、この考え方は変わる事は無いだろう。」
この引用からは、海猿氏の理論に対する絶対的な自信と、それを裏付ける実釣能力の高さが伺えます。理論だけでなく実践で証明し続けている点が、多くのアングラーから支持される理由となっています。
海猿氏が重視するのは、アクション以上に「アプローチの精度」です。キャスト精度、着水点の選択、リトリーブコース等、ルアーをアジの前に正確に通すための技術こそが最重要だと説いています。
ドラグ調整とライン強度の正しい認識方法
アジングにおけるドラグ調整について、海猿氏は多くのアングラーが間違った設定をしていると指摘しています。特に、「ライン強度の限界よりも遥かに緩いドラグ設定」をしているアングラーが多すぎるという問題を取り上げています。
海猿氏によると、適切なドラグ調整には明確な目的があります。第一に「ライン強度が限界に達する前に力を逃がしてラインブレイクを防ぐ」こと、第二に「魚が暴れてテンションが抜けた状態を抑えフックアウトを防ぐ」ことです。しかし、多くのアングラーは後者の理解が不十分で、必要以上に緩いドラグ設定をしているのです。
⚙️ 適切なドラグ調整の基準
| 対象魚サイズ | 推奨ドラグ設定 | 理由 |
|---|---|---|
| 極豆アジ(表層) | やや緩め | フックアウト防止重視 |
| 一般サイズ | ライン強度に近い設定 | 効率的なやり取りのため |
| 大型アジ | ライン強度上限 | 十分なストッピングパワー確保 |
| 不明サイズ | 標準設定 | 汎用性を重視 |
海猿氏が特に問題視するのは、20センチクラスのアジにもかかわらずドラグが「ジージー」と音を立てて滑る設定にしているアングラーです。このような設定では、不必要にやり取り時間が長くなる上、ラインに無駄なヨレを与えてしまいます。
ライン強度についても、メーカー表示をそのまま信じることの危険性を指摘しています。各メーカーのテスト条件や表示基準が異なるため、表示強度と実際の使用時強度には差があることを理解する必要があるのです。
海猿氏の推奨するライン強度の確認方法は、実釣を通じた体感的な把握です。理論値だけでなく、実際の使用感を通じてそのラインの真の強度を理解することが重要だと説明しています。
また、ラインブレイクの原因分析も重要な要素として挙げられています。ライン本来の強度不足なのか、結束部分の問題なのか、正確な原因把握なしに極端なドラグ調整をすることの危険性も警告しています。
まとめ:アジング海猿が業界に与える革命的インパクト
最後に記事のポイントをまとめます。
- 海猿(中村剛士氏)は30年間の陸上自衛隊勤務を経て釣りメーカーMIZARを設立した異色の経歴を持つ
- 15年以上のアジング歴で培った豊富な実釣経験と理論構築能力を持つベテランアングラーである
- 「アミパターンは存在しない」という従来常識を覆す理論を実釣データで証明している
- ワームのカラーは釣果に影響しないという画期的な主張を展開している
- アジングに高感度ロッドは不要で安価なロッドでも十分な性能があると断言している
- バイト感度よりも操作感度、特にスローな操作感度が重要だと説いている
- マッチザベイトよりもマッチザレンジが圧倒的に重要だという独自理論を確立している
- レンジコントロールこそがアジング上達の最重要要素だと位置づけている
- アクションの違いは釣果に影響せず、アプローチの精度が決定的だと主張している
- 多くのアングラーが間違ったドラグ調整をしており適切な設定方法を提唱している
- アジングチャンピオンシップなどイベント企画を通じて業界発展に貢献している
- 清掃活動による釣り場環境保全に積極的に取り組んでいる人物である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 【Real.アジング~真実へ~】第5章
- 第2話【釣れない理由を正しく知る】その1 – MIZAR オンラインショップ
- 海猿的アジング考察|【Real.アジング~真実へ~】第5章
- 【Real.アジング~真実へ~】 【海猿的アジング考察】
- 【海猿的アジング考察73】アジングと感度 | 【Real.アジング~真実へ~】第5章
- 【Real.アジング~真実へ~】 【海猿的アジング考察55】とご報告
- 【海猿的アジング考察76】ドラグとライン強度 | 【Real.アジング~真実へ~】第5章
- 海猿さんのプロフィールページ
- 【Real.アジング~真実へ~】第5章
- #海猿 人気記事(一般)|アメーバブログ(アメブロ)
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。