茨城県の野池でバス釣りを楽しむ方が増えています。高場池緑地広場や北条大池など、つくば市周辺には40cmアップの大物が狙える野池が点在しており、アクセスの良さと手軽さから人気を集めているスポットがあります。
野池は大きな湖や川と比べてコンパクトなフィールドのため、地形を把握しやすく、バスの居場所も絞りやすいという特徴があります。ただし、水深が浅く障害物も多いため、適切なタックル選びとアプローチ方法を知っておく必要があります。
記事のポイント!
- 茨城県の主要な野池スポットの特徴と釣果情報
- 季節や時間帯によるポイントの使い分け方
- 野池で効果的なタックルとルアーの選び方
- 釣り場のマナーと長く楽しむためのルール
茨城県の野池バス釣りスポット完全ガイド
- 人気の野池が集中するつくば市エリアの特徴
- かすみがうら市周辺の野池でバスが釣れるポイント
- 小美玉市の野池で40アップが狙える場所
- 土浦市エリアの野池の特徴と釣果情報
- 水戸市周辺の野池で釣れるバスの特徴
- アクセスが良く初心者向けの野池スポット
人気の野池が集中するつくば市エリアの特徴
つくば市には北条大池をはじめとする野池が点在しています。特に北条大池は無料の駐車場が完備されており、足場も良好です。池の周囲は歩きやすく整備されており、初心者でも安心して釣りを楽しめます。
護岸整備されている側と護岸整備されていない側に分かれており、それぞれ異なるアプローチが可能です。目に見えるストラクチャーは少ないものの、水中には豊富なカバーがあり、バスの居場所を見つけやすい特徴があります。
プレッシャーが高いため、タイミングとルアーのチョイスが重要になってきます。シャロークランクやワームなど、状況に応じて使い分けることで結果を出せます。
夏場は水生植物が生い茂り、釣りづらくなる場所もありますが、その分バスのホールドも良くなります。天候や時期によって状況が大きく変化するため、その日の状況を見極めることが重要です。
朝マズメや夕マズメなど、時合いを狙って訪れる人が多いスポットです。ヘラブナ釣りの方も多く訪れるため、お互いの釣り場を譲り合うマナーも大切です。
かすみがうら市周辺の野池でバスが釣れるポイント
かすみがうら市の野池群は、水深が浅く、オーバーハングやブッシュなど、バスの隠れ場所が豊富です。特に葦が生い茂るエリアは、バスのホールディングポイントとして注目です。
水質はステイン気味で、夏場はアオコが発生する場合もあります。そのため、フローティングワームやフロッグなど、表層を意識したルアーが効果的です。水中植物が多いため、タックルは強めのものを選択するのがおすすめです。
駐車スペースは限られており、2-3台程度が限界の場所がほとんどです。そのため、早朝や平日を狙って訪れる人が多く見られます。季節によって水位が変動するため、同じポイントでも違った釣り方が必要になってきます。
ここではダウンショットリグやネコリグなど、繊細なアプローチが効果的です。特に小バスが多く生息しており、数釣りを楽しむことができます。
釣り場周辺には民家も多いため、騒音や駐車には特に注意が必要です。ゴミの持ち帰りはもちろん、周辺住民への配慮を忘れずに楽しみましょう。
小美玉市の野池で40アップが狙える場所
小美玉市の高場池緑地広場は、3つの池が連結した珍しい構造を持つ野池です。それぞれの池で異なる特徴があり、バスの生息密度も異なります。駐車場は4-5台分のスペースがあり、アクセスも良好です。
第一の池は足場が良く、様々なストラクチャーがあるため、多彩な釣り方を試すことができます。水中で根がかかりにくい特徴があり、巻物のルアーも使いやすい環境です。
第二の池は長靴またはウェーダーが必須で、やや藪漕ぎが必要になりますが、良いサイズが期待できます。ぬかるみが多く滑りやすいため、安全面での注意が必要です。
第三の池は水中植物が多く、巻物での釣りは難度が高めです。多くのアングラーがスモラバやワームを使用しており、対岸のオーバーハングを狙うアプローチが効果的です。
フローター使用も可能ですが、池のサイズを考えると岸からのアプローチで十分にカバーできます。この池では40アップのビッグバスも生息しているため、強めのタックル選びがおすすめです。
土浦市エリアの野池の特徴と釣果情報
土浦市の鶴沼公園は、釣りが公認されている数少ない公園内の野池です。無料駐車場が東西に設けられており、合計で25台程度の駐車が可能です。足場も良好で、初心者でも安心して釣りを楽しめる環境が整っています。
チャターやアシ打ちなど、様々な釣り方でアプローチが可能です。ストラクチャーも点在しているため、場所によって異なる釣り方を楽しむことができます。時合いやタイミングが合えば、良いサイズのバスも狙えます。
ただし、足場の良さから人気のポイントとなっているため、プレッシャーは比較的高めです。公園という性質上、他の利用者への配慮も必要になってきます。特に投げ方には注意が必要です。
水質はややステインで、季節によって変化します。ゴミ問題が重要視されており、看板等でも注意喚起がされています。ルールを守って釣りを楽しまないと、釣り禁止になる可能性もあるため、マナーには特に気を付けましょう。
東駐車場からコンビニまでは車で約2分と近く、長時間の釣行でも安心です。ただし、現地に自動販売機はないため、飲み物などは事前に準備しておくことをおすすめします。
水戸市周辺の野池で釣れるバスの特徴
水戸市の清水沼は、公園として整備された野池です。春先には桜が咲き、景観も楽しめるスポットとなっています。駐車スペースは最低でも5台分は確保されており、アクセスの良さが特徴です。
水質は比較的クリアで、魚影を確認しやすい特徴があります。ブルーギルも多く生息しており、バスのエサ場として機能しています。水深はそれほど深くないため、シャローパターンでの釣りが中心となります。
リリーパッドが多く生息しているため、巻物での釣りには工夫が必要です。フロッグやワームでの釣りがメインとなり、特にリリーパッド周りの攻略が重要になってきます。50センチアップのビッグバスも生息しており、大物狙いの醍醐味も味わえます。
公園利用者も多いため、キャスト時は周囲への注意が必要不可欠です。駐車スペースは広めですが、プレッシャーも高いため、時間帯を考えた釣行が重要になってきます。
汲み取り式のトイレは設置されていますが、現地には自販機がないため、必要な装備や飲み物は事前に準備しておく必要があります。コンビニは車で約3分の位置にあり、補給も容易です。
アクセスが良く初心者向けの野池スポット

つくば市の四ツ谷池は、プレッシャーは高いものの、初心者でも楽しめる野池です。駐車スペースは6-7台分あり、周辺の住宅地への配慮が必要です。スモールマウスバスが生息する珍しいポイントとして知られています。
コンビニは車で約6分の場所にあり、長時間の釣行にも対応できます。夏場は水生植物が生い茂り、冬場は減水するなど、季節によって異なる様相を見せる特徴があります。
護岸整備がされている箇所と自然のままの箇所があり、それぞれで異なるアプローチが可能です。足場の良い場所が多く、安全に釣りを楽しめる環境が整っています。
水質はステインまたはややマッディで、シーズンによって変化します。杭やブッシュなど、様々なストラクチャーが存在し、バスのホールディングポイントとして機能しています。
ヘラブナ釣りの方も多く訪れるため、お互いの釣り場を譲り合うマナーが重要です。初心者でも安全に釣りを楽しめる環境が整っているため、バス釣りデビューにもおすすめのポイントとなっています。
茨城県の野池バス釣りで確実に釣果を上げる方法
- 野池で効果的なタックル選びのポイント
- 季節別の攻略ポイントと釣れるルアー
- 野池特有の地形を活かした釣り方のコツ
- 水質や天候による釣果の変化と対応策
- マナーを守って長く楽しめる野池の使い方
- まとめ:茨城県の野池バス釣りを楽しむためのポイント
野池で効果的なタックル選びのポイント
野池での釣りには、障害物の多さを考慮したタックル選びが重要です。水深が浅く、水中に沈んだ木や水生植物が多いため、ラインは6ポンドクラスのものが適しています。PEラインに0.3号のショックリーダーを組み合わせることで、フッキング率を上げることができます。
ワームには3.5インチのカットテールワームが効果的です。特にゲーリーヤマモトのカットテールワームは実績が高く、ウォーターメロンペッパーカラーがおすすめです。ヘッドはダウンショットリグやネコリグなど、状況に応じて使い分けることで結果を出せます。
ロッドはPALMS EDGE PRIDE EPGC-604改などのベイトフィネスタックルが有効です。リールはカルカッタコンクエストBFSやSVスプール搭載のT3など、精密なキャストが可能なものを選びましょう。アベイルのカスタムパーツを組み合わせることで、さらなる性能向上も期待できます。
ネットは長めのものを選択すると安心です。ジャクソンのスーパートリックスターネット 380は、障害物に絡んだ際の手繰り寄せにも対応できる優れものです。
タモは必須アイテムとなりますが、それ以外にも虫よけスプレーや長靴、帽子なども必要装備となります。特に夏場は蚊が多いため、虫よけは重要なアイテムとなります。
季節別の攻略ポイントと釣れるルアー
春先は水温の上昇とともにバスの活性が高まります。この時期は水生植物が少なく、巻物のルアーが効果的です。特にシャロークランクやスイムジグでの攻略が有効で、朝マズメ時に良い結果を残せます。
夏場は水生植物が繁茂し、特にリリーパッドが目立ってきます。この時期はフロッグやフローティングワームなど、表層を意識したルアーが効果的です。朝夕の時間帯がベストで、日中は活性が下がる傾向にあります。
秋は再びバスの活性が上がり、サイズアップも期待できる季節です。チャターベイトやスピナーベイトなどのバイブレーション系ルアーが効果的で、水面直下を意識したアプローチが重要です。
冬場は水位が下がり、ポイントが限定される傾向にあります。この時期はスモールラバーやワームなど、シビアなアプローチが必要となります。バスのサイズは小さめですが、数は狙えます。
雨後は水質が濁ることが多く、バスの活性も変化します。この時期はダウンショットリグやネコリグなど、バスに見つけやすいセッティングが効果的です。
野池特有の地形を活かした釣り方のコツ
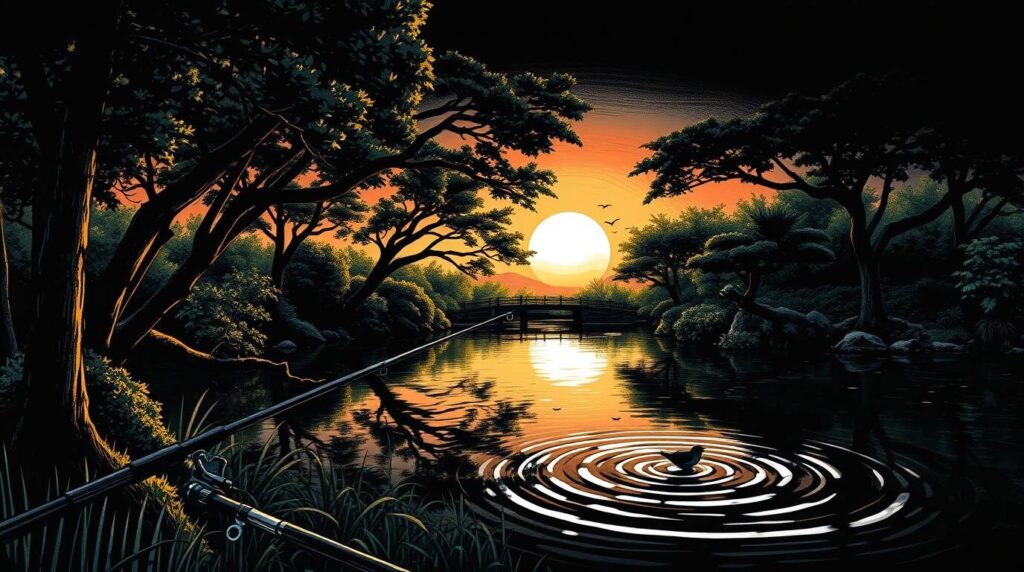
野池では、オーバーハングやブッシュなどの自然のカバーが重要なポイントとなります。特に木の根や倒木周りは、バスの定位置となっていることが多く、丁寧なアプローチが必要です。
護岸整備されている場所では、コンクリートの隙間や段差がバスのホールディングポイントとなります。この場合、ルアーを護岸に当てながらスローに巻くアプローチが効果的です。
浅場は特に重要なポイントとなります。水深1メートル前後の場所では、小型のベイトフィッシュが多く集まり、バスの活性も高くなります。この場合、シャロークランクやスピナーベイトでの探り釣りが有効です。
水生植物帯はバスの隠れ家となっています。特に葦際やリリーパッド周りは、重点的にチェックすべきポイントです。フロッグやワームでの攻略が基本となります。
池の中央部は意外と見落としがちですが、重要なポイントとなることがあります。特に池底に段差がある場所では、その落ち込みにバスが定位置を構えていることがあります。
水質や天候による釣果の変化と対応策
野池の水質は、ステインからマッディまで様々です。クリアな水質の場合は、ナチュラルカラーのワームが効果的です。濁った状況では、視認性の高いカラーを選択することで、バスに見つけてもらいやすくなります。
天候の変化は、バスの活性に大きく影響します。曇天時は比較的安定した釣果が期待できますが、晴天時は朝夕の時間帯に活性が集中する傾向があります。雨天時は水位の上昇に注意が必要です。
アオコの発生は夏場に多く見られる現象です。この場合、表層を意識したルアーの使用が効果的です。また、アオコの少ない場所を探して釣りを進めることで、安定した釣果を狙えます。
風向きも重要な要素となります。特に風下側は、ベイトフィッシュが集まりやすく、バスの活性も高くなります。ただし、強風時は安全面に十分注意が必要です。
季節による水温の変化も、バスの活性に大きく影響します。水温が低い時期は、ゆっくりとしたアプローチが効果的です。水温が上がってくると、アグレッシブなアプローチも有効となります。
マナーを守って長く楽しめる野池の使い方
野池でのマナーは、継続的な釣行を可能にする重要な要素です。特にゴミの持ち帰りは最重要事項で、ラインやルアーなどの釣具のゴミも必ず回収する必要があります。
駐車マナーも重要です。指定された駐車スペース以外には停めず、台数制限のある場所では確実に守る必要があります。特に野池周辺は住宅地が近いことが多く、地域住民への配慮が欠かせません。
他の釣り人との共存も重要です。特にヘラブナ釣りの方々との共存が必要で、お互いの釣り場を尊重し合うことが大切です。声を掛け合って、気持ちよく釣りができる環境を作りましょう。
道具の放置や大声での会話は避けるべきです。特に早朝や夕方は、静かに釣りを楽しむことを心がけましょう。また、岸辺の草刈りなどの環境整備にも協力的な姿勢を持つことが重要です。
安全面での配慮も忘れてはいけません。特に子供連れの方や散歩している方への注意が必要です。キャスト時は周囲の安全確認を徹底し、事故のない釣り場づくりに貢献しましょう。
まとめ:茨城県の野池バス釣りを楽しむためのポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- 野池は水深が浅く障害物が多いため、6ポンド程度の適切なラインとロッド選びが重要
- ダウンショットリグやネコリグなど、状況に応じたリグの使い分けが必須
- 季節によって水生植物の量や水質が変化するため、それに応じたルアー選択が必要
- オーバーハングやブッシュなどの自然のカバー周りが重要なポイント
- 朝マズメ・夕マズメなど、時合いを見極めた釣行計画が効果的
- 駐車スペースは限られているため、早めの到着を心がける
- ヘラブナ釣りの方との共存を意識し、お互いの釣り場を尊重
- ゴミの持ち帰りは必須で、特にライン類の回収を徹底
- 長靴や虫よけなど、環境に応じた装備の準備が重要
- 周辺住民への配慮を忘れず、継続的に釣りを楽しめる環境づくりを心がける
- 水質や天候の変化に応じて、ルアーやアプローチを変える柔軟性が必要
- 安全面での配慮を忘れず、事故のない釣り場づくりに貢献する
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。






