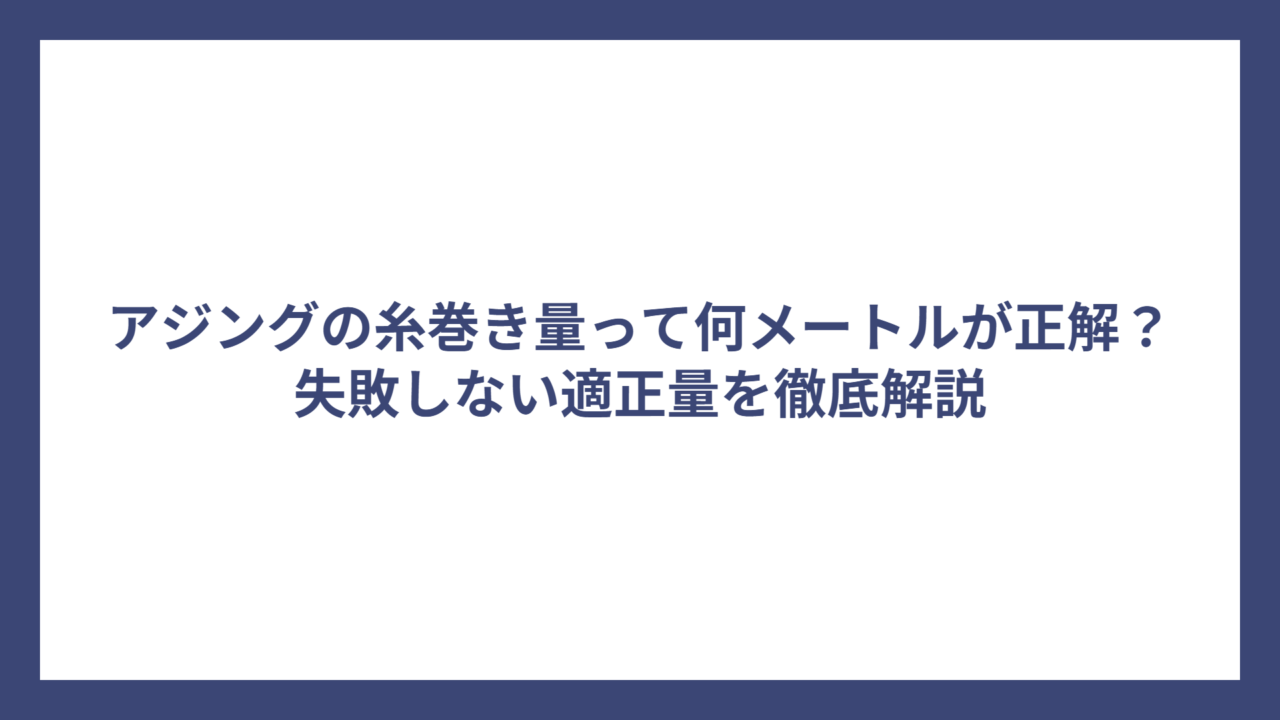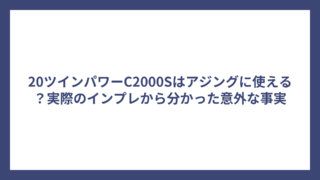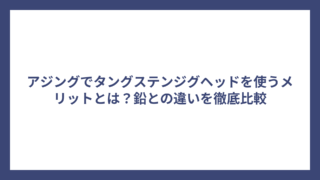アジングを始めようとして、いざリールにラインを巻こうとしたとき「何メートル巻けばいいの?」と迷った経験はありませんか?実は糸巻き量はアジングの快適さや釣果を左右する重要な要素です。多すぎればライントラブルの原因になり、少なすぎれば高切れした際に釣りが続けられなくなってしまいます。
この記事では、インターネット上に散らばるアジング上級者の意見や、メーカーの推奨値、実際の使用感などを総合的に収集・分析し、初心者から中級者まで納得できる糸巻き量の答えを提供します。さらにライン選びやリール選び、下巻きの活用法など、糸巻き量と関連する情報も網羅的に解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジングに最適な糸巻き量は100m〜150m |
| ✓ ライントラブルを防ぐシャロースプールの選び方 |
| ✓ エステルライン・PEライン別の推奨巻き量 |
| ✓ 高切れ対策としての予備ライン確保術 |
アジングの糸巻き量は100m〜150mがベスト
- アジングの適正糸巻き量は100m〜150m
- 飛距離は20m前後なので50mでも理論上は足りる
- 高切れやトラブルに備えて余裕を持たせることが重要
- シャロースプールを選ぶべき理由
- 下巻きを活用してラインを無駄なく使う方法
- 糸巻き量が多すぎるとライントラブルの原因になる
アジングの適正糸巻き量は100m〜150mが結論
アジングにおける糸巻き量の結論は、100m〜150mが最適です。この数値は多くの経験豊富なアジンガーや専門サイトで推奨されており、実用性と安全性のバランスが取れた範囲と言えるでしょう。
100m以下では高切れやライントラブルが発生した際に釣りを続けられなくなるリスクが高まります。一方で、150mを大きく超える量を巻くと、細いラインの特性上、スプールへの巻き厚が増してライントラブルが起こりやすくなります。
PEを巻くときは150mの物を巻いてます、なぜなら50m飛ばしても100m残るからです、100mの物で50m飛ばすと50mしか残らないでしょ?もしも高切れで20m、30mを何度か失うとどうします?
上記の引用からも分かるように、ベテランアングラーは予備ラインの重要性を強調しています。実際の釣行では、根掛かりによる切断、高切れ(キャスト時にラインが切れること)、擦れによる劣化など、ラインが減っていく要因は多数存在します。
一般的なアジングでは1g前後のジグヘッドを使用するため、飛距離は20m程度が平均的です。極端に言えば50mあれば釣りは成立しますが、トラブル時の予備を考慮すると、やはり100m〜150mという範囲が現実的な選択肢となります。
特に夜釣りがメインとなるアジングでは、暗闇でのライン交換は非常に困難です。釣行中にラインが足りなくなって帰宅を余儀なくされることは避けたいものです。そのため、初めてアジングに挑戦する方は、まず150m程度を目安に巻いておくことをおすすめします。
また、リールに巻き替えるタイミングとしては、キャストして下巻きが見えそうになったとき、つまり最後の40〜50m程度になったときが一つの目安となります。この段階で新しいラインに交換すれば、常に十分な量を確保でき、安心して釣りに集中できるでしょう。
飛距離は20m前後なので理論上50mでも足りる理由
アジングにおける実際の飛距離を考えると、理論上は50mでも釣りは成立します。なぜなら、ジグ単(ジグヘッド単体)での飛距離は20m程度が平均的だからです。
メバリングでは1g前後のジグヘッドを多く使うことになりますし、飛距離は20m飛べばいいほうでしょう。もっと軽いジグヘッドを使うと、10mも飛びません。
上記はメバリングについての記述ですが、アジングも同様の軽量リグを使用するため、飛距離の考え方は共通しています。1g以下のジグヘッドを使用する場合は、さらに飛距離が短くなり、10m程度ということも珍しくありません。
📊 ジグヘッドの重さと飛距離の関係
| ジグヘッドの重さ | 平均飛距離 | 必要な糸巻き量(理論値) |
|---|---|---|
| 0.6g〜0.8g | 10m〜15m | 30m〜40m |
| 1g〜1.5g | 20m前後 | 50m程度 |
| 2g以上 | 30m以上 | 70m以上 |
しかし、この理論値はあくまで「釣りが成立する最低限の量」であり、実釣においては推奨できません。なぜなら以下のようなリスクが存在するからです。
まず、高切れのリスクです。キャスト時にラインが切れてジグヘッドとワームが飛んでいってしまうことがあります。1回の高切れで20m〜30mのラインを失うこともあり、50mしか巻いていない場合、2〜3回の高切れで釣りが続けられなくなります。
次に、根掛かりによるライン切断です。アジングは底を攻める釣りも多く、根掛かりは避けられません。根掛かりで切れる位置は予測不可能で、手元近くで切れることもあります。30m出して根掛かりし、手元近くで切断された場合、残りのラインは20mということもあり得ます。
さらに、ラインの劣化による定期的なカットも必要です。特に擦れやすい先端部分は、数回の釣行ごとに1〜2mカットすることが推奨されます。これを繰り返すと、あっという間にラインが短くなってしまいます。
したがって、飛距離だけを基準に糸巻き量を決めるのではなく、トラブル時の予備や消耗を考慮した量を巻くことが、快適なアジングには不可欠です。
高切れやトラブルに備えて余裕を持たせることの重要性
アジングでは高切れやライントラブルが頻繁に発生するため、糸巻き量に余裕を持たせることが極めて重要です。特にエステルラインを使用する場合、その傾向は顕著になります。
高切れとは、キャスト時にラインが切れてしまう現象です。エステルラインは感度が良い反面、強度が低く伸びが少ないため、キャストの衝撃でプチッと切れることがあります。PEラインに比べて直線強度が低いため、0.3号のエステルラインは1.5〜1.8lbsという細さです。
糸巻き量を少なめに巻くことでライントラブルは激減します。「ルミナシャイン」の糸巻量は200m。ジグ単ゲームでメインに使用されることの多い、シャロースプールの小型スピニングリールに巻く場合は、下巻き無しのリーリング100回転前後、長さで言うと65m程を巻いて使用しています。
このように、プロアングラーでも100回転(約65m)程度を基準にしていますが、これは最低限の量です。初心者の場合、高切れの頻度が高くなる傾向があるため、さらに余裕を持たせた方が安全でしょう。
ライントラブルの種類としては、以下のようなものがあります。
⚠️ アジングで起こりやすいライントラブル
- ✅ 高切れ:キャスト時にラインが切れる(20〜30m消失)
- ✅ 根掛かり:底の障害物に引っかかって切れる(10〜40m消失)
- ✅ バックラッシュ:ラインが絡まって使用不可(数メートル〜数十メートル消失)
- ✅ 擦れによる劣化:ガイドやリーダーとの結束部の擦れ(1〜2m定期的にカット)
特に注意すべきなのは、これらのトラブルが連続して起こる可能性があることです。たとえば、釣行開始後まもなく高切れで30m失い、その後根掛かりで20m失うと、わずか50mで釣りが終了してしまいます。
また、遠征での釣行や夜間の釣行では、ラインが足りなくなった際の対処が困難です。営業している釣具店が近くにない場合や、夜中で店が閉まっている場合、予備のスプールやリールを持っていなければ、その場で釣りを諦めるしかありません。
したがって、糸巻き量には十分な余裕を持たせ、万が一のトラブルに備えることが、アジングを楽しむための基本と言えるでしょう。100m〜150mという推奨値は、こうしたリスク管理の観点からも妥当な範囲です。
シャロースプールを選ぶべき3つの理由
アジングにおいては、シャロースプール(浅溝スプール)のリールを選ぶことが強く推奨されます。シャロースプールとは、通常のスプールよりも溝が浅く設計されたもので、細いラインを少量巻くのに適した構造です。
メバリングで使うリールですが、シマノであってもダイワであっても「2000番手」がおすすめで、絶対的に【シャロースプール】モデルの選択をおすすめします。
シャロースプールを選ぶべき理由は主に3つあります。
第一に、ライントラブルの軽減です。アジングでは0.3号前後の極細ラインを使用しますが、深溝のスプールに少量だけ巻くと、スプール径が小さくなりすぎて、ラインに強い癖がついてしまいます。これがライントラブルの原因となります。シャロースプールであれば、適切なスプール径を維持しながら少量のラインを巻くことができます。
第二に、キャスト時の放出性向上です。スプールからラインが放出される際、浅溝の方が抵抗が少なくスムーズに放出されます。これにより飛距離が伸び、軽量リグでもストレスなくキャストできます。特にアジングロッドはガイド径が小さく設計されているため、ライン放出性の良いシャロースプールとの相性が抜群です。
第三に、リールの軽量化です。シャロースプールは通常のスプールよりも軽量に作られているため、リール全体の自重も軽くなります。アジングは繊細な釣りであり、手感度が重要です。リールが軽ければ軽いほど、アジの小さなアタリを感じ取りやすくなります。
🎣 シャロースプールと通常スプールの比較
| 項目 | シャロースプール | 通常スプール |
|---|---|---|
| ライントラブル | 少ない | 多い(少量巻き時) |
| キャスト性能 | 良好 | やや劣る |
| 自重 | 軽い | やや重い |
| 適正糸巻き量 | 100〜150m程度 | 200m以上 |
| 価格 | やや高い | 標準 |
シャロースプール搭載のリールを選ぶ際は、品番に「S」や「SS」といった記号が付いているモデルを探すとよいでしょう。たとえば「2000S」や「C2000S」といった表記がシャロースプールを示しています。
ただし、シャロースプールモデルは通常モデルに比べてやや価格が高い傾向があります。予算が限られている場合は、通常スプールに下巻きを施すことで、ある程度同様の効果を得ることも可能です。とはいえ、長期的に快適なアジングを楽しむのであれば、最初からシャロースプールモデルを選んでおくことをおすすめします。
下巻きを活用してラインを無駄なく使う方法
糸巻き量を適正に保ちつつ、ラインを経済的に使うための方法が下巻きの活用です。下巻きとは、メインラインの下に別のラインを巻いて、スプール容量を調整する技術です。
下巻きを使用するメリットは複数あります。まず、ラインの節約です。たとえば150mのラインを購入した場合、リールの糸巻き量が200mあると、ラインだけでは適切な巻き量に達しません。下巻きを使えば、150mのラインを無駄なく使い切ることができます。
次に、スプール径の調整です。前述のとおり、スプール径が小さすぎるとラインに癖がつきやすくなります。下巻きを施すことで、適切なスプール径を維持できます。
さらに、コストパフォーマンスの向上です。高価なPEラインやエステルラインを大量に巻くよりも、安価なナイロンラインで下巻きをした方が経済的です。
💡 下巻きの計算方法
下巻きに必要なライン量を計算するには、シマノの公式サイトにある「糸巻量計算ツール」が便利です。このツールでは、リールの型番、使用したいラインの種類と太さ、目標の巻き量を入力すると、必要な下巻き量が自動計算されます。
すると下巻きにナイロン2号(DUELのCN500)を使うのですが、これを36メートル巻けば良いと出ました。ボクが今回巻きたいリールはシマノのC2000Sですがこれの一回転の糸巻量がたしか64cmですので下巻きのラインを56回転分巻けば良いという事になります。
このように、リールのハンドル1回転あたりの糸巻量から、必要な回転数を計算することもできます。ただし、実際にはトラブル回避のため、計算値よりも若干少なめに巻くことが推奨されます。
下巻きに使用するラインの種類としては、ナイロンラインが最も一般的です。太さは2号程度が扱いやすく、適度なクッション性があるため、メインラインとの段差も気になりません。色は視認性の高い色でも構いませんが、メインラインとの境界が分かりやすい色を選ぶと、巻き替えのタイミングが把握しやすくなります。
下巻きを施す際の注意点として、テンションをかけすぎないことが挙げられます。強く巻きすぎるとスプールが変形したり、ラインが食い込んでトラブルの原因となります。適度なテンションで、均一に巻いていくことが重要です。
糸巻き量が多すぎるとライントラブルが増える理由
糸巻き量は少なすぎても問題ですが、多すぎてもライントラブルの原因となります。特に細いエステルラインやPEラインを使用するアジングでは、この傾向が顕著です。
糸巻き量が多すぎることによる具体的な問題点は以下のとおりです。
まず、スプールからの糸飛びです。スプールにラインが満載に近い状態だと、リールを巻く際や振動が加わった際に、ラインがスプールから飛び出してしまうことがあります。これが絡まりの原因となり、いわゆるバックラッシュ状態になります。
次に、スプール上部での巻き癖です。スプール容量いっぱいに巻くと、上部に巻かれたラインは使用頻度が低くなります。長期間巻かれたままのラインは強い癖がつき、いざ使おうとしたときにトラブルの元となります。
ピンキー03を使ってます。一巻200mを丸々リールに巻いてしまうと下のほうの巻きグセか酷くなるので100mづつ使ってます。残り30m位になったら新しい100mに巻きかえる感じです。
上記のように、200mを一度に巻くのではなく、100mずつ使うという工夫をしているアングラーもいます。これは巻き癖を防ぐための合理的な方法と言えるでしょう。
さらに、リールの自重増加も見過ごせません。ラインを多く巻くほどリールは重くなり、繊細なアジングにおいて手感度が低下します。わずか数グラムの違いでも、長時間の釣行では疲労度に影響します。
また、**エアノット(空中での結び目)**のリスクも高まります。エステルラインは特にエアノットが発生しやすく、糸飛びしたラインが空中で勝手に結び目を作ってしまうことがあります。これを知らずに巻き取ると、結び目がガイドに引っかかって高切れの原因となります。
したがって、適正な糸巻き量を守ることは、単に「足りる量を確保する」だけでなく、「トラブルを予防する」という意味でも重要です。150mを上限の目安とし、それ以上巻かないようにすることで、快適なアジングが実現します。
アジングで使うラインの種類と糸巻き量の関係
- エステルラインの糸巻き量とその特性
- PEラインの糸巻き量と下巻きの必要性
- フロロカーボンラインを使う場合の糸巻き量
- リーダーの長さと糸巻き量への影響
- リールの番手による糸巻き量の違い
- ギア比と糸巻き量の関係性
- まとめ:アジング糸巻き量の最適解
エステルラインの糸巻き量は65m〜150mが実用的
エステルラインはアジングのジグ単で最も人気のあるラインであり、その特性に合わせた糸巻き量の設定が重要です。一般的には65m〜150mの範囲が実用的とされています。
エステルラインの最大の特徴は、高感度と低伸度です。ナイロンやフロロカーボンに比べて伸びが少ないため、アジの小さなアタリを明確に感じ取ることができます。また、比重が軽いため水馴染みが良く、軽量ジグヘッドの操作性にも優れています。
しかし、エステルラインには強度が低いという弱点があります。0.3号のエステルラインの直線強度は1.5〜1.8lbs程度で、同じ太さのPEラインの約4分の1です。そのため、高切れのリスクが高く、頻繁にラインをカットして結び直す必要があります。
糸巻き量を少なめに巻くことでライントラブルは激減します。「ルミナシャイン」の糸巻量は200m。ジグ単ゲームでメインに使用されることの多い、シャロースプールの小型スピニングリールに巻く場合は、下巻き無しのリーリング100回転前後、長さで言うと65m程を巻いて使用しています。
プロアングラーの中には、エステルラインを65m程度に抑えて使用する方もいます。これはライントラブルの軽減を最優先にした選択です。エステルラインは糸が硬くゴワゴワしているため、多く巻きすぎると糸飛びやバックラッシュが起こりやすくなります。
📌 エステルライン使用時の推奨糸巻き量
| 使用目的 | 推奨糸巻き量 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ライトラ軽減重視 | 65m〜80m | トラブル最小限 | 高切れ後の予備が少ない |
| バランス型 | 100m〜120m | 実用的な量 | やや糸飛びリスクあり |
| 予備重視 | 130m〜150m | 長時間釣行も安心 | トラブル率やや上昇 |
エステルラインを使用する場合、リーダーの結束が必須です。エステルライン単体では根ズレに弱く、リーダーなしでは根掛かり時にメインラインから切れてしまいます。リーダーはフロロカーボンの0.8号〜1号を70cm〜1ヒロ(約1.5m)結束するのが一般的です。
また、エステルラインは釣行ごとに先端をカットする習慣をつけることが推奨されます。擦れやすい先端部分を1〜2mカットし、新しい部分でリーダーを結び直すことで、強度を維持できます。このカットを繰り返すと数釣行でラインが短くなるため、初期の糸巻き量は余裕を持たせておく方が賢明です。
エステルラインは使いこなせば非常に快適ですが、初心者には若干ハードルが高いラインとも言えます。ライントラブルが心配な方は、まず100m程度から始めて、慣れてきたら調整するという方法もあります。
PEラインの糸巻き量は150m〜200mが標準的
PEラインは高強度と高感度を両立したラインで、アジングでも人気があります。エステルラインに比べて強度が高いため、糸巻き量は150m〜200mが標準的です。
PEラインの最大の利点は、圧倒的な直線強度です。0.3号のPEラインで6lbs程度の強度があり、同じ太さのエステルラインの約4倍です。そのため、高切れのリスクが低く、安心してキャストできます。
また、PEラインは伸びが少ないため、エステルライン同様に高感度です。遠投性能にも優れており、キャロライナリグやフロートリグなど、遠くのポイントを狙う釣りにも適しています。
PEを巻くときは150mの物を巻いてます、なぜなら50m飛ばしても100m残るからです、100mの物で50m飛ばすと50mしか残らないでしょ?もしも高切れで20m、30mを何度か失うとどうします?
PEラインの糸巻き量を150m以上にする理由は、主に遠投への対応と予備の確保です。フロートリグやキャロライナリグを使う場合、50m以上飛ばすことも珍しくありません。その場合、100mでは予備が足りなくなるリスクがあります。
ただし、PEラインにもデメリットがあります。最大の弱点は根ズレへの弱さです。PEラインは摩擦に対して非常に弱く、岩や貝殻などに触れるとすぐに毛羽立ったり切れたりします。そのため、リーダーの結束が必須となります。
リーダーはフロロカーボンの0.8号〜1.5号を1ヒロ(約1.5m)程度結束するのが一般的です。リーダーが長いほど根ズレへの対応力は上がりますが、結束部がガイドに引っかかるリスクも高まるため、バランスが重要です。
🎣 PEライン0.3号使用時の推奨設定
| 項目 | 推奨値 | 備考 |
|---|---|---|
| PE本線 | 150m〜200m | 遠投対応 |
| リーダー太さ | 0.8号〜1.5号 | フロロカーボン |
| リーダー長さ | 1〜1.5ヒロ | 約1.5〜2.3m |
| 結束方法 | FGノットまたは電車結び | 強度重視ならFG |
PEラインのもう一つの特徴は、比重が軽いことです。水に浮くため、強風時には糸がたわんでライン操作が難しくなることがあります。この点はエステルラインの方が優位です。
また、PEラインはトラブル時の対処が難しいという側面もあります。一度絡まると解きにくく、最悪の場合はカットして結び直す必要があります。そのため、ライン管理には十分な注意が必要です。
PEラインを選ぶ際は、編み数にも注目しましょう。4本編みよりも8本編みの方が表面が滑らかで、飛距離とトラブル軽減の両面で有利です。価格は高くなりますが、快適性を求めるなら8本編みがおすすめです。
フロロカーボンラインは150m〜200m巻くのが基本
フロロカーボンラインはシンプルで扱いやすいため、アジング初心者に特におすすめです。糸巻き量は150m〜200mが基本となります。
フロロカーボンラインの最大の利点は、リーダーが不要なことです。エステルラインやPEラインと異なり、フロロカーボンは根ズレに強いため、メインライン単体で使用できます。これにより、ライン管理がシンプルになり、夜間の釣行でも結束作業に手間取ることがありません。
また、フロロカーボンは比重が高いため、水馴染みが良く沈みやすい特性があります。ボトム(底)を攻める釣りに適しており、軽量ジグヘッドでもしっかりと沈んでくれます。さらに透明度が高いため、魚に警戒されにくいというメリットもあります。
フロロでも150~200m巻きます、切りながら使っても2年ほど問題なく使えています。
上記のように、フロロカーボンは耐久性が高く、長期間使用できることも魅力です。先端を定期的にカットしながら使えば、2年程度は問題なく使えるという報告もあります。
アジングで使用するフロロカーボンの太さは、**0.6号(2.5lbs)〜0.8号(3lbs)**が一般的です。0.6号は繊細なアタリを取りやすく、0.8号は強度とのバランスが良いとされています。
💡 フロロカーボンライン使用時のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ✅ リーダー不要でシンプル | ❌ 感度はエステル・PEに劣る |
| ✅ 根ズレに強い | ❌ 飛距離が出にくい |
| ✅ 水馴染みが良い | ❌ 巻き癖がつきやすい |
| ✅ 透明で警戒されにくい | ❌ やや伸びがある |
| ✅ 長期間使用可能 | ❌ 価格がやや高い |
フロロカーボンラインのデメリットとして、感度と飛距離がエステル・PEに劣る点が挙げられます。伸びがある分、アタリの伝達がややぼやけます。また、比重が高く空気抵抗も大きいため、軽量リグでは飛距離が出にくいです。
それでも、トータルの扱いやすさを考えると、フロロカーボンは初心者に最適な選択肢と言えるでしょう。特に、夜間の釣行がメインで結束作業を避けたい方や、ライントラブルに不安がある方には強くおすすめします。
フロロカーボンを選ぶ際は、ライトゲーム専用やアジング専用と銘打たれた製品を選ぶと良いでしょう。これらは柔らかく設計されており、巻き癖がつきにくく、細いラインでも扱いやすい特性を持っています。
糸巻き量については、150mを基本とし、頻繁に先端をカットする方は200m巻いておくと安心です。フロロカーボンは比較的安価なので、多めに巻いてもコスト負担は少ないでしょう。
リーダーの長さが糸巻き量に与える影響
エステルラインやPEラインを使用する場合、リーダーの長さも糸巻き量に影響します。リーダーが長いほど、メインラインの消費量が増えるためです。
リーダーの標準的な長さは**1ヒロ(約1.5m)**とされています。これは根ズレへの対応とライン操作性のバランスを考慮した長さです。しかし、釣り場の状況や個人の好みによって、70cm〜2ヒロ(約3m)まで幅があります。
リーダーを長くするメリットは、根ズレへの耐性向上です。岩礁帯や障害物の多いポイントでは、リーダーが長い方が安心です。また、リーダー部分が擦れて劣化した際も、カットして結び直すことで対応できます。
一方、リーダーを長くするデメリットは、結束部がガイドに引っかかるリスクです。特にキャスト時、結束部がトップガイドを通過する際に引っかかり、高切れの原因となることがあります。また、夜間の結束作業も長いほど手間がかかります。
PEライン 0.3号(6lb)にフロロカーボン1号(4lb)を1ヒロ程度で十分です。
上記のように、汎用的なセッティングとしては1ヒロが推奨されます。これにより、根ズレへの対応とライン操作性の両立が可能です。
リーダーの消費量を考慮すると、糸巻き量への影響は以下のようになります。
📊 リーダー長と年間消費量の目安
| リーダー長 | 1回の結束消費量 | 年間結び直し回数(推定) | 年間消費量 |
|---|---|---|---|
| 70cm | 0.7m | 20〜30回 | 14〜21m |
| 1ヒロ(1.5m) | 1.5m | 20〜30回 | 30〜45m |
| 2ヒロ(3m) | 3m | 20〜30回 | 60〜90m |
たとえば、2ヒロの長いリーダーを使用し、年間30回結び直すと、リーダーだけで90m消費することになります。メインラインを100mしか巻いていない場合、ほとんどがリーダーで消えてしまう計算です。
したがって、長いリーダーを好む方は、メインラインも多めに巻いておく必要があります。逆に、ライントラブルを最小限にしたい方は、リーダーを短めにしてメインラインの消費を抑えるという選択肢もあります。
また、リーダーの結束方法も重要です。強度の高いFGノットは結び目が小さくガイド抜けが良い反面、結束に時間がかかります。簡易的な電車結びは素早く結べますが、強度がやや劣ります。釣り場の状況や自分のスキルに応じて使い分けましょう。
リーダーの太さについては、メインラインより太めを選ぶのが基本です。PEライン0.3号(6lbs)に対してはフロロカーボン0.8〜1.5号(3〜6lbs)、エステルライン0.3号(1.5lbs)に対してはフロロカーボン0.6〜0.8号(2.5〜3lbs)が一般的な組み合わせです。
リールの番手で変わる適正糸巻き量
アジングで使用するリールの番手によって、適正糸巻き量が変わります。一般的には1000番〜2000番が推奨されますが、それぞれに最適な糸巻き量があります。
1000番クラスは、最も軽量でコンパクトなサイズです。自重は170g前後で、ジグ単メインのアジングに適しています。糸巻き量の目安は、PE0.3号で150m〜200m程度です。ただし、シャロースプール仕様(1000S)の場合は、PE0.3号で100m〜120m程度が適正となります。
アジングには細く軽いロッドと極細タイプのPEラインやエステルラインを用いるため、小型のスピニングリールが適しています。具体的なリールの番手としては、1000~2000番台が最もよく使われます。
2000番クラスは、汎用性の高いサイズです。自重は190g〜210g程度で、ジグ単からキャロライナリグまで幅広く対応できます。糸巻き量の目安は、PE0.3号で200m〜240m程度です。シャロースプール仕様(2000S)では、PE0.3号で150m〜180m程度が適正です。
🎣 リール番手別の推奨糸巻き量
| リール番手 | 自重(目安) | PE0.3号糸巻き量 | 適した釣り方 |
|---|---|---|---|
| 1000番 | 170g前後 | 150〜200m | ジグ単メイン |
| 1000S番 | 165g前後 | 100〜120m | 軽量ジグ単特化 |
| 2000番 | 190〜210g | 200〜240m | オールラウンド |
| 2000S番 | 185〜200g | 150〜180m | ジグ単・軽量キャロ |
| 2500番 | 220〜240g | 250m以上 | 遠投特化 |
番手選びで重要なのは、ロッドとのバランスです。軽量なアジングロッド(5〜6ft、50〜70g)には1000番が、やや長めのロッド(7〜8ft、80〜100g)には2000番がマッチします。リールが重すぎると先重りして操作性が悪くなり、軽すぎてもバランスが崩れます。
また、スプール径も糸巻き量に影響します。一般的に、番手が大きくなるほどスプール径も大きくなり、ラインの放出性が向上します。その結果、同じラインを使っても飛距離が伸びる傾向があります。
ただし、アジングは繊細な釣りであるため、軽さを優先する傾向が強いです。そのため、多くのアジンガーは1000S〜2000S番のシャロースプールを選択します。これにより、必要十分な糸巻き量を確保しつつ、リール自重を抑えることができます。
糸巻き量を決める際は、リールのスペック表を必ず確認しましょう。同じ番手でも、メーカーや機種によって糸巻き量が異なる場合があります。たとえば、ダイワとシマノでは番手の基準が若干異なるため、注意が必要です。
番手が大きいほど巻き取り量も増えるため、ハイギアモデルと組み合わせると、素早い回収が可能になります。これは遠投して広範囲を探る釣りには有利ですが、ジグ単のスローな釣りには不向きな場合もあります。用途に応じて選択しましょう。
ギア比と糸巻き量の意外な関係性
リールのギア比と糸巻き量には意外な関係性があります。ギア比とは、ハンドル1回転でローターが何回転するかを示す数値で、リールの巻き取り速度を決定する重要な要素です。
アジングで使用されるリールのギア比は、大きく分けて**ローギア(4.8〜5.2)とハイギア(6.0以上)**に分類されます。一般的には、ジグ単メインならローギア、遠投メインならハイギアが推奨されます。
ギア比が糸巻き量に与える影響は、主にラインの消費速度です。ハイギアのリールは巻き取りが速いため、手返しが良く効率的に釣りができます。その反面、糸巻き量が少ないと、すぐにスプール下部まで到達してしまい、ラインの巻き癖が強くなるリスクがあります。
ハイギアのリールを使って、あえて速い動きで誘うと、その釣り方に食ってくるアジの方がデカいから…という理由らしい。つまり遊泳力のある大きな個体は、ハイギアで狙って釣る…と言うことか。
ハイギアを使う上級者の中には、あえて速い動きでアジを誘い、大型個体を狙うテクニックを使う方もいます。この場合、ハンドル1回転あたりの巻き取り量が80cm以上になることもあり、150m巻いていても比較的早くラインが消費されます。
⚙️ ギア比別の特徴と推奨糸巻き量
| ギアタイプ | ギア比 | 巻き取り量/回転 | 推奨糸巻き量 | 適した釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| ローギア | 4.8〜5.2 | 60〜70cm | 100〜150m | スローなジグ単 |
| ノーマルギア | 5.3〜5.9 | 70〜80cm | 120〜150m | オールラウンド |
| ハイギア | 6.0〜6.5 | 80〜90cm | 150〜200m | 遠投・手返し重視 |
| エクストラハイギア | 6.6以上 | 90cm以上 | 150〜200m | 速巻き・大型狙い |
ローギアのメリットは、巻きが軽く繊細なコントロールができることです。ゆっくりとワームを動かしたい場合、ローギアの方が操作しやすく、アジのバイトも拾いやすいとされています。また、巻き取り量が少ない分、スプール径の減少も緩やかで、ライン性能が長く維持されます。
ハイギアのメリットは、手返しの良さと風対策です。仕掛けを素早く回収できるため、数多くキャストでき、広範囲を効率的に探れます。また、風が強い日は糸ふけが出やすいですが、ハイギアであれば素早く巻き取って対処できます。
ただし、ギア比はあくまで個人の好みによる部分が大きいです。初心者の方は、まずノーマルギア(ギア比5.0〜5.5程度)から始めて、自分の釣りスタイルに合わせて調整していくと良いでしょう。
糸巻き量との関係で言えば、ハイギアを使う場合はやや多めに巻いておくことをおすすめします。150m以上あれば、手返し良く釣りをしてもラインが極端に減ることはありません。逆に、ローギアでゆっくり釣る場合は、120m程度でも十分に対応可能です。
まとめ:アジング糸巻き量の最適解は用途で決まる
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングの適正糸巻き量は100m〜150mが基本であり、これは飛距離とトラブル時の予備を考慮した実用的な範囲である
- 飛距離は20m前後が平均なので理論上50mでも足りるが、高切れや根掛かりなどのトラブルに備えて余裕を持たせることが重要である
- シャロースプールのリールを選ぶことで、ライントラブルの軽減、キャスト性能の向上、リールの軽量化という3つのメリットが得られる
- 下巻きを活用することで、ラインを経済的に使いつつ適切なスプール径を維持できる
- 糸巻き量が多すぎるとスプールからの糸飛びや巻き癖、エアノットなどのトラブルが増加する
- エステルラインの糸巻き量は65m〜150mが実用的で、ライントラブル軽減を重視するなら少なめ、予備重視なら多めにする
- PEラインは150m〜200mが標準的で、遠投への対応と強度の高さから多めに巻くことが推奨される
- フロロカーボンラインは150m〜200mが基本で、リーダー不要のシンプルさから初心者に特におすすめである
- リーダーの長さは通常1ヒロ(約1.5m)が標準だが、長くするほどメインラインの消費量が増える
- リールの番手によって適正糸巻き量が異なり、1000番で100〜150m、2000番で150〜200mが目安となる
- ギア比はハイギアほど手返しが良い反面、ラインの消費も早いため、やや多めに巻いておくと安心である
- 最適な糸巻き量は釣り方や使用ラインによって変わるため、自分のスタイルに合わせて調整することが重要である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- Yahoo!知恵袋 – メバリング・アジングのメインラインって何Mあれば足りますか?
- リグデザイン – メバリング「糸巻き量」の適正は何m?
- TSURI HACK – アジングタックルは3パターンで考えるべし!
- ルアーニュース – アジングで「エステルライン」を使用する時に注意すべき2つのポイント
- Marvelous Act – 2024年新作のエステルラインを巻いてみた
- 孤独のフィッシング – 21カルディアLT2500S‐XHのインプレ
- TSURINEWS – 今さら聞けないアジングのキホン:リールの選び方と使用の注意点
- おだやかなる釣りの時間 – 22サハラC2000Sをエリアとアジングでレビュー
- FISHING JAPAN – アジングリールのおすすめ16選!プロ直伝の選び方
- ほやけんちゃアジング – 18タトゥーラLT2000S-XH
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。