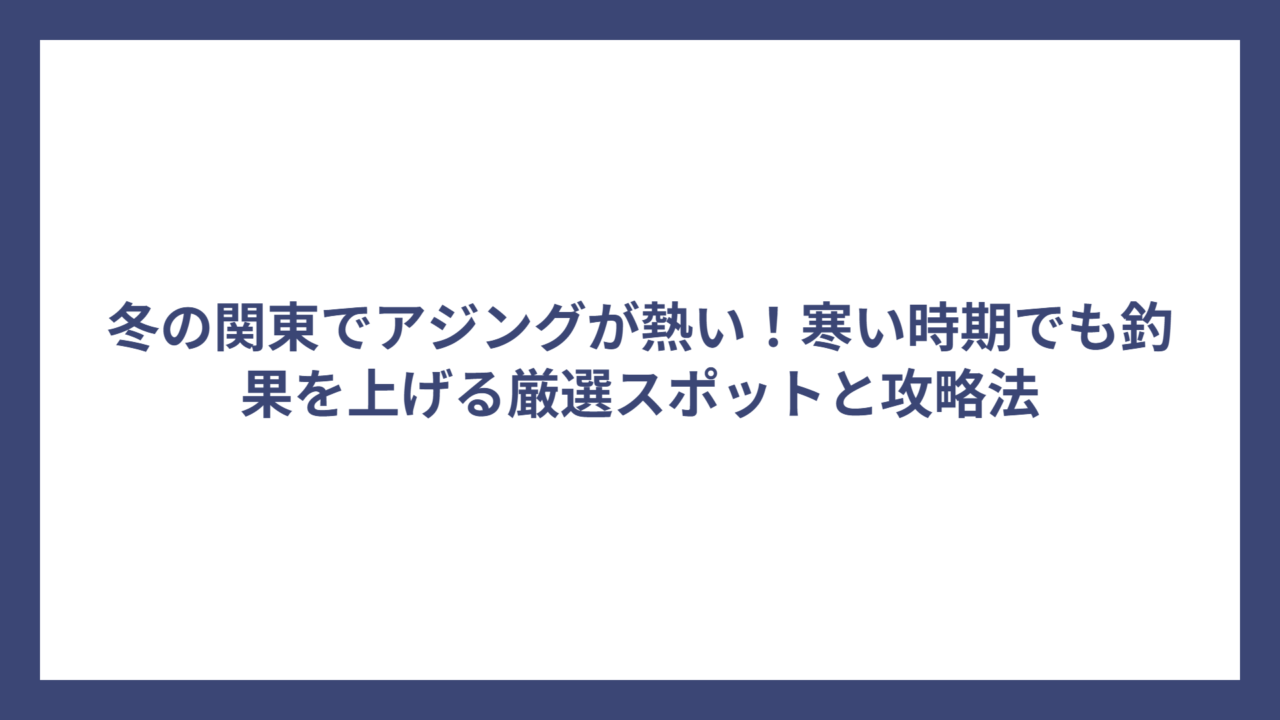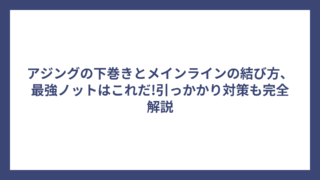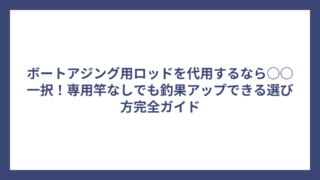冬になるとアジング(アジのルアー釣り)は難しくなると思われがちですが、関東エリアには真冬でも好釣果が期待できるポイントが数多く存在します。一般的に海水温が15℃を下回るとアジの活性が低下すると言われていますが、黒潮の影響を受ける外房エリアや湾内の温排水周辺など、冬でもコンスタントに釣果が上がる場所があるのです。
本記事では、インターネット上に散らばる釣果情報や釣り場レポートを徹底的に収集・分析し、冬の関東でアジングを楽しむための実践的な情報をまとめました。真冬の厳しい条件下でも釣果を上げるためのポイント選びから、効果的なタックルセッティング、時間帯の選び方まで、幅広く解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 冬でも釣れる関東のアジングポイントが分かる |
| ✓ 低水温期のアジの習性と攻略法が理解できる |
| ✓ 効果的なジグヘッドとワームの選び方が学べる |
| ✓ 時間帯やポイント選びのコツが身につく |
冬の関東アジングで押さえるべき基本知識とポイント選定術
- 冬のアジングは水温15℃がボーダーライン
- 関東の優良ポイントは千葉外房と横浜エリアに集中
- 低活性時のアジはボトム付近に群れる傾向
- 常夜灯周りとストラクチャー際が有望
- 時間帯は夕マズメから日没後が最も期待できる
冬のアジングは水温15℃を基準に釣り場を選ぶこと
冬季のアジング成功の鍵を握るのが海水温です。一般的にアジの適水温は15℃以上とされており、13℃を下回ると極端に活性が落ちるとされています。このため、冬のアジングでは水温が比較的高く保たれるエリアを選ぶことが重要になります。
関東エリアを大きく分けると、東京湾の湾奥部と外洋に面したエリアでは水温に大きな差が生じます。東京湾の湾奥では2月に最低水温を記録し、12℃以下になることも珍しくありません。一方で、千葉県の外房エリアや相模湾沿岸は黒潮の影響を受けるため、真冬でも15℃前後の水温が維持されやすい傾向にあります。
ある釣り情報サイトでは以下のように記載されています。
横浜は湾奥のため、冬(2月など)には水温が12℃以下になる時期がある。アジの適水温は15℃以上であるとか、13℃を下回るとかなり釣れにくいとか言われているので、その時期は横浜などでのアジングは難しいことになる。
この情報から分かるように、冬季は釣行する地域によって釣果に大きな差が出ることが予想されます。特に1月後半から2月にかけての厳寒期は、湾奥部よりも外洋に面したエリアの方が釣果が安定する傾向があると言えるでしょう。
水温の確認方法としては、釣具店の釣果情報や海上保安庁の海洋速報などを参考にするのが有効です。多くの海釣り施設では日々の水温をホームページで公開しているので、釣行前にチェックすることをおすすめします。
また、水温が低くても局所的に温排水が流れ込む場所や、日当たりの良い湾内など、周囲より水温が高いスポットが存在します。こうしたマイクロスポットを見つけることも、冬のアジング攻略の重要なテクニックと言えるでしょう。
千葉外房エリアは冬でもアジ・カマスが狙える貴重なフィールド
関東で真冬にアジングを楽しむなら、千葉県の外房エリアは外せません。特に勝浦、小湊、鴨川といった漁港は、冬季でも安定した釣果が期待できる優良ポイントとして知られています。
外房エリアが冬でも釣れる理由は、先述した通り黒潮の影響で水温が比較的高く保たれるためです。さらに、これらの漁港には豊富なベイトフィッシュが集まりやすく、それを追ってアジやカマスが接岸する好条件が揃っています。
ある釣行レポートでは勝浦地区について以下のように紹介されています。
今日はアジングから比較的混雑が少ないポイントでスタート。周りには投げサビキの釣り人が多く、話を聞けば皆アジ狙いという事だ。足元を見れば��イトの姿も多く見られた。
真冬の千葉外房でアジ&カマスが連発! | 釣りビジョン マガジン
このレポートは真冬の釣行ですが、アジとカマスが連発したとのこと。特に注目すべきは「沖から入ってきた群れが、ある一定の場所でグルグルと回遊している」という状況です。冬のアジは広範囲に散らばるのではなく、限定的なエリアに群れる傾向があるため、釣れるポイントを見極めることが釣果の鍵となります。
📊 外房エリア主要ポイントの特徴
| ポイント名 | 特徴 | アクセス | 混雑度 |
|---|---|---|---|
| 勝浦港 | 魚影が濃く冬でも好釣果。複数のポイントあり | 車推奨 | 非常に高い |
| 小湊港 | 真冬でもアジ・カマスが爆釣する貴重なポイント | 車必須(有料駐車場600円) | 高い |
| 鴨川港 | 規模が大きく初心者でも釣りやすい | 比較的アクセス良好 | 中程度 |
| 松部港 | 勝浦湾対岸に位置。人気の釣り場 | 車推奨 | 中~高 |
外房エリアの注意点として、人気が高いため土日祝日は非常に混雑することが挙げられます。ある情報によると「土日祝前日は、夜中の12時に行っても場所取りの荷物でいっぱい」という状況もあるようです。このため、朝夕のマズメが終わる時間帯を狙うか、平日の釣行がおすすめされています。
また、小湊港については「ギャング鈎・ルアー・投げ釣り・コマセ禁止」という制限があるものの、アジングについては黙認されているグレーな状態とのこと。マナーを守り、漁業関係者の邪魔にならないよう配慮することが、釣り場を守ることにつながります。
横浜エリアは時期と場所を選べば都心から近くて便利
東京都心からのアクセスが良く、手軽にアジングを楽しめるのが横浜エリアです。ふれーゆ裏、根岸港、大黒ふ頭西緑地(ベイ下)、東扇島西公園などが代表的なポイントとして知られています。
横浜エリアの特徴は、都心に近い利便性と、ポイントごとに異なる特性があることです。ただし、湾奥に位置するため冬季は水温が下がりやすく、厳寒期(1月後半~2月)は釣果が不安定になる傾向があります。
ある釣りブログでは横浜エリアのポイントについて詳しく解説されています。
根岸港は近くのローソンでトイレが借りられたり買い物ができたりと便利な釣り場。ここはGWあたりから1ヶ月くらいの産卵の時期にアジが釣れ続くためその時期には多くのアジンガーが通っている。
この情報から、根岸港は春から初夏にかけてが特に好シーズンであることが分かります。一方で、冬季については「5~6月あたり以外の時期にはあまり行ったことがないため釣れるのかどうかよくわからないが、秋や冬などもアングラーズを見る限り釣れてはいそう」とのこと。必ずしも冬がベストシーズンとは言えないかもしれません。
🎣 横浜エリア人気ポイントの比較
| ポイント | 冬の期待度 | 施設充実度 | おすすめ時期 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 根岸港 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 5~6月が最盛期 | 夕マズメから日没後が狙い目 |
| 大黒ふ頭西緑地 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 秋~冬 | 22時~5時は道路封鎖 |
| ふれーゆ裏 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 春~秋 | 根が多く根掛かりに注意 |
| 東扇島西公園 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 通年 | 釣具店出張所あり |
大黒ふ頭西緑地(ベイ下)は、秋から冬にかけて特にアジンガーが集まる人気スポットです。横浜ベイブリッジの真下に位置し、「ベイブリッジ真下より少し左にある防波堤周辺」や「緑地の左端、右端」が人気ポイントとされています。注意点として、22時から5時の間は道路が封鎖されるため、22時までに帰るか朝5時まで釣り続けるかの選択を迫られます。
横浜エリアで冬にアジングをする場合、厳寒期を避けて12月や3月など、比較的水温が高い時期を選ぶのが賢明でしょう。また、釣果情報をこまめにチェックし、実際に釣れているポイントを選ぶことが重要です。
低活性時のアジはボトム付近を重点的に探ること
冬の低水温期におけるアジの行動パターンを理解することは、釣果を上げるための重要な要素です。水温が下がると、アジは活性が落ち、動きが鈍くなります。このとき、アジはエネルギー消費を抑えるためボトム(海底)付近に群れる傾向が強くなります。
ある釣りメディアでは冬のアジの居場所について次のように解説されています。
冬のアジの着き場所、上述のように「キーレンジ」ともいえる水深はボトム周辺だ。ただ夜の常夜灯下では表層の巻きで簡単に出てしまうこともあるが、適水温の下限に近付くほど、やはり深いところになる。
真冬の低活性アジの居場所の見つけ方3選 | TSURINEWS
この情報から、冬のアジングではボトムを中心に探ることが基本戦略となることが分かります。ただし、常夜灯周辺では例外的に表層でも反応することがあるため、状況に応じて柔軟にレンジ(水深)を変えることが大切です。
ボトム攻略の具体的な方法としては、以下のようなアプローチが効果的と考えられます。まず、やや重めのジグヘッド(1.5g~2g程度)を使用し、しっかりとボトムまで沈めます。着底を感じたら、ゆっくりとリトリーブ(巻き取り)し、時折ストップを入れて「ふわふわ」とワームを漂わせるイメージです。
また、潮の流れがある場所では、ボトムでワームをドリフト(漂流)させる釣り方も有効です。重めのジグヘッドでボトムをキープしながら、潮の流れに乗せて自然にワームを流すことで、活性の低いアジにも口を使わせることができる可能性があります。
特に冬場は「居食い」と呼ばれる、アジがその場でワームを吸い込むような食い方をすることが多くなります。このため、アタリが出てもラインが走らず、違和感程度の微妙な変化しか感じられないことも。繊細なアタリを取るためには、感度の高いエステルラインの使用や、ロッドを持つ手に神経を集中させることが重要になります。
常夜灯周りとストラクチャー際は冬でも魚が集まりやすいホットスポット
冬のアジングでポイントを絞り込む際、最も重要な目印となるのが常夜灯です。夜間、常夜灯の光は海中のプランクトンを集め、それを餌とする小魚が集まり、さらにそれを捕食するアジが寄ってくるという食物連鎖が形成されます。
特に冬場は、こうした限定的なポイントに魚が集中しやすい傾向があります。ある釣り情報サイトでは、冬のアジの居場所を見つけるヒントとして以下のように述べられています。
灯りに群がるアジを狙う。夜の常夜灯周りには餌となるプランクトンなどが集まってきます。特に冬場は数少ないアジを見つける大指針となるので、見逃せないシチュエーションとなります。
常夜灯周りを攻略する際のポイントは、明暗部の境目を重点的に探ることです。アジは明るすぎる場所を避け、やや暗い場所から明るい場所を見上げるように位置取りすることが多いとされています。このため、常夜灯の光が届く範囲の少し外側や、影になっている部分を狙うのが効果的でしょう。
また、ストラクチャー(障害物)も重要な要素です。防波堤の際、テトラポッドの隙間、係留船の周辺など、潮がクッションする場所や身を隠せる場所に魚は集まりやすくなります。
💡 冬のアジが集まりやすいポイントの特徴
- ✅ 常夜灯の明かりが届く範囲(特に明暗部の境目)
- ✅ 防波堤の際や壁沿い
- ✅ テトラポッドなどのストラクチャー周辺
- ✅ 係留船の陰
- ✅ 潮の流れがクッションする場所
- ✅ 水深の変化がある駆け上がり周辺
- ✅ 温排水の流れ込み付近
冬のアジは夏場のように広範囲を回遊することが少なく、条件の良い限定的なスポットに群れる傾向があります。このため、こうしたホットスポットを見つけることができれば、短時間で効率的に釣果を上げることが可能になります。
ポイント選びの際には、浮きゴミや気泡の溜まり方も参考になります。これらはプランクトンが集まる場所の目印となり、その周辺にアジが潜んでいる可能性が高いとされています。釣り場に着いたら、まず水面をよく観察し、こうしたサインを見逃さないようにしましょう。
時間帯は夕マズメから日没後2時間がゴールデンタイム
冬のアジングにおいて、時間帯の選択は釣果を大きく左右する要素です。一般的に魚の活性が高まるのは「マズメ時」と呼ばれる朝夕の薄明かりの時間帯ですが、冬のアジングでは特に夕マズメから日没後の数時間が最も期待できる時間帯とされています。
ある釣行レポートでは根岸港の時間帯について以下のように記載されています。
時間帯としては夕マズメから日が沈んでしばらくが一番釣れるイメージで、深夜から入った場合や朝マズメなどは周りも含めあまり釣れている印象がない。
この情報から、冬場は朝マズメよりも夕マズメの方が実績が高い傾向にあることが分かります。おそらく、日中に太陽光で温められた表層の海水が夕方以降も温度を保ち、アジの活性が一時的に上がるためではないかと推測されます。
⏰ 冬のアジング推奨タイムスケジュール
| 時間帯 | 期待度 | 特徴・攻略法 |
|---|---|---|
| 日の出前~朝マズメ | ★★☆☆☆ | 冬は活性低め。常夜灯周りなら可能性あり |
| 日中 | ★☆☆☆☆ | 厳しい時間帯。水温上昇を待つのも一手 |
| 夕マズメ | ★★★★★ | 最も期待できる時間。早めに場所取りを |
| 日没後1~2時間 | ★★★★★ | ゴールデンタイム継続。常夜灯周りを重点的に |
| 深夜 | ★★☆☆☆ | 時合いが続けば釣れるが、基本的には厳しい |
| 夜明け前 | ★★★☆☆ | 朝マズメに向けて徐々に活性上昇 |
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、ポイントや状況によって異なることもあります。例えば、常夜灯が充実している釣り場では深夜でも釣果が上がることがありますし、潮の動きによっては朝マズメでも好釣果が期待できる場合もあるでしょう。
冬のアジは活性が低いため、回遊してくる時間が非常に限られることがあります。「一日のうちで1時間、日によっては数十分」という短時間しか食い気が立たないこともあるとされています。このため、タイミングを逃さないよう、時合い(魚の食いが立つ時間帯)を捉えることが重要になります。
効率的な釣行のためには、釣果情報をチェックして「何時頃に釣れた」という情報を事前に把握しておくことをおすすめします。また、一度釣れた時間帯は翌日以降も同じような時間に時合いが来る可能性が高いため、記録を取っておくと次回の釣行に活かせるでしょう。
冬の関東アジングで釣果を上げるタックルとテクニック
- ジグヘッドは0.4g~2gを状況に応じて使い分ける
- ワームサイズは1~2インチが基本
- エステルラインで感度を最大限に高める
- ゆっくりとしたリトリーブとステイを組み合わせる
- 風裏の釣り場を選んで快適性を確保する
- 防寒対策を万全にして長時間の釣りに備える
ジグヘッドは軽量から中重量まで複数用意すること
冬のアジングで釣果を左右する最も重要な要素の一つが、ジグヘッドの重さ選びです。状況に応じて適切なウェイトを選択することで、アジのいるレンジ(水深)を効率的に探ることができます。
冬のアジングに関する記事では、ジグヘッドの使い分けについて以下のように解説されています。
例えば、夏以降、1gに2インチのストレートワームでやり通して結果が出ていた釣りを、ライズがあるのにアタリが少ないタイミングでは、0.4gと1インチクラスの小さなワームで近距離の極表層をスローに漂わせるのを試してみたり、潮が動くタイミングでは1.5gや2gのやや重たいウエイトで沖に生じた潮目の流心やボトムを探ってみたりするなど、アプローチにメリハリを付けてやることで、釣れるペースやサイズが変わる場面に遭遇しやすくなるでしょう。
この情報から、状況に応じて0.4g~2gまでのジグヘッドを使い分けることの重要性が分かります。それぞれのウェイトが活きる状況を整理すると以下のようになります。
🎯 ジグヘッドウェイト別の使用状況
| ウェイト | 適した状況 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 0.4~0.6g | 表層の活性高いアジ、常夜灯周り | スローフォール、ナチュラルアクション | 飛距離が出ない、風に弱い |
| 0.8~1g | 最も汎用性が高い基本ウェイト | バランスが良く使いやすい | 深場や潮が速い時は不足 |
| 1.5~2g | ボトム攻略、潮が速い時、遠投必要時 | 素早く沈む、飛距離が出る | アクションが不自然になりやすい |
| 2.5g以上 | 深場、強風時、遠投が必須の状況 | 最も飛距離が出る | アジには重すぎる場合も |
実際の釣行では、まず基本となる0.8~1gのジグヘッドから始め、反応を見ながら調整するのが効率的でしょう。表層でライズ(水面で魚が捕食する様子)が見られるのにアタリがない場合は、より軽いジグヘッドに変更してスローに誘うのが効果的です。
逆に、ボトム付近にアジが着いていると予想される場合や、風や潮流が強い状況では、1.5g以上の重めのジグヘッドを選択することで、しっかりとボトムまで沈めることができます。ただし、重すぎるジグヘッドは沈下スピードが速すぎて不自然なアクションになる可能性もあるため、「最低限必要な重さ」を見極めることが大切です。
冬の勝浦でのアジング実釣レポートでは、ジグヘッドの重さによってアジとカマスの釣れ分けができたというエピソードが紹介されています。重いジグヘッドの速い沈下がリアクションバイトを誘いカマスが連発したのに対し、軽いジグヘッドでスローに誘うとアジのアタリが出始めたとのこと。このように、ジグヘッドの選択は魚種の選択にもつながる重要な要素なのです。
冬のアジングでは最低でも3種類程度のウェイトを用意しておくことをおすすめします。具体的には、0.4g、1g、1.5~2gを基本セットとして、状況に応じて使い分けられるようにしておくと良いでしょう。
ワームは1~2インチのコンパクトサイズを基本に選ぶこと
ジグヘッドの重さとともに重要なのが、ワームのサイズとカラー選択です。冬の低活性なアジは、夏場に比べて捕食活動が控えめになるため、小さめのワームが効果的とされています。
一般的に、冬のアジングでは1~2インチ程度のコンパクトなワームが基本となります。アジの口のサイズは体長に比例するため、豆アジと呼ばれる小型の個体が多い場合は1インチクラス、20cm以上の良型が期待できる場合は2インチ前後のワームが適していると考えられます。
ワームの形状については、ストレートタイプとピンテールタイプが主流です。ストレートタイプはアクションが控えめで自然な波動を出し、ピンテールタイプは微波動でアピールするという特徴があります。冬の低活性時には、より自然で控えめなアクションのストレートタイプが有効な場面が多いかもしれません。
🐟 冬のアジング推奨ワームサイズと特徴
- 1インチクラス
- 対象:豆アジ~15cm程度の小型
- 特徴:吸い込みやすく、アタリを確実にフッキングに持ち込める
- 適した状況:活性が極端に低い時、常夜灯周りの表層狙い
- 1.5~2インチクラス
- 対象:18~25cm程度の中型
- 特徴:バランスが良く、最も汎用性が高い
- 適した状況:ほとんどの状況で使用可能な基本サイズ
- 2.5インチ以上
- 対象:25cm以上の良型~尺アジ
- 特徴:アピール力が強く、大型を選んで釣れる
- 適した状況:良型実績のあるポイント、ベイトが大きい時
カラー選択については、基本的にはクリア系やナチュラル系のカラーが無難とされています。特に常夜灯周りでは、クリア系やホワイト系が実績が高いようです。一方で、濁りがある状況や暗い時間帯では、チャート系やグロー系などの視認性の高いカラーが効果を発揮することもあります。
ある釣り具メーカーの情報では、外房エリアのアジに効くワームとして特定の製品が紹介されています。ただし、ワームの効果はその日の状況や個体差によって大きく変わるため、複数のカラーとサイズを用意して、現場で試しながら最適解を見つけることが重要でしょう。
また、冬場は根掛かりのリスクも考慮する必要があります。ボトム付近を攻める際は、ワームやジグヘッドのロストは避けられません。このため、予備のワームとジグヘッドは多めに用意しておくことをおすすめします。特に釣れるワームが分かった場合、同じものが複数あると安心して釣りを続けられます。
エステルラインで感度を最大化し微妙なアタリも逃さない
冬のアジングでは、低活性なアジの微妙なアタリを確実に捉えることが釣果を左右します。そのため、ラインの選択は非常に重要な要素となります。アジングで主に使用されるラインには、ナイロン、フロロカーボン、PE、エステルがありますが、冬のジグヘッド単体(ジグ単)の釣りでは、エステルラインが最も適していると言えるでしょう。
エステルラインの最大の特徴は、低伸度(伸びにくい)であることです。伸びが少ないため、ジグヘッドの動きがダイレクトに手元に伝わり、アジの小さなアタリも明確に感じ取ることができます。
プロアングラーの記事では、エステルラインについて以下のように解説されています。
「鯵の糸ナイトブルー」は細糸から太い号数までラインナップされたアジング特化のエステルラインです。エステルラインの特長である低伸度から来る操作性やフッキングレスポンスの良さを活かしながら強度的にも非常に安定した糸質を実現しています。
エステルラインの号数選択については、ターゲットのサイズと使用するジグヘッドの重さに応じて選ぶのが基本です。一般的なアジングでは0.2~0.5号が使用されますが、冬のアジングに適した号数を状況別に整理すると以下のようになります。
📏 エステルライン号数選択の目安
| 号数 | 適した状況 | メリット | 使用ジグヘッド |
|---|---|---|---|
| 0.2号 | 豆アジ狙い、超軽量ジグヘッド使用時 | 最高の飛距離と感度 | 0.2~0.6g |
| 0.3~0.4号 | 一般的なアジング、18~25cmの中型狙い | バランスが良く扱いやすい | 0.4~1.5g |
| 0.5号 | 良型~尺アジ狙い、根掛かりリスクが高い場所 | 強度に余裕があり安心 | 1~3g |
エステルラインを使用する際の注意点として、PEラインやナイロンラインと比べて結び目が弱いことが挙げられます。このため、適切なノット(結び方)を習得し、こまめにラインをチェックして傷んだ部分はカットすることが重要です。
また、エステルラインは直接ジグヘッドに結ぶと破断のリスクが高いため、ショックリーダー(先糸)としてフロロカーボンラインを結束するのが一般的です。リーダーの長さは40~60cm程度が標準とされ、太さは本線よりやや太めを選ぶのが基本です。例えば、本線が0.35号なら、リーダーは4lb(約1号)程度が適切でしょう。
冬の夜釣りでは、視認性も重要な要素となります。エステルラインの中には、紫外線で発光するタイプや視認性の高いカラーリングが施されたものもあります。こうしたラインを使用することで、暗闇でもラインの動きを目で追うことができ、視覚的にもアタリを捉えやすくなります。
リトリーブは超スローが基本でステイも効果的
冬の低活性なアジを攻略するには、リトリーブ(巻き取り)のスピードとアクションの工夫が不可欠です。夏場のように速めの巻きで広範囲を探るのではなく、ゆっくりとしたアプローチでアジに口を使わせる時間を与えることが重要になります。
基本的なリトリーブ方法は、ジグヘッドを着水させた後、しっかりとカウントダウンしてボトムまで沈めるか、狙いたいレンジまで沈めます。その後、ゆっくりとリールを巻き、時折ステイ(動きを止める)やトゥイッチ(竿先を軽く動かす)を入れてワームに変化を与えます。
ある釣りメディアでは、冬のアジの釣り方について以下のように説明されています。
ボトムふわふわで足元を釣る。冬のアジの着き場所、上述のように「キーレンジ」ともいえる水深はボトム周辺だ。ただ夜の常夜灯下では表層の巻きで簡単に出てしまうこともあるが、適水温の下限に近付くほど、やはり深いところになる。
真冬の低活性アジの居場所の見つけ方3選 | TSURINEWS
「ふわふわ」というキーワードから、ワームをゆっくりと漂わせるイメージのアクションが効果的であることが分かります。具体的には、ボトムタッチ後、ゆっくりとリールを2~3回転させ、そこでステイを入れて再びゆっくりと巻く、というリズムを繰り返すのが基本パターンとなるでしょう。
🎣 冬のアジング効果的なアクションパターン
- カウントダウン法
- ジグヘッド着水後、レンジまでカウントダウン
- 同じカウントで探ることで水平方向に探れる
- アタリが出たカウント数を記憶しておく
- ボトムドリフト
- ボトムにジグヘッドを着底させる
- ほとんど動かさず、潮の流れに任せる
- ラインの変化やわずかな重みの変化に注目
- スローリトリーブ&ステイ
- 超スローで2~3回転巻く
- 2~3秒ステイ
- 再びスローで巻く
- アタリはステイ直後に出ることが多い
- リフト&フォール
- ロッドをゆっくり持ち上げる(リフト)
- テンションを緩めてフォールさせる
- フォール中のアタリに注意
- ただ巻き
- 一定速度で巻き続ける
- スピードは目視で「ゆっくり」と感じる程度
- レンジキープを意識
アタリの出方も冬は独特です。夏場のようにガツンと食い込むのではなく、「コツッ」とした小さな前アタリや、「モゾッ」とした違和感程度のアタリであることが多くなります。また、「居食い」と呼ばれる、その場で吸い込んで動かない食い方をすることもあり、この場合はラインのたるみやテンションの抜けとして現れます。
こうした微妙なアタリを確実にフッキングに持ち込むには、常にラインにテンションをかけ、わずかな変化も見逃さない集中力が必要です。冬のアジングは忍耐力が試される釣りとも言えるでしょう。
風裏のポイントを選んで快適性と釣果の両立を図ること
冬の釣りで見落としがちだが重要なのが、風の影響です。冬は北西の季節風が強く吹くことが多く、風が強いと釣りにくいだけでなく、体感温度も大きく下がって釣行の快適性が損なわれます。
千葉外房での釣行レポートでは、風対策について以下のように記載されています。
元気な活き餌も仕入れることができたので、いざ釣り場へ!と言いたいところだが風が…風が、強いのじゃ~。私の頭はすでにボッサボサ。とにかく風向きの予報と地図を照らし合わせて、風裏になる場所を探すことから始めたのだが、見つけ出した場所は勝浦地区!どうにか風を交わしてくれている事を祈りつつ向かう事に。
真冬の千葉外房でアジ&カマスが連発! | 釣りビジョン マガジン
このように、プロのアングラーでも風裏のポイント探しから始めるほど、風対策は重要なのです。風裏のポイントを選ぶメリットは以下の通りです。
💨 風裏ポイントを選ぶメリット
- ✅ 軽量ジグヘッドでもキャストしやすい
- ✅ ラインが風に煽られず、アタリが取りやすい
- ✅ 体感温度が上がり、長時間の釣りが可能
- ✅ ラインコントロールがしやすい
- ✅ 風波が立たず、水面の変化が観察しやすい
風裏のポイントを見つける方法としては、事前に天気予報で風向きを確認し、その風を遮る地形の場所を地図上で探すのが基本です。例えば、北西の風が予報されている場合、南東側に開けた湾や、岬の南側などが風裏になります。
また、高い建物や防風林、大きな倉庫などが風を遮る場所も狙い目です。工業地帯の釣り場などでは、こうした人工物が意外と風除けになることがあります。
ただし、風裏だけで釣り場を選ぶと、魚影の薄い場所に当たってしまうリスクもあります。理想的なのは、実績のあるポイントの中から風裏になる場所を選ぶことです。このため、複数のポイント情報を持っておき、当日の風向きに応じて選択できるようにしておくと良いでしょう。
冬は風が強い日が多いため、釣行予定日の風速予報も必ずチェックしましょう。一般的に風速10m以上になると釣りが困難になり、施設によっては閉鎖されることもあります。風速7~8mでもアジングには厳しい条件となるため、できれば風速5m以下の日を選ぶのが理想的です。
防寒対策を徹底し長時間の釣行に耐えられる装備を整えること
冬のアジングを快適に楽しむには、徹底した防寒対策が欠かせません。特に夜釣りでは気温が一段と下がるため、十分な装備なしでは集中力が続かず、結果的に釣果にも影響します。
防寒対策の基本は重ね着(レイヤリング)です。ベースレイヤー(肌着)、ミドルレイヤー(中間着)、アウターレイヤー(外着)の3層構造を基本に、気温に応じて調整します。
🧥 冬のアジング推奨ウェアリング
| レイヤー | アイテム例 | 機能・選び方のポイント |
|---|---|---|
| ベースレイヤー | 吸湿発熱インナー、メリノウール | 汗を吸収し保温。綿素材は避ける |
| ミドルレイヤー | フリース、ダウンベスト | 空気の層を作り保温効果を高める |
| アウターレイヤー | 防水・防風ジャケット | 風と水を遮断。透湿性も重要 |
| ボトムス | 裏起毛パンツ、防風パンツ | 下半身の冷えは体全体に影響 |
| アクセサリー | ネックウォーマー、手袋、ニット帽 | 首、手、頭部からの熱損失を防ぐ |
特に重要なのが、首と手の防寒です。首は太い血管が通っているため、ここが冷えると体全体が冷えてしまいます。ネックウォーマーやフェイスマスクで首周りをしっかりと保護しましょう。
手については、アジングは繊細な操作が必要なため、厚手の手袋では困難です。薄手のフィッシンググローブや指先が出せるタイプの手袋を使用し、休憩時には厚手の手袋をはめるなど、状況に応じて使い分けるのが良いでしょう。
また、ホッカイロなどの使い捨てカイロを活用するのも効果的です。背中や腰に貼るタイプのカイロは、体の中心部を温めるため全身の保温に効果があります。手用のカイロをポケットに入れておけば、手が冷えたときにすぐ温めることができます。
足元の冷え対策も重要です。厚手の靴下を重ね履きする、防寒ブーツを履く、靴用カイロを使用するなど、様々な方法があります。長時間の釣りでは、立ちっぱなしによる足の冷えが辛くなってくるため、できるだけ保温性の高い履物を選びましょう。
さらに、車内で暖を取れる環境を作っておくことも有効です。冬のアジングでは、釣れない時間帯は車内で休憩し、時合いの時間に集中して竿を出すという戦略も考えられます。車内で温かい飲み物を飲めるよう、保温ボトルに熱い飲み物を入れておくのもおすすめです。
防寒対策を怠ると、寒さに耐えられず早めに切り上げることになり、もしかしたら時合いを逃してしまうかもしれません。冬のアジングで釣果を上げるには、魚を釣る技術だけでなく、長時間釣り場に留まれる体力と装備も重要な要素なのです。
まとめ:冬の関東でアジングを成功させるための総合ガイド
最後に記事のポイントをまとめます。
- 冬のアジング成功の鍵は海水温15℃以上が維持されるエリアを選ぶこと
- 千葉外房エリア(勝浦、小湊、鴨川)は真冬でも好釣果が期待できる優良フィールド
- 横浜エリアは都心から近く便利だが、厳寒期は釣果が不安定になる傾向あり
- 冬のアジはボトム付近に群れる傾向が強く、重点的に探ることが重要
- 常夜灯周りとストラクチャー際は魚が集まりやすいホットスポット
- 時間帯は夕マズメから日没後2時間がゴールデンタイムとなる
- ジグヘッドは0.4g~2gを状況に応じて使い分ける必要がある
- ワームは1~2インチのコンパクトサイズが低活性時に効果的
- エステルラインを使用することで微妙なアタリも確実に捉えられる
- リトリーブは超スローが基本でステイやドリフトも効果的
- 風裏のポイントを選ぶことで快適性と釣果の両立が図れる
- 徹底した防寒対策が長時間の釣行を可能にし結果的に釣果向上につながる
- 釣果情報をこまめにチェックし、実際に釣れているポイントを選ぶことが効率的
- 冬のアジは活性が低いため時合いが短く、タイミングを逃さないことが重要
- マナーを守り漁業関係者に配慮することで釣り場環境を守ることができる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 真冬の千葉外房でアジ&カマスが連発! | 釣りビジョン マガジン
- 首都圏でのアジングについて|宮
- アジ釣りは『時期』が重要! シーズンごとの傾向とポイントが合えば簡単に釣れます | TSURI HACK
- 真冬の関東でアジ・カマスが爆釣!?千葉 外房【小湊港】の釣り場紹介! | 釣りロマン倶楽部
- 関東のアジングポイントベスト20 | 魚速報
- 真冬の低活性アジの居場所の見つけ方3選 アジングで釣る方法も紹介 | TSURINEWS
- 冬のアジングで押さえるべきポイントとは?【藤原真一郎】 | サンライン
- 関東近郊の釣りスポット・釣り場おすすめ5選 – くるまも|三井住友海上
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。