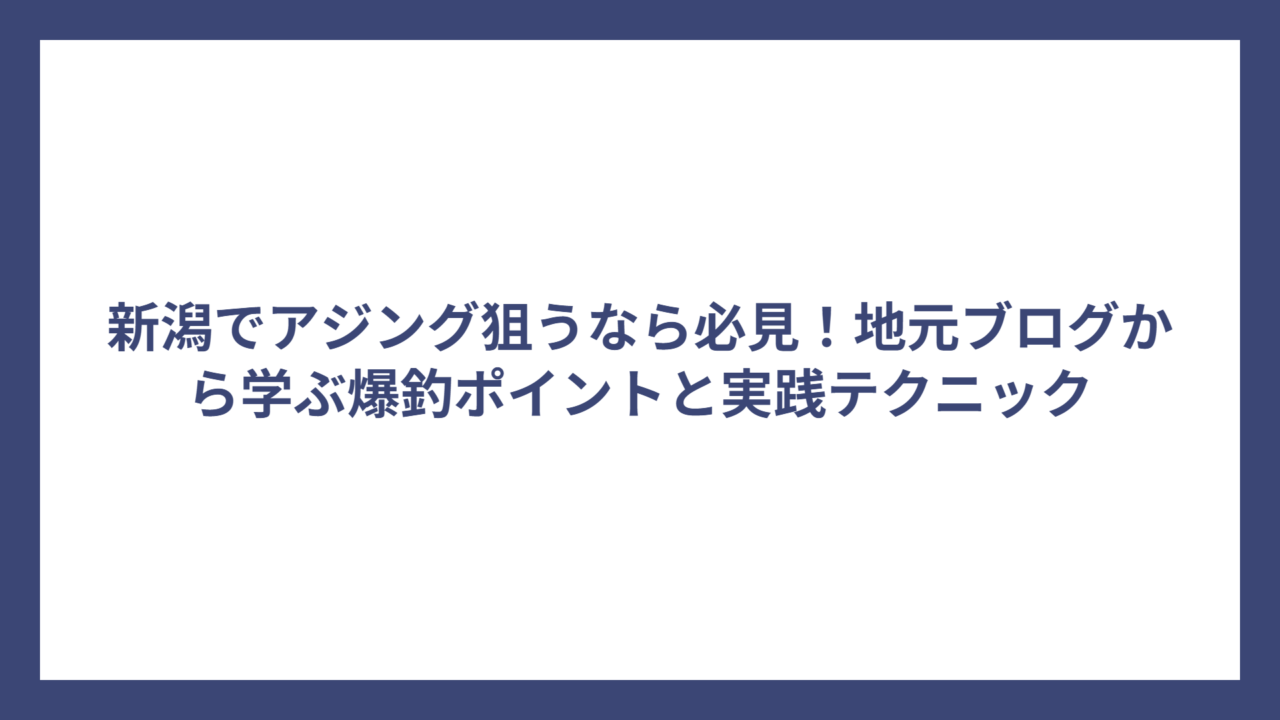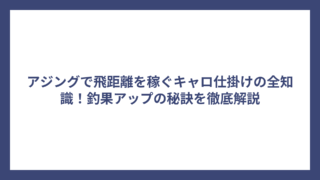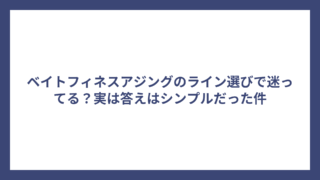新潟県は日本海に面し、良質なアジングポイントが数多く点在するエリアとして知られています。特に尺アジ(30cm以上)やギガアジ(40cm以上)といった大型個体が狙える数少ない地域として、全国のアジンガーから注目を集めています。しかし、初めて新潟でアジングに挑戦する方や、より良い釣果を求める方にとって、どのポイントでいつ狙うべきか、どんなタックルやリグが有効なのかといった情報は非常に重要です。
そこで本記事では、新潟県内の地元アングラーが運営するブログやSNSの情報を徹底的にリサーチし、新潟アジングの実態を多角的に分析しました。実際の釣行記録から見えてくるポイント選びのコツ、シーズナリティ、タックルセレクション、そして地域特有の釣り方まで、初心者から経験者まで役立つ情報を網羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 新潟アジングで参考になる地元ブログの特徴と活用法 |
| ✓ 新潟県内の主要アジングポイントとその特性 |
| ✓ 尺アジ・ギガアジが釣れる時期とタイミング |
| ✓ 新潟特有のアジングタックルとリグセッティング |
新潟アジングのブログから見える地元釣り場の実態
- 新潟のアジング情報を発信する代表的なブログとその特徴
- 地元ブログが教えてくれる新潟アジングの魅力
- ブログ情報から読み解く新潟県内のエリア別特性
- 釣果情報の読み方と活用のコツ
- SNSとブログを組み合わせた情報収集術
- 地元アングラーのブログに見る季節ごとの攻略法
新潟のアジング情報を発信する代表的なブログとその特徴
新潟県内でアジング情報を発信しているブログは複数存在し、それぞれが独自の視点と情報を提供しています。
代表的なものとしては、**新潟市を拠点とする「Marvelous Act(2)」**があります。このブログは新潟市からライトゲームやエギングの情報を発信しており、ショアからの釣りを中心に幅広い釣種をカバーしています。パックロッドを愛用している点が特徴的で、機動力を重視したスタイルが読み取れます。
また、**「釣り上げ.com」**は新潟県柏崎市をホームとする週末アングラーが運営するブログで、アジング・メバリング・ライトショアジギングなど多彩な釣りの実釣記録を詳細に記録しています。実釣データや使用タックルの詳細、インプレ記事なども充実しており、実践的な情報が豊富です。
さらに注目すべきは**「新潟東港周辺デイアジング専科」**というブログです。その名の通り、新潟東港周辺でのデイアジング(日中のアジング)に特化した情報を発信しており、一般的に夜釣りがメインとされるアジングにおいて、昼間でも尺アジが狙えるという新潟の特異性を象徴するブログと言えるでしょう。
📊 新潟アジング情報発信ブログの特徴比較
| ブログ名 | 拠点エリア | 主な特徴 | 情報の詳細度 |
|---|---|---|---|
| Marvelous Act(2) | 新潟市(下越) | パックロッド使用、多魚種対応 | 中〜高 |
| 釣り上げ.com | 柏崎市(中越) | 詳細な実釣データ、タックルインプレ充実 | 非常に高 |
| 新潟東港周辺デイアジング専科 | 新潟東港 | デイアジング特化、スプリットリグ多用 | 高 |
| トビヌケ新潟店のブログ | 新潟市 | 釣具店視点、セミナー情報も豊富 | 中 |
| FishBull | 新潟全域(現在は関西) | 初心者向け解説が充実 | 中 |
これらのブログに共通するのは、単なる釣果自慢ではなく、状況分析や試行錯誤のプロセスを詳細に記録している点です。天候、水温、潮汐、使用リグ、アクションなどの詳細データが記載されており、読者が同じ状況に遭遇した際に参考にできる実践的な情報となっています。
地元ブログが教えてくれる新潟アジングの魅力
新潟のアジングブログを読み込んでいくと、この地域特有の魅力が浮かび上がってきます。
最も印象的なのは、**30〜40cmクラスのアジが「普通に釣れる」**という表現が頻出することです。他地域では尺アジ(30cm以上)を釣ることが一つの大きな目標とされますが、新潟では尺アジがスタンダードサイズとして扱われ、40cm超えの「ギガアジ」も決して珍しくないという状況が読み取れます。
FishBullさんのブログでは「新潟県のアジングとはそういうポテンシャルがあります!」と述べられており、「30〜40cmのアジが普通に釣れる」「そのサイズの数釣りができる」「デイアジングも成立する」という3点が新潟アジングの凄さとして挙げられています。
この指摘は非常に重要です。一般的なアジングでは20cm前後のアジを数釣りすることが楽しみの中心ですが、新潟では「大型アジの数釣り」という、他地域では考えられない贅沢な釣りが展開できるのです。これは新潟の海洋環境、特に日本海側特有の水温変化やベイトフィッシュの豊富さが関係していると推測されます。
また、デイアジングが成立するという点も見逃せません。通常アジングは夜釣りが基本とされますが、新潟東港周辺では昼間でも尺アジクラスが狙えることが複数のブログで報告されています。これは仕事の都合で夜釣りが難しい方や、初心者で夜釣りに不安がある方にとって大きなメリットとなります。
さらに、年間を通じて長期間アジングが楽しめる点も魅力です。一般的には秋のアジングがメインとされますが、新潟では春から初冬まで、おそらく半年以上の期間でアジングを楽しむことができると考えられます。
ブログ情報から読み解く新潟県内のエリア別特性
新潟県は南北に長い県であり、エリアによってアジングの特性が異なります。ブログ情報を総合すると、大きく下越・中越・上越の3エリアに分けて考えることができます。
🎣 下越エリア(新潟市・新潟東港周辺)
新潟市を中心とする下越エリアは、新潟東港が最大のアジングポイントとして機能しています。複数のブログで新潟東港での釣果が報告されており、特に「ハッピーフィッシング」と呼ばれる管理釣り場が人気を集めています。
このエリアの特徴はデイアジングが成立することと、水深が比較的深いことです。新潟東港周辺デイアジング専科のブログでは、スプリットリグを多用した釣法が紹介されており、水深に対応した重めのジグヘッドとロングリーダーの組み合わせが効果的であることが示唆されています。
また、河口部も重要なポイントとして機能しています。信濃川や阿賀野川といった大河川の河口域は、ベイトフィッシュが集まりやすく、それを追って大型のアジが回遊してくると考えられます。
🎣 中越エリア(柏崎市周辺)
柏崎市を中心とする中越エリアは、磯場や堤防など多様なポイントが存在します。釣り上げ.comの詳細な釣行記録からは、このエリアでギガアジ(40cm超)の釣果が複数報告されており、大型アジを狙うアングラーにとって魅力的なエリアであることが分かります。
中越エリアの特徴は磯場でのアジングが盛んである点です。磯場は足場が不安定な反面、潮通しが良く、大型のアジが回遊してくる確率が高いと考えられます。また、河口や流れ込みといった変化のあるポイントも多く、ポイント選択の幅が広いことも特徴です。
🎣 上越エリア(上越市・糸魚川市周辺)
上越エリアは富山湾に近く、地理的にも日本海の深い海域に面しています。このエリアではサーフでのアジングも成立することが複数のブログで報告されており、特に回遊型の大型アジを狙う際に有効なポイントとなっています。
また、直江津港周辺も重要なポイントとして機能しており、堤防からのアジングで尺アジクラスが狙えることが報告されています。
📍 新潟県エリア別アジング特性まとめ
| エリア | 主要ポイント | 特徴 | 適した釣法 |
|---|---|---|---|
| 下越 | 新潟東港、河口域 | デイアジング可能、水深深い | スプリットリグ、重めのジグヘッド |
| 中越 | 柏崎市の磯場、堤防 | ギガアジ実績高い、変化に富む | ジグ単、キャロ |
| 上越 | サーフ、直江津港 | 回遊型大型アジ、潮通し良好 | 遠投リグ、フロートリグ |
釣果情報の読み方と活用のコツ
ブログの釣果情報を効果的に活用するためには、単に「釣れた・釣れなかった」だけでなく、状況データを総合的に分析することが重要です。
優れたアジングブログでは、以下のような情報が記載されています:
- 日時(具体的な時刻まで)
- 天候・風向・風速
- 潮汐(大潮・中潮・小潮など)
- 水温
- 使用タックル(ロッド・リール・ライン)
- リグセッティング(ジグヘッド重量・ワームサイズ・カラー)
- アクション(リトリーブ速度・シェイクの有無など)
- レンジ(表層・中層・ボトムなど)
- 釣果(サイズ・匹数)
これらの情報を複数の釣行記録と比較することで、「どういう条件の時にどんな釣り方が有効か」というパターンが見えてきます。
例えば、釣り上げ.comのブログでは、試行錯誤のプロセスが詳細に記録されています。ワームのカラーを変えた、ジグヘッドの重さを変えた、レンジを変えた、という変更とその結果が明確に記載されており、読者は「なぜその選択をしたのか」「結果はどうだったのか」を追体験できます。
釣り上げ.comでは「個人的にリグのローテーションで意識していること」として、①ワームのカラーを真逆の色に変える、②ワームのサイズダウン、③ジグヘッドの重さを軽くする、という順序で変更していくことが推奨されています。重要なのは「一度に複数の要素を変えない」ことで、これにより何が効いたのかを明確にし、再現性を高められると述べられています。
このアプローチは科学的な実験手法と同じで、変数を一つずつ変えることで因果関係を明確にするという考え方です。ブログの釣果情報を読む際も、このような「なぜそうしたのか」「結果はどうだったのか」という思考プロセスに注目することで、自分の釣行に活かせる知見が得られます。
また、釣れなかった記録も非常に重要です。多くのアングラーは釣果があった時だけを記録しがちですが、釣れなかった条件を知ることで、無駄な時間を減らすことができます。トビヌケ新潟店のブログでは、釣れない日の状況も含めて記録されており、「この条件では厳しかった」という情報も提供されています。
SNSとブログを組み合わせた情報収集術
近年はブログに加えて、X(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどのSNSでも釣果情報が発信されています。これらを組み合わせることで、よりリアルタイムで詳細な情報を得ることができます。
リアルタイム性ではSNS、詳細情報はブログという使い分けが効果的です。SNSでは「今日この場所でアジが釣れている」という速報性の高い情報が得られますが、詳細なタックル情報や試行錯誤のプロセスまでは記載されないことが多いです。一方、ブログでは釣行後に落ち着いて詳細を記録するため、情報の質と深さが異なります。
Marvelous Act(2)のブログでは、Instagram(@yutakayos)も併用して情報発信されており、ビジュアル面での情報補完がなされています。また、釣り上げ.comでもYouTubeチャンネルを運営しており、動画でアクションやポイントの様子を確認できます。
効果的な情報収集の流れとしては:
- SNSで最新の釣果情報をチェック(どのエリアで釣れているか)
- ブログで詳細な釣行記録を確認(どんな条件でどう釣ったか)
- YouTubeで動画を視聴(実際のアクションやポイントの様子)
- 自分の釣行計画を立案(得た情報を基に戦略を練る)
という順序が考えられます。
また、複数のブログを横断的に比較することも重要です。同じ日に異なるアングラーが異なるポイントで釣行している場合、それぞれのブログを比較することで、エリア全体の状況が把握できます。
地元アングラーのブログに見る季節ごとの攻略法
新潟のアジングは季節によって大きく様相が変わります。地元ブログの記録を追っていくと、シーズナルパターンが見えてきます。
🌸 春(4月〜6月):尺アジシーズンの到来
春は新潟アジングにおいて最も期待が高まる時期です。多くのブログで「4月頃から尺アジが釣れ始める」と報告されています。
FishBullのブログでは「尺アジは冬の終わりから釣れ始め、アジングで釣るにはもう少し後の春になってから、大体4月頃から釣れ始める」と述べられており、それまでは投げサビキなど餌で狙った方が良いとされています。
春のアジングの特徴は、産卵を控えた大型個体が接岸することです。体力をつけるために活発に捕食するため、ルアーへの反応も良好と考えられます。また、水温が徐々に上昇していく時期でもあり、魚の活性が上がるタイミングでもあります。
タックルとしては、大型個体に対応できるやや強めのロッドとリーダーが推奨されます。ジグヘッドは2〜2.5g程度の重めのものを使用し、ワームも2.5〜3インチと大きめのサイズが効果的という情報が複数のブログで確認できます。
☀️ 夏(7月〜8月):デイアジングとサイズダウン
夏季は水温が上昇し、アジのサイズが小さくなる傾向があります。新潟東港周辺デイアジング専科のブログでは、8月の記録として「豆アジ、豆サバ、豆カマス」という表現があり、小型個体が中心になることが示されています。
ただし、新潟の夏アジングには独特の魅力があります。それはデイアジングが本格的に楽しめることです。水温が高い夏は、昼間でもアジの活性が保たれやすく、日中の明るい時間帯でも釣果が期待できます。
夏のアジングでは軽量リグと小型ワームが基本となります。0.5〜1.5g程度の軽いジグヘッドに、2インチ以下の小型ワームを組み合わせることが多いようです。また、表層から中層をゆっくりと探る繊細な釣りが求められます。
🍂 秋(9月〜11月):数釣りとサイズアップ
秋は新潟アジング最盛期です。水温が下がり始め、冬に向けて荒食いする個体が増えるため、数釣りとサイズアップの両方が狙える贅沢な時期となります。
釣り上げ.comのブログでは、9月から10月にかけての釣行記録が多く、「胴長15cm」「ツ抜け(10匹以上)達成」といった釣果が報告されています。エギングと並行してアジングを楽しむアングラーも多く、マルチな釣行が可能な時期です。
秋のアジングではベイトフィッシュの種類と位置を把握することが重要です。イワシやカタクチなどのベイトが岸際に寄ってくるタイミングを捉えることで、それを追うアジの群れに遭遇できる確率が高まります。
❄️ 冬(12月〜3月):厳しいが大型の可能性
冬季は水温の低下により、一般的にはアジングが厳しくなる時期とされています。しかし、新潟では完全にシーズンオフになるわけではなく、条件が整えば釣果が得られることがブログ記録から確認できます。
トビヌケ新潟店のブログでは3月の釣行記録があり、「冷え込みで喰い渋っている+激流で、ちょっとテクニカルでしたが、パターンがわかっちゃうと連発でした」という報告があります。冬から春への移行期は、日によって状況が大きく変わるため、こまめな情報収集が重要です。
冬のアジングではタングステン製の重めのジグヘッドが効果的とされています。流れが強い冬の海で、しっかりとボトムを取り、アジのいるレンジを的確に攻めるためには、小型でも重量のあるタングステンジグヘッドが有利です。
新潟アジングのブログから学ぶ実践テクニックと装備選び
- ブログから読み解く新潟アジング必勝タックルセッティング
- 地元ブロガーが多用するワームとカラーローテーション
- 新潟特有のリグセッティングと使い分け
- ブログで頻出する効果的なアクションとレンジ攻略
- 常夜灯周りの攻略法とブログでの実例
- 河口・流れ込みポイントでの釣り方
- 堤防先端部での大型アジ攻略術
- デイアジング特有のテクニックとポイント
- 新潟東港でのバチコンアジング情報
- ブログから学ぶアジングの再現性と記録の重要性
- 集魚灯・ライトの活用法とブログでの実例
- 新潟アジングで注意すべき安全対策
- まとめ:新潟アジングをブログ情報で攻略する
ブログから読み解く新潟アジング必勝タックルセッティング
新潟のアジングブログを詳細に分析すると、この地域特有のタックルセッティングの傾向が見えてきます。全国的なアジングのセオリーとは若干異なる部分もあり、新潟でアジングを始める方は参考にすべきポイントが多くあります。
ロッド選択は大型対応が基本という点が重要です。一般的なアジングでは6フィート台の軽量ロッドが主流ですが、新潟では尺アジ・ギガアジが普通に釣れるため、やや長めでパワーのあるロッドが推奨されます。
トビヌケ新潟店のブログでは、アジングロッドとして十分なパワーを持ったものを使用していることが記載されており、「大サバにも対応できる」ことが条件として挙げられています。新潟では40cm前後のサバも一緒に釣れることが多いため、これらの魚を確実にランディングできる強度が必要です。
また、Marvelous Act(2)のブログでは、シマノのソアレエクスチューンMB S76UL-Sというパックロッドが紹介されています。これは7.6フィートという長めのレングスで、5ピースのパックロッド、バットパワーがしっかりしている点が評価されています。新潟のような大型アジが狙えるフィールドでは、「軽量ジグヘッドも扱えるが、大型魚にも負けないバットパワー」という相反する要素を両立したロッドが理想的です。
リールは2000〜2500番台が主流で、ドラグ性能が重要視されています。突然の大型ヒットに対応するため、スムーズなドラグワークが求められます。
ラインシステムについては複数のアプローチが見られます:
📌 新潟アジング推奨ラインシステム
| ラインタイプ | 太さ | メリット | デメリット | 使用場面 |
|---|---|---|---|---|
| エステル | 0.3〜0.5号 | 感度最高、軽量リグ対応 | 強度低い、大型魚には不安 | 小型〜中型アジ専門 |
| PE | 0.2〜0.3号 | 強度高い、大型対応 | 風に弱い、価格高い | 大型狙い、サバ混じり |
| フロロリーダー | 3〜4号 | 根ズレに強い、沈みやすい | 硬い、結束面倒 | PE使用時のリーダー |
新潟東港周辺デイアジング専科のブログでは、エステル0.5号の使用が基本とされていますが、大型サバが多い状況ではPE0.2号に変更したという記録があります。このように、状況に応じてラインを使い分ける柔軟性が新潟アジングでは求められます。
また、リーダーについては10m程度のロングリーダーを取る例が多く見られます。これは根ズレ対策だけでなく、魚に警戒心を与えないという効果も期待できます。特に日中のデイアジングでは、ラインの視認性がバイトに影響する可能性があるため、リーダーを長めに取ることが推奨されます。
地元ブロガーが多用するワームとカラーローテーション
新潟のアジングブログで頻繁に登場するワームとカラーには、明確な傾向があります。
サイズは2.5〜3インチが主流で、全国的なアジングで使われる1.5〜2インチよりも大きめです。これは新潟のアジ自体が大型であること、ベイトフィッシュも大きめであることが理由と考えられます。
トビヌケ新潟店のブログでは、ケイテック イージーシェイカーが頻繁に登場します。3インチサイズのものが「メガアジ」(30cm超)のヒットワームとして紹介されており、カラーはクリアチャートリュースが推奨されています。また、2.5インチサイズも併用されており、状況に応じてサイズダウンすることの重要性が示されています。
釣り上げ.comのブログでは、34(サーティフォー)のビーディ3インチやマーズ ナノシャッド1.9などが使用されています。特にビーディは「大きいのが釣りたい」という意図で選択されており、大型狙いに特化したワームセレクトの考え方が参考になります。
FishBullのブログでは、JACKALL ペケリングが推奨ワームとして紹介されています。このワームはテール部分のアクションが特徴的で、新潟の大型アジに効果的とされています。
カラーローテーションについては地域特性が見られます。新潟市周辺では河川からの流入があり濁りがあることが多いため、白やピンクなどの視認性の高いカラーが好まれる傾向があります。
Marvelous Act(2)のブログでは「新潟市だとピンクよりも白の方が反応が良いことが多い」と述べられており、濁りがある海域では白系のカラーが効果的であることが示唆されています。
一方、常夜灯周りや深場ではクリアー系やチャート系も効果的とされています。トビヌケ新潟店のブログでは「クリアーチャートリュース」が常夜灯周りや濁り、深場におすすめカラーとして紹介されています。
🎨 新潟アジング推奨ワームカラーと使用状況
| カラータイプ | 代表カラー | 効果的な状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 白・ピンク系 | ホワイト、ピンク | 濁り、河口域、マズメ | 視認性が高い、シルエット強調 |
| クリア系 | クリア、スモーク | 常夜灯下、澄み潮 | プレッシャーが高い時に自然 |
| チャート系 | チャートリュース | 深場、常夜灯、濁り | アピール力高い、光を反射 |
| グロー系 | グロー、蓄光 | ナイトゲーム | 暗闇で発光、長時間アピール |
カラーローテーションの基本的な考え方として、前述の釣り上げ.comの記事が参考になります。「最初に選んだカラーで反応がなければ、真逆の色に変える」というアプローチは、魚が何を見て反応しているかを探る上で効果的です。例えば、クリア系で反応がなければチャート系に変える、白系で反応がなければ黒系に変える、といった対照的な選択が推奨されます。
新潟特有のリグセッティングと使い分け
新潟のアジングでは、通常のジグ単(ジグヘッド単体)に加えて、スプリットショットリグやキャロライナリグ、さらにはバチコンアジングなど、多様なリグが使用されています。
スプリットショットリグは新潟東港で特に有効とされています。新潟東港周辺デイアジング専科のブログでは、このリグが頻繁に使用されており、デイアジングの主力リグとなっています。
スプリットショットリグは、ラインに小型のガン玉(割ビシ)を打ち、そこから30〜50cm程度離してジグヘッドを付けるセッティングです。このリグのメリットは:
- 飛距離が出る(重りで遠投可能)
- ゆっくり沈む(ジグヘッド自体は軽量でOK)
- 自然なフォール(ジグヘッドが軽いため不自然な動きにならない)
- レンジキープしやすい(重りとジグヘッドの距離調整で)
という点が挙げられます。特に水深のある新潟東港では、ボトム付近を効率的に探るのに適したリグと言えます。
あるブログでは、某管理堤防(おそらくハッピーフィッシング)での釣行において、「ジグヘッド単体3gで始めるもサバにちょっかいを出されフォール中のラインにはマイワシがばんばん当たるので着底がわからない」という状況で、三叉サルカンを使ってバチコン風にアレンジした例が紹介されています。
釣行記では「水深もあるのでフリーフォールさせても海水とラインの抵抗により着底地点が手前になりどうにもHitに持ち込めそうにないのでTackleBOXに忍ばせていた三叉サルカンを使ってバチコン風にアレンジ!」とあり、工夫によって状況を打開したことが記されています。
このように、状況に応じてリグをアレンジする柔軟性が新潟アジングでは重要です。特に水深が深い場所、流れが強い場所、ベイトフィッシュが多い場所では、ジグ単だけでは対応できないケースがあります。
また、釣り上げ.comのブログでは、バチコンアジングの実践記録も掲載されています。新潟東港沖で水深50mのバチコンアジングに挑戦した記事では、ボトム攻略の重要性やドラグ管理の反省点などが詳細に記録されており、オフショアのアジングに興味がある方には非常に参考になる内容です。
リグの使い分け基準としては:
✅ ジグ単(0.5〜2.5g)
- 浅場(水深5m以内)
- 表層〜中層狙い
- 風が弱い日
- 繊細な釣りをしたい時
✅ スプリットショットリグ
- 中深場(水深5〜15m)
- ボトム〜中層狙い
- 遠投したい時
- デイゲーム
✅ キャロライナリグ
- 遠投重視
- サーフや大型堤防
- 回遊待ち
✅ バチコンアジング(オフショア)
- 水深30m以上
- ボート釣り
- 大型狙い
という区分けが考えられます。
ブログで頻出する効果的なアクションとレンジ攻略
新潟のアジングブログを読み込むと、基本的なアクションはシンプルであることが分かります。複雑なテクニックよりも、状況に応じた適切なレンジ選択とリトリーブスピードの調整が重要視されています。
**最も頻出するアクションは「スローリトリーブ+時々シェイク」**です。基本的にゆっくりとリールを巻き、時折ロッドティップを小刻みに振ってワームにアクションを加えるという方法です。
釣り上げ.comのブログでは「細かいシェイクを入れてからのテンションフォール」というアクションが紹介されており、「テンションフォールしながらもすこーしだけリーリングも加えています。イメージは水面から1メートルくらいの同じレンジをゆっくりと引いてくる感じ」と具体的に説明されています。
このアクションのポイントは**「同じレンジをキープする」**ことです。アジは一定のレンジに群れていることが多いため、そのレンジを見つけたら、できるだけ長くその層を引いてくることが釣果につながります。
**レンジ攻略については「表層から順に探る」**というセオリーが新潟でも基本です。まず表層(水面直下〜1m)を探り、反応がなければ中層(1〜3m)、それでもダメならボトム付近、という順序で探っていきます。
ただし、新潟東港のようなデイアジングポイントでは**「ボトム付近で釣れる」**ケースが多いことがブログから読み取れます。トビヌケ新潟店のブログでは「デカいアジはボトム付近で釣れている模様」という情報があり、重めのジグヘッドでボトムを攻める重要性が示されています。
また、興味深いのは**「足元でライズしているアジを狙う」**というテクニックです。fimoのブログでは、夏の新潟アジングで足元表層を探ると水面直下に浮上してくる魚影が見えたため、「足元でワームを水面直下で8の字を描くようにグルグル回していたら、下からアジが食い上げてきてヒット」という経験が記録されています。この釣り方を「のべ竿釣法」と名付けており、キャストせずに足元だけで完結する効率的な釣り方として紹介されています。
🎣 新潟アジング効果的アクション一覧
| アクション名 | 方法 | 効果的な状況 |
|---|---|---|
| スローリトリーブ | 一定速度でゆっくり巻く | 基本、高活性時 |
| シェイク&ポーズ | 細かく振って止める | 低活性、居食い対策 |
| テンションフォール | テンションかけながら沈める | レンジ探り、バイト多発 |
| リフト&フォール | 持ち上げて落とす | ボトム攻略 |
| 足元8の字 | 足元で円を描く | 表層ライズ時 |
常夜灯周りの攻略法とブログでの実例
夜釣りにおいて常夜灯周りは最重要ポイントです。新潟のブログでも、常夜灯攻略に関する記述が多く見られます。
常夜灯の攻略で重要なのは**「明暗の境目を狙う」**ことです。真っ暗な場所よりも、明るい場所でもなく、その境界線にアジが溜まっていることが多いとされています。
トビヌケ新潟店のブログでは、集魚灯の使用が推奨されています。「集魚灯<ラグゼ フラットライト>と<アジングボール>も効果抜群でした!」という記載があり、自ら光源を作り出すことの有効性が示されています。
集魚灯を使う際のポイントは:
- 釣り開始30分前から点灯(プランクトンを集める時間が必要)
- 水面ではなく少し水中に沈める(表層だけでなく中層も照らす)
- 明暗の境目を作る(真下ではなく境界を狙う)
- 周囲の釣り人への配慮(眩しくないように角度調整)
という点が重要です。
また、常夜灯周りではワームカラーの選択も重要です。一般的にクリア系やグロー系が効果的とされていますが、新潟では前述の通りクリアチャート系の実績が高いようです。
常夜灯下では表層から中層を重点的に探ることが基本ですが、プレッシャーが高い場合はあえてボトムを攻めるという逆転の発想も有効です。多くのアングラーが表層を攻めている場合、ボトム付近には意外とプレッシャーのかかっていない魚がいる可能性があります。
河口・流れ込みポイントでの釣り方
新潟は信濃川、阿賀野川をはじめとする多くの河川が日本海に注いでおり、河口域は重要なアジングポイントとなっています。
FishBullのブログでは、河口・流れ込みが尺アジのポイントとして紹介されています。
「アジは大きくなればなるほど、プランクトンではなく小魚を食べる習性が強くなると聞きます。ではどこに大きなアジが集まるかというと必然的にベイトが溜まりやすい、流れて来やすい河口や流れこみではないでしょうか。実際に河口部分では尺越えのアジが連発したことがあります」
この指摘は生態学的にも理にかなっています。大型のアジは効率的にエネルギーを得るため、小魚を積極的に捕食するようになります。河口域はベイトフィッシュが豊富で、淡水と海水が混じり合うことで栄養分も多く、様々な生物が集まるポイントです。
河口攻略のポイントは:
🌊 流れの把握 河口は流れが複雑です。満潮時と干潮時では流れの向きや強さが変わります。一般的には、満潮から干潮に向かう下げ潮の時が良いとされています。この時、河川水が海に流れ出し、それに乗ってベイトフィッシュが流されるため、それを狙ってアジも集まると考えられます。
💧 濁りへの対応 河口域は濁っていることが多く、特に雨後は著しく濁ります。そのため、白やピンクなどの視認性の高いワームカラーが効果的です。Marvelous Act(2)のブログでも、新潟市周辺では白系のカラーが効果的と述べられており、河口域では特にこの傾向が強いと推測されます。
🎯 ポイント選定 河口の中でも、特に流れがヨレる場所や駆け上がりが狙い目です。流れがぶつかり合う場所や、急に深くなる場所(ブレイク)には魚が溜まりやすいとされています。
⚠️ 安全面での注意 河口域は流れが強く、足場が悪い場所も多いため、安全面での配慮が不可欠です。ライフジャケットの着用は必須であり、特に暗い時間帯は足元に十分注意する必要があります。
堤防先端部での大型アジ攻略術
堤防の先端部は潮通しが良く、回遊魚が回ってくる可能性が高いポイントです。新潟のブログでも、堤防先端での釣果報告が多く見られます。
FishBullのブログでは「堤防の先端付近では堤防の根本とは雲泥の差が出るほど釣果が変わります」と述べられており、わざわざ先端まで歩く価値があることが示されています。
堤防先端攻略のポイントは:
🎯 潮目を見つける 堤防先端では、異なる流れがぶつかり合って潮目ができることがあります。潮目は水面を見るとわかりやすく、泡やゴミが線状に溜まっている場所です。この潮目周辺にベイトが溜まり、それを狙ってアジも集まります。
🌀 流れの変化を意識 堤防先端では、表層と底層で流れの向きが異なることがあります。表層は沖に向かって流れているのに、底層は手前に向かって流れているという状況も珍しくありません。このため、使用するリグによってワームが流される方向が変わることを意識する必要があります。
軽いジグ単は表層の流れに乗り、重いスプリットリグは底層の流れに影響されます。状況に応じてリグを使い分け、魚がいるレンジの流れに合わせることが重要です。
🕒 時合を逃さない 堤防先端では、回遊してくるアジを狙うスタイルになることが多いため、時合(魚が活発に捕食するタイミング)が短いことがあります。一度回遊が来たら、できるだけ効率的に釣ることが重要です。
トビヌケ新潟店のブログでは「パターンがわかっちゃうと連発でした」という記載があり、一度パターンを掴めば短時間で複数匹釣れることが示されています。逆に言えば、パターンを掴むまでの試行錯誤をいかに早く行うかが鍵となります。
🎣 遠投の重要性 堤防先端では、沖の潮目を狙うために遠投が必要になることがあります。そのため、ある程度重めのリグ(2g以上のジグヘッドやスプリットリグ、キャロライナリグ)を準備しておくことが推奨されます。
デイアジング特有のテクニックとポイント
新潟アジングの大きな特徴の一つがデイアジング(日中のアジング)が成立することです。通常、アジングは夜釣りが基本とされていますが、新潟では昼間でも尺アジクラスが狙えます。
新潟東港周辺デイアジング専科のブログは、まさにこのデイアジングに特化した情報を提供しており、非常に参考になります。
デイアジングの特徴とコツは:
☀️ 水深のある場所を選ぶ 日中は日光が水中に入り込むため、アジは表層を避けて深場に潜る傾向があります。そのため、デイアジングでは水深10m以上ある場所を選ぶことが基本となります。新潟東港のハッピーフィッシングでは水深15m程度あると報告されており、デイアジングに適した条件と言えます。
🎣 重めのリグでボトムを攻める 日中のアジは底付近にいることが多いため、2〜3gのジグヘッドやスプリットリグでボトムを攻めることが基本です。前述のブログでも「デカいアジはボトム付近で釣れている模様」という情報があり、ボトム攻略の重要性が示されています。
🐟 サバやイワシとの混在 デイアジングのポイントでは、アジだけでなくサバやイワシも多数混在していることがあります。ある釣行記では「サバにちょっかいを出されフォール中のラインにはマイワシがばんばん当たる」という状況が記録されており、これらの魚をかわしながらアジを狙う技術が求められます。
対策としては:
- フォールスピードを速くする(タングステンジグヘッドでストンと落とす)
- ボトムまで一気に沈める(カウントダウンして底を取る)
- ワームサイズを大きくする(大型アジだけに狙いを絞る)
などが考えられます。
⏰ 時間帯の工夫 完全な真昼よりも、朝マズメ後や夕マズメ前の時間帯の方が釣果が上がることが多いようです。また、曇りの日は日中でも比較的アジの活性が高いとされています。
🔍 ベイトの動向を観察 デイゲームでは視界が良いため、ベイトフィッシュの動きを目視で確認できるメリットがあります。水面でベイトが逃げ惑っている場所や、鳥が集まっている場所は、その下にフィッシュイーターがいる可能性が高いです。
新潟東港でのバチコンアジング情報
新潟東港はショアからのアジングだけでなく、ボートからのバチコンアジングも楽しめるフィールドです。釣り上げ.comでは、新潟東港沖でのバチコンアジング実釣記録が詳細に記載されています。
バチコンアジングとは、ボートから水深30m以上の深場でアジを狙う釣法で、専用のロッドとリグを使用します。新潟東港沖では水深50mという記録があり、かなり本格的なバチコンアジングが楽しめるようです。
バチコンアジングのポイント:
⚙️ 専用タックルが必要 通常のアジングロッドでは、水深50mのバチコンアジングは対応できません。専用のバチコンロッドや、ライトゲームロッドの中でもバットパワーがあるものを選ぶ必要があります。
🎣 リグセッティング バチコンでは、三叉サルカンを使用し、オモリと2本のハリス(エダス)を出すセッティングが基本です。オモリは20〜40号程度、ハリスの長さは50cm〜1m程度が標準的です。
📍 ボトムの取り方 水深が深いため、正確にボトムを取ることが重要です。オモリが着底したら、すぐに50cm〜1m程度リールを巻いて少しオモリを浮かせ、そのレンジをキープします。
🎯 アタリの取り方 バチコンアジングでは、穂先で明確にアタリが出ることが多いです。コンコンという明確なアタリが出たら、少し待ってから大きくアワセを入れます。
釣り上げ.comの記事では、「ドラグ管理」の重要性も指摘されています。水深が深いため、アワセを入れた時に大型がかかると、ラインブレイクのリスクが高まります。適切なドラグ設定(ラインの60〜70%程度の強さ)を心がけることが重要です。
ブログから学ぶアジングの再現性と記録の重要性
釣りにおいて**「再現性」**は非常に重要な概念です。一度釣れたパターンを次回も再現できるかどうかが、安定した釣果を得るための鍵となります。
釣り上げ.comのブログでは、この再現性について非常に示唆に富んだ考察がなされています。
「個人的な優先順位としては①ワームのカラーを真逆の色に変える②ワームのサイズダウン。カラーは初めに使っていたものを先に使い、次に①で変更したものを使う③ジグヘッドの重さを軽くする。ワームは一番初めに使っていたもの→カラーを変えたもの→サイズを落としたものの順で変えていく この順番で行うことが多いです。」
「釣れない時にいっぺんにワームもジグヘッドも変えることはオススメしません。それはなぜかたとえローテーションして釣れたとしても、釣れた理由が ・ワームのカラー由来なのか・ワームのサイズ由来なのか・ジグヘッドの重さ由来なのか わからなくなってしまうからです。」
この考え方は科学的な実験手法と全く同じです。変数を一つずつ変えることで、何が結果に影響を与えたかを明確にするというアプローチです。
この方法を実践するためには、詳細な釣行記録を付けることが不可欠です。記録すべき項目は:
📝 釣行記録チェックリスト
| カテゴリ | 記録項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 日時、場所、天候、気温、水温 |
| 海況 | 風向・風速、波高、潮汐、潮位 |
| タックル | ロッド、リール、ライン(種類・太さ) |
| リグ | ジグヘッド重さ、ワーム(種類・サイズ・カラー) |
| アクション | リトリーブ速度、シェイクの有無、レンジ |
| 釣果 | 匹数、サイズ、釣れた時刻、ヒットレンジ |
| その他 | ベイトの種類、他の釣り人の状況 |
これらを記録することで、後日振り返った時に「あの時はこういう条件でこのリグが効いた」という知見が蓄積されていきます。
また、釣れなかった時の記録も重要です。「この条件では釣れなかった」という情報も、貴重なデータとなります。次回同じような条件の時に、無駄な時間を使わずに済みます。
スマートフォンのメモアプリや専用の釣りアプリを使えば、簡単に記録を残すことができます。写真も一緒に保存しておけば、視覚的にも分かりやすい記録となります。
集魚灯・ライトの活用法とブログでの実例
夜釣りにおいて、集魚灯やライトの活用は釣果を大きく左右する要素です。新潟のアジングブログでも、ライト類の使用に関する記述が複数見られます。
トビヌケ新潟店のブログでは、ラグゼ フラットライトとアジングボールの使用が推奨されており、「効果抜群でした!」と評価されています。
集魚灯の効果的な使い方:
💡 点灯タイミング 釣り開始の30分〜1時間前から点灯するのが理想的です。プランクトンが光に集まり、それを食べに小魚が寄ってきて、さらにそれを狙ってアジが集まるという食物連鎖ができるまでには時間がかかります。
🌊 設置位置 集魚灯は水面に浮かべるタイプと、水中に沈めるタイプがあります。水中に沈めるタイプの方が効果的とされています。理由は、表層だけでなく中層にも光が届き、より広い範囲にベイトを集められるからです。
ただし、沈める深さは1〜2m程度で十分です。あまり深く沈めると光が拡散してしまい、効果が薄れます。
📐 釣る位置 集魚灯の真下ではなく、光の縁(明暗の境目)を狙うのが基本です。アジは警戒心が強いため、明るすぎる場所には出てこないことが多いです。薄明かりの場所で餌を待ち伏せしているイメージです。
👥 周囲への配慮 集魚灯を使用する際は、周囲の釣り人への配慮が不可欠です。明るすぎるライトや、角度が悪くて他の釣り人の目に入ってしまうようなセッティングは避けるべきです。
また、Marvelous Act(2)のブログでは、竿先に付けるケミホタルの使用が複数回言及されています。ケミホタルは集魚効果というよりも、アタリを目視で確認するために使用されます。
夜釣りでは、ラインの動きだけでアタリを取るのは難しいことがあります。特に居食い(その場で食って動かない)タイプのアタリは、ラインの変化だけでは分かりにくいです。竿先にケミホタルを付けておけば、竿先の微妙な動きでアタリが分かります。
🔦 ヘッドライトの選び方 手元の作業をするためのヘッドライトも重要です。最近は釣り用に設計されたキャップライトも人気があります。
釣り上げ.comでは、がまかつのキャップライトLEHL151のインプレ記事があり、ヘッドライトよりも軽量で付けていても気にならない点が評価されています。
ヘッドライト・キャップライト選びのポイントは:
- 明るさ調整機能(状況に応じて明るさを変えられる)
- 赤色LED機能(魚を警戒させにくい)
- 防水性能(IPX4以上が望ましい)
- 軽量性(長時間使用でも疲れない)
新潟アジングで注意すべき安全対策
釣りは楽しい趣味ですが、安全対策を怠ると重大な事故につながる可能性があります。特に新潟の日本海側は、急な天候変化や高波のリスクがあるため、十分な注意が必要です。
FishBullのブログでは、安全対策について明確に言及されています。
「特にテトラ帯や河口など見え辛く転倒や踏み外し一つで大事故に繋がる可能性があります。ライフジャケット、ヘッドライト、状況に合った靴 しっかりと装着の上での釣行をお願いします。初心者の方、ベテランの方も初めてのポイントでの釣行は日中に行なってください。」
この指摘は非常に重要です。アジングで訪れることの多い磯場、堤防、河口域は、それぞれ特有の危険があります。
⛑️ ライフジャケットの着用 これは絶対条件です。「泳げるから大丈夫」「浅い場所だから大丈夫」という考えは危険です。転落した際、パニック状態になったり、頭を打って気を失ったりする可能性があります。ライフジャケットを着用していれば、意識を失っても浮いていられるため、救助の可能性が高まります。
近年は自動膨張式のコンパクトなライフジャケットも普及しており、着用の負担も少なくなっています。
👟 滑りにくい靴の選択 磯場や堤防は海藻や苔で滑りやすくなっています。特に夜間は足元が見えにくいため、スパイクシューズやフェルトスパイクシューズの着用が推奨されます。
一般的なスニーカーやデッキシューズでは、濡れた堤防や磯では非常に滑りやすく危険です。
🔦 照明の確保 夜釣りでは、ヘッドライトやキャップライトは必須です。両手がフリーになる照明を選ぶことで、トラブルが起きた時にも対応しやすくなります。
また、予備の電池やモバイルバッテリーも持参することが推奨されます。途中で照明が切れてしまうと、暗闇の中を歩いて帰らなければならなくなり、非常に危険です。
📱 通信手段の確保 万が一の事故に備えて、携帯電話は必ず持参し、防水ケースに入れておくことが推奨されます。また、可能であれば釣行先を家族や友人に伝えておくことも重要です。
🌊 気象・海象の確認 釣行前には必ず天気予報と波浪予報を確認します。特に日本海側は急に時化ることがあるため、予報で風速が強まる予報が出ている場合は、釣行を中止する勇気も必要です。
また、現地に着いてから「波が高い」「風が強い」と感じた場合は、無理をせず釣りを中止することも重要です。
👥 単独釣行の注意 できれば複数人での釣行が望ましいですが、単独で行く場合は特に注意が必要です。トラブルが起きた時に助けを呼べる人がいないため、より慎重な行動が求められます。
まとめ:新潟アジングをブログ情報で攻略する
最後に記事のポイントをまとめます。
- 新潟のアジングブログは「Marvelous Act(2)」「釣り上げ.com」「新潟東港周辺デイアジング専科」などが充実しており、詳細な実釣データを提供している
- 新潟では30〜40cmのアジが「普通に釣れる」という他地域にはない特徴があり、ギガアジ(40cm超)も珍しくない
- 新潟県内は下越・中越・上越の3エリアに分けられ、それぞれ特性が異なる(下越はデイアジング、中越は磯場、上越はサーフ)
- 釣果情報を活用する際は、天候・潮汐・タックル・リグ・アクションなどの詳細データを総合的に分析することが重要である
- SNSはリアルタイム情報、ブログは詳細情報という使い分けで効率的に情報収集できる
- 春(4〜6月)は尺アジシーズン、夏はデイアジング、秋は数釣り最盛期、冬は厳しいが大型の可能性ありという季節パターンがある
- 新潟アジングではやや長めでパワーのあるロッド(7フィート前後)が推奨され、大型対応が基本となる
- ラインはエステル0.3〜0.5号が基本だが、大型・サバ混じりの状況ではPE0.2〜0.3号への変更も有効である
- ワームは2.5〜3インチの大きめサイズが主流で、カラーは濁り対策の白系、常夜灯下のクリアチャート系などが効果的である
- スプリットショットリグやバチコンアジングなど、状況に応じた多様なリグセッティングが新潟では使用されている
- 基本アクションは「スローリトリーブ+時々シェイク」で、レンジキープが重要である
- リグ変更の際は一度に一つの要素だけを変えることで、何が効いたかを明確にし、再現性を高められる
- 河口・流れ込みは大型アジの好ポイントで、白系カラーと流れの把握が攻略のカギとなる
- 堤防先端部は潮通しが良く回遊魚が期待できるが、潮目の把握と遠投が重要である
- 新潟東港ではデイアジングが成立し、水深のある場所で重めのリグでボトムを攻めることが基本となる
- 集魚灯は釣り開始30分〜1時間前から点灯し、明暗の境目を狙うことが効果的である
- 釣行記録を詳細に付けることで、パターンの再現性が高まり、安定した釣果につながる
- ライフジャケット、滑りにくい靴、照明の確保など、安全対策を徹底することが最優先事項である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- Marvelous Act(2)
- 【アジング】新潟で狙う尺アジ?ギガアジ!狙い目と釣り方を解説します! – FishBull
- 新潟アジング | 日本は狭いのブログ
- あべちゃん釣行記新潟修行編その66<アジングNight Party!>: トビヌケ新潟店のブログ
- 【ブログ】 〜夏の新潟アジング〜
- アジング調査!: トビヌケ新潟店のブログ
- 釣り上げ.com-新潟釣りブログ
- 新潟東港周辺デイアジング専科
- これぞ新潟のアジ!アジングの再現性について生意気ながら考察してみた | Enjoy Fishing!
- アジング – 釣り上げ.com
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。