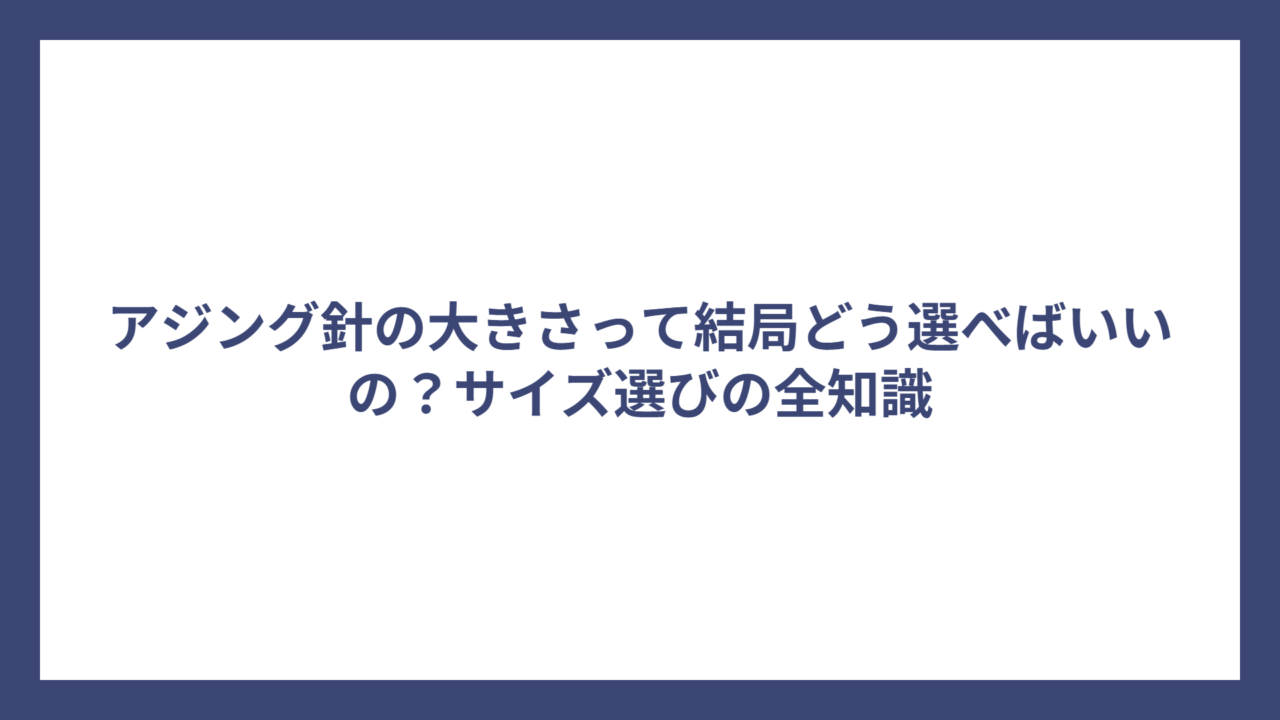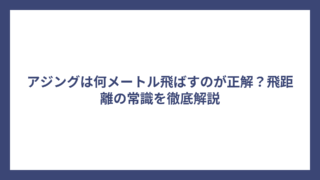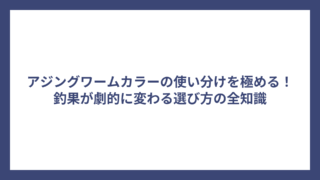「アジングを始めたけど、針の大きさってどう選べばいいんだろう?」「#8とか#10とか数字が書いてあるけど、何が違うの?」そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。アジングにおいて針の大きさ選びは、釣果を大きく左右する重要な要素です。適切なサイズを選べば、今まで釣れなかったアジが面白いように釣れるようになるかもしれません。
この記事では、インターネット上に散らばるアジング針の大きさに関する情報を収集し、初心者の方でも理解しやすいように整理しました。基本的な表記の読み方から、アジのサイズ別・釣り方別の選び方まで、実践的な情報を網羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジング針の大きさ表記(#数字とS/M/L)の読み方がわかる |
| ✓ 狙うアジのサイズに合わせた針の選び方が理解できる |
| ✓ フックの形状(ゲイブ・シャンク)による違いがわかる |
| ✓ 釣り方や状況に応じた針のローテーション方法が身につく |
アジング針の大きさを理解するための基礎知識
このセクションでは、アジング針の大きさに関する基本的な知識を整理していきます。
- アジング針の大きさは数字が大きいほど小さくなる
- フックサイズ表記にはアルファベット表記もある
- アジのサイズに合わせた針の大きさ選びが釣果を左右する
- フックの形状も針の大きさと同じくらい重要
- ゲイブの違いが吸い込みやすさに影響する
- シャンクの長さで使い分けが必要
アジング針の大きさは数字が大きいほど小さくなる
アジング針の大きさを表す最も一般的な表記が「#(番号)表記」です。この表記方法には、初心者が混乱しやすい特徴があります。それは数字が大きくなるほど、針のサイズは小さくなるという点です。
例えば、#4よりも#8の方が小さく、#8よりも#12の方がさらに小さい針になります。これは釣り針全般に共通する表記ルールですが、直感的ではないため注意が必要です。
で表記してるやつですね。
数字が大きい方が鈎のサイズが小さいです。 #10 > #8 > #6 > #4
この情報からもわかるように、アジングで一般的に使用される針のサイズは概ね#4から#14程度の範囲です。ただし、メーカーによって若干の誤差があるため、同じ#8でもメーカーが違えば微妙にサイズが異なる場合があります。
アジング初心者の方が最初に揃えるべきサイズとしては、#8から#10あたりが汎用性が高いと言えるでしょう。このサイズであれば、15cm~25cm程度の中型アジに対応でき、多くのフィールドで活躍してくれます。
針の大きさを理解する上で重要なのは、単純にサイズだけでなく、そのサイズが持つ意味を知ることです。小さい針(数字が大きい)は小さなアジの口にも入りやすい反面、大型のアジとのファイトでは伸びや折れのリスクが高まります。逆に大きい針(数字が小さい)は強度がある反面、小型のアジには大きすぎてフッキングしにくくなります。
フックサイズ表記にはアルファベット表記もある
針の大きさ表記には、#数字以外にも**アルファベット表記(SS/S/M/L)**を採用しているメーカーがあります。これは衣服のサイズ表記と同様で、比較的わかりやすい方式です。
📊 主要なフックサイズ表記の対応表(一般的な目安)
| アルファベット表記 | #表記の目安 | 対象アジサイズ | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| SS | #12~#14 | 10~15cm(豆アジ) | 極小アジ専用 |
| S | #10 | 15~20cm(小アジ) | 小~中型アジの数釣り |
| M | #8 | 18~28cm(中アジ) | オールラウンド |
| L | #6~#4 | 25cm~(尺アジ以上) | 大型アジ・ギガアジ |
ただし、この対応関係はあくまで一般的な目安であり、メーカーによって規格が異なる点には注意が必要です。同じMサイズでも、メーカーAとメーカーBでは実際のサイズが違うケースもあります。
アルファベット表記のメリットは、直感的にサイズがイメージしやすい点です。SSが最小、Lが最大という理解は誰にとってもわかりやすいでしょう。一方で、#数字表記の方が細かいサイズ刻みで選択できる場合が多いため、より精密な調整を求める上級者は#表記を好む傾向があります。
初心者の方がジグヘッドを選ぶ際は、パッケージに「対象魚サイズ:15~25cm」などの表記がある製品を選ぶと失敗が少ないでしょう。また、複数のサイズを少量ずつ購入して、実際に釣り場で試してみることをおすすめします。
重要なのは、表記方法にかかわらず「自分が狙うアジのサイズに適した針を選ぶ」という基本原則です。表記が異なっても、この原則さえ押さえておけば大きな失敗は避けられます。
アジのサイズに合わせた針の大きさ選びが釣果を左右する
アジング針の大きさ選びで最も重要なのが、狙うアジのサイズとのマッチングです。これは人間が食事をする時に、口のサイズに合った食べ物を選ぶのと同じ理屈です。
あるブログでは、顎関節症の例えを使って非常にわかりやすく説明されていました。
人間でも同じ。私は顎関節症なのだが、正直、ビック○ックとか食べ辛い。口がそこまで開かんのです。でもナゲットやポテトフライなら余裕で入る。
この例えは本質を突いています。アジも同様に、自分の口のサイズに合わないルアーには反応が鈍くなるか、バイトしても針掛かりしないのです。
なぜサイズマッチングが重要なのか、その理由は複数あります。第一に、針が大きすぎると物理的にアジの口に入りません。バイトはあってもフッキングしない「空振り」が続出します。第二に、針が小さすぎると大型アジとのファイト中に針が伸びたり、フッキングポイントが弱い部分になってバラシにつながります。
📌 アジのサイズ別・推奨針サイズの目安
| アジのサイズ区分 | 体長の目安 | 推奨フックサイズ(#) | 推奨フックサイズ(アルファベット) |
|---|---|---|---|
| 極豆アジ | ~10cm | #14~#16 | SS(極小) |
| 豆アジ | 10~15cm | #12~#14 | SS |
| 小アジ | 15~20cm | #10~#12 | S |
| 中アジ | 20~25cm | #8~#10 | M |
| 良型アジ | 25~30cm | #6~#8 | M~L |
| 尺アジ以上 | 30cm~ | #4~#6 | L |
この表はあくまで一般的な目安です。実際の釣り場では、アジの活性や捕食しているベイトのサイズによって、ワンサイズ上下させる調整が必要になる場合もあります。
特に注意したいのが、同じフィールドでも季節やタイミングによってアジのサイズが変わるという点です。夏場は豆アジが群れをなしているのに、秋になると良型が増えるといったケースは珍しくありません。そのため、複数のサイズを準備しておくことが釣果アップの鍵となります。
フックの形状も針の大きさと同じくらい重要
針の大きさだけでなく、フックの形状も釣果に大きく影響します。形状の主な要素は以下の4つです。
🔧 フック形状を決める4大要素
- ゲイブ(ゲイプ): 針先の向き(開いているか閉じているか)
- シャンク: 針軸の長さ(ショート/ロング)
- 軸の太さ: 強度と刺さりやすさのバランス
- ワームキーパーの有無: ワームのズレ防止機能
これらの形状要素は、針の大きさ(サイズ)とは別の概念です。例えば同じ#8サイズでも、ショートシャンクとロングシャンクでは使用感や適した釣り方が異なります。
形状による違いを理解していないと、たとえ正しいサイズを選んでいても思うような釣果が得られないことがあります。逆に、形状を使い分けることで、同じフィールド・同じ日でも釣果が劇的に変わるケースも報告されています。
ある釣行記では、フックサイズを変えることで釣果が激変した事例が紹介されていました。
この日はボートアジングでの釣行。(中略)漁港ヘッドクロスS2gで釣っていたところ、隣の友人が40cm近いアジを水面でバラシ。そこで漁港ヘッドクロスSではフック強度が足りないかもと、漁港ヘッドギガにチェンジ。するとアタリはあってもそれまで掛けていた20cm前後のアジがアタっても乗りにかったため、ここでスライドヘッド3g(約8番フック)にチェンジ。
この事例からわかるのは、状況に応じてフックサイズと形状を変えることの重要性です。大物を狙って太軸に変えたら中型が掛からなくなり、再びサイズを調整して対応した、という実践的な話です。
初心者の方は、まず基本となる「オープンゲイブ×ショートシャンク」のジグヘッドを軸にして、状況に応じて他の形状を試していくアプローチがおすすめです。
ゲイブの違いが吸い込みやすさに影響する
**ゲイブ(ゲイプ)**とは、針先の向きを表す用語です。主に「オープンゲイブ」と「クローズゲイブ(ストレートゲイブ)」の2種類に分類されます。
📐 ゲイブの種類と特徴比較
| タイプ | 針先の向き | メリット | デメリット | 推奨される使用場面 |
|---|---|---|---|---|
| オープンゲイブ | 外側に開いている | ・初期掛かりが早い<br>・吐き出されにくい<br>・初心者でもフッキングしやすい | ・バイトを弾くことがある<br>・フッキング時のパワーロスがある | 低活性時、初心者、リフト&フォール |
| クローズゲイブ(ストレート) | 軸と平行または閉じている | ・バイトを弾きにくい<br>・パワーロスが少ない<br>・上アゴを狙いやすい | ・初期掛かりが遅い<br>・吐き出されやすい<br>・即アワセが必要 | 高活性時、上級者、タダ巻き |
オープンゲイブは、針先が外を向いているため、アジが吸い込んだ瞬間に口の中のどこかに引っかかりやすい特徴があります。半自動的にフッキングが決まることも多く、アタリの感知に慣れていない初心者にとっては非常に心強い味方です。
一方、クローズゲイブは針先が立っていないため、アジが吸い込みやすいのが最大の特徴です。しかし吸い込みやすいということは吐き出しやすいのと同義なので、アタリを感じたら素早くアワセを入れる技術が求められます。どちらかと言えば玄人向けの形状と言えるでしょう。
ゲイブの選択は、釣り方や自分のスキルレベルに合わせて行うのが基本です。初心者の方や、アタリはあるのに掛からないという状況では、オープンゲイブを選ぶことをおすすめします。逆に、アジの活性が高くてバイトが明確な場合は、クローズゲイブでより確実なフッキングを狙うのも有効です。
ただし、フックサイズが適切でない場合、オープンゲイブでもクローズゲイブでも釣果は変わりません。ゲイブの違いを活かすためには、まず針の大きさが適切であることが前提条件となります。
シャンクの長さで使い分けが必要
シャンクとは針軸の長さのことで、「ショートシャンク」と「ロングシャンク」に大別されます。この違いは見た目以上に釣果に影響する要素です。
ショートシャンクは針軸が短いため、ワームの可動域が広く、よりアクティブに動きます。これによりアピール力が高まり、特にリフト&フォールなどのアクションを付ける釣り方で効果を発揮します。小さなワームでも存在感を出せるのが強みです。
一方、ロングシャンクは針軸が長いため、ワームの尻尾から針先までの距離が短くなります。これにより、アジが後方から吸い込んできた場合でも針先が口に入りやすく、フッキング率が向上します。特にタダ巻き(リトリーブ)の釣りで有利になります。
専門的な記事では、釣り方に応じたシャンク長の使い分けが詳しく解説されています。
リフト&フォールの釣りだと食わせの間のフォールの時に、アジが下や左右などからヘッド部に捕食してくる場合が多い。となると、シャンクの長さが短いショートシャンクのジグヘッドを選択した方が、ロングシャンク使用時よりもフッキング率が高くなります。
リトリーブの釣りの場合だと、アジが後ろから捕食してくる場合が多い。よってショートシャンクを使用していると、フックが口の部分まで吸い込まれなかったり、口の浅い部分に掛かってしまう場合が多くなる。
この説明は非常に理にかなっています。アジがどの方向から捕食してくるかという視点で考えると、シャンク長の選択理由が明確になります。
📌 シャンク長の選び方の基本指針
- ショートシャンク推奨: リフト&フォール、ジャーク、ドリフトなど、縦の動きや不規則な動きをさせる釣り方
- ロングシャンク推奨: タダ巻き、スローリトリーブなど、横方向に一定速度で引く釣り方
ただし、これはあくまで基本的な考え方です。実際の釣り場では、使用するワームのサイズや形状、アジの活性などを総合的に判断して選択する必要があります。迷った場合は、まずショートシャンクから試してみるのが無難でしょう。ショートシャンクは汎用性が高く、様々な釣り方に対応できます。
アジング針の大きさを状況に応じて最適化する実践テクニック
ここからは、より実践的な針の大きさ選びのテクニックを解説していきます。
- 豆アジ(15cm以下)には#12~#14の極小針が最適
- 中アジ(15~25cm)には#8~#10が汎用性が高い
- 尺アジ以上(30cm超)には#4~#6の大型針を選ぶ
- リフト&フォールではショートシャンクを選ぶべき
- タダ巻きではロングシャンクが有利になる
- 活性が低い時は針を小さくするのが鉄則
- まとめ:アジング針の大きさは状況に応じた使い分けが重要
豆アジ(15cm以下)には#12~#14の極小針が最適
豆アジ釣りは、アジングの中でも特に繊細な針選びが求められる分野です。体長15cm以下の豆アジは口が非常に小さく、通常サイズの針では物理的に口に入らないケースが多発します。
豆アジ専用の針として、市場には**#12~#16の極小フック**を搭載したジグヘッドが販売されています。これらは豆アジの小さな口でも吸い込みやすいように設計されており、バイトからフッキングまでの成功率が格段に上がります。
🎣 豆アジ用フックの選択ポイント
- ✅ フックサイズは#12~#14が基本(#16は超極小)
- ✅ ゲイブはオープンでもクローズでもOK(吸い込みやすさ優先)
- ✅ シャンクはショートが基本(小さいワームとのバランス)
- ✅ 細軸タイプを選ぶ(刺さりやすさ重視)
- ✅ ワームは1.5インチ以下の極小サイズと組み合わせる
豆アジ釣りで多くのアングラーが経験するのが、「アタリはあるのに全く掛からない」という状況です。これは針が大きすぎることが原因であるケースが大半です。試しに針を#10から#12に変更するだけで、急にヒット率が上がることも珍しくありません。
実際の製品例としては、ジャッカルの「アジマメマイクロジグヘッド」やダイワの「月下美人SWライトジグヘッドSS極み」(#12)などが豆アジ用として高い評価を得ています。これらは極小フックでありながら、一定の強度も確保されているため、20cm前後のアジまで対応できる汎用性も持ち合わせています。
ただし、豆アジ用の極小針には注意点もあります。針が小さい分、フッキングポイントが浅くなりがちで、ファイト中のバラシが増える傾向があります。また、予想外の大型がヒットした場合、針が伸びるリスクも高まります。ドラグ設定を適切にして、無理な引きを避けることが重要です。
中アジ(15~25cm)には#8~#10が汎用性が高い
アジングで最も対象となることが多いのが、15~25cm程度の中型サイズです。このサイズ帯には#8~#10の針が最も汎用性が高く、多くのアングラーが基本として使用しています。
中アジ用の針選びでは、単にサイズだけでなく、バランスの良さが重要になります。小さすぎず大きすぎず、フッキング率と強度の両立を図れるのがこのサイズ帯です。
📊 中アジ用フックサイズの詳細比較
| フックサイズ | 対応アジサイズ | 推奨ワームサイズ | フッキング性能 | 強度 | 汎用性 |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 15~22cm | 1.5~2.0インチ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| #8 | 18~28cm | 2.0~2.5インチ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| #6 | 22~30cm以上 | 2.5~3.0インチ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
#8が「最強の汎用サイズ」と言われる理由は、そのバランスの良さにあります。20cm前後の中アジを確実に掛けられる十分なサイズがありながら、意外と豆アジ(15cm程度)にも対応でき、さらに尺近い良型がヒットしても針が伸びにくい強度を持っています。
複数の情報源で、中アジ用として#8が推奨されています。例えば、土肥富の「レンジクロスヘッド」はM(#4)サイズで18~30cmのアジに対応するとされ、「フロードライブヘッド」はS(#6)サイズで15~20cmに対応するとされています。これらの情報を総合すると、#6~#8が中アジの核心サイズと言えるでしょう。
中アジ用の針を選ぶ際のもう一つのポイントは、フィールドのアベレージサイズを見極めることです。同じ「中アジ」と言っても、フィールドによって18cm前後が主体の場所もあれば、23cm前後が平均の場所もあります。何度か通って平均サイズを把握したら、それに合わせて針をチューニングしていくと釣果が安定します。
初心者の方がとりあえず1サイズだけ選ぶなら、#8のショートシャンク・オープンゲイブを軸にすることをおすすめします。このスペックならば、豆アジから良型まで幅広くカバーでき、様々な釣り方にも対応できます。
尺アジ以上(30cm超)には#4~#6の大型針を選ぶ
尺アジ(30cm)以上の大型アジを狙う場合は、針のサイズアップが必須です。#4~#6の大型フックを選択することで、大物とのファイトでも安心感が得られます。
尺アジ以上を狙う状況は、一般的な漁港でのアジングとは異なるアプローチが必要です。離島遠征、潮通しの良い一級ポイント、ボートアジングなど、尺クラスが高確率で釣れるフィールドが対象となります。
🏆 尺アジ以上を狙う際の針選びのポイント
- ✅ フックサイズは#4~#6(通常より2サイズ程度大きく)
- ✅ 太軸タイプを選択(強度優先)
- ✅ ゲイブはオープンが基本(大きな口でも確実にフッキング)
- ✅ シャンクの長さは使用するワームサイズに合わせる
- ✅ 3インチ前後の大きめワームとの組み合わせも視野
大型針を使用する最大の理由は強度の確保です。尺アジともなると引きが強く、細軸の小さな針では伸びたり折れたりするリスクが高まります。特に、根に潜られないように強引にファイトする必要がある状況では、太軸の大型針が不可欠です。
ただし、大型針にもデメリットがあります。針が大きい分、刺さる時の抵抗が増えるため、軽いフッキング動作では貫通しにくくなります。また、中型以下のアジには明らかに大きすぎるため、バイトを弾いてしまう可能性も高まります。
大型針の選択は、ターゲットを絞り込んでいる場合に限るというのが基本的な考え方です。「もしかしたら尺が釣れるかも」という程度の期待であれば、#8程度で十分対応できます。本気で尺以上だけを狙う、数よりサイズという明確な目的がある場合にのみ、大型針にシフトするのが賢明でしょう。
製品例としては、土肥富の「レンジクロスヘッドギガ」や「ラッシュヘッドLサイズ」(#2)などが、尺アジ・ギガアジ対応として市販されています。これらは#2~#4の大型フックに太軸を採用し、テラアジクラス(40cm超)にも対応できる設計となっています。
リフト&フォールではショートシャンクを選ぶべき
リフト&フォールは、アジングで最も基本的かつ効果的な釣り方の一つです。この釣法では、ショートシャンクのジグヘッドが圧倒的に有利になります。
リフト&フォールとは、ロッドをシャクってジグヘッドを上昇させ(リフト)、その後テンションを緩めて自然に沈ませる(フォール)を繰り返す釣り方です。アジは特にフォール中のルアーに反応しやすく、多くのバイトがこのタイミングで発生します。
ショートシャンクが有利な理由は、アジの捕食行動の特性にあります。フォール中のルアーは、アジから見て上方または横方向に位置しています。アジはこれを下から、あるいは横から吸い込もうとします。この時、シャンクが短ければ針全体が口に入りやすく、フッキング率が向上するのです。
別の角度から見ると、ショートシャンクはワームの動きを妨げないという利点もあります。針軸が短い分、ワームの可動域が広くなり、フォール中に微妙に揺れたり、イレギュラーな動きをしたりします。この動きがアジの捕食スイッチを刺激し、バイトを誘発します。
リフト&フォールに適したジグヘッドの選び方をまとめると、以下のようになります。
🎯 リフト&フォール用ジグヘッドの理想スペック
- シャンク: ショート(必須)
- ゲイブ: オープン(推奨)
- フックサイズ: 狙うアジのサイズに合わせて#8~#10を基本とする
- ヘッド形状: 丸型またはラウンド型(フォールスピードが安定)
- 重さ: 水深や潮の流れに応じて0.5~2.0g程度
オープンゲイブを推奨する理由は、フォール中のバイトは瞬間的であり、アジが針を深く吸い込む前に吐き出すケースが多いためです。オープンゲイブであれば、口の中のどこかに引っかかりやすく、浅い吸い込みでもフッキングが決まりやすくなります。
実際の製品で言えば、34の「ストリームヘッド」や土肥富の「レンジクロスヘッド」、ダイワの「アジスタ」などは、いずれもショートシャンク・オープンゲイブの設計で、リフト&フォールに最適化されたジグヘッドとして高い評価を得ています。
タダ巻きではロングシャンクが有利になる
タダ巻き(リトリーブ)でアジを狙う場合は、リフト&フォールとは逆にロングシャンクのジグヘッドが有利になります。
タダ巻きとは、キャスト後に一定の速度でリールを巻き続ける釣り方です。ルアーが水平方向に進み続けるため、アジは後方から追いかけてワームを吸い込むという捕食パターンになります。
ロングシャンクが有利な理由は明確です。アジが後ろから吸い込んでくる場合、ワームの尻尾から針先までの距離が短いほど、針が口に入りやすいのです。ショートシャンクだと、アジがワームの後端部分だけを咥えてしまい、針まで到達しないケースが増えてしまいます。
また、タダ巻きではゲイブはストレート(クローズ)が推奨されます。オープンゲイブだと、浅い吸い込みの段階で針先が口に触れてしまい、アジが違和感を感じて吐き出すタイミングが早まる可能性があるためです。ストレートゲイブなら、針先が口に触れるまでの時間が稼げ、追い食いを誘いやすくなります。
📋 タダ巻き用ジグヘッドの選び方チェックリスト
| 項目 | 推奨スペック | 理由 |
|---|---|---|
| シャンク | ロング | 後方からの吸い込みに対応 |
| ゲイブ | ストレート/クローズ | 追い食いを誘いやすい |
| フックサイズ | #6~#8 | やや大きめが安定 |
| ヘッド形状 | 弾丸型や矢じり型 | 水切りが良く巻きやすい |
| 軸の太さ | やや太め | 巻き抵抗に耐える強度 |
タダ巻き専用のジグヘッドとしては、土肥富の「ラッシュヘッド」シリーズが代表的です。これはロングシャンク・ストレートゲイブの設計で、弾丸型のヘッドが特徴です。飛距離も出やすく、一定層をキープしやすい設計となっています。
ただし、タダ巻きはアジの活性が高い時に特に有効な釣り方です。低活性時にはリフト&フォールの方が反応が良いことが多いため、状況に応じて使い分けることが重要です。朝夕のマズメ時や、ベイトフィッシュを追い回している高活性なアジには、タダ巻き×ロングシャンクの組み合わせが威力を発揮するでしょう。
活性が低い時は針を小さくするのが鉄則
アジの活性が低い時、つまり吸い込む力が弱い状況では、針のサイズダウンが釣果アップの鍵となります。これはアジングの重要なセオリーの一つです。
活性が低いアジは、エサやルアーに対して積極的にアタックしてきません。バイトがあっても口を大きく開けず、吸い込む力も弱いため、通常サイズの針では物理的に口に入りきらないのです。
複数の情報源で、活性とフックサイズの関係が言及されています。
20cm以上のアジでも、アミパターンや産卵期などで吸い込みが弱い、低水温期や酸欠など諸々の事情で活性が低い場合は、レンジクロスヘッドよりもフロードライブヘッド(小さめフック)の方が、フッキング率が良くなる場合があります。
この指摘は実践的です。20cm以上の中型アジであっても、状況次第では小さめの針にサイズダウンすることで劇的にフッキング率が改善することがあるのです。
⚠️ 活性が低いと判断できるサイン
- ✓ アタリはあるが小さく、コツコツという感触のみ
- ✓ バイトがあっても針掛かりしない「空振り」が続く
- ✓ ワームが噛まれた跡はあるが、フッキングに至らない
- ✓ 目視でアジは確認できるが、ルアーへの反応が鈍い
- ✓ 潮が動いていない、または極端に水温が低い
このようなサインが見られた場合、ワンサイズ~ツーサイズ小さい針に変更してみることをおすすめします。例えば、普段#8を使っている方なら#10に、#10を使っている方なら#12に変更してみるのです。
サイズダウンの効果は、単に口に入りやすくなるだけではありません。針が小さくなることでルアー全体の存在感も控えめになり、警戒心の強い低活性のアジにも違和感を与えにくくなります。また、細軸の小さな針は刺さり込みの抵抗が少ないため、弱い吸い込みでもフッキングしやすいというメリットもあります。
ただし、サイズダウンには限度があります。あまりに小さくしすぎると、フッキングポイントが浅くなりバラシが増えたり、針の強度不足で伸びたりするリスクも高まります。#12より小さいサイズは豆アジ専用と考え、通常のアジングでは#8~#12の範囲で調整するのが現実的でしょう。
まとめ:アジング針の大きさは状況に応じた使い分けが重要
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジング針のサイズ表記は「#数字」が基本で、数字が大きいほど針は小さくなる
- メーカーによっては「SS/S/M/L」のアルファベット表記もあるが、規格は統一されていない
- 狙うアジのサイズに合わせた針選びが釣果を大きく左右する最重要ポイント
- 豆アジ(15cm以下)には#12~#14の極小フックが必須
- 中アジ(15~25cm)には#8~#10が汎用性が高く、初心者にもおすすめ
- 尺アジ以上(30cm超)を本格的に狙うなら#4~#6の大型針と太軸が必要
- 針の大きさだけでなく、ゲイブ(針先の向き)とシャンク(針軸の長さ)も重要な選択要素
- オープンゲイブは初期掛かりが早く初心者向き、クローズゲイブは上級者向き
- ショートシャンクはリフト&フォールに最適で、ワームの動きが良くなる
- ロングシャンクはタダ巻きに有利で、後方からの吸い込みに対応しやすい
- アジの活性が低い時は、通常より1~2サイズ小さい針にダウンするのがセオリー
- 同じフィールドでも季節やタイミングで最適な針サイズは変わるため、複数サイズの準備が推奨される
- 細軸は刺さりやすいが強度が低く、太軸は強度があるが刺さりにくいというトレードオフがある
- 初心者はまず「#8のショートシャンク・オープンゲイブ」を軸にすると失敗が少ない
- 「アタリはあるのに掛からない」という状況では、針のサイズミスマッチを疑うべき
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- アジングで使うジグヘッドなんですけど、大きさはどのぐらいのを使ってますか – Yahoo!知恵袋
- 針屋が教えるアジングジグヘッドの選び方のコツとおすすめ3選!|あおむしの釣行記4
- 釣果アップの秘策!アジングジグヘッドのフック形状の違いと使い分け方を解説!- しゅみんぐライフ
- アジのサイズ毎に考えるジグヘッドの選び方 汎用性の高さは豆アジ用が一番? | TSURINEWS
- 釣果を左右するアジングのフック選び!4つのポイントとおすすめの使い分けを解説。 | AjingFreak
- 店長日記35…フックサイズって重要? | レベロクSHOP「Junkfish」
- 【アジング】ジグヘッドが飛ばない?なら月下美人アジングジグヘッドTGがおすすめ!|おだやかなる釣りの時間
- アジング ジグヘッド作成 東京湾バチコン用│飛び釣り
- アジングの話 その壱 フックサイズ | マイペースにのんびりフィッシング
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。