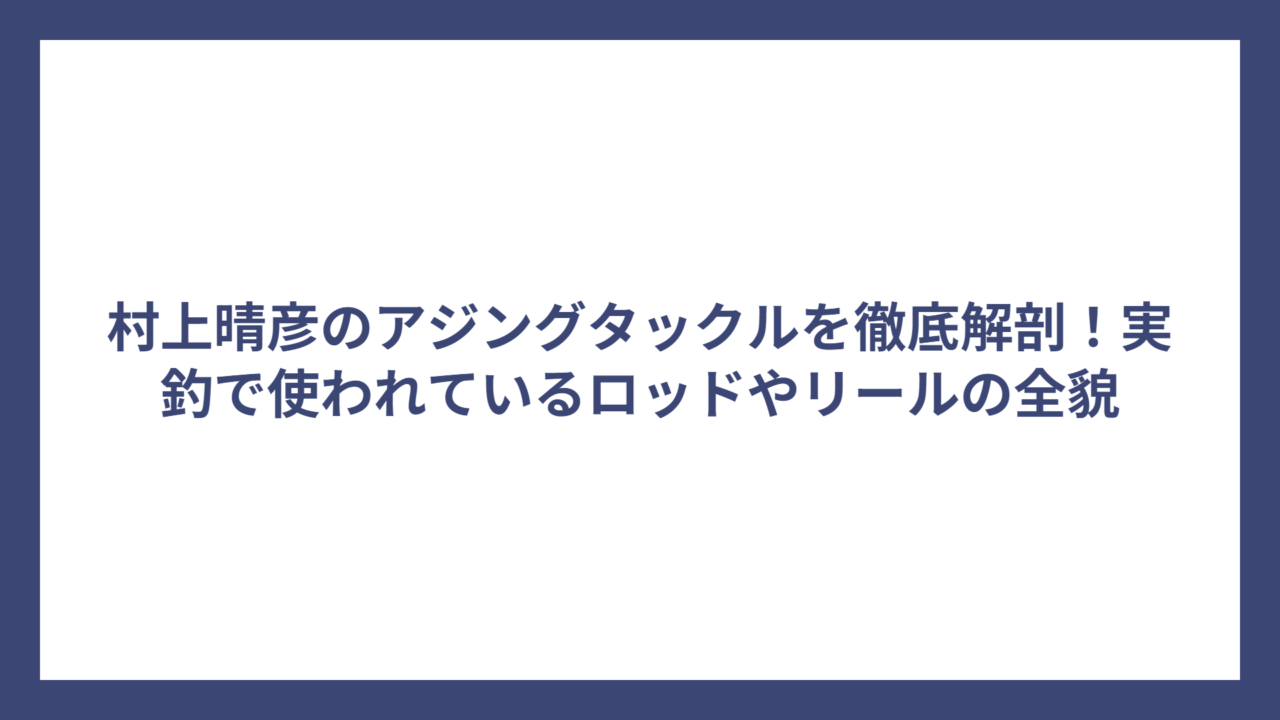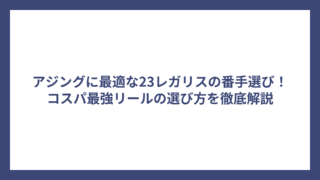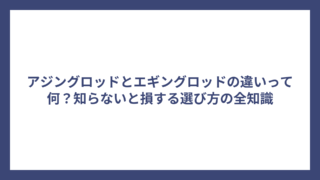「村上晴彦さんってどんなタックルでアジングしてるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。バス釣りで「ネコリグ」や「常吉リグ」を生み出した天才肌アングラーとして知られる村上晴彦氏は、ソルトの世界でもその卓越したセンスを発揮しています。特にアジングにおいては、自身がプロデュースする「一誠・海太郎」ブランドから数々のアイテムをリリースし、独自のスタイルを確立してきました。本記事では、インターネット上に散らばる村上晴彦氏のアジング釣行情報や動画、製品情報などを丁寧に収集し、実際に使用されているタックルセッティングから釣り方のコツまで、徹底的に解説していきます。
村上晴彦氏のアジングタックルは、ライトゲームの汎用性を最大限に活かした実戦的なセッティングが特徴です。ジグ単からバチコン、ボートアジングまで、シチュエーションに応じて使い分けるロッドの選択、極細PEラインの活用による高感度セッティング、そして自ら開発した仕掛けやワームの使いこなしなど、アジングを本気で楽しむための工夫が随所に見られます。本記事では、参考キーワードとして挙げられている村上晴彦氏のリールやロッド、PEラインの選択、さらにはバス釣りで培われた技術がソルトにどう活かされているかといった観点も交えながら、多角的に情報をお届けしていきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 村上晴彦氏が実釣で使用しているアジング用ロッド・リール・ラインの詳細セッティング |
| ✓ ジグ単・バチコン・ボートアジングなどシチュエーション別のタックル選択基準 |
| ✓ 海太郎ブランドの代表的なアジング製品とその特徴・使い分け方法 |
| ✓ 村上晴彦流のアジング釣法と独自に開発された仕掛けやワームの活用術 |
村上晴彦のアジングタックル基本セッティング
- 村上晴彦のアジングタックルは「碧」シリーズを軸にした高感度セッティング
- ジグ単スタイルでは極細PEラインを活用した遠投性と感度の両立がキモ
- リールはイグジストやルビアスエアリティなど軽量高感度モデルを選択
- ワームは自社開発のスパテラとバルキースパテラを状況に応じて使い分け
- ジグヘッドはレベリングヘッドを中心に0.3g〜1.8gをローテーション
- バチコンでは専用仕掛けとヌケガケロケットシンカーのセットが基本
村上晴彦のアジングタックルは「海太郎 碧」シリーズが中核を担っている
村上晴彦氏のアジングタックルを語る上で欠かせないのが、自身がプロデュースする「海太郎」ブランドの「碧(あおい)」シリーズです。調査した情報によると、村上氏が最も頻繁に使用しているのが**海太郎「碧」IUS-72ULS-HN2「ハネエビ」**というモデルで、これは全長7.2フィート(約2.2m)のスピニングロッドとなっています。
このロッドの特徴は、ライトゲーム全般に対応できる汎用性の高さにあります。一般的にアジング用ロッドはジグ単用とキャロ用に大別されることが多いのですが、村上氏が開発した「碧」シリーズは、その中間的な性能を持ち合わせているといえるでしょう。ULS(ウルトラライトソリッド)というティップ仕様により、繊細なアタリを感じ取れる感度と、魚を掛けた後のバラシを防ぐしなやかさを両立しています。
「ハネエビ」という愛称は、村上氏が開発したジグヘッド「ハネエビヘッド」との組み合わせを想定して命名されたものと推測されます。このロッドについて、村上晴彦の小アジング釣行に密着!現場に持ち込んだ小アジの数釣り用!一誠・海太郎のNEWアイテムを一挙紹介という記事では以下のように紹介されています。
ハネエビゲームで使っていたロッドはライトゲームSWロッドの「碧(あおい)」IUS-70ULS-HNのブラッシュアップ版「碧ライトゲームIUS-72ULS-HN「ハネエビ」」でした! ベンドカーブをさらに美しくし、キャスティング、アクション性、魚とのやり取り等、全てにおいて性能を向上さてあるそうな。 旧モデルよりレングスが2インチ伸びて、より大きなアドバンテージを得たロッドに仕上がっているとのこと。
出典:LureNewsR
この引用から分かるように、村上氏は常にロッドの性能向上を追求し、実釣での使用感をフィードバックしながらモデルチェンジを行っているようです。7フィート超のレングスは、堤防や漁港からのキャスティングにおいて飛距離を稼ぎやすく、かつ取り回しもそれほど悪くないという絶妙なバランスといえます。
また、ボートアジングやバチコンといったオフショアでの釣りには、**海太郎「碧」IUC-70LS/LG-Offshore2(ベイトモデル)やIUS-70LS/LG-Offshore2(スピニングモデル)**を使用しているケースも確認できました。こちらは7フィートのセンターカット2ピースで、持ち運びの利便性も考慮されています。オフショア用モデルは10〜60gまでのルアーウエイトに対応し、SLJ(スーパーライトジギング)やイカメタルなど、アジング以外のライトゲーム全般に使える汎用性を持っているのが特徴です。
さらに遠投性を重視する場合には、海太郎「碧」IUS-78L ライトゲーム・遠投という7.8フィート(約2.4m)のモデルも使用されています。このロッドは20g前後のメタルジグやサカナサカナスピンといった重めのルアーにも対応し、大型のアジを沖の深場から狙う際に威力を発揮すると考えられます。村上氏のロッド選択を見ると、常に「その釣り場で最も効率よくアジにアプローチできる道具は何か」という実戦的な視点が貫かれていることが分かります。
ジグ単スタイルでは極細PEライン0.15〜0.2号の高感度セッティングが基本
村上晴彦氏のアジングタックルで特に注目すべきなのが、ラインシステムの選択です。調査した情報によると、ショアからのジグ単スタイルではPE0.2号を基本としつつ、状況によってはPE0.15号やPE0.6号まで使い分けているようです。一般的なアジングでは、エステルラインや細めのフロロカーボンライン(0.8〜1.5lb)を使うアングラーが多い中、村上氏があえてPEラインを選択している理由には明確な戦略があります。
PEラインの最大のメリットは、伸びが少ないため感度が高く、かつ同じ強度であれば圧倒的に細くできるという点です。例えばPE0.2号の強度は約4lb(約1.8kg)ありますが、同等の強度を持つフロロカーボンラインは3〜4lb程度となり、直径はPEラインの方がはるかに細くなります。この細さは風の抵抗を受けにくく、飛距離に直結します。さらに伸びの少なさは、深場でのアタリの感知や、リフト&フォールなどのアクションをダイレクトにルアーへ伝えることを可能にします。
村上晴彦のバチコン・ディープアジング講座という記事では、PEラインの活用について以下のような説明が見られます。
ジグ単タックルでもラインをPEにすることで高強度&高感度になり汎用性が一気に高まり、リグはジグ単だけでもアジ、メバルはもちろん、アイナメや小型回遊魚まで狙える。アジングだけをとってもPEラインのメリットは多数あり、特に水深のあるエリアでは感度と操作性のメリットはかなり大きい。
出典:LureNewsR
この引用から分かるように、村上氏はPEラインの持つポテンシャルを最大限に活用し、単なるアジング専用タックルではなく、様々な魚種に対応できる汎用性の高いセッティングを構築しているといえます。特に水深のある漁港や堤防では、モノフィラ系ラインでは感じ取りにくい微細なアタリもPEラインなら明確に手元に伝わるため、フッキング率の向上にもつながるでしょう。
リーダーについては、フロロカーボン1.5〜3号を使用しているケースが多く確認できました。リーダーの長さは1m前後が基本のようです。フロロカーボンは根ズレに強く、PEラインのデメリットである擦れへの弱さを補完してくれます。また、適度な張りがあるため、ジグヘッドの姿勢を安定させる効果も期待できます。
📊 村上晴彦氏のアジング用ラインシステム比較
| シチュエーション | メインライン | リーダー | 使用ロッド | 特徴・用途 |
|---|---|---|---|---|
| ショアジグ単 | PE0.2号 | フロロ1.5〜3号 | 碧IUS-72ULS-HN2 | 高感度・遠投性重視 |
| 遠投アジング | PE0.6号 | フロロ2.5〜3号 | 碧IUS-78L | 20g前後のメタルジグ対応 |
| ボートアジング | PE0.2〜0.6号 | フロロ1.5〜2.5号 | 碧IUC-70LS | バチコン仕掛けに対応 |
| バチコン | PE0.6〜0.8号 | フロロ2.5号 | 碧IUS-70LS | ディープ攻略・大型狙い |
ただし、PEラインにもデメリットはあります。風の強い日にはラインが煽られやすく、軽量ジグヘッドでのキャストが困難になることがあります。また、根掛かりした際にはリーダーではなくメインラインから切れてしまうリスクもあります。そのため、村上氏も釣り場の状況に応じてエステルラインやフロロカーボンラインを使い分けている可能性は十分に考えられます。
イグジストとルビアスエアリティ―村上晴彦が選ぶリールの条件
村上晴彦氏がアジングで使用しているリールは、主にダイワのイグジストシリーズとルビアスエアリティシリーズです。調査した情報から確認できる具体的なモデルとしては、イグジスト2000、イグジストLT2000S、イグジスト2004、ルビアスエアリティ2500などが挙げられます。
これらのリールに共通するのは、軽量かつ高感度という特性です。イグジストシリーズはダイワのフラッグシップモデルであり、マグネシウム合金を多用した軽量ボディと、精密な巻き心地が特徴です。特にLTコンセプト(Light & Tough)を採用したモデルは、軽さと強度を高次元で両立しています。
リールの番手については、2000番から2500番が中心となっています。アジングでは軽量なジグヘッドを扱うため、あまり大きな番手は必要ありません。2000番クラスであれば、PE0.2号を150〜200m巻くことができ、ショアからのアジングには十分な容量です。また、自重が軽いため、長時間の釣行でも疲労が少ないというメリットがあります。
ギア比については、ハイギアモデル(H)を選択しているケースが多く見られます。ハイギアはハンドル1回転あたりの糸巻き量が多いため、リフト&フォールやダートアクションなどの縦方向の動きを多用する釣りに適しています。また、魚が掛かった後の素早いラインの回収も可能になります。
🎣 村上晴彦氏が使用するリールの特徴
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカー | ダイワ(DAIWA) |
| 主要モデル | イグジスト、ルビアスエアリティ |
| 番手 | 2000〜2500番 |
| ギア比 | ハイギア(H)が中心 |
| 重視する性能 | 軽量性・感度・巻き心地 |
| 適合ライン | PE0.2〜0.8号 |
ボートアジングやバチコンといったオフショアの釣りでは、若干大きめの3000番クラスを使用することもあるようです。これは、より深い水深や重いシンカーを扱う際に、巻き上げパワーが必要になるためと推測されます。また、すごかby九州 53 いま話題のソルトゲームに挑戦だぜぇい!という釣り番組の情報では、ボートアジング時にダイワ キャタリナICという電動リールを使用していたケースも確認できました。バチコンのような深場の釣りでは、電動リールの使用も一つの選択肢となるようです。
リール選びにおいて村上氏が重視しているのは、おそらく「タックル全体のバランス」でしょう。軽量なロッドに重いリールを組み合わせると、キャスト時やアクション時のバランスが悪くなり、疲労も蓄積しやすくなります。碧シリーズのロッドは自重が100〜120g程度と軽量なため、リールも150〜200g程度の軽量モデルを合わせることで、理想的なバランスを実現しているものと考えられます。
スパテラとバルキースパテラ―村上晴彦が開発したアジング用ワームの使い分け
村上晴彦氏のアジングタックルを語る上で、ワームの選択も非常に重要な要素です。調査した情報から、村上氏が最も頻繁に使用しているのが海太郎 スパテラと海太郎 バルキースパテラの2シリーズであることが分かりました。
スパテラは、もともとバス釣り用に開発されたストレート系ワームをアジングサイズにダウンサイジングしたものです。サイズバリエーションとしては1.5インチ、2インチ、2.5インチ、3インチなどがラインナップされており、アジングでは主に2インチと2.5インチが使用されています。
このワームの特徴は、シンプルなストレート形状でありながら、ダートアクションからただ巻きまで幅広いアクションに対応できる汎用性の高さにあります。初心者向け:アジングではこの3種類のワームさえあればいいという記事では、スパテラについて以下のように評価されています。
これのいいところは、アジが好むストレート系で、しかもトータルバランスが良くオールマイティに使える点。ダートのような激しい誘いもこなせるし、ただ巻きでも釣れるユーティリティ性が挙げられます。この特徴から、アジ、メバルだけでなく、ガシラやソイ、小さなハタからカマスまで幅広く攻略が可能です。
出典:note
一方、バルキースパテラは、スパテラよりも太めのボディを持つワームで、2.5インチ、2.8インチ、3インチといったサイズがあります。「バルキー」という名前が示す通り、ボリューム感のあるシルエットが特徴で、アピール力が高いのが強みです。特にバチコンアジングでは、バルキースパテラ2.8インチや3インチが多用されているようです。
📦 村上晴彦愛用ワームの特徴比較
| ワーム名 | サイズ展開 | 形状 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| スパテラ | 1.5〜3in | ストレート | ジグ単全般 | 汎用性が高くダート・ただ巻き対応 |
| バルキースパテラ | 2.5〜3in | 太めストレート | バチコン・大型狙い | ボリューム感でアピール力高 |
| サビキ的 | 2in | ピンテール風 | バチコン仕掛け | サビキを模したデザイン |
| ガメシャッド | 2.5in | シャッドテール | メバル兼用 | テールアクション特化 |
カラーの選択については、村上氏はグロー系とクリア系を基本としているようです。グロー系は夜間や濁り潮で視認性が高く、アジにアピールしやすいとされます。一方、クリア系は昼間やプレッシャーの高い状況で効果的とされています。調査した情報では、クリアレインボー、クリアシルバーフレーク、オレンジグローなどのカラーが頻繁に登場していました。
また、スパテラにはシルキーシャッドという派生モデルもあります。こちらはテール部分が小さなキックテールになっており、水中で微細な波動を発生させます。ただし、前述のnoteの記事では「シルキーシャッドもあるけど、ぶっちゃけスパテラでいい」という評価もあり、初心者がまず揃えるべきはスパテラ本体といえるかもしれません。
ワームの入数については、各パッケージに9本入りが基本のようで、価格は500〜550円(税抜)程度です。集魚材が配合されているモデルもあり、2022年モデルからはバルキースパテラ2.8インチにも集魚材が配合されるようになったという情報も確認できました。
レベリングヘッドとハネエビヘッド―ジグヘッドの使い分けが釣果を左右する
ワームとセットで使用するジグヘッドも、村上晴彦氏が独自に開発したものが中心となっています。最も頻繁に登場するのが海太郎 レベリングヘッドと**海太郎 ハネエビヘッド(マイクロハネエビヘッド)**です。
レベリングヘッドは、その名の通り「レベル(水平)を保つ」ことを目的に設計されたジグヘッドです。ヘッド形状が独特で、フォール中やただ巻き時にワームが水平姿勢を維持しやすくなっています。ウエイトバリエーションは0.3g、0.5g、0.75g、1g、1.5gなど細かく設定されており、状況に応じた使い分けが可能です。
バチコン用としてはレベリングヘッド太軸金鈎0.3g #8が定番のようです。太軸の金鈎は強度が高く、大型のアジが掛かっても曲がりにくいという特徴があります。金鈎は銀鈎よりも錆びにくく、視認性も高いため、水中でのアピール力も期待できます。
一方、**ハネエビヘッド(マイクロハネエビヘッド小鈎)**は、跳ねるようなアクションを生み出すことをコンセプトとしたジグヘッドです。村上晴彦の小アジング釣行の記事によると、新バージョンでは以下のような改良が加えられているようです。
NEWバージョンは以前に増して跳ね度があがったモデルに! 1つが針が少し小針になったこととフックがスズメッキのいわゆる白針と呼ばれるモノになったこと。 もう1つはヘッドのマテリアルが少し高比重化されたこと。 そして上記2つの変更にともなって、全体のバランスを最適化したこと。
出典:LureNewsR
ウエイトは1.3gと1.8gの2種類がラインナップされており、旧モデルの1.25gから微妙に変更されています。この変更により、フォールスピードや跳ね上がりのアクションが最適化されたものと推測されます。価格は1パック2個入りで480円(税抜)となっています。
🎣 村上晴彦愛用ジグヘッドの特徴
| ジグヘッド名 | ウエイト展開 | フック仕様 | 主な用途 | 価格目安 |
|---|---|---|---|---|
| レベリングヘッド | 0.3〜1.5g | 太軸金鈎 | ジグ単・バチコン | 400〜500円 |
| ハネエビヘッド | 1.3g、1.8g | スズメッキ白針 | 跳ねアクション | 480円/2個 |
| アジ弾丸・メバル弾丸 | 0.5〜2g | 各種 | 汎用ジグヘッド | メーカー標準価格 |
ジグヘッドの選択で重要なのは、ウエイトと釣り場の水深・潮の速さのマッチングです。浅い場所や潮の緩い場所では0.5〜1g程度の軽めのジグヘッドを使い、深場や潮の速い場所では1.5〜2g程度の重めを使うのが基本とされています。村上氏の実釣動画などを見ると、状況に応じて頻繁にジグヘッドを交換している様子が確認でき、この使い分けの重要性が伺えます。
バチコン仕掛けとヌケガケロケット―ディープアジング攻略の切り札
村上晴彦氏のアジングタックルの中でも、特に独創的なのがバチコン(バーチカルコンタクト)アジング用の仕掛けとシンカーです。バチコンとは、ボートから垂直にリグを落とし込み、深場の大型アジを狙う釣法のことを指します。
村上氏が開発した海太郎特製バチコン仕掛けには、TYPE 0、TYPE 1、TYPE 2の3種類があります。バチコン・ディープアジング講座という記事から、それぞれの特徴を整理すると以下のようになります。
TYPE 0【喰わせ!一本鈎仕様】
- 35cmのロングリーダーでワームを自然に漂わせる
- 絡みにくいシンプルな一本鈎設計
- 入数は3組で価格は900円(税抜)
TYPE 1【喰わせ!】
- 30〜35cmのロングリーダー
- ボトム周辺と中層を同時に狙える段差仕掛け仕様
- 入数は2組で価格は900円(税抜)
TYPE 2【誘いリアクション!】
- 20〜25cmのショートリーダー
- ロッドワークに応じてトリッキーなアクションを演出
- 喰い渋り時のリアクションバイト狙い
- 入数は2組で価格は900円(税抜)
すべての仕掛けに共通しているのは、リーダーとジグヘッドの結束がフリーノットになっている点です。これにより、ジグヘッドが自由に動き、常にフックポイントが上向きをキープするという工夫が施されています。
🔧 バチコン仕掛けの比較表
| 仕掛けタイプ | リーダー長 | コンセプト | 適した状況 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| TYPE 0 | 35cm | 一本鈎・ナチュラル | スタンダード | 3組 |
| TYPE 1 | 30〜35cm | 段差・喰わせ | 活性高め | 2組 |
| TYPE 2 | 20〜25cm | ショート・リアクション | 喰い渋り | 2組 |
シンカーには海太郎 ヌケガケロケットが推奨されています。このシンカーは、その名の通りロケットのような流線型をしており、水中抵抗が少なく素早く深場に到達できるのが特徴です。ウエイトバリエーションは10号(38g)から40号(150g)まで幅広く展開されており、水深や潮の速さに応じて選択できます。
特徴的なのは、ライン結束部から離れた先端部がグロー塗装されている点です。これは深場でのアピール効果だけでなく、カマスやサゴシといった歯の鋭い魚の攻撃を先端部で受け止め、ラインを守るという狙いもあるようです。
また、村上氏は天秤仕掛けとして**海太郎 村上式天秤「伊勢天秤」**も開発しています。これはシンカーとエダスを分離させることで、根掛かりのリスクを減らしつつ、ワームの自然な動きを演出するための仕掛けです。バチコンアジングをこれから始めたい方は、まずTYPE 0の仕掛けとヌケガケロケット15号程度から始めるのが良いかもしれません。
村上晴彦のアジングタックル応用編とシチュエーション別セッティング
- ボートアジングでは碧IUC-70LSとバチコン仕掛けの組み合わせが定番
- 遠投が必要な場合は78Lロッドと0.6号PEラインで飛距離を稼ぐ
- メバルとの五目釣りにも対応できる汎用性がタックルの強み
- 村上晴彦流アクションはリフト&フォールとツンツンしゃくりが基本
- 小アジ狙いではハネエビヘッドとスパテラ2inの繊細なアプローチ
- 大型狙いではバルキースパテラ3inとレベリングヘッド1g以上で勝負
ボートアジングタックルは碧IUC-70LSベイトモデルが核心的存在
村上晴彦氏のアジングタックルの中でも、特にボートアジングやバチコンといったオフショアの釣りで活躍するのが**海太郎「碧」IUC-70LS/LG-Offshore2(ベイトモデル)**です。このロッドは全長7フィート、自重111gと軽量でありながら、10〜60gまでのルアーウエイトに対応する懐の深さを持っています。
ベイトロッドを選択する理由は、おそらくバチコンアジングにおける垂直方向の操作性にあると考えられます。スピニングタックルと比較して、ベイトタックルは真下に落とし込む動作やバーチカルなジャークアクションがしやすいというメリットがあります。また、太めのラインでも扱いやすく、大型のアジとのファイトでもパワー負けしにくいという特性もあります。
よく釣れるから?理由はそれだけにあらず!村上晴彦が広島までボートアジングに行ったワケという記事では、実際のボートアジング釣行の様子が詳しく紹介されています。
「昔ここの海域のアジを釣って食べたことがあるんやけど、ヤバいヤツやで」 そう、船長の中さんが案内してくれる安芸灘という海域で釣れるアジは、小さくとも丸々している良アジ。 地元では「太豆アジ」なんて呼ばれ方もされている。とても旨いアジなのである。
出典:ISSEI TIMES
この記事から分かるように、村上氏は単に釣りを楽しむだけでなく、釣ったアジを美味しく食べることも重視しています。そのため、良質なアジが釣れる海域を求めて全国を釣り歩いているようです。
ボートアジングでのタックルセッティングを見ると、リールにはダイワ イグジスト2000やダイワ キャタリナIC(電動リール)を使用し、ラインはPE0.2〜0.6号、リーダーはフロロカーボン1.5〜2.5号が基本となっています。仕掛けには前述のバチコン仕掛けTYPE 1やTYPE 2を使い、ワームはバルキースパテラ2.5〜2.8インチ、スパテラ2〜2.5インチ、サビキ的2インチなどをローテーションしているようです。
⚓ ボートアジング用タックルセッティング例
| パーツ | 太豆アジ狙い | 良型アジ狙い |
|---|---|---|
| ロッド | 碧IUS-72ULS-HN2 | 碧IUS-72ULS-HN2 |
| リール | イグジスト2000 | イグジスト2000 |
| ライン | PE0.2号 | PE0.2号 |
| リーダー | フロロ1.5号 | フロロ1.5号 |
| 仕掛け | レンジ移動式バチコン | 自作胴突き仕掛け |
| シンカー | ヌケガケロケット10号 | 浜キャロロケット5号 |
| ワーム | サビキ的、バルキースパテラ | スパテラ1.5in |
村上氏が開発したレンジ移動式バチコン仕掛けは、幹糸から出ている枝バリのレンジを変えられる対応力の高い仕掛けです。アジの活性や泳層に応じて、ワームを提示するレンジを素早く調整できるのが強みといえます。また、記事によると表層にルアーを漂わせてシーバスと思われる魚を狙ったところ、34cmの大型アジがヒットしたというエピソードもあり、アジが表層まで浮いてくることもあるようです。
ボートアジングの大きな魅力は、陸からではアプローチできない深場や潮通しの良いポイントを攻められることです。特に水深20〜40m程度の激流エリアでは、プランクトンが豊富で脂の乗った良型アジが期待できます。村上氏の釣行記事を見ると、そうしたポイントを的確に選び、適切なタックルセッティングで効率よくアジをキャッチしている様子が伺えます。
遠投アジングでは碧IUS-78Lと0.6号PEラインで沖のポイントを攻略
堤防や磯から遠投してアジを狙う場合、村上晴彦氏は海太郎「碧」IUS-78L ライトゲーム・遠投という7.8フィート(約2.4m)のロングロッドを使用しています。このロッドは通常のアジングロッドよりも長く、20g前後のメタルジグやキャロライナリグにも対応できる設計となっています。
遠投が必要になるシチュエーションとしては、以下のようなケースが考えられます。
✅ 遠投が有効な状況
- 足元から急深になっている堤防や磯
- 沖に潮目やナブラが見えている時
- 小型のサバやカマスが岸際で邪魔をする時
- 大型のアジが警戒して沖に居着いている時
アジングタックル1本で何魚種釣れる?三陸エリアのライトソルト五目ゲームという記事では、遠投アジングの有効性について以下のような記述があります。
ちなみに、アジングタックルとメバリングタックルの明確な定義の違いはないが、アジングタックルは高感度で操作性が高く繊細、メバリングタックルはパワーとトルクがありフッキングとキャストがしやすいものが多い。ただし、近年のメバリングタックルはアジング寄りのテイストになっているものも多い。
出典:anglingnet
この記事は村上氏本人の釣行ではありませんが、アジングタックルの汎用性について示唆に富んだ内容となっています。遠投モデルのロッドを用意しておくことで、アジだけでなくサバ、カマス、小型青物など、様々な魚種に対応できるというメリットがあります。
遠投タックルでのラインシステムは、PE0.6号にリーダーフロロ2.5〜3号というやや太めのセッティングが基本のようです。PE0.6号の強度は約12lb(約5.4kg)あるため、不意の大物にも対応できます。また、20g程度のメタルジグをフルキャストしても安心です。
使用するルアーとしては、村上氏が開発したネコメタル20g前後やサカナサカナスピン20〜40gといったメタルジグが中心となります。調査した情報によると、「アジのサイズと捕食しているベイト次第では20g以上の大きめのメタルジグでもアジを狙うことが可能」とのことで、一般的なアジングの常識を覆すアプローチといえるでしょう。
🎯 遠投アジング用タックルの特徴
| 項目 | 仕様・選択基準 |
|---|---|
| ロッド長 | 7.8〜8フィート以上 |
| ルアーウエイト | 5〜30g対応 |
| メインライン | PE0.6〜0.8号 |
| リーダー | フロロ2.5〜3号 |
| 主なルアー | メタルジグ20〜40g |
| 有効な状況 | 沖のナブラ・潮目攻略 |
遠投アジングのアクションは、基本的にはキャストして着底させ、素早く巻き上げるというシンプルなものが多いようです。メタルジグの場合は、リフト&フォールでフラッシング効果を出すのも効果的とされています。ただし、あまり激しいアクションは必要なく、むしろ「まっすぐ泳がせる」ことを意識した方が良いという村上氏のコメントも確認できました。
遠投タックルを1セット用意しておくことで、釣行の幅が大きく広がります。特に秋のハイシーズンには、沖で小型青物やサバの群れが回遊していることも多く、そうした状況ではアジングタックルでも十分に対応可能です。村上氏のように、常に複数のロッドを持ち込み、状況に応じて使い分けるスタイルは、釣果を伸ばす上で非常に合理的といえるでしょう。
メバルとの五目釣りにも対応―タックルの汎用性が釣りの幅を広げる
村上晴彦氏のアジングタックルの大きな特徴の一つが、アジ専用ではなく、メバルや根魚など他魚種にも対応できる汎用性の高さです。調査した情報を見ると、村上氏はアジング用のタックルをそのまま使ってメバルやカサゴ、アイナメなども釣っている様子が確認できます。
特に東北三陸エリアでは、アジとメバルが同じポイントで混在していることが多いようです。アジングタックル1本で何魚種釣れる?三陸エリアのライトソルト五目ゲームという記事では、以下のような記述があります。
初めて牡鹿半島を訪れたが、最初に立ち寄った漁港でさっそく魚影の濃さに驚いた。堤防から1mほど離れたところに黒い魚影がポツポツと見えており、そこにジグヘッドリグを落とすとフォール中にバイトしてくる。
出典:anglingnet
この記事の筆者は村上氏ではありませんが、ライトソルトゲームの汎用性を示す好例といえます。メバルとアジは生息環境が似ており、同じタックルで狙えることが多いのです。
メバルとアジの釣り分けについては、狙うレンジと使用するワームで調整するのが基本のようです。メバルは表層から中層を好むことが多いのに対し、アジはボトム付近にいることが多いとされています。ただし、夜間や朝夕のマズメ時にはアジも表層まで浮いてくることがあるため、一概には言えません。
🐟 アジとメバルの釣り分けポイント
| 項目 | アジ | メバル |
|---|---|---|
| 主なレンジ | ボトム〜中層 | 表層〜中層 |
| 好むアクション | リフト&フォール | ただ巻き・トゥイッチ |
| 適したワーム | ストレート系 | ピンテール・シャッドテール |
| 釣れやすい時間 | 夜間・マズメ | 日中も可 |
| 居場所 | 港内・堤防際 | ストラクチャー周り |
村上氏が使用しているワームは、アジ・メバル兼用で使えるものが多いのも特徴です。スパテラやバルキースパテラはもちろん、ガメシャッドのようなシャッドテール系ワームも使用されています。シャッドテールは水中でテールが震えるため、メバルへのアピール力が高いとされています。
また、根魚狙いの際には、村上氏はキャラメルシャッドやジャコバグといったやや大きめのワームも使用しているようです。カサゴやアイナメは口が大きいため、2.5〜3.5インチ程度のワームでも問題なく食ってきます。ジグヘッドも1.5〜3g程度のやや重めを使うことで、ボトムをしっかり攻めることができます。
ライトソルトゲームの魅力は、1つのタックルで複数の魚種が狙えることにあります。アジだけを狙って釣行したものの、その日はアジの活性が低く、代わりにメバルやカサゴが好調だったということもよくあります。そうした状況でも柔軟に対応できる汎用性の高いタックルを組んでおくことが、釣果を伸ばすコツといえるでしょう。
村上晴彦流アクションの基本はリフト&フォールとツンツンしゃくり
タックルセッティングも重要ですが、それ以上に重要なのが実際の誘い方(アクション)です。村上晴彦氏のアジングにおける基本アクションは、リフト&フォールとツンツンしゃくりの2つに集約されるようです。
リフト&フォールは、ロッドを軽く持ち上げてルアーをリフトさせ、その後テンションフォール(ラインを張ったままの落下)またはフリーフォール(ラインを緩めた自由落下)させるアクションです。このアクションの狙いは、フォール中のバイトを誘発することにあります。アジは落ちてくるものに反応しやすい習性があるため、フォール中にアタリが集中することが多いとされています。
村上晴彦のバチコン・ディープアジング講座の動画では、村上氏が実際にリフト&フォールのアクションを実演しています。その特徴を整理すると以下のようになります。
✅ 村上流リフト&フォールのコツ
- リフトは素早く、フォールはゆっくりと
- フォール中はラインのテンションに注意し、わずかな変化を見逃さない
- ボトムタッチ後は3〜5秒ステイさせてからリフト開始
- リフト幅は30〜50cm程度(水深によって調整)
- 連続で5〜10回リフト&フォールを繰り返す
一方、ツンツンしゃくりは、ロッドティップを細かく動かして、ルアーに小刻みな動きを与えるアクションです。このアクションは主にリアクションバイトを誘うために使われます。アジの活性が低い時や、プレッシャーの高いポイントで特に有効とされています。
調査した情報によると、村上氏は「ツンツンと軽くシャクったあとにフリーフォールさせてリアクションバイトさせる」という方法を多用しているようです。特に日中のメバルやアジは警戒心が高く、ゆっくりしたアクションでは見切られてしまうことが多いため、素早いアクションとフォールの組み合わせが効果的なのでしょう。
🎣 村上流アクションパターン別適用状況
| アクション | 動かし方 | 有効な状況 | 期待できる効果 |
|---|---|---|---|
| リフト&フォール | 50cm持ち上げ→フォール | 活性普通〜高 | フォール中のバイト |
| ツンツンしゃくり | 細かく10回しゃくり | 活性低・日中 | リアクションバイト |
| ただ巻き | 一定速度で巻く | 活性高・夜間 | 追い食いパターン |
| ステイ | ボトムで5秒停止 | スレた状況 | 食わせの間を作る |
また、村上氏の釣り方で特徴的なのが、細かいアクションよりも広く探ることを重視している点です。魚速タックルDBの情報には「投げ続けて釣る(継続的に投げることが最重要)」というコメントが見られ、一箇所で粘るよりも、広範囲をテンポよく探っていくスタイルが基本のようです。
ただし、これはあくまで基本パターンであり、実際の釣り場では状況に応じた臨機応変な対応が求められます。村上氏自身も動画の中で「魚がいればどんなアクションでも釣れる。いないところでいくら工夫してもダメ」という趣旨の発言をしており、まずは魚のいる場所を見つけることが最優先ということでしょう。
小アジ狙いの繊細なアプローチ―ハネエビヘッドとスパテラ2inの組み合わせ
村上晴彦氏のアジングの中でも、特に力を入れているのが小アジングです。小アジとは、おおむね10〜15cm程度のアジを指し、一般的には「豆アジ」とも呼ばれます。なぜ村上氏が小アジングにこだわるのか、その理由は「いろいろ料理して食べたい」という食味へのこだわりにあるようです。
村上晴彦の小アジング釣行の記事では、以下のように紹介されています。
村上さんが小アジのアジングが好きな理由は、いろいろ料理して食べたい!っていうことに加えて、繊細な釣りの面白さ、それから自分が考えたルアーやワームなどを投入してその効果がすぐに確認できるから!!
出典:LureNewsR
小アジ狙いでは、タックルセッティングもより繊細なものになります。ロッドは前述の碧IUS-72ULS-HN2「ハネエビ」、リールはイグジスト2000、ラインはPE0.2号、リーダーはフロロ1.5号といった軽量セッティングが基本です。
ジグヘッドはマイクロハネエビヘッド小鈎1.3gやレベリングヘッド0.5〜0.75gを使用し、ワームはスパテラ2インチやスパテラ1.5インチといった小型サイズを合わせます。小アジは口が小さいため、大きなワームでは吸い込みきれずバラシが多くなってしまいます。
🔬 小アジング専用セッティングの特徴
| パーツ | 仕様 | 選択理由 |
|---|---|---|
| ジグヘッド | 0.5〜1.3g | 小アジの吸い込みやすさ |
| フックサイズ | #10〜#12 | 小さな口に対応 |
| ワームサイズ | 1.5〜2in | 小アジのベイトサイズに合わせる |
| リーダー | 1.5号以下 | 違和感を減らす |
| アクション | ゆっくり・繊細 | 警戒心を刺激しない |
小アジングのアクションは、大型狙いよりもゆっくりと繊細に行うのがコツのようです。小アジは遊泳力が弱いため、あまり激しく動くルアーには反応しにくいとされています。そのため、ゆっくりしたフォールやナチュラルなただ巻きが基本となります。
また、小アジは群れで行動することが多いため、1匹釣れたポイントでは続けて釣れることが期待できます。村上氏の動画を見ると、同じポイントで連続してヒットさせている場面が多く確認できます。小アジングでは「数釣り」が醍醐味の一つであり、効率よく数を伸ばすためには、魚のいる層を素早く見つけることが重要といえるでしょう。
小アジは食味が良く、唐揚げや南蛮漬け、刺身(ゼイゴを取って)など、様々な料理で楽しめます。村上氏のように釣りと食を一体で楽しむスタイルは、アジングの新たな魅力を示しているといえるかもしれません。
大型アジ狙いのタックルセレクト―バルキースパテラ3inと重めジグヘッドの威力
一方、尺アジ(25cm以上)やギガアジ(30cm以上)といった大型アジを狙う場合のタックルセッティングも見ていきましょう。大型アジは小アジとは異なり、パワフルな引きと警戒心の高さが特徴です。
大型アジ狙いでは、ワームサイズをバルキースパテラ2.8〜3インチといったやや大きめにするのが基本のようです。大型のアジは小魚を捕食していることも多く、ある程度ボリュームのあるルアーでないと見向きもしないことがあります。ジグヘッドも1〜2gとやや重めを使い、深場までしっかり沈めることが重要です。
バチコンアジングでは、さらに本格的なタックルが必要になります。調査した情報によると、村上氏はバチコン仕掛けTYPE 1またはTYPE 2にヌケガケロケット15〜25号といった重めのシンカーを組み合わせ、水深30〜50mのディープエリアを攻略しているようです。
大型アジは深場の潮通しの良いポイントに居着いていることが多く、そうした場所では潮の流れも速いため、軽いシンカーでは底が取れないことがあります。また、大型アジは引きが強いため、ドラグ設定やリールのパワーも重要になります。
⚡ 大型アジ狙いのタックル強化ポイント
| 項目 | 小アジ狙い | 大型アジ狙い |
|---|---|---|
| ワームサイズ | 1.5〜2in | 2.8〜3in |
| ジグヘッド | 0.5〜1g | 1〜2g |
| リーダー | 1.5号 | 2.5〜3号 |
| ドラグ設定 | 軽め | やや強め |
| ランディング | 手で掴む | ネット推奨 |
よく釣れるから?理由はそれだけにあらず!という記事では、村上氏が34cmの大型アジをキャッチした際の様子が紹介されています。
表層にはアジもいた!これぞ激流に揉まれた極上のアジ 船長の話では、春ごろは40cmクラスのアジが出ていたという。
出典:ISSEI TIMES
40cmのアジとなると、もはやバス釣り並みのサイズであり、相応のタックルパワーが必要になります。ただし、むやみに太いラインやゴツいタックルを使うと、アジの繊細なアタリが分かりにくくなってしまうため、バランスが重要といえます。
大型アジのいるポイントを見極めるには、地形や潮の流れを読むことが重要です。一般的には、船道の駆け上がりや、瀬と砂地の境目、沈み根周辺などが好ポイントとされています。村上氏の釣行記事を見ると、船長や地元アングラーから情報を得て、効率よくポイントを絞り込んでいる様子が伺えます。
シーズン別・時間帯別のタックルローテーション戦略
アジングは基本的に周年楽しめる釣りですが、シーズンや時間帯によって最適なタックルセッティングは変化します。村上晴彦氏の釣行情報を分析すると、季節や時間帯に応じた戦略が見えてきます。
春(3〜5月)は産卵を控えたアジが接岸し、良型が期待できるシーズンです。この時期のアジは体力をつけるために積極的に捕食しており、比較的釣りやすいとされています。村上氏の釣行記録を見ると、春は2〜2.5インチのワームに1〜1.5gのジグヘッドという標準的なセッティングが多いようです。
夏(6〜8月)は高水温の影響で、日中の活性は下がる傾向にあります。ただし、夜間や朝夕のマズメ時には活発に捕食活動を行います。この時期はPE0.2号の極細ラインに0.5〜1gの軽めジグヘッドで繊細にアプローチするのが効果的かもしれません。
**秋(9〜11月)**はアジングのハイシーズンです。水温が下がり始め、アジの活性が一気に上がります。この時期は群れのサイズも大きく、数釣りが期待できます。村上氏も秋の釣行が多く、様々なタックルを試している様子が確認できます。
冬(12〜2月)は水温低下により、アジは深場へと落ちていきます。この時期はボートアジングやバチコンが有効です。村上氏の冬の釣行記録を見ると、バチコン仕掛けに重めのシンカーという組み合わせが多くなっています。
🗓️ シーズン別アジングタックル戦略
| シーズン | 主な釣り方 | ワームサイズ | ジグヘッド | 狙うレンジ |
|---|---|---|---|---|
| 春 | ショアジグ単 | 2〜2.5in | 1〜1.5g | 中層〜ボトム |
| 夏 | ナイトゲーム | 1.5〜2in | 0.5〜1g | 表層〜中層 |
| 秋 | 数釣り | 2in | 1g | 全レンジ |
| 冬 | バチコン | 2.5〜3in | 専用仕掛け | ディープ |
時間帯による違いも重要です。日中は太陽光が水中に届くため、アジの警戒心が高くなります。そのため、クリア系カラーや小さめのワームが効果的とされています。一方、夜間は視認性の高いグロー系カラーややや大きめのシルエットが有効です。
また、満月の夜は月明かりで海中が明るくなるため、日中に近いアプローチが必要になることもあります。逆に新月の夜は真っ暗になるため、グロー系カラーの効果が最大限に発揮されるでしょう。
村上氏の釣行スタイルを見ると、常に複数のロッドとタックルボックスを持ち込み、状況に応じて柔軟に対応している様子が伺えます。アジングで安定した釣果を上げるには、一つのパターンに固執せず、常に試行錯誤を続ける姿勢が重要といえるでしょう。
まとめ:村上晴彦のアジングタックルから学ぶ実戦的セッティング術
最後に記事のポイントをまとめます。
- 村上晴彦のアジングタックルは海太郎「碧」シリーズを軸に、状況に応じて7〜7.8フィートのロッドを使い分けている
- リールはイグジスト2000番クラスの軽量高感度モデルを基本とし、ボートアジングでは電動リールも活用
- ラインシステムはPE0.15〜0.8号を中心に、極細PEラインの高感度と遠投性を最大限に活かしたセッティング
- ワームは自社開発のスパテラとバルキースパテラを状況に応じて使い分け、サイズは1.5〜3インチを網羅
- ジグヘッドはレベリングヘッドとハネエビヘッドが中心で、0.3〜2gまで細かくローテーション
- バチコンアジングでは専用仕掛けTYPE 0/1/2とヌケガケロケットシンカーの組み合わせが基本
- 基本アクションはリフト&フォールとツンツンしゃくりで、フォール中のバイトを重視
- 小アジ狙いでは1.5〜2インチワームと0.5〜1gジグヘッドの繊細なセッティング
- 大型アジ狙いでは2.8〜3インチワームと1〜2gジグヘッドでディープを攻略
- シーズンや時間帯に応じてタックルをローテーションし、常に最適なアプローチを追求
- メバルや根魚との五目釣りにも対応できる汎用性の高さがタックル選択の特徴
- 遠投が必要な状況では7.8フィートロッドとPE0.6号のセッティングで沖のポイントを攻略
- ボートアジングではベイトタックルの操作性を活かしたバーチカルな釣りを展開
- 釣ったアジの食味にもこだわり、良質なアジが釣れる海域を全国から厳選
- バス釣りで培った技術と発想力をソルトに応用し、独自のアジングスタイルを確立
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 村上晴彦のタックル!使用ロッドやリール,ルアーについて | 魚速タックルDB
- 村上晴彦の小アジング釣行に密着!現場に持ち込んだ小アジの数釣り用!一誠・海太郎のNEWアイテムを一挙紹介 | LureNewsR
- よく釣れるから? 理由はそれだけにあらず! 村上晴彦が広島までボートアジングに行ったワケ | ISSEI TIMES
- 【村上晴彦のバチコン・ディープアジング講座】超初心者でも明日から「バチコン」が始められるゾ! | LureNewsR
- 【村上的】#001 ライトアジング タックル紹介 – YouTube
- アジングタックル1本で何魚種釣れる? 三陸エリアのライトソルト五目ゲーム | anglingnet
- 初心者向け:アジングではこの3種類のワームさえあればいい|突撃部隊モモンガ
- すごかby九州 53 いま話題のソルトゲームに挑戦だぜぇい! | 釣りビジョン
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。