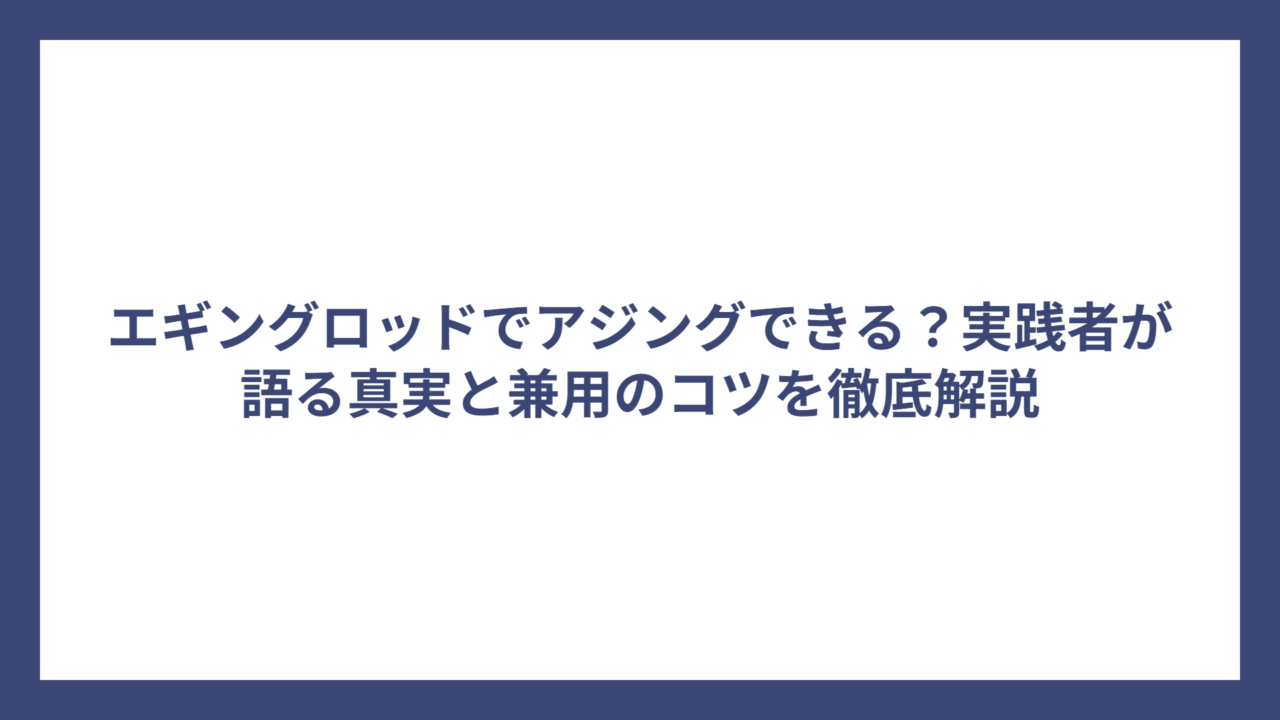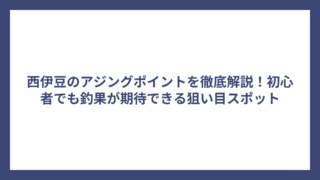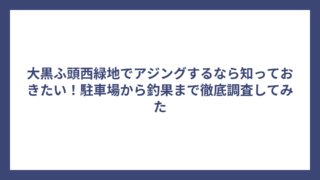「エギングロッドでアジングできないかな?」そう考えたことはありませんか?エギングとアジング、両方楽しみたいけれど専用ロッドを2本も買うのは予算的にきつい。そんな悩みを抱えている釣り人は少なくないでしょう。実は、エギングロッドでもアジングは可能です。ただし、すべてのアジング手法に対応できるわけではなく、いくつかの制約があることを理解しておく必要があります。
この記事では、エギングロッドでアジングを楽しむための具体的な方法、使える仕掛け、注意点、そして兼用に最適なロッドの選び方まで徹底的に解説します。ジグ単が難しい理由、フロートリグが最適な理由、ドラグ設定やラインテンションの調整方法など、実践的なテクニックも網羅。エギングとアジングの兼用を考えている方に必要な情報をすべて詰め込みました。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ エギングロッドでアジングできる条件と制約を理解できる |
| ✓ ジグ単が難しい理由とフロートリグが最適な理由がわかる |
| ✓ エギングとアジング兼用に適したロッドの選び方を習得できる |
| ✓ 実践的な仕掛けの作り方とテクニックを学べる |
エギングロッドでアジングできる条件と制約
- エギングロッドでアジングできるかの答えは「条件付きで可能」
- エギングロッドとアジングロッドの決定的な違いは長さと硬さ
- ジグ単アジングにエギングロッドを使うのは困難
- フロートリグやキャロなら快適に使える
- エギングロッドでアジングをするメリットは遠投性能
- エギングロッドでアジングをするデメリットは感度の低下
エギングロッドでアジングできるかの答えは「条件付きで可能」
エギングロッドでアジングができるかという問いに対する答えは、**「条件付きで可能」**というのが正確な表現です。完全に不可能というわけではありませんが、アジングの醍醐味を最大限に楽しめるかといえば、そうではありません。
インターネット上の実釣情報を見ると、エギングロッドでアジングを実践している釣り人は確かに存在します。しかし、多くの実践者が「快適に楽しめるとは言い難い」「釣果を伸ばす難易度は高い」といった感想を述べています。これは、エギングロッドとアジングロッドの設計思想が根本的に異なることに起因します。
エギングロッドは、2.5号(約10g)から4.0号(約25g)程度のエギを扱うために設計されており、一般的に8~9フィートの長さと硬めのアクションが特徴です。一方、アジングロッドは0.5g~7g程度の軽量ルアーを扱うことを目的とし、6~7フィート程度の長さで非常に高感度なティップを備えています。
この設計の違いにより、エギングロッドでアジングを行う場合、使える仕掛けが限定されるという制約が生じます。具体的には、アジングの主軸となる1g前後のジグ単(ジグヘッド単体)を快適に扱うことは困難で、フロートリグやキャロライナリグなど、ある程度重量のある仕掛けに限定されるのが現実です。
とはいえ、「エギング中の隙間時間にアジングも楽しみたい」「持っているロッドでアジングを体験してみたい」という目的であれば、十分に楽しむことができます。重要なのは、エギングロッドの特性を理解し、それに適した仕掛けと釣り方を選択することです。
条件さえ整えば、エギングロッドでもアジを釣ることは可能ですし、実際に釣果を上げている釣り人も多数います。次の見出し以降で、その具体的な条件と方法を詳しく解説していきます。
エギングロッドとアジングロッドの決定的な違いは長さと硬さ
エギングロッドとアジングロッドの違いを理解することは、エギングロッドでアジングを成功させるための第一歩です。両者の**最も大きな違いは「長さ」と「硬さ」**にあります。
📊 エギングロッドとアジングロッドの比較表
| 特徴 | アジングロッド | エギングロッド |
|---|---|---|
| 主流の長さ | 6フィート前後 | 8フィート6インチ前後 |
| 主流の硬さ | UL、L | ML、M |
| 適応ルアー重量 | 0.5g~7g | 6g~20g |
| 用途 | アジなどの小型魚 | イカ釣り(エギング) |
| 感度 | 非常に高い | 高い |
| 強度 | 低~中程度 | 中~高程度 |
| アクション | ファーストアクション | ミディアム~ファースト |
この表からわかるように、エギングロッドは約2.5フィート(約76cm)も長く、扱えるルアーの重量範囲も大きく異なります。この長さと硬さの違いが、アジングにおける使い勝手に直接影響を与えるのです。
長さの違いによる影響として、エギングロッドは遠投性能に優れる一方で、繊細な操作が求められるアジングでは取り回しに難があります。6フィート台のアジングロッドであれば、手元から穂先までの距離が短く、わずかなロッドワークでもルアーにダイレクトに伝わりますが、8フィート以上のエギングロッドでは、この感覚が鈍くなってしまいます。
硬さの違いも重要です。エギングロッドのML(ミディアムライト)やM(ミディアム)クラスは、アジングロッドのUL(ウルトラライト)やL(ライト)と比べて明らかに硬く、0.5g~1g程度の軽量ジグヘッドでは、ロッドが曲がらず、何をしているかわからない状態になってしまいます。
エギングロッドでのジグ単は、「飛距離が出ない、何やっているか分からない、お手上げ状態」となります。1gになると特に厳しく、風が吹くと無理ゲーです。
この引用からもわかるように、軽量ルアーに対するエギングロッドの反応の鈍さは、実際に使用してみないとわからない部分です。一方で、2g以上のジグヘッドやフロートリグなど、ある程度の重量がある仕掛けであれば、エギングロッドでも十分に操作感を得られます。
また、感度の違いも見逃せません。アジングロッドは「ツッ…」という微細なアタリを捉えるために超高感度に設計されていますが、エギングロッドでは、この繊細なアタリを感じ取ることが難しくなります。結果として、アタリに気づかずにチャンスを逃したり、フッキングが遅れたりする可能性が高まります。
こうした違いを踏まえると、エギングロッドでアジングを楽しむには、ロッドの特性に合わせた仕掛け選びが不可欠であることが理解できるでしょう。
ジグ単アジングにエギングロッドを使うのは困難
アジングの主流であり、最も楽しいとされる釣り方が「ジグ単(ジグヘッド単体)」です。しかし、エギングロッドでジグ単アジングを行うのは極めて困難と言わざるを得ません。
ジグ単とは、ジグヘッドにワームを装着し、それをラインの先に直接結ぶだけのシンプルな仕掛けです。0.5g~2g程度の軽量ジグヘッドを使うことで、アジの微細なアタリを感じ取りやすく、また自然な動きでアジに違和感を与えにくいため、釣果を伸ばしやすいとされています。
しかし、エギングロッドでこの軽量ジグヘッドを扱おうとすると、以下のような問題が生じます。
🚫 エギングロッドでジグ単が困難な理由
- 操作感がわからない:ロッドが硬すぎて、ジグヘッドの重みや動きを感じ取れない
- アタリを取れない:アジの繊細なアタリがロッドに伝わらない
- 飛距離が出ない:軽量ルアーではロッドがしっかり曲がらず、遠投できない
- 風に弱い:1g以下のジグヘッドでは、風が吹くと制御不能になる
- 引きがわからない:アジの引きを感じにくく、「なんか釣れてた」案件が増える
実際の使用例を見てみましょう。
スタンダードなエギングタックルで扱えるのは1.5~2g以上を目安にしてください。1gになると飛距離が出ない、何やっているか分からないお手上げ状態。ちょっとでも風が吹いてしまうと無理ゲーです。
この体験談が示すように、一般的なアジングで使用される0.5~1g程度のジグヘッドは、エギングロッドではほぼ使用不可能です。最低でも1.5~2g以上のジグヘッドが必要となりますが、アジングではジグヘッドが重すぎると釣果が落ちる傾向があります。
なぜジグヘッドが重いと釣果が落ちるのでしょうか?理由は主に2つあります。第一に、重いジグヘッドは沈下速度が速く、アジが捕食しているレンジ(層)を素早く通過してしまうため、アピール時間が短くなります。第二に、重いジグヘッドは吸い込みにくく、アジが違和感を感じやすいため、バイト(食いつき)率が低下します。
また、感度の問題も深刻です。エギングロッドの感度はアジングロッドに比べて劣るため、感知できるアタリの数が減るという現象が起こります。アジングでは、明確な「ゴン!」というアタリもありますが、多くの場合は「コツッ」「モゾッ」といった微細なアタリです。これを逃すと、アワセが決まらず、釣果が大きく落ちてしまいます。
どうしてもエギングロッドでジグ単をやりたい場合は、7フィート台のライトエギング特化タイプのロッドを選び、ジグヘッドの重さを2g前後にする必要があります。硬さもライトエギング系であればULやLクラスになるため、アジングに近い使用感になりますが、それでも専用ロッドには及びません。
現実的には、エギングロッドでアジングを楽しむなら、ジグ単は諦めて他の仕掛けを選択するのが賢明です。
フロートリグやキャロなら快適に使える
エギングロッドでジグ単が困難である一方、フロートリグやキャロライナリグであれば快適にアジングを楽しめます。これらの仕掛けは、ある程度の重量があるため、エギングロッドの特性と相性が良いのです。
📌 フロートリグとは
フロートリグとは、フロート(浮き)を使った遠投用の仕掛けです。フロート自体に重みがあるため、遠くまで飛ばすことができ、なおかつ一定のレンジをキープしやすいという特徴があります。代表的な製品としては、アルカジックジャパンの「シャローフリーク」が有名で、10.5g~16.6g程度の重量があります。
フロートリグのメリットは以下の通りです。
✅ フロートリグのメリット
- 遠投性能が高い:50m以上の飛距離が出せる
- 棚が安定する:フロートが浮いているため、一定の深さを保てる
- 初心者でも釣りやすい:基本的に投げて巻くだけで釣れる
- エギングロッドとの相性抜群:10g前後の重量はエギングロッドで扱いやすい
- 表層のアジに効果的:夜間など、アジが表層にいるときに有効
実際の使用例を見てみましょう。
フロートリグで定番のシャローフリークだとスローシンキングタイプの「ダイブ」で16.6g。通常のアジングロッドが大体5gまで推奨なのでオーバースペックです。つまり遠投系リグを使う時にはエギングロッドの方が有利になるというわけです。
この指摘は非常に重要です。アジングロッドの多くは5g程度までの対応ですが、フロートリグでは10g以上の重量が一般的。そのため、むしろエギングロッドの方が適しているというケースもあるのです。
📌 キャロライナリグとは
キャロライナリグ(通称:キャロ)は、細長い形をした中通し錘を使った仕掛けです。フロートリグと同様に遠投性能が高く、なおかつ軽めのジグヘッドと組み合わせられるという利点があります。
キャロのメリットは以下の通りです。
✅ キャロのメリット
- 遠投しつつ軽いジグヘッドが使える:5g程度のキャロに0.5~1gのジグヘッドを組み合わせられる
- アジの吸い込みが良い:ジグヘッド自体は軽いため、違和感を与えにくい
- フォール中のアタリが多い:キャロを使った場合、沈下中にバイトすることが多い
- エギングロッドで操作感を得られる:キャロ本体の重みでロッドが曲がり、操作感がわかる
キャロを使う場合の釣り方は、ストップ&ゴーが基本です。リールを数回巻いて止める、を繰り返すことで、フォール(沈下)中にアジがバイトします。エギングロッドでも、このメリハリのあるアクションであれば十分に対応可能です。
フロートリグとキャロ、どちらを選ぶべきかは状況次第ですが、表層を攻めたいならフロートリグ、広範囲を探りつつ軽いジグヘッドを使いたいならキャロという使い分けが一般的です。いずれにせよ、エギングロッドでアジングを楽しむなら、これらの仕掛けが最適解と言えるでしょう。
エギングロッドでアジングをするメリットは遠投性能
エギングロッドでアジングを行うことには、いくつかのメリットがあります。最大のメリットは遠投性能の高さです。8フィート以上の長さと適度なパワーを持つエギングロッドは、重めの仕掛けを遠くまで飛ばすのに適しています。
🎯 エギングロッドでアジングをするメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 遠投性能 | 8~9フィートの長さにより、遠心力を活かした遠投が可能 |
| コストパフォーマンス | 1本のロッドでエギングとアジングの両方を楽しめる |
| 広範囲のサーチ | 遠投できることで、広いエリアを効率的に探れる |
| 沖のポイント攻略 | 岸から離れた沖のブレイクラインなどを狙える |
| 荷物の削減 | ロッド1本で済むため、持ち運びが楽 |
特に遠投性能の高さは、アジングにおいて大きなアドバンテージとなります。アジは時として岸から30~50m離れた沖のブレイクライン(水深が急に深くなる場所)に群れていることがあり、通常のアジングロッドでは届かない距離です。
エギングロッドにフロートリグやキャロを組み合わせることで、ショートロッドでは攻められない遠距離のポイントにアプローチできます。これは、釣り場によっては決定的な差になることもあります。
エギングロッドの場合はフロートやキャロリグ、メタルジグを使用して”操作感”優先の釣りで釣果に繋げましょう。ロッドは長いと、遠心力を加えやすくなるため基本遠投有利になりやすくなります。
また、コストパフォーマンスの面でも優れています。エギング専用ロッドとアジング専用ロッドをそれぞれ購入すると、合計で2~6万円程度の出費になりますが、1本で兼用できれば半分のコストで済みます。特に釣りを始めたばかりで、まだ何本もロッドを揃える段階ではない初心者にとって、この点は大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、エギングとアジングは釣れる時期や場所が重なることが多く、1本のロッドで両方楽しめるというのは実用的です。例えば、秋の夕マズメにエギングをして、日が暮れたらアジングに切り替える、といった使い方ができます。
ただし、これらのメリットを享受するには、適切な仕掛けと釣り方を選択することが前提となります。次の見出しで説明するデメリットも理解したうえで、総合的に判断することが重要です。
エギングロッドでアジングをするデメリットは感度の低下
メリットがある一方で、エギングロッドでアジングを行うことには明確なデメリットも存在します。最大のデメリットは感度の低下です。
❌ エギングロッドでアジングをするデメリット
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 感度が低い | アジの微細なアタリを感じ取りにくい |
| 操作感がわかりづらい | 軽量ルアーでは何をしているか不明 |
| 引きを楽しめない | アジの引きが伝わりにくく、醍醐味半減 |
| バラシが増える | 口切れしやすく、ランディング率が低下 |
| ジグ単が使えない | アジング最大の武器を封じられる |
感度の低下は、釣果に直結する重大な問題です。アジングでは、明確な「ゴン!」というアタリもありますが、多くの場合は「コツッ」「モゾッ」といった微細なアタリです。アジングロッドであれば感じ取れるこれらのアタリが、エギングロッドではほとんど感じ取れないという事態が起こります。
エギングロッドでは基本的にジグ単ができないというのも、なかなかキツイ点です。アジングで最強かつ一番おもしろい仕掛け(リグ)は「ジグ単」。ジグ単とは、ジグヘッドにワームをつけ、それをラインの先に結ぶだけのシンプルな仕掛けです。
この指摘が示すように、アジングの醍醐味であるジグ単が使えないというのは、釣りの楽しみを大きく損ないます。ジグ単でのアジングは、微細なアタリを感じ取り、適切なタイミングでアワセを入れ、アジの引きを楽しむという一連の流れが魅力です。エギングロッドでは、この体験が半減してしまいます。
また、バラシ(フッキングした魚が途中で外れること)が増えるのも大きな問題です。アジの口は非常に柔らかく、特に上アゴ以外の部分は針が掛かっても簡単に切れてしまいます。アジングロッドは柔軟性があり、アジの動きに追従してバラシを軽減しますが、硬いエギングロッドではこの追従性が不足します。
エギングロッドでは、アジの動きに竿が追従してバラシを軽減する追従性で劣ります。なので、口ギレなどによるバラシがどうしても多くなってしまいます。
対策として、ドラグを緩めに設定することである程度バラシを減らすことは可能ですが、根本的な解決にはなりません。特に良型のアジ(20cm以上)がヒットした場合、ドラグが緩すぎるとやり取りに時間がかかり、その間にバラシてしまうリスクも高まります。
さらに、操作感のわかりづらさも見逃せません。軽量ルアーを使った場合、「今ルアーがどこにあるのか」「底に着いたのか」「流れに乗っているのか」といった情報が伝わってこないため、手探り状態での釣りになってしまいます。これでは、釣りの面白さが大きく損なわれてしまうでしょう。
これらのデメリットを踏まえると、エギングロッドでアジングを行うのは、あくまで「専用ロッドを買うまでの一時的な対処法」と考えるのが妥当かもしれません。
エギングロッドでアジングできる実践テクニックと注意点
- エギングロッドでアジングできる仕掛けはフロートリグが最適
- 重めのジグヘッド(2g以上)なら対応可能
- ドラグ設定を緩めにしてバラシを防ぐ
- ラインテンションは張りすぎないのがコツ
- エギングとアジングの兼用にはMLクラスが最適
- 兼用リールは2500番台がバランス良好
- まとめ:エギングロッドでアジングできる条件を理解して楽しもう
エギングロッドでアジングできる仕掛けはフロートリグが最適
エギングロッドでアジングを楽しむなら、フロートリグが最適です。フロートリグは、フロート(浮き)を使った遠投用の仕掛けで、エギングロッドの長所を最大限に活かせる釣り方です。
フロートリグの基本的な構造は、PEラインにフロロカーボンリーダーを結び、そのリーダーの余り糸部分にフロートを取り付け、先端に軽量ジグヘッド+ワームを装着するというものです。この仕掛けは「Fシステム」と呼ばれ、アジング界で広く普及しています。
🎣 フロートリグ(Fシステム)の作り方
- PEライン(0.4~0.6号)にフロロカーボンリーダー(2~2.5ポンド)を結ぶ
- リーダーの余り糸(捨て糸)を10~15cm程度長めに残す
- その余り糸にフロート(シャローフリークなど)を取り付ける
- リーダーの先端にジグヘッド(0.5~1.5g)を結ぶ
- ジグヘッドにワームを装着して完成
この仕掛けの優れている点は、セッティングが非常に簡単なことです。複雑な結び方や特別な道具は不要で、初心者でも5分程度で組むことができます。
フロートの選び方も重要です。代表的な製品である「シャローフリーク」には、F(フロート)タイプとD(ダイブ)タイプがあり、Fタイプは浮くタイプ、Dタイプは沈むタイプです。
📊 シャローフリークの選び方
| タイプ | 重量 | 特徴 | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| Fタイプ | 10.5g | 浮くタイプ | 表層狙い、夜釣り |
| Fタイプ | 15g | 浮くタイプ | 遠投重視、風が強い日 |
| Dタイプ | 11.7g | 沈むタイプ | 中層~底層狙い |
| Dタイプ | 16.6g | 沈むタイプ | 深場、潮が速い場所 |
夜のアジングでは表層にアジがいることが多いため、Fタイプの10.5gが最も汎用性が高く、初めての方にはこれがおすすめです。50m以上の飛距離が必要な場合は15gを選ぶと良いでしょう。
フロートリグの釣り方は、以下の3つの基本パターンがあります。
✅ フロートリグの基本的な釣り方
- ただ巻き:一定の速度でリールを巻き続ける。表層のアジに効果的
- ストップ&ゴー:巻いて止める、を繰り返す。フォール中のバイトが多い
- トゥイッチ:巻きながら竿先でチョンチョンとアクションを入れる。食いが渋い時に有効
特にストップ&ゴーは、フロートリグで最も釣果が上がりやすい釣り方です。リールを3~5回転巻いて、2~3秒止める、を繰り返すことで、ワームがフォール(沈下)する際にアジがバイトします。エギングロッドでも、このメリハリのあるアクションは十分に再現できます。
フロートアジングと言えば、Arukazik Japanの藤原真一郎氏考案のFシステムと呼ばれる仕掛けが有名です。フロートには浮力があって浮いているので、棚は一定に保たれます。
実際に初心者がフロートリグでアジングを行った事例では、エギングロッドを使用して短時間で尺アジ(25cm以上)を含む5匹を釣ったという報告もあります。これは、フロートリグが初心者にも優しく、なおかつエギングロッドとの相性が良いことを示しています。
フロートリグは、エギングロッドの遠投性能を活かしつつ、アジングを楽しめる最適な仕掛けと言えるでしょう。
重めのジグヘッド(2g以上)なら対応可能
フロートリグ以外の選択肢として、重めのジグヘッド(2g以上)を使うという方法もあります。エギングロッドの硬さでも操作感を得られる重量にすることで、ジグ単に近い感覚でアジングを楽しむことができます。
通常のアジングでは0.5~1.5g程度のジグヘッドが主流ですが、エギングロッドでは、この重量では操作感がほとんど得られません。そのため、最低でも2g、できれば2.5~3g程度のジグヘッドを使用する必要があります。
📌 エギングロッドで使えるジグヘッドの重さ
| ジグヘッド重量 | エギングロッドでの使用感 |
|---|---|
| 0.5~1g | ×使用不可(操作感ゼロ、飛距離も出ない) |
| 1.5~2g | △やや困難(操作感は薄いが、なんとか使える) |
| 2~3g | ○使用可能(操作感あり、飛距離も出る) |
| 3g以上 | ○快適(操作感良好、ただしアジの食いが悪くなる可能性) |
ただし、重いジグヘッドにはデメリットもあります。最大の問題は、アジの食いが悪くなることです。重いジグヘッドは沈下速度が速く、アジが捕食しているレンジを素早く通過してしまいます。また、吸い込みにくいため、バイト率が低下します。
ジグヘッドを重くしすぎるとアタリが遠のくこともあります。エギングロッドの場合はフロートやキャロリグ、メタルジグを使用して”操作感”優先の釣りで釣果に繋げましょう。
この問題を解決する方法として、**キャロライナリグ(キャロ)**を使うという選択肢があります。キャロは、中通しの錘を使った仕掛けで、錘自体は5g程度あっても、先端のジグヘッドは0.5~1g程度の軽量なものを使えます。
キャロの仕組みは、中通し錘がラインを自由に動くため、アジがバイトした際に錘の重みを感じにくいというものです。これにより、遠投性能と軽量ジグヘッドの両立が可能になります。
🎣 キャロライナリグの利点
- 遠投できる(錘が5g程度あるため)
- 軽いジグヘッドが使える(0.5~1.5g)
- アジの吸い込みが良い(ジグヘッドの重さを感じにくい)
- フォール中のバイトが多い
- エギングロッドでも操作感がある
キャロを使う場合の釣り方は、基本的にストップ&ゴーです。リールを巻いて止める、を繰り返すことで、フォール中にアジがバイトします。エギングロッドでも、キャロの重みでロッドが適度に曲がるため、操作感を得られます。
代表的なキャロ製品としては、ティクトの「Mキャロ」があり、5.3g(Lタイプ)が使いやすいとされています。周りでジグ単でアジが釣れているような状況下であれば、Mキャロに軽いジグヘッドという組み合わせで十分に釣果が期待できます。
重めのジグヘッドやキャロを使うことで、エギングロッドでもジグ単に近い釣りが可能になりますが、やはり専用ロッドには及ばないというのが正直なところです。本格的にジグ単アジングを楽しみたいなら、専用ロッドの購入を検討すべきでしょう。
ドラグ設定を緩めにしてバラシを防ぐ
エギングロッドでアジングを行う際、ドラグ設定を緩めにすることが非常に重要です。これは、硬いエギングロッドの弱点を補い、バラシを減らすための必須テクニックです。
ドラグとは、リールに備わっている機構で、一定以上の負荷がかかるとラインが出ていくようになっています。これにより、魚の強い引きや急な走りに対応し、ラインブレイクや口切れを防ぎます。
アジングロッドは柔軟性があり、アジの動きに追従してショックを吸収しますが、硬いエギングロッドではこの追従性が不足します。そのため、ドラグでショックを吸収する必要があるのです。
🔧 エギングロッドでのドラグ設定の目安
- 通常のアジングロッド:やや強め(フッキングが決まりやすい)
- エギングロッド:やや緩め(口切れを防ぐ)
- 具体的な設定方法:ロッドを45度に曲げて、ゆっくりラインが出るくらい
ドラグが強すぎると、アジの口が切れてバラシてしまいます。特に、良型のアジ(20cm以上)は引きが強く、ドラグが適切でないと簡単にバレてしまいます。一方、ドラグが緩すぎると、フッキングが決まりにくく、またやり取りに時間がかかってバラシのリスクが高まります。
アジングロッドのような吸収力がないので、ドラグは普段より緩めにしておきます。釣り場ではアジのサイズに合わせて”フッキングが決まり・口切れしない”ベストドラグを探してみてください。
ドラグ設定は、釣り場でアジのサイズを見ながら微調整するのがベストです。豆アジ(10cm以下)が多い場所では、やや緩めに設定し、良型が多い場所では、やや強めに設定するといった具合です。
また、ドラグ設定と合わせてやり取りのテクニックも重要です。アジがヒットしたら、無理に引き寄せず、ロッドを立ててゆっくりとリールを巻きます。アジが走ったら、ドラグからラインが出るのに任せ、走りが止まったらまた巻く、という対応が必要です。
エギングロッドでアジングを行う場合、このドラグ設定とやり取りのテクニックを習得することで、バラシを大幅に減らすことができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、数回の釣行で感覚をつかめるでしょう。
ラインテンションは張りすぎないのがコツ
エギングロッドでアジングを成功させるもう一つの重要なテクニックが、ラインテンションを張りすぎないことです。これは、硬いエギングロッドでアタリをはじいてしまうのを防ぐための工夫です。
ラインテンション(糸の張り具合)が強すぎると、アジがワームを吸い込もうとした瞬間に違和感を感じて吐き出してしまいます。また、アジのアタリがロッドに伝わる前に、張ったラインが反発してアタリをはじいてしまうこともあります。
🎯 ラインテンションのコツ
- 基本は軽く張る程度:完全に緩めるのではなく、軽く張った状態をキープ
- アタリがあったポイントでは緩める:アジがいるレンジや場所がわかったら、やや緩めに
- 風が強い日は調整が難しい:ラインが風に煽られるため、やや強めに張る必要がある
- フォール中は緩める:ワームが沈下する際は、ラインテンションを緩めてナチュラルに落とす
ラインテンションの調整は、アジングの中でも高度なテクニックの一つです。アジングロッドであれば、ロッド自体の柔軟性でカバーできる部分が大きいですが、硬いエギングロッドでは、釣り人がラインテンションを意識的にコントロールする必要があります。
固いエギングロッドではアタリをはじいてしまい、なかなかフッキングへ持ち込めません。アジがいるレンジや毎回アタリがある場所を見つけたら、ラインテンションを少し緩めて待ちましょう。ラインを緩めることで、ワームを吸い込みやすい状態になります。
具体的な方法としては、アタリがあったポイントで一度リトリーブ(巻き上げ)を止め、ロッドを少し下げてラインを緩めます。この状態で2~3秒待つと、アジがワームをしっかり吸い込むタイミングが生まれます。その後、ゆっくりとロッドを上げてアワセを入れます。
ただし、ラインテンションを緩めすぎると、今度はアタリがわからなくなるという問題が生じます。完全にラインがたるんでしまうと、アジがバイトしても情報が伝わってきません。そのため、「軽く張った状態」と「やや緩めた状態」の中間を見つけることが重要です。
フロートリグを使う場合は、フロート自体が適度なテンションを保ってくれるため、ラインテンションの管理が比較的楽になります。これも、エギングロッドでアジングを行う際にフロートリグが推奨される理由の一つです。
ラインテンションのコントロールは、経験を積むことで自然に身につくスキルです。最初はうまくいかなくても、何度か釣行を重ねることで、最適なテンションの感覚がつかめるようになるでしょう。
エギングとアジングの兼用にはMLクラスが最適
エギングとアジングの両方を1本のロッドで楽しみたい場合、MLクラス(ミディアムライト)のエギングロッドが最適です。MLクラスは、硬すぎず柔らかすぎず、バランスの取れた特性を持っています。
📊 エギングロッドの硬さ別特徴
| 硬さ | エギング適性 | アジング適性 | 適したエギサイズ | 適したジグヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| L(ライト) | △春イカ向き | ○フロート・キャロOK | 1.8~3.0号 | 1.5g~ |
| ML(ミディアムライト) | ○オールシーズンOK | ○フロート・キャロOK | 2.0~3.5号 | 2g~ |
| M(ミディアム) | ○秋イカ・大型向き | △やや硬い | 2.5~4.0号 | 3g~ |
| MH(ミディアムヘビー) | ○大型・ディープ向き | ×硬すぎる | 3.0~4.5号 | 使用困難 |
MLクラスが兼用に適している理由は、以下の通りです。
✅ MLクラスが兼用に適している理由
- エギングで年間通して使える:2.5号~3.5号のエギに対応し、春・秋どちらもOK
- アジング用フロートリグと相性良好:10~15g程度のフロートを快適に扱える
- 2g以上のジグヘッドにも対応:キャロと組み合わせれば、ジグ単に近い釣りも可能
- バラシが少ない:Mクラスより柔軟性があり、アジの口切れを防ぎやすい
- 価格帯が豊富:エントリーモデルからハイエンドまで選択肢が多い
また、ロッドの長さも重要な要素です。エギングでは8フィート6インチ(約2.6m)が標準的ですが、アジングでの取り回しを考えると、8フィート~8フィート3インチ程度がバランスが良いとされています。
エギングと遠投アジングでの兼用におすすめの機種は「83ML」です。年間を通してエギングを楽しめて、なおかつアジングの遠投リグとも好相性な8.3ft×MLクラス。
具体的な製品としては、以下のようなモデルが兼用に適しています。
🎣 兼用におすすめのエギングロッド(MLクラス)
- ダイワ エメラルダスX 83ML:実売9,000円前後、コスパ良好
- シマノ セフィアBB S83ML:実売13,000円前後、バランス型
- メジャークラフト エギゾースト1G 832ML:実売13,000円前後、高感度
これらのロッドは、いずれも8フィート前後のMLクラスで、エギングでもアジングでも活躍できるスペックを持っています。特に、ダイワのエメラルダスXは、1万円を切る価格ながら「ブレーディングX」というブランク強化技術を採用しており、コストパフォーマンスが非常に高いと評価されています。
ただし、MLクラスのエギングロッドであっても、ジグ単アジングには不向きという点は変わりません。あくまでフロートリグやキャロなど、重量のある仕掛けを使う前提での兼用です。ジグ単をメインに楽しみたい場合は、やはりアジング専用ロッドを購入すべきでしょう。
兼用ロッドを選ぶ際は、自分が主にどちらの釣りをするのかを考え、その比重に応じて選択することが重要です。エギングがメインならM寄りのML、アジングもしっかり楽しみたいならL寄りのML、という具合に微調整すると良いでしょう。
兼用リールは2500番台がバランス良好
エギングとアジングを兼用する場合、ロッドだけでなくリールの選択も重要です。兼用に最適なのは2500番台のスピニングリールです。
エギングでは通常、2500番~3000番のリールが推奨され、アジングでは1000番~2000番が一般的です。この両方をカバーできるのが2500番台というわけです。
📊 番手別リールの特徴
| 番手 | エギング適性 | アジング適性 | ライン容量(PE) | 重量 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000番 | ×小さすぎ | ◎最適 | 0.4号-100m | 約180g | 軽量、感度良好 |
| 2000番 | △やや小さい | ○適している | 0.6号-150m | 約200g | バランス型 |
| 2500番 | ○適している | ○適している | 0.8号-200m | 約220g | 兼用に最適 |
| 3000番 | ◎最適 | △やや大きい | 1.0号-200m | 約250g | パワー重視 |
2500番台が兼用に適している理由は、以下の通りです。
✅ 2500番が兼用に最適な理由
- エギング用ラインが巻ける:PE0.6~0.8号を200m巻ける
- アジング用ラインも対応:PE0.4号も問題なく使用可能
- 重量バランスが良い:8フィート前後のロッドとバランスが取れる
- ドラグ力が適度:アジングでもエギングでも十分なドラグ力
- 価格帯が豊富:エントリーからハイエンドまで選択肢多数
ただし、ラインの使い分けには注意が必要です。エギングでは通常PE0.6~0.8号を使用し、アジングでは PE0.3~0.4号が一般的です。兼用する場合、PE0.6号を巻いておき、両方に対応するという方法が現実的でしょう。
エギングとアジングで兼用できるリールを探しています。エギングとライトエギングくらいならアジングで使われる0.4号のPEくらいならラインとリールも併用できます。
リーダー(ショックリーダー)についても、兼用を考えるならフロロカーボン2.5~3号が妥当です。エギングでは通常2~3号、アジングでは1.5~2.5号程度を使用するため、中間の2.5号であればどちらにも対応できます。
🎣 兼用におすすめのスピニングリール(2500番)
- ダイワ 23レガリス LT2500S:実売8,000円前後、コスパ最強
- シマノ 23ストラディック 2500S:実売15,000円前後、性能良好
- ダイワ 24エアリティ LT2500S:実売30,000円前後、超軽量
これらのリールは、いずれも2500番台のシャロースプール(Sモデル)で、細いPEラインを巻くのに適しています。特に、ダイワの23レガリスは、1万円を切る価格ながら基本性能がしっかりしており、初めての兼用リールとしておすすめです。
また、一部の上級者は、2500番ボディに2000番スプールを装着するという方法も取っています。これにより、アジング寄りのライン容量にしつつ、リール本体のパワーはエギングに対応できるという、良いとこ取りが可能になります。ただし、この方法はスプールを別途購入する必要があるため、コストは上がります。
兼用リールを選ぶ際の最大のポイントは、自分がどちらの釣りを優先するかです。エギングがメインなら3000番を選び、アジングもしっかり楽しみたいなら2500番を選ぶ、というのが基本的な考え方です。
まとめ:エギングロッドでアジングできる条件を理解して楽しもう
最後に記事のポイントをまとめます。
- エギングロッドでアジングは条件付きで可能だが、すべての釣り方に対応できるわけではない
- エギングロッドとアジングロッドの最大の違いは長さと硬さにある
- ジグ単アジングにエギングロッドを使うのは極めて困難
- フロートリグやキャロライナリグならエギングロッドでも快適に楽しめる
- エギングロッドでアジングをするメリットは遠投性能とコストパフォーマンス
- デメリットは感度の低下、操作感のわかりづらさ、バラシの増加
- フロートリグはエギングロッドで最も相性の良いアジング仕掛け
- 重めのジグヘッド(2g以上)またはキャロを使えば対応可能
- ドラグ設定は緩めにしてバラシを防ぐことが重要
- ラインテンションを張りすぎないことでアタリをはじかない
- 兼用にはMLクラス、8~8.3フィート程度のエギングロッドが最適
- リールは2500番台がエギングとアジング両方に対応できてバランス良好
- PE0.6号のラインとフロロ2.5号のリーダーで両方に対応可能
- 完全な兼用は難しく、専用ロッドには及ばないことを理解すべき
- 「エギング中の隙間時間にアジングも」という目的なら十分に楽しめる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- エギングロッドでアジングに挑戦してみた!釣果を上げる5つのポイントを実釣解説 | TSURI HACK
- エギングロッドとアジングロッドは併用できるとあなたは思いますか – Yahoo!知恵袋
- アジングにエギングロッドはむしろ推奨レベル!? 使い所を解説! | アジング専門/アジンガーのたまりば
- エギングロッドでアジングを楽しむことは可能? | リグデザイン
- エギングロッドでアジングは可能ですか? – Yahoo!知恵袋
- エギングロッドでアジングはできるのか解説!おすすめの兼用ロッドも紹介 – 釣りメディアGyoGyo
- エギングロッドでもアジングはできる!おすすめの釣り方をご紹介 | 孤独のフィッシング
- アジングロッドでエギングを楽しむ方法とおすすめロッド|釣りGOOD
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。