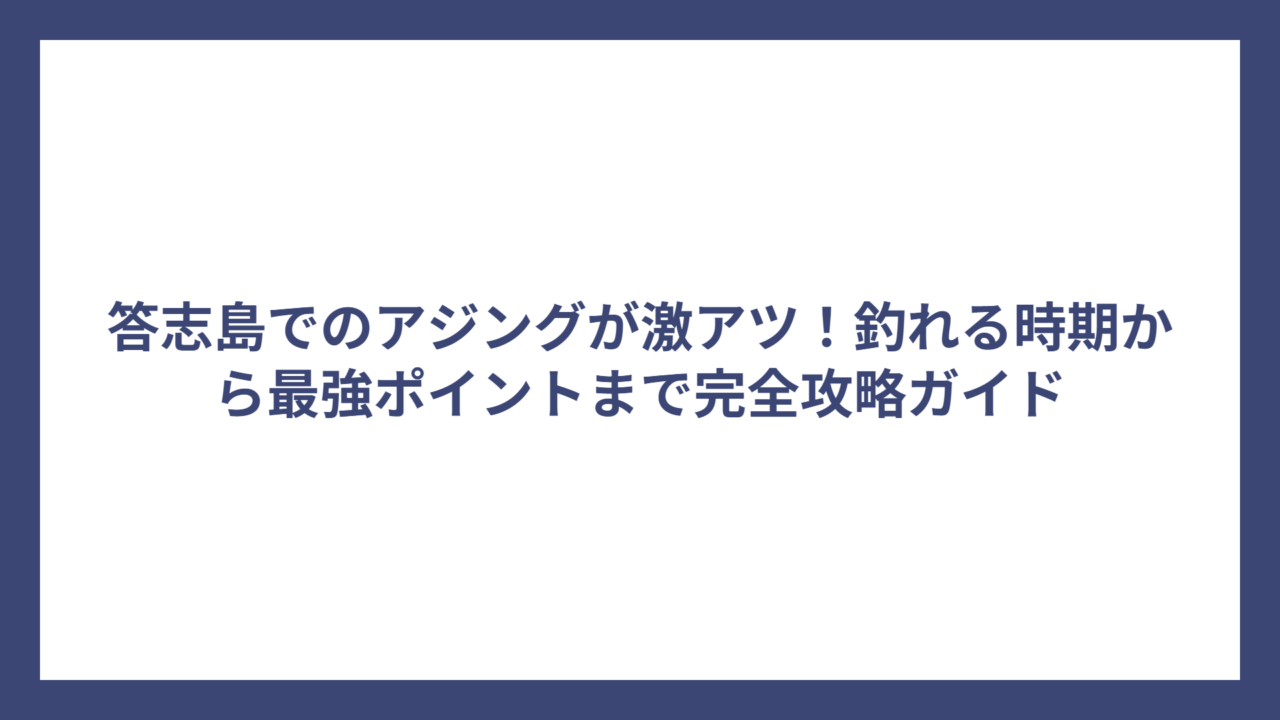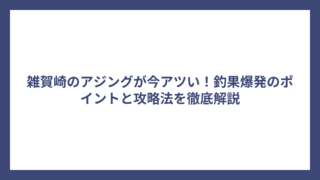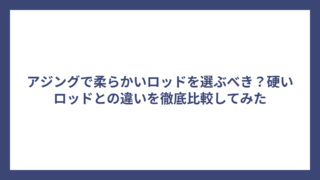三重県鳥羽市沖に浮かぶ離島・答志島は、アジングファンの間で「聖地」とも呼ばれる好ポイントです。本州から定期船でアクセスできる手軽さながら、離島ならではの魚影の濃さと型の良さで、年間を通して多くのアングラーを魅了しています。県内屈指の釣り場として知られる答志港をはじめ、和具港、桃取港という3つの主要ポイントがあり、それぞれに特徴があります。
この記事では、答志島でのアジングに関する情報をインターネット上から収集し、釣れる時期やポイント選び、実践的なテクニック、注意すべきルールなどを網羅的にまとめました。初めて答志島を訪れる方でも安心して釣行できるよう、アクセス方法から現地の設備情報まで詳しく解説していきます。離島釣行ならではの魅力と注意点を理解して、最高のアジング体験を実現しましょう。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 答志島のアジングは9〜11月が最盛期で良型が狙える |
| ✓ 答志港・和具港・桃取港の3つの港それぞれに特徴がある |
| ✓ 港内では投げ釣り禁止などのルールを必ず守る必要がある |
| ✓ 島内の移動は徒歩が基本で釣具店は限られている |
答志島のアジングで狙える魚種と釣果実績
- 答志島のアジングは年間を通して好釣果が期待できる
- 答志島でアジング中に釣れる魚はアジだけじゃない
- 答志島の3つの港それぞれの特徴と釣果傾向
- 答志島アジングで20cm超えの良型が狙える時期
- 答志島への行き方はフェリーのみ、時刻表を要チェック
- 答志島内の移動は徒歩が基本、釣り具店情報も要確認
答志島のアジングは年間を通して好釣果が期待できる
答志島でのアジングは、季節を問わず楽しめるのが最大の魅力です。一般的にアジは水温が下がる冬場には釣果が落ちる傾向がありますが、答志島では真冬でも釣果報告が上がっています。
特に注目すべきは、答志島の立地条件です。離島という環境が釣り荒れを防ぎ、常に一定の魚影を保っています。本州の港では釣り人が多すぎて魚がスレてしまうことがありますが、答志島は定期船でしかアクセスできないため、プレッシャーが比較的低い状態が維持されているのです。
さらに、答志島周辺は潮通しが良好で、常に新鮮な海水が流れ込みます。これにより、プランクトンなどのベイトフィッシュが豊富に存在し、それを追ってアジが集まる好循環が生まれています。水深も十分にあるため、水温が安定しやすく、冬場でも釣果が期待できる理由の一つとなっています。
実際の釣果情報を見ると、1日に100匹以上のアジが釣れたという報告や、25cm級の良型が複数匹釣れたという情報も散見されます。これは本州の一般的な堤防ではなかなか達成できない釣果です。離島ならではのポテンシャルの高さを物語っていると言えるでしょう。
ただし、天候や潮の状況によっては釣れない日もあるのは事実です。特に強風や大雨の後は濁りが入り、一時的に釣果が落ちることもあります。それでも、他の釣り場と比較すれば平均的な釣果は高いレベルにあると推測されます。
答志島でアジング中に釣れる魚はアジだけじゃない
答志島でアジングをしていると、アジ以外の魚種も頻繁にヒットします。これは答志島の魚影の濃さと魚種の多様性を示す証拠と言えるでしょう。
まず最も頻繁に混じるのがメバルです。答志島は「メバルの島」として有名で、三重県内でもメバルの魚影が最も濃い場所の一つとされています。
三重県近辺で メバルの魚影が一番濃いのが答志島かも。時期的には早いが、他の根魚と一緒に狙っても そこそこは充分に釣れます。
<cite>出典:三重県答志島での釣り – Yahoo!知恵袋</cite>
この引用からもわかるように、答志島ではメバルも同時に狙える環境が整っています。アジング用のジグヘッドとワームでメバルも釣れるため、一石二鳥の楽しみ方ができるのです。メバルは15〜23cm程度のサイズが多く、時には良型の20cm超えも期待できます。
さらに、**セイゴ(シーバスの幼魚)**も頻繁にヒットします。特に常夜灯周りで夜釣りをしている際に、20〜30cm程度のセイゴがバイトしてくることが多いようです。アジングタックルでもやり取りは可能なサイズですが、ドラグ設定には注意が必要でしょう。
その他にもカサゴ、ムラソイ、タケノコメバル、アイナメなどの根魚類、タチウオ、アオリイカなども釣れることがあります。タチウオは夏から秋にかけて、アオリイカは秋がシーズンのピークです。アジングをしながら、これらの魚種が釣れる可能性があるというのは、答志島ならではの魅力と言えます。
特に驚きなのが、**40cmを超えるキジハタ(アコウ)**が釣れた報告もあることです。これはアジングタックルでは荷が重いサイズですが、底付近を探っている際に思わぬ大物がヒットする可能性があるということです。このように、答志島では何が釣れるかわからないワクワク感を常に味わえます。
答志島の3つの港それぞれの特徴と釣果傾向
答志島には答志港、和具港、桃取港という3つの主要な港があり、それぞれに異なる特徴があります。自分の釣りスタイルや条件に合わせて選ぶことが、釣果を上げるカギとなります。
📊 答志島3大港の比較表
| 港名 | 定期船所要時間 | 水深 | 潮通し | 魚種の豊富さ | 足場の良さ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答志港 | 約40分 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 県内屈指のポテンシャル |
| 和具港 | 約30分 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | バランスの良い好ポイント |
| 桃取港 | 約15分 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 潮の流れが速く複雑 |
答志港は、間違いなく答志島で最もポテンシャルの高いポイントです。青灯波止から沖に投げると水深が15mを超えると言われており、この深さが冬場でも水温を安定させ、年間を通して釣果が期待できる理由となっています。過去のデータでは青物の回遊やマダイの釣果も確認されており、大型魚との遭遇チャンスもあります。
新波止も優秀なポイントで、クロダイや根魚の魚影が濃いとされています。ただし、テトラポッドで足場が悪いため、安全装備は必須です。初心者やファミリーフィッシングには向かない場所かもしれません。
和具港は、答志港に比べると若干浅いものの、魚影の濃さは十分です。答志港ほど釣果が爆発的ではないかもしれませんが、それでも十分に楽しめるレベルです。赤灯堤がメインのポイントで、足場も比較的良好なため、初めて答志島を訪れる方にはこちらがおすすめかもしれません。
和具港周辺には砂地が多いため、キスやマゴチ、カレイが釣れるとの情報もあります。アジング以外の釣りも同時に楽しみたい方には適したポイントと言えるでしょう。定期船の発着場に近く、アクセスの利便性も高いです。
桃取港は、定期船で最も早く到着できる港(約15分)で、時間的な制約がある方には便利です。潮通しが非常に良く、潮の流れが速く複雑なため、魚のサイズは大きめが期待できます。ただし、大潮回りには流れが強すぎて釣りづらい場合もあるようです。
白灯堤がメインのポイントですが、先端周りはテトラに囲まれているため、足場には要注意です。新港の堤防も釣り座となりますが、全体的に経験者向けのポイントと言えるかもしれません。
答志島アジングで20cm超えの良型が狙える時期
答志島でのアジングは年間を通して楽しめますが、サイズと数を両立できるベストシーズンは9月〜11月です。この時期は小アジから中アジ、さらには尺アジ(30cm以上)まで狙える最高の時期となります。
🗓️ 答志島アジング季節別ガイド
| 時期 | アジのサイズ | 釣れやすさ | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 12月〜2月 | 20cm前後 | ★★☆☆☆ | 真冬期、東側の港が有利 |
| 3月〜4月 | 20〜25cm | ★★★☆☆ | 水温上昇前、サイズアップ傾向 |
| 5月〜6月 | 10cm未満(豆アジ) | ★★★★★ | 豆アジシーズン、数釣り可能 |
| 7月〜8月 | 10〜15cm | ★★★★☆ | 小アジメイン、夕マズメが有利 |
| 9月〜11月 | 15〜30cm | ★★★★★ | 最盛期、良型と数が両立 |
冬場(12月〜2月)は、答志島の中でも東側の港(答志港、和具港など)が有利とされています。これは西側の水深が浅い港では水温が早く下がりやすいためです。サイズは20cm前後が中心で、前年の初夏に生まれた豆アジが成長したものと推測されます。ただし、魚影は薄くなる傾向があるため、釣果を求めるなら情報収集が重要です。
春(3月〜4月)は、水温的にはまだ冬と同じような状態が続きますが、徐々にサイズアップの傾向が見られます。20〜25cmのアジが狙える時期で、一部では25cm超えの良型も混じることがあります。また、この時期はマイワシも釣れることがあり、サビキ釣りも楽しめるでしょう。
初夏(5月〜6月)になると、島全域で10cm未満の豆アジが大量発生します。数釣りを楽しみたい方には最高の時期ですが、豆アジ専用の小さな針(4号程度)が必要です。この時期は20cm前後のアジも混じりますが、徐々に豆アジに取って代わられていきます。
真夏(7月〜8月)も豆アジから小アジ(10〜15cm)がメインとなります。この時期は夕マズメから夜にかけての時間帯が特に有利で、日中は厳しいことが多いようです。常夜灯周りでの釣りが効果的とされています。
そして最盛期の**秋(9月〜11月)**は、初夏の豆アジが15cm程度に成長し、数・型ともに最高の状態となります。特に11月は小アジから中アジ、尺アジ、さらには40cm超えの「ギガアジ」まで狙えるという情報もあります。ただし、ギガアジは沖堤防など限定的な場所での釣果が多いようです。
アジ :安定して釣れると思います。アジング、エサ釣り、どちらも良さそうですが、答志漁港はアミエビが禁止されているのでご注意下さい。時間帯は夕マズメから夜がおススメで2桁の釣果が狙えると思います。
<cite>出典:答志島の釣り場マップと現地情報</cite>
この引用からもわかるように、答志島では時期を選べば安定して2桁の釣果が期待できる優良ポイントなのです。
答志島への行き方はフェリーのみ、時刻表を要チェック
答志島へのアクセスは鳥羽マリンターミナルから定期船のみとなります。車で島に渡ることはできないため、釣行計画を立てる際は定期船の時刻表を必ず確認しましょう。
🚢 答志島定期船アクセス情報
| 出発地 | 到着港 | 所要時間 | 片道料金(2025年5月時点) |
|---|---|---|---|
| 鳥羽マリンターミナル | 桃取港 | 約15分 | 550円 |
| 鳥羽マリンターミナル | 和具港 | 約30分 | 550円 |
| 鳥羽マリンターミナル | 答志港 | 約40分 | 550円 |
定期船は各港に寄港する便と、直行便があるため、時刻表で確認が必要です。釣りで最終便を逃すと島に取り残されてしまうため、帰りの便の時刻は必ず頭に入れておくことが重要です。特に夜釣りをする場合は、最終便の時刻に間に合うように釣りを切り上げる必要があります。
ただし、宿泊施設を利用すれば時間を気にせず釣りを楽しめます。答志島には民宿やホテルがいくつかあり、特に和具港周辺に宿泊施設が集中しているようです。宿泊者向けに釣り具セットのレンタルや、釣った魚の調理サービスを提供している宿もあります。
例えば「くつろぎの宿 美さき」では、宿泊者は釣り具セット1,500円でレンタルでき、釣った魚を夕食時に調理してもらえるサービスがあるとのことです(宿泊者は1人2匹まで無料)。こうした宿を利用すれば、釣りをより快適に楽しめるでしょう。
鳥羽マリンターミナル周辺には駐車場がありますが、釣行シーズンには混雑する可能性があります。早めに到着して駐車場を確保することをおすすめします。また、鳥羽駅周辺にも駐車場があるため、そちらを利用するのも一つの方法です。
釣り道具を持っての移動となるため、荷物が多くなりがちです。定期船には十分なスペースがあるとは言え、他の乗客の迷惑にならないよう、コンパクトにまとめる工夫も必要でしょう。パックロッドを使用するなど、持ち運びやすさも考慮した道具選びが推奨されます。
答志島内の移動は徒歩が基本、釣り具店情報も要確認
答志島に到着した後の移動手段は、基本的に徒歩となります。島内にはレンタカーがなく、一般向けの定期船で車を持ち込むこともできないため、釣り場間の移動は歩くことになります。
答志島は東西約6km、南北約1.5kmの細長い形をしており、徒歩での移動も可能な範囲です。ただし、釣り道具を持っての移動は意外と大変かもしれません。和具港から答志港までは徒歩で約30分とされていますが、クーラーボックスなど荷物が多いと、さらに時間がかかる可能性があります。
自転車の持ち込みやレンタサイクルは可能なようなので、軽装備であれば自転車での移動も検討する価値があります。島内は基本的に平坦な道が多いため、自転車があれば効率よくポイントを回れるでしょう。
答志島はグーグルマップ等で確認してみると分かる様にそこそこ大きな島です。各漁港や堤防も各地に点在しており、可能なら自動車でポイント移動したい所。ですが、現在(※2024年3月時点)では島内にレンタカーは無く、一般向けのフェリーで自動車は乗船できないみたいなので、ポイント間の移動は基本的に「徒歩」となります。
<cite>出典:3月末の答志島アジング・メバリング</cite>
この引用からもわかるように、事前に移動手段を考えておくことが重要です。
釣具店に関しては情報が限られています。和具港に釣具店があるとの情報はありますが、確認できていないとの記述も見られます。島内での釣具の調達は難しいと考え、本州で必要なものをすべて揃えてから渡島することを強くおすすめします。
鳥羽駅周辺には「橋本釣具店」(三重県鳥羽市鳥羽3丁目27-15)があるため、忘れ物があった場合はここで補充してから定期船に乗るのが賢明でしょう。ジグヘッドやワームは消耗品ですから、十分な量を用意しておくことが大切です。
また、島内にコンビニは基本的にありません。定期船発着場に商店があるとの情報もありますが、営業時間が限られている可能性があります。飲食物も事前に準備しておくのが無難です。特に夏場の釣行では、熱中症対策として十分な水分を持参しましょう。
島内でのゴミ処理も課題です。ゴミは必ず持ち帰るのが原則です。近年、釣り場でのマナー違反が問題となっており、ゴミの放置は釣り禁止につながる可能性があります。美しい島の環境を守るためにも、ゴミ袋を持参し、自分のゴミは責任を持って処理しましょう。
答志島のアジングで押さえるべき実践テクニック
- 答志島の答志港は県内屈指のポテンシャルを誇る
- 和具港は答志港に次ぐ好ポイント、足場も良好
- 桃取港は潮通しが良く大型が期待できる穴場
- 答志島アジングで釣り禁止エリアを必ず確認すること
- ジグヘッドは0.6g〜2.0gを状況に応じて使い分ける
- ワームカラーは透明系やグリーン系が実績高い
- 夕マズメから夜間が最も釣果が上がりやすい時間帯
- まとめ:答志島のアジングは初心者から上級者まで楽しめる
答志島の答志港は県内屈指のポテンシャルを誇る
答志港は、三重県内でも屈指の釣り場として知られています。その理由は、抜群の潮通し、十分な水深、豊富な魚種、そして高い魚影密度にあります。
答志港の最大の特徴は、青灯波止から沖に投げると水深が15mを超えることです。この深さは、冬場でも水温が安定しやすいという大きなメリットをもたらします。一般的な堤防では水深が浅く、冬になると水温が急激に下がってしまいますが、答志港では深い水深が緩衝材となり、年間を通して魚が付きやすい環境が保たれています。
過去のデータを見ると、答志港では以下のような驚異的な釣果が報告されています:
✅ 答志港の過去釣果実績
- アジ:100匹以上(1日で)、25cm級が複数
- アナゴ:80cm級
- カワハギ:30cm級
- セイゴ:20匹超(1日で)
- メバル:40匹超(1日で)
- ブリ:80cm級(メジロ)
これらの釣果はあくまで伝聞情報の域を出ませんが、答志港のポテンシャルの高さを示唆するものと言えるでしょう。特にアジングに関しては、1日で100匹以上という数字は、本州の一般的な堤防ではまず達成できない数です。
答志港には複数のポイントがありますが、主なものは以下の通りです:
📍 答志港の主要ポイント
| ポイント名 | 特徴 | 水深 | 足場 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| 青灯波止 | 水深15m超、潮通し抜群 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 新波止 | 根魚・クロダイの魚影濃い | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 答志新港 | 投げ釣り禁止 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
青灯波止は答志港の中でも最も人気の高いポイントです。潮通しが良く、常に新鮮な海水が流れ込むため、アジをはじめとする回遊魚が集まりやすい環境です。ただし、テトラポッドがあるエリアもあるため、夜釣りの際は足元に十分注意が必要です。
新波止は特に根魚類の魚影が濃いとされています。クロダイやカサゴなどがメインターゲットとなりますが、アジも十分に狙えます。ただし、全体的にテトラポッドで足場が不安定なため、ライフジャケットと滑りにくい靴は必須です。初心者には向かないポイントかもしれません。
答志港で釣りをする際の最大の注意点は、港内では投げ釣りが禁止されていることです。さらに、答志漁港内はアミエビの使用も禁止されています。これは地元の漁業者との共存のためのルールですから、必ず守りましょう。アジングはジグヘッドとワームを使用するため、この規制の影響は受けませんが、サビキ釣りをする場合は注意が必要です。
答志港への移動ですが、定期船の発着場からは少し離れており、徒歩で約400m程度(トンネルを通過)の距離があります。荷物が多いと大変ですが、その分だけ価値のある釣り場と言えるでしょう。
和具港は答志港に次ぐ好ポイント、足場も良好
和具港は、答志港と並ぶ答志島の主要ポイントです。答志港ほどではないものの、十分な魚影と釣果が期待できる上に、足場が比較的良好で初心者にも釣りやすいという利点があります。
和具港の最大の特徴は、答志港に比べて若干浅いものの、魚影の濃さは十分に保たれていることです。答志港との距離が近いため、魚の回遊ルートが重なっている可能性が高く、離島ならではの高い魚影密度が維持されています。
和具港周辺は砂地が多いため、アジング以外の魚種も豊富です。キス、マゴチ、カレイなどが狙えるとの情報があり、投げ釣りファンにも人気があります(ただし港内は投げ釣り禁止)。多様な釣り方ができるため、ファミリーフィッシングにも適したポイントと言えるでしょう。
県内最高クラスの釣り場である答志港に近く魚影が濃く、魚種も豊富です。ただ答志港に比べ少し浅いようで、若干釣果が落ちると言われています。しかし、心配はいりません。ここは答志島です。比べる対象が凄いだけです。ここもとてもよく釣れています。
<cite>出典:答志島の釣り場マップと現地情報</cite>
この引用が示すように、和具港は答志港と比較されることが多いものの、それ自体が優良ポイントであることに変わりはありません。「比べる対象がすごいだけ」という表現が、和具港のポテンシャルを物語っています。
和具港の主要ポイントは赤灯堤です。堤防の根元付近にはテトラが入っていますが、先端の方は足場が良好で釣りやすい環境です。初めて答志島を訪れる方や、家族連れでの釣行には、和具港がおすすめかもしれません。
和具港でのアジングのメリットは、定期船の発着場に近いことです。徒歩での移動距離が短いため、荷物が多くても負担が少なく済みます。また、周辺には宿泊施設も集中しているため、宿泊を伴う釣行を計画している方には特に便利です。
和具港でも、答志港と同様に港内は投げ釣り禁止です。ちょい投げでも、沖向きに投げる必要があります。この規制を守らないと、地元の漁業者とのトラブルにつながる可能性があるため、十分に注意しましょう。
アジングに関しては、夕マズメから夜間にかけての釣りが効果的です。常夜灯周りでは、アジが浮いてきて表層での釣りが成立しやすくなります。軽めのジグヘッド(0.6〜1.0g程度)で表層をゆっくりと引いてくると、好反応が得られることが多いようです。
和具港では、アジング中にメバルやセイゴが混じることも頻繁です。特にメバルの魚影は濃く、20cm超えの良型も期待できます。アジとメバルを同時に狙えるのは、和具港の大きな魅力の一つと言えるでしょう。
桃取港は潮通しが良く大型が期待できる穴場
桃取港は、答志島の3つの主要港の中では最もアクセスが良いポイントです。鳥羽マリンターミナルから定期船で約15分という近さは、時間に制約がある日帰り釣行には大きなメリットとなります。
桃取港の最大の特徴は、潮通しが非常に良く、潮の流れが速いことです。答志港や和具港よりも潮の動きが速く複雑とされており、これが大型魚を引き寄せる要因となっています。潮の流れが速いポイントは、ベイトフィッシュが集まりやすく、それを追って良型のアジも回遊してくる可能性が高いのです。
ただし、潮の流れが速いことは諸刃の剣でもあります。大潮回りには流れが強すぎて釣りづらい場合もあるようです。ジグヘッドが流されてしまったり、糸がふけて当たりが取りにくくなったりすることがあります。そのため、桃取港で釣りをする際は、潮の状況を事前に確認し、中潮や小潮の日を選ぶのも一つの戦略かもしれません。
📊 桃取港のポイント特性
| 要素 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|
| アクセス | ★★★★★ | 船で15分、最短 |
| 潮通し | ★★★★★ | 非常に良好、速い |
| 水深 | ★★★★☆ | 十分な深さ |
| 足場 | ★★★☆☆ | テトラあり、要注意 |
| 魚種の多様性 | ★★★★☆ | 豊富、カレイも |
| 混雑度 | ★★☆☆☆ | 比較的空いている |
桃取港には旧港と新港があり、それぞれに釣りポイントが存在します。新港の白灯堤がメインのポイントとされていますが、先端周りはテトラに囲まれており、足場には十分な注意が必要です。
旧港の2本の堤防も釣り座となりますが、こちらは小場所です。外向きで釣りをすることになりますが、潮通しは抜群です。初心者よりは、経験者向けのポイントと言えるかもしれません。
桃取港では、過去にカレイがよく釣れたとの情報があります(かなり昔の話のようですが)。これは砂地が広がっているためと推測されます。アジング以外の釣りも楽しみたい方には、桃取港は魅力的な選択肢となるでしょう。
桃取港の利点は、他の2港に比べて釣り人が少ない可能性があることです。アクセスは最も良いにもかかわらず、答志港や和具港ほど知名度が高くないためか、比較的空いていることが多いようです。ゆっくりと釣りを楽しみたい方には、桃取港がおすすめかもしれません。
ただし、桃取港も他の港と同様に、港内での投げ釣りは禁止されている可能性が高いです。ルールを守って釣りを楽しみましょう。
答志島アジングで釣り禁止エリアを必ず確認すること
答志島での釣りで最も重要なのが、地元のルールを守ることです。近年、全国各地で釣り場のマナー違反が問題となっており、釣り禁止になる場所が増えています。答志島でも同様の問題が発生しないよう、一人ひとりが責任ある行動を取る必要があります。
⚠️ 答志島釣りの主な禁止事項
| 禁止事項 | 適用範囲 | 理由 |
|---|---|---|
| 港内での投げ釣り | 答志港・和具港・桃取港 | 漁船の航行妨害防止 |
| アミエビの使用 | 答志漁港内 | 海洋環境保護 |
| ゴミの放置 | 島内全域 | 環境保護 |
| 路上駐車 | 島内全域 | 該当なし(車不可) |
最も重要な規制が、港内での投げ釣り禁止です。答志港、和具港ともに港内では投げ釣りが禁止されています。これは漁船の出入りの妨げになるためと考えられます。ちょい投げであっても、港内では控えるべきでしょう。投げ釣りをする場合は、堤防の沖向きに投げる必要があります。
さらに答志漁港内では、アミエビの使用も禁止されています。これは海洋環境を保護するための措置と推測されます。アジングではアミエビを使用しないため、この規制の直接的な影響はありませんが、サビキ釣りを併用する場合は注意が必要です。オキアミや虫エサは使用できるようですが、現地の看板等で最新のルールを確認することをおすすめします。
答志島は年間を通して釣り人が多く訪れており、海遊性の行動をとる魚以外は小物が多いです。ポイントになる堤防に住み着いても直ぐに釣られてしまい大きなサイズのカサゴなどは希に出れば良い感じです。
<cite>出典:三重県答志島での釣り – Yahoo!知恵袋</cite>
この引用は、答志島が釣り人に人気のある場所であることを示しています。多くの釣り人が訪れるからこそ、一人ひとりのマナーが重要になるのです。
ゴミの持ち帰りは、すべての釣り場で最も基本的なルールです。答志島のような美しい離島では、特に環境保護が重要です。釣り場の看板にも「ゴミは持ち帰って、きれいな釣り場をみんなで守っていきましょう」という呼びかけが掲示されています。
ゴミ袋を持参し、自分のゴミはもちろん、可能であれば落ちているゴミも拾って帰るくらいの心構えが望ましいでしょう。特にワームやラインの切れ端などは、鳥や海洋生物に害を及ぼす可能性があるため、確実に回収する必要があります。
また、騒音にも注意が必要です。早朝や夜間の釣りでは、大声で話したり、音楽を大音量で流したりすることは控えましょう。答志島は住民の生活の場でもあります。釣り人として、地域住民との共存を心がけることが大切です。
近年、答志島では定期船の利用者が増えているとの情報もあります。釣り人が増えることで、マナー違反も目立つようになる可能性があります。一人ひとりが模範的な行動を心がけることで、将来にわたって答志島での釣りを楽しめる環境を守っていきましょう。
ジグヘッドは0.6g〜2.0gを状況に応じて使い分ける
答志島でのアジングでは、ジグヘッドの重さ選択が釣果を大きく左右します。水深、潮の流れ、アジの活性、狙うレンジなどに応じて、適切な重さを選ぶ必要があります。
🎣 答志島アジング推奨ジグヘッド重量
| ジグヘッド重量 | 使用状況 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 0.3〜0.6g | 表層、常夜灯下、活性高 | ゆっくり誘える、食い込み良い | 風・潮に弱い、飛距離短い |
| 0.8〜1.0g | 中層、標準的な状況 | バランス良い、汎用性高い | 特になし |
| 1.5〜2.0g | 底付近、潮速い、風強い | 底取りしやすい、飛距離出る | 食い込み悪化の可能性 |
| 3.0g | 深場、強風時 | 深場対応、遠投可能 | ナチュラルな誘い困難 |
軽いジグヘッド(0.3〜0.6g)は、表層付近を狙う際や、アジの活性が高い時に効果的です。特に夕マズメ後の常夜灯周りでは、アジが表層に浮いてくることが多いため、軽いジグヘッドでゆっくりと誘うと好反応が得られます。ただし、風が強い日や潮が速い日には、軽すぎるジグヘッドは使いづらくなります。
標準的な重さ(0.8〜1.0g)は、最も汎用性が高い選択です。表層から中層まで幅広くカバーでき、ある程度の風や潮にも対応できます。答志島での釣行が初めての方は、まずこの重さから始めると良いでしょう。
「 ストリームヘッド 」(0.8g)と新型ワームの「こうはくカラー」の組合せから釣り始めました。
<cite>出典:家邊克己の三重県・答志島アジング遠征レポート</cite>
この引用からも、プロアングラーが0.8gをスタートの重さとして選んでいることがわかります。これは多くの状況に対応できる重さだからでしょう。
重めのジグヘッド(1.5〜2.0g)は、底付近を探る際や、潮の流れが速い桃取港などで有効です。また、風が強い日にも重宝します。答志島は水深があるポイントも多いため、底を攻める際には1.5g以上のジグヘッドが必要になることもあります。
さらに重い3.0gのジグヘッドは、深場専用と考えて良いでしょう。答志港の青灯波止のような水深15m以上のポイントで、底付近を効率よく攻めたい場合に使用します。ただし、重すぎるジグヘッドはワームの動きが不自然になりやすいため、使いどころを見極める必要があります。
実際の釣行では、複数の重さを用意しておくことが重要です。釣り始めは標準的な重さでスタートし、反応を見ながら軽くしたり重くしたりと調整していくのが基本的なアプローチです。
ジグヘッドの形状も重要な要素です。ダート系のジグヘッド(例:ジャコヘッドTG ミクロ)は、キビキビとしたアクションを演出でき、アジの捕食スイッチを入れやすいとされています。一方、丸型のジグヘッド(例:月下美人アジングジグヘッドTG)は、安定したスイミングが得意で、リトリーブ主体の釣りに向いています。
タングステン素材のジグヘッドは、鉛製よりも比重が高いため、同じ重さでも小型で、風の影響を受けにくいメリットがあります。価格は高めですが、答志島のような風が吹きやすい離島では、タングステン製ジグヘッドの導入を検討する価値があるでしょう。
ワームカラーは透明系やグリーン系が実績高い
答志島でのアジングにおいて、ワームのカラー選択も重要な要素です。ネット上で収集した情報から、特に実績の高いカラーパターンが見えてきました。
🎨 答志島アジング推奨ワームカラー
| カラータイプ | 具体例 | 使用状況 | 実績度 |
|---|---|---|---|
| クリア系 | クリア、透明グロー | 常夜灯下、月夜、プレッシャー高 | ★★★★★ |
| グリーン系 | モスグリーン、釣れ釣れグリーン | デイゲーム、マズメ、常夜灯下 | ★★★★★ |
| ナチュラル系 | ソリッドモスグリーン | スレた状況、クリアウォーター | ★★★★☆ |
| グロー系 | ピンクグロー、グリーングロー | 夜間、濁り | ★★★☆☆ |
| ケイムラ系 | ケイムラ入りカラー | 日中、紫外線あり | ★★★☆☆ |
クリア(透明)系は、答志島に限らずアジングで最も基本となるカラーです。特に常夜灯下や月明かりがある夜には、シルエットがはっきりと出るクリア系が効果的です。アジは視覚でエサを探すため、シルエットがはっきりしているワームに反応しやすい傾向があります。
グリーン系も答志島で高実績のカラーです。特に「釣れ釣れグリーン」というカラーは、複数の釣行レポートで使用されており、実績の高さが伺えます。
「レイン アジアダー 2インチ 釣れ釣れグリーン」でした。当ブログ発のオリジナルカラーで、あえてラメ・蛍光・ケイムラ無しのナチュラル系のコアショットのグリーン系カラー。メバリング、アジング共にデイゲーム(マズメ含む)や常夜灯下で特に強いカラーです。
<cite>出典:3月末の答志島アジング・メバリング</cite>
この引用から、グリーン系がデイゲームやマズメ、常夜灯下で特に効果的であることがわかります。ラメや蛍光、ケイムラを入れないナチュラルなグリーンが、プレッシャーの高い状況でも効果を発揮するようです。
ソリッドモスグリーンのような1/4ソリッドカラーも注目です。光の反射を抑えつつ、透明感も残すバランスの良いカラーで、スレた状況に強いとされています。
「34 プランクトン 1/4ソリッドモスグリーン」は34さんに作ってもらった当ブログ発のオリジナルカラー。グリーン系カラーはアジングで反応が良い事が多く、意外にあまり作られていないカラーなので作ってもらいました。
<cite>出典:答志島でメバリング&シーバストップゲーム</cite>
グリーン系が効果的な理由は、海中でのプランクトンの色に近いためと推測されます。アジはプランクトンを主食としているため、その色に近いワームに違和感なく反応するのかもしれません。
グロー系は夜釣りで定番のカラーです。暗闇の中で発光するため、アジに発見されやすくなります。ただし、答志島のような常夜灯があるポイントでは、グローが逆に不自然に見える可能性もあります。常夜灯のないポイントや、濁りが入っている時に特に有効でしょう。
ケイムラ系は、紫外線に反応して発光するカラーで、日中の釣りで効果を発揮することがあります。ただし、夜間や常夜灯下ではケイムラの効果は発揮されないため、時間帯に応じた使い分けが必要です。
ワームのカラー選択で重要なのは、複数のカラーを用意しておくことです。その日の水質、天候、時間帯によって、効果的なカラーは変わります。最初はクリア系やグリーン系から始めて、反応が悪ければ他のカラーをローテーションしていくのが基本的なアプローチです。
また、ワームのサイズ選択も重要です。答志島では、1.8〜2.3インチ程度のワームが主流のようです。アジのサイズに合わせて、小型の時は小さめのワーム、良型が多い時は大きめのワームを選ぶと良いでしょう。
夕マズメから夜間が最も釣果が上がりやすい時間帯
答志島でのアジングは、時間帯によって釣果が大きく変わります。一日の中で最も釣れやすい時間帯を理解しておくことが、効率的な釣行につながります。
⏰ 答志島アジング時間帯別攻略法
| 時間帯 | 釣れやすさ | 主な釣り場 | 攻め方 |
|---|---|---|---|
| 日中(8〜16時) | ★★☆☆☆ | 水深のある場所 | 底付近、日陰 |
| 夕マズメ(16〜18時) | ★★★★★ | 全ポイント | 表層〜中層 |
| 夜間前半(18〜22時) | ★★★★★ | 常夜灯周り | 表層中心 |
| 夜間後半(22〜4時) | ★★★☆☆ | 常夜灯周り | 中層〜底 |
| 朝マズメ(4〜6時) | ★★★★☆ | 全ポイント | 表層〜中層 |
最も釣果が期待できるのは、夕マズメから夜間にかけてです。夕マズメは日没前後の1〜2時間で、アジの活性が一気に上がる時間帯です。この時間帯は表層付近にアジが浮いてくることが多く、軽めのジグヘッド(0.6〜1.0g)でゆっくりと表層を引いてくると好反応が得られます。
時間帯は夕マズメから夜がおススメで2桁の釣果が狙えると思います。
<cite>出典:答志島の釣り場マップと現地情報</cite>
この引用からも、夕マズメから夜が最も効率的な時間帯であることがわかります。2桁(10匹以上)の釣果を狙うなら、この時間帯に集中するのが賢明でしょう。
夕マズメ後の**夜間前半(18〜22時頃)**も高活性が続きます。この時間帯は常夜灯周りが特に有望で、明暗の境目を狙うと効果的です。アジは常夜灯に集まるベイトフィッシュを捕食するために寄ってくるため、明暗部を丁寧に探ると良いでしょう。
ただし、常夜灯周りは他の釣り人も集中しやすいポイントです。マナーを守り、適度な距離を保って釣りをすることが重要です。また、答志島の場合、常夜灯が点灯しないこともあるようですので、ヘッドライトなど自前の照明も用意しておくと安心です。
**夜間後半(22時以降)**になると、アジの活性はやや落ちる傾向があります。表層での反応が悪くなったら、中層から底付近にレンジを下げてみましょう。ジグヘッドを1.5〜2.0gに変更し、底付近をリフト&フォールで探ると良型のメバルやアジがヒットすることがあります。
**朝マズメ(日の出前後1〜2時間)**も、夕マズメと同様に活性が上がる時間帯です。ただし、答志島の場合、朝マズメは夕マズメほど爆発的な釣果にはならないという報告もあります。おそらく、夜間の釣りでプレッシャーがかかっているためかもしれません。
日中は最も厳しい時間帯です。アジは日光を嫌う傾向があり、日中は深場や日陰に落ちていることが多いです。ただし、水深のある答志港の青灯波止などでは、日中でも底付近を丁寧に探れば釣果が期待できることもあります。
日中に釣りをする場合は、底付近を重点的に攻めるのが基本です。1.5〜2.0gのジグヘッドで底まで落とし、リフト&フォールやズル引きで誘います。日中は活性が低いため、ゆっくりとしたアクションが効果的な場合が多いでしょう。
時間帯による水温の変化も考慮に入れると良いでしょう。特に夏場は、日中に水温が上がりすぎて活性が落ちることがあります。逆に、冬場は日中の方が水温が安定している場合もあります。季節や天候に応じて、最適な時間帯を判断することが大切です。
まとめ:答志島のアジングは初心者から上級者まで楽しめる
最後に記事のポイントをまとめます。
- 答志島は三重県鳥羽市沖の離島で、鳥羽マリンターミナルから定期船で15〜40分でアクセス可能
- 島内には答志港、和具港、桃取港という3つの主要ポイントがあり、それぞれに特徴がある
- 答志港は県内屈指のポテンシャルを誇り、水深15m超で年間を通して好釣果が期待できる
- 和具港は答志港に次ぐ好ポイントで、足場が良好なため初心者にもおすすめ
- 桃取港は潮通しが良く、定期船で最も早く到着できるアクセスの良さが魅力
- アジングのベストシーズンは9〜11月で、良型と数が両立する最盛期
- 冬場(12〜2月)でも釣果報告があり、離島ならではの魚影の濃さが維持されている
- 港内では投げ釣り禁止、答志漁港内はアミエビ使用禁止などのルールを必ず守る必要がある
- ジグヘッドは0.6〜2.0gを状況に応じて使い分け、タングステン製が有利
- ワームカラーはクリア系やグリーン系が高実績で、ナチュラル系が効果的
- 釣れる時間帯は夕マズメから夜間が最も有望で、2桁の釣果が狙える
- アジング中にメバル、セイゴ、カサゴ、タチウオなど多彩な魚種が混じる
- 島内の移動は徒歩が基本で、釣具店は限られているため事前準備が重要
- 宿泊施設もあり、時間を気にせず釣りを楽しむなら宿泊がおすすめ
- ゴミの持ち帰りや騒音への配慮など、基本的なマナーを守ることが釣り場の環境保護につながる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 三重県の答志島の釣り場マップと現地情報
- 家邊克己の三重県・答志島アジング遠征レポート
- 3月初旬の答志島でアジング&メバリング
- 答志島で釣れたアジの釣り・釣果情報 – アングラーズ
- 離島で楽しむRIDE&FISH 東西8kmの答志島を自転車で釣る!
- 3月末の答志島アジング・メバリング
- 三重県答志島での釣り – Yahoo!知恵袋
- 答志島でメバリング&シーバストップゲーム
- 答志島アジング釣果情報 – カンパリ
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。