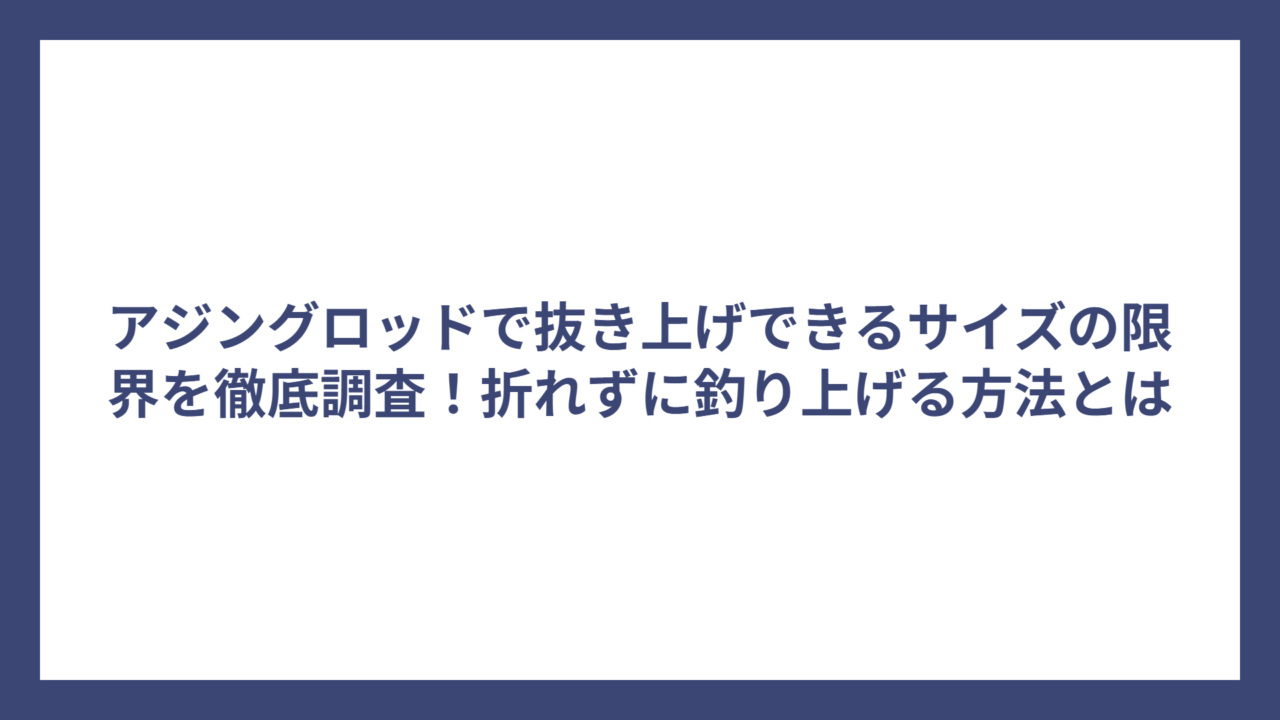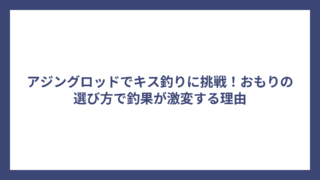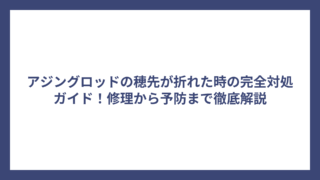アジングをしていると、想定外の大物がヒットすることがあります。繊細なアジングロッドで果たして抜き上げは可能なのか、どのサイズまでなら安全に取り込めるのか——これは多くのアングラーが気になるポイントではないでしょうか。
実際にネット上の情報を調査してみると、エステルライン0.2号でも25cm程度までなら抜き上げ可能という体験談から、フロロ2.5lbで50cmのシーバスは無理だったという失敗談まで、さまざまな報告が見られます。抜き上げの成否は単純にロッドのパワーだけでなく、ラインシステム、ドラグ設定、そして何よりロッドの角度やテクニックが大きく関わってくるようです。本記事では、これらの情報を総合的に分析し、アジングロッドでの安全な抜き上げ方法を詳しく解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ アジングロッドで抜き上げできるサイズの目安と限界値 |
| ✓ ロッド破損を防ぐための正しい角度とテクニック |
| ✓ ラインシステムとドラグ設定の最適解 |
| ✓ ショートロッドとロングロッドの抜き上げ性能比較 |
アジングロッドで抜き上げできるサイズと実際の限界
- 25cmまでなら抜き上げ可能だが条件次第
- ラインの強度が最大のボトルネック
- ロッドパワーより角度とテクニックが重要
- エステル0.2号とフロロ2.5lbの実力差
- 尺アジ(30cm)が抜き上げの分水嶺
- 大型外道(シーバス、チヌ)は抜き上げNG
25cmまでなら抜き上げ可能だが条件次第
アジングロッドでの抜き上げについて、実際の釣行記録を調査すると、25cmクラスまでであれば抜き上げ可能というのがおおよその目安のようです。ただし、これはあくまで「可能」というレベルであり、万全の条件が揃った場合に限られます。
具体的には、ロッドのパワー、ラインの状態、針掛かりの位置、魚の暴れ具合など、複数の要素が絡み合って成否が決まります。例えば、同じ25cmのアジでも、口の堅い部分にしっかり掛かっている場合と、口の柔らかい部分に掛かっている場合では、抜き上げの難易度が大きく異なるでしょう。
また、ロッドの適合ウエイトも重要です。0.3~1.8g推奨のジグ単専用モデルであっても、適切なテクニックを用いれば25cmクラスの抜き上げは十分可能との報告があります。ただし、これはロッドメーカーが想定している使い方ではないため、自己責任での判断となります。
ロッドは0.3〜1.8g推奨のジグ単専用モデルでしたが、まったく折れることもなかったですし、めちゃ曲がりましたがドラグぎりぎりまで緩めたので不安もなかったです。
この報告から分かるように、ドラグ調整が適切であれば、比較的パワーのないロッドでも抜き上げは可能です。しかし、重要なのは「ドラグぎりぎりまで緩めた」という点です。つまり、ロッドのパワー不足をドラグ性能で補っているわけですね。
さらに、抜き上げ時の状況も考慮する必要があります。足場の高さ、風の強さ、魚の活性度など、その日のコンディションによっても成功率は変わってきます。特に足場が高い堤防などでは、抜き上げの難易度が跳ね上がるため、より慎重な判断が求められるでしょう。
経験豊富なアングラーであれば、魚のサイズや引きの強さから「これは抜き上げできる」「これはネットが必要」という判断が瞬時にできるかもしれません。しかし、初心者の場合は無理をせず、20cm程度までに留めておくのが安全策と言えます。
ラインの強度が最大のボトルネック
抜き上げの成否を決める最大の要因は、実はラインの強度です。どんなに高性能なロッドを使っていても、ラインが切れてしまえば元も子もありません。特にアジングで使用される極細ラインは、抜き上げ時に大きなリスクを抱えています。
エステルライン0.2号の破断強度は一般的に約1lb(450g程度)とされています。しかし、これはあくまで新品時の最大強度であり、ノット部分では強度が6~7割程度に低下します。さらに、使用による劣化や傷、結び直しの回数などで、実際の強度はさらに低下していきます。
📊 ラインシステム別の実用強度比較
| ライン種類 | 号数 | 公称強度 | ノット部強度 | 実用強度目安 | 抜き上げ可能サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| エステル | 0.2号 | 1lb (450g) | 約300g | 約250g | 15~20cm |
| エステル | 0.3号 | 1.5lb (680g) | 約470g | 約400g | 20~25cm |
| フロロ | 2.5lb | 約1.2lb | 約800g | 約700g | ~25cm |
| PE | 0.3号 | 約5lb | 約3.5lb | 約3lb | 30cm以上 |
この表を見ると分かるように、エステル0.2号の実用強度では、20cmを超えるアジの抜き上げはかなりリスクが高いと言えます。特に、ラインが劣化している場合や、何度も結び直している場合は、さらに強度が低下している可能性があります。
前に使ったときからノットを結び直してないことを思い出す。リーダーを付け直して、同じ場所にジグヘッドを通すと22センチメートルほどのアジで、しかも抜き上げ後にアジが暴れてノット部上でエステルラインがまた切れた。
この体験談からも分かるように、ノット部分は最も弱点となりやすいポイントです。特にエステルラインは結束強度が低く、適切なノットを使用しても強度低下は避けられません。そのため、定期的なノットの結び直しと、ラインの状態チェックが重要になってきます。
また、抜き上げ時には瞬間的に大きな負荷がかかります。魚の重量だけでなく、空中で暴れた際の衝撃や、水面から引き上げる際の抵抗なども加わるため、実際には魚の重量の2~3倍程度の負荷がかかると考えられます。つまり、200gのアジであっても、抜き上げ時には400~600g程度の負荷がラインにかかる可能性があるわけです。
フロロカーボンリーダーを使用することで、ノット部分の強度低下をある程度補うことができますが、それでもエステル本線の強度以上にはなりません。より大きなアジを安全に抜き上げたい場合は、エステル0.3号以上にラインアップするか、PE+フロロリーダーのシステムを検討する必要があるでしょう。
ロッドパワーより角度とテクニックが重要
抜き上げで最も重要なのは、実はロッドの角度とテクニックです。どれだけ強いロッドを使っていても、角度を誤れば簡単に折れてしまいます。逆に、適切な角度とテクニックを使えば、比較的パワーのないロッドでも安全に抜き上げることが可能です。
足元近くまで寄せたら、逆にロッドを前へ倒すようにするか、斜め前方に倒して、ロッドの角度をなるべき変えない(立てない)で、後ろへロッドを引き込むように、ロッドの角度が60度を超えないように取り込まないと、ロッドは折れます。
この指摘は非常に重要です。多くのアングラーが陥りがちなミスが、ロッドを立てすぎることです。魚を寄せてきて、あともう少しというところでロッドを垂直近くまで立ててしまい、そこで魚が暴れて「バキッ」という悲劇が起こります。
正しい抜き上げのテクニックは以下のような流れになります:
🎣 正しい抜き上げの手順
- 魚を足元まで寄せる – ドラグを適切に設定し、無理な引きはしない
- ロッドを45度程度に保つ – 絶対に垂直に立てない
- ロッドを前方に倒しながら – 魚が水面に出るタイミングを見計らう
- 後ろに引き込むように – 腰を使って後ろに下がる動作で引き上げる
- 一気に抜き上げる – ためらわず、スムーズな動作で
特に重要なのが、「ロッドを前方に倒す」という動作です。これにより、ロッドの角度が極端に立つことを防ぎ、同時に魚を水面から出やすくします。そして、ロッドを引き上げるのではなく、体ごと後ろに下がるイメージで抜き上げるのがコツです。
また、抜き上げ時にロッドの中ほどを持つのは厳禁です。ティップ側だけが極端に曲がり、負荷が集中してしまうため、折れるリスクが格段に高まります。必ずグリップエンドを持ち、ロッド全体で負荷を分散させることが大切です。
さらに、足場の高さも考慮に入れる必要があります。海面までの距離が1m程度であれば比較的楽に抜き上げられますが、3m以上になると難易度が跳ね上がります。高い足場では、ロッドを寝かせるスペースも限られるため、より高度なテクニックが求められます。
このように、抜き上げの成否はロッドのパワーよりも、適切な角度管理とテクニックに大きく依存しています。高価なハイパワーロッドを買う前に、まずは正しいテクニックを身につけることが先決と言えるでしょう。
エステル0.2号とフロロ2.5lbの実力差
アジングで使用される代表的なライン、エステル0.2号とフロロカーボン2.5lbの実力差について、実際の使用例から分析してみましょう。両者は同じような細さですが、特性が大きく異なるため、抜き上げ時の挙動も変わってきます。
まず、フロロカーボン2.5lbの破断強度は約1.2lb(約540g)で、エステル0.2号の1lb(約450g)よりやや強いです。しかし、この差以上に重要なのが「伸び」の違いです。エステルラインはほとんど伸びないのに対し、フロロカーボンは適度に伸びるため、瞬間的なショックを吸収してくれます。
フロロ2.5だと破断強度的に無理だしPEでリーダーを組んだとしても無理です。要するにすごく分かりやすく言うと水面に手が届いてハンドランディング出来ないと絶対に獲れません。
この回答は、50cmクラスのシーバスに対する見解ですが、フロロ2.5lbの限界を示す重要な指摘です。つまり、フロロ2.5lbでも30cm以上の魚を抜き上げるのは極めて困難ということです。
📈 エステルとフロロの特性比較
| 特性 | エステル0.2号 | フロロ2.5lb |
|---|---|---|
| 破断強度 | 約450g | 約540g |
| 伸び率 | ほぼゼロ | 20~30% |
| 感度 | 非常に高い | やや劣る |
| 耐摩耗性 | 低い | 高い |
| 結束強度 | 60~70% | 70~80% |
| 抜き上げ適性 | △ | ○ |
この表から分かるように、純粋な破断強度ではそれほど大きな差はありませんが、伸び率の違いが抜き上げに大きく影響します。エステルはショックを吸収できないため、魚が暴れた瞬間にプツンと切れやすいのです。
実際の使用例を見ると、エステル0.2号では25cmを超えると抜き上げ失敗の報告が増えています。一方、フロロ2.5lbでも25cmクラスが限界という意見が多く、結局のところ両者とも安全に抜き上げられるのは20cm前後までというのが現実的な目安のようです。
また、ライン劣化の進行速度も異なります。エステルラインは使用による劣化が早く、特に同じ場所を繰り返し使うと急激に強度が落ちます。対してフロロカーボンは比較的劣化が遅いですが、根ズレには弱いという特性があります。
どちらのラインを選ぶかは、釣りのスタイルや優先する要素によって変わってきます。感度を最優先するならエステル、多少の伸びを許容して抜き上げの安定性を取るならフロロ、という選択になるでしょう。ただし、いずれにしても極細ラインでの抜き上げは常にリスクを伴うという認識は必要です。
尺アジ(30cm)が抜き上げの分水嶺
アジングにおいて、尺アジ(30cm)は一つの大きな壁となります。20cm台のアジと30cmのアジでは、重量も引きの強さも段違いであり、抜き上げの難易度も格段に上がります。ネット上の情報を見ても、尺アジを抜き上げできたという報告は限定的です。
尺アジの重量はおよそ300~400g程度と推定されます。しかし、前述の通り、抜き上げ時には魚の重量の2~3倍の負荷がかかるため、実質的には600~1200g程度の負荷に耐える必要があります。エステル0.2号やフロロ2.5lbでは、理論上も実用上も厳しい数字です。
🎯 サイズ別の抜き上げ難易度
| サイズ | 重量目安 | 抜き上げ負荷 | エステル0.2号 | フロロ2.5lb | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15cm | 約50g | 約100~150g | ○ | ○ | 容易 |
| 20cm | 約100g | 約200~300g | ○ | ○ | やや容易 |
| 25cm | 約200g | 約400~600g | △ | ○ | 難しい |
| 30cm | 約350g | 約700~1000g | × | △ | 非常に難しい |
| 35cm | 約550g | 約1100~1500g | × | × | ほぼ不可能 |
この表から明らかなように、尺アジになると通常のアジングラインでの抜き上げは極めて困難です。特にエステル0.2号では、まず成功しないと考えた方が良いでしょう。
尺アジ(30cmクラス)であれば、4ftのロッドだろうがどのアジングロッドでも問題なくファイトできます。エステルライン0.2号でも少々時間をかけて丁寧にやれば寄せてきてそのまま持ち上げられますし。
ただし、この回答には重要な前提条件があります。「少々時間をかけて丁寧にやれば」という部分です。つまり、十分に弱らせてから慎重に抜き上げるということです。また、針掛かりの位置が良く、魚が大暴れしなかった場合に限られるでしょう。
実際には、多くのアングラーが尺アジサイズになるとランディングネットを使用しています。特に足場の高い堤防や、風が強い日などは、無理に抜き上げようとせずネットを使う方が確実です。せっかくの尺アジをバラしてしまうリスクを考えれば、ネットの使用は賢明な判断と言えます。
また、ドラグ設定も重要です。尺アジクラスになると、ドラグを緩めすぎても締めすぎても上手くいきません。魚の引きに合わせて滑り、かつ最後の抜き上げ時にはしっかり締められる、絶妙な調整が求められます。この感覚は経験を積むことでしか身につかないため、初心者のうちは無理せずネットを使うことをおすすめします。
大型外道(シーバス、チヌ)は抜き上げNG
アジングをしていると、アジ以外の魚が掛かることもよくあります。特にシーバスやチヌなどの大型外道は、アジングタックルでの抜き上げはほぼ不可能です。無理に抜き上げようとすると、ロッドが折れる、ラインが切れる、あるいは両方が起こる可能性が高いです。
50cmクラスのシーバス(フッコ)の重量は1kg以上になります。これをアジングロッドで抜き上げようとするのは、かなり無謀な試みと言わざるを得ません。実際、多くの失敗例が報告されています。
先日、アジングタックル(ロッド:ブルカレ610、ライン:フロロ2.5lb)使用中に、目視で50cm前後のフッコがかかりました。とりあえず、寄せることまではしましたが、抜き上げが無理だろうと判断し、ラインを持って上げようとしたら、ジグヘッドとラインの結束部で切れました。
この事例では、抜き上げを諦めてライン手繰りに切り替えていますが、それでも結局切れてしまっています。フロロ2.5lbで50cmのシーバスは、どう頑張っても無理ということですね。
🚫 大型外道への対処法
- シーバス(40cm以上) – ランディングネット必須、または水際まで寄せてハンドランディング
- チヌ(35cm以上) – 同様にネットまたはハンドランディング、根に潜られないよう注意
- カサゴ(25cm以上) – 根に潜る前に一気に浮かせる、抜き上げは20cmまで
- メバル(25cm以上) – 繊細な口なのでネット推奨、無理な抜き上げは口切れのリスク
特にチヌは、掛かった瞬間に根や障害物に潜り込もうとする習性があります。磯釣りの世界では「チヌは竿で釣れ」と言われるほど、ロッドワークが重要な魚です。しかし、アジングロッドのような繊細なタックルでは、チヌの強烈な引きに対抗するのは困難です。
アジングロッドでチヌを狙う場合、やはり「そこそこパワーのあるロッド」をセレクトすべきです。アジングロッドでチヌを釣ることができます。ただし、最適解でないことを理解した上でのゲーム展開、タックル編成を行う必要性がある。
この指摘は重要です。アジングロッドでも外道を釣り上げることは可能ですが、それは「最適解ではない」ということです。特に抜き上げに関しては、大型外道は基本的にNGと考えるべきでしょう。
また、アジングロッドでの大型魚とのやり取りは、ロッドに想定外のダメージを与える可能性があります。見た目には問題なくても、内部的にマイクロクラックが入っていることもあり、次回の使用時に突然折れるということもあり得ます。
大型外道が掛かった場合の最善策は、ランディングネットやタモを用意しておくことです。「アジングだからネットは不要」と考えず、念のため携行しておくことで、貴重な大物を確実にキャッチできるでしょう。
アジングロッドでの抜き上げを成功させる実践テクニック
- ロッドの角度は60度以内に抑えること
- ドラグ設定は「やや締め」がベスト
- ロッドの中ほどを持つのは厳禁
- 短いロッド(5~6ft)の方が有利な理由
- フィッシングギップとランディングネットの使い分け
- バラシを減らすドラグとロッドワークの連携
- まとめ:アジングロッドでの抜き上げは慎重に
ロッドの角度は60度以内に抑えること
抜き上げで最も重要なポイントは、ロッドの角度を60度以内に保つことです。これを守るだけで、ロッド破損のリスクは大幅に減少します。しかし、実際の釣り場では、興奮や焦りからついロッドを立ててしまいがちです。
折れる直前は第5ガイドぐらいから先がものすごく曲がっていて、角度が120度以上になっていたと思います。私が「ロッドが折れる」と一声かけようとした瞬間、バシっと折れた、のを見たことがあります。
この体験談は衝撃的ですね。120度というのは、ほぼ垂直に立てた状態です。このような角度になると、ティップ部分に過度な負荷が集中し、簡単に折れてしまいます。特に高感度を追求した繊細なアジングロッドは、折れやすい傾向にあります。
正しい角度管理のためには、以下のポイントを意識しましょう:
📐 角度管理のチェックポイント
- 魚を寄せる段階 – ロッド角度45度程度、バット部分で魚の引きを受け止める
- 水面直下に来たら – ロッドを前方に倒し始め、角度を40度程度に
- 抜き上げの瞬間 – 角度を30~40度に保ったまま、体ごと後退
- 水面から離れたら – そのままの角度で後方に引き続ける
- 完全に抜き上げ完了まで – 60度を超えないように意識し続ける
特に重要なのが、「体ごと後退する」という動作です。ロッドを上げるのではなく、自分が後ろに下がることで魚を引き上げるイメージです。この動作により、ロッドの角度が急激に立つことを防げます。
また、足場の高さによって戦略を変える必要があります。海面まで1m程度の低い足場であれば、比較的容易に角度を保てます。しかし、3m以上の高い堤防では、物理的に角度を寝かせるのが難しくなります。そのような場所では、最初から抜き上げを諦めてネットを用意しておく方が賢明です。
さらに、ロッドの長さも角度管理に影響します。ショートロッド(5~6ft)の方が角度管理がしやすく、ロングロッド(7~8ft)は角度が立ちやすい傾向があります。これについては後ほど詳しく解説します。
夜釣りの場合は、視覚的にロッドの角度を確認しにくいため、より注意が必要です。ヘッドライトでロッドを照らして角度を確認するか、感覚で覚えるまで練習するしかありません。初心者のうちは、昼間に練習して角度感覚を身につけることをおすすめします。
ドラグ設定は「やや締め」がベスト
抜き上げにおけるドラグ設定は、非常に微妙なバランスが求められます。緩すぎると魚をコントロールできず、締めすぎるとラインブレイクやロッド破損のリスクが高まります。多くのベテランアングラーが推奨するのは、「やや締め」の設定です。
一般的に、アジングでのドラグ設定は「ラインの破断強度の3分の1程度」と言われています。つまり、エステル0.2号(破断強度450g)であれば、150g程度の負荷で滑り出すように調整するわけです。しかし、これは通常の釣りの話であり、抜き上げ時にはやや締める必要があります。
ドラグが出なかったせいもあり、そのまま抜き上げようと試みましたが中々上がってきません。さらに締めこみ、いつもより30分程締めた状態でやっと抜き上げ成功です。
この体験談から分かるように、抜き上げ時には通常よりドラグを締める必要があります。ただし、「30分締めた」という表現はドラグノブを時計回りに30分(0.5時間?)回転させたという意味ではなく、おそらくドラグノブの目盛りや角度の話でしょう。
🎚️ シチュエーション別ドラグ設定
| 状況 | ドラグ設定 | 理由 |
|---|---|---|
| 通常のやり取り | 破断強度の1/3 | ラインブレイク防止、魚の突っ込みに対応 |
| 寄せの段階 | やや締める(1/2程度) | 魚をコントロールしやすくする |
| 抜き上げ直前 | さらに締める(2/3程度) | 一気に引き上げるためのパワー確保 |
| 大型外道時 | 緩める(1/4以下) | ロッド保護、時間をかけて弱らせる |
ドラグ設定で注意すべき点は、締めすぎによるロッドへのダメージです。ドラグを固くすると、魚の暴れる力が直接ロッドに伝わります。繊細なアジングロッドでは、この衝撃がロッド破損につながる可能性があります。
したがって、ドラグは「やや締め」を基本としつつ、ロッドのしなりで衝撃を吸収することが重要です。ロッドをしっかり曲げることで、ドラグとロッドの両方で負荷を分散させるイメージですね。
また、リールのドラグ性能も重要な要素です。エントリーモデルのリールでは、ドラグの効きが不安定だったり、微調整が難しいこともあります。できれば、ミドルクラス以上のリールを使用した方が、細かなドラグ調整がしやすいでしょう。
実際の釣り場でドラグを調整する際は、ラインを手で引いてチェックします。強めに引いた時にジリジリと滑り出すくらいが「やや締め」の目安です。ただし、この感覚は経験によって変わってくるため、何度も釣行を重ねて自分なりの最適値を見つけることが大切です。
ロッドの中ほどを持つのは厳禁
抜き上げ時に**ロッドの中ほど(バット部分)を持つのは厳対です。これをやってしまうと、ティップ側だけが極端に曲がり、最も細い部分に負荷が集中してしまいます。結果として、簡単に折れてしまう原因になります。
横へ魚を上げてくる場合も、ロッドの中ほどに手を添えることもやめましょう。先の方だけが極端に曲がって、ロッドは折れます。
この指摘は非常に重要です。特に初心者は、魚が重いと感じると無意識にロッドの中ほどを持ってしまいがちです。しかし、これは最悪の行為です。ロッドは全体で曲がることで負荷を分散する設計になっているため、一部だけに負荷が集中すると簡単に破損します。
正しい持ち方とテクニックは以下の通りです:
✋ 正しいロッドの持ち方と抜き上げ動作
- グリップエンドをしっかり握る – 人差し指と中指でトリガー(リールシート)を挟む
- もう片方の手はリールを支える – ロッド本体は絶対に持たない
- 肘を体に引きつける – 腕だけでなく体全体を使う
- 膝を使って体を沈める – より低い姿勢から引き上げる余地を作る
- 腰を使って後退 – 後ろに下がる動作で自然と抜き上げられる
特に重要なのが、「体全体を使う」という意識です。腕の力だけで魚を持ち上げようとすると、どうしてもロッドの中ほどを持ちたくなります。しかし、体全体、特に腰と膝を使えば、グリップを持ったままでも十分な力を発揮できます。
また、足場の位置取りも重要です。抜き上げる方向に体重を移動できるよう、あらかじめ後方にスペースを確保しておきましょう。障害物がない場所で釣りをすることが、安全な抜き上げにつながります。
さらに、ロッドの長さによっても持ち方の重要性は変わります。ショートロッド(5~6ft)の場合は比較的問題になりにくいですが、ロングロッド(7~8ft)では中ほどを持つ誘惑が強くなります。長いロッドほど、グリップエンドをしっかり持つ意識が必要です。
夜釣りでは視界が悪いため、無意識にロッドの中ほどを持ってしまうこともあります。ヘッドライトで手元を確認するか、常にグリップエンドに意識を集中させることが大切です。万が一、ロッドを持ち変える必要がある場合は、いったん魚を緩めてから行いましょう。
短いロッド(5~6ft)の方が有利な理由
抜き上げに関しては、ショートロッド(5~6ft)の方が圧倒的に有利です。これには複数の理由があり、物理的な側面と操作性の両面から説明できます。ロングロッドにもメリットはありますが、こと抜き上げに関してはショートロッドに軍配が上がります。
まず、ショートロッドが有利な理由を整理してみましょう:
🎣 ショートロッドが抜き上げに有利な理由
| 理由 | 詳細 | 効果 |
|---|---|---|
| 取り回しの良さ | 軽量で振り回しやすい | 角度調整が容易、咄嗟の対応ができる |
| 角度を寝かせやすい | 短い分、低い角度を保ちやすい | ロッド破損リスクの低減 |
| ティップへの負荷集中を防ぐ | 全体で負荷を分散しやすい | 折れにくい |
| 重心が近い | 操作の支点が手元に近い | 力のコントロールがしやすい |
| 風の影響を受けにくい | ロッドが風に煽られにくい | 安定した抜き上げ動作 |
特に重要なのが、「角度を寝かせやすい」という点です。前述の通り、抜き上げではロッド角度が最重要ですが、ロングロッドでは物理的に角度を寝かせにくいのです。例えば、8ftのロッドを60度以内に保とうとすると、かなり広いスペースが必要になります。
短いロッドの方が竿を振り回しやすく、魚の引きにラインの角度を俊敏に変えることができたのです。ロングロッドの場合その場で耐えることはできても、振り回しにくく瞬間的な動きはできないので、やり取りには向いていない
この経験談は、磯釣りでの尾長グレとのやり取りに関するものですが、アジングにも通じる教訓です。ロングロッドは一見パワフルに見えますが、実際には「瞬間的な動き」ができないため、抜き上げのような繊細な操作には向いていないのです。
一方、ロングロッドのメリットも存在します:
🎣 ロングロッドのメリット(抜き上げ以外)
- 飛距離が出る – 遠投性能が高い
- ラインメンディングしやすい – 長いロッドでラインをコントロール
- 足場の高い場所に対応 – 海面まで距離がある堤防で有利
- バットパワーがある – 大型魚とのやり取りに余裕
しかし、これらのメリットは抜き上げには直接関係しません。むしろ、足場の高い場所では、ロングロッドでも抜き上げは困難であり、結局ランディングネットが必要になります。
したがって、抜き上げを重視するなら、5~6ft台のショートロッドを選ぶのがベストです。特に、足場の低い漁港や河口部でのアジングでは、ショートロッドの取り回しの良さが光ります。21月下美人MXアジング510UL-Sのような5ft台のロッドであれば、25cmクラスのアジでも安全に抜き上げることができるでしょう。
ただし、釣り場の状況や釣り方によって最適なロッド長は変わります。遠投が必要な場合や、フロートを使う場合は7~8ftのロッドが適しています。自分の釣りスタイルに合わせて、メインロッドとサブロッドを使い分けるのも一つの方法です。
フィッシングギップとランディングネットの使い分け
抜き上げが難しい状況では、フィッシングギップやランディングネットの使用を検討すべきです。これらの道具を適切に使い分けることで、確実に魚をキャッチでき、同時にロッドやラインへのダメージも防げます。
まず、それぞれの道具の特徴を整理しましょう:
🎣 ランディングツールの比較
| ツール | メリット | デメリット | 適した状況 |
|---|---|---|---|
| 抜き上げ | 道具不要、手返しが早い | ロッド破損リスク、サイズ制限 | 20cm以下、足場が低い |
| フィッシングギップ | コンパクト、素早く掴める | 魚にダメージ、暴れると外れる | 25cm以上、リリースしない魚 |
| ランディングネット | 確実、魚に優しい | かさばる、セッティングに時間 | 30cm以上、足場が高い、リリース前提 |
| ハンドランディング | 道具不要、魚に触れる | 水面まで手が届く必要、危険 | 超低足場、小型魚 |
フィッシングギップ(魚ばさみ)は、魚の口や体を挟んで引き上げる道具です。コンパクトで携帯しやすく、素早く使えるのがメリットです。しかし、魚にダメージを与えやすく、特にリリース前提の釣りには向きません。
「フィッシンググリップ(魚ばさみ)」を使うときも、注意が必要です。「ランディングネット」を使うのが一番ですが、ランディングネットに魚を入れる際、ロッドを立てたまま暴れる魚をネットで追いかけている人もよく見ます。
この指摘は重要です。ランディングネットを使う際も、ロッドを立てたままにしてはいけません。ネットで魚をすくう際は、ロッドを横に倒し、魚をネットの方に誘導するのが正しい方法です。
ランディングネットの正しい使い方は以下の通りです:
🥅 ランディングネットの正しい使用手順
- 魚を足元まで寄せる – ロッドは45度程度を保つ
- ネットを水中に沈める – 先にネットを準備しておく
- ロッドを横に倒す – 魚が水面に浮いたタイミングで
- 魚をネットの上に誘導 – ネットを魚に近づけるのではなく、魚をネットに近づける
- ネットを持ち上げる – 魚が完全にネット内に入ってから
- ロッドのテンションを緩める – ネットに入った時点でテンションを抜く
特に重要なのが、「魚をネットに近づける」という意識です。ネットを魚に近づけようとすると、魚が驚いて逃げてしまいます。魚をネットの上に誘導し、下からすくい上げるイメージが正解です。
また、ランディングネットの選び方も重要です。アジングでは、軽量でコンパクトなネットが適しています。玉の枠の直径は30~40cm程度、柄の長さは3~5m程度が使いやすいでしょう。あまり大きなネットは取り回しが悪く、アジングには不向きです。
フィッシングギップは、持ち帰る魚限定で使うのがおすすめです。特に、型の良いアジを確実にキャッチしたい場合には有効です。ただし、使用する際は魚をしっかり弱らせてから使いましょう。元気な状態で使うと、暴れて外れてしまうことがあります。
究極的には、状況に応じて使い分けるのがベストです。20cm以下なら抜き上げ、25cm前後ならフィッシングギップ、30cm以上や足場の高い場所ではランディングネット、という感じでしょうか。自分の釣り場の状況や、釣れるサイズに合わせて準備しておくことが大切です。
バラシを減らすドラグとロッドワークの連携
抜き上げの成功率を高めるには、ドラグとロッドワークの連携が重要です。これらは別々に機能するのではなく、一体となって魚の動きに対応する必要があります。特にアジングのような繊細な釣りでは、この連携が釣果を大きく左右します。
まず、ドラグとロッドワークの役割分担を理解しましょう:
⚙️ ドラグとロッドワークの役割
| 要素 | 主な役割 | タイミング |
|---|---|---|
| ドラグ | 過度な負荷の吸収、ラインブレイク防止 | 魚の突っ込み時、急な動き |
| ロッドワーク | 魚の動きの先読み、角度調整 | 常時、特に寄せと抜き上げ時 |
| 両者の連携 | スムーズな負荷分散、バラシ防止 | やり取り全体を通じて |
ドラグは「最後の防波堤」のような役割です。魚が急に走った時、ロッドだけでは吸収しきれない負荷を、ドラグが滑ることで逃がします。一方、ロッドワークは「予防」の役割です。魚の動きを予測し、ロッドの角度や位置を調整することで、そもそもドラグが滑る必要がない状況を作り出します。
実際の連携例を見てみましょう:
🎯 シーン別のドラグ×ロッドワーク連携
シーン1:魚が横に走った時
- ドラグ:やや締め(負荷の50%程度で滑る設定)
- ロッド:魚の走る方向に竿先を向ける→ラインとロッドの角度を直線に近づける
- 結果:ドラグの滑りが最小限に、魚をコントロールしやすい
シーン2:魚が下に突っ込んだ時
- ドラグ:やや緩め(負荷の30%程度で滑る設定)
- ロッド:横に倒して負荷を分散、バットで受け止める
- 結果:根に潜られる前に浮かせられる
シーン3:抜き上げの瞬間
- ドラグ:締める(負荷の70%程度で滑る設定)
- ロッド:角度30~40度を保ち、体ごと後退
- 結果:一気に抜き上げられる、ロッド破損も防げる
このように、状況に応じてドラグ設定を変え、同時にロッドワークも調整することで、最適なやり取りができます。ただし、実際の釣り場でドラグをその都度調整するのは難しいため、基本は「やや締め」に設定しておき、ロッドワークで微調整するのが現実的です。
また、リールのドラグ性能も重要な要素です。特に、スムーズなドラグの滑り出しが重要です。ガクンとした滑り出しでは、その瞬間にバラシが発生しやすくなります。ミドルクラス以上のリールでは、ATD(オートマチックドラグシステム)やX-Ship(耐久性の高いギア構造)などの機能により、スムーズなドラグを実現しています。
ドラグ性能が大事な釣りで、抜き上げにもドラグを使う。ドラグを滑らせすぎずうまく食いつかせながら、サオを頭上に差し上げるようにして抜き上げるのだ。
この記述にあるように、「ドラグを滑らせすぎず、うまく食いつかせる」というのがポイントです。完全に滑らない状態でも、完全に滑る状態でもダメなんですね。この微妙なバランスが、抜き上げの成功率を高めます。
さらに、ロッドのアクション(調子)も連携に影響します。ファストテーパー(先調子)のロッドは、ティップが敏感に反応するため、魚の動きを素早くキャッチできます。一方、レギュラーテーパー(胴調子)のロッドは、バット部分も含めて全体で負荷を受け止めるため、粘り強いやり取りができます。
自分の使っているロッドとリールの特性を理解し、それに合わせたドラグ設定とロッドワークを習得することが、バラシを減らす最良の方法と言えるでしょう。これは経験を積むことでしか身につかないスキルですが、意識して練習すれば必ず上達します。
まとめ:アジングロッドでの抜き上げは慎重に
最後に記事のポイントをまとめます。
- アジングロッドでの抜き上げは25cmまでが現実的な限界である
- ラインの強度が抜き上げの成否を決める最大の要因である
- エステル0.2号では20cm前後、フロロ2.5lbでも25cmが限界
- 尺アジ(30cm)以上はランディングネットの使用が推奨される
- シーバスやチヌなどの大型外道は抜き上げNG
- ロッドの角度は60度以内に保つことが絶対条件である
- ロッドを立てすぎると、ティップに負荷が集中して折れる
- 抜き上げ時はドラグを「やや締め」に設定するのがベスト
- ロッドの中ほどを持つのは厳禁、必ずグリップエンドを持つ
- ショートロッド(5~6ft)の方が抜き上げに有利である
- 取り回しの良さと角度管理のしやすさがショートロッドの強み
- 体全体を使って後退する動作が正しい抜き上げテクニック
- ドラグとロッドワークの連携がバラシを減らす鍵である
- 状況に応じてフィッシングギップやランディングネットを使い分ける
- 無理な抜き上げはロッド破損の原因、慎重な判断が必要である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- Yahoo!知恵袋 – アジングタックルで不意な大物が掛かったときの対応について
- sohstrm424のブログ – アジング備忘録 ⑩ ロッドは折れる
- TSURINEWS – 今さら聞けないアジングのキホン:バラしにくい「抜き上げ」術とは?
- Yahoo!知恵袋 – アジングロッドについてです。
- リグデザイン – アジングロッドで「チヌ」は釣れる?
- LureNewsR – アジングロッドはショートが有効?
- アジング一年生re – エステルライン0.2号の切れないで抜き上げできるアジの大きさ
- 基本は鯰とナマズ釣り – 鯰釣りで使っているロッドについて
- AJI HUNT – 2023年12月17日のアジングブログです。
- 孤独のフィッシング – アジングロッドでメバリングはできる?
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。