横浜でアジングを楽しむ人が年々増えています。工業地帯からの温排水の影響で、東京湾には豊富なプランクトンが存在し、一年中アジを狙うことができます。特に横浜エリアは、春先や秋のハイシーズンには体高のある良型アジが狙えることでも知られています。
アジングは釣り方や仕掛けによって成果が大きく変わる釣りです。横浜エリアでは、漁港の常夜灯周りや河川の明暗部、岸壁沿いの明暗部などが有力なポイントとなっています。この記事では、横浜でアジングを楽しむために必要な情報を、シーズン、タックル、釣り方まで詳しく解説していきます。
記事のポイント!
- 横浜エリアの季節ごとの釣果パターンと狙い目の時期
- 初心者でも釣果が期待できる具体的なポイントと攻め方
- アジングに最適なタックルセッティングとワームの選び方
- 確実に釣果を上げるための実践的なテクニックとコツ
横浜でアジングを始めるための完全ガイド
- 横浜のアジングシーズンと釣れる時期を解説
- アジングに最適な横浜エリアの釣り場13選
- 初心者でも釣果が期待できる横浜の常夜灯ポイント
- 横浜アジングで使用する基本タックル
- アジングで重要なジグヘッドの選び方と使い分け
- 横浜エリアで効果的なワームの選定方法
横浜のアジングシーズンと釣れる時期を解説
横浜エリアのアジングシーズンは、7月から9月の真夏が豆アジを狙うベストシーズンとなっています。この時期は特に豆アジの攻略が重要で、リグや場所選びが釣果を左右します。
秋になるとイワシなどの小魚が沿岸に寄ってくるため、大型のアジが期待できる時期となります。この時期は良型アジを狙う絶好のチャンスです。
春先から初夏にかけては産卵期となり、その後豆アジ釣りのシーズンに入ります。ただし、年によって若干の時期のズレがあることも覚えておく必要があります。
アジングは夜間の方が釣りやすい特徴があります。これは疑似餌を見切られにくいという利点があるためです。特に夕まずめから夜にかけての時間帯が狙い目です。
東京湾のアジにはオフシーズンがないと言われており、工場の明かりや埠頭の作業灯、温排水の影響で一年中アジを狙うことが可能です。特に横浜エリアは、工業地帯が多く、豊富なプランクトンが存在するため、年間を通じて安定した釣果が期待できます。
アジングに最適な横浜エリアの釣り場13選
横浜でアジが釣れる主なポイントをご紹介します。まず大黒海づり施設は、有料の釣り場ですが常に釣り人が入っており、コマセの効果で魚が集まりやすい特徴があります。
本牧海づり施設も同様に有料施設で、大黒海づり施設と同じ会社が運営しています。両施設ともホームページで釣果情報を確認できるため、出発前のチェックに便利です。
根岸港・根岸湾は首都高からすぐのところにある広大な釣り場で、収容人数も多いため混雑時でも釣り場を確保しやすい特徴があります。特に火力発電所方面の奥のポイントでアジが釣れやすく、夜間はどこでも釣れる可能性があります。
磯子海づり施設は、足場が金網となっているため小さい魚を釣り上げる際は注意が必要です。海面までの距離もあり、やや釣りにくい面もありますが、釣果はホームページで確認可能です。
杉田臨海緑地は、タチウオも良く釣れるポイントとして知られています。近くの釣具店に定期的に釣果情報が掲載されるため、最新の状況を確認しやすいです。
初心者でも釣果が期待できる横浜の常夜灯ポイント
横浜でアジを狙う際は、常夜灯のある場所が重要なポイントとなります。常夜灯の光に集まるプランクトンを求めて小魚が集まり、それを追ってアジも集まってきます。
特に常夜灯の光が海面を照らしている場所と暗い部分の境目が、アジの活性が高まるポイントです。この明暗の境目を狙うことで、効率的に釣果を上げることができます。
夜間の釣りでは、道の街灯でも十分な効果があります。港湾エリアの後ろに設置されている街灯付近も有効なポイントとなります。また、人間の視認性も確保できるため、安全に釣りを楽しむことができます。
アジは比較的水深のある層を回遊していることが多いため、常夜灯周辺でもボトム付近を意識した釣り方が効果的です。特に潮の流れがある場所は、餌となる生物も多く集まるため、良いポイントとなります。
港湾エリアの常夜灯周辺は、アジの定番ポイントとして多くの釣り人に知られています。休日は混雑することもありますが、平日の夜間であれば比較的空いていることが多いです。
横浜アジングで使用する基本タックル
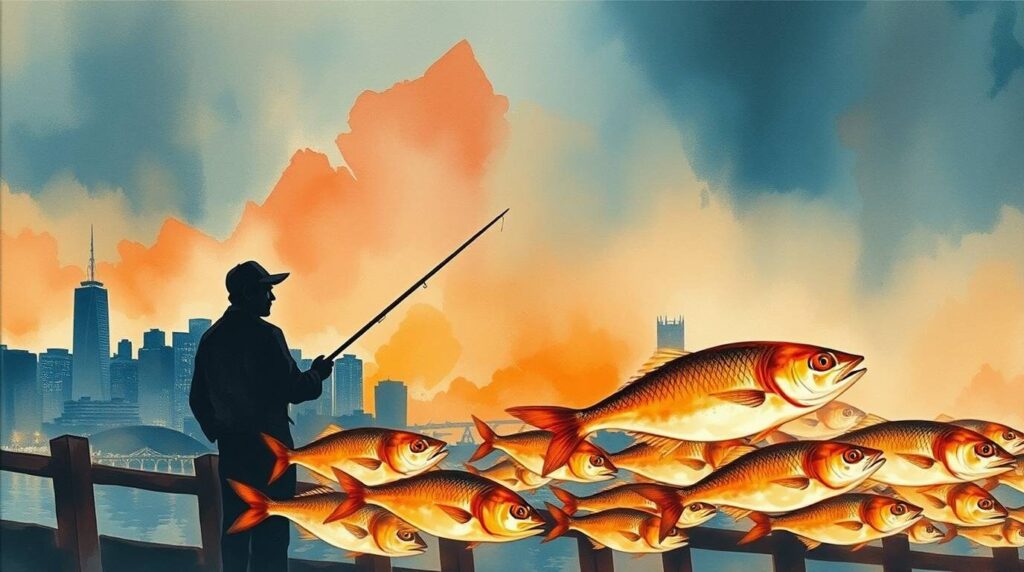
アジングで使用するロッドは、5-6.4フィートのものが適しています。特に5フィート台の短いロッドは取り回しが良く、ボートアジングにも使えるため重宝します。
リールは1000から2000番を使用し、ラインはエステルライン0.3号が標準的です。リーダーには0.8-1.0号を使用します。PEラインはアジングには向いていないため、エステルラインの使用がおすすめです。
ジグヘッドは1.2-3.0g(1.5g基準)を用意し、深場や潮が早い場合は4.0gまで必要となることがあります。潮の流れや釣り場の状況に応じて、適切な重さを選択することが重要です。
陸っぱりで使用しているアジングロッドで十分対応可能ですが、ジグヘッド単体に向かない強めのロングロッドは不向きです。ティップが繊細で、アタリを取りやすいロッドを選ぶことがポイントです。
ドラグの設定は非常に重要で、アジは口が弱いため、強すぎると魚が掛かっても針が抜けてしまう可能性があります。リールだけを持った時に、リールがチリチリと音を立てながら落ちていく程度の緩めの設定が適しています。
アジングで重要なジグヘッドの選び方と使い分け
15cm以下の豆アジを狙う場合、ジグヘッドは小さなものを選択する必要があります。針の長さや大きさは、対象となるアジのサイズに合わせて選ぶことが重要です。
基本的には1gのジグヘッドからスタートし、そこから状況に応じて0.8g、0.6gと軽いものや、1.3g、1.5gと重いものを使い分けていきます。特に0.6g以下の軽量なものを使えることが、攻略の近道となります。
ジグヘッドとワームの組み合わせでは、まっすぐに刺すことが重要です。曲がって刺さっていると、アクション時にくるくる回ってしまい、スムーズな誘いができなくなってしまいます。
潮の流れや水深によってジグヘッドの重さを変える必要があります。風が強い場合や水深が深い場所では重めのジグヘッドを、ナチュラルな動きを演出したい場合は軽めのジグヘッドを選択します。
整理用のケースに重さごとに分けて収納し、袋の重さが書いてある部分も一緒に入れておくと、現場での選択がスムーズになります。使用頻度の高い1.0g~1.5g前後のジグヘッドは多めに用意しておくと安心です。
横浜エリアで効果的なワームの選定方法
アジ用のワームは、基本的に小さめのサイズがメインとなります。代表的なものとしては、アジール2.0インチやピンチ1インチなどが挙げられます。
常夜灯が当たりくっきりと明暗ができる場所では、シルエットがはっきりと出るワームが効果的です。ただし、アジは大型でも口が小さいため、大きすぎるルアーは逆効果となってしまいます。
豆アジが渋い時には、意外とボリュームのあるワームが効果を発揮することがあります。例えば、セクシービー2.0インチなどの吸い込みを妨げない柔らかいワームがおすすめです。特にスーパーソフトタイプは効果的です。
ワームは色ごとにケースに分けて収納することをおすすめします。クリアカラーとチャートカラーを一緒に保管すると色が映り込んでしまう可能性があるため、分けて収納するのがベストです。
実践的な使い方としては、まずは濃い目の色から使用してみて、反応を見ながら薄い色に変更していくという方法が効果的です。ケムが入っているものと入っていないものも状況に応じて使い分けることで、より多くのチャンスを作ることができます。
横浜アジングを成功させるためのポイント解説
- 潮の流れと時間帯による釣果の違い
- 横浜エリアでアジを探すコツと実践テクニック
- 横浜アジングでよく釣れるポイントの特徴
- アジの美味しい持ち帰り方と血抜きのコツ
- まとめ:アジング横浜で確実に釣果を上げるポイント
潮の流れと時間帯による釣果の違い
潮の流れが入ってくるポイントは、アジングにおいて重要な要素となります。運河の中の淀んでいる場所や、流れが全く入ってこないような場所では、アジは釣れにくい傾向にあります。
夜釣りの場合、明暗の境目を意識することが重要です。特に常夜灯周辺では、光に集まるプランクトンを追って小魚が集まり、それを狙ってアジが回遊してきます。
アジングは疑似餌を見切られにくいという点でも、夜の方が釣りやすい特徴があります。日中と比べて魚が警戒心を緩める夜間は、より自然な誘いでアジを釣ることができます。
水深のある場所や流れがある場所も狙い目です。手前が浅く沖が深いような場所は、アジが好む環境の一つとなっています。
海水温が上がってくると、アジはより過ごしやすく餌の豊富な場所を探すようになります。特に河川周辺は、水温が比較的安定し、流れもあるため餌も豊富で、酸素量も多いため、有力なポイントとなります。
横浜エリアでアジを探すコツと実践テクニック

まずはボトムに付けることを覚えると良いでしょう。糸のたわみを見ながら、落ちていく感覚を掴むことが重要です。糸が止まった時がボトムに到達したタイミングです。
アジを探る基本的な動作は、3回シャクって止めるという動作の繰り返しです。シャクリはエギングのように大きく動かすのではなく、竿先をチョンチョンと小さく動かす程度で十分です。
チョンチョンと動かした後の止めている間に、アジが食ってくることが多いです。この時、ツンという明確なアタリだけでなく、ズズズというような微細なアタリにも注意を払う必要があります。
アタリがあった場合は、ワンテンポ遅らせてゆっくりとアワセを入れることで、バラシを減らすことができます。アジは口が弱いため、強すぎるアワセは禁物です。
動かし過ぎると違和感を与えてしまうため、ワームの形状を利用してよりナチュラルに誘うことを意識すると良いでしょう。特に流して釣る釣り方の場合は、控えめな動作が効果的です。
横浜アジングでよく釣れるポイントの特徴
横浜エリアの釣り場は、9割型フェンス(転落防止柵)があり、いわゆる”The漁港”は少ないのが特徴です。多くの釣り場は立ち入り禁止となっているため、釣りができる場所は混雑しやすい傾向にあります。
工場の明かりや埠頭の作業灯、温排水の影響で、東京湾には豊富なプランクトンが存在します。これにより、体高のある良型アジが狙えるポイントが多く存在します。
横浜エリアでは柵が多いものの、アジは手前の岸壁際の浅い明暗を回遊していることが多いです。横に投げられない場合は、後ろに下がって岸壁際を狙うテクニックも有効です。
河川がらみの場所は、比較的水温が安定し流れもあるため、餌も豊富で酸素量も多いポイントとなっています。特に水深のある場所、流れがある場所は狙い目となります。
夜間は、工場の明かりや埠頭の作業灯の周辺が有効なポイントとなります。これらの光に集まるプランクトンを求めて小魚が集まり、それを追ってアジも集まってきます。
アジの美味しい持ち帰り方と血抜きのコツ
アジを美味しく持ち帰るための準備として、クーラーボックスと氷が必要です。クーラーボックスには海水を入れ、氷で冷やしておくことがポイントです。
血抜きの手順は、まずアジの目の後ろの部分を小さなハサミで切り、神経を締めます。次に、鰓の上部にある太い血管を切ります。サバのように首を切る必要はなく、上部の血管だけを切ることで十分です。
血抜きをした後は、氷の入った冷たい水の中でアジを振り、中の血を抜いていきます。この作業により、より多くの血抜きが可能となり、美味しく食べることができます。
最終的な保管は、氷の入ったクーラーボックスに直接入れるのではなく、ビニール袋に入れて保管します。氷買った時の袋を再利用すると便利です。
この方法で保管することで、アジの鮮度を最大限保ったまま持ち帰ることができ、刺身やなめろう、骨せんべいなど、様々な料理で美味しく味わうことができます。
まとめ:アジング横浜で確実に釣果を上げるポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- 横浜のアジングシーズンは7~9月が豆アジ、秋は大型アジが狙える
- 常夜灯周辺の明暗の境目が特に有効なポイント
- 基本タックルはエステルライン0.3号、リーダー0.8-1.0号が標準
- ジグヘッドは1.2-3.0g(1.5g基準)を状況に応じて使い分ける
- 基本的な釣り方は3回シャクって止める動作の繰り返し
- アタリは「ツン」だけでなく「ズズズ」という感触にも注意
- 工場の明かりや埠頭の作業灯周辺は良型アジが期待できる
- 河川周辺は水温が安定し餌も豊富な有力ポイント
- ドラグは緩めに設定し、アジの弱い口への配慮が重要
- 血抜きは目の後ろと鰓の上部の血管を切ることがポイント
- 横浜の特徴として9割がフェンス付きで、漁港は少ない
- 温排水の影響で一年中アジを狙うことが可能
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。






