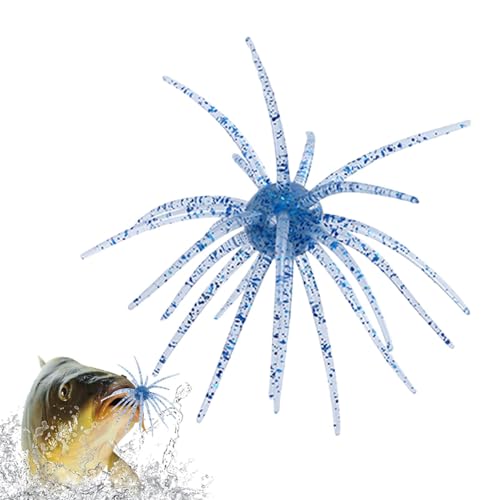バス釣りを趣味にしている方なら、「オワコン」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。釣り場の減少や特定外来生物指定による規制強化、さらにはメーカーの海釣りシフトなど、バス釣り業界を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。
実際に、各地で野池が釣り禁止になり、大手釣具メーカーがソルトルアー製品にシフトするなど、バス釣り業界の衰退を示す動きが見られます。この記事では、バス釣り業界の現状と課題、そして今後の展望について詳しく解説していきます。
この記事のポイント!
- バス釣り業界が直面している具体的な問題点
- 釣り場の減少と規制強化の実態
- メーカーの対応戦略と業界動向
- バス釣り業界の今後の展望と可能性
バス釣りがオワコンと言われる理由と現状分析
- 釣り場の減少と環境規制が深刻化
- プレッシャーの増加で釣果が激減
- 特定外来生物指定による規制強化
- メーカーの海釣りシフトが加速
- 後継者不足と高齢化問題
- マナー違反による釣り場閉鎖の実態
釣り場の減少と環境規制が深刻化
埼玉県では昔の野池が次々と釣り禁止になっており、バス釣りのできる場所が急速に減少しています。特に農業用ため池での釣りが禁止されるケースが増加しているのが現状です。
琵琶湖や霞ヶ浦でもバスが減少し、かつての賑わいは失われつつあります。首都圏でバス釣りを楽しむなら、相模湖や津久井湖、芦ノ湖、河口湖など、限られた場所に絞られてきています。
入間川ではコクチバスが釣れ、秩父地方の合角ダムではオオクチバスが生息していますが、2019年の東日本台風以降は釣果が激減しています。現在は、ハイシーズンでもボートに乗って釣る必要があり、以前のような手軽さは失われています。
バス釣り場の減少は、地域の釣具店にも影響を与えており、チェーン店の統廃合も進んでいます。新しい世代の参入も少なく、釣り場でも子供の姿を見かけることが少なくなっています。
池の水を抜いての駆除活動も行われており、バス釣りを取り巻く環境は厳しさを増す一方です。外来魚駆除が盛んに行われ、生態系を元に戻す取り組みが各地で進められています。
プレッシャーの増加で釣果が激減
15年前と比べると、バスの釣果は著しく低下しています。20cmクラスでも嬉しいと感じるほど、魚影が薄くなっているのが現状です。
プレッシャーの高まりにより、バスが釣りづらくなっているという声が多く聞かれます。特に初心者にとっては、釣果を得ることが難しい状況となっています。
ハイプレッシャーな環境では、従来の釣り方では通用しなくなってきており、テクニックの向上が必要不可欠となっています。しかし、それが新規参入者の障壁ともなっています。
フィールドのハイプレッシャー化は、後進の育成を困難にしており、バス釣り業界の衰退の一因となっています。初心者が気軽に始められる環境が失われつつあります。
子供の頃から気軽にバス釣りができた世代と比べ、現在の若い世代にとっては、ハードルが高くなっているのが実情です。
特定外来生物指定による規制強化
2005年6月、当時の小池百合子環境大臣の下で、ラージマウスバス(フロリダバスを含む)とスモールマウスバスが特定外来生物に指定されました。これにより、バス釣り業界は大きな転換点を迎えることになりました。
特定外来生物の指定後、都道府県によって再放流の規制が異なり、完全に禁止している地域と管理された形で認めている地域が混在しています。この規制の違いが、バス釣り人の活動範囲を制限する要因となっています。
業界全体として、特定外来生物指定に対する統一した対応が取れなかったことも、現在の状況を招いた一因となっています。2005年のフィシングショーでは、パブリックコメントの呼びかけ程度の対応に留まりました。
バス釣り団体、雑誌、釣具店、シマノ、ダイワといった業界全体が一体となって対応する必要があったにもかかわらず、それが実現しませんでした。
養殖できない魚種であるバスの資源管理という課題に対して、具体的な解決策を見出せていないのが現状です。入漁料による管理なども提案されていますが、実現には至っていません。
メーカーの海釣りシフトが加速
シマノやダイワといった大手メーカーが、バス釣り製品から海釣り製品へとシフトする動きを見せています。カタログを見ても、バス専用製品の掲載が減少傾向にあります。
メーカー各社は、バス製品の開発に慎重になっており、1ピースロッドなどの出荷制限のある製品は、今後数年で生産が終了する可能性も指摘されています。
ジャッカルやバスルアーメーカーも、海釣り製品の展開を強化しています。これは、市場規模の変化に対応した経営戦略の一環と考えられます。
釣具メーカーのバス離れは、製品開発の停滞や品揃えの縮小につながり、バス釣り人の選択肢を狭める結果となっています。
バス業界の市場規模縮小により、メーカーは利益の見込める海釣り市場へとシフトせざるを得ない状況となっています。商業的な観点からも、バス釣り専業での継続が難しくなってきているのです。
後継者不足と高齢化問題
バス釣り業界では、新規参入者の減少と高齢化が深刻な問題となっています。90年代のバス釣りブームで700万人いた人口が、70万人以下にまで減少したという報告もあります。
初心者向けの製品開発や情報発信が減少しており、メーカー側も新規ユーザーの獲得に消極的な姿勢を見せています。YouTube等のチャンネルでも、初心者向けのコンテンツが少なくなっています。
釣り業界全体で人手不足が問題となっており、特にバス業界では深刻です。釣具メーカーの社員募集よりもテスター募集の方が人気があり、業界の持続的な発展に影響を及ぼしています。
釣り場の減少と規制強化により、若い世代が気軽にバス釣りを始められる環境が失われつつあります。これは、次世代のバス釣り人口の育成を困難にしている要因の一つです。
新規参入者の減少は、業界の活力低下につながり、負のスパイラルを形成しています。この問題を解決しない限り、業界の衰退に歯止めをかけることは困難でしょう。
マナー違反による釣り場閉鎖の実態
90年代の大きなバス釣りブームの際、ゴミの投棄や違法駐車、騒音など、マナー違反が社会問題となりました。特に農業用の灌漑用水として使用されるため池での釣りが次々と禁止されていきました。
琵琶湖では、漁港内での釣りが禁止されたエリアがあります。これは、漁師の船にラインが絡んだり、ルアーが放置されたりする問題が発生したためです。一度釣りが禁止になったエリアは、その後も規制が継続されています。
河川でのゴミ問題は、実は家庭ごみが大半を占めていますが、釣り人が早朝など「普通の人がしない」時間帯に活動することで、近隣住民とのトラブルの原因となっています。
バス釣り業界の現状とこれからの展望
- 釣具業界の市場規模と今後の予測
- 釣り人口の推移と世代交代の課題
- メーカーの生き残り戦略とソルト参入
- 釣り場確保と管理の新たな取り組み
- プロトーナメントシーンの衰退
- まとめ:バス釣りオワコンの真実と今後の可能性
釣具業界の市場規模と今後の予測
2022年の世界の釣り市場規模は131億ドル(約1兆8995億円)で、2031年には191億ドル(約2兆7695億円)に成長すると予測されています。
コロナ禍による釣りブームの影響で、2021年には日本の釣り人口が約1200万人に増加しました。これは2006年と同程度の水準となっています。
世界的に見ると、中国では若年層を中心にルアーフィッシングが流行しており、2022年の調査では1億2000万人の釣り人口を抱えています。
しかし、日本国内の釣り業界には業界団体がなく、ルール変更や新設が増加する可能性があります。メーカーや釣具店の寄り合いはありますが、監督官庁との円滑なコミュニケーションが取れていない状況です。
高額な商品が売上の多くを占めているため、船釣りなど比較的高価な道具が必要な釣りの人口増加が業界にとって重要となっています。
釣り人口の推移と世代交代の課題
1998年には釣り人口が2020万人でピークを迎えましたが、その後は減少傾向が続いています。コロナ禍で一時的な回復は見られたものの、持続的な成長には課題が残ります。
新規参入者の獲得が難しくなっており、特に子供の姿が釣り場で見られなくなってきています。釣具店でも若い世代の来店が減少しているという声が聞かれます。
人手不足も深刻な問題となっており、特に社員としての就職希望者が少ないのが現状です。テスターやフィールドスタッフへの応募は多いものの、正社員としての採用は難しい状況が続いています。
社員として採用された場合、他社との並行したテスター契約が難しくなるなど、制限も多くなります。これが人材確保を困難にしている一因となっています。
労働環境の整備が遅れており、さらなる人手不足を招く悪循環に陥るリスクも指摘されています。
メーカーの生き残り戦略とソルト参入
大手メーカーのシマノやダイワは、バス製品からソルトウォーター製品へのシフトを加速させています。ジャッカル、一誠、ノリーズなど、多くのメーカーが海釣り製品の展開を強化しています。
メーカーも現状のバス市場では利益確保が難しいと判断し、成長が見込める海釣り市場への展開を進めています。売上データからもその傾向は明確です。
今後数年で、流通上出荷制限のある1ピースロッドなどの製品が絶滅する可能性も指摘されています。バス専用製品の開発も慎重になってきています。
メーカー側は初心者向けの製品開発やプロモーションに消極的で、現在のユーザー層を維持することに注力しています。新規ユーザーの開拓よりも、既存顧客の維持を重視する傾向が強まっています。
商業的な観点から見ても、バス釣り専業での継続は困難になってきており、事業の多角化が進んでいます。
釣り場確保と管理の新たな取り組み
バス釣り特区として、河口湖のような管理された釣り場を全国に増やす提案もありますが、実現にはまだ課題が残ります。狭山湖や多摩湖でも同様の話が出ていますが、具体的な進展は見られていません。
現状では、入漁料を徴収して管理する形態が一つの解決策として考えられています。しかし、具体的な実施例はまだ限られています。
合角ダムでは数年前からバス釣り客からも遊漁料を徴収し、ワカサギを放流する取り組みを始めています。ダム湖最寄りのコンビニで遊漁券を購入できる仕組みを導入しています。
しかし、都市部の飲料水源となっているダム湖では、釣り場としての開放に慎重な姿勢が続いています。水質保全の観点から、新規の釣り場開放は難しい状況です。
釣り場の管理には、ゴミ問題や駐車場の整備など、様々な課題があり、一朝一夕には解決できない状況が続いています。
プロトーナメントシーンの衰退
バストーナメントの「一般人」への訴求力は低下しており、以前のような盛り上がりは見られなくなっています。1995年度のバスクラシックでは、ファミコンソフトの会社がメインスポンサーを務めるなど、かつては大きな注目を集めていました。
現在は、中年のバスプロの中には日本に見切りをつけて渡米し、トーナメントに参加する傾向が強まっています。環境意識や生物多様性の価値観が重視される現代では、バスのプロアングラーになることは以前より難しくなっています。
本業を持ちながら、小さなメーカーのテスターとして釣具開発に携わる程度であれば、まだ可能性は残されています。釣りビジョンでは、数年前までそうした副業プロの活動を紹介する番組が放送されていました。
トーナメントの運営面でも課題が山積しています。「ラージマウスのみ」「スモールマウスのみ」といった偏った大会形式では、一般の釣り人の興味を引くことが難しくなっています。
こうした状況の中、プロトーナメントシーンは閉鎖的な世界となり、新たな盛り上がりを見せることが難しくなっています。
まとめ:バス釣りオワコンの真実と今後の可能性
最後に記事のポイントをまとめます。
- 釣り場の減少と規制強化が加速している
- 特定外来生物指定以降、業界全体の転換点となった
- メーカーは海釣り製品へのシフトを強めている
- 釣り人口は1998年の2020万人をピークに減少傾向
- 新規参入者の獲得が困難になっている
- プロトーナメントシーンは衰退傾向にある
- 業界団体の不在が規制対応を困難にしている
- 人手不足と労働環境の問題が深刻化
- 管理された釣り場の確保が今後の課題
- 世界的な市場は拡大傾向だが、日本国内は厳しい状況
- マナー違反による釣り場閉鎖が継続している
- バス釣り特区などの新しい取り組みが模索されている
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。