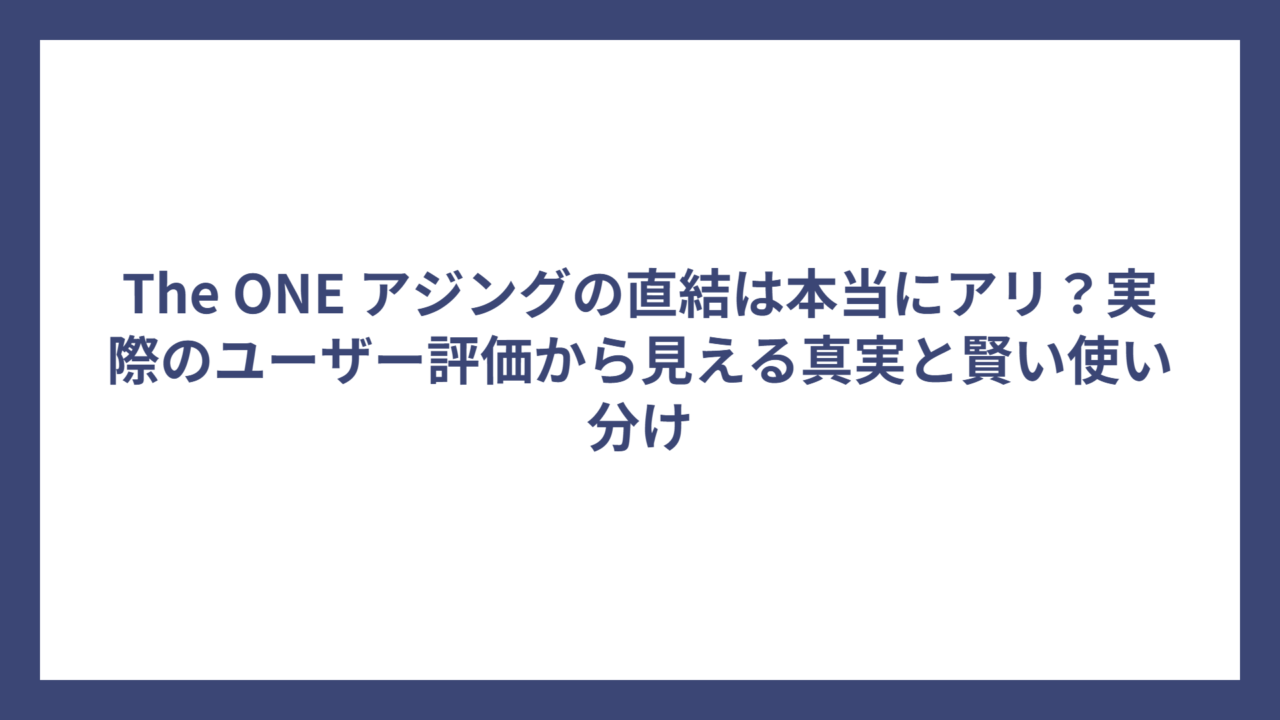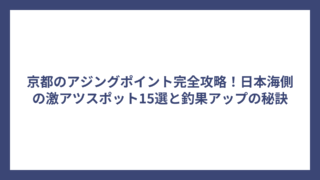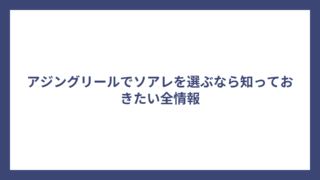DUELから発売されたThe ONE アジングは、独自のポリエチレンフュージョン(PF)製法により「直結でも使える」という触れ込みで注目を集めているラインです。従来のPEラインと同じ素材ながらモノフィラメント構造を実現し、「絶対感度」というキャッチコピーとともに、リーダーレスでの使用可能性が話題になっています。しかし、インターネット上の情報を収集してみると、実際のユーザーからは賛否両論の声が上がっており、「本当に直結で使えるのか」という疑問に対する答えは一筋縄ではいかないようです。
本記事では、メーカー公式情報や複数のインプレ記事、実釣レポートなど、様々な角度からThe ONE アジングの直結使用について徹底的に検証していきます。直結のメリット・デメリット、適した状況、リーダーを付けるべきケース、号数による違い、ノットの選び方まで、「the one アジング 直結」というキーワードで検索しているあなたが知りたい情報を網羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ The ONEアジングの直結可否についてメーカー見解と実際のユーザー評価を比較検証 |
| ✓ 直結使用時のメリット・デメリットと適した釣り場の条件を具体的に解説 |
| ✓ 号数別の直結リスクと推奨されるリーダーシステムの実践的な選び方 |
| ✓ 耐摩耗性・比重・感度など性能面から見た直結使用の現実的な判断基準 |
The ONE アジングで直結が可能な理由と実際の評価
- The ONEアジングは直結可能だがリーダー推奨が基本
- 直結が可能とされる理由はモノフィラメント構造にある
- メーカー公式見解では状況に応じてリーダー使用を推奨
- 0.08~0.13号の極細ラインでは直結リスクが高い
- 直結使用時の最大の弱点は耐摩耗性の低さ
- オープンエリア限定なら直結のメリットを享受できる
- 直結時の感度向上効果は確かに体感できる
The ONEアジングは直結可能だがリーダー推奨が基本
「The ONE アジング 直結」で検索している方がまず知りたいのは、「結局のところ直結で使えるのか?」という点でしょう。結論から言えば、The ONEアジングは構造上直結使用が可能ですが、多くのユーザーや専門家はリーダーの使用を推奨しているというのが現実です。
メーカーであるDUEL公式サイトのFAQページでは、直結の可能性について触れつつも、基本的にはリーダーを付けることを推奨しています。特にアルティメットモデル(0.08~0.13号)については、「直結での可能性を広げてくれる」としながらも、「基本的にはリーダーを付けることをお勧めし」という表現を使っており、直結を全面的に推奨しているわけではありません。
DUELから発売のポリエチレン製ライン、「The ONE アジング」をインプレ投稿します。根ズレの心配がない場所でならリーダー無しでも使える(リーダーを結ぶ手間が省ける)。
一方で、実際に使用したユーザーからは「表層、中層、ボトム問わずアジのアタリも難なく感じることができた」という肯定的な意見もあります。ただし、同じユーザーも「ボトム、障害物周りを探る時はリーダーは必要」と明確に述べており、直結使用には明確な条件があることが分かります。
📊 直結使用の可否判断マトリクス
| 使用環境 | 直結の可否 | 推奨度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| オープンエリア(障害物なし) | 可能 | △ | 感度は良いが万が一に備えリーダー推奨 |
| 常夜灯周りの表層 | 可能 | ○ | 比較的安全だが号数に注意 |
| ボトム攻略 | 不可 | × | 根ズレリスク高く確実にリーダー必要 |
| テトラ周辺 | 不可 | × | 一瞬の接触で切れる可能性大 |
| 岩場・堤防際 | 不可 | × | 硬いものへの耐性が極めて低い |
| 砂地のポイント | 可能 | ○ | 根ズレリスク低く直結メリット享受可能 |
このように、The ONEアジングの直結使用は「できるかできないか」という二択ではなく、使用する場所や狙い方によって判断すべきというのが実情です。感度の良さや手返しの速さといった直結のメリットを活かしたい気持ちは理解できますが、ラインブレイクによるルアーロストや魚へのダメージを考えると、慎重な判断が求められます。
特に初心者の方や、アジング経験が浅い方は、まずはリーダーを付けた状態でThe ONEアジングの特性を理解することをおすすめします。その上で、ポイントの特性や自分の釣りスタイルに応じて、直結を試してみるかどうかを判断するのが賢明でしょう。
直結が可能とされる理由はモノフィラメント構造にある
The ONEアジングが「直結可能」とされる最大の理由は、その独自の製造方法にあります。従来のPEラインは4本編みや8本編みといった、複数の細い原糸を編み込んで1本のラインとする製法が一般的でした。これに対してThe ONEアジングは、ポリエチレン素材でありながらモノフィラメント(単線)構造を実現している点が革新的なのです。
DUEL公式サイトでは、「従来のPEラインと同じ超高分子量ポリエチレンですが、従来のPEラインの編み込む製法ではなく、弊社独自の特殊製法で製造しております」と説明されています。この製法により、PEラインの高強度を保ちながら、モノフィラメントラインの扱いやすさを兼ね備えることに成功しているとされています。
モノフィラメント構造の最大のメリットは、結束部が決まりやすく、滑りにくいという点です。通常のPEラインでは、編み込み構造ゆえにノットを組む際に糸が滑りやすく、強力なFGノットなどの摩擦系ノットが推奨されます。しかしThe ONEアジングの場合、簡易的なトリプルエイトノットやクインテットノットでも実用に耐える強度が得られるという報告が多数あります。
一方でTheONEアジングの場合はコーティングが剥がれてボロボロになるのが目で分かりにくいので、毛羽立ちが発生した時点で既にラインは弱くなっていると考えた方が良いです。
ただし、モノフィラメント構造だからといって耐摩耗性が高いわけではありません。むしろPE素材特有の「硬いものに擦れると一発で切れる」という弱点はそのまま残っているため、直結使用時には障害物との接触を極力避ける必要があります。
🔍 モノフィラメント構造がもたらす特性比較
| 特性項目 | 編み込みPEライン | The ONEアジング(PFライン) | 一般的なエステルライン |
|---|---|---|---|
| 結束のしやすさ | △(滑りやすい) | ○(決まりやすい) | ○(モノフィラメント) |
| 簡易ノットの強度 | △(不安定) | ○(実用レベル) | ○(安定) |
| 表面の滑らかさ | △(ザラつき感) | ◎(ツルツル) | ○(滑らか) |
| 飛距離 | ○(良好) | ◎(最も飛ぶ) | △(比重で劣る) |
| 耐摩耗性 | △(編み込み故の弱さ) | △(PE素材の宿命) | ○(比較的強い) |
| ライントラブル | △(絡みやすい) | ○(絡みにくい) | ◎(最も少ない) |
この表からも分かるように、モノフィラメント構造は多くのメリットをもたらしますが、耐摩耗性という致命的な弱点はカバーできていません。そのため、「直結できる=どんな状況でも直結で問題ない」という解釈は危険であり、使用環境の見極めが極めて重要になります。
また、モノフィラメント構造によって「解れない」という特性も得られています。通常のPEラインは、服のマジックテープに絡まったり、ライントラブルが発生したりすると繊維がバラバラになってしまい、カットして結び直す必要がありました。The ONEアジングではそのような心配が少なく、トラブル発生時の復旧も比較的容易だという点も、直結使用を後押しする要因の一つと言えるでしょう。
メーカー公式見解では状況に応じてリーダー使用を推奨
DUEL公式サイトのFAQページには、「リーダーは必要?」という質問に対する詳細な回答が掲載されています。この公式見解を正確に理解することが、The ONEアジングの適切な使用方法を知る上で非常に重要です。
公式FAQでは、号数によって直結の可能性とリスクを明確に分けて説明しています。0.08~0.13号のアルティメットモデルについては、「その細さも相まって、直結での可能性を広げてくれます」としながらも、重要な注意点を挙げています。
⚠️ アルティメットモデル直結時の注意点(公式FAQより)
- ✓ 数十センチのリーダーを取り除くことで感度は驚異的に上昇する
- ✓ しかし魚の急激なショックに対してはドラグの初期負荷が高くなる
- ✓ 瞬間的に糸の破断強度を超えてしまう場合がある
- ✓ 竿の調子やタックルバランスが大きく関わる
- ✓ 基本的にはリーダーを付けることをお勧め
- ✓ 安心できるのはFG等の摩擦系ノット
- ✓ アルティメットモデルについては実用上トリプルエイトノットでも十分
一方、0.2~0.4号のストロングモデルについては、「糸の強度が十分にあるので、急激的なショックに対しても対応でき」としていますが、やはり結束部が最も切れやすくなるため、「対象魚に合わせて、摩擦系か結び系のノットを選択してください」と述べています。つまり、ストロングモデルでもリーダーの使用が前提とされていることが分かります。
釣り博でDUELスタッフの方とお話する中で「ジグ単でアジングだけなら0.13号を直結で十分ですよ!」と教えてくれました。
興味深いのは、釣りイベントでのDUELスタッフの発言として「ジグ単でアジングだけなら0.13号を直結で十分」という情報が報告されていることです。これは公式FAQ以上に踏み込んだ発言であり、条件付きではあるものの直結使用の可能性を示唆しています。ただし、「ジグ単で」「アジングだけなら」という限定的な条件がついていることに注目すべきでしょう。
📋 メーカー推奨のリーダー素材と号数(公式FAQより)
| The ONE号数 | 適合リーダー(Lbs.) | エステル対比目安 | 対象魚サイズ目安 | 推奨素材 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08号 | 2~4 Lbs. | 0.2号相当 | ~20cm | フロロカーボン |
| 0.1号 | 3~5 Lbs. | 0.3号相当 | ~30cm | フロロカーボン |
| 0.13号 | 4~6 Lbs. | 0.4号相当 | ~35cm | フロロカーボン |
| 0.2号 | 4~7 Lbs. | 0.5号相当 | ~40cm | フロロカーボン |
| 0.3号 | 5~8 Lbs. | – | ~50cm | フロロカーボン |
| 0.4号 | 6~10 Lbs. | – | ~60cm | フロロカーボン |
※タックルバランスに大きく左右されます
メーカーがリーダー素材としてフロロカーボンを推奨している理由は、「比重の面から」としています。The ONEアジング自体の比重が0.97と軽いため、リーダーに高比重のフロロカーボンを使うことで、リグの沈下速度をコントロールしやすくなるという考え方です。
これらの公式見解から読み取れるのは、メーカー自身も直結使用を全面的に推奨しているわけではなく、あくまで「可能性がある」「状況次第では選択肢になる」というスタンスであることです。安全性と確実性を重視するなら、リーダーを付けるのが基本だと理解すべきでしょう。
0.08~0.13号の極細ラインでは直結リスクが高い
The ONEアジングのラインナップの中でも、特に0.08号、0.1号、0.13号といった極細号数は、その細さゆえに直結使用時のリスクが高くなります。これらはアルティメットモデルと呼ばれ、高感度を追求したラインナップですが、細さは諸刃の剣でもあるのです。
まず数値的な観点から見てみましょう。0.13号の直径は0.055mm、0.1号は0.05mm、0.08号に至っては0.045mmという驚異的な細さです。これは髪の毛と同程度か、それよりも細いレベルで、実際に手に取ったユーザーからは「細すぎて笑ってしまった」「髪の毛やん」といったコメントが多数見られます。
この極細ラインで直結した場合、最も問題になるのが不意のトラブル時の対応力の低さです。例えば、想定外の大型魚がヒットした場合、外道としてメバルやカサゴが掛かった場合、あるいは根掛かりからの回収を試みた場合など、ラインに予期せぬ負荷がかかる状況は頻繁に発生します。
耐摩耗性という点においては、正直言って極細のPEラインなので、硬いものに擦れると簡単にブレイクします。TheONEアジングを使っていて、一度外道で3kgオーバー、60cm強のイシダイがヒットしました。足元で突っ込まれたときに少しラインが岸壁際のカキガラにスレたんですが、ほんのわずか触れただけでラインブレイクでした。
この引用は、極細PEラインの耐摩耗性の低さを端的に示しています。0.13号でも「ほんのわずか触れただけ」でラインブレイクするのですから、さらに細い0.08号や0.1号では、より一層のリスクが伴うことは容易に想像できます。
⚡ 極細号数直結時の具体的リスク
- キャスト時の高切れリスク
- 3g以上のジグヘッドでは特に注意が必要
- 垂らしを長く取り、フルキャストを避ける必要がある
- エステルライン使用時以上に気を使う
- 根掛かり時のルアーロスト
- 回収を試みると簡単に切れてしまう
- ジグヘッド+ワームならまだしも、高価なプラグやメタルジグのロストは痛い
- 環境への配慮からも問題
- 魚とのファイト時の不安
- 尺アジクラスになると抜き上げ時に不安が残る
- ドラグ設定がシビアになる
- 竿の調子との相性が非常に重要
- 経年劣化の見極めの難しさ
- 細すぎて毛羽立ちや劣化が分かりにくい
- 気づかないうちに強度が落ちている可能性
- こまめなラインチェックとカットが必須
- 指への食い込みリスク
- ノットを組む際に指に食い込んで痛い
- 締め込み時に指が切れそうな怖さがある
- 特に乾燥した手では要注意
これらのリスクを考えると、極細号数での直結は「技術と経験のあるアングラーが、条件を選んで使う」べき上級者向けのテクニックと言えます。初心者や中級者がいきなり0.08号や0.1号で直結に挑戦するのは、トラブルの元になる可能性が高いでしょう。
それでも極細号数の直結にチャレンジしたい場合は、最低限以下の条件を満たすことをおすすめします:完全なオープンエリアであること、狙うのは豆アジ~20cm台前半まで、根掛かりのリスクがほぼゼロの場所、竿の調子が柔らかめでショックを吸収しやすいこと、そしてルアーロストを覚悟すること。
直結使用時の最大の弱点は耐摩耗性の低さ
The ONEアジングを直結で使用する際に最も注意すべき点は、間違いなく耐摩耗性の低さです。この点については、ほぼすべてのインプレ記事や使用レポートで指摘されており、直結使用の可否を決める最も重要な判断材料となります。
まず基本的な理解として、The ONEアジングの耐摩耗性は「従来のPEラインと同程度」とされています。つまり、モノフィラメント構造になったからといって、PE素材特有の「硬いものに弱い」という弱点が克服されたわけではないのです。むしろ、極細であるがゆえに、耐摩耗性の問題は一層シビアになっていると考えるべきでしょう。
具体的にどのような状況で問題が発生するかを見ていきましょう。あるユーザーは「岩場と堤防の壁際を攻めていた時にダメージを受けたライン」の写真を公開しており、根掛かりして何とか外すことができたものの、「0.3号のラインでも回収できるくらいの根掛かりなので、深くは根掛かってないと思いますが、それでもかなりの傷ついているな」というのが正直な感想だったと述べています。
従来のPEラインと同じようにボトムや障害物周りを探ることが想定される状況ならリーダーなら使用をオススメします。また、The ONEの製品紹介ページに直結で使うことで得られるメリットが書いてある一方で、リーダーの使用を推奨する内容も同時に書いてあります。
別のインプレでは、テトラでのアジングにおいて「ちょっとしたスレでも簡単に切れます」と明言されており、テトラでの使用時は極細ラインを使用することはないと結論づけています。テトラ帯は多くのアジングポイントで代表的なストラクチャーですから、ここで直結が使えないというのは大きな制約と言えるでしょう。
🚫 直結使用を避けるべき具体的な状況
| 状況・環境 | リスクの内容 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| テトラポッド周辺 | 角や隙間への接触で一瞬で切れる | 必ずリーダー使用、できれば太めの号数選択 |
| 岩場・ゴロタ場 | 底ズレで簡単にダメージ蓄積 | フロロリーダー必須、ボトム攻略は慎重に |
| 堤防の壁際 | 抜き上げ時にラインが壁に擦れる | 短めでもリーダーは必要 |
| カキガラのある場所 | 最も危険、一瞬の接触で即切れ | 絶対にリーダー必須、直結は論外 |
| 海藻エリア | 絡まった際の摩擦で切れやすい | リーダー推奨、もしくは高比重PEライン |
| 流木・ゴミの多い場所 | 不意の接触リスク高い | リーダー使用、ポイント自体の変更も検討 |
耐摩耗性の問題は、ボトムや障害物周辺だけでなく、日常的な使用における劣化にも関係してきます。キャスト時に指に当たる部分、ガイドとの摩擦が発生する部分、魚とのやり取りで負荷がかかった部分などは、見た目には分かりにくくても着実にダメージが蓄積していきます。
The ONEアジングの場合、アーマードシリーズのようにコーティングが剥がれてボロボロになるといった「目で見て分かる劣化」が少ないため、劣化の判断が難しいという問題もあります。毛羽立ちが発生した時点で既にラインは弱くなっていると考えるべきで、毎釣行後の入念なラインチェックと、怪しいと感じた部分の早めのカットが必須です。
直結使用する場合は、エステルライン使用時以上にこまめなラインメンテナンスが求められます。釣行後には必ず先端から数メートルをチェックし、少しでも毛羽立ちや白っぽくなっている部分があれば躊躇なくカット。また、一度でも底ズレや障害物への接触があった場合は、その場で即座にチェックとカットを行う慎重さが必要です。
オープンエリア限定なら直結のメリットを享受できる
これまで直結使用のリスクや注意点を中心に解説してきましたが、条件が整えば直結のメリットを十分に享受できるのも事実です。特にオープンエリアでの使用では、The ONEアジングの特性を最大限に活かすことができるでしょう。
オープンエリアとは、具体的には以下のような場所を指します:砂地が広がるサーフエリア、障害物のない堤防の先端部、常夜灯周りの表層エリア(底を取らない釣り)、漁港内でも根掛かりリスクの低い場所など。これらの場所では、ラインが障害物に接触するリスクが極めて低く、直結による感度向上のメリットを安全に享受できます。
あるユーザーは「普段使っているラインに近い太さのラインナップがあれば、そのまま置き換えても問題ないと思います。また、リーダーを結ばなくても良いシュチュエーションはライトゲームの場合意外とあるので、その分釣りに集中することができます」と述べています。リーダーの結束に時間を取られることなく、すぐに釣りを開始できるというのは、確かに大きなメリットです。
私は普段砂地のポイントにも行くので、そういった場所では直結で使って釣りの回転率アップを図ると思います(^^)
砂地のポイントは、底ズレのリスクが低く、根掛かりもほとんど発生しないため、直結使用に最も適した環境の一つです。こうした場所で直結を使うことで、リーダー結束の手間を省き、釣りの回転率を上げることができます。
🎯 オープンエリアでの直結使用がもたらすメリット
感度面でのメリット
- リーダーレスによる情報伝達のダイレクト化
- 微細なアタリもクリアに感じ取れる
- ジグヘッドの着底感知が明確になる
- 潮の変化やボトムの質感が手に取るように分かる
操作性でのメリット
- リーダー分の重さがない分、より繊細なリグコントロールが可能
- 表層での釣りでは浮力の恩恵を受けやすい
- ラインの軌道が読みやすく、リグの位置把握が容易
実用面でのメリット
- リーダー結束の時間短縮(1回あたり2~3分の節約)
- 結束ミスによるトラブルリスクの排除
- ナイトゲームでの作業負担軽減
- 釣りに集中できる時間の増加
特に表層での釣りにおいては、The ONEアジングの軽い比重(0.97)が有利に働きます。あるインプレでは「表層でのアジのキャッチ率は比重が大きいラインよりも高いと感じており、ラインの比重が小さいことによる影響でしょうか」と分析されています。比重の軽さは、ボトムを攻める場合にはデメリットになりますが、表層を攻める場合には逆にメリットとなるのです。
ただし、オープンエリアだからといって完全に安心というわけではありません。以下の点には常に注意を払う必要があります:
⚠️ オープンエリアでも注意すべきポイント
✓ 予期せぬ大型魚のヒット – ヒラメ、マゴチ、シーバスなどが掛かる可能性
✓ 流木やゴミとの接触 – 一見綺麗なエリアでも水中にゴミがある場合も
✓ 風による操作性の低下 – 横風が強いと直結のメリットが薄れる
✓ ラインの劣化確認 – オープンエリアでも定期的なチェックは必須
✓ 号数の選択 – あまりに細すぎる号数は避ける(0.13号以上推奨)
結論として、オープンエリアでの直結使用は、条件が整えば非常に有効な選択肢となります。ただし、「オープンエリアだから絶対安全」という油断は禁物です。常にラインの状態をチェックし、少しでも異常を感じたら躊躇なくカットする慎重さを持ちつつ、直結のメリットを楽しむというスタンスが理想的でしょう。
直結時の感度向上効果は確かに体感できる
The ONEアジングの最大のセールスポイントは「絶対感度」というキャッチコピーに象徴される、その高い感度です。そして直結使用時には、この感度の良さを最大限に体感できるとされています。実際のユーザーレポートからも、感度向上効果については概ね肯定的な評価が多く見られます。
メーカーの公式データによれば、The ONEアジングの感度はエステルラインの3.4倍、PEラインの1.36倍とされています。この数値の根拠となっている測定方法については賛否両論ありますが、「ラインが張った状態」での感度の良さについては、多くのユーザーが実感しているようです。
一番の売り?として絶対感度と言うぐらいなので最初から期待値は高いです。結論から言うと、飛距離ほどはビビりませんでしたw 悪くないです。普通にめっちゃいいですよ!正直、同じ状況下でPEと比べるとそこまで大差はないかなって感じはしましたが当然、使ってる竿によってアタリの出方が変わったりするので個人的意見としてです。
この引用にあるように、「飛距離ほどのインパクトはない」という意見もありますが、それでも「普通にめっちゃいい」という評価です。感度については個人の感覚や使用するロッドの性能にも大きく左右されるため、劇的な差を感じる人もいれば、そこまでの差は感じないという人もいるようです。
別のインプレでは、より具体的な表現で感度の良さが語られています。「大袈裟ではなく、『感度は超絶良い』と言えます。バイトに対する感度も水中の変化を捉える感度も、今まで使っていたエステルやPEとは比べ物になりません。とくに、遊泳力の低いベイトを捕食する時のチッやヌッといった、小さく瞬間的なバイトもボヤけることなくクリアに伝わってきます」という表現は、感度の良さを実感している様子が伝わってきます。
💡 直結時に体感できる感度向上の具体例
微細なアタリの感知
- 豆アジの吸い込むようなアタリが明確に分かる
- 潮目でのラインのテンション変化を敏感に察知
- ワームへの興味を示すアジの「コツコツ」が手に取るように分かる
水中情報の把握
- ボトムの質感(砂地、泥、小石など)が明確
- ジグヘッドの着底がピンポイントで分かる
- 潮の効き具合や流れの変化を感じ取りやすい
操作感の向上
- ワームの動きをリアルタイムで把握できる
- 意図した通りのアクションが入れやすい
- リフト&フォールの際のテンション変化が明確
フッキングの精度向上
- アタリを感じてからの合わせタイミングが取りやすい
- アジが吐き出す前にフッキングできる確率が上がる
- バイトの種類(本気食い、探り食い)の判別が容易
ただし、この高感度には注意点もあります。感度が良すぎるゆえに、ノイズを拾いやすいという側面もあるのです。あるインプレでは「硬くて感度が良いせいか、ラインとロッドの角度によってはややノイズが入るかもしれません」と指摘されています。ロッドを立ててリトリーブすると、ラインが鋭角にトップガイドと干渉するのが理由だと分析されています。
また、感度の良さはフッキングの安定性にも影響を与える可能性があります。あるユーザーは「アジの活性が低い時にフッキングが少し不安定になったり、口切れによるバラシが増えやすい印象がありますね」と述べています。感度が良すぎるがゆえに、アジが完全に吸い込む前に合わせてしまったり、過剰な合わせで口切れを起こしたりする可能性が考えられます。
🔔 感度の良さがもたらす注意点
| 注意点 | 具体的な影響 | 対策 |
|---|---|---|
| ノイズの増加 | ガイドとの摩擦音が気になる | ラインコートスプレーの使用 |
| 過剰な合わせ | 口切れによるバラシ増加 | 合わせを控えめにする意識 |
| 精神的な疲労 | 情報量が多すぎて疲れる | 集中力の配分に注意 |
| 低活性時の不利 | 吸い込みが浅い段階で反応 | アタリを待つ余裕を持つ |
結論として、直結時の感度向上効果は確かに体感できるものの、それが必ずしも釣果向上に直結するわけではないという点を理解しておくことが重要です。感度の良さを活かすには、それに見合った技術と経験が必要であり、初心者がいきなり直結でThe ONEアジングを使っても、かえって釣りにくさを感じる可能性もあります。
感度の良さというメリットを最大限に活かすには、まずはリーダーを付けた状態でThe ONEアジングに慣れ、その特性を理解した上で、必要に応じて直結を試してみるというステップを踏むのが賢明でしょう。
The ONE アジング直結のメリットとリスク管理の実践
- リーダーを付けた場合でも高感度は維持される
- 簡易ノットでも十分な強度が得られる特徴
- 比重の軽さが直結時の沈下速度に影響する
- 障害物周辺では確実にリーダーが必要
- 風の影響を考慮した使い分けが重要
- まとめ:The ONE アジング直結は状況次第で判断を
リーダーを付けた場合でも高感度は維持される
「直結すれば感度が上がる」というのは確かに事実ですが、それでは「リーダーを付けると感度が大きく落ちるのか?」という疑問が湧いてきます。結論から言えば、適切な長さとシステムでリーダーを組めば、直結に迫る高感度を維持できるというのが実際のところです。
あるインプレでは非常に重要な指摘がされています。「試しにリーダーレスと比較してみましたが、フロロリーダーを50cmくらい入れても感度はほとんど変わりませんでしたよ」という実体験に基づいた情報です。50cmという長さは、リーダーとしては決して短くない長さですが、それでも感度の低下はほとんど感じられなかったというのは、非常に参考になる情報です。
普段から細かなラインメンテナンスをされる方は、あまり気にする必要はないかもしれませんが、それでもエステルラインは吸水による劣化が起こります。もちろん、ポリエチレン素材でも起こるでしょうが、劣化スピードは間違いなくエステルラインの方が早いです。
The ONEアジング自体の高い感度特性により、リーダーを介しても十分な情報が伝わってくるということです。これは、直結のリスクを取らずとも、The ONEアジングのメリットを享受できることを意味しています。
📏 推奨リーダーシステムの具体例
基本セッティング(万能型)
- メインライン:The ONE 0.13号
- リーダー:フロロカーボン 4~5Lbs.(1~1.25号相当)
- リーダー長:30~50cm
- ノット:クインテットノットまたはFGノット
- 適用場面:オールラウンド、初心者にもおすすめ
ボトム攻略セッティング(耐摩耗重視)
- メインライン:The ONE 0.2~0.3号
- リーダー:フロロカーボン 6~8Lbs.(1.5~2号相当)
- リーダー長:50~80cm
- ノット:FGノットまたはSFノット
- 適用場面:テトラ周辺、岩場、ゴロタ場
表層特化セッティング(軽量重視)
- メインライン:The ONE 0.1号
- リーダー:ナイロン 3~4Lbs.(0.8~1号相当)
- リーダー長:20~30cm(短め)
- ノット:トリプルエイトノットまたは3.5ノット
- 適用場面:常夜灯周り、表層の豆アジ狙い
大型対応セッティング(強度重視)
- メインライン:The ONE 0.3~0.4号
- リーダー:フロロカーボン 8~10Lbs.(2~2.5号相当)
- リーダー長:60~100cm
- ノット:FGノットまたはPRノット
- 適用場面:尺アジ狙い、キャロやフロートリグ使用時
リーダーを付けることで得られるメリットは、感度の維持だけではありません。**耐摩耗性の向上、万が一の大物対応、精神的な安心感、環境への配慮(ラインブレイク時のルアーロスト防止)**など、多くの副次的メリットがあります。
特に注目したいのが、リーダーの「クッション効果」です。The ONEアジングは伸びが少ないラインですが、リーダーに若干伸びのあるフロロカーボンやナイロンを使うことで、魚の突っ込みや急な引きに対するバッファーとなり、バラシの軽減につながります。これは特に、口の柔らかいアジを相手にする場合に重要な要素です。
また、リーダーを付けることでラインの劣化管理が容易になるというメリットもあります。劣化しやすい先端部分をリーダーが受け持つため、メインラインの The ONEアジングは長持ちします。釣行ごとにリーダーだけを交換または短くカットしていけば、コストパフォーマンスも向上します。
🎨 リーダーカラーの選択による視認性向上
リーダーを使用するもう一つのメリットとして、視認性のコントロールが挙げられます。The ONEアジング自体は白色系(ゴーストまたはハーフゴースト)ですが、リーダーに異なる色を使うことで、より見やすくしたり、逆に魚に警戒されにくくしたりといった調整が可能です。
- クリア系リーダー – 警戒心の強いアジ、プレッシャーの高いポイント向け
- ピンク系リーダー – 視認性重視、ナイトゲームでの操作性向上
- イエロー・オレンジ系 – デイゲームでの視認性最優先
- ブラウン・グリーン系 – 自然な色合い、デイゲームの澄んだ水向け
結論として、「直結でなければThe ONEアジングのメリットを享受できない」という考えは誤りです。適切なリーダーシステムを組むことで、直結に近い感度を維持しながら、安全性と実用性を大幅に向上させることが可能です。特に初心者や中級者、あるいは様々な環境で釣りをする方にとっては、リーダーを使用したセッティングの方が圧倒的におすすめできます。
簡易ノットでも十分な強度が得られる特徴
The ONEアジングのもう一つの大きな特徴は、簡易的なノットでも実用に耐える強度が得られるという点です。これはモノフィラメント構造ならではのメリットであり、従来のPEラインとの大きな違いの一つです。
通常、PEラインにリーダーを接続する際は、FGノットやSFノット、PRノットといった摩擦系ノットが推奨されます。これらのノットは高い結束強度を誇る反面、習得に時間がかかり、特に極細ラインでは組むのが非常に困難です。0.1号以下のPEラインでFGノットを組むのは、熟練者でも神経を使う作業です。
しかしThe ONEアジングの場合、トリプルエイトノット、クインテットノット、3.5ノットといった簡易ノットでも十分な強度が得られるという報告が多数あります。メーカー公式FAQでも「PEに比べて結束部が滑らないので、アルティメットモデルについては、実用上トリプルエイトノットでも十分釣りが楽しめます」と明言されています。
ノットはオルブライトノットが良いそうです。因みに同社のアーマードシリーズも細めの原糸を編み込まずに周りをシリコンやフロロで固めたやつ、という事でした。
実際の使用例として、あるアングラーは「0.13号でリーダー4Lbs.、3.5ノットで尺アジを抜き上げても何の問題もなかった」と報告しています。また別のユーザーは「クインテットノットでリーダーを結束し、3回強度測定を行ってみました。直線強度は標準で1.1kgということでしたが、結果は0.8kg~0.9kgと、中々良いところで安定していました」という具体的なデータを提供しています。
🔗 The ONEアジング推奨ノット比較表
| ノット名 | 難易度 | 結束強度 | 所要時間 | 推奨度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGノット | ★★★★☆ | 95%以上 | 3~5分 | ★★★☆☆ | 最強だが極細では困難 |
| SFノット | ★★★★★ | 95%以上 | 4~6分 | ★★☆☆☆ | FGより難しい |
| PRノット | ★★★★☆ | 95%以上 | 2~4分 | ★★★☆☆ | 専用ツール必要 |
| クインテットノット | ★★☆☆☆ | 80~85% | 1~2分 | ★★★★★ | バランス最良 |
| 3.5ノット | ★★☆☆☆ | 75~80% | 1~2分 | ★★★★☆ | 簡単で実用的 |
| トリプルエイトノット | ★☆☆☆☆ | 70~75% | 1分以下 | ★★★☆☆ | 最も簡単 |
| ユニノット | ★☆☆☆☆ | 60~70% | 1分以下 | ★★☆☆☆ | 強度やや不安 |
| オルブライトノット | ★★★☆☆ | 80~85% | 2~3分 | ★★★★☆ | メーカー推奨あり |
※強度パーセンテージは直線強力に対する結束強力の割合の目安
簡易ノットで十分な強度が得られる理由は、The ONEアジングのモノフィラメント構造にあります。編み込みのPEラインは、結束部で個々の繊維がずれたり滑ったりすることで強度が低下しやすいのですが、モノフィラメントのThe ONEアジングは「ガチっと結び目が決まりやすく、変にフワフワしたり、滑りにくい印象がある」とインプレされています。
⚙️ 簡易ノット実践のポイント
クインテットノットの組み方のコツ
- メインラインを5回リーダーに巻きつける(5の意味)
- 巻きつけは隙間なく綺麗に並べる
- 結び目を作る際は唾液で湿らせる
- ゆっくりと均等に締め込む
- 余分なラインは1mm程度残してカット
3.5ノットの組み方のポイント
- 基本は3回巻きつけるが、途中で半回転を加える(3.5の意味)
- The ONEアジングは滑りにくいので綺麗に巻ける
- 締め込みは段階的に、一気に締めない
- 結び目がコンパクトにまとまるよう意識
トリプルエイトノットの組み方のポイント
- ∞(インフィニティ)の形を3回作る
- 最も簡単で覚えやすいノット
- 強度はやや劣るが実用レベル
- 豆アジ~20cm台なら問題なし
簡易ノットが使えることのメリットは、釣り場での作業時間短縮だけではありません。特にナイトゲームでは、複雑なノットを組むのは照明が必要で手間がかかりますが、簡易ノットなら暗闇でも組めます。また、釣行中にリーダーを交換する必要が出た場合も、短時間で対応できるため、貴重な釣り時間を無駄にしません。
ただし、簡易ノットを使う場合でも、以下の点には注意が必要です:
⚠️ 簡易ノット使用時の注意事項
✓ 初回は必ず強度テストを – 実釣前に思い切り引っ張って確認
✓ 唾液での湿潤は必須 – 摩擦熱によるライン劣化を防ぐ
✓ 均等な締め込みを意識 – 片側だけに力がかかると強度低下
✓ 余分なラインは1mm程度残す – 短すぎるとすっぽ抜けリスク
✓ 大型狙いでは摩擦系ノット推奨 – 尺アジ以上は安全を優先
結論として、The ONEアジングでは簡易ノットが実用的に使えるというメリットは非常に大きく、釣りの効率と快適性を大幅に向上させる要素です。ただし、「簡易だから適当でいい」というわけではなく、基本に忠実に、丁寧に組むことが大切です。正しい手順で組んだ簡易ノットは、一般的なアジングにおいて十分すぎる強度を発揮してくれるでしょう。
比重の軽さが直結時の沈下速度に影響する
The ONEアジングの比重は0.97と、ほぼ水と同じかわずかに軽い値です。これは一般的なPEラインとほぼ同等の比重であり、水に浮きやすい特性を持っています。この比重の軽さは、直結使用時に特に顕著な影響を及ぼします。
まず基本的な理解として、比重が軽いラインは水に浮きやすく、重いラインは沈みやすいという性質があります。参考までに各ラインの比重を比較すると、エステルライン(1.35~1.38)、フロロカーボン(1.78)、ナイロン(1.14)、PE・PFライン(0.97~0.98)となります。The ONEアジングは最も軽い部類に入ることが分かります。
この比重の軽さが直結使用時にどのような影響を与えるかというと、ジグヘッドリグの沈下速度が遅くなるという点です。リーダーを付けている場合は、高比重のフロロカーボンリーダーがある程度沈下を助けてくれますが、直結の場合はその助けがありません。
一方でThe ONEアジングの場合は低比重なので、まずはラインを沈めることを優先するのが無難ですね。
あるユーザーは「いくら細いラインとは言え、低比重なラインはジグヘッドリグの沈下に影響を与えますからね」と指摘し、30cm~60cm前後のフロロカーボンリーダーを接続して使うことを推奨しています。特に「足場が高い場所を狙ったり、横風が吹く時は、リーダーを1ヒロなどに長くして使うのもおすすめ」とのことです。
📊 比重による影響の具体的シミュレーション
0.6gジグヘッド使用時(水深5m、無風)
| ラインシステム | 沈下速度目安 | 着底時間 | ラインの軌道 |
|---|---|---|---|
| エステル0.3号直結 | 速い | 約4秒 | ほぼ真下 |
| The ONE 0.13号直結 | やや遅い | 約6~7秒 | やや斜め |
| The ONE 0.13号+フロロ50cm | 普通 | 約5秒 | ほぼ真下 |
| The ONE 0.13号+ナイロン50cm | 遅い | 約7~8秒 | 斜め |
1.0gジグヘッド使用時(水深5m、無風)
| ラインシステム | 沈下速度目安 | 着底時間 | ラインの軌道 |
|---|---|---|---|
| エステル0.3号直結 | 速い | 約3秒 | ほぼ真下 |
| The ONE 0.13号直結 | 普通 | 約4~5秒 | ほぼ真下 |
| The ONE 0.13号+フロロ50cm | やや速い | 約3~4秒 | ほぼ真下 |
| The ONE 0.13号+ナイロン50cm | 普通 | 約5秒 | ほぼ真下 |
この表から分かるように、軽いジグヘッドほど比重の影響を受けやすく、直結時の沈下速度の遅れが顕著になります。逆に、ある程度重いジグヘッド(1g以上)であれば、比重の影響は相対的に小さくなります。
比重の軽さによる影響は、沈下速度だけではありません。ラインの軌道にも大きく影響します。比重の重いエステルラインは、キャスト後に素早く沈んでリグとメインラインがほぼ一直線になりますが、比重の軽いThe ONEアジングは、ラインが水面に浮いた状態が続き、リグとの間に「たるみ」ができやすくなります。
🌊 比重の軽さを逆手に取った釣り方
比重の軽さはデメリットばかりではありません。状況によっては、これをメリットとして活用できます:
表層攻略での優位性
- ラインが浮くことでリグが沈みすぎない
- 表層をゆっくり引くドリフト釣法に最適
- プラグの動きを自然に演出できる
レンジキープの容易さ
- 中層をキープしやすい
- カウントダウンでの誤差が小さい
- レンジを少しずつ変えながらサーチしやすい
アジの警戒心を下げる効果
- ラインが浮いているため水中での存在感が薄い
- 特にクリアウォーターで効果的
- デイゲームでの有利性
風の弱い日の遠投性能
- ラインが浮くことで飛距離が伸びる
- 空気抵抗が少なく飛行姿勢が安定
- 無風時は最も飛距離が出るライン
ただし、比重の軽さを活かすには、使用するジグヘッドの重さの調整が重要になります。通常エステルラインで使っていたジグヘッドよりも、0.2~0.5g程度重めのものを選ぶことで、沈下速度の遅さを補うことができます。例えば、エステルで0.6gを使っていた場面では、The ONEアジング直結なら0.8~1.0gを選択するといった調整です。
また、直結ではなくリーダーを付けることで比重の問題を解決するというアプローチも有効です。50cm程度のフロロカーボンリーダー(比重1.78)を接続すれば、リグの沈下を助けてくれます。これにより、エステルラインに近い操作感で釣りができるようになります。
結論として、The ONEアジングの比重の軽さは、ボトムを攻める釣りでは明確なデメリットとなりますが、表層~中層を攻める釣りではメリットにもなり得るという二面性を持っています。直結使用を考える際は、この比重による影響を十分に理解し、狙うレンジやジグヘッドの重さを適切に選択することが重要です。
障害物周辺では確実にリーダーが必要
これまで何度も触れてきましたが、改めて強調しておきたいのは、障害物周辺でThe ONEアジングを直結で使うのは極めて危険だということです。どれだけ高感度で、どれだけ細くて飛距離が出ても、一瞬の接触でラインブレイクしては意味がありません。
障害物周辺での釣りが危険な理由は、The ONEアジングの耐摩耗性が従来のPEラインと同程度であることに尽きます。PE素材は高強度である一方、擦れには非常に弱いという致命的な弱点を持っています。これはモノフィラメント構造になったからといって改善されるものではありません。
具体的にどのような障害物が危険かというと、最も危険なのはカキガラ(牡蠣殻)です。鋭利な刃物のようなカキガラに一瞬でも触れれば、極細のThe ONEアジングは確実に切れます。次に危険なのがテトラポッド、特に角や隙間部分です。コンクリートの鋭角な部分への接触は、ラインにとって致命的です。
個人的には、従来のPEラインと同じようにボトムや障害物周りを探ることが想定される状況ならリーダーなら使用をオススメします。
岩場やゴロタ場も要注意です。ボトムを引いてくる際に岩に擦れるリスクが高く、また根掛かりからの回収時にもラインが岩に当たります。さらに堤防の壁際も意外な盲点で、魚を抜き上げる際にラインが壁に擦れて切れるケースがあります。
🚨 障害物別リスク評価と対策
| 障害物の種類 | 危険度 | ラインへの影響 | 必須対策 |
|---|---|---|---|
| カキガラ | ★★★★★ | 一瞬の接触で即断 | リーダー必須、可能なら回避 |
| テトラポッド | ★★★★★ | 角・隙間が特に危険 | 太めリーダー、0.2号以上推奨 |
| 岩・ゴロタ | ★★★★☆ | 底ズレで徐々に劣化 | フロロリーダー50cm以上 |
| 堤防壁面 | ★★★☆☆ | 抜き上げ時に注意 | 短めでもリーダーは必要 |
| 海藻 | ★★★☆☆ | 絡まると摩擦で切れる | リーダー+高比重選択 |
| 流木・ゴミ | ★★★☆☆ | 不意の接触リスク | リーダー+ポイント見極め |
| 砂地 | ★☆☆☆☆ | ほぼ問題なし | 直結も選択肢に |
実際の事例として、あるアングラーは「上の写真は岩場と堤防の壁際を攻めていた時にダメージを受けたラインです。根掛かりして何とか外すことができたのですが、ダメージのある部分のカットを余儀なくされました」と報告しています。これは0.3号という比較的太い号数でさえ、障害物への接触でダメージを受けることを示しています。
障害物周辺でアジングをする場合の具体的な対策としては、以下が挙げられます:
📋 障害物周辺での推奨セッティング
テトラ・岩場攻略セット
- メインライン:The ONE 0.2~0.3号(太めを選択)
- リーダー:フロロカーボン 6~8Lbs.(1.5~2号)
- リーダー長:60~80cm(長めに取る)
- ノット:FGノットまたはSFノット(強力なノット推奨)
- 注意点:ボトムを引きずらない、根掛かりは即座に諦める
堤防際・壁際攻略セット
- メインライン:The ONE 0.13~0.2号
- リーダー:フロロカーボン 4~6Lbs.(1~1.5号)
- リーダー長:40~60cm
- ノット:クインテットノットまたはFGノット
- 注意点:抜き上げ時にラインが壁に当たらないよう意識
また、障害物周辺では釣り方自体を工夫することも重要です。具体的には、ボトムべったりではなく少し浮かせて引く、リフト&フォールではなくミッドステイで誘う、根掛かりしそうなエリアは思い切って飛ばすなど、ラインへの負担を最小限にする釣り方を心がけます。
さらに、万が一に備えたスペアの準備も大切です。障害物周辺での釣りでは、どれだけ注意してもラインブレイクのリスクはゼロにはなりません。替えのジグヘッドやワーム、可能であればスペアのリーダーを準備しておくことで、トラブル発生時にも速やかに釣りを再開できます。
結論として、The ONEアジングは障害物周辺での使用には向いていません。これはThe ONEアジング特有の問題ではなく、PE素材全般に共通する宿命的な弱点です。障害物周辺でアジングをする場合は、素直にリーダーを付ける、もしくはエステルラインやフロロカーボンラインを選択するのが賢明でしょう。The ONEアジングの真価は、オープンエリアや表層攻略で発揮されるのです。
風の影響を考慮した使い分けが重要
The ONEアジングを直結で使用する際の最大の課題の一つが、風の影響を受けやすいという点です。比重が0.97と軽く、水面に浮きやすい特性を持つため、風が吹くとラインが流されてしまい、操作感が著しく低下します。この問題は、直結使用時に特に顕著になります。
風による影響は、単に「ラインが流される」というだけではありません。ラインが流されることでリグとの間に「たるみ(フケ)」が発生し、この状態では感度が極端に落ちます。せっかくの「絶対感度」も、ラインがフケた状態では意味を成しません。アジのアタリを感じ取ることも、リグの位置を正確に把握することも困難になります。
複数のインプレ記事で、風の影響については否定的な意見が見られます。「風速3~5mの中でやりましたが操作感も薄れて何やってるか分かりづらかったです」「横風が吹き付ける状況下で使用したところ、2時間ほどの釣行で数回、トップガイド下にラインが絡みました」といった具体的な報告があります。
風や潮の影響で極端に糸ふけが出てしまう状況では少しでも糸の馴染みが早いエステル、フロロカーボンが良いと思います。
メーカー側は「比重は軽いけどその分、糸自体が細いので影響受けづらい」という見解を示しているようですが、実際に使用したユーザーの多くは「横風3~5mの中とかでやりましたが操作感も薄れて何やってるか分かりづらかった」と感じているようです。糸が細いというメリットよりも、比重が軽いというデメリットの方が上回るケースが多いと考えられます。
🌬️ 風速別の使用感と推奨ライン
| 風速 | The ONE直結 | The ONE+リーダー | エステル直結 | 推奨選択 |
|---|---|---|---|---|
| 無風~1m | ◎ 最高の感度 | ○ 十分使える | ○ 問題なし | The ONE直結 |
| 2~3m | ○ やや影響あり | ○ 問題なし | ◎ 快適 | The ONE+リーダー |
| 4~5m | △ 操作感低下 | △ やや使いづらい | ○ 問題なし | エステル推奨 |
| 6m以上 | × 使用困難 | △ 何とか使える | ○ 使える | エステル一択 |
| 横風強い | × 非常に厳しい | △ リーダー長くすれば | ○ 問題なし | エステル一択 |
この表から分かるように、風速4m以上、特に横風が強い状況では、The ONEアジングの直結使用は現実的ではないと言えます。こうした状況では、素直にエステルラインに切り替えるか、リーダーを長めに取って対応するのが賢明です。
風の影響を軽減するための対策としては、以下のような方法が考えられます:
💨 風対策の具体的方法
リーダーを長くする
- 通常30~50cmのリーダーを、1ヒロ(約1.5m)に延長
- フロロカーボンの高比重を活かして沈下を助ける
- リーダーが長い分、風の影響を受ける部分が減る
ジグヘッドを重くする
- 通常より0.3~0.5g重いものを選択
- 沈下速度が上がり、ラインのたるみを抑制
- ただし、アジの活性によっては逆効果の可能性も
キャスト後のメンディングを徹底
- キャスト直後にラインを張り直す動作
- 風上側にロッドを倒してラインの弛みを取る
- こまめなメンディングで操作感を維持
風裏のポイントを選ぶ
- 堤防や建物の陰など、風が遮られるエリアを狙う
- ポイント選択の段階で風を考慮
- 釣果を優先するなら釣り場自体を変えることも検討
ロッドアクションで対応
- ティップを水面近くに下げてラインのたるみを抑制
- リールの巻き速度を上げて常にテンションをかける
- ただし、これらはアジングの繊細さを損なう可能性も
実際のところ、風が強い日にわざわざThe ONEアジングの直結を使う必要性は低いと言えます。風の強い日はエステルラインの方が圧倒的に釣りやすいのが現実です。無理にThe ONEアジングを使い続けるよりも、状況に応じてラインを使い分ける柔軟性の方が重要です。
理想的なアプローチとしては、複数のリールやスプールを用意し、状況に応じて使い分けることです。例えば:
- 無風~微風時 → The ONEアジング 0.13号直結(感度最優先)
- やや風がある時 → The ONEアジング 0.13号+フロロ50cm(バランス型)
- 風が強い時 → エステル 0.3号直結(操作性最優先)
- 障害物周辺 → エステル 0.3号+フロロ60cm(安全性最優先)
このように使い分けることで、それぞれのラインの長所を最大限に活かすことができます。The ONEアジングは決して「万能なライン」ではなく、条件が整った時に真価を発揮する特化型のラインだと理解すべきでしょう。
結論として、風の影響を考慮した賢い使い分けこそが、The ONEアジングを有効活用する鍵となります。無風~微風の日を選んで釣行する、もしくは複数のラインシステムを準備しておくことで、The ONEアジングのポテンシャルを最大限に引き出せるはずです。
まとめ:The ONE アジング直結は状況次第で判断を
最後に記事のポイントをまとめます。
- The ONEアジングは構造上直結可能だが、メーカーも基本的にはリーダー使用を推奨している
- モノフィラメント構造により、従来のPEラインにはない結束のしやすさと安定性を実現
- 0.08~0.13号の極細号数では直結リスクが高く、上級者向けのテクニックと言える
- 最大の弱点は耐摩耗性の低さで、障害物への接触には極めて脆弱
- オープンエリアや砂地のポイントでは直結のメリットを十分に享受できる
- 直結時の感度向上効果は確実に体感できるが、釣果向上に直結するとは限らない
- リーダーを50cm程度付けても感度はほとんど変わらず、安全性が大幅に向上する
- 簡易ノット(クインテットノット、3.5ノット等)でも実用に耐える強度が得られる
- 比重0.97という軽さは、ボトム攻略では不利だが表層攻略では有利に働く
- テトラ、岩場、堤防際などの障害物周辺では確実にリーダーが必要
- 風速4m以上、特に横風が強い状況では直結使用は非現実的
- 風の影響を考慮し、エステルラインとの使い分けが重要
- 直結は「できるかできないか」ではなく「すべきかすべきでないか」で判断すべき
- 初心者や中級者は、まずリーダー付きでThe ONEの特性を理解することが推奨される
- 結論として、The ONEアジングの直結は条件を見極めた上での選択肢であり、万能ではない
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- The ONE® アジング よくあるご質問|釣具の総合メーカー デュエル
- モノフィラメントPFライン「The ONE アジング」インプレ | 31ippoの日常
- The ONE アジングをインプレ。”絶対感度”に偽りなし! | TSURI HACK[釣りハック]
- DUELThe ONE アジングを徹底インプレッション! | まるなか大衆鮮魚
- アジングライン「ザ・ワン」のインプレ。ライトゲーム用PEラインのアンサー。 : 釣果で証明する釣りの理論 ── 私が思うところ。
- 極細PEライン「The ONE アジング0・08号」の特徴と魅力
- FISHING TACKLE STORE つり具 山陽 SANYO
- 話題の新ライン『The ONE』をエステルライン(2種)と比較してみました。 | AJI HUNT
- 絶対感度「The ONEアジング」の秘密、にいがたフィッシングショーにて。 – Marvelous Act(2)
- TheONEアジング使ってきました – pencil59’s blog
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。